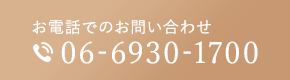胃カメラと大腸カメラの同時検査〜メリット・費用・所要時間を徹底解説

「胃カメラと大腸カメラって、同じ日に受けられるの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実は、胃カメラと大腸カメラを同時に検査することは可能です。1日で両方の検査が完了し、通院回数や前処置の負担が大きく軽減されます。
忙しい日常を送る現役世代の方にとって、何度も病院に通うことは大きな負担です。また、検査前の食事制限や下剤の内服といった準備も、1回で済めば心身への負担が減ります。
この記事では、胃カメラと大腸カメラの同時検査について、メリット・デメリット、費用、所要時間、適している方の条件などを、消化器内科専門医の視点から詳しく解説します。効率的に検査を受けたい方は、ぜひ参考にしてください。
胃カメラ・大腸カメラの順序で迷ったら
症状や目的によって「先に行う検査」が変わることがあります。初診では所要時間や当日の注意点も含めて確認できます。
不安解消メモ:初診で検査の流れ・準備(食事/下剤/鎮静)をまとめて案内します。
胃カメラと大腸カメラの同時検査とは
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)と大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)を、同じ日に続けて実施する検査方法です。通常、それぞれ別の日に受けることが多いですが、鎮静剤を使用することで、1回の来院で両方の検査を済ませることができます。
検査の流れとしては、まず胃カメラで食道・胃・十二指腸を観察し、その後、検査台に寝たまま体勢を変えて大腸カメラで直腸から盲腸まで観察します。鎮静剤を使用すれば、ウトウトした状態で両方の検査を受けられるため、苦痛を最小限に抑えることが可能です。
同時検査は、専門的な内視鏡技術と特殊な設備を完備した医療機関でのみ実施可能です。内視鏡専門医が常駐し、リカバリールームなどの環境が整った施設で安全に行われます。
同時検査の3つの大きなメリット
時間的・経済的な負担が軽減される
最大のメリットは、1回の来院で済むことです。
胃カメラと大腸カメラを別々に受ける場合、それぞれの検査日に半日から1日の時間を確保する必要があります。事前の診察、検査当日、結果説明と、最大で6回の通院が必要になることもあります。
同時検査なら、これらをすべて大腸カメラの検査日にまとめることができます。仕事や家庭の日程調整も1回で済み、待ち時間も短縮できます。忙しい現役世代の方にとって、時間的な負担が大幅に軽減されるのです。
食事制限と前処置が1回で完了
検査前の準備も、同時検査なら1回で済みます。
胃カメラでは前日の夕食後から絶食が必要で、大腸カメラでは前日から食事制限と下剤の内服が必要です。別々に受ける場合、これらの準備を2回繰り返すことになります。
同時検査では、大腸カメラの準備に合わせて胃カメラの準備も同時に行えるため、食事制限の回数が減り、心身への負担が軽くなります。前日の食事制限、当日朝の下剤内服といった一連の流れを1回で完結できるのです。
鎮静剤と検査時の緊張が1回で済む
検査への緊張感も、1回で済むのは大きなメリットです。
検査台に上がる緊張、点滴を受ける不安、検査中の苦痛・・・これらを2回経験するのは、精神的にも負担が大きいものです。同時検査なら、鎮静剤を使用して眠った状態で両方の検査を受けられるため、緊張や不安を感じる回数が減ります。
また、鎮静剤使用後は車の運転ができませんが、同時検査なら運転制限も1日で済むため、日常生活への影響も最小限に抑えられます。
知っておきたいデメリットと注意点
鎮静剤の使用がほぼ必須となる
同時検査では、鎮静剤の使用が強く推奨されます。
鎮静剤を使用せずに検査を受けると、胃カメラでの嘔吐反射が強く出た場合、お腹にガスが溜まり、大腸カメラの検査が困難になる可能性があります。また、検査時間が長くなるため、患者様の苦痛も増してしまいます。
鎮静剤を使用することで、リラックスした状態で両方の検査を受けられ、正確な診断も可能になります。ただし、鎮静剤の使用量は単独検査と比べてやや増える可能性があります。もちろん、適切な量を調整しながら安全に使用しますので、過度な心配は不要です。
検査時間と休憩時間がやや長くなる
同時検査の所要時間は、単独検査よりも長くなります。
胃カメラと大腸カメラを合わせた検査時間は、20〜30分程度です。ポリープの切除や生検を行う場合は、さらに時間がかかることもあります。また、鎮静剤の効果が切れるまで、院内のリカバリールームで30〜60分程度休憩していただく必要があります。
検査前の準備から結果説明まで含めると、半日程度の時間を確保していただくことになります。ただし、2回に分けて受けるよりは、トータルの時間は短縮できます。
症状がない場合は保険適用にならない
無症状の方が同時検査を受ける場合、自費診療となります。
内視鏡検査は、腹痛・下痢・便秘・血便・胃痛・胸やけなどの症状がある場合、または医師から定期検査を指示されている場合に保険適用となります。症状がない方が検診目的で受ける場合は、自費での検査となります。
ただし、地域によっては保険適用の条件が異なる場合もあります。検査を検討される際は、事前に医療機関に確認することをおすすめします。
同時検査の費用はどのくらい?
同時検査の費用は、保険適用の有無や処置内容によって変わります。
保険診療(3割負担)の場合、同時検査の費用は約14,000円が目安です。胃カメラ単独では約4,500円、大腸カメラ単独では約7,500円ですので、別々に受けるよりも若干お得になります。
ポリープの切除を行った場合は、約25,000〜35,000円程度となります。生検(組織検査)を行った場合は、胃カメラで約7,000円、大腸カメラで約10,000円が目安です。
自費診療の場合は、医療機関によって費用が異なりますので、事前に確認することをおすすめします。
検査の流れと所要時間
前日の準備
検査前日は、繊維の少ない食事を摂っていただきます。
夕食は20時頃までに済ませ、それ以降は絶食となります。水分は摂取可能ですが、牛乳やジュースなど不透明な飲み物は避けてください。就寝前に、指定された下剤を内服していただきます。
何を食べればよいか分からない方には、検査食をご用意している医療機関もありますので、事前に確認してみてください。
当日の朝から検査まで
当日の朝8時頃から、下剤を内服していただきます。
約2リットルの下剤を2〜3時間かけて飲み、便がきれいになるまで待ちます。12時頃までに便が透明になったら、指定された時間に来院していただきます。便がきれいにならない場合は、医療機関に連絡すれば対応してもらえます。
来院後は検査着に着替え、検査室に入室します。生体モニターを装着し、点滴を開始します。鎮静剤を使用して、ウトウトした状態で検査を開始します。
検査中の流れ
まず胃カメラで食道・胃・十二指腸を観察します。
必要に応じて生検(組織検査)を行います。胃カメラが終了したら、検査台に寝たまま体勢を変え、速やかに大腸カメラを開始します。盲腸まで挿入した後、上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸・直腸をしっかりと観察します。
ポリープが見つかった場合は、可能な範囲で切除を行います。検査時間は20〜30分程度ですが、処置内容によって前後します。
検査後の休憩と結果説明
検査後は、鎮静剤の効果を拮抗する薬を投与します。
その後、リカバリールームで30分程度休憩していただきます。鎮静剤の効果が切れてきたら着替えていただき、医師から検査結果の説明を受けます。生検やポリープ切除を行った場合は、後日、病理結果の説明がありますので、再診予約を取って帰宅していただきます。
同時検査が適している方・おすすめの方
以下のような方には、同時検査が特におすすめです。
- 健康診断で便潜血陽性と胃の不調がある方 – 両方の検査が必要な場合、1回で済ませられます
- 胃がん・大腸がんの家族歴がある方 – 定期的な検査が必要な方にとって、負担軽減になります
- 多忙で何度も通院が難しい方 – 仕事や家庭の都合で時間が取りにくい方に最適です
- 検査のたびに緊張しやすい方 – 1回で済ませることで、精神的負担が軽減されます
- 鎮静剤を使った楽な検査を希望される方 – 苦痛を最小限に抑えた検査が可能です
ただし、ご高齢の方や持病をお持ちの方は、安全を優先して別日に分けることをおすすめする場合もあります。医師と相談しながら、最適な検査方法を選択してください。
検査前後に気をつけたいポイント
事前準備について
検査前日は、繊維の多い食品を避けてください。
海藻類・きのこ類・こんにゃく・ごぼうなどは、消化に時間がかかるため控えましょう。また、種のある果物(いちご・キウイなど)も避けた方が良いでしょう。
常用薬がある方は、事前に医師に相談してください。血液をサラサラにする薬(抗凝固薬・抗血小板薬)を服用している方は、休薬が必要な場合があります。糖尿病の薬も、検査当日は調整が必要です。
検査後の過ごし方
検査後は、鎮静剤の影響で眠気やふらつきが残ることがあります。
当日は車やバイク、自転車の運転は絶対に避けてください。公共交通機関を利用するか、ご家族に送迎をお願いすることをおすすめします。また、重要な判断を伴う仕事や契約なども避けた方が良いでしょう。
食事は、検査後1時間程度経過してから、消化の良いものから始めてください。ポリープを切除した場合は、当日はお粥やうどんなど、柔らかいものを選びましょう。アルコールや刺激物は、数日間控えることをおすすめします。
激しい運動や重いものを持つことも、1週間程度は避けてください。特にポリープ切除後は、出血のリスクがあるため注意が必要です。
よくあるご質問
胃カメラと大腸カメラは必ず同時に受けないといけませんか?
いいえ、必ずしも同時に受ける必要はありません。
患者様の体調やご希望に応じて、別々に受けることも可能です。ご高齢の方や持病をお持ちの方は、安全を優先して別日に分けることをおすすめする場合もあります。医師と相談しながら、最適な方法を選択してください。
検査は痛いですか?
鎮静剤を使用すれば、ほとんど痛みを感じることなく検査を受けられます。
ウトウトした状態で検査が進むため、苦痛を最小限に抑えることができます。鎮静剤を使用しない場合は、胃カメラでの嘔吐反射や、大腸カメラでの腹部の張りを感じることがありますが、医師が丁寧に対応しますので、ご安心ください。
検査後はすぐ帰れますか?
鎮静剤の効果が切れるまで、30分〜1時間程度の休憩が必要です。
リカバリールームで休憩していただき、医師が問題ないと判断したら帰宅していただけます。検査前の準備から結果説明まで含めると、半日程度の時間を確保していただくことになります。
まとめ:同時検査で効率的に健康管理を
胃カメラと大腸カメラの同時検査は、時間的・経済的な負担を軽減できる効率的な検査方法です。
1回の来院で両方の検査が完了し、食事制限や前処置も1回で済みます。鎮静剤を使用すれば、苦痛を最小限に抑えながら、正確な診断を受けることができます。
ただし、検査時間がやや長くなることや、鎮静剤の使用がほぼ必須となることなど、注意点もあります。また、症状がない場合は自費診療となる点も理解しておく必要があります。
胃腸に症状がある方、健康診断で要再検査となった方、家族歴がある方は、早めの検査をおすすめします。忙しい方にこそ、同時検査は大きなメリットがあります。
当院では、消化器内科・内視鏡専門医として、患者様一人ひとりの状況に合わせた最適な検査方法をご提案しています。同時検査についてご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。
あなたの健康を守るために、適切なタイミングで検査を受けることが大切です。
胃カメラ・大腸カメラの同時検査をご検討の方へ
石川消化器内科内視鏡クリニックでは、消化器内科専門医による安全で正確な内視鏡検査を提供しています。鎮静剤を使用した苦痛の少ない検査も可能です。
お電話またはWEBからご予約いただけます。
🌐 公式サイト:https://www.sanreikai.com/
次の一歩:まずは「どちらから」を相談
受ける順番・同日検査の可否は、症状や既往歴で変わります。無理のないスケジュールで調整しましょう。
不安解消メモ:当日の過ごし方(食事・運転可否など)も事前に確認できます。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
家族に胃がん・大腸がんがいる人の検診戦略|何歳から何年ごとに内視鏡を受けるべきか

「親が胃がんだった」「兄弟が大腸がんになった」・・・そんな経験をお持ちの方は、ご自身の健康についても不安を感じているのではないでしょうか。
家族にがんの既往がある場合、一般の方よりもリスクが高まることが知られています。
しかし、具体的に何歳から検査を始めればよいのか、どのくらいの頻度で受ければよいのか、明確な答えを持っている方は少ないかもしれません。
本記事では、家族歴がある方に最適な検診戦略について、最新のエビデンスと専門医の見解をもとに詳しく解説します。
📞 石川消化器内科内視鏡クリニック
TEL: 06-6930-1700
🌐 WEB予約: https://www.sanreikai.com/
📍 大阪市城東区「蒲生四丁目駅」5番出口すぐ
家族歴があるとリスクはどれくらい高まるのか
家族に胃がんや大腸がんの既往がある場合、発症リスクは確実に上昇します。
これは医学的に明らかになっている事実であり、適切な対策を講じることが重要です。
胃がんでは、家族に胃がんになった方がいる場合、いない場合と比べて**男性で1.6倍、女性で2.4倍**発症率が高くなるとされています。
大腸がんにおいても、第1度近親者(親・兄弟・子ども)が大腸がんと診断されている場合、リスクが高まることが明らかになっています。
特に、若い年齢で家族が発症している場合や、複数の家族ががんになっている場合は、より注意が必要です。

胃がんの家族歴とリスク要因
胃がんの発症には、「ピロリ菌感染」や「食生活」が大きく影響しています。
家族内でピロリ菌感染が共有されやすいこと、また食習慣が似ることから、家族歴が重要な意味を持つと考えられています。
日本では、特に高齢世代でピロリ菌の感染率が高く、親から子への感染も起こりやすい環境にありました。
ただし、必ずしも遺伝によって胃がんを発症するとは限りません。
環境要因の影響が大きいため、適切な予防と早期発見が重要です。
ピロリ菌の除菌治療を受けることで、胃がんのリスクを大幅に下げることができます。
大腸がんの家族歴とリスク要因
大腸がんは、遺伝性の要因が関与するケースが一定数存在します。
全体の約5%程度は「リンチ症候群」や「家族性大腸腺腫症(FAP)」などの遺伝性大腸がんです。
また、原因遺伝子は特定されていないものの、血縁者に多くの大腸がん患者がいる「家族集積性大腸がん」が20~30%程度存在します。
第1度近親者が2人以上大腸がんと診断されている場合、または1人が60歳未満で診断されている場合は、特に注意が必要です。
このような場合、遺伝性腫瘍症候群の可能性も考慮し、専門医に相談することが推奨されます。
何歳から内視鏡検査を始めるべきか
家族歴がある場合、一般的な検診開始年齢よりも早めに検査を始めることが推奨されます。
具体的な開始年齢は、家族歴の濃さや遺伝性疾患の有無によって異なります。
ここでは、それぞれのケースに応じた推奨開始年齢について解説します。

胃がんの家族歴がある場合
胃がんは45歳を過ぎたあたりから増加していきます。
家族歴がある方は、**40歳前後**から胃カメラ検査を開始することが望ましいと考えられます。
特にピロリ菌感染が確認されている場合は、より早期からの検査開始が推奨されます。
ピロリ菌の除菌治療を受けた後も、定期的な内視鏡検査が必要です。
除菌後も胃がんのリスクはゼロにはならないため、継続的な観察が重要となります。
また、親が若い年齢(50歳未満)で胃がんと診断された場合は、さらに早めの検査開始を検討することもあります。
大腸がんの家族歴がある場合
大腸がんの発生数は40代から増加し、高齢になるほど発症率が上がります。
家族歴がある方は、**最も若い家族の発症年齢より10歳若い年齢**、または**40歳**のいずれか早い方から大腸カメラ検査を開始することが推奨されます。
例えば、親が50歳で大腸がんと診断された場合、40歳から検査を始めるのが適切です。
親が35歳で診断された場合は、25歳から検査を開始することが推奨されます。
このように、家族の発症年齢を基準に検査開始時期を決定することで、早期発見の可能性を高めることができます。
遺伝性腫瘍症候群が疑われる場合
リンチ症候群では、**30歳頃**から1~2年ごとの内視鏡検査が目安とされています。
家族性大腸腺腫症(FAP)の場合は、さらに早期からの検査が必要になることがあります。
FAPでは、10代から大腸ポリープが多発するため、10代後半から大腸カメラ検査を開始することが推奨されます。
遺伝性のがんについて心配がある方は、遺伝性がんの相談体制のある医療機関にご相談ください。
遺伝カウンセリングを受けることで、適切な検査計画を立てることができます。
何年ごとに内視鏡検査を受けるべきか
検査の頻度は、リスクの程度によって調整する必要があります。
一般的な対策型検診では、胃がん検診は50歳以上で2年に1回、大腸がん検診は40歳以上で1年に1回が推奨されています。
しかし、家族歴がある場合は、より短い間隔での検査が望ましいと考えられます。
胃がんの検査間隔
ピロリ菌感染がある、または除菌後の方で家族歴がある場合は、**1~2年ごと**の胃カメラ検査が推奨されます。
ピロリ菌未感染で家族歴がある場合でも、**3~5年に1度**は検査を受けることが望ましいでしょう。
前回の検査で萎縮性胃炎や腸上皮化生などの所見があった場合は、より短い間隔での検査が推奨されます。
症状がある場合は、時期を問わず早めに受診することが重要です。
胃の不快感、食欲不振、体重減少などの症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。
大腸がんの検査間隔
家族歴がある場合、**3~5年ごと**の大腸カメラ検査が推奨されます。
ポリープが見つかった場合は、その大きさや数によって次回の検査時期が決まります。
大腸ポリープは切除することで大腸がんの予防につながるため、定期的な検査が非常に重要です。
小さなポリープ(5mm未満)が1~2個程度であれば、5年後の検査でも問題ないことが多いです。
一方、大きなポリープ(10mm以上)や多数のポリープが見つかった場合は、1~3年後の再検査が推奨されます。
腺腫性ポリープが見つかった場合は、より短い間隔での検査が必要になることがあります。
リスクに応じた個別化された検査計画
年齢、家族歴の濃さ、生活習慣、併存症などを総合的に考慮し、医師と相談しながら最適な検査間隔を決定することが大切です。
喫煙、多量飲酒、高塩分食、肥満などのリスク要因がある場合は、より短い間隔での検査が推奨されます。
また、糖尿病や炎症性腸疾患などの併存症がある場合も、検査頻度を調整する必要があります。
検査結果や健康状態の変化に応じて、柔軟に検査計画を見直すことが重要です。

内視鏡検査を受ける際のポイント
家族歴がある方が内視鏡検査を受ける際には、いくつかの重要なポイントがあります。
これらのポイントを押さえることで、より精度の高い検査を受けることができます。
消化器・内視鏡専門医による検査を選ぶ
高度な観察技術を持つ専門医による検査が、早期発見の鍵となります。
特に、家族歴がある方では見つけにくいタイプのがんが発生することもあるため、拡大内視鏡やNBI(狭帯域光)などの高度な観察技術を用いた検査が推奨されます。
消化器・内視鏡専門医は、微細な病変を見逃さない観察力と、適切な生検・治療の判断力を持っています。
検査を受ける際は、医師の専門性や経験を確認することが大切です。
鎮静剤を使用した無痛検査を選択する
定期的な検査を継続するためには、検査の苦痛を最小限に抑えることが重要です。
鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の胃カメラ・大腸カメラ検査を選択することで、検査への心理的ハードルを下げることができます。
特に大腸カメラ検査は、鎮静剤を使用することで、ほとんど苦痛を感じることなく検査を受けることができます。
検査後は少し休んでから帰宅できますが、当日の車の運転は控える必要があります。
家族歴を必ず医師に伝える
検査前の問診で、家族のがんの既往について詳しく伝えることが大切です。
何歳で診断されたか、何人の家族ががんになったかなどの情報は、検査の精度や今後の検査計画に影響します。
また、家族が受けた治療内容や、遺伝性腫瘍症候群の診断を受けているかどうかも重要な情報です。
これらの情報を正確に伝えることで、より適切な検査と診断が可能になります。
ポリープが見つかった場合は切除を
大腸カメラ検査でポリープが見つかった場合、その場で切除できることが多くあります。
ポリープの切除は大腸がんの予防に直結するため、積極的に対応することが推奨されます。
切除したポリープは病理検査に提出され、良性か悪性かを判定します。
この結果によって、次回の検査時期が決定されます。
検診だけでなく生活習慣の改善も重要
定期的な検査と並行して、生活習慣の改善もがん予防には欠かせません。
検査で早期発見することも大切ですが、そもそもがんを発症させないための予防が最も重要です。
胃がん予防のための生活習慣
塩分の摂りすぎは胃がんのリスクを高めます。
減塩を心がけ、野菜や果物を積極的に摂取することが推奨されます。
特に、塩辛い食品や加工食品の摂取を控えることが重要です。
喫煙は胃がんの発症リスクを高めるため、禁煙が強く推奨されます。
ピロリ菌感染が確認された場合は、除菌治療を受けることが重要です。
除菌治療は1週間程度の内服で完了し、成功率は約80~90%です。
除菌後も定期的な検査を継続することで、胃がんのリスクをさらに下げることができます。
大腸がん予防のための生活習慣
飲酒は大腸がんの発症に関係しているため、適量を守ることが大切です。
特に、多量飲酒(1日あたり日本酒換算で2合以上)は大腸がんのリスクを高めます。
肥満は結腸がんの発生リスクを高めるため、適正体重の維持が推奨されます。
BMI(体格指数)を25未満に保つことが目標です。
運動不足は大腸がんのリスクを高めるため、定期的な運動習慣を持つことが重要です。
週に150分程度の中等度の運動(ウォーキングなど)が推奨されます。
喫煙は大腸がん、特に直腸がんとの関係性が高いため、禁煙が推奨されます。
食物繊維を多く含む食品(野菜、果物、全粒穀物など)を積極的に摂取することも、大腸がん予防に有効です。

まとめ|家族歴がある方の検診戦略
家族に胃がんや大腸がんの既往がある方は、一般の方よりも高いリスクを持っています。
しかし、適切な時期から定期的な内視鏡検査を受けることで、早期発見・早期治療が可能です。
胃がんの家族歴がある方は40歳前後から、大腸がんの家族歴がある方は最も若い家族の発症年齢より10歳若い年齢または40歳から検査を開始しましょう。
検査の頻度は、胃がんでは1~2年ごと、大腸がんでは3~5年ごとが目安となります。
消化器・内視鏡専門医による高精度な検査を選び、鎮静剤を使用した無痛検査で継続的な検診を実現することが重要です。
また、検診だけでなく、生活習慣の改善も並行して行うことで、がんのリスクをさらに下げることができます。
ご自身やご家族の健康を守るため、今日から適切な検診戦略を始めてみませんか。
詳しい検査内容や検診計画については、消化器・内視鏡専門医にご相談ください。
石川消化器内科内視鏡クリニックでは、家族歴がある方に最適な検診プランをご提案しています。
鎮静剤を使用した無痛の胃カメラ・大腸カメラ検査を実施しており、初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しています。
高性能な拡大内視鏡を導入し、大学病院に劣らない精度の高い検査が可能です。
ご予約は電話(06-6180-7778)またはWEBから承っております。
大阪市城東区「蒲生四丁目駅」5番出口すぐの好立地で、お気軽にご来院いただけます。
家族歴がある方の不安を解消し、安心して検査を受けていただけるよう、スタッフ一同サポートいたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
胃カメラと大腸カメラは同日受診可能!メリットと予約のコツを徹底解説

「胃カメラと大腸カメラを同じ日に受けられたら、時間も手間も省けるのに・・・」
そう感じたことはありませんか?
実は、胃カメラと大腸カメラの同日検査は可能です。忙しい日常の中で、何度も医療機関に足を運ぶ負担を減らせるだけでなく、食事制限や検査前の準備も一度で済ませられるため、多くの患者様にとって大きなメリットがあります。
この記事では、内視鏡専門医の視点から、胃カメラと大腸カメラを同日に受けるメリット、注意点、予約時のポイント、そして検査の流れまでを詳しく解説します。初めて同日検査を検討される方も、以前の検査で苦しい経験をされた方も、安心して検査を受けていただけるよう、実践的な情報をお届けします。
【お問い合わせ・ご予約】
石川消化器内科内視鏡クリニック
電話予約・Web予約(24時間受付)対応
胃カメラと大腸カメラは同日に受けられます
結論から申し上げますと、胃カメラ(胃内視鏡検査)と大腸カメラ(大腸内視鏡検査)は同じ日に受けることが可能です。
これは特別な検査方法ではありません。多くの医療機関で実施されている検査方法であり、適切な設備と専門的な技術を持つ施設であれば対応可能です。

ただし、すべての医療機関で実施できるわけではないため、事前の確認が必要となります。
同日検査の基本的な流れ
同日検査では、まず胃カメラ検査を行い、その後すぐに大腸カメラ検査を実施します。
検査の順番は医療機関によって異なる場合もありますが、一般的には胃カメラを先に行うケースが多いです。これは、大腸カメラ検査の前処置(下剤の服用)が胃の中を空にする効果も持つため、効率的に両方の検査を行えるからです。
検査台に横になったまま、胃カメラ検査が終了した後、そのまま体勢を変えて大腸カメラ検査に移行します。鎮静剤を使用している場合は、ウトウトした状態のまま両方の検査を受けられるため、患者様の負担を最小限に抑えられます。
同日検査が可能な理由
胃カメラと大腸カメラは、検査の準備や流れに多くの共通点があります。
どちらも消化管の内部を観察する検査であり、食事制限や鎮静剤の使用、検査後の休憩といったプロセスが重なります。この共通性を活かすことで、一度の来院で両方の検査を効率的に実施できるのです。
また、最新の内視鏡機器と専門的な技術を持つ医師であれば、両方の検査を安全かつスムーズに行うことが可能です。当院では、日本内視鏡学会認定の内視鏡専門医が、オリンパス社製の最上位機種「EVIS X1」を使用して検査を行っており、高い精度と安全性を確保しています。
同日検査の3つの大きなメリット
胃カメラと大腸カメラを同日に受けることで、患者様にとって多くのメリットがあります。ここでは、特に重要な3つのメリットについて詳しく解説します。

時間的・経済的な負担が大幅に軽減される
最も大きなメリットは、通院回数を減らせることです。
通常、胃カメラと大腸カメラを別々に受ける場合、それぞれに事前診察、検査当日、結果説明と、最大で6回の通院が必要になることがあります。同日検査であれば、これを2〜3回程度に抑えられます。
仕事や家庭の都合で何度も休みを取ることが難しい方にとって、この時間的負担の軽減は非常に大きな意味を持ちます。また、交通費や駐車場代などの経済的負担も削減できます。
食事制限が一度で済む
内視鏡検査では、検査前日からの食事制限が必要です。
胃カメラでは朝食を抜く必要があり、大腸カメラでは前日から繊維の少ない食事に制限し、当日は下剤を服用します。これらの準備を2回行うのは、想像以上に大変なものです。
同日検査であれば、この食事制限を一度で済ませられます。特に大腸カメラの前処置は胃の中も空にするため、両方の検査を同時に行う準備が整います。日常生活への影響を最小限に抑えられる点は、多くの患者様から高く評価されています。
検査に伴う心理的負担が減る
検査台に上がる緊張感は、慣れている方でも感じるものです。
点滴を受ける際の針の痛みや、検査前の不安な気持ちを2回経験するよりも、1回で済ませられる方が精神的な負担は軽くなります。特に、以前の検査で苦しい経験をされた方にとって、検査回数を減らせることは大きな安心材料となります。
また、鎮静剤を使用する場合、当日は車やバイクの運転ができなくなりますが、同日検査であればこの制限も1日で済みます。付き添いの方の負担も軽減できる点も見逃せないメリットです。
同日検査を受ける際の注意点
メリットが多い同日検査ですが、いくつか注意すべき点もあります。事前に理解しておくことで、より安心して検査を受けていただけます。
鎮静剤の使用が推奨される
同日検査では、鎮静剤を使用することを強くお勧めします。
鎮静剤なしで胃カメラを受けると、嘔吐反射が強く出る方がいらっしゃいます。この状態で大腸カメラ検査に移行すると、お腹にガスが溜まりやすくなり、検査が困難になる可能性があります。
また、検査時間が通常より長くなるため、鎮静剤を使用してリラックスした状態で検査を受けていただく方が、患者様の負担を軽減できます。当院では、患者様の体格や既往歴を考慮して、適切な量の鎮静剤を使用し、安全に配慮した検査を行っています。
使用する鎮静剤の量について
単独の検査と比較すると、同日検査では鎮静剤の使用量が増える場合があります。
これは検査時間が長くなるため、途中で鎮静効果が薄れてきた場合に追加投与が必要になることがあるためです。ただし、適切に管理された鎮静剤の使用は安全性が高く、検査後のリカバリールームでの休憩時間を十分に取ることで、安全に帰宅していただけます。
保険適応について
内視鏡検査は、症状がある場合や医師からの定期検査の指示がある場合に保険適応となります。
無症状の方が予防目的で検査を受ける場合は、自費診療となることがあります。また、地域によっては胃カメラと大腸カメラの同日検査が保険診療で認められない場合もあるため、事前に医療機関に確認することをお勧めします。
症状がある方であれば保険診療で同日検査を受けていただけます。詳細については、予約時にお気軽にご相談ください。
実施できる医療機関が限られる
同日検査は、専門的な内視鏡技術と設備を完備した医療機関でのみ実施可能です。
内視鏡専門医が常駐し、リカバリールームなどの環境が整った施設に限られます。そのため、すべての医療機関で受けられるわけではありません。事前に対応可能な医療機関を調べ、予約時に同日検査を希望する旨を伝えることが重要です。
同日検査の詳しい流れと準備
実際に同日検査を受ける際の流れを、時系列に沿って詳しく説明します。

検査前日の準備
前日は、繊維の少ない食事を摂っていただきます。夕食は20時頃までに済ませてください。
何を食べればよいか不安な方には、検査食もご用意しています。就寝前には、指定された下剤を服用していただきます。この段階での準備が、翌日の検査の質を左右します。
不明な点があれば、事前に医療機関に確認することをお勧めします。
検査当日の朝の準備
朝8時頃から、自宅で下剤を服用していただきます。約2リットルの下剤を、指示された時間をかけて飲んでいただきます。
12時頃までにお通じがきれいになることを目指します。便の色が透明に近い黄色になったら、準備完了のサインです。お通じがきれいにならない場合や、体調に不安がある場合は、すぐに医療機関に連絡してください。
来院後の流れ
指定された時間に来院していただき、受付を済ませます。検査着に着替えていただいた後、検査室に入室します。
生体モニターを装着し、鎮静剤を投与してから検査を開始します。
胃カメラ検査
ウトウトした状態で、胃カメラ検査を行います。食道、胃、十二指腸を丁寧に観察し、必要に応じて組織検査(生検)も実施します。
検査時間は通常5〜10分程度です。
大腸カメラ検査
胃カメラ終了後、検査台に寝たまま速やかに大腸カメラ検査に移行します。盲腸まで内視鏡を挿入した後、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸としっかりと観察します。
ポリープが見つかった場合は、その場で切除することも可能です。検査時間は15〜30分程度です。
検査後の休憩と結果説明
検査終了後は、鎮静剤の効果を拮抗する薬を投与し、リカバリールームで30分程度お休みいただきます。鎮静剤の効果が切れてきたら、着替えていただき、医師から検査結果の説明を受けます。
生検やポリープ切除を行った場合は、後日病理結果の説明があるため、再診予約を取って帰宅していただきます。
予約時のコツと確認すべきポイント
同日検査をスムーズに受けるためには、予約時の確認が重要です。
事前に確認すべき項目
予約時には、以下の点を必ず確認してください。
- 同日検査に対応しているか – すべての医療機関で実施できるわけではありません
- 内視鏡専門医が担当するか – 専門医による検査は精度と安全性が高まります
- 鎮静剤の使用が可能か – 同日検査では鎮静剤の使用が推奨されます
- リカバリールームがあるか – 検査後の休憩に必要な設備です
- 保険適応の条件 – 症状の有無や地域によって異なります
予約方法と準備
多くの医療機関では、電話またはWebからの予約が可能です。当院では、24時間対応のWeb予約システムをご用意しています。
大腸カメラの予約フォームから、胃カメラも同時に希望する旨をチェックしていただくことで、同日検査の予約が可能です。予約後は、事前のWeb問診にご協力いただくと、当日の診察や検査がスムーズに進行します。
キャンセルポリシーの確認
内視鏡検査の予約変更やキャンセルには、期限が設けられている場合があります。一般的には、検査の4日前までの連絡が必要です。
やむを得ない事情で変更が必要な場合は、できるだけ早めに医療機関に連絡することをお勧めします。
同日検査を安全に受けるための条件
すべての方が同日検査を受けられるわけではありません。安全を最優先するため、以下に該当する方は別日での検査をお勧めする場合があります。

高齢の方や基礎疾患のある方
ご高齢の方や、心臓病、呼吸器疾患などの基礎疾患をお持ちの方は、検査時間が長くなることで体への負担が増える可能性があります。主治医と相談の上、別日での検査を検討することもあります。
ただし、個々の状態によって判断が異なりますので、まずはご相談ください。
過去に検査で強い苦痛を感じた方
以前の内視鏡検査で非常に苦しい思いをされた方は、まず単独の検査で鎮静剤の効果を確認してから、同日検査を検討することをお勧めします。
当院では、患者様の不安を軽減するため、事前に十分なカウンセリングを行い、最適な検査方法をご提案しています。
体重制限について
安全面の理由から、体重が一定以上の方は検査をお受けいただけない場合があります。これは検査台の耐荷重や鎮静剤の投与量の管理に関わる重要な要素です。
詳細については、予約時にご確認ください。
よくある質問と回答
患者様からよくいただく質問にお答えします。
検査は痛いですか?
鎮静剤を使用することで、ほとんど痛みを感じることなく検査を受けていただけます。「気づいたら終わっていた」という感想を多くの患者様からいただいています。
当院では、豊富な経験を持つ内視鏡専門医が、丁寧で迅速な検査を行っています。
検査後はすぐに帰れますか?
鎮静剤を使用した場合、リカバリールームで30分程度お休みいただいた後、医師の結果説明を受けてから帰宅していただきます。当日は車やバイクの運転ができませんので、公共交通機関をご利用いただくか、ご家族の送迎をお願いします。
検査後は食事できますか?
胃カメラのみの場合は、検査後1時間程度で食事が可能です。大腸カメラでポリープ切除を行った場合は、当日は消化の良い食事を摂っていただき、飲酒や激しい運動は控えていただく必要があります。
詳しい食事制限については、検査後に医師から説明いたします。
どのくらいの時間がかかりますか?
検査自体は20〜30分程度ですが、準備や検査後の休憩を含めると、来院から帰宅まで2〜3時間程度を見込んでいただくとよいでしょう。
当日の持ち物は何が必要ですか?
保険証、診察券(再診の方)、お薬手帳、検査費用をご持参ください。当院では、現金のほか、クレジットカードや電子マネーでのお支払いにも対応しています。
当院での同日検査の特徴
石川消化器内科内視鏡クリニックでは、患者様に安心して検査を受けていただけるよう、万全の体制を整えています。
日本内視鏡学会認定の内視鏡専門医による検査
当院のすべての内視鏡検査は、日本内視鏡学会より認定された内視鏡専門医が担当します。豊富な経験と専門知識を持つ医師が、見落としのない丁寧で迅速な検査を行い、患者様の健康と安心をお守りします。
最新の内視鏡システムによる高精度診断
オリンパス社製の最上位機種「EVIS X1」を導入しています。NBI(狭帯域光法)、RDI(赤色光観察)、EDOF(被写界深度拡大技術)といった先端技術により、がんなどの病変の早期発見に大いに貢献します。
大学病院に劣らない正確な診断を提供できます。
苦痛を最小限に抑える鎮静剤の使用
初めての方でも安心していただけるよう、ウトウトと半分眠ったような状態になる鎮静剤をご用意しています。患者様の既往歴や体格を考慮して、適切な量を投与し、安全に配慮した検査を行います。
充実したアフターフォロー体制
検査後、精密検査や入院治療が必要になった場合は、速やかに高度医療機関と連携します。「検査の受けっぱなし」で終わることなく、必要な医療がお届けできるよう万全のフォローをいたします。
まとめ:同日検査で効率的に健康管理を
胃カメラと大腸カメラの同日検査は、時間的・経済的負担を軽減し、効率的に消化器の健康状態を確認できる優れた方法です。忙しい日常の中で、何度も医療機関に足を運ぶ負担を減らせるだけでなく、食事制限や検査前の準備も一度で済ませられます。
鎮静剤を使用することで、苦痛を最小限に抑えながら、両方の検査を安全に受けていただけます。
ただし、同日検査はすべての方に適しているわけではありません。ご高齢の方や基礎疾患をお持ちの方は、安全を最優先し、別日での検査を検討する場合もあります。また、実施できる医療機関が限られているため、事前の確認と予約が重要です。
当院では、内視鏡専門医が最新の内視鏡システムを使用し、高精度で安全な検査を提供しています。患者様一人ひとりの状態に合わせた最適な検査方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
胃がんや大腸がんは、早期発見が何よりも重要です。定期的な検査で、ご自身の健康、そしてご家族の安心を守りましょう。
胃カメラと大腸カメラの同日検査について、詳しくは石川消化器内科内視鏡クリニックまでお問い合わせください。Web予約は24時間受付中です。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
内視鏡の鎮静あり・なしの選び方|体質・持病・運転で決める最適な検査法

胃カメラの鎮静剤、使うべき?使わないべき?
胃カメラ検査を受ける際、多くの方が「鎮静剤を使うかどうか」で悩まれます。
「苦しくない検査がしたい」「でも、検査後に運転する予定がある」「持病があるけど大丈夫?」
こうした不安や疑問をお持ちの方は少なくありません。鎮静剤の使用には、それぞれメリットとデメリットがあります。大切なのは、あなたの体質や生活スタイル、検査後の予定に合わせて最適な方法を選ぶことです。
当院では、日本内視鏡学会認定の内視鏡専門医が、患者さまお一人おひとりの状況に応じた検査方法をご提案しています。この記事では、鎮静剤の使用を判断する際のポイントを、医師の視点から詳しく解説します。
【ご予約・お問い合わせ】
📞 電話予約:06-6930-1700(平日・土日祝 9:00~17:00)
🌐 Web予約:24時間受付中
🏥 大阪消化器内科・内視鏡クリニック
📍 大阪市中央区難波(なんば駅直結)
鎮静剤とは?その役割と効果
鎮静剤は、胃カメラ検査の際に患者さまの不安や緊張、不快感を和らげるために使用される薬剤です。
ウトウトと半分眠ったような状態になり、「気づいたら検査が終わっていた」という感覚で検査を終えられます。

鎮静剤の主な効果
鎮静剤を使用することで、以下のような効果が期待できます。
- 不安や緊張の軽減・・・検査への恐怖心が和らぎます
- 嘔吐反射の抑制・・・「オエッ」となる反射が起こりにくくなります
- 身体の緊張緩和・・・リラックスした状態で検査を受けられます
- 検査精度の向上・・・患者さまが落ち着いていると、医師も細部まで観察しやすくなります
当院で使用する鎮静剤の種類
当院では、主に2種類の鎮静剤を患者さまの状態に応じて使い分けています。
プロポフォールは即効性が高く、比較的短時間で覚醒するため、検査時の鎮静剤として広く使用されています。明瞭な鎮静作用と予測しやすい薬物動態が特徴です。
ミダゾラムは、鎮静だけでなく抗不安作用もあるため、内視鏡検査での緊張緩和に役立ちます。ただし、覚醒までの時間がやや長くなることがあります。
これらの薬剤を組み合わせることで、より効果的な鎮静状態を作り出すことも可能です。患者さまの体質や反射の強さ、過去の検査履歴などを考慮し、適切な種類と量を慎重に調整します。
鎮静剤を使うべき人・使わない方がいい人
鎮静剤の使用には、向き不向きがあります。
あなたの体質や状況に合わせて、最適な選択をすることが大切です。
鎮静剤の使用をおすすめする方
以下のような方には、鎮静剤の使用をおすすめしています。
- 嘔吐反射が強い方・・・過去の検査で「オエッ」となって辛かった経験がある方
- 検査への不安が強い方・・・初めての検査で緊張している方
- 過去に辛い経験をされた方・・・以前の検査がトラウマになっている方
- リラックスして検査を受けたい方・・・苦痛を最小限に抑えたい方
特に嘔吐反射が強い方は、鎮静剤を使用することで検査がスムーズに進み、精度の高い観察が可能になります。
鎮静剤を使わない方がいい方
一方で、以下のような方は鎮静剤を使用しない検査をおすすめする場合があります。
- 検査後すぐに運転する予定がある方・・・鎮静剤使用後は当日の運転ができません
- 検査後すぐに仕事に戻る必要がある方・・・覚醒までに時間がかかります
- 付き添いの方を手配できない方・・・検査後はお一人での帰宅が困難です
- 特定の持病がある方・・・呼吸器疾患や心疾患がある場合は慎重な判断が必要です
これらの条件に該当する方でも、経鼻内視鏡を選択することで、鎮静剤なしでも比較的楽に検査を受けられる可能性があります。

持病がある方の鎮静剤使用について
持病をお持ちの方は、鎮静剤の使用に特に注意が必要です。
安全に検査を受けていただくため、事前に必ず医師にご相談ください。
注意が必要な持病
以下のような持病がある方は、鎮静剤の使用について慎重な判断が求められます。
- 呼吸器疾患・・・喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など
- 心疾患・・・不整脈、心不全など
- 肝機能障害・・・鎮静剤の代謝に影響します
- 腎機能障害・・・薬剤の排泄に影響します
- 高齢の方・・・鎮静剤が効きやすい傾向があります
これらの持病がある場合でも、検査は可能です。ただし、鎮静剤の種類や量を慎重に調整する必要があります。当院では、患者さまの健康状態を詳しく伺い、全身状態を把握するモニターをつけて検査を行います。
服用中の薬について
抗血栓薬(血液をサラサラにする薬)を服用されている方は、事前にご相談ください。
組織検査が必要になった場合、出血のリスクを考慮する必要があります。多くの場合、薬を継続したまま検査が可能ですが、状況によっては休薬が必要になることもあります。
また、アレルギー歴がある方は、鎮静剤に対するアレルギー反応の可能性も考慮します。過去に薬剤アレルギーを経験された方は、必ず医師にお伝えください。
検査後の運転予定がある方へ
「検査後に車で帰りたい」「仕事の合間に検査を受けたい」
このような方は、鎮静剤を使わない検査方法を選択することをおすすめします。
鎮静剤使用後の運転制限
鎮静剤を使用した場合、当日は自動車の運転ができません。
これは、鎮静剤の効果が完全に切れるまでに時間がかかるためです。検査後は1時間ほど休んでいただきますが、その後も注意力や判断力が低下している可能性があります。
安全のため、鎮静剤を使用した場合は、必ずご家族やご友人の付き添いをお願いしています。公共交通機関やタクシーでのご帰宅も可能です。
運転予定がある方の選択肢
検査後に運転する予定がある方には、以下の選択肢があります。
- 経鼻内視鏡(鎮静剤なし)・・・検査後30~60分で水を飲んだり、運転したりできます
- 経口内視鏡(鎮静剤なし)・・・嘔吐反射が少ない方に適しています
経鼻内視鏡は、鼻から細いスコープ(約5~6mm)を挿入するため、舌の奥に触れず、嘔吐反射が起こりにくいのが特徴です。検査中も医師と会話ができるため、モニターを見ながら質問することもできます。

経口内視鏡と経鼻内視鏡、どちらを選ぶ?
胃カメラには、口から入れる「経口内視鏡」と鼻から入れる「経鼻内視鏡」の2種類があります。
それぞれの特徴を理解し、あなたに合った方法を選びましょう。
経口内視鏡の特徴
経口内視鏡は、口から直径8~9mm程度のスコープを挿入する従来型の検査方法です。
メリット
- 高画質で詳細な観察が可能
- 検査時間が比較的短い
- 病変部が見つかった場合、拡大観察も可能
- 処置や組織採取がしやすい
デメリット
- 嘔吐反射が起きやすい
- 不快感を感じることがある
- 検査中に医師と会話ができない
経口内視鏡は、精密な観察が必要な場合や、処置を伴う可能性がある場合に適しています。当院では、嘔吐反射を抑えるため、鎮静剤の使用をおすすめしています。
経鼻内視鏡の特徴
経鼻内視鏡は、鼻から直径5~6mm程度の細いスコープを挿入する検査方法です。
メリット
- 嘔吐反射が少なく、検査が楽
- 検査中に医師と会話ができる
- 鎮静剤なしでも受けやすい
- 検査後すぐに水を飲んだり、運転したりできる
デメリット
- スコープが細いため、画質がやや劣る
- 鼻腔が狭い方や鼻に持病がある方は受けられない場合がある
- 検査時間がやや長くなることがある
経鼻内視鏡は、嘔吐反射が強い方や、検査後すぐに日常生活に戻りたい方に適しています。当院では、最新式のハイビジョン内視鏡を使用しているため、経鼻でも高品質な観察が可能です。
あなたに合った選択は?
以下の表を参考に、あなたの状況に合った検査方法を選んでください。
- 苦痛が心配/嘔吐反射が強い方→ 経鼻内視鏡
- 詳細な観察・処置が必要な方→ 経口内視鏡
- できるだけ楽に受けたい方→ 鎮静剤+経口内視鏡
- 検査後にすぐ仕事や運転がある方→ 経鼻内視鏡(非鎮静)
当院では、患者さまのご希望や体質に合わせて検査方法を選択できます。どちらが良いか迷われる場合は、お気軽にご相談ください。
鎮静剤が効きにくい方への対応
「以前、鎮静剤を使ったのに効かなかった」という経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
鎮静剤が効きにくい原因はいくつかあります。
鎮静剤が効きにくい原因
以下のような要因が、鎮静剤の効果に影響することがあります。
- アルコールに強い体質・・・日常的に飲酒している方は耐性ができている可能性があります
- 投与量が不足していた・・・体格や体質に対して適切な量でなかった場合
- 強い不安や緊張・・・精神的なストレスが鎮静効果を弱めることがあります
当院での対応
当院では、鎮静剤が効きにくい方にも対応できる体制を整えています。
鎮静剤には「眠る作用が強いもの」と「反射を抑える作用が強いもの」など、いくつか種類があります。これらを組み合わせることで、より効果的な鎮静状態を作り出すことが可能です。
また、検査中も患者さまの状態を常にモニタリングし、必要に応じて追加投与を行います。「検査中に鎮静剤の効果がなくなったらどうしよう」と心配する必要はありません。
検査前の段階で、過去の検査経験や体質について詳しくお伺いし、最適な鎮静方法をご提案します。

検査前後の注意点
安全で快適な検査を受けていただくため、検査前後の注意点をお守りください。
検査前の準備
検査前日は、消化の良い食事を心がけてください。検査当日は、指定された時間から絶食・絶飲となります。
服用中の薬がある方は、事前に医師にご相談ください。多くの薬は継続して服用できますが、一部の薬は休薬が必要になる場合があります。
鎮静剤を使用する場合は、必ず付き添いの方を手配してください。当日は自動車の運転ができません。
検査後の過ごし方
鎮静剤を使用した場合、検査後は1時間ほど休んでいただきます。当院にはリカバリールームを用意しており、ゆっくりお休みいただけます。
検査後の食事は、のどの麻酔が切れてから(約1時間後)摂っていただけます。最初は水分から始め、徐々に通常の食事に戻してください。
鎮静剤を使用しなかった場合は、検査後30~60分で水を飲んだり、食事をしたりできます。運転も可能です。
組織検査を行った場合
組織検査(生検)を行った場合は、当日の激しい運動や飲酒は控えてください。出血のリスクがあるためです。
検査結果は、通常1~2週間後にお伝えします。結果説明の際は、今後の治療方針や定期検査の必要性についてもご説明します。
当院の内視鏡検査の特徴
大阪消化器内科・内視鏡クリニックでは、患者さまに安心して検査を受けていただくため、さまざまな工夫をしています。
内視鏡専門医による高精度な検査
当院のすべての内視鏡検査は、日本内視鏡学会認定の内視鏡専門医が担当します。豊富な経験と知識を持つ医師の丁寧な操作で、見落としのない精度の高い検査を提供します。
最新の内視鏡システム
オリンパス社製の最上位機種「EVIS X1」を導入しています。NBI(狭帯域光法)、RDI(赤色光観察)、EDOF(被写界深度拡大技術)といった先端技術により、がんなどの病変の早期発見が可能です。
苦痛を最小限に抑える工夫
鎮静剤の使用に加え、炭酸ガス送気を採用しています。空気の100倍吸収が早く、検査後のお腹の張りが少なくなります。
また、患者さまの体質や希望に応じて、経口・経鼻の選択、鎮静剤の有無を柔軟に対応しています。
検査後のフォロー体制
検査後、精密検査や入院治療が必要になった場合は、速やかに高度医療機関と連携します。「検査の受けっぱなし」で終わることなく、必要な医療をお届けできるよう万全のフォローをいたします。
まとめ:あなたに最適な検査方法を選びましょう
胃カメラ検査の鎮静剤使用は、あなたの体質、持病、検査後の予定によって最適な選択が変わります。
嘔吐反射が強い方や不安が大きい方には鎮静剤の使用をおすすめしますが、検査後に運転する予定がある方や、すぐに仕事に戻りたい方には、経鼻内視鏡(鎮静剤なし)が適しています。
持病をお持ちの方は、事前に医師にご相談ください。安全に検査を受けていただくため、鎮静剤の種類や量を慎重に調整します。
当院では、患者さまお一人おひとりの状況に合わせた検査方法をご提案しています。過去に辛い経験をされた方も、初めての方も、安心してご相談ください。
胃がんや食道がんは、早期発見できれば内視鏡での治療が可能です。40歳を過ぎたら、定期的な検査をおすすめします。
詳しい検査方法や予約については、大阪消化器内科内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。電話またはWebから24時間予約を受け付けています。
あなたに合った検査方法で、安心して健康を守りましょう。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
肝機能異常で再検査と言われたら|消化器内科での検査の流れと順番を解説

健康診断で肝機能異常を指摘されたあなたへ
健康診断の結果を受け取り、「肝機能異常」「要再検査」という文字を見て不安になっていませんか?
実は、健康診断で肝機能の異常を指摘される方は年々増加しており、決して珍しいことではありません。
近年では食生活の乱れや運動不足といった生活習慣の変化、内臓肥満による「脂肪肝」が増加しているため、肝機能障害を指摘される方が多くなっているのです。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、初期段階では自覚症状がほとんどありません・・・
しかし、放置すると「肝硬変」や「肝がん」といった重篤な病気へ進行するリスクがあります。
だからこそ、異常を指摘されたら早めに消化器内科を受診し、精密検査を受けることが大切です。
この記事では、消化器・内視鏡専門医として多くの肝機能異常の患者様を診察してきた経験から、検査の流れと順番をわかりやすく解説します。
肝機能検査の数値が示すもの
健康診断の血液検査では、主に3つの数値で肝機能を評価します。

AST(GOT)とALT(GPT)
「AST」「ALT」は、肝臓の細胞に含まれる酵素です。
肝臓が何らかのダメージを受けて細胞が壊されると、血液中にこれらの酵素が溢れ出してしまい、数値が高くなります。
つまり、AST・ALTの数値は肝臓へのダメージの程度を反映しているのです。
ただし、ASTは肝臓以外の筋肉や赤血球にも存在するため、ALTが正常値でASTだけが高い場合は、肝臓以外の原因も考えられます。
γ-GTP(ガンマ・ジーティーピー)
「γ-GTP」は、肝臓の解毒作用に関係する酵素です。
肝臓がダメージを受けているとき以外にも、胆道や膵臓の疾患で数値が高くなることがあります。
特にアルコールに敏感に反応する特徴があるため、日常的にお酒を飲んでいる方は数値が高くなりやすいです。
最近では、飲酒しない方でも肝臓に中性脂肪が溜まり、γ-GTPの数値が高くなるケースが増えています。
再検査が必要な数値の目安
健康診断で「要注意」と判定される数値は以下の通りです。
- AST:31〜50 U/L
- ALT:31〜50 U/L
- γ-GTP:51〜100 U/L
これらの数値が出た場合は、精密検査を受けることをおすすめします。
さらに、AST・ALTが51以上、γ-GTPが101以上の場合は「異常」と診断され、必ず精密検査が必要です。
医療機関での治療が必要なケースも考えられるため、数値を確認して早めに受診しましょう。
消化器内科での初診の流れ
肝機能異常を指摘されたら、消化器内科を受診しましょう。
初診では、まず受付で健康保険証と健康診断の結果を提出します。
健康診断の結果があると、医師にこれまでの数値の推移を正確に伝えることができるため、必ず持参してください。

問診票の記入
受付で問診票をお渡ししますので、以下の内容について記入していただきます。
- 現在の症状(倦怠感、食欲不振、腹部の違和感など)
- 症状が始まった時期
- 既往歴(過去にかかった病気)
- 服用中のお薬やサプリメント
- 飲酒習慣(頻度と量)
- 家族歴(肝臓病の家族がいるか)
症状の詳細をメモしておくと、医師に正確に伝えることができます。
医師による問診と身体診察
診察室では、まず医師が問診票をもとに詳しくお話を伺います。
「いつから症状がありますか?」「どのような時に不調を感じますか?」「食事との関連はありますか?」「便通はどうですか?」といった質問に答えていただきます。
問診の後、身体診察を行います。
腹部の視診(見て観察する)、聴診(聴診器で音を聞く)、触診(手で触れて確認する)などを行い、腹部の異常や腫瘤の有無などを確認します。
これらの問診と身体診察の結果から、必要な検査を判断します。
消化器内科で行う精密検査の順番
肝機能異常の原因を特定するため、段階的に検査を進めていきます。
ステップ1:血液検査
まず、詳細な血液検査を行います。
健康診断よりも詳しい項目を調べることで、肝臓の状態をより正確に把握できます。
具体的には、以下のような項目を測定します。
- 肝酵素(AST、ALT、γ-GTP、ALP、LAP)
- 黄疸の数値(ビリルビン)
- 肝臓の線維化や合成能(血小板数、プロトロンビン時間、アルブミン)
- ウイルス検査(B型肝炎、C型肝炎、EBウイルス、サイトメガロウイルスなど)
- 自己免疫反応の抗体
採血は腕の静脈から行い、痛みはほんの一瞬です。
結果は数時間から数日で出ますが、当院では迅速検査システムを導入しており、多くの項目は当日中に結果が出ます。
ステップ2:腹部超音波検査(エコー検査)
血液検査と並行して、腹部超音波検査を行います。
超音波を用いて肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腎臓などの臓器の状態を観察する検査です。
放射線被ばくがなく、痛みもない安全な検査方法です。
検査前に4〜6時間程度の絶食が必要な場合があります。
これは、胆のうの収縮状態や膵臓の観察をしやすくするためです。
検査時は、上半身を露出して検査台に仰向けに寝ていただきます。
お腹にゼリー状の超音波用ジェルを塗り、プローブと呼ばれる機器を当てて検査を行います。
検査時間は15〜20分程度です。
腹部超音波検査では、肝臓の脂肪化や腫瘤、胆石、膵臓の腫大や腫瘤、腎臓の結石や腫瘤などを発見することができます。

ステップ3:CT検査(必要に応じて)
超音波検査で異常が見つかった場合や、より詳しい画像診断が必要な場合は、CT検査を行います。
当院では院内にCTを完備しており、必要になったときには速やかにご案内できます。
胸部レントゲン同等の被ばく量で胸部CT検査が可能という特徴もあります。
CT検査では、肝臓の形状、脂肪肝の程度、腫瘍の有無、脾臓の腫れ、腹水の有無などを詳しく調べることができます。
また、閉塞性黄疸(胆石や腫瘍などにより胆汁の流れが悪くなる疾患)を除外するためにも有用です。
ステップ4:肝生検(原因不明の場合)
血液検査や画像検査を行っても原因が分からず、肝機能障害が改善しない場合に行うことがあります。
超音波検査で肝臓を確認した上で、腹部に生検針を刺し、組織の一部を採取します。
採取した組織を顕微鏡で観察することで、炎症や線維化の程度を正確に評価できます。
肝生検は入院が必要な検査のため、必要に応じて専門医療機関へご紹介することもあります。
肝機能異常の主な原因疾患
検査の結果、肝機能異常の原因として以下のような疾患が見つかることがあります。
非アルコール性脂肪肝炎(NAFLD/NASH)
肥満や糖尿病、脂質異常症などが原因で肝臓に脂肪が蓄積し、炎症や線維化を引き起こす疾患です。
近年増加している疾患の一つで、飲酒習慣がなくても発症します。
放置すると肝硬変や肝がんへ進行するリスクがあるため、早期発見と生活習慣の改善が重要です。
アルコール性肝障害
過度な飲酒により、肝臓がアルコールを分解する際にダメージを受けることで発症します。
脂肪肝、アルコール性肝炎、肝硬変へと進行することがあります。
治療の基本は禁酒であり、早期に飲酒をやめることで肝機能の改善が期待できます。
ウイルス性肝炎
B型肝炎ウイルス(HBV)やC型肝炎ウイルス(HCV)の感染が原因で肝臓に炎症を起こします。
慢性化すると肝硬変や肝がんのリスクが高まりますが、近年では抗ウイルス薬による治療が劇的に進歩しており、適切な治療で完治や病状のコントロールが可能になっています。
自己免疫性肝炎
免疫システムが肝臓を攻撃することで炎症を引き起こす疾患です。
血液検査で自己抗体が検出されることで診断されます。
ステロイド治療などの免疫抑制療法が有効です。
薬剤性肝障害
特定の薬剤やサプリメントの使用により、肝臓がダメージを受けることがあります。
原因となる薬剤の中止が治療の基本です。
普段服用している薬やサプリメントは、必ず医師に伝えるようにしましょう。
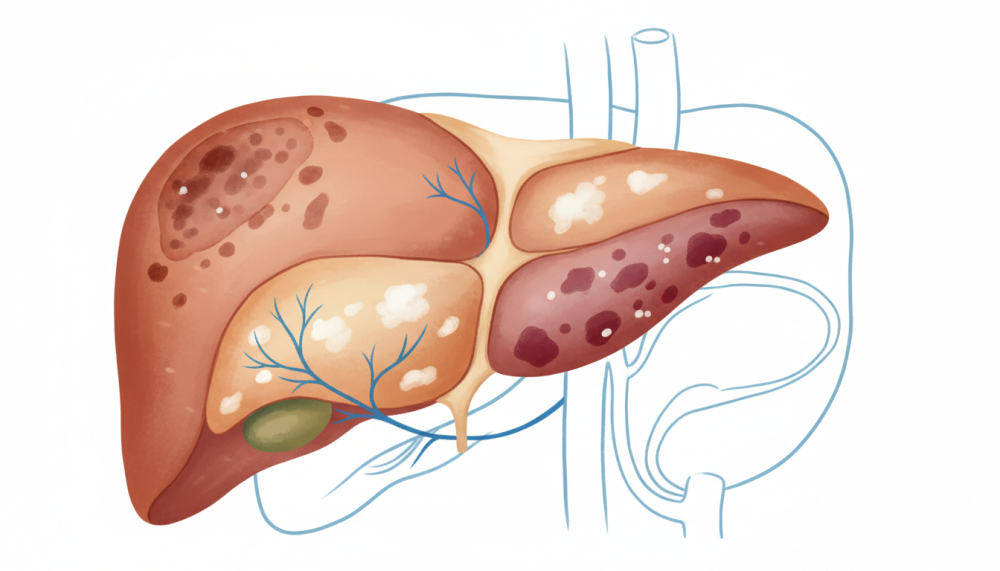
治療と生活習慣の改善
肝機能異常の治療は、原因に応じて異なります。
生活習慣の改善
多くの場合、生活習慣の改善が治療の基本となります。
- 飲酒の制限:アルコール性肝障害の場合は禁酒が必須です
- 食生活の見直し:バランスの取れた食事を心がけ、脂肪肝の改善を目指します
- 適度な運動:肥満や糖尿病がある場合、運動療法が効果的です
- 体重管理:肥満がある場合は、適正体重への減量が重要です
薬物療法
原因疾患に応じて、以下のような薬物療法を行います。
- 肝保護薬:肝臓の負担を軽減し、機能回復を促進します
- 抗ウイルス薬:ウイルス性肝炎の場合に使用します
- 免疫抑制薬:自己免疫性肝炎の場合に使用します
- 利尿剤や制酸薬:肝硬変の対症療法に使用します
定期的な経過観察
肝機能異常は、一度改善しても再び悪化することがあります。
そのため、定期的に血液検査や超音波検査を受けて、肝臓の状態を確認することが大切です。
特に、肥満や糖尿病、脂肪肝がある方は、肝線維化が進行する可能性があるため、継続的なフォローが必要です。
当院では、消化器・内視鏡専門医として、すべての診察、検査、検査結果説明までを担当いたしますので、安心してご相談ください。
放置すると危険な理由
肝機能異常を放置すると、どうなるのでしょうか?
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、症状が現れにくい臓器です。
初期段階では自覚症状がないことが多く、異常に気づいた時には病気がかなり進行していることがあります。
肝機能異常が続くと、以下のような経過をたどることがあります。
- 慢性肝炎:肝臓の炎症が6か月以上持続する状態
- 肝硬変:肝臓が硬くなり、機能が低下する状態
- 肝不全:肝臓の機能が著しく低下し、命に関わる状態
- 肝がん:肝臓に悪性腫瘍ができる状態
特に、肝硬変や肝がんに進行すると、完治することが難しくなります。
だからこそ、健康診断で異常を指摘されたら、すぐに消化器内科を受診して精密検査を受けることが重要なのです。
自覚症状が出た頃には、すでに病状が進行している可能性があります。
発熱、倦怠感、頭痛、褐色尿、黄疸、食欲不振などの症状が出たときには、かなり悪化していることが多いです。
まとめ
健康診断で肝機能異常を指摘されたら、放置せずに早めに消化器内科を受診しましょう。
肝臓は自覚症状が出にくい臓器ですが、放置すると肝硬変や肝がんといった重篤な病気へ進行するリスクがあります。
早期に原因を特定し、適切な治療や生活習慣の改善を行うことで、肝機能の回復や病状の進行を防ぐことができます。
消化器内科での精密検査は、血液検査、腹部超音波検査、必要に応じてCT検査や肝生検を段階的に行います。
これらの検査により、肝機能異常の原因を正確に特定し、最適な治療方針を決定します。
当院では、消化器・内視鏡専門医として、すべての診察、検査、検査結果説明までを担当いたします。
初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しており、お忙しい方でも受診しやすい環境を整えています。
肝機能異常でお悩みの方は、どうぞ安心してご相談ください。
詳しい検査や治療については、石川消化器内科内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
大腸ポリープ切除後の注意点|食事・運動・出血時の受診目安を徹底解説

大腸ポリープを切除された後、多くの患者様から「いつから普通の食事に戻れるの?」「運動はいつから再開できる?」「出血があったらどうすればいいの?」といった質問をいただきます。
大腸ポリープ切除は、大腸がんの予防に非常に有効な治療法です。
しかし、術後の過ごし方を誤ると、出血や穿孔といった合併症を引き起こす可能性があります。適切なケアと注意点を守ることで、安全に日常生活に戻ることができるのです。
この記事では、消化器・内視鏡専門医として数多くの大腸ポリープ切除を行ってきた経験から、術後の食事制限や運動制限、出血などの合併症が起きた際の受診タイミングについて詳しく解説します。安心して回復期間を過ごし、スムーズに日常生活に戻るための具体的なポイントを整理しました。
大腸ポリープ切除後の回復期間と基本的な注意点
大腸ポリープ切除後の回復期間は、切除したポリープの大きさや数、切除方法によって個人差があります。
一般的には、切除後1週間程度は特に注意が必要な期間となります。
大腸ポリープ切除後は、腸内に「傷」ができた状態です。
この傷が完全にふさがるまでには数日かかるため、特に術後2〜3日目は出血などの合併症が起こりやすい時期となります。切除部位は一時的に「潰瘍」のような状態になり、そこから出血することがあります。
安静期間の重要性
切除後当日から3日間は特に安静にし、激しい運動や腹圧がかかる行動を避けることが大切です。
この期間は出血のリスクが比較的高いため、無理をしないことが重要です。
安静期間中に避けるべき行動として、以下のようなものがあります。
- 飲酒 ・・・ 血管を拡張させ、出血を助長する作用があります
- 激しい運動 ・・・ 腹圧がかかり、切除部位に負担をかけます
- 長距離の移動 ・・・ 特に飛行機は気圧変化により腸に圧力がかかります
- 長時間の入浴やサウナ ・・・ 体を過度に温めると血流が増加し、出血リスクが高まります
切除方法による違い
大腸ポリープの切除方法には、主に「コールドポリペクトミー(CSP)」と「内視鏡的粘膜切除術(EMR)」があります。
コールドポリペクトミーは、高周波電流のような熱を加えずに切除する方法で、10mm未満の小さな腫瘍性ポリープに適応されます。
この方法は出血や穿孔のリスクが比較的低く、後出血率は0%というデータもあります。
一方、EMRは高周波電流を使用するため、切除部位が熱傷になり、粘膜下層まで影響が及びます。そのため、出血率は1.1%から1.7%程度と報告されています。
切除方法によって注意期間も異なり、コールドポリペクトミーの場合は3日間、EMRの場合は1週間程度の注意が必要です。
大腸ポリープ切除後の食事で気をつけるべきこと
大腸ポリープ切除後の食事は、腸への負担を最小限に抑えることが重要です。
切除部位はまだ傷がある状態なので、消化に良い食事を心がけましょう。
硬いものや繊維の多い食べ物が腸を通ると、切除した傷をこすって出血を引き起こす可能性があります。

切除直後の食事メニュー
切除直後の1〜2日間は特に注意が必要です。
おすすめの食事メニューとしては、以下のようなものが挙げられます。
- おかゆやうどん ・・・ 柔らかい炭水化物で消化に優しい
- 豆腐や白身魚 ・・・ 消化の良いタンパク源
- 野菜スープ ・・・ 形を細かくした野菜で栄養補給
- ヨーグルトやバナナ ・・・ 腸に優しい食品
避けるべき食品
この時期に避けるべき食品としては、以下のようなものがあります。
- 油分の多い揚げ物や脂っこい食べ物 ・・・ 消化に時間がかかり、腸に負担をかけます
- 唐辛子やカレー粉などの刺激の強い香辛料 ・・・ 腸の粘膜に炎症を起こしやすい
- アルコール飲料や炭酸飲料 ・・・ 血管を拡張させ、出血リスクを高めます
- 生野菜やキノコ類、海藻類 ・・・ 食物繊維が多く、傷をこする可能性があります
水分補給と便秘予防
水分も積極的に摂取し、便秘を予防することも大切です。
便が硬くなると排便時に腸に負担がかかり、出血のリスクが高まる可能性があります。
ただし、過度な食事制限は栄養不足を招く恐れもあります。
ポリープの大きさや切除方法によって異なりますが、一般的には術後3日目以降から徐々に通常の食事に戻していくことが可能です。
まずは消化の良いものから始めて、様子を見ながら食べられるものを増やしていきましょう。
運動や入浴はいつから再開できる?
大腸ポリープ切除後の運動再開については、多くの患者様から質問を受けます。
運動をすると血流が増え、血圧も上がります。
それによって、腸の切除部位にあるかさぶたがはがれ、再出血のリスクが高まる可能性があるのです。
特に腹圧がかかる運動は、創部への圧力が直接的にかかるため危険です。

運動再開の段階的アプローチ
運動再開の目安としては、以下のようなステップを踏むことをお勧めします。
- 術後3日間程度 ・・・ 安静にし、運動は控える
- 術後4日目〜1週間程度 ・・・ 体調が安定していれば、散歩や軽いストレッチなどの軽い運動から始める
- 術後1週間以降 ・・・ ジョギング、ゴルフ、テニス、筋力トレーニングなどの激しい運動や腹圧のかかる運動は、医師の許可を得てから再開する
「発汗を伴うような運動」が一つの目安となることもあります。
入浴とサウナの注意点
入浴についても注意が必要です。
長時間の入浴やサウナは血行が促進され、再出血の可能性が高まります。
術後2日目以降に短時間のシャワーから始め、1週間程度経過してから湯船に浸かるという段階的なアプローチが安全です。
ただし、サウナや岩盤浴などは術後2週間程度は避けるのが無難でしょう。
アルコールとカフェインの摂取
アルコールやカフェインの摂取再開も慎重に行う必要があります。
アルコールは血管を拡張させ、出血を助長する作用があります。
特に赤ワインやビールなどの発酵酒は刺激が強いため、術後最低でも1週間は控えることをお勧めします。
コーヒーなどのカフェインを含む飲み物も腸を刺激する作用があるため、数日程度は控え、再開するときも薄めのものから少量ずつ様子を見ながら飲むようにしましょう。
仕事復帰と日常生活への戻り方
「大腸ポリープを切除したけれど、立ち仕事っていつからできるの?」
「デスクワークなら明日から大丈夫?」このような質問をよく受けます。
仕事復帰のタイミングは、仕事の内容や個人の回復状況によって異なります。
デスクワークの場合
身体への負担が少ないデスクワークであれば、翌日から可能なケースもあります。
ただし、体調には十分注意し、お腹の張りや違和感、出血などがないかを確認しながら、無理のない範囲で進めましょう。
長時間座りっぱなしは避け、適度に休憩を取ることも大切です。
腹圧がかかる仕事の場合
介護職、運送業、建設業など、重い物を持ったり、お腹に力が入ったりする仕事の場合は、少なくとも3日〜1週間程度は避けるのが賢明です。
クリニックによっては、10日間程度の安静を指示されることもあります。
必ず医師に確認し、許可を得てから復帰するようにしてください。
復帰後も、しばらくは体調の変化に気を配り、出血や強い腹痛など異変を感じた場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
日常生活での注意点
日常生活では、排便時の強い努責を避けることも重要です。
便秘にならないよう水分を十分に摂取し、必要に応じて医師に相談して緩下剤を使用することも検討しましょう。
また、性行為についても、術後1週間程度は控えるよう指示されることが多いです。
これは、性行為によって腹圧が上昇し、出血のリスクを高める可能性があるためです。
大腸ポリープ切除後の出血:色・量・続く期間の目安
大腸ポリープを切除された後、多くの方が気になるのが「出血」の問題です。
切除後はある程度の出血が起こりうるものですが、その色や量、続く期間によっては注意が必要な場合もあります。

出血が起こる理由と時期
大腸ポリープは、大腸の粘膜からキノコのように盛り上がったものです。
これを内視鏡で切り取るわけですから、多かれ少なかれ出血するのは自然なことです。
切除した部分は一時的に「傷」や「潰瘍」のような状態になり、そこから出血することがあります。
ポリープには栄養を送るための血管が存在し、特に茎が太いポリープや大きなポリープでは、内部の血管も太く、出血のリスクがやや高まることがあります。
出血しやすい期間として、治療後24時間以内が最も出血が起こりやすい期間です。
特に切除当日の夜間から翌朝の排便時に出血が見られることが多いとされています。
治療後1週間程度は遅発性の出血にも注意が必要で、稀に2週間程度後にかさぶたが剥がれるようにして出血することもあります。
一般的に、術後1週間を過ぎると出血のリスクはかなり低くなり、0%に近づくとされています。
比較的心配の少ない出血の目安
排便時に出血が見られたら、まずは慌てずにその「色」と「量」を確認しましょう。
比較的心配の少ない出血としては、以下のようなものがあります。
- トイレットペーパーに鮮血が少量付着する程度
- 便の表面に、筋状に少量の血液が付着している
- ごく少量の暗赤色の血の塊が少量混じる程度で、すぐに出血が止まる
このような場合は、多くが自然に止血するため、過度な心配は不要なことが多いです。
できるだけ安静にし、無理な動きを避け、引き続き便の状態を観察しましょう。
注意が必要な出血・病院へ連絡すべきサイン
以下のような出血の場合は、自己判断せずに速やかに手術を受けた医療機関に連絡し、指示を仰いでください。
- 便全体が赤黒い血液に染まっている
- 鮮血がポタポタと垂れる、またはシャーっと出る
- 何度も血便が続く
- 生理の多い日のような出血量
- 1日に何度もトイレットペーパーが真っ赤になるほどの出血がある
- 持続する腹痛、または徐々に強くなる腹痛がある
- めまい、ふらつき、立ちくらみ、顔面蒼白、冷や汗、動悸、息切れなど貧血を疑う症状がある
特に注意すべきサイン(緊急性が高い可能性)
便器が真っ赤に染まるほど多量の鮮血が出る、意識が遠のく感じがする、我慢できないほどの強い腹痛、冷や汗が止まらないといった症状がある場合は、夜間や休日であってもためらわずに、手術を受けた医療機関の緊急連絡先に連絡するか、救急病院を受診してください。
状況によっては救急車の要請も考慮しましょう。
出血した場合の病院での対応と治療法
万が一、ポリープ切除後に出血が続いたり、量が多い場合は、適切な処置が必要です。
まずはクリニックへ連絡
自己判断せず、まずは手術を受けた医療機関に連絡しましょう。
夜間や休診日であっても、緊急連絡先が案内されているはずです。
電話で状況を説明し、指示を仰いでください。
出血の色、量、頻度、その他の症状(腹痛、めまいなど)を具体的に伝えることが重要です。
病院での対応
少量の出血であれば、経過観察で止血されることがほとんどです。
患者様はこの間、安静に過ごし、無理な動きを避けることが重要です。
一方で、予期しない痛みや一時間に複数回トイレに行く程の出血が見られた場合は、すぐに医師に連絡する必要があります。
比較的多くのケースでは、内視鏡を用いた止血処置が取られます。
この方法は、出血箇所を直接観察しながら行うため、非常に効果的です。
内視鏡下でクリップや高周波を用いて止血を行うことができます。
稀に輸血を要する出血もありますが、適切な処置により多くの場合は回復します。
大腸ポリープ切除の合併症とリスク要因
大腸ポリープ切除後の合併症として最も多いのが出血です。
その他にも、穿孔(大腸の壁に穴があくこと)や腹痛などがあります。
特に高齢者や抗血栓薬を内服中の患者様は、合併症のリスクが高まることが知られています。
出血リスクが高まる要因
以下のような要因がある場合、出血リスクが高まります。
- 抗血栓薬の内服 ・・・ 血液をサラサラにする薬を服用している場合
- 高齢者 ・・・ 加齢により血管の脆弱性が増すため
- いきみやアルコール ・・・ 腹圧の上昇や血管拡張により出血リスクが高まる
切除方法による合併症率の違い
コールドポリペクトミーは、EMRと比較して後出血率が低いことが報告されています。
コールドポリペクトミーの後出血率は0%で、遅発性穿孔は認めなかったというデータがあり、大きな合併症は少ないです。
これは、熱を使わずにポリープを切除するため、EMRに比べ合併症が少ないといわれております。
一方、EMRの場合は出血率が1.1%から1.7%程度と報告されています。
大腸がん予防のための定期検診の重要性
大腸ポリープ切除は、大腸がん予防に非常に有効です。
大腸がんの多くは大腸ポリープから派生すると考えられており、大腸ポリープ切除により53%の大腸がん死亡を予防できるという報告もあります。
早期発見のメリット
早期発見がなぜ重要かというと、小さいうちに腫瘍性ポリープを摘除することにより、大腸がん発生の予防につながるからです。
症状が起きないうちから大腸カメラを受けることが推奨されます。
大腸がんは早期の段階では自覚症状はほとんどありません。
進行すると、便に血が混じる(血便や下血)、便の表面に血液が付着するなどの症状があらわれます。
定期検診の頻度
大腸ポリープを切除した後は、定期的な検診が重要です。
ポリープの大きさや数、組織型によって異なりますが、一般的には1〜3年ごとの大腸カメラ検査が推奨されます。
医師の指示に従い、定期的な検診を受けることで、再発や新たなポリープの早期発見につながります。
まとめ:安心して回復期間を過ごすために
大腸ポリープ切除後の注意点について、詳しく解説してきました。
術後の過ごし方を適切に守ることで、合併症を予防し、安全に日常生活に戻ることができます。
重要なポイントをまとめると、以下のようになります。
- 安静期間 ・・・ 術後3日間は特に安静にし、激しい運動や腹圧がかかる行動を避ける
- 食事 ・・・ 消化に良い食事を心がけ、刺激物や食物繊維の多い食品は避ける
- 運動 ・・・ 段階的に再開し、激しい運動は医師の許可を得てから
- 出血 ・・・ 少量の出血は経過観察で問題ないが、多量の出血や持続する出血は速やかに受診
- 定期検診 ・・・ 再発予防のため、医師の指示に従い定期的な検診を受ける
最も大切なのは自己判断せず、必ず担当医の指示に従うことです。
不安なことや気になる症状があれば、ためらわずに医療機関にご相談ください。
当院では、消化器・内視鏡専門医がすべての診察、検査、検査結果説明までを担当いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
大腸ポリープ切除後の詳しい注意点や、無痛での内視鏡検査については、石川消化器内科内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
内視鏡検査は朝イチがベスト?予約時間・食事制限・仕事調整の完全ガイド

目次
- 朝イチ予約のメリットとデメリット
- 胃カメラと大腸カメラで異なる予約時間の選び方
- 前日の食事制限を成功させるコツ
- 当日の下剤服用と来院タイミング
- 鎮静剤使用時の注意事項と帰宅後の過ごし方
- よくある質問と回答
📞 お問い合わせ・ご予約
石川消化器内科内視鏡クリニック
📍 大阪市城東区「蒲生四丁目駅」5番出口すぐ
内視鏡検査を受けることが決まったとき、「何時に予約すればいいの?」「前日は何を食べたらいいの?」と不安になる方は多いです。
検査の予約時間によって、準備の仕方や当日のスケジュールが大きく変わります。
この記事では、消化器内視鏡専門医として数多くの検査を行ってきた経験から、最適な予約時間の選び方や前日の食事制限、仕事との調整方法まで詳しく解説します。
検査をスムーズに受けるための段取りを、医療現場の実情に基づいてお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
朝イチ予約のメリットとデメリット
内視鏡検査の予約時間として「朝イチ」を選ぶ方は少なくありません。
朝の早い時間帯に検査を受けることには、いくつかのメリットがあります。
朝イチ予約の主なメリット
まず、空腹時間が短く済むという点が大きな利点です。
前日の夜から絶食が必要な内視鏡検査では、朝早い時間に検査を受けることで、空腹を我慢する時間を最小限に抑えられます。
午前9時30分や10時30分に検査を受ければ、11時から12時頃にはご帰宅いただけます。
次に、午後の時間を有効活用できるという利点があります。
仕事が忙しい方や子育て中の方にとって、丸1日を検査で費やすのは負担が大きいです。
朝イチの検査なら、午後からは通常の予定を入れることが可能です。
さらに、検査前の不安な時間が短いというメリットもあります。
検査を待つ時間が長いほど、緊張や不安が増してしまうものです。
朝イチであれば、起きてすぐに検査に向かえるため、心理的な負担も軽減されます。
朝イチ予約の注意点
一方で、朝イチ予約にはいくつかの注意点もあります。
早朝からの準備が必要という点です。
大腸カメラ検査の場合、検査の4時間前から下剤を服用する必要があります。
9時30分の検査であれば、朝5時30分頃から下剤を飲み始めることになります。
また、朝の通勤ラッシュと重なる可能性があります。
都市部では朝の移動が混雑するため、余裕を持った移動計画が必要です。
鎮静剤使用後の運転制限も考慮すべき点です。
検査で鎮静剤を使用した場合、当日の車・バイク・自転車の運転はできません。
朝イチの検査でも、この制限は変わりませんので、ご家族の送迎や公共交通機関の利用を検討してください。
胃カメラと大腸カメラで異なる予約時間の選び方
内視鏡検査には「胃カメラ」と「大腸カメラ」があります。
それぞれ準備方法が異なるため、最適な予約時間も変わってきます。

胃カメラ検査の予約時間
胃カメラ検査は、午前中の予約が一般的です。
検査前日の夜9時頃までに消化の良い夕食を済ませ、当日の朝は絶食で来院します。
検査自体は20分程度で終わり、検査後1時間ほどで食事が可能になります。
午前中に検査を受ければ、昼食から通常の食事に戻れるため、生活リズムへの影響が最小限です。
ただし、午後に検査を受ける場合は、朝食を検査の6時間以上前に済ませる必要があります。
大腸カメラ検査の予約時間
大腸カメラ検査では、朝イチから午前中の予約が推奨されます。
検査3日前から食物繊維の多い食品を控え、前日は消化の良い食事に限定します。
当日は検査の4時間前から下剤を服用し、便の状態が適切になったら来院します。
朝イチの検査であれば、早朝から下剤を飲み始め、午前中に検査を終えることができます。
検査後は通常の食事が可能ですが、ポリープ切除を行った場合は、飲酒や激しい運動を控える必要があります。
仕事との調整を考えた予約時間
仕事をされている方にとって、検査のための休みをどう取るかは重要な問題です。
胃カメラ検査なら、午前中に検査を受けて午後から出勤することも可能です。
ただし、鎮静剤を使用した場合は、検査後の眠気や集中力の低下を考慮し、半日休みを取ることをお勧めします。
大腸カメラ検査の場合は、丸1日の休みを取るのが理想的です。
下剤の服用から検査、検査後の体調回復までを考えると、無理に仕事を入れない方が安全です。
前日の食事制限を成功させるコツ
内視鏡検査の精度を高めるためには、前日の食事制限が非常に重要です。
適切な食事制限ができていないと、検査がスムーズに進まず、再検査が必要になることもあります。
胃カメラ検査前日の食事
胃カメラ検査の前日は、消化の良い食事を心がけることが基本です。
おかゆ、うどん、白身魚、豆腐、卵など、脂肪分や食物繊維が少ない食品を選びます。
前日の夕食は20時までに済ませ、それ以降は水やお茶、スポーツドリンクのみ摂取可能です。
避けるべき食品は、脂身の多い肉、揚げ物、きのこ、海藻、豆類、乳製品などです。
これらは胃の中に残りやすく、検査の妨げになります。

大腸カメラ検査前日の食事
大腸カメラ検査では、検査3日前から食事制限が始まります。
検査3日前からは、こんにゃく、海藻、きのこ、繊維質の多い野菜、乳製品、玄米などを控えます。
前日の夕食は20時までに済ませ、消化の良い食事または検査食を摂取します。
食べて良いものは、白米、おかゆ、うどん、そうめん、白身魚、鶏むね肉、豆腐、じゃがいも、バナナなどです。
前日の夕食後は、水やお茶、スポーツドリンクを積極的に摂取し、腸内をきれいにする準備をします。
食事制限中の注意点
食事制限中は、水分補給を十分に行うことが大切です。
特に大腸カメラ検査では、下剤の効果を高めるために、前日から当日にかけて2リットル程度の水分摂取が推奨されます。
ただし、牛乳やコーヒー、アルコールは避けてください。
また、普段服用している薬は医師の指示に従うことが重要です。
血圧の薬や心臓の薬など、継続が必要な薬もあれば、休薬が必要な薬もあります。
事前の診察時に必ず確認しましょう。
当日の下剤服用と来院タイミング
大腸カメラ検査では、当日の下剤服用が避けられません。
下剤の飲み方と来院タイミングが、検査の成否を左右します。
下剤服用の基本的な流れ
当日は検査の4時間前から下剤を服用します。
9時30分の検査であれば、朝5時30分頃から下剤を飲み始めます。
下剤は1時間から2時間かけて、指示された量を少しずつ飲んでいきます。
下剤を飲み始めてから1時間から2時間後に、便意を感じ始めます。
その後、何度もトイレに行くことになりますので、自宅で落ち着いて過ごせる環境を整えておくことが大切です。
適切な便の状態とは
検査に適した便の状態は、透明から薄い黄色の水様便です。
便に固形物が混じっていたり、茶色い色が残っていたりする場合は、まだ腸内が十分にきれいになっていません。
この状態で検査を受けると、観察が不十分になり、病変を見逃す可能性があります。
適切な便の状態になったら、クリニックに連絡して来院します。
検査の15分前には到着するようにしましょう。
院内で下剤を服用する選択肢
当院では、**トイレ付き個室で下剤を服用できる体制**を整えています。
自宅のトイレ環境に不安がある方や、通勤途中でトイレに行きたくなるのが心配な方は、院内での下剤服用をお勧めします。
事前にご相談いただければ、スケジュールを調整いたします。
鎮静剤使用時の注意事項と帰宅後の過ごし方
内視鏡検査では、苦痛を軽減するために鎮静剤を使用することがあります。
鎮静剤の使用には、いくつかの注意事項があります。

鎮静剤使用時の運転制限
鎮静剤を使用した場合、当日の車・バイク・自転車の運転は禁止です。
鎮静剤の効果は個人差がありますが、検査後数時間は眠気やふらつきが残ることがあります。
安全のため、ご家族の送迎や公共交通機関の利用を計画してください。
また、検査当日は重要な判断を伴う仕事や、危険を伴う作業も避けるべきです。
鎮静剤の影響で集中力や判断力が低下している可能性があるためです。
検査後の食事と過ごし方
胃カメラ検査後は、1時間ほど経過してから食事が可能です。
組織採取を行った場合は、刺激の強い食べ物や熱いものは避け、消化の良い食事から始めます。
油分の多い食事や過度の飲酒も控えてください。
大腸カメラ検査後は、通常の食事が可能ですが、ポリープ切除を行った場合は特別な注意が必要です。
飲酒や激しい運動は1週間程度控え、出血や腹痛などの症状があれば、すぐにクリニックに連絡してください。
検査結果の説明
検査後は、リカバリー室で休んでいただいた後、結果説明を行います。
当院では、すべての診察、検査、検査結果説明を院長が担当しますので、安心してご相談いただけます。
検査で採取した組織の病理検査結果は、約1か月後の外来時に説明いたします。
よくある質問と回答
内視鏡検査について、患者様からよくいただく質問をまとめました。
Q1. 検査前日にお酒は飲んでも良いですか?
**少量であれば問題ありません**。
ビール350ml程度、ハイボールやワインならグラス2杯程度が目安です。
ただし、大量の飲酒は検査の精度に影響しますので、控えめにしてください。
Q2. 検査当日に薬を飲んでも良いですか?
**医師の指示に従ってください**。
血圧の薬や心臓の薬など、継続が必要な薬もあります。
一方、糖尿病の薬やインスリンは、検査当日朝の使用を中止します。
事前の診察時に、服用している薬をすべて医師に伝えてください。
Q3. 生理中でも検査は受けられますか?
**胃カメラ検査は問題なく受けられます**。
大腸カメラ検査も基本的には可能ですが、生理の状態によっては延期をお勧めすることもあります。
ご予約時にご相談ください。
Q4. 検査後すぐに仕事に戻れますか?
**鎮静剤を使用しない場合は可能です**。
ただし、鎮静剤を使用した場合は、眠気やふらつきが残る可能性があるため、半日から1日の休みを取ることをお勧めします。
検査の種類や体調によっても異なりますので、事前に医師にご相談ください。
まとめ:あなたに最適な予約時間を選ぶために
内視鏡検査の予約時間は、検査の種類や生活スタイルによって最適な選択が異なります。
朝イチの予約は、空腹時間が短く午後の時間を有効活用できるメリットがありますが、早朝からの準備が必要です。
胃カメラ検査なら午前中の予約が一般的で、大腸カメラ検査では朝イチから午前中の予約が推奨されます。
前日の食事制限は検査の精度を左右する重要な要素です。
消化の良い食事を心がけ、水分補給を十分に行いましょう。
当日の下剤服用では、適切な便の状態になるまで自宅で落ち着いて過ごすことが大切です。
鎮静剤を使用する場合は、当日の運転制限や検査後の過ごし方に注意が必要です。
検査後は医師の指示に従い、無理のない範囲で日常生活に戻ってください。
当院では、患者様が安心して検査を受けられるよう、さまざまな工夫を行っています。
初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しており、お忙しい方でも受診しやすい環境を整えています。
内視鏡検査に関するご不安やご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。
消化器・内視鏡専門医として、すべての診察、検査、検査結果説明を担当いたします。
詳しい検査内容や予約方法については、石川消化器内科内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
胃カメラの結果「異常なし」でも症状が続くときの次の一手|追加検査と受診タイミング
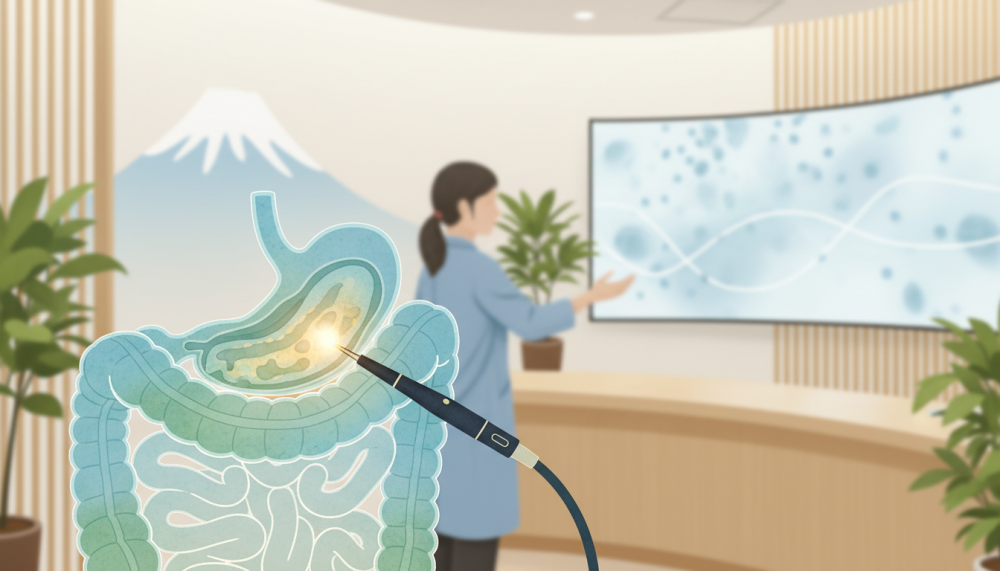
胃カメラ検査を受けて「異常なし」と言われたのに、胃もたれや胸やけ、みぞおちの痛みが続いている・・・
そんな経験はありませんか?
検査で異常が見つからないと、「気のせい」と思われがちですが、決してそうではありません。胃カメラで映らない疾患や、胃の機能的な問題が隠れている可能性があります。
消化器内科医として多くの患者様を診てきた経験から、「異常なし」と言われた後も症状が続く場合、次に何をすべきか、どのタイミングで受診すべきかを丁寧に解説します。
胃カメラで「異常なし」と言われる理由
胃カメラ検査は、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察する有用な検査です。
逆流性食道炎、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、食道がんなど、粘膜に明らかな変化がある疾患を診断できます。

しかし、胃カメラはあくまで「構造(形)に異常があるか」を確認する検査です。
つまり、粘膜に傷や腫瘍、明らかな炎症がなければ、「異常なし」と判定されます。
ここに落とし穴があります。胃の「動き」や「知覚」の異常は、胃カメラでは映らないのです。
胃カメラでわかること・わからないこと
胃カメラでわかることは、粘膜の状態です。炎症、潰瘍、ポリープ、がんなど、目に見える変化を捉えます。
胃カメラでわからないことは、胃の運動機能や知覚の異常です。胃の動きが悪い、胃酸に過敏になっている、といった機能的な問題は画像では判断できません。
また、胃以外の臓器(胆のう、膵臓、心臓など)が原因で胃の症状が出ている場合も、胃カメラだけでは見つかりません。
「異常なし」でも症状が続く原因
胃カメラで異常が見つからないのに症状が続く場合、いくつかの可能性が考えられます。
機能性ディスペプシア(FD)
多くの場合、「機能性ディスペプシア」が原因です。
これは、胃の動きや知覚の異常によって症状が出る病気で、近年増えています。国内の10人に1人が該当すると言われており、受診に至っていない方も少なくありません。
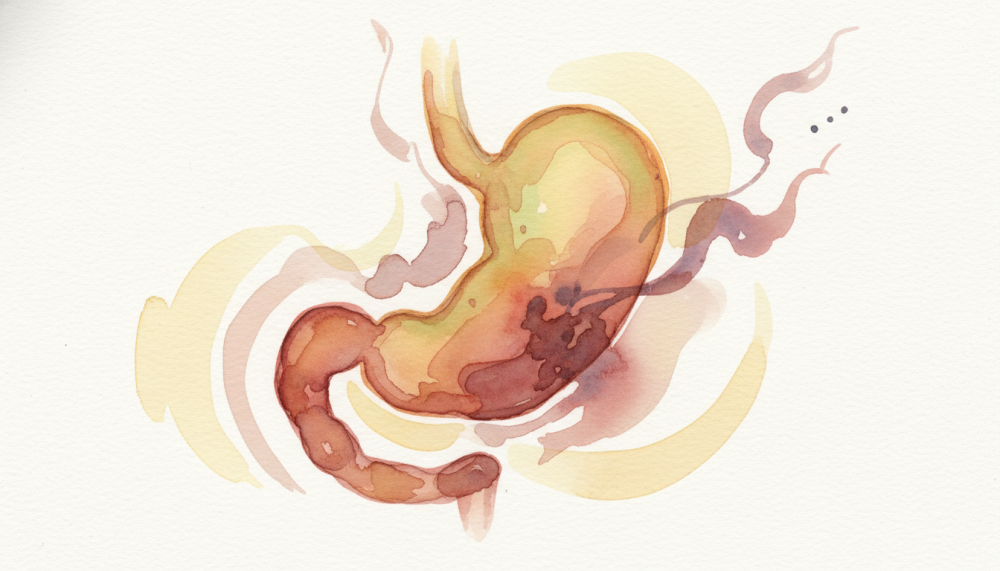
機能性ディスペプシアの主な症状
- 食後すぐにお腹がいっぱいになる
- 少量で苦しくなる
- 胃の上の方が痛む・焼ける
- 空腹時や緊張時に胃が不快になる
- 食後の胃もたれが続く
機能性ディスペプシアには、大きく分けて2つのタイプがあります。
食後愁訴症候群(PDS)は、食後に胃がもたれたり、すぐにお腹いっぱいになるタイプです。胃の排出機能の低下や、胃の拡張反応の異常が原因と考えられています。
心窩部痛症候群(EPS)は、空腹時にみぞおちが痛くなったり、チクチク・シクシクするタイプです。胃の知覚過敏が主な原因で、通常では痛みを感じない程度の刺激でも過敏に反応してしまいます。
実際には、この2つのタイプが混在することも珍しくありません。
胃以外の原因
胃の症状だと思っていても、実際は胃以外が原因のこともあります。
胆のう疾患(胆石、胆のう炎)は、みぞおちの痛みや吐き気を伴います。特に脂っこい食事の後に症状が出やすいのが特徴です。
膵炎は、胃痛に似た痛みが背中まで響くことがあります。
食道アカラシア・機能性食道障害は、飲み込みづらさや胸の詰まり感を引き起こします。
心因性(ストレス、うつ、パニック障害)の場合、胃に症状が集中しやすくなります。自律神経の乱れが胃の機能に影響を与えるためです。
心臓疾患(狭心症など)も、みぞおちや上腹部の痛みとして出ることがあります。
このように、「胃が原因だと思っていたら別の臓器だった」というケースも珍しくありません。
次に検討すべき検査
胃カメラで異常が見つからなかった場合、次に検討すべき検査があります。
ピロリ菌検査
胃カメラでピロリ菌感染を「疑う」ことは可能ですが、確定診断には検査が必要です。

ピロリ菌は、胃の粘膜にすみつく細菌で、多くは幼少期に感染します。一度感染すると自然には消えず、慢性的な胃の炎症を引き起こし、長期的には胃潰瘍・十二指腸潰瘍・慢性胃炎、そして胃がんの発症リスクを高めます。
ピロリ菌は抗生物質と胃酸を抑える薬を組み合わせた内服治療で除菌できます。除菌治療を保険で行うには、事前に胃カメラで「胃炎の所見がある」かつ「その他検査でピロリ菌陽性」を確認する必要があります。
ピロリ菌を放置すると、加齢とともに胃の粘膜が萎縮し、胃がんのリスクが高まります。早めの検査と除菌が大切です。
腹部エコー検査
腹部エコー検査は、肝臓、胆のう、総胆管、膵臓、大腸・小腸など、胃の近辺の臓器の異常の有無を調べます。
胆石や胆のう炎、膵炎などが見つかることがあります。
CT検査
胃カメラ検査、超音波検査の上、精密検査としてCT検査が必要になることがあります。
全身の断層像だけでなく、3Dの立体像で鮮明な画像が取得でき、肺などの胸部の病変、肝臓・腎臓などの腹部の病変の早期発見に役立ちます。
当院では、GEヘルスケア社製の16列CT装置「Revolution ACT」を導入しており、撮影時間が短いため、被ばく量も最小限に抑えられます。
血液検査
貧血、肝機能、膵酵素、炎症反応などを調べることで、胃以外の臓器の異常を見つけることができます。
受診の緊急性を見分けるポイント
症状が続いている場合、どのタイミングで受診すべきか悩む方も多いでしょう。
以下のような症状がある場合は、早めの受診をおすすめします。
すぐに受診すべき症状
- 血便や黒い便(タール便)が出た
- 体重が急激に減少している
- 貧血が進行している
- 激しい腹痛が続く
- 吐血があった
- 嚥下困難(飲み込みにくさ)がある
これらの症状は、重大な病気のサインである可能性があります。すぐに医療機関を受診しましょう。
早めの受診を検討すべき症状
- 市販薬を服用しても症状が全く治らない
- 症状が数週間以上続いている
- 症状が徐々に悪化している
- 食欲不振が続き、栄養が不足している
- 日常生活に支障が出ている
これらの症状がある場合は、早めに専門医に相談することをおすすめします。

受診時に持参すべきもの
受診時には、以下のものを持参すると診察がスムーズに進みます。
過去の検査結果
胃カメラの検査結果、血液検査の結果、CT検査の画像など、過去の検査結果をすべて持参してください。
検査結果の推移を見ることで、より正確な診断が可能になります。
症状の記録
いつ、どんなタイミングで症状が出るのか、症状の詳細を記録しておくと、医師に伝えやすくなります。
- 食前or食後に症状が起こる
- 起きてすぐ胃がむかつく
- 夕方になると決まって痛む
- ストレスで症状が強くなる
- 症状が断続的か継続的か
症状の記録があると、根本にある原因を特定しやすくなります。
服用中の薬
現在服用している薬(市販薬を含む)をすべて伝えてください。
お薬手帳があれば持参してください。
機能性ディスペプシアの治療法
機能性ディスペプシアと診断された場合、以下のような治療法があります。
生活習慣の改善
機能性ディスペプシアの原因となる生活習慣の乱れを改善します。
- 暴飲・暴食・早食いを避ける
- 脂っこいもの・刺激物を摂り過ぎない
- 十分に睡眠を摂る
- 規則正しい生活を送る
- ストレスを上手に解消する
これらの改善だけで症状が軽減することもあります。
薬物療法
消化管の蠕動運動を改善する薬、胃酸の分泌を抑える薬などを使用します。
また、六君子湯・半夏瀉心湯・半夏厚朴湯といった漢方薬、抗うつ剤・抗不安薬が有効になることもあります。
患者様の症状に合わせて、最適な薬を選択します。
ピロリ菌の除菌治療
ピロリ菌の感染が認められる場合には、その除菌治療を行うことで、症状の改善が期待できます。
除菌治療では、胃酸の分泌を抑制する薬1種類と、抗生物質2種類を、連日1週間内服します。
当院での取り組み
大阪消化器内科・内視鏡クリニックでは、日本内視鏡学会の内視鏡専門医による、鎮静剤を用いた胃カメラ検査・大腸カメラ検査を行っています。
豊富な経験と知識を持つ医師の丁寧な操作、苦痛・不安を和らげる鎮静剤が、患者様のご負担を最小限に抑えます。
検査前後にはお一人おひとり、分かりやすく丁寧な説明をいたしますので、ご理解・ご納得して検査を受けていただけます。
また内視鏡は、オリンパス社製の最上位機種「EVIS X1」を導入しております。特殊な光で病変部を強調する機能、拡大観察できる機能が、胃がん・大腸がんをはじめとする疾患の早期発見を可能とします。
胃カメラ検査・大腸カメラ検査の「辛い・苦しい」というイメージを払拭する決意ですので、どうぞ安心して、お気軽にご相談ください。
検査後、精密検査・入院治療が必要になった場合は、速やかに高度医療機関と連携します。当院は内視鏡検査に注力したクリニックですが、「検査の受けっぱなし」で終わることなく、必要な医療がお届けできるよう万全のフォローをいたします。
まとめ
胃カメラで「異常なし」と言われても、症状が続く場合は決して「気のせい」ではありません。
機能性ディスペプシアや胃以外の臓器の病気が隠れている可能性があります。
症状が続いている場合は、追加検査や継続的なフォローを受けることが大切です。
ピロリ菌検査、腹部エコー検査、CT検査、血液検査など、必要な検査を適切に受けることで、原因を特定し、適切な治療につなげることができます。
当院では、検査後も症状に合わせたきめ細やかな治療を重視しています。単に「異常なし」と伝えて終わりではなく、つらさの背景まで丁寧に考える診療を行います。
『検査をしたのに解決しない』という不安も、ぜひご相談ください。
詳しくは、大阪消化器内科内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。
なんば駅から駅直結ビルで、平日・土日祝日も診療しています(9:00~17:00)。電話・Web予約も可能です。
胃の不調でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
便潜血陽性後の大腸カメラはいつ受ける?放置リスクと受診先の選び方
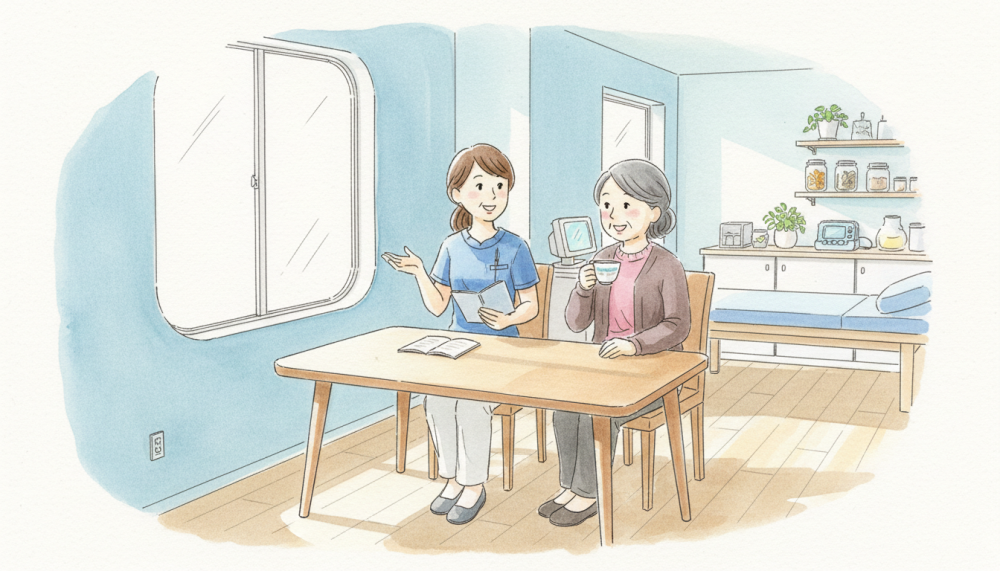
健康診断で「便潜血陽性」と判定されたら、不安になりますよね。
「いつまでに検査を受ければいいの?」「少し様子を見てもいいかな?」そんな疑問を抱く方は少なくありません。
実は、便潜血陽性後の精密検査受診率は約70%にとどまっており、残りの約30%の方が精密検査を受けないまま放置している現状があります。しかし、この「放置」が、命に関わる大きなリスクを生むことをご存じでしょうか。
消化器内科・内視鏡専門医として、これまで多くの患者様の大腸カメラ検査を担当してきた経験から、便潜血陽性後の適切な対応について詳しく解説します。
便潜血陽性とは?その意味を正しく理解する
便潜血検査は、目に見えない微量の血液が便に混じっていないかを調べる検査です。
大腸がんやポリープがあると、便が通過する際に組織が傷つき、わずかな出血が起こることがあります。この微量の血液を検出するのが便潜血検査の役割です。
陽性判定が出たということは、「消化管のどこかで出血が起きている可能性がある」というサインなのです。
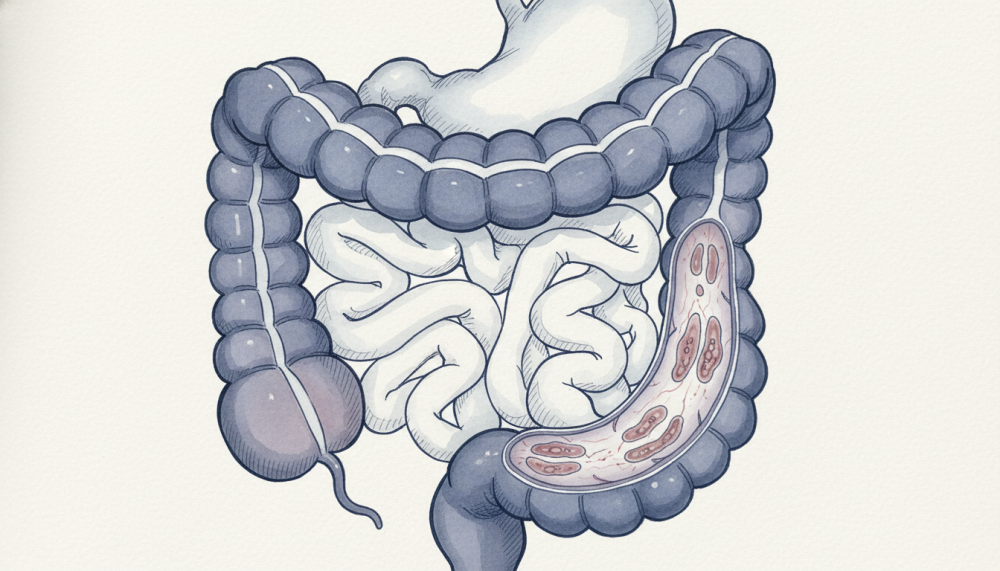
便潜血陽性でも症状がないのはなぜ?
「体調は普通だし、お腹も痛くないのに陽性なんて…」と思われる方も多いでしょう。
実は、大腸がんは早期の段階では自覚症状がほとんどありません。症状が出てから発見されるケースでは、すでに進行している可能性が高いのです。
だからこそ、症状がなくても便潜血陽性という「サイン」を見逃してはいけません。
便潜血陽性の精度について
便潜血検査で陽性となった方のうち、実際に大腸がんが見つかる割合は約3~5%です。
「たった数%か」と思われるかもしれませんが、この数%の中に早期発見によって救える命があるのです。
また、大腸がんに至る前段階である大腸ポリープが見つかるケースも多く、これらを早期に切除することで将来の大腸がんを予防できます。
便潜血陽性後、いつまでに大腸カメラを受けるべきか
結論から申し上げます。
便潜血陽性の判定が出たら、できるだけ早く、遅くとも1~2か月以内に精密検査を完了することをお勧めします。
推奨される受診タイミング
海外の研究では、便潜血陽性後の精密検査が9~10か月以上遅れると、がんの進行度が上がり、発見時の病期が進んでいることが報告されています。
具体的な目安としては、以下のスケジュールを意識してください。

- 0~4週間以内:医療機関を受診し、大腸カメラの予約を取る(最も理想的)
- ~8週間(2か月)以内:この期間内に検査を終えることがベスト
- 3か月以上:できるだけ早めの受診を(病気が進行するリスクが高まります)
- 9~10か月以上:リスクが大幅に増加するため、避けるべき
仕事や家庭の都合ですぐに検査が難しい場合でも、まずは外来を受診して検査日だけでも先に予約しておくことが安心につながります。
「4週間以内」が一つの目安となる理由
大腸がんは、4週間以上放置することで予後が悪化することが報告されています。
そのため、もし大腸がんだったとしても4週間以内に検査・治療ができれば、放置による予後悪化の可能性は低くなると考えられます。
また、大腸がんは自覚症状がない状態から進行がんになるまで約7年続くとされており、この期間に発見できれば早期治療が可能で、大腸がんによる死亡を防げる可能性が高まります。
便潜血陽性を放置するリスク
「忙しいから」「怖いから」「痔だと思うから」…
さまざまな理由で精密検査を先延ばしにする方がいらっしゃいます。しかし、放置することのリスクは想像以上に大きいのです。
死亡リスクが約4倍に上昇
大規模な追跡調査の結果、便潜血陽性となったにもかかわらず精密検査を受けなかった人は、検査を受けた人に比べて、大腸がんが見つかったときの死亡リスクが約4倍高まることが明らかになっています。
これは、精密検査を受けないことで発見が遅れ、進行した状態でがんが見つかるためです。
早期がんと進行がんの違い
早期の大腸がんであれば、内視鏡での切除が可能で、お腹を切る手術は不要です。治療後の5年生存率は98%以上と、ほぼ完治が期待できます。
一方、進行がんになると手術が必要となり、場合によっては抗がん剤治療も必要になります。生活の質(QOL)にも大きな影響が出てしまいます。
「今しか見つけられないかもしれない小さなサイン」を見逃さないことが、何より大切なのです。
「痔だから大丈夫」という思い込みは危険
「痔があるから便潜血陽性になっただけ」と自己判断する方もいらっしゃいます。
確かに痔は便潜血陽性の原因の一つですが、痔があると思っている人と痔がないと思っている人の間で、便潜血陽性の場合の大腸がんや大腸ポリープの発見割合に差がないという報告もあります。
つまり、痔があっても大腸がんが隠れている可能性は十分にあるのです。自己判断せず、必ず精密検査を受けましょう。
大腸カメラ検査とは?何がわかるのか
便潜血陽性後の精密検査として最も有効なのが、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)です。
肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体の粘膜を直接観察することで、出血の原因を特定できます。

大腸カメラで発見できる疾患
大腸カメラ検査では、以下のような疾患を発見できます。
- 大腸がん:早期発見により内視鏡治療が可能
- 大腸ポリープ:がん化する前に切除できる
- 潰瘍性大腸炎:慢性的な炎症性腸疾患
- 大腸憩室:出血や炎症の原因となることがある
- 虚血性腸炎:血流障害による炎症
- 痔核・裂肛:肛門疾患の確認
大腸カメラのメリット
大腸カメラ検査の最大のメリットは、「診断と治療が同時にできる」ことです。
小さなポリープであれば、検査中にその場で切除することが可能です。大きめのポリープや早期がんの場合でも、特殊な内視鏡治療で対応できるケースが多く、お腹を切る手術を避けられます。
また、組織を採取して病理検査を行うことで、「良性か悪性か」「どれくらい進んでいるか」を正確に判断でき、次の治療方針が明確になります。
「苦しい」「痛い」というイメージについて
大腸カメラに対して「辛い・苦しい」というイメージをお持ちの方も多いでしょう。
しかし、現在は鎮静剤(麻酔)を使用することで、半分眠ったような状態で検査を受けることができます。多くの患者様が「気づいたら終わっていた」と感じられるほど、苦痛を最小限に抑えた検査が可能です。
当院でも鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査を提供しており、患者様の不安や恐怖感を取り除く工夫をしています。
信頼できる受診先の選び方
大腸カメラ検査を受けるなら、信頼できる医療機関を選ぶことが重要です。
どのようなポイントに注目すれば良いのでしょうか。
消化器・内視鏡専門医がいるか
大腸カメラ検査は、医師の技術と経験によって検査の精度や患者様の負担が大きく変わります。
日本消化器病学会の消化器病専門医や、日本消化器内視鏡学会の内視鏡専門医といった資格を持つ医師が在籍しているかを確認しましょう。
専門医であれば、微細な病変も見逃さず、安全かつ正確な検査が期待できます。
鎮静剤(麻酔)を使用した無痛検査が可能か
鎮静剤を使用することで、検査中の苦痛や恐怖感を大幅に軽減できます。
「以前の検査が辛かった」「初めてで不安」という方は、鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査を提供しているクリニックを選ぶと安心です。
当日検査や土曜検査に対応しているか
平日は仕事で忙しい方にとって、土曜日に検査を受けられることは大きなメリットです。
また、初診当日に検査が可能なクリニックであれば、スムーズに精密検査を進められます。待ち時間や滞在時間の短縮に取り組んでいる医療機関を選ぶことで、負担を減らせます。

高性能な内視鏡設備が整っているか
拡大内視鏡やNBI(狭帯域光観察)などの最新設備を導入しているクリニックでは、粘膜の微細な変化まで観察でき、早期がんの発見率が向上します。
大学病院に劣らない高精度の検査が可能な設備を備えているかも、選択のポイントです。
CTや超音波エコーなど総合的な検査が可能か
大腸カメラだけでなく、必要に応じてCT検査や超音波エコー検査も実施できる体制が整っていると、より包括的な診断が可能です。
肝臓、胆嚢、膵臓などの精査も同時に行えるクリニックであれば、消化器全体の健康管理を任せられます。
大腸カメラ検査の流れと準備
大腸カメラ検査を初めて受ける方にとって、「どんな準備が必要なの?」「当日はどうなるの?」という疑問があるでしょう。
ここでは、検査の流れと準備について簡単にご説明します。
検査前日の食事制限
大腸カメラは、腸の中がきれいになっていないと正確な検査ができません。
検査前日は消化に良いものを選び、繊維質の多い食品や脂っこい食事は避けましょう。クリニックから専用の食事指示がある場合は、それに従ってください。
当日の下剤服用
検査当日は、腸管洗浄剤(下剤)を服用して腸の中をきれいにします。
約2リットルの洗浄液を2~3時間かけて飲み、便が透明になるまで排便を繰り返します。この過程が「辛い」と感じる方もいらっしゃいますが、適切な指導とサポートがあれば安心して進められます。
検査当日の流れ
検査当日は、鎮静剤を使用する場合は点滴を行い、リラックスした状態で検査室に入ります。
検査自体は通常15~30分程度で終了します。鎮静剤を使用した場合は、検査後に休憩室で30分~1時間程度お休みいただき、意識がはっきりしてからご帰宅いただきます。
検査結果は当日または後日、医師から詳しく説明があります。組織検査を行った場合は、結果が出るまで1~2週間程度かかります。
検査後の注意事項
鎮静剤を使用した場合、当日の車や自転車の運転は控えてください。
また、ポリープ切除を行った場合は、一時的に運動や食事の制限があります。医師の指示に従って、安静に過ごしましょう。
よくある質問と誤解
「2回のうち1回だけ陽性だから様子を見てもいい?」
便潜血検査は通常2回分の便を検査しますが、「2回とも陽性でなければ大丈夫」というわけではありません。
1回でも陽性であれば精密検査を受けることが推奨されています。検査の精度上、2回実施して1度でも引っかかってほしいという設計になっているためです。
「もう一度便潜血検査をして陽性だったら検査する」はNG
便潜血陽性後に再度便潜血検査を行い、「次も陽性だったら大腸カメラを受ける」という考え方は、医学的には推奨されません。
便潜血検査は、大腸がんがあるから必ず陽性になるものではなく、7年間で一度くらいは陽性になる可能性が高いという程度の検査です。一度でも陽性となった時点で、精密検査を受けることが重要です。
「便潜血陰性なら大腸がんの心配はない?」
便潜血検査が陰性でも、大腸がんではないと断言できるわけではありません。
腸内で出血が起きていても便に血液が混ざらないケースもあるため、便潜血検査の精度には限界があります。長く続く下痢や便秘、腹痛、血便、細い便などの症状がある場合は、便潜血検査の結果にかかわらず、消化器内科を受診することをお勧めします。
まとめ:早期発見が命を救う
便潜血陽性は、体からの重要なサインです。
「忙しいから」「怖いから」と先延ばしにせず、できるだけ早く、遅くとも1~2か月以内に精密検査を受けることが、あなたの命と健康を守ります。
大腸がんは早期発見できれば、ほぼ完治が期待できる病気です。進行してから見つかると治療も大変になり、生活の質にも大きな影響が出てしまいます。
「今しか見つけられないかもしれない小さなサイン」を見逃さず、勇気を持って一歩を踏み出してください。
当院では、消化器・内視鏡専門医による丁寧な診察と、鎮静剤を使用した無痛の大腸カメラ検査を提供しています。初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しており、お忙しい方でも安心して受診いただけます。
便潜血陽性と言われたら、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの健康を守るために、私たちが全力でサポートいたします。
詳しくはこちら:石川消化器内科内視鏡クリニック

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
初めての大腸内視鏡、当日の流れと予約前に聞くべき5項目|不安を減らす受診ガイド

大腸内視鏡検査を初めて受ける方にとって、「検査は痛いのだろうか」「当日はどんな流れなのか」といった不安は尽きないものです。
検査前の準備から当日の流れまで、事前に知っておくことで心の準備ができ、安心して検査に臨めます。
この記事では、消化器内視鏡専門医として多くの患者様を診てきた経験から、初めての大腸内視鏡検査を安心して受けていただくための情報をお伝えします。
大腸内視鏡検査とは・・・どんな検査なのか
大腸内視鏡検査は、肛門から内視鏡を挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体を観察する検査です。
大腸がんや大腸ポリープ、炎症性腸疾患などの早期発見に非常に有効です。
検査では、腸内の粘膜を直接観察できるため、画像検査では見つけにくい小さな病変も発見できます。

検査で発見できる主な疾患
大腸内視鏡検査では、**大腸がん**や**大腸ポリープ**をはじめ、さまざまな疾患を発見できます。
過敏性腸症候群、虚血性大腸炎、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)、大腸憩室症なども診断可能です。
特に大腸がんは早期発見が重要で、初期段階では自覚症状がほとんどありません。
定期的な検査により、がんになる前のポリープの段階で発見し、切除することで大腸がんの予防につながります。
検査時間と鎮静剤の使用
検査時間は通常15~30分程度です。
当院では、患者様の苦痛を最小限に抑えるため、鎮静剤(麻酔)を使用した検査を行っています。
半分眠ったような状態で検査を受けていただけるため、「あっという間に終わった」と感じる方がほとんどです。
痛みや恐怖をほとんど感じることなく、リラックスした状態で検査を受けられます。
鎮静剤を使用することで、検査中の不快感が大幅に軽減され、医師も丁寧に観察できるため、検査の精度も向上します。
予約前に必ず確認すべき5つの重要項目
大腸内視鏡検査をスムーズに受けるためには、予約前の確認が欠かせません。
ここでは、医療機関に問い合わせる際に確認しておきたい5つのポイントをご紹介します。
これらを事前に把握しておくことで、当日の不安を大きく減らせます。

1. 鎮静剤の使用について
鎮静剤を使用するかどうかは、検査の快適さに大きく影響します。
当院では、ご希望に応じて鎮静剤を使用し、痛みや不快感を最小限に抑えた検査を提供しています。
鎮静剤を使用した場合、検査後は1時間ほど休憩が必要です。
また、当日の車やバイク、自転車の運転はできませんので、ご家族の送迎や公共交通機関の利用をお願いしています。
鎮静剤の使用を希望される場合は、予約時にその旨をお伝えください。
2. 検査当日のスケジュール
検査当日の流れを事前に把握しておくことで、心の準備ができます。
当院では、初診当日の検査にも対応していますが、通常は事前診察で検査日を予約していただきます。
検査当日は、朝から下剤(腸管洗浄液)を服用し、腸内をきれいにする必要があります。
自宅で下剤を服用する方法と、院内で服用する方法があり、患者様のご希望に応じて選択できます。
院内で服用される場合は、朝9時頃にご来院いただき、個室で腸管洗浄液を服用していただきます。
3. 前日の食事制限について
検査前日の食事内容は、検査の精度に直接影響します。
前日は消化の良い食事(おかゆ、素うどん、白身魚、豆腐など)を午後8時頃までに済ませてください。
野菜類、きのこ類、海藻類、豆類、ナッツ類など、食物繊維が多い食品は避ける必要があります。
これらは腸内に残りやすく、検査の妨げになるためです。
前日の食事制限を守ることで、腸内をきれいにしやすくなり、検査がスムーズに進みます。
4. ポリープ切除の対応可否
検査中にポリープが発見された場合、その場で切除できるかどうかは重要なポイントです。
当院では、大腸ポリープが発見された場合、条件を満たせば検査と同時に日帰りで切除を行っています。
ポリープ切除後は、刺激物の摂取や飲酒、激しい運動を1週間程度控えていただく必要があります。
ポリープを切除することで、将来の大腸がん発症リスクを大幅に減らせます。
5. 検査費用と保険適用について
検査費用は、保険適用の有無や検査内容によって異なります。
予約時に、保険適用の範囲や自己負担額の目安を確認しておくと安心です。
当院では、電話予約とWEB予約に対応しており、アプリ決済、クレジットカード、電子決済もご利用いただけます。
検査費用についてご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
検査前日の準備・・・食事と下剤の服用
検査前日の準備は、検査の成功を左右する重要なステップです。
適切な食事制限と下剤の服用により、腸内をきれいな状態にすることが求められます。
前日の準備をしっかり行うことで、検査当日の腸管洗浄がスムーズに進みます。
前日の食事メニュー例
前日の朝食・昼食・夕食すべてにおいて、消化の良いものを選びましょう。
**白米やおかゆ**、**素うどん**、**食パン**(雑穀やドライフルーツが入っていないもの)が適しています。
おかずは、**白身魚**、**鶏肉**(皮なし)、**豆腐**、**卵**などがおすすめです。
じゃがいもは皮をむいたものであれば食べられますが、野菜全般は避けてください。
味付けは薄味にし、油を使った料理は控えめにしましょう。
避けるべき食品リスト
以下の食品は、腸内に残りやすいため前日は避けてください。
- 野菜類(葉物、根菜など)
- きのこ類(椎茸、エノキタケ、マイタケなど)
- 海藻類(海苔、わかめ、昆布、ひじきなど)
- 豆類、ナッツ類、ごま
- 果物(特に皮つきや種のあるもの)
- こんにゃく、玄米、雑穀米
- 脂っこい揚げ物や脂身の多い肉
- 乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)
これらの食品は消化に時間がかかり、腸内に残りやすいため、検査の精度を下げる原因になります。
前日夜の下剤服用
検査前日の就寝前(午後9時頃)に、処方された下剤(錠剤)を服用していただきます。
脱水を防ぐため、お水などでこまめに水分補給を心がけてください。
早めの就寝を心がけ、体調を整えることも大切です。
前日夜の下剤により、翌朝の腸管洗浄がスムーズに進みます。
検査当日の流れ・・・来院から検査終了まで
検査当日は、指定された時間にクリニックへご来院いただきます。
ここでは、来院から検査終了までの詳しい流れをご説明します。
当日の流れを事前に知っておくことで、落ち着いて検査を受けられます。

来院後の腸管洗浄
自宅で下剤を服用する場合は、検査当日の朝7時頃から腸管洗浄液を飲み始めます。
約2リットルの液体を数回に分けて服用し、何度かトイレに通います。
便が液体のような水様便になれば、腸内がきれいになった合図です。
院内で下剤を服用する場合は、朝9時頃にご来院いただき、個室で腸管洗浄液を服用していただきます。
スタッフが適宜サポートしながら、排便状況を確認いたします。
腸管洗浄には個人差がありますが、通常2~3時間程度かかります。
検査前の準備
腸内がきれいになったことを確認後、検査着にお着替えいただきます。
鎮静剤を使用する場合は、点滴の準備を行います。
前処置室もしくは待合室で名前を呼ばれるまでお待ちください。
リラックスした状態で検査を受けていただけるよう、スタッフが丁寧にサポートいたします。
不安なことがあれば、遠慮なくスタッフにお声がけください。
検査室での処置
検査台に横になり、おなかをラクにします。
鎮静剤を注射し、半分眠ったような状態になります。
場合によっては、腸の緊張をやわらげる薬も注射します。
力を抜いてリラックスしていただくことが、スムーズな検査のポイントです。
鎮静剤が効いてくると、意識が薄れていき、検査中の記憶がほとんど残らない方も多くいらっしゃいます。
内視鏡検査の実施
肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体を丁寧に観察します。
医師はモニターに映る腸内をすみずみまで確認し、異常がないかチェックします。
検査時間は15~30分ほどで、患者様ごとに多少異なります。
当院では、高性能な拡大内視鏡を使用し、大学病院に劣らない精度の検査を提供しています。
ポリープが見つかった場合は、その場で切除することもあります。
検査終了後の休憩
検査が終わったら、リカバリールームで横になって休みます。
鎮静剤を使用した場合は、40分~1時間ほど安静にしていただきます。
気分が悪い時や変調がある時は、すぐに医師やスタッフにお伝えください。
お着替えが終わり次第、コーヒーや紅茶などのドリンクをご用意していますので、個室でゆっくりとお休みいただけます。
十分に休憩し、体調が回復してからご帰宅いただきます。
検査結果の説明と今後の対応
検査終了後は、撮影した画像をもとに検査結果をご説明します。
当院では、すべての診察、検査、検査結果説明を院長が担当していますので、安心してご相談いただけます。
検査結果に応じて、今後の治療方針や生活上の注意点をお伝えします。
当日の結果説明
身支度を整えたら、撮影した画面を見ながら検査の結果を聞きます。
観察のみで処置がなかった場合は、その場で詳しい説明を受けられます。
組織採取やポリープ切除を行った場合は、病理検査の結果を後日(10日~3週間後)に再度ご来院いただき、詳しくご説明いたします。
病理検査により、ポリープの性質やがん細胞の有無を正確に判断できます。
検査後の注意事項
検査後は、おなかが張ってくるため、おならをどんどん出しましょう。
鎮静剤を使用した場合、検査後の車の運転は禁止です(翌日からは可能)。
飲食は1時間後から可能で、便に少量の血が混じる場合があります。
観察のみの検査であれば、特に食事制限はありませんが、ポリープを切除された場合は、刺激物の摂取、飲酒、激しい運動を1週間程度お控えください。
入浴はせずにシャワー程度にし、医師の指示を守りましょう。
検査後に腹痛や発熱、大量の出血がある場合は、すぐに当院までご連絡ください。
よくある質問・・・患者様の不安を解消
初めての大腸内視鏡検査では、さまざまな疑問や不安が生じるものです。
ここでは、患者様からよく寄せられる質問にお答えします。
疑問を解消することで、安心して検査を受けていただけます。

検査は本当に痛くないのですか?
鎮静剤を使用することで、ほとんどの方が「眠っている間に終わった」と感じられます。
痛みや不快感をほとんど覚えないまま検査を終えられるため、安心してください。
当院では、患者様の苦痛を最小限に抑えるため、二酸化炭素送気装置を使用し、腹部の張りを軽減しています。
二酸化炭素は空気よりも早く体内に吸収されるため、検査後の腹部膨満感が少なくなります。
下剤を飲むのが不安です
下剤の服用は、多くの方が「大変だった」と感じる部分です。
約2リットルの液体を飲む必要がありますが、数回に分けて時間をかけて服用していただけます。
院内で下剤を服用する場合は、スタッフがサポートしながら排便状況を確認しますので、安心です。
自宅で服用する場合も、嘔吐や体調不良があれば、すぐに当院までご連絡ください。
下剤の味が苦手な方には、冷やして飲むと飲みやすくなるとお伝えしています。
検査後すぐに食事はできますか?
観察のみの検査であれば、検査後1時間後からお食事が可能です。
ポリープを切除された場合は、当日は消化の良い食事をおすすめしています。
刺激物や飲酒は、2~3日避けるようにしましょう。
検査後の食事について不安がある場合は、医師やスタッフにご相談ください。
家族に大腸がんの人がいます。何歳から検査を受けるべきですか?
家族に大腸がんを患っている方がいる場合、遺伝的リスクが高まります。
40歳以上で大腸内視鏡検査を受けたことがない方は、一度検査を受けることをおすすめします。
早期発見により、大腸がんの発症を予防できる可能性が高まります。
家族歴がある方は、定期的な検査を受けることで、より安心して生活できます。
まとめ・・・安心して検査を受けるために
大腸内視鏡検査は、大腸がんやポリープの早期発見に欠かせない重要な検査です。
初めての方にとっては不安が大きいかもしれませんが、事前に流れを知り、適切な準備をすることで、安心して検査を受けられます。
予約前には、鎮静剤の使用、検査当日のスケジュール、前日の食事制限、ポリープ切除の対応可否、検査費用の5つのポイントを確認しましょう。
当院では、消化器・内視鏡専門医がすべての診察と検査を担当し、鎮静剤を使用した無痛の検査を提供しています。
初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しており、お忙しい方でも受診しやすい環境を整えています。
些細なことでもお気軽にご相談ください。
詳しい検査内容やご予約については、石川消化器内科内視鏡クリニックの公式サイトをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。
あなたの健康を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
胃カメラ検査の所要時間~受付から帰宅まで完全ガイド
胃カメラ検査の所要時間~受付から帰宅まで完全ガイド

胃カメラ検査の所要時間とは?~検査時間を正しく把握しよう
胃カメラ検査を受けようと思っても、「どのくらいの時間がかかるのか」「仕事や予定は入れられるのか」など、不安に感じる方も多いでしょう。
実は、胃カメラ検査の所要時間は鎮静剤(麻酔)の使用有無や検査方法によって大きく異なります。検査自体は5〜15分程度ですが、来院から帰宅までの総所要時間は状況によって変わってきます。
当院では消化器・内視鏡専門医として、患者さんの状態や希望に合わせた検査方法をご提案しています。鎮静剤を使用した「無痛胃カメラ」も多くの方に選ばれており、「思ったより楽だった」というお声をいただいています。
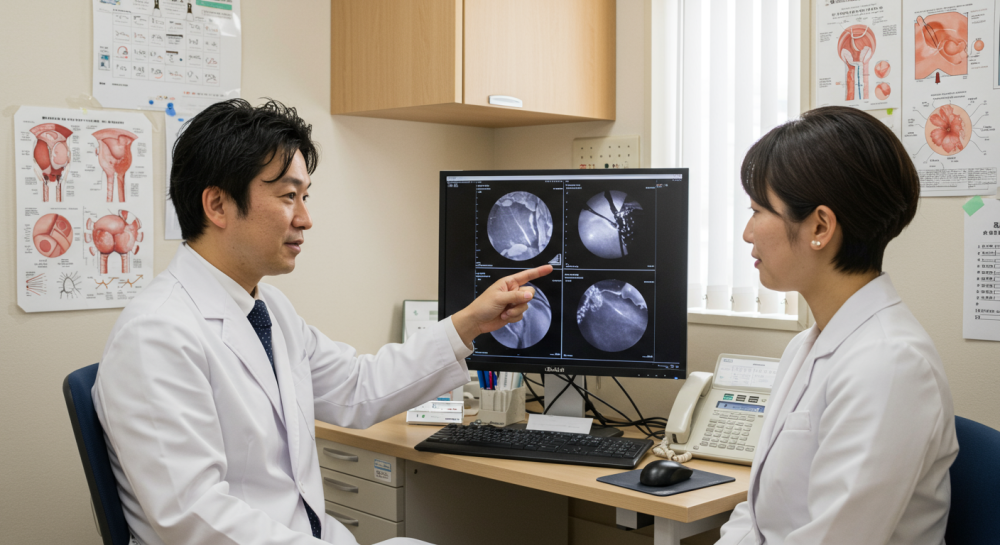
今回は、胃カメラ検査にかかる時間について、受付から帰宅までの流れに沿って詳しくご説明します。検査方法による時間の違いや、スムーズに検査を受けるためのポイントもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
胃カメラ検査の基本的な所要時間
胃カメラ検査当日の来院からお帰りまでの時間は、大きく分けて以下の要素で変わります。
- 鎮静剤(麻酔)の使用有無
- 経口か経鼻かの検査方法
- 初診か再診か
- 検査中に組織採取(生検)を行うかどうか
一般的な目安として、鎮静剤なしの場合は来院から帰宅まで約20〜30分程度、鎮静剤を使用する場合は約45〜60分程度、最大で2時間程度の滞在時間を見込んでおく必要があります。
初めて受診される方は、検査前の説明や問診にも時間がかかりますので、さらに10〜30分ほど余裕を持ってお越しいただくとよいでしょう。
どう思いますか?意外と短時間で終わると感じませんか?
胃カメラ検査の流れと各ステップの所要時間
胃カメラ検査の全体の流れを時間とともに見ていきましょう。検査方法によって異なる部分もありますが、基本的な流れは共通しています。
1. 受付・問診(約5〜10分)
まず来院されたら、受付で診察券や保険証を提示します。初診の方は問診票の記入が必要です。
当院では待ち時間と滞在時間の短縮に取り組んでおり、電話予約とWEB予約を導入しています。事前に予約をしていただくと、待ち時間を大幅に減らすことができます。
また、アプリ決済やクレジットカード、電子決済にも対応していますので、会計の際もスムーズに済ませることが可能です。
2. 検査前の説明と準備(約10〜15分)
医師による検査前の説明があります。ここで検査方法(経口か経鼻か)や鎮静剤の使用有無について相談し、決定します。
その後、消泡剤を飲んでいただきます。これは胃の中の泡を除去し、より鮮明に胃の粘膜を観察するためのものです。
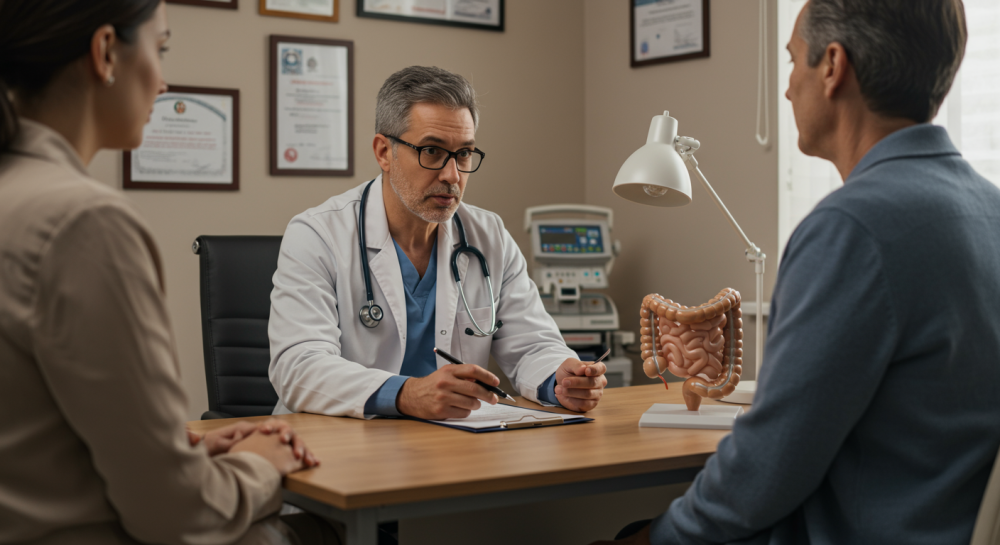
経口胃カメラの場合は喉の麻酔を、経鼻胃カメラの場合は鼻の麻酔を行います。麻酔が効くまで数分間待ちます。
3. 検査の実施(約5〜15分)
実際の胃カメラ検査は、多くの場合5〜15分程度で終了します。鎮静剤を使用する場合は、まず点滴の準備に2〜3分、鎮静剤を注入してから効果が出るまで2〜3分ほど待ちます。
鎮静剤を使用すると、半分眠ったような状態になるため、検査中の苦痛や不安感が大幅に軽減されます。当院では高性能な拡大内視鏡を導入しており、大学病院に劣らない精度で早期の病変発見が可能です。
経鼻胃カメラは経口よりもスコープが細いため、挿入に慎重を要したり、胃の中を洗浄する水の出し入れに時間がかかったりするため、若干時間がかかる傾向があります。
検査中に異常が見つかった場合は、その場で組織を採取(生検)することがあります。この場合、検査時間が少し延びることがあります。
鎮静剤の有無による所要時間の違い
胃カメラ検査の所要時間は、鎮静剤(麻酔)を使用するかどうかで大きく変わります。それぞれの特徴と所要時間の違いを詳しく見ていきましょう。
鎮静剤なしの場合(約20〜30分)
鎮静剤を使用しない場合の胃カメラ検査は、準備から検査後の休憩まで含めても比較的短時間で終わります。
- 受付・問診:約5〜10分
- 検査前の説明と準備(喉の麻酔など):約10分
- 内視鏡挿入から観察終了まで:約5〜15分
- 終了後の身支度や医師からの説明:約5〜10分
トータルで20〜30分程度で帰宅可能なケースもあります。検査後すぐに運転や仕事に戻ることも可能です。
ただし、鎮静剤を使用しない場合は、検査中に不快感や嘔吐反射を感じる方もいらっしゃいます。以前に胃カメラを受けて辛かった経験のある方は、鎮静剤の使用をご検討ください。
鎮静剤ありの場合(約45〜60分、最大2時間)
鎮静剤を使用する場合は、検査中の苦痛が大幅に軽減される反面、前後の準備と休憩の時間が多めに必要です。
- 受付・問診:約5〜10分
- 検査前の説明と準備(喉の麻酔など):約10分
- 点滴の準備:約2〜3分
- 鎮静剤注入から効果発現まで:約2〜3分
- 内視鏡挿入から観察終了まで:約5〜15分
- 検査後の回復・休憩:約15〜30分(クリニックによっては1時間程度)
- 医師からの結果説明:約5〜10分
鎮静剤を使用した場合の来院から帰宅までの合計時間は、約45〜60分程度、最大で2時間程度見込んでおく必要があります。
当院では「無痛胃カメラ」として、鎮静剤を使用した検査を多くの患者さんに選んでいただいています。半分眠ったような状態で検査を受けられるため、「あっという間に終わった」「全く苦しくなかった」という声をよくいただきます。
鎮静剤を使えば胃カメラの苦痛はほとんど感じません。検査への恐怖感が胃カメラ回避の最大の障壁です。その恐怖を取り除くことが、早期発見・早期治療への第一歩なのです。
検査後の注意点と帰宅までの時間
胃カメラ検査が終わった後も、いくつか注意点があります。特に鎮静剤を使用した場合は、安全に帰宅できるようにしっかりと休息をとることが大切です。
鎮静剤なしの場合の注意点
鎮静剤を使用しなかった場合でも、喉の麻酔が効いている間(約30分程度)は、飲食を控える必要があります。麻酔が効いている状態で飲食すると、誤嚥の危険性があるためです。
検査後に喉の違和感が残ることがありますが、通常は数時間で改善します。検査当日は刺激物の摂取を控え、喉に優しい食事を心がけましょう。
鎮静剤を使用しない場合は、検査後すぐに運転や仕事に戻ることが可能です。ただし、初めて検査を受ける方は、体調の変化に備えて、可能であれば無理のないスケジュールを組むことをお勧めします。

鎮静剤ありの場合の注意点と回復時間
鎮静剤を使用した場合は、検査後に回復室で15〜30分ほど、クリニックによっては1時間程度横になって休む必要があります。鎮静剤の効果がしっかり醒めてから、医師の結果説明を受けます。
鎮静剤の効果は個人差がありますが、通常は投与後30分〜1時間程度で意識がはっきりしてきます。ただし、完全に効果が切れるまでには数時間かかることもあります。
そのため、鎮静剤を使用した場合は、当日の車やバイクの運転、重要な契約や判断を要する業務、危険を伴う作業などは避けてください。可能であれば、ご家族やご友人に付き添ってもらうことをお勧めします。
当院では患者さんの安全を第一に考え、鎮静剤の使用後は十分な回復時間を確保しています。「もう大丈夫」と感じても、医師の判断があるまでは無理に帰宅せず、しっかり休息をとりましょう。
検査後に強い痛みや出血などの異常を感じた場合は、すぐに医師にお伝えください。
スムーズに胃カメラ検査を受けるためのポイント
胃カメラ検査をより短時間で、スムーズに受けるためのポイントをご紹介します。事前の準備と心構えで、検査の負担を軽減しましょう。
検査前日からの準備
胃カメラ検査の前日は、午後8時以降の食事は控えてください。水やお茶、スポーツ飲料などの透明な飲み物は検査当日も飲んでいただけます。むしろ、適度な水分摂取は胃の中をきれいにするのに役立ちます。
検査当日の朝は絶食が基本ですが、常用している薬(血圧薬や心臓の薬など)は、少量の水で服用していただいて構いません。ただし、糖尿病のお薬については医師の指示に従ってください。
アルコールは検査前日から控えていただくと、より鮮明な画像が得られます。
当日の心構えとリラックス方法
胃カメラ検査で最も大切なのは、リラックスすることです。緊張すると喉の反射が強くなり、検査が難しくなることがあります。

深呼吸をしたり、検査中は鼻から息を吸って口から吐くことを意識したりすると、リラックスしやすくなります。また、医師や看護師の指示に従い、力を抜いて検査を受けることも大切です。
当院では患者さんの不安を和らげるため、検査前の説明を丁寧に行っています。わからないことや不安なことがあれば、遠慮なくお尋ねください。
予約システムの活用
当院では電話予約とWEB予約を導入しており、待ち時間の短縮に努めています。特に胃カメラ検査は予約制となっていますので、事前に予約をしていただくとスムーズです。
また、初診当日の検査や土曜日の検査にも対応していますので、お仕事で平日が忙しい方でも受診しやすい環境を整えています。
検査に関するご質問やご不安な点があれば、予約時にお伝えいただくと、当日の説明がよりスムーズになります。
まとめ:安心して胃カメラ検査を受けるために
胃カメラ検査の所要時間は、鎮静剤の使用有無や検査方法によって異なりますが、一般的には以下の通りです。
- 鎮静剤なしの場合:来院から帰宅まで約20〜30分
- 鎮静剤ありの場合:来院から帰宅まで約45〜60分(最大2時間)
検査自体は5〜15分程度と短時間ですが、準備や検査後の休息を含めると上記の時間が必要になります。特に鎮静剤を使用した場合は、安全のために十分な回復時間を確保することが大切です。
当院では「辛い・苦しい」というイメージがある内視鏡検査を「より気軽に」「よりスピーディーに」そして安心して受けられるよう工夫を重ねています。鎮静剤を使用した無痛胃カメラや、高性能な拡大内視鏡による精密検査など、患者さんの負担を軽減しながら、高精度な検査を提供しています。
胃カメラ検査は、胃がんをはじめとする消化器疾患の早期発見・早期治療に非常に重要な検査です。少しでも気になる症状がある方、50歳を迎えて健康管理に気を配りたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
検査への不安や疑問がある方も、お気軽に当院までお問い合わせください。消化器・内視鏡専門医として、皆さまの健康をサポートいたします。
詳しい情報や予約については、石川消化器内科内視鏡クリニックのウェブサイトをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
大腸カメラ検査の所要時間~準備から終了まで徹底解説
大腸カメラ検査の所要時間~準備から終了まで徹底解説

大腸カメラ検査とは?基本的な理解から
大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)は、肛門から細いカメラを挿入して大腸内部を直接観察する検査です。この検査によって、大腸ポリープや大腸がんなどの病変を早期に発見することができます。
「大腸カメラって痛いんじゃないの?」「どのくらい時間がかかるの?」と不安に思われる方も多いでしょう。
実は大腸カメラ検査自体は、何も病変がなければ10〜15分程度で終わる比較的短時間の検査なのです。しかし、検査前の準備や検査後の休憩時間も含めると、半日から1日がかりになることが一般的です。

当院では、患者さんの負担を最小限に抑え、安心して検査を受けていただくために、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛での大腸カメラ検査を提供しています。半分眠ったような状態で検査を受けることができるため、痛みや恐怖感をほとんど感じることなく検査を終えることができます。
この記事では、大腸カメラ検査にかかる時間を中心に、検査前の準備から検査後の流れまで詳しく解説します。検査を控えている方はぜひ参考にしてください。
大腸カメラ検査の全体的な所要時間
大腸カメラ検査は、検査自体の時間だけでなく、前処置や検査後の休憩時間も含めると、合計で3〜6時間程度かかります。
具体的な内訳は以下の通りです。
- 腸内をきれいにするための時間:2〜4時間(腸管洗浄液の摂取に約2時間)
- 大腸カメラ検査の所要時間:10〜15分程度(病変があった場合は30分程度)
- 検査後の安静時間(鎮静剤使用時):1〜2時間
検査自体は短時間で終わりますが、腸内をきれいにする前処置に時間がかかるため、検査当日は半日〜1日がかりと考えておくと良いでしょう。
「え?そんなに時間がかかるの?」と驚かれるかもしれませんね。
しかし、この時間は大腸をしっかりと観察するために必要なものです。特に前処置は検査の精度に直結するため、丁寧に行うことが重要なのです。
当院では、患者さんの状況に合わせて、前処置の方法や検査の進め方を調整しています。例えば、前処置薬の種類を選べたり、自宅で前処置を行うか院内で行うかを選択していただけます。
検査前日からの準備と所要時間
大腸カメラ検査は当日だけでなく、前日からの準備が重要です。検査前日と当日の流れについて詳しく見ていきましょう。
検査前日の準備(食事制限と下剤)
検査前日は、以下のような準備が必要です。
- 軽めの食事で消化に良いものを食べる(食物繊維を多く含むものは避ける)
- 夕食は午後5〜6時頃までに済ませる
- 便秘がひどい場合は、夕食後に下剤を服用する
- 早めに就寝する
前日の食事内容はとても重要です。食物繊維を多く含む食べ物(野菜、海藻、きのこ、こんにゃく、果物など)は消化されにくく、翌日も腸内に残りやすいため、避けるようにしましょう。
当院では、患者さんの便通状態に合わせて、前日の下剤の使用についても個別に指導しています。日常的に便秘がひどい方は、事前にご相談いただくことをおすすめします。
検査当日の前処置(腸管洗浄)
検査当日は、腸内をきれいにするための前処置が必要です。当院では、患者さんの負担を減らすために、前日の下剤をなくし、当日の腸管洗浄剤の量も従来の半分〜2/3程度で済む前処置薬(モビプレップ)を使用しています。
腸管洗浄剤の摂取には約2時間かかり、その後、腸内がきれいになるまでに2〜4時間程度かかります。早ければ内服してから2〜3時間ほどで腸内がきれいになります。
当院では、腸管洗浄剤の服用場所についても、患者さんの環境に合わせて選択していただけます。
- ご自宅で腸管洗浄剤を飲んでからクリニックに来ていただく方法
- クリニックに来院後に腸管洗浄剤を飲む方法
自宅での服用を選ばれる場合、洗浄剤の内服を開始して2〜3時間経ち、ひとしきり便が出てしまうと、その後はあまり便意を感じなくなるので、電車などで来院できるようになります。
クリニックでの服用を選ばれる場合は、医師・看護師が確認しながら洗浄剤を服用していただけるので、安心して前処置を行うことができます。また、便の状態を確認しながら飲んでいただくので、早く腸の中がきれいになれば、前処置薬の量が少なくて済む場合もあります。
大腸カメラ検査自体の所要時間と流れ
腸の洗浄が終わったら、いよいよ検査の準備に入ります。検査自体の流れと所要時間について詳しく見ていきましょう。
検査直前の準備(着替えと鎮静剤)
検査の直前には、以下のような準備を行います。
- 検査着への着替え(5分程度)
- ベッドに横になり、希望者には点滴と鎮静剤の投与(5〜10分程度)
鎮静剤は2〜3分で効いてきますので、しっかりと効いた状態になったことを確認してから検査を開始します。鎮静剤の量は、「ぐっすりと眠った状態」や「苦痛を取り除いてボーっとして画面を見ながらの状態」など、患者さんの希望に応じて調整することが可能です。
もちろん、鎮静剤を使用せずに検査を受けることもできます。当院では、患者さんの希望や状態に合わせて、最適な方法で検査を行っています。
実際の検査時間(10〜15分)
大腸カメラ検査自体の所要時間は、通常10〜15分程度です。検査は、肛門から内視鏡を挿入し、大腸の一番奥(盲腸)まで進めた後、引き抜きながら丁寧に観察していきます。

当院では、苦痛のない方法で丁寧に挿入・観察することで、痛みやお腹の張りを最小限にすることが可能です。過去に受けた検査で「痛かった」「お腹が張って辛かった」という経験をお持ちの方も、安心して検査を受けていただけます。
ただし、ポリープなどの病変が見つかった場合は、その場で組織検査や切除を行うことがあります。その場合は、検査時間が30分程度に延びることがあります。
大腸ポリープが見つかった場合、大きさや数によっては、その場で切除することも可能です。当院では、日帰りでのポリープ切除にも対応していますので、ご安心ください。
検査後の休憩と説明(1〜2時間)
検査後は、鎮静剤を使用した場合、効果が切れるまで1〜2時間程度の安静時間が必要です。鎮静剤の効果には個人差がありますので、当日は時間に余裕を持っておくことをおすすめします。
鎮静剤の効果が切れて意識がはっきりとした後、医師から検査結果の説明を受けます。当院では、検査当日に大腸がんの有無などの結果説明を行っています。ただし、組織検査を行った場合は、結果が出るまで2週間程度かかります。
検査のみの場合は、検査後に少量の水分を摂って様子を見て、気分が悪くなるなどの症状がなければ、通常の食事を摂っていただいて構いません。
検査時間に影響する要因と注意点
大腸カメラ検査の所要時間は、いくつかの要因によって変わることがあります。検査をスムーズに進めるための注意点とともに解説します。
検査時間が延びる可能性のある要因
以下のような場合は、検査時間が延びることがあります。
- 腸の形状が複雑で挿入に時間がかかる場合
- 前処置が不十分で腸内がきれいになっていない場合
- ポリープなどの病変が見つかり、組織検査や切除を行う場合
- 過去の手術で腸の癒着がある場合
特に前処置が不十分だと、腸内の観察が難しくなり、検査の精度が下がってしまいます。前日からの食事制限や当日の腸管洗浄剤の服用は、指示通りに行うことが重要です。
便秘がひどい方は、前処置に時間がかかることがありますので、事前に医師にご相談ください。当院では、患者さんの便通状態に合わせて、最適な前処置方法をご案内しています。
検査をスムーズに進めるための注意点
検査をスムーズに進めるためには、以下の点に注意しましょう。
- 検査前日は指示された食事制限を守る
- 腸管洗浄剤は指示された量と時間で飲み切る
- 検査当日は、鎮静剤を使用する可能性があるため、車やバイク、自転車の運転は控える
- 検査当日は時間に余裕を持って来院する
当院では、検査当日に鎮静剤を使用する可能性があるため、公共の交通機関を利用するか、ご家族に送迎をしてもらうことをおすすめしています。
また、検査前日と当日は水分制限がないため、積極的に水分を摂取することで、前処置をスムーズに進めることができます。ただし、アルコールは飲まないようにしましょう。
当院の大腸カメラ検査の特徴と工夫
当院では、患者さんの負担を最小限に抑え、安心して検査を受けていただくために、さまざまな工夫を行っています。
無痛検査への取り組み
「大腸カメラは痛い」というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、当院では以下のような取り組みで、痛みを最小限に抑えた検査を提供しています。
- 鎮静剤(麻酔)を使用した無痛検査
- 苦痛のない挿入方法と丁寧な観察
- 経験豊富な消化器・内視鏡専門医による検査
半分眠ったような状態でほとんど苦痛・恐怖感なく検査を受けていただける鎮静剤の使用は、患者さんから特に好評をいただいています。「あっという間に終わった」「全く痛みを感じなかった」という声をよくいただきます。
患者さんの利便性を考慮した検査体制
当院では、患者さんの生活スタイルに合わせて検査を受けていただけるよう、以下のような体制を整えています。
- 初診当日の検査対応
- 土曜日の検査対応
- 前処置方法の選択(自宅または院内)
- 待ち時間と滞在時間の短縮
- 電話予約とWEB予約の導入
特に、平日お忙しい方のために土曜日にも内視鏡検査を行っていることは、多くの患者さんに喜ばれています。「仕事を休まずに検査が受けられて助かる」という声をいただくことが多いです。
また、当院では高性能な拡大内視鏡を導入しており、大学病院に劣らない内視鏡検査が可能です。特殊な光によって粘膜の微細な変化まで観察できるため、早期がんの発見率が向上しています。
まとめ:大腸カメラ検査の所要時間と心構え
大腸カメラ検査の所要時間について、まとめてみましょう。
- 検査自体は10〜15分程度(病変があれば30分程度)
- 前処置(腸管洗浄)に2〜4時間
- 鎮静剤使用時の安静時間に1〜2時間
- 全体では3〜6時間程度の所要時間
大腸カメラ検査は、大腸がんの早期発見・早期治療に非常に有効な検査です。大腸がんは早期に発見すれば90%以上の確率で治癒する病気ですので、定期的な検査をおすすめします。
当院では、患者さんの不安や負担を最小限に抑えるために、鎮静剤を使用した無痛検査や、患者さんの状況に合わせた前処置方法の選択など、さまざまな工夫を行っています。
「大腸カメラ検査を受けたいけど不安…」という方は、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富な消化器・内視鏡専門医が、丁寧に対応させていただきます。
大腸カメラ検査に関するご質問やご予約は、お電話(06-6930-1700)またはWEBからお気軽にお問い合わせください。
詳細は石川消化器内科内視鏡クリニックのウェブサイトでもご確認いただけます。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
胃カメラ検査方法の進化~2025年最新の検査技術とは
胃カメラ検査方法の進化~2026年最新の検査技術とは

胃カメラ検査の現状と進化の背景
「胃カメラ=つらい」というイメージをお持ちの方は少なくありません。かつての胃カメラ検査は、太いスコープを喉に通す際の不快感や痛みが強く、多くの患者さんにとって大きな負担となっていました。
しかし、近年の医療技術の進歩は目覚ましく、胃カメラ検査も大きく変わりつつあります。特に2026年現在では、患者さんの負担を軽減するための様々な工夫が取り入れられています。
当院でも最新の内視鏡システムを導入し、患者さんの苦痛を最小限に抑えながら、より精度の高い検査を提供できるよう日々努めています。胃カメラ検査は、胃がんをはじめとする様々な消化器疾患の早期発見に欠かせない重要な検査です。
内視鏡検査の技術革新は、単に検査の苦痛を減らすだけでなく、より早期の段階で病変を発見できる精度の向上にもつながっています。これにより、治療の選択肢が広がり、患者さんの予後改善に大きく貢献しているのです。

胃カメラ検査を受けたことがある方なら、あの喉の違和感や不安感を思い出されるかもしれません。でも、今日お伝えする最新の検査方法を知れば、きっとそのイメージが変わるはずです。
経鼻内視鏡と経口内視鏡の進化
胃カメラ検査には、大きく分けて「経鼻内視鏡」と「経口内視鏡」の2種類があります。それぞれの特徴と最新の進化について詳しくご説明します。
経口内視鏡は従来型の胃カメラで、口からスコープを挿入する方法です。かつては9mm前後の太さがありましたが、現在では7mm台の細いスコープが主流となっています。当院でも口からの検査用に細径スコープを導入し、患者さんの負担軽減に努めています。
一方、経鼻内視鏡は鼻から細いスコープ(約5〜6mm)を挿入する方法で、舌の奥を通らないため嘔吐反射が起きにくいという大きなメリットがあります。2026年現在、この経鼻内視鏡の技術はさらに進化し、画質や処置能力も向上しています。

経鼻内視鏡のメリットは以下の通りです:
- 嘔吐反射が少なく、検査が楽
- 会話が可能なので不安の軽減につながる
- 鎮静剤なしでも受けやすく、検査後すぐに運転・仕事が可能
経口内視鏡も進化しており、以下のようなメリットがあります:
- 太めのスコープなので高画質で、詳細な観察が可能
- 鉗子口が大きく、処置や組織の採取がしやすい
- 吸引・送水性能が高く、検査時間が比較的短い
どちらを選ぶべきかは、患者さんの状態や検査の目的によって異なります。例えば、嘔吐反射が強い方や検査への不安が強い方には経鼻内視鏡が、より詳細な観察や処置が必要な方には経口内視鏡がおすすめです。
当院では患者さん一人ひとりの状態に合わせて最適な検査方法をご提案しています。初めての方も、過去につらい経験をされた方も、ぜひご相談ください。
AI搭載内視鏡システムの革新
2026年現在、胃カメラ検査の世界で最も注目すべき進化の一つが、AI(人工知能)搭載内視鏡システムです。この革新的な技術により、検査の精度と効率が飛躍的に向上しています。
当院でも導入している最新のAI搭載内視鏡診断支援機能「CAD EYE」は、深層学習(Deep Learning)を活用して内視鏡検査時の病変の検出と鑑別をサポートします。2025年5月には進化したAI「EW、10-EG01 ver2.0」へバージョンアップされ、さらに正確な診断が可能になりました。
AIの導入によって、どのような変化がもたらされたのでしょうか?
まず、病変の検出率が大幅に向上しました。人間の目では見逃してしまうような微細な変化もAIが検出し、医師に提示します。特に早期胃がんの発見率が向上したことは、患者さんの予後改善に大きく貢献しています。
次に、検査の効率化が進みました。AIが瞬時に異常を検出することで、医師はより詳細な観察や診断に集中できるようになりました。これにより、検査時間の短縮にもつながっています。
さらに、診断の標準化も進んでいます。医師の経験や技術による診断のばらつきが減少し、どの患者さんも均質で高精度な検査を受けられるようになりました。
当院では、このAI技術と消化器・内視鏡専門医の経験を組み合わせることで、より確実な診断を目指しています。技術は進化しても、それを使いこなす医師の経験と判断力が重要であることに変わりはありません。
AIは医師の代わりになるものではなく、医師の診断をサポートする強力なツールです。最終的な判断は、患者さんの状態を総合的に評価できる医師が行います。

鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査
胃カメラ検査に対する不安や恐怖感の多くは、「痛みや不快感」に関するものです。この問題を解決する画期的な方法として、鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査が広く普及してきました。
鎮静剤とは、検査中に患者さんを「半分眠ったような状態」にする薬剤です。完全に意識がなくなる全身麻酔とは異なり、必要に応じて患者さんとコミュニケーションを取ることも可能な状態を作り出します。
当院では、患者さんの状態に合わせて適切な量の鎮静剤を使用し、安全かつ快適な検査環境を提供しています。多くの患者さんが「気がついたら終わっていた」と驚かれるほど、苦痛を感じることなく検査を終えられます。
鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査のメリットは以下の通りです:
- 検査中の痛みや不快感をほとんど感じない
- 嘔吐反射や緊張による筋肉の硬直が起こりにくい
- 医師が落ち着いて丁寧に検査できるため、より精度の高い検査が可能
- 患者さんの検査への恐怖感が軽減され、定期的な検査を受けやすくなる
一方で、鎮静剤使用にあたって注意すべき点もあります。検査後は薬の効果が完全に切れるまで、運転や重要な判断を要する作業は避ける必要があります。当院では検査後にリカバリールームでゆっくり休んでいただき、安全に帰宅できる状態になるまでサポートしています。
鎮静剤を使用するかどうかは患者さん自身が選択できますが、検査への不安が強い方や過去に苦しい経験をされた方には特におすすめしています。経鼻内視鏡と鎮静剤を組み合わせることで、さらに快適な検査体験が可能です。
「検査は必要だとわかっていても怖くて受けられない」という方は、ぜひ鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査をご検討ください。検査への恐怖心が軽減されることで、定期的な検査が可能になり、早期発見・早期治療につながります。
特殊光観察と拡大内視鏡技術
胃カメラ検査の精度を飛躍的に向上させている技術として、特殊光観察と拡大内視鏡技術があります。これらの技術は、肉眼では見えにくい微細な病変を発見するのに非常に有効です。
特殊光観察とは、通常の白色光ではなく、特定の波長の光を使用して粘膜の状態をより鮮明に観察する技術です。2026年現在、主に以下のような技術が普及しています:
- Blue Laser Imaging (BLI):青色レーザー光を使用して血管や粘膜の微細な変化を強調
- Linked Color Imaging (LCI):赤色の色調を強調し、炎症や発赤を見やすくする
- Narrow Band Imaging (NBI):特定の波長の光で血管パターンを強調
当院では最新のLED光源搭載の内視鏡システムを導入し、これらの特殊光観察を駆使して詳細な検査を行っています。特に早期胃がんの発見には非常に有効で、通常の観察では見逃してしまうような微細な変化も捉えることができます。
また、拡大内視鏡技術も大きく進化しています。最大で約80〜100倍まで拡大観察が可能となり、細胞レベルの変化を観察できるようになりました。これにより、病変の良性・悪性の判断がより正確になり、不必要な生検(組織採取)を減らすことも可能になっています。
特殊光観察と拡大内視鏡を組み合わせることで、以下のようなメリットがあります:
- 早期胃がんの発見率向上
- 病変の範囲や深達度のより正確な評価
- 炎症と腫瘍性病変の鑑別精度向上
- ピロリ菌感染の有無や程度の評価
これらの技術は、大学病院などの高度医療機関だけでなく、当院のような地域のクリニックでも導入が進んでいます。患者さんは身近な医療機関で最先端の検査を受けられるようになり、早期発見・早期治療の機会が広がっています。
胃カメラ検査は「つらい」というイメージから「精度が高く、早期発見に役立つ重要な検査」というイメージに変わりつつあります。定期的な検査で、ご自身の健康を守りましょう。
検査の流れと患者さんへの配慮
胃カメラ検査に対する不安を軽減するために、当院では検査の流れを明確にご説明し、様々な配慮を行っています。ここでは、検査前から検査後までの流れと、患者さんへの配慮についてご紹介します。
検査前の準備
胃カメラ検査の前には、胃の中を空にしておく必要があります。当院では、検査の2時間前からの絶飲食をお願いしています。これは必要最小限の絶食時間で、患者さんの負担を軽減するための配慮です。
検査当日は、首元がゆったりした服装でお越しいただくと楽に検査を受けられます。また、入れ歯をお使いの方は、検査前に外していただきます。
検査への不安が強い方には、事前に医師や看護師が丁寧に説明し、質問にお答えします。鎮静剤の使用や経鼻・経口の選択など、患者さんの希望を最大限尊重した検査方法をご提案します。
検査中の配慮
検査室に入ると、まず喉の麻酔を行います。経口内視鏡の場合はスプレーやうがい薬で、経鼻内視鏡の場合は鼻腔内に麻酔薬を塗布します。鎮静剤を使用する場合は、この時点で静脈から投与します。
検査中は、患者さんの状態を常に観察し、苦痛を最小限に抑えるよう配慮しています。必要に応じて声をかけ、安心感を提供します。また、最新の内視鏡システムにより、検査時間の短縮も図っています。
検査後のケア
検査後は、喉の麻酔や鎮静剤の効果が切れるまでリカバリールームでゆっくり休んでいただきます。当院では広々としたリカバリールームを完備し、患者さんがリラックスできる環境を整えています。
検査結果は、可能な限り当日に医師から詳しく説明します。画像をお見せしながら、わかりやすく丁寧に説明することを心がけています。不安な点や疑問点があれば、遠慮なくお尋ねください。
当院では、患者さん一人ひとりの状態や不安に寄り添った検査を提供することを大切にしています。「検査は怖い」というイメージを変え、「安心して受けられる検査」と感じていただけるよう努めています。
胃カメラ検査は、胃がんをはじめとする様々な消化器疾患の早期発見に欠かせない重要な検査です。少しでも不安や疑問があれば、ぜひ当院にご相談ください。
定期検査の重要性と早期発見のメリット
胃カメラ検査は、症状がある時だけでなく、定期的に受けることで多くの疾患を早期に発見できる重要な検査です。特に40歳を過ぎたら、症状がなくても定期的な検査をお勧めします。
なぜ定期検査が重要なのでしょうか?それは、多くの消化器疾患、特に胃がんは初期段階では自覚症状がほとんどないからです。症状が現れた時には、すでに進行している場合が少なくありません。
当院の院長である私も、「念のため」と受けた検査でポリープが見つかった経験があります。その時は全く症状がなかったにもかかわらず、です。このような「無症状の段階での発見」こそが、定期検査の大きなメリットです。

早期発見のメリットは計り知れません。例えば、胃がんの場合:
- 早期胃がんの5年生存率は90%以上と非常に高い
- 早期であれば内視鏡的治療で切除可能な場合が多く、体への負担が少ない
- 入院期間の短縮や社会復帰の早期化につながる
- 医療費の負担軽減にもつながる
また、ピロリ菌感染が見つかった場合には、除菌治療を行うことで胃がんのリスクを大幅に減らすことができます。これも早期発見・早期治療の重要な例です。
当院では、患者さんの負担を最小限に抑えた検査方法を提供することで、定期検査のハードルを下げる努力をしています。鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査や、経鼻内視鏡による楽な検査方法など、患者さんに合った方法をご提案します。
また、忙しい方のために土曜日の検査や、初診当日の検査にも対応しています。「時間がない」という理由で検査を先延ばしにすることがないよう、柔軟な対応を心がけています。
健康診断でバリウム検査を受けている方も、より詳細な検査として胃カメラ検査をお勧めします。バリウム検査では見つけられない小さな病変も、胃カメラなら発見できる可能性が高まります。
あなたの健康を守るために、定期的な胃カメラ検査を検討してみませんか?当院では、患者さん一人ひとりの不安や疑問に丁寧にお答えしながら、最適な検査をご提供します。
まとめ:進化する胃カメラ検査と当院の取り組み
胃カメラ検査は、技術の進歩により大きく変わりました。経鼻内視鏡や細径スコープの普及、鎮静剤を使用した無痛検査の一般化、AI技術や特殊光観察の導入など、患者さんの負担を軽減しながら診断精度を向上させる取り組みが進んでいます。
当院では、これらの最新技術を積極的に導入し、患者さんに最適な検査環境を提供しています。消化器・内視鏡専門医である私が全ての検査を担当し、高い精度と安全性を確保しています。
また、患者さんの利便性を考慮し、初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しています。待ち時間と滞在時間の短縮にも取り組み、忙しい方でも受診しやすい環境を整えています。
胃カメラ検査は、胃がんをはじめとする様々な消化器疾患の早期発見に欠かせない重要な検査です。かつての「つらい検査」というイメージを払拭し、「安心して受けられる検査」として多くの方に定期的に受けていただきたいと考えています。
健康に不安のある方はもちろん、症状がない方も、40歳を過ぎたら定期的な胃カメラ検査をお勧めします。早期発見・早期治療が、あなたの健康と生活の質を守ります。
当院では、患者さん一人ひとりの状態や不安に寄り添い、最適な検査方法をご提案します。胃カメラ検査に関する疑問や不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
最後に、胃カメラ検査は「受けたくない検査」ではなく、「あなたの健康を守るための大切な検査」です。検査技術の進化により、その負担は大きく軽減されています。ぜひ、定期的な検査で健康管理にお役立てください。
詳しい情報や予約については、石川消化器内科内視鏡クリニックのウェブサイトをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。皆様の健康を誠心誠意サポートいたします。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
内視鏡検査の前日に守るべき注意点~安心して検査を受けるために
内視鏡検査の前日に守るべき注意点~安心して検査を受けるために

内視鏡検査前日の注意点の重要性
内視鏡検査は、食道・胃・十二指腸や大腸の状態を直接観察できる重要な検査です。検査の精度を高め、スムーズに進めるためには、前日からの準備が非常に重要になります。
私が消化器内科医として日々感じるのは、検査前の準備が適切に行われているかどうかで、検査の質が大きく変わるということです。
特に大腸内視鏡検査では、腸内をきれいにしておかないと、小さなポリープや初期のがんを見逃してしまう可能性があります。胃カメラでも、胃の中に食べ物が残っていると、粘膜の状態を正確に観察できません。
検査前日に適切な準備をすることで、より正確な診断が可能になるだけでなく、検査自体の苦痛も軽減できるのです。

どうしても検査に対して不安を感じる方も多いと思います。しかし、適切な準備をすることで、検査当日の負担を大幅に減らすことができます。
胃カメラ(上部消化管内視鏡)検査前日の注意点
胃カメラ検査を受ける方は、検査の3日前から、お酒や脂質の多い食事はなるべく控えるようにしましょう。これは胃の状態を整え、検査をスムーズに行うための基本的な準備です。
検査前日の食事については、特に夕食が重要になります。夜9時頃までには消化の良い夕食を済ませるようにしてください。
消化の良い食事とは、食物繊維や脂肪分が少なく、炭水化物やたんぱく質中心の食事を指します。具体的には、白米やうどん、食パン、脂身の少ない白身魚や鶏むね肉、豆腐などが適しています。
胃カメラ検査前日に避けるべき食品
検査前日は以下のような食品は避けるようにしましょう:
- 乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズなど)
- 繊維質の多い野菜や果物(ごぼう、キャベツ、りんごなど)
- 豆類(納豆、煮豆など)
- きのこ類(しいたけ、しめじなど)
- 海藻類(海苔、わかめなど)
- 脂肪分の多い肉類(ばら肉、ベーコンなど)
- 揚げ物や油っこい料理
- 香辛料の強い食品
これらの食品は消化に時間がかかり、胃の中に残りやすいため、検査の妨げになる可能性があります。

検査前日の夕食後は、水やお茶などの透明な飲み物以外は口にしないようにしましょう。カフェインを含む飲み物は睡眠の妨げになる可能性があるため、夜遅くの摂取は控えた方が良いでしょう。
胃カメラ検査前日の服薬について
普段服用している薬がある場合は、事前に医師に相談することが大切です。特に血液をサラサラにする薬(抗血栓薬)を服用している方は、検査前に休薬が必要な場合があります。
ただし、観察のみの内視鏡検査であれば、基本的には休薬の必要はないケースが多いです。高血圧の薬など、毎日服用が必要な薬については、少量の水で服用しても問題ないことが多いですが、必ず事前に医師の指示を仰いでください。
大腸内視鏡検査前日の注意点
大腸内視鏡検査は、腸内をきれいにしておくことが何よりも重要です。検査の精度を高めるためには、前日の食事選びが大きなカギを握っています。
大腸内視鏡検査の前日は、消化の良い食事を心がけましょう。これにより、腸内に残渣が残りにくくなり、検査当日の下剤の効果も高まります。
大腸内視鏡検査前日に食べても良い食品
前日の食事で摂取しても問題ない食品には、以下のようなものがあります:
- 白米・おかゆ(玄米や雑穀米は避ける)
- うどん・そうめん(そばやラーメンは避ける)
- 食パン(具材の入っていないもの)
- 脂肪の少ない肉(鶏むね肉、赤身の牛肉など)
- 白身魚(たら、ひらめなど)
- 豆腐
- 卵
- じゃがいも
- バナナ(他の果物は避ける)
これらの食品は消化が良く、腸内に残りにくいため、検査前日の食事として適しています。
大腸内視鏡検査前日に避けるべき食品
一方、以下のような食品は避けるべきです:
- 食物繊維の多い野菜(葉物野菜、根菜類など)
- 海藻類(わかめ、のりなど)
- きのこ類
- 豆類(納豆、煮豆など)
- 種のある果物(イチゴ、キウイ、トマトなど)
- 全粒粉パンや玄米
- 脂肪分の多い肉(ばら肉、ベーコンなど)
- 乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズなど)
これらの食品は消化されにくく、腸内に残りやすいため、検査の妨げになる可能性があります。
前日の夕食は21時までに済ませるようにし、それ以降は水やお茶などの透明な飲み物のみにしましょう。
大腸内視鏡検査前日の下剤について
医療機関によっては、検査前日の夜に下剤(ラキソベロンなど)を服用するよう指示される場合があります。これは腸内をあらかじめ空にしておくためのものです。
指示された下剤は必ず決められた時間に服用してください。下剤の効果は個人差がありますが、服用後は何度かトイレに行く必要があるため、夜間の外出予定がない時間帯に服用するとよいでしょう。
内視鏡検査前日のアルコールと喫煙について
内視鏡検査の前日は、アルコールの摂取は避けるようにしましょう。アルコールは胃粘膜を刺激し、炎症を起こしやすくするため、検査結果に影響を与える可能性があります。
また、アルコールには利尿作用があり、体内の水分バランスを崩す恐れがあります。特に大腸内視鏡検査前は、下剤の服用により脱水状態になりやすいため、アルコールの摂取は控えた方が良いでしょう。
喫煙についても、検査前日から当日にかけては控えることをお勧めします。喫煙は胃酸の分泌を促進し、胃粘膜を刺激する可能性があります。また、咳込みのリスクが高まり、検査中の安全性に影響することもあります。
どうしても禁煙が難しい方は、少なくとも検査当日の朝は喫煙を控えるようにしましょう。
内視鏡検査前日の服薬について
普段から薬を服用している方は、内視鏡検査を受ける際に注意が必要です。特に以下の薬については、事前に医師に相談することが重要です。
血液をサラサラにする薬(抗血栓薬)
アスピリンやクロピドグレルなどの抗血小板薬、ワーファリンやDOACなどの抗凝固薬を服用している方は、検査前に休薬が必要な場合があります。
ただし、これらの薬は重要な病気の治療や予防のために服用していることが多いため、自己判断で中止せず、必ず処方医と内視鏡検査を行う医師に相談してください。
観察のみの内視鏡検査であれば、多くの場合は休薬の必要はありませんが、組織検査(生検)やポリープ切除を行う可能性がある場合は、休薬が必要になることがあります。
糖尿病のお薬
インスリンや経口血糖降下薬を使用している糖尿病患者さんは、検査前の絶食に伴い、薬の用量調整が必要になることがあります。低血糖を防ぐため、検査当日の朝のインスリン注射や内服薬は、医師の指示に従って減量または中止してください。
その他の常用薬
高血圧の薬や心臓の薬など、毎日服用が必要な薬については、通常通り服用しても問題ないことが多いです。少量の水で服用することができます。
ただし、利尿剤については検査当日の朝は服用を控えるよう指示されることがあります。これは検査中のトイレの問題を避けるためです。

内視鏡検査前日の心構えと準備物
内視鏡検査を受ける前日は、精神的な準備も大切です。不安や緊張は誰にでもあるものですが、過度に心配すると検査当日の負担が大きくなってしまいます。
当院では鎮静剤(麻酔)を使用した無痛内視鏡検査を行っており、半分眠ったような状態で検査を受けることができます。多くの患者さんが「思ったより楽だった」と感想を述べられます。
検査前日は、以下のような準備をしておくと安心です:
- 検査当日の持ち物の確認(保険証、診察券、お薬手帳など)
- 検査後の予定を空けておく(特に鎮静剤を使用する場合)
- 楽な服装の準備(締め付けのない服、ベルトのないズボンなど)
- 爪の長さを整える(マニキュアは落としておく)
- アクセサリー類は外しておく
鎮静剤を使用する場合は、検査当日の車の運転ができませんので、公共交通機関の利用や家族の送迎を手配しておくことも重要です。
検査前日の睡眠について
検査前日は、十分な睡眠をとるよう心がけましょう。良質な睡眠は、検査当日の緊張を和らげるのに役立ちます。
寝る前にリラックスできる時間を作り、スマートフォンやパソコンなどの画面を見る時間は控えめにするとよいでしょう。温かい飲み物(カフェインを含まないもの)を飲んだり、軽いストレッチをしたりするのもおすすめです。
内視鏡検査前日に関するよくある質問
内視鏡検査の前日に関して、患者さんからよく質問を受けます。ここでは、そのような質問にお答えします。
前日に食べてはいけないものを食べてしまった場合はどうすればいいですか?
誤って食べてしまった場合でも、パニックにならないでください。少量であれば大きな問題にはならないことが多いです。ただし、大量に摂取した場合や、検査直前に食べてしまった場合は、医療機関に連絡して指示を仰ぐことをお勧めします。
前日の夕食を21時までに終えられない場合はどうすればいいですか?
仕事などの都合で21時までに夕食を済ませることが難しい場合は、可能な限り軽めの食事にし、消化の良いものを選びましょう。また、事前に医療機関に相談しておくことをお勧めします。
検査前日に運動してもいいですか?
軽い運動は問題ありませんが、激しい運動や長時間の運動は避けた方が良いでしょう。特に大腸内視鏡検査前は、下剤の服用により脱水状態になりやすいため、激しい運動は控えることをお勧めします。
前日からの絶食で空腹感が強い場合はどうすればいいですか?
水やお茶などの透明な飲み物は摂取できますので、これらで空腹感を紛らわせましょう。どうしても空腹感が強い場合は、医師に相談してください。
まとめ:安心して内視鏡検査を受けるために
内視鏡検査は、消化器疾患の早期発見・早期治療に非常に重要な検査です。検査の精度を高め、スムーズに進めるためには、前日からの適切な準備が欠かせません。
胃カメラ検査では、検査前日の夕食は消化の良いものを選び、夜9時以降は水やお茶以外は口にしないようにしましょう。大腸内視鏡検査では、前日の食事選びが特に重要で、食物繊維や脂肪分の多い食品は避け、消化の良い食事を心がけてください。
また、アルコールや喫煙は控え、服用中の薬がある場合は事前に医師に相談することが大切です。検査前日は十分な睡眠をとり、精神的にもリラックスできるよう心がけましょう。
当院では、患者さんの不安や負担を軽減するために、鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査を提供しています。また、検査に関するご質問やご不安な点があれば、いつでもご相談ください。
適切な準備と心構えで、安心して内視鏡検査を受けていただき、皆さまの健康維持・増進にお役立ていただければ幸いです。
詳しい情報や内視鏡検査のご予約については、石川消化器内科内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
内視鏡検査後の食事はいつから?正しい回復食と注意点
内視鏡検査後の食事はいつから?正しい回復食と注意点

内視鏡検査後の食事再開タイミング
内視鏡検査を受けた後、「いつから食事ができるのか」という疑問をお持ちの方は多いでしょう。検査後の食事再開タイミングは、検査の種類や使用した薬剤によって異なります。
胃カメラ検査では、のどや鼻に麻酔をかけるため、検査後1時間は飲食を控える必要があります。麻酔が残った状態での飲食は誤嚥や窒息の危険性があるからです。
一方、大腸カメラ検査の場合は、基本的に食事制限はありません。鎮静剤を使用した場合は、薬剤の効果がなくなる1時間後から食事が可能です。
ただし、組織採取(生検)やポリープ切除を行った場合は、切除部位からの出血リスクを考慮して、より慎重な食事管理が必要になります。
どう思いますか?検査後に「早く食べたい」という気持ちはわかりますが、安全のためにも医師の指示に従うことが大切です。
胃カメラ検査後の適切な食事と注意点
胃カメラ検査後、麻酔が切れた1時間後から少しずつ水を飲み始めましょう。むせたり違和感がなければ、通常の食事に移行できます。
検査直後の胃は敏感な状態です。最初は消化の良い食品を選ぶことが重要です。
検査後におすすめの食品としては、やわらかいご飯やおかゆ、うどんなどの麺類、煮魚や鶏のささみ肉、赤身肉、みそ汁、野菜の煮物(大根・にんじん・かぼちゃなど)、りんごやバナナなどの果物、ヨーグルト、プリンなどが適しています。

一方、控えるべき食品としては、カレーや麻婆豆腐、ラーメン、パスタなどの刺激物、キムチ、揚げ物、炒め物、柑橘類(みかん、グレープフルーツ、レモン、ゆず)、アルコール、コーヒー、紅茶、炭酸飲料、冷たすぎる飲み物などがあります。
検査で組織を採取した場合は特に注意が必要です。当日は消化の良いものを食べ、アルコールなどの刺激物や脂っこい食べ物は控えましょう。
胃カメラ検査後に起こりうる症状として、腹部の張りやのどの違和感、ガスの排出などがありますが、これらは検査による一時的な刺激の結果であり、多くの場合は翌日には自然に改善します。
青い便が出ることがありますが、これは検査時に使用した色素(インジゴカルミンなど)によるものなので心配ありません。
大腸カメラ検査後の食事プラン
大腸カメラ検査後は基本的に食事制限はありませんが、ポリープ切除を行った場合は注意が必要です。ポリープ切除後は10日間ほど食事制限があり、段階的に普通の食事に戻していきます。
ポリープ切除後の食事は、4つのステップで徐々に普通の食事に戻すことをお勧めします。1ステップにつき2~3日かけて進めていきましょう。
ステップ1:液状・流動食(1-3日目)
コンソメスープ、みそ汁(具なし)、おもゆ、ゼラチンゼリーなど、消化に非常に優しい液状の食品から始めます。
ステップ2:飲み込める軟らかさ(4-6日目)
三分がゆ、煮込みうどん、卵豆腐、はんぺん、茶碗蒸しなど、咀嚼をあまり必要としない軟らかい食品に移行します。

ステップ3:消化の良い食事(7-9日目)
白米、豆腐、白身魚、鶏ささみ、煮野菜など、消化は良いが栄養価の高い食品へと範囲を広げます。
ステップ4:通常食(10日目以降)
通常の食事に戻しますが、しばらくは脂っこいものや刺激物、アルコールは控えめにするのが賢明です。
大腸ポリープ切除後に食べても良い食品の例としては、白米のおかゆ、食パン、素うどん、白身魚、魚のすり身、脂の少ない肉、鶏ささみ、皮のない鶏肉、卵、卵豆腐、豆腐、豆乳、納豆、みそ、ほうれん草、かぼちゃ(種・皮は除く)、白菜、大根・かぶ(葉は除く)、アボカド、いも(皮は除く)、バナナ、りんご、プリン、具のないゼリーなどがあります。
一方、避けるべき食品としては、玄米、オートミール、ラーメン、焼きそば、脂の多い魚、いか、たこ、ハム、ソーセージ、脂の多い肉、揚げ物料理、枝豆、ごぼう、たけのこ、れんこん、とうもろこし、こんにゃく、きのこ、海藻、香辛料、ハーブ、すいか、いちご、ドライフルーツ、ナッツ、コーンフレーク、チョコレート、ケーキ、アルコールなどがあります。
内視鏡検査後の生活上の注意点
内視鏡検査後の食事だけでなく、生活面での注意点も重要です。特にポリープ切除や組織採取を行った場合は、より慎重な生活管理が必要になります。
大腸ポリープ切除後の生活面での注意点として、切除当日の入浴は湯船に入らず、シャワーで済ませることをお勧めします。翌日からは長湯にならない程度に湯船に入っても問題ありません。
また、切除後1週間は腹圧が強くかかるような行動は控えるようにしましょう。具体的には、筋トレやゴルフなどの運動は避け、旅行や出張もなるべく避けることが望ましいです。これは出血した場合のリスクを軽減するためです。
内視鏡検査後24時間はアルコールを控えることをお勧めします。検査の負担や薬剤の影響で体調が崩れやすく、特に鎮静剤を使用した場合はアルコールとの併用による副作用も懸念されます。
検査後に黒い便(血便)や嘔吐、強い腹痛、ふらつきなどの症状が出た場合は、腸壁や消化管に傷や出血、生検部位からの出血の可能性があるため、早急に医療機関を受診してください。
当院では、内視鏡検査後の患者様の回復をサポートするため、検査後の食事や生活についての詳細なガイドラインをお渡ししています。不安なことがあれば、遠慮なくご相談ください。
内視鏡検査後の回復を早める食事の工夫
内視鏡検査後の回復を早めるためには、単に食べ物の種類を選ぶだけでなく、食べ方にも注意が必要です。
まず、食事はゆっくりとよく噛んで食べることが重要です。早食いや大食いは胃腸に一度に大きな負担をかけてしまいます。一口ずつ時間をかけて、よく噛んで食べましょう。
食事の量は「腹八分目」を目安にし、満腹になるまで食べるのは避けましょう。必要であれば、1日の食事回数を3回から5~6回に増やして、一回あたりの量を減らすのも良い方法です。
胃腸の回復を助ける栄養素として、タンパク質とビタミンが重要です。タンパク質は組織の修復に必要で、ビタミンA・C・Eは粘膜の回復を促進します。消化に優しい形で、これらの栄養素を含む食品を取り入れましょう。
水分摂取も大切です。十分な水分は消化を助け、体内の老廃物の排出を促します。ただし、冷たすぎる飲み物や炭酸飲料、カフェインを含む飲み物は避け、常温の水やお茶を少しずつ飲むようにしましょう。
食事の環境も回復に影響します。リラックスした状態で食事をすることで、消化活動がスムーズになります。テレビを見ながらや立ったままの食事は避け、座って落ち着いた環境で食事をしましょう。
消化を助ける工夫として、食材を小さく切る、よく煮込む、蒸す、茹でるなどの調理法を選びましょう。油で揚げる、強火で炒めるなどの調理法は消化に負担をかけるため避けてください。
皆さんは検査後の食事で何か工夫されていますか?
まとめ:安全な回復のための食事ガイド
内視鏡検査後の食事は、検査の種類や処置内容によって異なりますが、基本的には消化に優しい食品から始め、徐々に通常の食事に戻していくことが重要です。
胃カメラ検査後は麻酔が切れる1時間後から水分摂取を始め、問題なければ消化の良い食事に移行します。大腸カメラ検査後は基本的に食事制限はありませんが、ポリープ切除を行った場合は10日間ほどかけて段階的に食事を戻していきます。
検査後に共通して避けるべき食品は、刺激物(香辛料、酸味の強い食品)、脂っこい食品(揚げ物、炒め物)、消化の悪い食品(食物繊維の多い野菜、海藻類、きのこ類)、アルコール、カフェイン、炭酸飲料などです。
内視鏡検査は消化管の健康を守るための重要な検査です。検査後の適切な食事管理は、検査の効果を最大化し、合併症のリスクを最小限に抑えるために不可欠です。
当院では、患者様一人ひとりの状態に合わせた食事アドバイスを提供しています。不安なことがあれば、遠慮なくご相談ください。
内視鏡検査後の適切な食事と生活習慣で、胃腸の健康を守り、快適な日常生活を取り戻しましょう。
詳しい内視鏡検査や消化器疾患の診断・治療については、石川消化器内科内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。消化器・内視鏡専門医として、皆様の健康をサポートいたします。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
内視鏡検査が初めての方へ〜不安を解消する7つの準備と心構え
内視鏡検査が初めての方へ〜不安を解消する7つの準備と心構え

内視鏡検査を受ける前に知っておきたい基本情報
内視鏡検査と聞くと、多くの方が「痛いのではないか」「苦しいのではないか」と不安を感じます。私が院長を務める石川消化器内科内視鏡クリニックでは、そんな患者さんの声を日々お聞きしています。
内視鏡検査は、食道・胃・十二指腸や大腸の内部を直接観察できる非常に重要な検査です。早期の胃がんや大腸がんの発見に役立つだけでなく、その場でポリープを切除することも可能な、予防医療の要となる検査なのです。

しかし、初めて検査を受ける方にとって、未知の経験への不安は当然のことです。この記事では、消化器内科・内視鏡専門医として、内視鏡検査を初めて受ける方の不安を解消するための7つの準備と心構えについてお伝えします。
1. 検査の種類と目的を理解する
内視鏡検査には主に「上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)」と「下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)」の2種類があります。それぞれの検査の目的と内容を理解しておくことで、心の準備ができます。
胃カメラは食道、胃、十二指腸を観察する検査で、胃炎や逆流性食道炎、胃潰瘍、胃がんなどの早期発見に役立ちます。一方、大腸カメラは大腸全体を観察し、大腸ポリープや大腸がんなどを発見するための検査です。
どちらも細い管の先端にカメラがついた内視鏡を体内に挿入して行います。最新の内視鏡カメラは高精細な画像を映し出すことができ、微細な病変も見逃さない精度を持っています。
あなたはなぜ内視鏡検査を受けることになったのでしょうか?
症状がある方、健康診断で異常を指摘された方、あるいは予防のために検査を受ける方など、目的は様々です。検査の目的を明確に理解しておくことで、検査への前向きな気持ちが生まれます。
胃カメラで分かること
胃カメラでは、食道では逆流性食道炎や食道がん、胃では胃炎、胃潰瘍、胃ポリープ、胃がんなどを発見できます。また、ピロリ菌感染の有無も調べることができます。
特に胃がんは早期発見が重要です。日本人に多い病気ですが、早期に発見できれば内視鏡治療で完治する可能性が高まります。
大腸カメラで分かること
大腸カメラでは、大腸ポリープ、大腸がん、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病など)、虚血性大腸炎などを発見できます。
大腸ポリープは放置すると大腸がんになる可能性があります。検査中に見つかったポリープはその場で切除できるため、がん予防にもつながる重要な検査です。
2. 検査前の準備を正しく行う
内視鏡検査の成功は、適切な事前準備にかかっています。検査の種類によって準備方法が異なりますので、しっかり理解しておきましょう。

胃カメラの場合、検査前日の夕食後から絶食が必要です。水分は検査当日の2時間前までなら少量摂取可能ですが、牛乳やジュースなどは避けてください。また、常用している薬がある場合は、事前に医師に相談することが重要です。
大腸カメラの準備はもう少し複雑です。検査の2〜3日前から食物繊維の多い食品や種のある食品を避け、検査前日は消化の良い食事を心がけます。そして最も重要なのが腸管洗浄液の服用です。
大腸をきれいに洗浄するために、検査前日の夜や当日の朝に下剤を服用します。下剤の味や量に負担を感じる方もいらっしゃいますが、腸内をしっかり空にすることで、より精度の高い検査が可能になります。
下剤を飲み始めると何度もトイレに行く必要がありますので、検査当日は余裕を持ったスケジュールを組むことをお勧めします。
準備が不十分だと、検査のやり直しが必要になることもあります。医師からの指示をしっかり守りましょう。
胃カメラの前日からの準備
検査前日は通常通りの食事が可能ですが、夕食は21時頃までに済ませましょう。検査当日は朝食を抜き、水分も検査の2時間前までにしておきます。
また、緊張しやすい方は、前日はゆっくり休んで、リラックスした状態で検査に臨むことが大切です。
大腸カメラの前日からの準備
検査前日の夕食は消化の良いものを20時頃までに摂り、就寝前に処方された下剤(錠剤)を服用します。検査当日は食事を控え、指定された時間に腸管洗浄液を飲みます。
脱水を防ぐため、水分はこまめに摂取してください。排便が透明な水様便になるまで洗浄を続けることが重要です。
3. 鎮静剤(麻酔)の選択肢を知る
「内視鏡検査は痛い」というイメージをお持ちの方も多いでしょう。しかし、現代の内視鏡検査では、鎮静剤(麻酔)を使用することで、ほとんど苦痛を感じることなく検査を受けることができます。
当院では、半分眠ったような状態で検査を受けられる鎮静剤を積極的に活用しています。鎮静剤を使用すると、検査中の不快感や痛みをほとんど感じることなく、「あっという間に終わった」という体験をしていただけます。

胃カメラの場合、鎮静剤を使用すると喉の反射が抑えられるため、のどの麻酔を省略できることもあります。のどの麻酔が苦手な方には特におすすめです。
大腸カメラでも鎮静剤は有効です。腸の曲がり角を通過する際の痛みや不快感を軽減し、リラックスした状態で検査を受けることができます。
ただし、鎮静剤を使用した場合は、検査後しばらく休憩が必要です。また、車の運転などは控える必要がありますので、公共交通機関を利用するか、ご家族に送迎をお願いすることをお勧めします。
鎮静剤を使うかどうかは患者さんの希望や体調によって選択できます。不安がある方は、事前に医師に相談してください。
鎮静剤のメリットとデメリット
鎮静剤のメリットは、検査中の痛みや不安を大幅に軽減できることです。多くの患者さんが「検査中のことをほとんど覚えていない」と言われます。
一方、デメリットとしては、検査後に車の運転ができないことや、まれにアレルギー反応が起こる可能性があることです。当院では安全に配慮し、鎮静剤使用中は常に血圧や酸素飽和度などのバイタルサインをモニタリングしています。
4. 検査当日の流れを把握する
検査当日の流れを事前に知っておくことで、不安が軽減されます。ここでは、胃カメラと大腸カメラの検査当日の一般的な流れをご説明します。
胃カメラの場合、まず問診と同意書の記入を行います。その後、のどの麻酔(鎮静剤を使用しない場合)や鎮静剤の投与を行い、左側を下にした横向きの姿勢で検査を開始します。
検査自体は通常10〜15分程度で終了します。鎮静剤を使用した場合は、検査後30分〜1時間程度の休憩が必要です。
大腸カメラの場合も同様に問診と同意書の記入から始まります。腸の準備ができていることを確認した後、検査着に着替えて検査室へ移動します。
左側を下にした横向きの姿勢で検査を開始し、内視鏡を肛門から挿入して大腸全体を観察します。検査時間は15〜30分程度ですが、腸の形状によって個人差があります。
検査中にポリープなどが見つかった場合は、その場で切除することもあります。鎮静剤を使用した場合は、検査後40分〜1時間程度の休憩が必要です。
検査結果は基本的にその日のうちに説明を受けることができますが、組織検査を行った場合は結果が出るまで1〜3週間ほどかかります。
検査中のコミュニケーション
鎮静剤を使用しない場合、検査中に不快感や痛みを感じたら、遠慮なく医師に伝えることが大切です。医師は検査の進行速度や空気の量を調整することができます。
当院では、患者さんの不安や苦痛を最小限にするよう心がけています。検査中も常に患者さんの状態に気を配り、声をかけながら進めていきます。
5. 検査後の注意点を理解する
検査が終わった後も、いくつか注意すべき点があります。適切なアフターケアを行うことで、安全に日常生活に戻ることができます。
胃カメラ検査後は、のどの麻酔が完全に切れるまで(約1時間程度)は飲食を控えてください。のどの感覚が麻痺している間に食事をすると、誤嚥の危険があります。
大腸カメラ検査後は、腸内に空気が残っているためおなかが張ることがあります。ガスをしっかり出すことで徐々に楽になります。ポリープ切除を行った場合は、激しい運動や飲酒、刺激物の摂取を1週間程度控える必要があります。
鎮静剤を使用した場合は、その日の車の運転や機械操作、重要な判断や契約行為は避けてください。また、翌日まで飲酒も控えるべきです。
検査後に強い腹痛や出血などの異常を感じた場合は、すぐに医療機関に連絡してください。特にポリープ切除後は、出血のリスクがあるため注意が必要です。
検査結果の受け取り方
検査結果は、基本的にその日のうちに説明を受けることができます。医師からの説明をしっかり聞き、分からないことがあれば質問することが大切です。
組織検査(生検)を行った場合は、結果が出るまで1〜3週間程度かかります。結果説明の予約をして、必ず受診するようにしましょう。
6. 不安を和らげるための心の準備
内視鏡検査への不安は、多くの方が感じるものです。ここでは、そんな不安を和らげるための心の準備についてお伝えします。

まず、信頼できる医療機関を選ぶことが重要です。内視鏡検査の経験が豊富で、患者さんの不安に寄り添ってくれる医師を選びましょう。事前に医療機関のホームページを確認したり、口コミを調べたりすることも役立ちます。
検査前には、不安なことや分からないことを医師やスタッフに質問することをためらわないでください。疑問点を解消することで、心の準備ができます。
検査当日は、深呼吸やリラクゼーション法を試してみるのも良いでしょう。緊張すると体が硬くなり、検査が難しくなることがあります。リラックスすることで、検査がスムーズに進みやすくなります。
過去に内視鏡検査を受けた方の体験談を聞くことも、不安解消に役立ちます。実際の体験に基づいた情報は、想像上の不安を和らげる効果があります。
あなたは一人ではありません。内視鏡検査は多くの方が受ける一般的な検査です。
検査中のリラックス法
検査中は、ゆっくりと鼻から息を吸い、口から吐く深呼吸を心がけましょう。また、検査と関係のない楽しいことを考えたり、好きな場所をイメージしたりすることで、気を紛らわせることができます。
鎮静剤を使用しない場合は、医師の指示に従い、適切なタイミングで息を吐いたり飲み込んだりすることが大切です。医師やスタッフとのコミュニケーションを大切にしましょう。
7. 定期的な検査の重要性を認識する
内視鏡検査は一度受けて終わりではありません。特に40歳を過ぎたら、定期的に受けることをお勧めします。
胃がんや大腸がんは、早期発見できれば治療の選択肢が広がり、治癒率も高くなります。症状が出てからでは、すでに進行している可能性があります。
胃カメラは1〜2年に1回、大腸カメラは3〜5年に1回の受診が一般的ですが、家族歴やリスク要因によって頻度は変わります。医師と相談して、適切な検査間隔を決めましょう。
初回の検査で異常がなかったとしても、年齢とともにリスクは高まります。定期的な検査を習慣にすることで、万が一の場合も早期発見・早期治療が可能になります。
内視鏡検査は、あなたの健康を守るための大切なパートナーです。最初は不安かもしれませんが、一度経験すれば次回からはずっと楽になります。
検査結果の活用法
検査結果は、単に異常の有無を知るだけでなく、生活習慣の改善にも役立てることができます。例えば、胃炎や逆流性食道炎が見つかった場合は、食生活や生活習慣の見直しのきっかけになります。
検査結果を医師としっかり相談し、必要に応じて生活改善や治療を行うことで、より健康な生活を送ることができるでしょう。
まとめ:内視鏡検査を前向きに受け入れるために
内視鏡検査は、消化器の健康を守るために非常に重要な検査です。初めての方にとっては不安が大きいかもしれませんが、適切な準備と心構えがあれば、その不安は大きく軽減できます。
この記事でご紹介した7つのポイント—検査の種類と目的の理解、適切な事前準備、鎮静剤の選択肢、検査当日の流れ、検査後の注意点、心の準備、そして定期的な検査の重要性—を参考に、ぜひ内視鏡検査に前向きに取り組んでいただければと思います。
当院では、患者さん一人ひとりの不安や疑問に丁寧にお応えし、できる限り苦痛の少ない検査を提供できるよう努めています。内視鏡検査に関するご質問やご不安があれば、いつでもご相談ください。
あなたの勇気ある一歩が、健康な未来への大きな投資になります。
詳しい情報や予約については、石川消化器内科内視鏡クリニックのホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。皆様の健康管理を誠心誠意サポートいたします。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
食後の吐き気を放置するリスクと専門医が勧める検査
食後の吐き気を放置するリスクと専門医が勧める検査
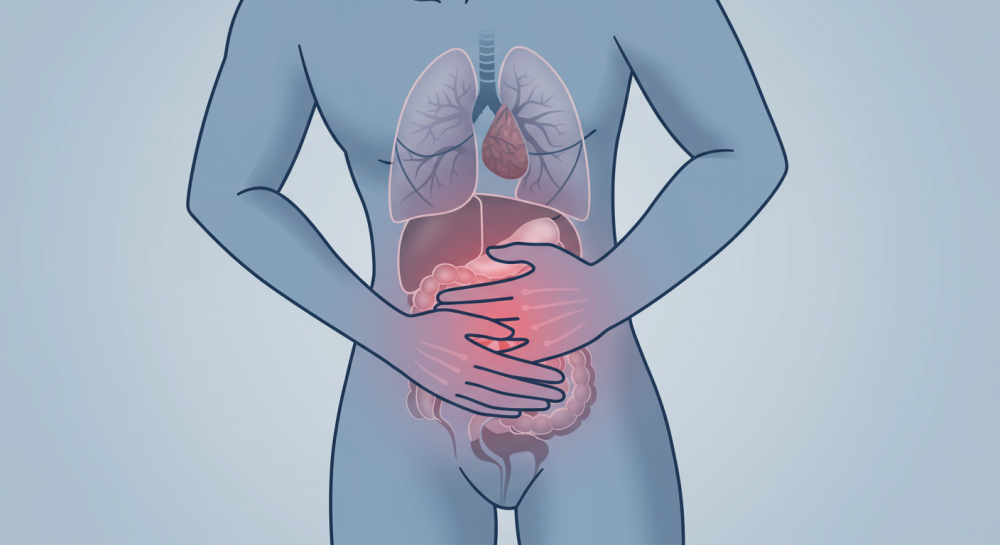
食後の吐き気はなぜ起こる?主な原因と症状
食後に吐き気を感じることは、誰にでも経験があるかもしれません。ときには食べ過ぎや飲み過ぎが原因となることもありますが、継続的に症状が現れる場合は、何らかの疾患が隠れている可能性があります。
食後の吐き気は、消化管におけるなんらかの異常を原因として起こるケースが多くなります。胃や腸の炎症や運動機能低下などが代表的です。
私が日々の診療で多く見かける食後の吐き気の主な原因には、次のようなものがあります。
逆流性食道炎による食後の吐き気
胃酸が食道へと逆流し、食道粘膜に炎症をきたすのが逆流性食道炎です。加齢、飲酒・喫煙、食生活の欧米化などが原因とされ、慢性的な吐き気、胸のむかつき、喉の痛みなどの症状を伴います。
以前はあまり見られなかった、若年層での症例数も増えています。特に不規則な食生活や過度なストレスを抱える現代人に多く見られる傾向があります。
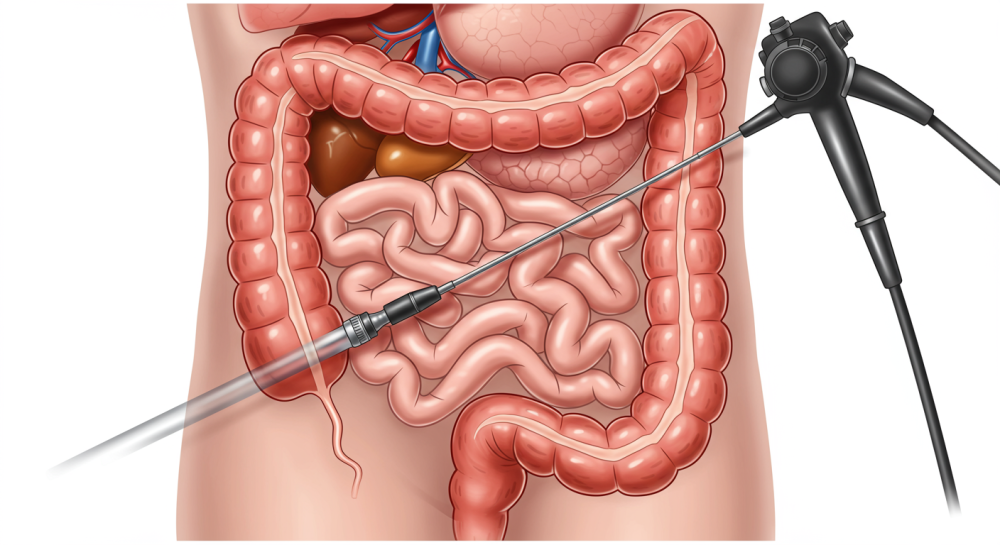
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
胃の粘膜が深く傷つき、粘膜が一部窪んでいる状態を胃潰瘍といいます。よく「胃に穴が開く」と表現されるのがこの胃潰瘍です。特に胃が活発に動いたとき(食事中、食後)に、吐き気・嘔吐の他、腹痛、胸やけなどの症状を伴います。
ヘリコバクター・ピロリ菌の感染、食べ過ぎ、飲み過ぎ、ストレス、痛み止めなどの薬剤などが主な原因だと言われています。
十二指腸潰瘍も同様に、粘膜が傷ついた状態で、吐き気・嘔吐、腹痛などの症状を伴います。これらの症状が、空腹時や夜間に現れやすいのも特徴です。
機能性ディスペプシア
慢性的な吐き気や胃もたれ、早期満腹感、みぞおちの痛みなどの症状があるにもかかわらず、内視鏡検査で粘膜に異常が見つからない場合には、機能性ディスペプシアと診断されます。
生活習慣や食習慣の乱れ、ストレス、胃・十二指腸の知覚過敏や運動機能の阻害など、さまざまな原因が複雑に絡み合って発症すると言われています。
投薬や生活習慣・食習慣の改善による治療が可能です。
感染性胃腸炎
ウイルスや細菌による感染が原因で起こる胃腸炎も、吐き気の大きな原因です。
代表的なものとしては、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルス性胃腸炎、サルモネラ属やカンピロバクターなどの細菌性胃腸炎があります。
感染性胃腸炎の場合は、吐き気だけでなく、発熱、下痢、腹痛なども伴うことが多いです。ウイルス性胃腸炎の場合は37度台の発熱が多いですが、カンピロバクター性腸炎などの細菌性腸炎、ノロウイルスなどは38度にまで達することもあります。

食後の吐き気を放置するリスク
「食後の吐き気くらいで病院に行くのは大げさではないか」と思われる方もいるかもしれません。しかし、継続的な吐き気を放置することには、いくつかの重大なリスクが伴います。
私の臨床経験から、食後の吐き気を放置することで生じる主なリスクをご説明します。
早期発見の遅れによる重篤化
食後の吐き気は、胃がんなどの重大な疾患の初期症状である可能性があります。胃がんは早期に発見できれば高い治療効果が期待できる病気です。しかし、初期症状がほとんどないため、見逃されやすいことが課題となっています。
吐き気や胸やけは、胃がんを含む胃の異常で現れる可能性のある症状の一つです。特に、胃がんによる胃壁の変形や胃酸の逆流が影響して、胸やけを感じることがあります。吐き気は食後に起こる場合が多く、食事をすること自体が億劫になることもでてきます。
これらの症状は日常的に起こりうるため、胃がんと断定するのは難しいです。しかし、症状が長く続く場合は医師に相談することが重要です。
栄養不足と体力低下
食後の吐き気が続くと、十分な食事を摂ることができなくなります。その結果、栄養不足に陥り、体力が低下してしまうことがあります。
特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、短期間の栄養不足でも体調を崩しやすくなります。
また、「身体が弱っているから、栄養を摂らなくては」という想いから、自己判断で無理に食べてしまうケースが見受けられますが、症状を悪化させることになりますのでお控えください。
脱水症状のリスク
吐き気が強く、嘔吐を繰り返すようになると、体内の水分が失われ、脱水症状を引き起こす可能性があります。
特に、水分摂取ができない(すぐに吐いてしまうなど)場合には、脱水症状のリスクが高まります。早急に医療機関を受診しましょう。点滴などの処置によって脱水症状を防ぐことができます。

食後の吐き気が続く場合に受けるべき検査
食後の吐き気が2週間以上続く場合や、症状が徐々に悪化している場合は、専門医による適切な検査を受けることをお勧めします。
消化器内科では、吐き気の原因を特定するために、いくつかの検査を行います。
内視鏡検査(胃カメラ)
食後の吐き気の原因を特定する上で、最も重要な検査の一つが胃カメラ検査です。食道・胃・十二指腸の粘膜をカメラで直接観察することで、炎症・潰瘍・ポリープ・がんなどの病変を早期に発見することができます。
「胃カメラは辛い・苦しい」というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、現在では鎮静剤(麻酔)を使用することで、半分眠ったような状態で検査を受けることができます。
当院では、患者様の苦痛や恐怖感を最小限に抑えた胃カメラ検査を実施しています。経口・経鼻の胃カメラを選択可能で、ご希望や症状に合わせて最適な方法をご提案します。
血液検査
血液検査では、炎症の有無や貧血の状態、肝機能や腎機能など、全身の状態を評価することができます。
特に、胃がんなどの消化器系のがんがある場合には、腫瘍マーカーと呼ばれる特定の物質が血液中に増加することがあります。
また、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染の有無を調べる検査も、血液検査で行うことができます。
超音波検査(エコー)
超音波検査は、お腹の臓器(肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓など)の状態を確認するための検査です。
食後の吐き気の原因が、胃以外の臓器にある可能性もあるため、総合的な診断のために行われることがあります。
当院では、院内に超音波エコーを完備しており、肝臓、胆嚢、膵臓の精査も実施できます。

食後の吐き気を改善するための生活習慣
食後の吐き気の原因が特定され、適切な治療が始まったとしても、日常生活での工夫も重要です。以下に、食後の吐き気を改善するための生活習慣をご紹介します。
食事の取り方を見直す
食後の吐き気を改善するためには、食事の取り方を見直すことが大切です。一度にたくさん食べず、少しずつ回数を多くすることで、胃への負担を減らすことができます。
また、食べ物はよくかみ、唾液と混ぜ合わせて口の中で粥状にしてから飲み込むようにしましょう。早食いは胃に負担をかけるだけでなく、空気も一緒に飲み込んでしまうため、胃の膨満感や不快感を増強させることがあります。
特に、ダンピング症候群(胃切除後に食べ物が一度に小腸に流れ込むことで起こる症状)がある方は、高たんぱく、低脂肪、低炭水化物の食事を心がけましょう。
食事内容の工夫
食後の吐き気を感じる方は、刺激物や脂っこい食事を避け、消化の良い食事を心がけることが大切です。
特に、脂っこいもの、糖質の多い物、キノコ類、こんにゃく、海藻などは控えめにしましょう。また、アルコールや刺激物(唐辛子など)も吐き気を誘発することがあります。
食事の時間も重要です。就寝直前の食事は避け、寝る前には少なくとも2〜3時間の間隔を空けるようにしましょう。
ストレス管理と規則正しい生活
ストレスは胃腸の動きに大きな影響を与えます。特に、機能性ディスペプシアの方は、ストレスによって症状が悪化することがあります。
日頃からストレスを溜めないよう、適度な運動や趣味の時間を持つなど、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。
また、規則正しい生活リズムを保つことも重要です。不規則な食事時間や睡眠不足は、胃腸の働きを乱す原因となります。
専門医が勧める定期検査の重要性
食後の吐き気などの症状が改善した後も、定期的な検査を受けることをお勧めします。特に、以下のような方は、定期的な検査が重要です。
定期検査が特に重要な方
50歳以上の方、ヘリコバクター・ピロリ菌感染の既往がある方、胃がんの家族歴がある方、喫煙習慣がある方、塩分の多い食事を好む方などは、胃がんのリスクが高いとされています。
これらに当てはまる方は、症状がなくても定期的に胃カメラ検査を受けることをお勧めします。
胃がんは早期に発見できれば、内視鏡治療で根治が目指せます。男性の3人に2人、女性の2人に1人ががんになる時代で、胃がん・大腸がんはがん死亡数の上位を占めています。
「まさか自分ががんになるなんて」、検診で要精密検査となっても「症状がなく、忙しいから受診しなかった」といった理由で、検査が遅れ、進行がんで見つかる患者さんも少なくありません。
当院での検査の特徴
当院では、患者様の負担を最小限に抑えた内視鏡検査を提供しています。半分眠ったような状態となる鎮静剤(麻酔)を使用することで、痛みや恐怖をほとんど感じなくなります。体感としても「あっという間」に検査が終えられますので、以前の検査が苦痛だった、初めてなので不安という方も、安心してご相談ください。
また、高性能な拡大内視鏡を導入し、大学病院に劣らない内視鏡検査が可能です。院内にCTと超音波エコーを完備しており、肺がん検診や肝臓、胆嚢、膵臓の精査も実施できます。
平日がお忙しい方のために、土曜日にも内視鏡検査を行っています。また、初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しており、平日忙しい方でも受診しやすい環境を整えています。
まとめ:食後の吐き気は早めの受診を
食後の吐き気は、一時的なものであれば心配ありませんが、継続的に症状がある場合は、何らかの疾患が隠れている可能性があります。
特に、2週間以上症状が続く場合や、症状が徐々に悪化している場合は、早めに消化器内科を受診しましょう。
胃カメラ検査は、食道・胃・十二指腸の状態を直接確認できる重要な検査です。現在では鎮静剤を使用することで、苦痛を最小限に抑えた検査が可能になっています。
当院では、患者様の不安や苦痛を軽減するための様々な工夫を行っています。食後の吐き気でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
食後の吐き気を放置せず、適切な検査と治療を受けることで、より健康で快適な生活を送ることができます。あなたの健康を守るために、専門医による適切な診断と治療を受けましょう。
詳しい情報や予約については、石川消化器内科内視鏡クリニックのウェブサイトをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
食後の吐き気は病気のサイン?7つの原因と治療法
食後の吐き気は病気のサイン?7つの原因と治療法
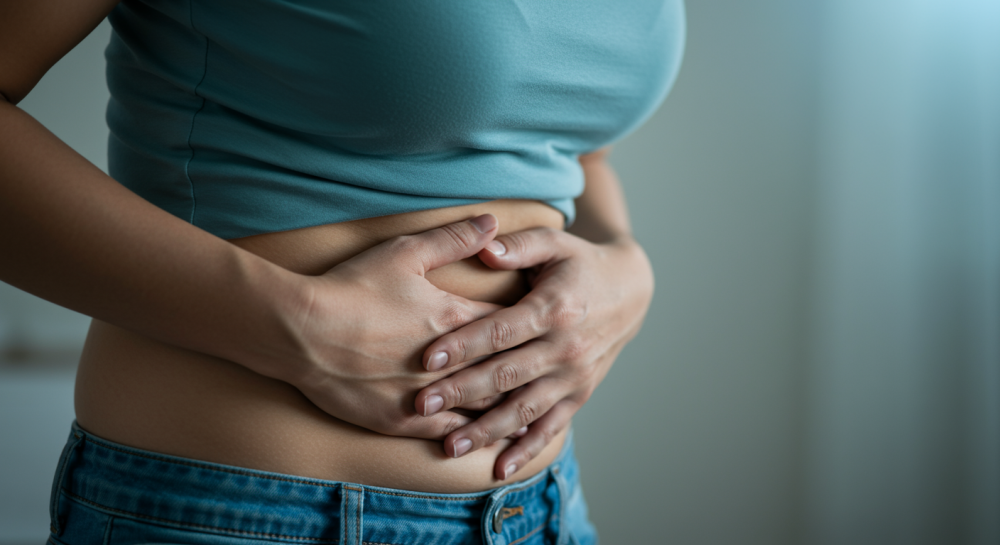
食後の吐き気が起こる主な原因とは?
食後に吐き気を感じることは、誰にでも経験があるかもしれません。「せっかく美味しい食事をしたのに、なぜか気持ち悪くなってしまう」という経験はとても辛いものです。
食後の吐き気は、単なる食べ過ぎだけでなく、様々な原因が考えられます。胃腸の機能低下から始まり、ストレスや自律神経の乱れ、さらには消化器系の病気のサインである可能性もあります。

私が日々の診療で多く見るケースでは、食後の吐き気の原因は大きく7つに分類できます。これらの原因を理解することで、適切な対処法や治療法を見つけることができるでしょう。
1. 消化不良による食後の吐き気
消化不良は食後の吐き気の最も一般的な原因の一つです。消化不良とは、胃腸の働きが低下することで、食べ物がうまく消化されない状態を指します。
特に食べ過ぎや早食い、脂っこい食事、アルコールの過剰摂取などが主な原因となります。消化不良になると、胃もたれや胸やけといった症状と共に吐き気を感じることがあります。
消化不良による吐き気は、食後30分から2時間程度で現れることが多いです。胃の中で食べ物が長時間とどまっているような不快感も特徴的です。
消化不良を改善するポイント
- よく噛んでゆっくり食べる習慣をつける
- 食事の量を適切に調整し、腹八分目を心がける
- 脂っこい食事やアルコールを控える
- 食後すぐに横にならない
- 規則正しい食事時間を守る
これらの対策を実践することで、消化不良による吐き気は改善されることが多いです。しかし、症状が長引く場合は、胃炎や胃潰瘍などの可能性も考えられますので、医療機関での検査をお勧めします。
2. 逆流性食道炎と食後の不快感
逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流することで起こる炎症性疾患です。本来、食道と胃の間には括約筋があり、胃酸が食道に逆流するのを防いでいます。しかし、この括約筋の機能が低下すると、胃酸が食道に逆流し、炎症を引き起こします。
食後に横になったり、前かがみになったりすると症状が悪化することが特徴です。主な症状としては、胸やけ、みぞおちや上胸部の痛み、喉の違和感や痛み、そして吐き気が挙げられます。
逆流性食道炎は、肥満の方や腰が曲がった方、油っぽいものをよく食べる方、ストレスの多い方に多い傾向があります。
逆流性食道炎の改善策
逆流性食道炎による吐き気を改善するためには、生活習慣の見直しが重要です。具体的には以下の対策が効果的です:
- 食後すぐに横にならない
- 就寝前3時間は食事を控える
- 食事は腹八分目にとどめる
- 脂っこい食事や刺激物を控える
- アルコールやカフェインの摂取を減らす
- タバコを控える
- 肥満の方は体重管理を心がける
これらの対策で症状が改善しない場合は、胃酸の分泌を抑える薬や胃の運動を改善する薬などの薬物療法が有効です。症状が続く場合は、内視鏡検査を含めた精密検査をお勧めします。
3. 機能性ディスペプシアと食後の吐き気
機能性ディスペプシアは、明らかな器質的疾患がないにもかかわらず、慢性的に胃もたれや吐き気などの不快な症状が続く状態です。
食後に胃部不快感や膨満感、早期満腹感、吐き気などの症状が現れますが、内視鏡検査などで異常が見つからないことが特徴です。ストレス、睡眠不足、飲酒や喫煙の習慣、消化器官の機能低下、遺伝など様々な要因が関与していると考えられています。
機能性ディスペプシアの対処法
機能性ディスペプシアによる食後の吐き気に対しては、以下のような対策が効果的です:
- 少量ずつ、回数を分けて食事をする
- ゆっくりよく噛んで食べる
- 刺激物や脂っこい食事を控える
- アルコールやカフェインの摂取を減らす
- ストレス管理と十分な睡眠を心がける
これらの生活習慣の改善で症状が軽減しない場合は、胃の運動を改善する薬や胃酸の分泌を抑える薬、抗不安薬などの薬物療法が検討されます。
機能性ディスペプシアは命に関わる病気ではありませんが、生活の質を大きく低下させる可能性があります。症状が続く場合は、専門医への相談をお勧めします。
4. 食物不耐症と食後の症状
食物不耐症は、特定の食品を消化する能力が低下している状態です。食物アレルギーとは異なり、免疫系の反応ではなく、消化酵素の不足や腸の機能異常が原因で起こります。

代表的な食物不耐症には、乳糖不耐症(牛乳に含まれる乳糖を消化できない)や小麦グルテン不耐症などがあります。これらの食品を摂取すると、腹痛、膨満感、下痢、そして吐き気などの症状が現れることがあります。
食物不耐症による吐き気は、原因となる食品を摂取してから30分〜2時間程度で現れることが多いです。
食物不耐症への対応
食物不耐症による吐き気に対しては、原因となる食品を特定し、摂取を控えることが最も効果的な対策です。
- 症状が出る食品を記録する食事日記をつける
- 疑わしい食品を一時的に除去し、症状の変化を観察する
- 乳糖不耐症の場合は、乳糖分解酵素のサプリメントを利用する
- 代替食品を探す(例:乳製品の代わりに豆乳など)
食物不耐症の診断は難しいことがあります。症状が続く場合は、消化器内科や アレルギー専門医に相談し、適切な検査を受けることをお勧めします。
5. ストレスと自律神経の乱れによる吐き気
ストレスや自律神経の乱れも、食後の吐き気の重要な原因の一つです。自律神経は消化管の働きを調節しており、ストレスによって乱れると、胃腸の動きが低下したり、胃酸の分泌が増加したりして、吐き気を引き起こすことがあります。
特に緊張状態が続いたり、強いストレスを感じたりした後の食事で吐き気を感じることが多いです。また、不規則な生活習慣や睡眠不足も自律神経の乱れを引き起こし、食後の吐き気につながることがあります。
ストレスと自律神経の乱れへの対策
ストレスや自律神経の乱れによる食後の吐き気に対しては、以下のような対策が効果的です:
- ストレス管理技術(深呼吸、瞑想、ヨガなど)を取り入れる
- 十分な睡眠と規則正しい生活リズムを心がける
- 適度な運動を定期的に行う
- リラックスできる時間を意識的に作る
- 食事はリラックスした環境でゆっくりと取る
長期間にわたるストレスは、胃腸だけでなく全身の健康に影響を及ぼします。ストレスが原因と思われる症状が続く場合は、心療内科や精神科への相談も検討してみてください。
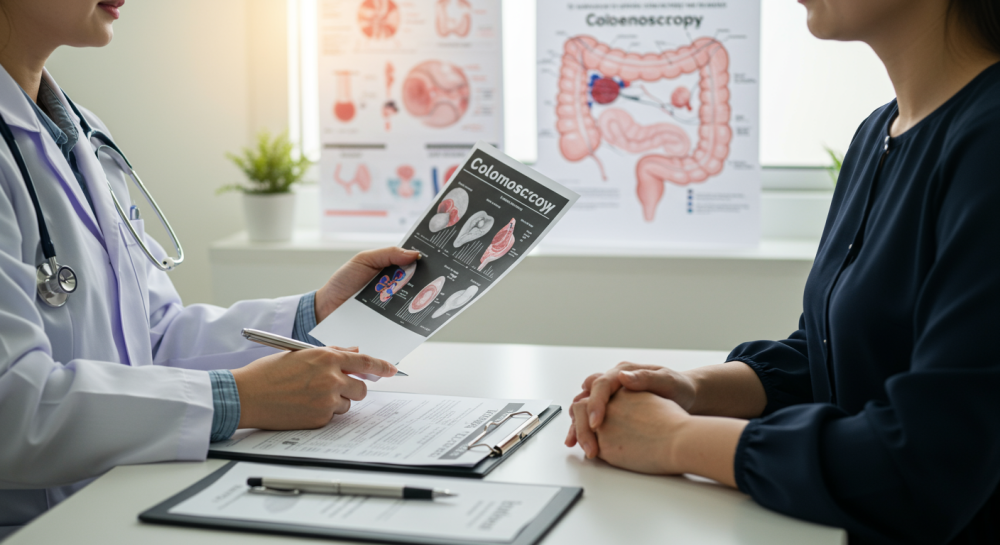
自分でできるストレス対策を行っても症状が改善しない場合は、専門家のサポートを受けることをためらわないでください。
6. 薬剤性の吐き気
様々な薬剤が副作用として吐き気を引き起こすことがあります。特に食後に服用する薬の場合、食事と薬の相互作用によって吐き気が強くなることがあります。
吐き気を引き起こしやすい薬剤としては、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、抗生物質、鉄剤、一部の高血圧薬や糖尿病薬などが挙げられます。また、複数の薬を併用している場合、薬の相互作用によって吐き気が生じることもあります。
薬剤性吐き気への対応
薬剤による食後の吐き気に対しては、以下のような対応が考えられます:
- 医師や薬剤師に相談し、服用方法の見直しを行う
- 食事と一緒に服用するか、食後に服用するかなど、タイミングを調整する
- 代替薬への変更を医師に相談する
- 吐き気止めの併用を検討する
薬の服用を自己判断で中止することは危険です。吐き気などの副作用が気になる場合は、必ず処方した医師や薬剤師に相談してください。
7. 消化器系の疾患による吐き気
食後の吐き気が続く場合、消化器系の疾患が隠れている可能性があります。特に注意が必要な疾患としては、胃炎、胃潰瘍、胆石症、膵炎、胆嚢炎、腸閉塞などが挙げられます。
これらの疾患による吐き気は、単なる食べ過ぎや消化不良とは異なり、持続的であったり、徐々に悪化したりする傾向があります。また、腹痛、発熱、体重減少などの他の症状を伴うことも特徴です。
消化器疾患が疑われる場合の対応
以下のような症状がある場合は、消化器系の疾患を疑い、早めに医療機関を受診することをお勧めします:
- 吐き気や嘔吐が2日以上続く
- 激しい腹痛を伴う
- 血液や胆汁(黄緑色の液体)を吐く
- 発熱や黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)がある
- 原因不明の体重減少がある
- 便に血が混じる
これらの症状がある場合は、内視鏡検査やCT検査、超音波検査などの精密検査が必要になることがあります。
食後の吐き気を改善するための生活習慣
食後の吐き気の原因が何であれ、以下のような生活習慣の改善が症状の軽減に役立ちます:
- 少量ずつ、回数を分けて食事をする
- よく噛んでゆっくり食べる
- 脂っこい食事や刺激物を控える
- 食後すぐに横にならない
- 規則正しい食事時間を守る
- 十分な水分を摂取する
- 適度な運動を定期的に行う
- ストレス管理と十分な睡眠を心がける
これらの生活習慣の改善で症状が軽減しない場合や、症状が長期間続く場合は、専門医への相談をお勧めします。
当院での検査・治療について
石川消化器内科内視鏡クリニックでは、食後の吐き気などの消化器症状でお悩みの患者様に対して、丁寧な問診と適切な検査・治療を提供しています。
特に、内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)は、消化器疾患の早期発見・早期治療に非常に有効です。当院では、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の内視鏡検査を実施しており、「辛い・苦しい」というイメージのある検査を「より気軽に」「よりスピーディーに」受けていただける体制を整えています。
食後の吐き気でお悩みの方は、お気軽に当院までご相談ください。
食後の吐き気は様々な原因で起こりますが、適切な対処と治療によって改善することが可能です。症状が続く場合は、自己判断せず、専門医に相談することをお勧めします。
詳しい情報や予約については、石川消化器内科内視鏡クリニックのウェブサイトをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
食後の吐き気が続く原因と対処法|消化器内科医が解説
食後の吐き気が続く原因と対処法|消化器内科医が解説

食後の吐き気が続く原因とは?消化器内科医の見解
食後に「気持ち悪くなる」「吐き気がする」という症状で悩まれている方は少なくありません。空腹時は大丈夫なのに、食事をすると胃がむかむかして気分が悪くなる。
このような症状が一度きりであれば心配ないかもしれませんが、繰り返し起こる場合は何らかの病気が隠れている可能性があります。消化器内科医として日々多くの患者さんを診察していると、食後の吐き気を訴える方の背景にはさまざまな原因が潜んでいることがわかります。

私が院長を務める石川消化器内科内視鏡クリニックでも、「食後に気持ち悪くなる」という訴えで来院される患者さんは多いです。症状の背景には単なる食あたりから、胃食道逆流症、機能性ディスペプシアといった慢性的な疾患まで、実にさまざまな原因が考えられます。
今回は消化器内科専門医の立場から、食後の吐き気が続く原因と効果的な対処法について詳しく解説していきます。この記事を読むことで、あなたの症状の原因が少し見えてくるかもしれません。
食後の吐き気が現れるメカニズムと主な原因疾患
食後に吐き気が起こるメカニズムを理解するには、まず消化器系の仕組みを知ることが大切です。食べ物は食道を通って胃に入り、そこで胃酸によって分解されます。
胃の中で食べ物と胃液がしっかり混ざり合い、少しずつ十二指腸へと送られていきます。この過程のどこかに問題が生じると、吐き気という形で症状が現れるのです。
胃食道逆流症(GERD)
食後の吐き気でまず疑われるのが「胃食道逆流症(GERD)」です。これは胃の内容物や胃酸が食道に逆流することで起こる疾患です。
本来、食道と胃の境目には「下部食道括約筋」という筋肉があり、胃の内容物が逆流するのを防いでいます。しかし、この機能が低下すると胃酸が食道に逆流し、胸やけや吐き気などの不快な症状を引き起こします。
特に食後に横になったり、前かがみの姿勢をとったりすると症状が悪化することが特徴です。また、脂っこい食事や甘いもの、香辛料の強い食品、アルコールなどを摂取すると胃酸の分泌が促進され、症状が出やすくなります。
どうですか?あなたも食後に胸やけや吐き気を感じることはありませんか?
機能性ディスペプシア
次に考えられるのが「機能性ディスペプシア」です。これは胃カメラなどの検査を行っても器質的な異常が見つからないにもかかわらず、胃もたれや吐き気などの不快な症状が続く状態を指します。
機能性ディスペプシアの方は、少量の食事でもすぐに満腹感を感じたり、食後に胃の不快感や吐き気を覚えたりします。ストレスや睡眠不足、不規則な食生活が原因となることが多いです。
現代社会ではストレスを抱えている方が非常に多く、それが自律神経の乱れを引き起こし、胃腸の動きに影響を与えていることがあります。自律神経のバランスが崩れると、胃の動きが悪くなり、食べ物が胃に長く留まることで不快感や吐き気を感じるのです。
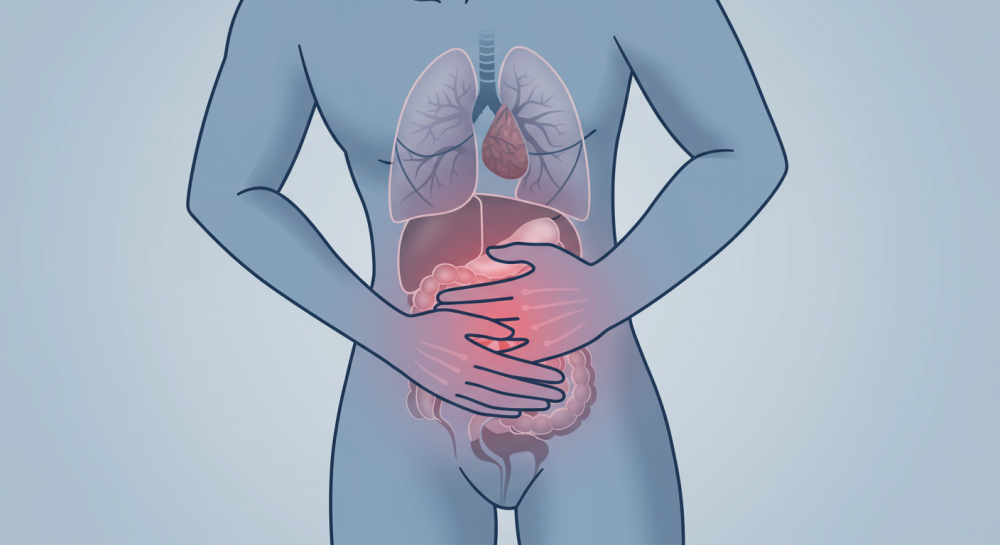
食後の吐き気が続く場合に考えられるその他の疾患
食後の吐き気が続く場合、上記の疾患以外にもいくつかの病気が考えられます。それぞれの特徴を見ていきましょう。
胃・十二指腸潰瘍
胃や十二指腸に潰瘍ができると、食事の刺激で痛みや吐き気を感じることがあります。胃潰瘍の場合は食後すぐに、十二指腸潰瘍の場合は空腹時に痛みが強くなる傾向がありますが、どちらも食後の吐き気を引き起こす可能性があります。
ピロリ菌感染や非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の長期服用が主な原因です。ピロリ菌は胃の粘膜を傷つけ、胃酸から胃を守る粘液の分泌を減少させます。その結果、胃酸が胃の壁を直接刺激し、潰瘍を形成するのです。
胃・十二指腸潰瘍の場合、適切な治療を行わないと症状が長引くだけでなく、出血や穿孔といった重篤な合併症を引き起こすこともあります。早期の診断と治療が非常に重要です。
急性胃腸炎
食後の吐き気が突然始まり、下痢や腹痛、発熱などを伴う場合は、急性胃腸炎の可能性があります。ウイルスや細菌による感染が主な原因で、食中毒もこれに含まれます。
ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルス性胃腸炎は、冬場に流行することが多く、感染力が非常に強いのが特徴です。一方、細菌性胃腸炎は、サルモネラ菌やカンピロバクターなどの細菌に汚染された食品を摂取することで発症します。
急性胃腸炎の場合、通常は数日から1週間程度で自然に回復しますが、脱水症状には注意が必要です。特に高齢者や小さなお子さんは、脱水症状が重症化しやすいので、水分補給を十分に行うことが大切です。
食後の吐き気が続く場合の対処法と治療
食後の吐き気が続く場合、原因となる疾患に応じた対処法や治療が必要です。ここでは、一般的な対処法と各疾患に対する治療法について説明します。
生活習慣の改善
食後の吐き気を軽減するためには、まず生活習慣の改善が重要です。具体的には以下のようなポイントに注意しましょう。
- 食事は腹八分目を心がけ、ゆっくりよく噛んで食べる
- 脂っこい食事や刺激物(香辛料、アルコール、カフェインなど)を控える
- 就寝前3時間は食事を避ける
- 食後すぐに横にならない
- ストレスを溜めないよう、適度な運動や趣味の時間を持つ
- 規則正しい生活リズムを保ち、十分な睡眠をとる
特に胃食道逆流症や機能性ディスペプシアの方は、これらの生活習慣の改善だけでも症状が軽減することがあります。
あなたは食事の後、どのような習慣がありますか?食後すぐに横になっていませんか?

薬物療法
生活習慣の改善だけでは症状が改善しない場合は、薬物療法が必要になることがあります。疾患ごとの主な治療薬は以下の通りです。
胃食道逆流症(GERD)の治療
胃食道逆流症の治療では、主に胃酸の分泌を抑える薬が使用されます。プロトンポンプ阻害薬(PPI)やH2受容体拮抗薬などがこれにあたります。
これらの薬は胃酸の分泌を抑えることで、食道への刺激を減らし、症状を緩和します。また、制酸薬や消化管運動改善薬が補助的に使用されることもあります。
薬物療法と並行して、前述した生活習慣の改善も重要です。特に肥満の方は、体重減少によって症状が改善することが多いので、適度な運動と食事制限を組み合わせた減量も効果的です。
機能性ディスペプシアの治療
機能性ディスペプシアの治療では、消化管運動改善薬や酸分泌抑制薬、漢方薬などが使用されます。症状のパターンに応じて、適切な薬剤を選択することが重要です。
また、ストレスが大きな要因となっている場合は、抗不安薬や抗うつ薬が処方されることもあります。ただし、これらの薬は医師の指示に従って正しく服用することが大切です。
機能性ディスペプシアの場合、薬物療法だけでなく、ストレス管理や食生活の改善、適度な運動なども含めた総合的なアプローチが効果的です。
食後の吐き気が続く場合、いつ病院を受診すべきか
食後の吐き気が続く場合、どのような状況で病院を受診すべきでしょうか。以下のような症状がある場合は、早めに消化器内科を受診することをお勧めします。
- 吐き気や嘔吐が2週間以上続く
- 食事量が減少し、体重が減少している
- 嘔吐物に血液や「コーヒー豆のかす」のような黒い物質が混じる
- 激しい腹痛を伴う
- 38度以上の発熱がある
- めまいや脱水症状(口の渇き、尿量減少など)がある
- 黒い便や血便が出る
特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、症状が重症化しやすいので、早めの受診が重要です。
また、一度症状が改善しても繰り返し起こる場合や、徐々に症状が悪化している場合も、何らかの慢性疾患が隠れている可能性があるので、専門医による精密検査を受けることをお勧めします。
あなたの症状は日常生活に支障をきたすほど辛いものですか?もしそうなら、早めに専門医に相談することを検討してみてください。
当院での検査と治療
当院では、食後の吐き気が続く患者さんに対して、まず詳細な問診と診察を行い、症状の原因を探ります。必要に応じて、胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)や血液検査、超音波検査などを実施します。
特に胃カメラ検査は、食道、胃、十二指腸の状態を直接観察できる重要な検査です。当院では鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の胃カメラ検査を提供しており、検査中の苦痛を最小限に抑えています。
検査結果に基づいて、適切な治療計画を立て、薬物療法や生活指導を行います。また、定期的な経過観察も重要ですので、症状の変化があればいつでもご相談ください。
食後の吐き気を予防するための日常生活のポイント
食後の吐き気を予防するためには、日常生活での心がけが重要です。ここでは、予防のためのポイントをいくつか紹介します。
食事のとり方
食事のとり方を工夫することで、食後の吐き気を予防できることがあります。
- 一度にたくさん食べるのではなく、少量ずつ回数を分けて食べる
- ゆっくりよく噛んで食べる(一口30回程度)
- 食事中の水分摂取は控えめにし、食間に水分をとる
- 温かいものは冷ましてから食べる
- 就寝前3時間は食事を避ける
特に夜遅い時間の食事は、胃に負担をかけやすいので注意が必要です。どうしても遅くなる場合は、消化のよいものを少量摂るようにしましょう。
食生活の見直し
食後の吐き気を予防するためには、食生活全体の見直しも大切です。
- 脂っこい食事や揚げ物を控える
- 刺激物(香辛料、アルコール、カフェインなど)の摂取を減らす
- 甘いものや炭酸飲料を控える
- 食物繊維を多く含む野菜や果物を積極的に摂る
- 規則正しい時間に食事をとる
バランスの良い食事を心がけ、胃に優しいメニューを選ぶことが大切です。また、食事の記録をつけることで、どのような食べ物が症状を悪化させるのかを把握することができます。
ストレス管理と生活リズム
ストレスは胃腸の動きに大きな影響を与えます。ストレスを適切に管理し、規則正しい生活リズムを保つことが重要です。
- 適度な運動を取り入れる(ウォーキングやヨガなど)
- 十分な睡眠をとる
- リラックスする時間を持つ(入浴、読書、音楽鑑賞など)
- 深呼吸や瞑想などのリラクゼーション法を実践する
特に自律神経のバランスを整えることは、胃腸の機能を正常に保つために非常に重要です。日々の生活の中で、ストレスを溜めないよう意識的に取り組むことをお勧めします。
まとめ:食後の吐き気が続く場合は専門医に相談を
食後の吐き気が続く場合、その背景にはさまざまな原因が考えられます。胃食道逆流症や機能性ディスペプシア、胃・十二指腸潰瘍、急性胃腸炎など、疾患によって適切な対処法や治療法が異なります。
症状が軽度であれば、生活習慣の改善や食事の工夫で改善することもありますが、症状が長引く場合や、体重減少、血便、激しい腹痛などの警告サインがある場合は、早めに消化器内科を受診することが重要です。
当院では、鎮静剤を使用した無痛の胃カメラ検査を提供しており、患者さんの負担を最小限に抑えながら、正確な診断と適切な治療を行っています。また、土曜日の検査にも対応しておりますので、平日お忙しい方でも安心して受診いただけます。
食後の吐き気でお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ一度専門医にご相談ください。適切な診断と治療により、症状の改善が期待できます。
詳しい情報や予約については、石川消化器内科内視鏡クリニックのウェブサイトをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。皆様の健康を誠心誠意サポートいたします。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
内視鏡専門医を選ぶ重要性〜精度の高い検査で早期発見を
内視鏡専門医を選ぶ重要性〜精度の高い検査で早期発見を
内視鏡検査の重要性と専門医を選ぶ理由
胃がんや大腸がんは早期発見できれば、9割以上が治癒可能な病気です。しかし、進行してしまうと生存率は大きく下がってしまいます。私が消化器内科医として長年診療してきた経験から言えることは、内視鏡検査の質が早期発見の鍵を握っているということです。
内視鏡検査は「辛い・苦しい」というイメージがあるかもしれません。実際、20年ほど前はそのような検査が一般的でした。しかし現在は、機器の進化や検査技術の向上により、苦痛を最小限に抑えた検査が可能になっています。
それでも多くの方が検査に不安を感じ、症状があっても検査を先延ばしにしてしまうことがあります。これが早期発見・早期治療の大きな障壁になっているのです。

では、なぜ内視鏡専門医による検査が重要なのでしょうか?
それは単に「内視鏡検査ができる」医師と「内視鏡専門医」の間には、検査の精度に大きな差があるからです。早期の胃がんや大腸がんは非常に発見しづらく、専門的な知識と経験がなければ見逃してしまう可能性があります。研究によると、早期胃がんの見落としは5〜26%程度あるとの報告もあります。
内視鏡検査の質を左右する要素とは
内視鏡検査の質を左右する要素はいくつかあります。まず第一に挙げられるのが「医師の専門性」です。日本消化器内視鏡学会の専門医資格を持つ医師は、豊富な症例経験と高度な技術を持っています。
次に重要なのが「使用する機器の性能」です。最新の内視鏡機器は、従来のものと比べて格段に画質が向上しています。特に拡大内視鏡や特殊光観察(NBI)などの技術は、微細な病変の発見に大きく貢献しています。
そして見落とされがちなのが「検査時間」です。丁寧に時間をかけて観察することで、見落としのリスクは大幅に減少します。実際、検査精度と観察時間は正の相関を示すことが研究で証明されています。

私が院長を務める石川消化器内科内視鏡クリニックでは、これらすべての要素にこだわり、高精度な内視鏡検査を提供しています。特に、大学病院に劣らない高性能な拡大内視鏡を導入し、微細な病変も見逃さない検査を心がけています。
内視鏡検査の質の違いは、あなたの命を左右する可能性があるのです。
では、具体的にどのような点に注目して内視鏡専門医を選べばよいのでしょうか?
内視鏡専門医を選ぶ際のポイント
専門医資格の有無を確認する
内視鏡検査を受ける際、最も重視すべきポイントは医師の専門性です。日本消化器内視鏡学会の「内視鏡専門医」資格を持つ医師は、厳しい基準をクリアした技術と知識を持っています。
この資格を取得するためには、数多くの症例経験と専門的な知識が求められます。内視鏡検査は「職人芸」的な側面があり、経験豊富な専門医と一般の医師では、病変の発見率に大きな差が生じることが研究でも明らかになっています。
医師の専門性は、ウェブサイトや院内掲示で確認できることが多いですが、直接クリニックに問い合わせるのも良いでしょう。
最新の内視鏡機器を導入しているか
内視鏡機器は急速に進化しています。従来の白色光観察に加え、NBI(狭帯域光観察)や拡大内視鏡などの技術が登場し、早期がんの発見率が向上しています。
特に拡大内視鏡は、通常の内視鏡では見えない微細な変化を観察できるため、早期がんの発見に非常に有効です。2018年には520倍もの倍率を持つ超拡大内視鏡(顕微内視鏡)も登場しました。

最新機器を導入しているクリニックは、それだけ検査の質にこだわっている証拠です。クリニックのウェブサイトや問い合わせで、どのような内視鏡機器を使用しているか確認してみましょう。
苦痛を軽減する取り組みがあるか
内視鏡検査の大きな障壁となるのが「苦痛」です。しかし、現在は様々な工夫により、苦痛を最小限に抑えた検査が可能になっています。
例えば、鎮静剤(麻酔)を使用することで、半分眠ったような状態で検査を受けられます。これにより痛みや恐怖感をほとんど感じることなく検査が可能です。また、胃カメラには経口と経鼻の選択肢があり、それぞれ特性が異なります。
経鼻内視鏡は直径が5-6mmと細く、通常の経口内視鏡(8-9mm)の約半分の太さです。そのため、挿入時の咽頭刺激が少なく、一般的には苦痛が少ないと評価されています。また、検査中も口呼吸ができるため、酸素飽和度の低下も少なく、心拍数や血圧の上昇も抑えられます。
ただし、鼻腔が狭い方は経鼻内視鏡が挿入できないこともあります。また、経鼻内視鏡は拡大機能が装備されていないものもあるため、病変の評価という点では経口内視鏡に劣ることもあります。
どのような苦痛軽減の取り組みがあるか、事前に確認しておくことをおすすめします。
内視鏡検査で見つかる主な疾患と早期発見の重要性
内視鏡検査で発見される代表的な疾患には、胃がん、大腸がん、食道がん、胃炎、逆流性食道炎、大腸ポリープなどがあります。特に注目すべきは「がん」の早期発見です。
胃がんや大腸がんは、早期に発見されれば内視鏡治療で完治できることが多いのです。しかし、進行すると外科手術や抗がん剤治療が必要になり、生存率も大きく下がります。
胃がんの進行度は、胃壁への「深さ」に基づいて判断されます。早期胃がん(I期)の5年生存率は90%以上ですが、進行がん(III期・IV期)になると50%以下に低下します。大腸がんも同様の傾向があります。
特に注目すべきは大腸ポリープです。大腸がんの多くは、大腸ポリープががん化して発生します。すべてのポリープががん化するわけではありませんが、がん化のリスクがあるポリープは内視鏡検査時に切除することで、将来の大腸がんを予防できるのです。
また、一度大腸ポリープを経験した方は、再度ポリープが発生する可能性が高くなります。定期的な内視鏡検査が重要です。
胃がんや大腸がんの早期は、ほとんど症状が現れません。そのため、症状がなくても定期的な検査が推奨されます。特に50歳以上の方、がんの家族歴がある方、過去にポリープが見つかった方は、定期的な内視鏡検査をお勧めします。
当院の内視鏡検査の特徴
石川消化器内科内視鏡クリニックでは、「辛い・苦しい」というイメージがある内視鏡検査を「より気軽に」「よりスピーディーに」そして安心して受けられるよう、様々な工夫を行っています。
まず、すべての診察、検査、検査結果説明を私が担当しています。消化器・内視鏡専門医として、微細な変化も見逃さない精度の高い検査を心がけています。
検査の苦痛を軽減するため、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛内視鏡検査を提供しています。半分眠ったような状態で検査を受けられるため、痛みや恐怖感をほとんど感じることなく、「あっという間」に検査が終わります。
胃カメラは経口・経鼻どちらも選択可能で、患者さんの状態や希望に合わせて最適な方法を提案しています。大腸カメラでは、必要に応じてその場でポリープ切除も行っています。
設備面では、高性能な拡大内視鏡を導入し、大学病院に劣らない内視鏡検査が可能です。また、院内にCTと超音波エコーを完備しており、必要に応じて肺がん検診や肝臓、胆嚢、膵臓の精査も実施できます。
忙しい方のために、初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しています。また、待ち時間と滞在時間の短縮に取り組み、電話予約とWEB予約を導入しています。
あなたはどのような内視鏡検査を受けたいですか?苦痛が少なく、高精度な検査を提供するクリニックを選ぶことで、健康を守る第一歩を踏み出せます。
内視鏡検査を受けるべき方とタイミング
症状がある方
以下のような症状がある方は、内視鏡検査をお勧めします。
- 繰り返す血便
- 便潜血検査で陽性
- 胃痛や腹痛が続く
- 胸やけや胃のむかつきが続く
- 便の状態に変化がある(細くなった、粘液が混じるなど)
- 原因不明の体重減少や食欲不振
- 貧血がある
これらの症状は、消化器の病気のサインかもしれません。早めに専門医に相談することをお勧めします。
症状がなくても検査を検討すべき方
症状がなくても、以下に該当する方は内視鏡検査を検討すべきです。
- 50歳以上の方
- 胃がん・大腸がんの家族歴がある方
- 過去に胃ポリープや大腸ポリープが見つかった方
- ピロリ菌感染がある、または除菌治療を受けた方
- 喫煙や飲酒の習慣がある方
特に大腸がんは、近年急増しています。増加の背景には食生活の欧米化が考えられ、今後も増加すると予測されています。便潜血検査は大腸がんの感度(がんがあるときに発見できる確率)が3割程度と言われており、より確実な検査として大腸内視鏡検査が推奨されています。
胃がんについては、50歳以上の日本人の多くがピロリ菌に感染しており、これが胃がんの最大の危険因子となっています。ピロリ菌の除菌療法の普及により胃がんは減少傾向にありますが、定期的な検査は依然として重要です。
内視鏡検査は、症状が出る前の早期発見が最大のメリットです。定期的な検査で、健康な未来を守りましょう。
まとめ:内視鏡専門医による検査で早期発見・早期治療を
内視鏡検査は、消化器の病気、特にがんの早期発見に非常に有効な検査です。しかし、その効果を最大限に発揮するためには、専門医による高精度な検査が不可欠です。
内視鏡専門医は豊富な経験と高度な技術を持ち、早期の微細な変化も見逃さない目を持っています。また、最新の内視鏡機器と組み合わせることで、その精度はさらに向上します。
かつては「辛い・苦しい」イメージが強かった内視鏡検査も、現在は鎮静剤の使用や細径内視鏡の導入により、苦痛を最小限に抑えた検査が可能になっています。
胃がんや大腸がんは早期に発見すれば90%以上が治癒可能ですが、進行すると生存率は大きく低下します。定期的な内視鏡検査で、早期発見・早期治療を心がけましょう。
石川消化器内科内視鏡クリニックでは、消化器・内視鏡専門医による高精度な検査と、患者さんの負担を最小限に抑える工夫を行っています。健康に不安がある方、定期検査をご希望の方は、ぜひご相談ください。
あなたの健康を守るために、専門医による内視鏡検査を選択することが、最も重要な一歩となるでしょう。
詳しい情報や予約については、石川消化器内科内視鏡クリニック公式サイトをご覧ください。専門医による高精度な内視鏡検査で、あなたの健康を守りましょう。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
大腸カメラの痛みを軽減する7つの対策〜専門医が解説
大腸カメラ検査の痛みはなぜ起こる?その仕組みを理解しよう
大腸カメラ検査(正式には下部消化管内視鏡検査)は、大腸がんやポリープの早期発見に非常に有効な検査です。しかし、「痛い」「苦しい」というイメージから検査を躊躇される方も少なくありません。
実際、大腸カメラ検査では個人差はあるものの、痛みを感じる方が多いのは事実です。この痛みはどのようなメカニズムで生じるのでしょうか?
大腸カメラ検査で生じる痛みには主に2つのタイプがあります。「腸が押されるような痛み」と「お腹が張るような痛み」です。
大腸は曲がりくねった形状をしているため、内視鏡を奥まで挿入する際には、腸を押したり引っ張ったりする必要があります。この物理的な刺激が腸を押されるような痛みを引き起こします。
また、検査中には進行方向を確認したり、腸のひだの裏まで観察したりするために、腸に空気や炭酸ガスを入れて膨らませます。これがお腹が張ったような痛みの原因となるのです。
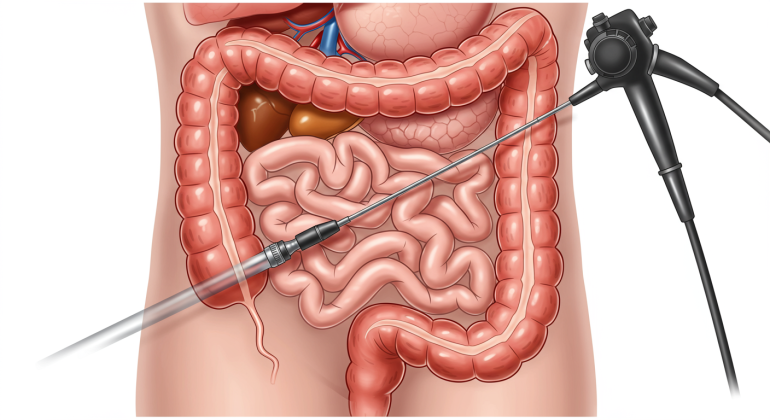
痛みが出やすい人の特徴とは?自分のリスクを知ろう
大腸カメラ検査の痛みの感じ方には個人差があります。中には「思ったより全然痛くなかった」という方もいれば、「冷や汗が出るほど痛かった」という方もいらっしゃいます。
では、どのような方が痛みを感じやすいのでしょうか?
- ・お腹の手術経験がある方:腸の癒着があると、内視鏡の挿入が難しくなります
- ・やせ型・小柄な体型の方:腸管が細く、スコープの通過が困難な場合があります
- ・肥満体型の方:腸管が動きやすく、スコープ操作が難しくなることがあります
- ・腸に炎症がある方:潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患がある場合、痛みを感じやすくなります
- ・便秘や下痢を繰り返している方:腸の状態が不安定で、刺激に敏感になっている可能性があります
一方、痛みを感じにくい傾向がある方もいます。特に中肉中背の男性(青年〜中年層)では、スコープの挿入が比較的スムーズで、痛みを感じにくい傾向があるようです。
ただし、これらはあくまで傾向であり、個人差が大きいことを覚えておきましょう。
また、痛みが発生しやすい部位も決まっています。特にS状結腸や横行結腸は腹膜に固定されておらず自由に動くため、スコープによる押し込みで腸が伸びやすく痛みが出やすい傾向があります。
さらに、脾弯曲(ひわんきょく)や肝弯曲といった腸の曲がりが急な部分では、スコープが引っかかりやすく、腸管が刺激されやすいため痛みを感じやすくなります。
大腸カメラの痛みを軽減する7つの対策
「大腸カメラは痛いから受けたくない」と思われる方も多いかもしれませんが、大腸がんの早期発見・早期治療のためには非常に重要な検査です。痛みを軽減するための対策をご紹介します。
1. 鎮静剤(麻酔)を使用した無痛検査を選ぶ
現在は鎮静剤(麻酔)を使用した「無痛検査」が一般的になってきています。鎮静剤を使うと、ウトウトと眠っているような「うたた寝状態」で検査を受けることができ、痛みや恐怖感をほとんど感じません。
当院では、患者さんの状態に合わせて適切な量の鎮静剤を使用し、安全かつ快適な検査を心がけています。検査後は「あっという間に終わった」という感想をいただくことが多いです。
2. 経験豊富な内視鏡専門医を選ぶ
大腸カメラ検査の痛みの有無は、施術を行う医師の技術に大きく左右されます。熟練の内視鏡医であれば、腸管の動きや形に応じた繊細な操作が可能となり、痛みを最小限に抑えることができます。
内視鏡専門医の資格を持つ医師や、過去に数千例以上の検査経験がある医師を選ぶことで、より快適な検査を受けられる可能性が高まります。
3. 炭酸ガス送気を使用した検査を選ぶ
従来の大腸カメラ検査では、腸を膨らませるために空気を使用していましたが、最近では炭酸ガスを使用する医療機関が増えています。炭酸ガスは空気よりも吸収されやすいため、検査後のお腹の張りや痛みが軽減されます。
当院では、患者さんの負担を減らすために炭酸ガス送気を導入し、検査後の不快感を最小限に抑える工夫をしています。
4. 軸保持短縮法による挿入技術
「軸保持短縮法」とは、大腸の形状に合わせてスコープを操作する技術で、腸を無理に伸ばさずに挿入することができます。この技術を習得した医師による検査では、痛みが大幅に軽減されることが多いです。
当院の医師は軸保持短縮法を含む様々な内視鏡挿入技術を習得しており、患者さん一人ひとりの腸の形状に合わせた最適な方法で検査を行っています。
5. 検査前の腸内環境を整える
検査前の腸内環境を整えることも、痛みの軽減に役立ちます。具体的には以下のような点に注意しましょう。
- ・適切な下剤の服用:医師の指示通りに下剤を服用し、腸内をきれいにしておくことで、検査がスムーズに進みます
- ・検査前日の食事管理:消化の良い食事を心がけ、食物繊維の多い食品は避けましょう
- ・水分摂取:下剤服用時には十分な水分を摂ることで、腸の洗浄効果が高まります
6. リラックスして検査に臨む
緊張や不安は筋肉を硬くし、痛みを増強させることがあります。検査前にリラックスする工夫をしましょう。
深呼吸やリラクゼーション法を試してみたり、検査中は医師の指示に従って呼吸を整えたりすることで、痛みを感じにくくなることがあります。
当院では、患者さんがリラックスして検査を受けられるよう、検査前の丁寧な説明や、検査中の声かけを大切にしています。
7. ウォーターイクスチェンジ法を活用する
「ウォーターイクスチェンジ・コロノスコピー(WEC)」という方法も、痛みを軽減するのに効果的です。これは空気の代わりに水を使って腸を拡張させる方法で、腸への負担が少なく、痛みを軽減できることが報告されています。
この方法を取り入れている医療機関もありますので、検査予約時に確認してみるとよいでしょう。
大腸カメラ検査を受ける際の心構えと準備
大腸カメラ検査をより快適に受けるためには、適切な心構えと準備が大切です。ここでは、検査前の準備から検査当日の流れまでをご説明します。
検査前日からの準備
大腸カメラ検査の成功の鍵は、腸内をきれいに洗浄することです。医師の指示に従って、以下の準備を行いましょう。
- ・食事制限:検査前日は消化の良い食事を心がけ、食物繊維の多い食品や種のある食品は避けましょう
- ・下剤の服用:医師から処方された下剤を指示通りに服用します。通常、検査前日の夕方と検査当日の朝に服用することが多いです
- ・水分摂取:下剤服用時には十分な水分(1.5〜2リットル程度)を摂ることで、腸の洗浄効果が高まります
下剤の効果は個人差がありますが、透明な水様便が出るようになれば腸の洗浄は十分です。下剤の効果が弱い場合は、追加で服用することもあります。
検査当日の流れ
検査当日は、以下のような流れで進みます。
- ・受付・問診:既往歴や服薬中の薬などを確認します
- ・着替え:検査用の着衣に着替えます
- ・鎮静剤の投与:無痛検査を選択した場合、点滴から鎮静剤を投与します
- ・検査開始:左側を下にした横向きの姿勢で、肛門から内視鏡を挿入します
- ・検査終了:通常、検査時間は15〜30分程度です
- ・回復・休憩:鎮静剤を使用した場合は、30分〜1時間程度の休憩が必要です
- ・結果説明:検査結果の説明を受けます
鎮静剤を使用した場合は、当日の車の運転や重要な判断を要する業務は避けるようにしましょう。また、検査後は腸内にガスが残っていることがあるため、ガスを出すことを我慢しないようにしましょう。
大腸カメラ検査を受けるべき理由と重要性
大腸カメラ検査は痛みや不快感を伴うことがありますが、それでも受けるべき重要な理由があります。特に40歳を過ぎたら、一度は大腸カメラ検査を受けることをお勧めします。
大腸がんの早期発見・早期治療のために
日本では、大腸がんは年々増加傾向にあり、女性のがん死亡原因の第1位、男性でも第3位となっています。2023年のデータでは、大腸がんによる死亡者数は約5万3千人にのぼり、肺がん(約7万6千人)に次いで多くなっています。
また、日本の大腸がん死亡率は世界第4位と高く、先進国の中でも深刻な状況です。この背景には、大腸がん検診受診率の低さがあります。日本の大腸がん検診受診率は約45%と、先進国の中でも低い水準にあります。
大腸がんは初期の段階では自覚症状がほとんどなく、症状が出てからでは進行しているケースが多いため、「予防・早期発見・早期治療」が命を守る鍵となります。
大腸ポリープの発見と切除
多くの大腸がんは、良性のポリープが時間をかけて癌化することで発生します。大腸カメラ検査中にポリープが見つかった場合、その場で切除することが可能であり、癌化する前に取り除くことで大腸がんの発生を予防できます。
アメリカからの報告では、大腸内視鏡を行って大腸ポリープ(腺腫)をすべて切除することで、大腸がんによる死亡率が53%低下したという結果が出ています。
早期に発見されれば、より身体への負担の少ない内視鏡手術で根治する可能性が高まります。進行した(他臓器に転移した)大腸がんの治療成績は、最新の医療をもってしても決して良くはありません。
当院の無痛大腸カメラ検査のご案内
石川消化器内科内視鏡クリニックでは、患者さんの負担を最小限に抑えた無痛大腸カメラ検査を提供しています。
当院の無痛内視鏡検査の特徴
- ・鎮静剤(麻酔)を使用:半分眠ったような状態で、ほとんど苦痛・恐怖感なく検査を受けていただけます
- ・消化器・内視鏡専門医による検査:院長の私(石川)が全ての診察、検査、検査結果説明までを担当します
- ・高性能な拡大内視鏡を導入:大学病院に劣らない高精度な検査が可能です
- ・炭酸ガス送気を使用:検査後のお腹の張りや痛みを軽減します
- ・初診当日・土曜日の検査にも対応:お忙しい方でも受けやすい環境を整えています
- ・大腸ポリープ切除にも対応:ポリープが見つかった場合、その場で切除することも可能です
「辛い・苦しい」というイメージがある内視鏡検査を「より気軽に」「よりスピーディーに」そして安心して受けられるよう、様々な工夫を行っています。
検査の予約・お問い合わせ
大腸カメラ検査のご予約やお問い合わせは、お電話またはWEB予約にて承っております。些細なことでもお気軽にご相談ください。
TEL:06-6930-1700
大腸がんは早期発見・早期治療が何よりも重要です。痛みへの不安から検査を躊躇されている方も、ぜひ一度当院の無痛検査をご検討ください。あなたの健康と命を守るために、私たちがサポートいたします。
まとめ:大腸カメラの痛みを軽減して健康を守ろう
大腸カメラ検査は、大腸がんの早期発見・早期治療のために非常に重要な検査です。痛みや不快感への不安から検査を避けてしまうと、早期発見の機会を逃してしまう可能性があります。
本記事でご紹介した7つの対策を参考に、より快適に検査を受けていただければ幸いです。
- ・鎮静剤(麻酔)を使用した無痛検査を選ぶ
- ・経験豊富な内視鏡専門医を選ぶ
- ・炭酸ガス送気を使用した検査を選ぶ
- ・軸保持短縮法による挿入技術を活用する
- ・検査前の腸内環境を整える
- ・リラックスして検査に臨む
- ・ウォーターイクスチェンジ法を活用する
当院では、患者さん一人ひとりに合わせた最適な検査方法をご提案し、安心して検査を受けていただける環境を整えています。大腸カメラ検査に関するご不安やご質問がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
あなたとご家族の健康を守るために、定期的な検査をお勧めします。早期発見・早期治療が、健やかな毎日を支える第一歩です。
石川消化器内科内視鏡クリニックでは、無痛での内視鏡検査を提供しています。詳しくは当院ウェブサイトをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。
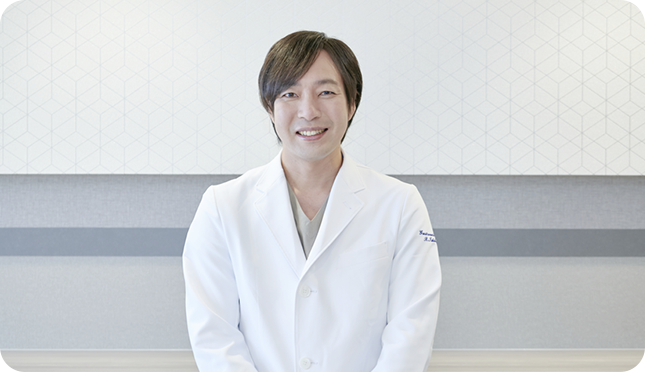
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
内視鏡検査の再検査、適切な時期と目安を専門医が解説
内視鏡検査を受けたあと、「次はいつ検査を受ければいいのだろう?」と疑問に思われる方は多いのではないでしょうか。
胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡検査は、消化器疾患の早期発見・早期治療に欠かせない重要な検査です。しかし、適切な検査間隔について明確に理解している方は意外と少ないようです。
実は、検査結果や年齢、家族歴などによって、次回の検査時期は大きく変わってきます。適切なタイミングで再検査を受けることが、あなたの健康を守る鍵となるのです。
この記事では、消化器内視鏡専門医の立場から、胃カメラ・大腸カメラの適切な再検査の時期や間隔について、わかりやすく解説します。
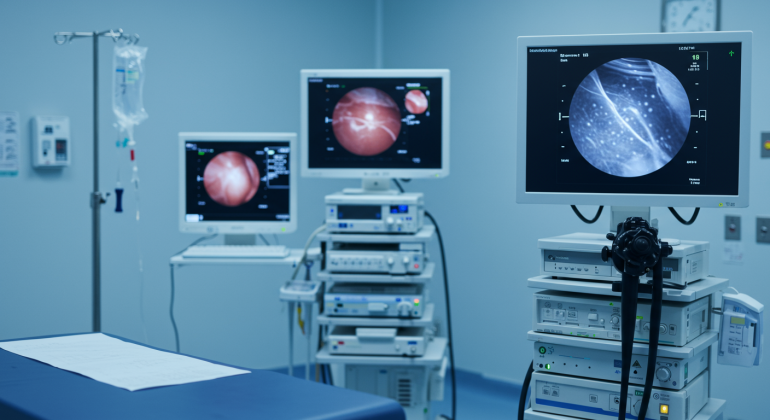
内視鏡検査の再検査が必要な理由
まず、なぜ定期的な内視鏡検査が重要なのかを理解しておきましょう。
消化器疾患、特に胃がんや大腸がんは、日本人の死亡原因として上位を占めています。しかし、早期に発見できれば治療効果は飛躍的に高まります。
内視鏡検査は、目に見えない消化管内部の状態を直接観察できる唯一の方法です。わずか数ミリの小さな病変も発見できるため、がんの早期発見に非常に有効な検査方法となっています。
また、ポリープなどの前がん病変を見つけて切除することで、がんになる前に予防することも可能です。これが「定期的な再検査」が推奨される最大の理由です。
検査で「異常なし」と言われたとしても、新たな病変が発生する可能性はあります。特に年齢を重ねるにつれて、消化器疾患のリスクは高まっていきます。
胃カメラ検査の意義
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)は、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察する検査です。
この検査により、胃炎、胃潰瘍、逆流性食道炎、そして早期の食道がんや胃がんなどを発見することができます。
特に日本人は胃がんの発症率が高く、世界的に見ても胃がん大国と言われています。定期的な胃カメラ検査は、胃がんの早期発見・早期治療に大きく貢献しています。
大腸カメラ検査の意義
大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)は、大腸全体の粘膜を観察する検査です。
大腸ポリープや大腸がん、炎症性腸疾患、虚血性腸炎などの発見に役立ちます。
大腸がんは近年増加傾向にあり、早期発見が非常に重要です。大腸ポリープは時間をかけてがん化することが知られており、定期的な検査でポリープを発見・切除することで、大腸がんの予防につながります。
胃カメラ(上部消化管内視鏡)の適切な再検査間隔
胃カメラの再検査の時期は、前回の検査結果や個人のリスク因子によって異なります。
検査結果が「異常なし」であっても、定期的な検査は重要です。年齢や家族歴、ピロリ菌感染の有無などによって、適切な間隔は変わってきます。
健康な方の場合(異常なし)
特に症状がなく、前回の検査で異常が見つからなかった健康な方の場合、一般的には2年に1回程度の検査が目安となります。
ただし、40歳未満の若年層で特にリスク因子がない場合は、3〜5年に1回でも良いでしょう。
50歳以上になると、胃がんのリスクが高まるため、より定期的な検査(1〜2年に1回)をお勧めします。
ピロリ菌感染歴がある方の場合
ピロリ菌は胃がんの発生リスクを約5倍高めることが報告されています。
ピロリ菌に感染している方、または過去に感染していて除菌治療を受けた方は、1年に1回の胃カメラ検査が推奨されます。
除菌治療後も胃がんのリスクは完全には消えないため、定期的な検査が重要です。特に萎縮性胃炎がある方は、胃がんのリスクが高いため、より慎重なフォローアップが必要です。
胃炎・潰瘍・ポリープなどが見つかった場合
慢性胃炎、胃潰瘍、胃ポリープなどが見つかった場合は、状態によって6ヶ月〜1年の間隔での再検査が推奨されます。
特に萎縮性胃炎や腸上皮化生(胃の粘膜が腸に似た状態に変化すること)がある方は、胃がんのリスクが高いため、1年に1回の定期検査が必要です。
胃ポリープの種類や大きさによっても再検査の間隔は変わります。腺腫性ポリープなど、がん化リスクの高いポリープが見つかった場合は、より短い間隔での再検査が必要です。
大腸カメラ(下部消化管内視鏡)の適切な再検査間隔
大腸カメラの再検査間隔も、前回の検査結果や個人のリスク因子によって大きく異なります。
大腸ポリープは、時間をかけて大腸がんに進展する可能性があるため、適切な間隔での再検査が重要です。
異常なしだった場合
前回の大腸カメラ検査で異常が見つからなかった場合、一般的には以下の間隔が推奨されます。
45歳未満で大腸がんの家族歴がない方は、5〜10年後の再検査が目安となります。
45歳以上の方は、大腸がんのリスクが高まるため、5年ごとの検査が推奨されます。
大腸がんの家族歴がある方は、より短い間隔(3〜5年)での検査が必要です。
ポリープを切除した場合
大腸ポリープを切除した場合、ポリープの種類・大きさ・数によって再検査の間隔が決まります。
小さな(10mm未満)良性ポリープが1〜2個だけだった場合は、3〜5年後の再検査が一般的です。
大きなポリープ(10mm以上)や多数(3個以上)のポリープ、または腺腫性ポリープ(がんの前段階)が見つかった場合は、1〜3年後の再検査が推奨されます。
特に高リスクと判断された場合(絨毛状構造を持つポリープや高度異型のポリープなど)は、6ヶ月〜1年以内の再検査が必要になることもあります。
大腸ポリープは体質・生活習慣・年齢などの影響で繰り返しできる傾向があり、特に切除後3年以内に新しいポリープが発見される確率は20〜40%とされています。定期的な再検査で早期発見・再切除することが大腸がん予防につながります。
炎症性腸疾患がある場合
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患がある方は、がんのリスクが高まるため、より頻繁な検査が必要です。
一般的には、疾患の活動性や罹患期間によって異なりますが、1〜2年ごとの定期検査が推奨されています。
長期間(8年以上)炎症性腸疾患に罹患している方は、大腸がんのリスクが特に高まるため、より短い間隔での検査が必要です。
再検査の時期を決める重要な要素
内視鏡検査の再検査時期を決める際には、いくつかの重要な要素を考慮する必要があります。
年齢と性別
年齢が上がるにつれて、消化器がんのリスクは高まります。特に50歳を超えると、胃がんや大腸がんの発生率が上昇します。
性別によっても、リスクは異なります。例えば、胃がんは男性に多く、大腸がんは性差が少ないとされています。
高齢になるほど、より頻繁な検査が推奨されますが、同時に患者さんの全身状態や余命も考慮する必要があります。
家族歴と遺伝的要因
胃がんや大腸がんの家族歴がある方は、そうでない方に比べてリスクが高くなります。
特に、第一度近親者(親・兄弟姉妹・子)に胃がんや大腸がんの罹患者がいる場合は、より短い間隔での検査が推奨されます。
家族性大腸腺腫症やリンチ症候群などの遺伝性疾患がある場合は、専門医と相談の上、より頻繁な検査スケジュールを組む必要があります。
生活習慣と環境要因
喫煙、過度の飲酒、塩分の多い食事、肥満などは、消化器がんのリスクを高める生活習慣です。
これらのリスク因子を持つ方は、より頻繁な検査が推奨されることがあります。
逆に、生活習慣の改善(禁煙、適正飲酒、バランスの良い食事など)によって、リスクを下げることも可能です。
内視鏡検査の再検査を受ける際の注意点
内視鏡検査の再検査を受ける際には、いくつかの重要な注意点があります。
前回の検査結果を持参する
可能であれば、前回の検査結果(検査レポートや画像)を持参しましょう。
特に別の医療機関で検査を受ける場合は、前回の結果があると、医師が比較検討できるため、より正確な診断が可能になります。
当院では、過去の検査データを電子カルテで管理しているため、当院で検査を受けられた方は、前回との比較が容易です。
検査前の準備を正しく行う
胃カメラ検査の場合は、検査前の絶食(通常6〜8時間)が必要です。
大腸カメラ検査の場合は、前日からの食事制限と下剤の服用が必要です。検査の精度を高めるためにも、医師の指示に従って正しく準備を行いましょう。
当院では、大腸カメラ検査の際には、下剤の飲み方や前日の食事について詳しく説明しています。準備が不十分だと、検査の精度が下がったり、再検査が必要になったりすることもあります。
定期検査を継続する重要性
「前回異常がなかったから」と安心して検査を怠ると、病変を見逃すリスクが高まります。
特に、ポリープを切除した方は、新たなポリープができる可能性が高いため、定期的な検査が重要です。
定期検査は「切除して終わり」ではなく「継続的な管理」が未来の健康を守る鍵となります。
当院での内視鏡検査の特徴
石川消化器内科内視鏡クリニックでは、患者さんの負担を最小限に抑えた内視鏡検査を提供しています。
無痛内視鏡検査
当院では、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛内視鏡検査を行っています。半分眠ったような状態で検査を受けられるため、痛みや恐怖感をほとんど感じることなく検査を受けていただけます。
「以前の検査が辛かった」という方も、当院の無痛内視鏡検査であれば、リラックスして受けていただくことが可能です。
経口・経鼻どちらの胃カメラも選択可能で、患者さんの状態や希望に合わせた検査方法をご提案しています。
高性能な内視鏡機器
当院では、最新の拡大内視鏡を導入しており、微細な病変も見逃さない高精度な検査が可能です。
特殊な光を用いることで、通常の内視鏡では見えにくい早期がんやポリープも発見しやすくなっています。
大学病院に劣らない内視鏡検査環境を整えており、早期発見・早期治療に貢献しています。
当日検査・土曜検査にも対応
当院では、初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しています。
平日は忙しくて時間が取れない方でも、土曜日に検査を受けることが可能です。
また、検査後の待ち時間短縮にも取り組んでおり、患者さんの負担を軽減しています。
まとめ:適切な再検査で健康を守る
内視鏡検査の再検査時期は、前回の検査結果や個人のリスク因子によって異なります。一般的な目安としては、以下のようになります。
胃カメラ検査:健康な方は2年に1回、ピロリ菌感染歴がある方は1年に1回、胃炎・潰瘍・ポリープがある方は6ヶ月〜1年に1回
大腸カメラ検査:異常なしの場合は5年に1回(45歳以上)、ポリープ切除後は1〜5年に1回(ポリープの種類・大きさ・数による)、炎症性腸疾患がある方は1〜2年に1回
定期的な内視鏡検査は、消化器がんの早期発見・早期治療に非常に重要です。「症状がないから大丈夫」と安心せず、適切な間隔で検査を受けることをお勧めします。
当院では、患者さん一人ひとりの状態に合わせた検査間隔をご提案しています。検査後には、次回の適切な検査時期についても詳しくご説明いたします。
内視鏡検査に関するご不安やご質問がありましたら、お気軽に当院までご相談ください。患者さんの健康を守るため、最適な検査計画をご提案いたします。
詳しくは石川消化器内科内視鏡クリニックのホームページをご覧ください
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
喫煙と飲酒が胃腸に与える影響と対策|消化器専門医の見解
喫煙と飲酒が胃腸に与える影響とは
皆さんは「タバコとお酒、どちらが胃に悪いですか?」という質問を受けることがあります。実はこれは診察室でもよく耳にする質問の一つです。
結論からお伝えすると、タバコもお酒も胃腸に対して悪影響を及ぼします。特に両方を習慣的に摂取している方は、消化器疾患のリスクが大幅に高まることが研究で明らかになっています。
消化器内科専門医として日々多くの患者さんを診察していると、生活習慣が胃腸の健康に大きく影響していることを実感します。特に喫煙と飲酒は、胃腸トラブルの主要な原因となっています。
今回は、喫煙と飲酒が胃腸にどのような影響を与えるのか、そしてどのような対策が効果的なのかについて、消化器専門医の立場から詳しく解説していきます。

喫煙が胃腸に与える影響
タバコに含まれるニコチンは、胃腸に様々な悪影響を及ぼします。特に以下の3つの作用が問題となります。
まず第一に、ニコチンは血管を収縮させ、胃粘膜への血流を低下させます。胃の粘膜は常に胃酸から自らを守るために再生を繰り返していますが、血流が悪くなると粘膜の修復能力が低下し、炎症や潰瘍が発生しやすくなります。
第二に、ニコチンは胃酸の分泌を促進します。過剰な胃酸は胃粘膜を攻撃し、すでに弱った粘膜にさらなるダメージを与えることになります。これにより、慢性胃炎や胃潰瘍、逆流性食道炎などのリスクが高まります。
胃がチクチク痛む、食後にムカムカする、空腹時に胃がシクシクするといった症状がある喫煙者は、すでに胃に何らかのダメージが生じている可能性が高いです。
第三に、喫煙はピロリ菌の除菌治療の成功率を下げることも分かっています。ピロリ菌感染は胃炎や胃潰瘍、さらには胃がんの主要なリスク因子ですが、喫煙によってその治療効果が減弱してしまうのです。
飲酒が胃腸に与える影響
アルコールは直接胃粘膜を刺激し、炎症を引き起こす物質です。特に空腹時や大量摂取の際には、胃壁がただれ、急性胃炎(いわゆる酒胃)を発症するリスクがあります。
お酒の種類によっても胃への影響は異なります。ビールやワインは酸性度が高く、胃酸とともに胃粘膜を刺激しやすい傾向があります。焼酎やウイスキーなどの高濃度アルコールは少量でも強い刺激となります。日本酒は糖質が高く、胃の消化活動に負担をかけることがあります。
つまり、「お酒は何を飲んでも胃には少なからず負担」になるのです。
特に注意が必要なのは、飲酒と喫煙を同時に行うことです。この組み合わせは胃腸への悪影響を相乗的に高め、胃がんリスクを加速度的に上昇させるという研究結果も報告されています。消化器内科医として、これは最も危険視している生活習慣の一つです。
胃腸からのSOSサイン|見逃してはいけない症状
胃腸が悲鳴を上げているとき、体はさまざまな形で警告を発します。以下のような症状が現れたら、胃腸からのSOSサインかもしれません。
食後の胃のもたれが1週間以上続く、空腹時や夜間の胃痛、頻繁なげっぷや胸やけ、食欲低下、みぞおちの不快感や鈍い痛みなどの症状があれば要注意です。
これらの症状は、単なる生活習慣の問題だけでなく、慢性胃炎、逆流性食道炎、胃潰瘍、ピロリ菌感染、さらには胃がんの初期症状である可能性もあります。
「なんとなく調子が悪いから市販薬で様子を見よう」と思われる方も多いでしょう。しかし、市販薬で症状を一時的に抑えても、根本的な原因が解決されないまま病気が進行してしまうことがあります。
特に40歳以上の方で、これらの症状が2週間以上続く場合は、早めに消化器内科を受診されることをお勧めします。
喫煙による胃腸への悪影響と具体的なメカニズム
喫煙が胃腸に与える影響について、もう少し詳しく見ていきましょう。
タバコの煙に含まれる有害物質は、吸い込むだけでなく唾液とともに胃に入ります。これらの有害物質は胃粘膜を直接刺激し、炎症を引き起こします。
私が診察した患者さんの中には、「朝一番のタバコを吸うと必ずお腹が痛くなる」と訴える方が少なくありません。これは夜間の絶食状態で弱った胃粘膜に、朝一番のタバコの刺激が直接作用するためです。
また、喫煙は消化管の運動にも影響します。タバコに含まれるニコチンは、胃の蠕動運動(食べ物を腸に送り出す動き)を抑制することがあります。その結果、食べ物が胃に長く留まり、胃もたれや膨満感の原因となります。
さらに深刻なのは、喫煙が潰瘍の治癒を遅らせる点です。研究によれば、同じ治療を受けた潰瘍患者でも、喫煙者は非喫煙者に比べて治癒率が30%以上も低いことが分かっています。これは喫煙による血流低下と粘膜修復能力の低下が主な原因です。
喫煙は胃腸だけでなく、肝臓や膵臓にも悪影響を及ぼします。タバコに含まれる有害物質は肝臓で解毒処理されますが、この過程で肝細胞に負担をかけます。また、喫煙は膵炎のリスクも高めることが知られています。
喫煙と消化器がんの関係
喫煙は様々な消化器がんのリスクを高めることが多くの研究で証明されています。特に食道がん、胃がん、大腸がん、膵臓がんなどとの関連が強いことが分かっています。
タバコに含まれる発がん物質は、消化管粘膜に直接接触することで細胞のDNAを傷つけ、がん化のリスクを高めます。また、喫煙による慢性炎症は、がんの発生・進展を促進する環境を作り出します。
特に注目すべきは、喫煙とピロリ菌感染の相乗効果です。両方のリスク因子を持つ方は、胃がんのリスクが単独の場合よりも大幅に高まります。
飲酒による胃腸への悪影響と種類別の特徴
飲酒が胃腸に与える影響は、アルコールの種類や飲み方によって異なります。ここでは、アルコール飲料の種類別に胃腸への影響を解説します。
ビールは炭酸ガスを含むため、胃を膨張させ内圧を高めます。これにより、胃酸が食道に逆流しやすくなり、逆流性食道炎のリスクが高まります。また、ビールの酸性度も胃粘膜への刺激となります。
ワインに含まれるポリフェノールには抗酸化作用がありますが、酸性度が高いため胃粘膜を刺激します。特に空腹時の白ワインは胃への刺激が強いので注意が必要です。
焼酎やウイスキーなどの蒸留酒は、アルコール濃度が高いため胃粘膜への直接的な刺激が強くなります。水やお湯で適度に薄めることで、ある程度刺激を軽減できます。
日本酒は比較的マイルドですが、糖質が多く含まれるため、消化に時間がかかり胃に負担をかけることがあります。また、温度によっても影響が変わり、熱燗は胃の血流を一時的に増加させますが、アルコールの吸収も早めます。
どうしても飲酒したい場合は、食事をしながら適量を楽しむことが胃腸への負担を減らすポイントです。空腹時の飲酒は絶対に避けるべきです。
飲酒と消化器疾患の関係
過度の飲酒は様々な消化器疾患のリスクを高めます。急性胃炎や胃潰瘍だけでなく、慢性的な飲酒は肝臓や膵臓にも深刻なダメージを与えます。
アルコール性肝障害は、脂肪肝から肝炎、肝硬変へと進行する可能性があります。また、過度の飲酒は急性膵炎や慢性膵炎のリスクも高めます。
特に注意が必要なのは、「マロリーワイス症候群」と呼ばれる状態です。これは、激しい嘔吐によって食道下部から胃の入り口付近の粘膜が裂け、出血する病態です。飲酒後の嘔吐で発症することが多く、大量に出血するとショック状態に陥る危険性もあります。
また、長期的な大量飲酒は大腸ポリープの発生リスクを高め、大腸がんの発症にも関連していることが研究で示されています。
胃腸を守るための具体的な対策
喫煙と飲酒による胃腸へのダメージを軽減するためには、禁煙・禁酒が最も効果的です。しかし、すぐに習慣を変えることが難しい方もいらっしゃるでしょう。ここでは、胃腸を守るための具体的な対策をご紹介します。
喫煙者のための胃腸保護策
まず第一に、禁煙を目指すことが最も重要です。禁煙することで、胃粘膜の血流は改善し、胃酸分泌も正常化に向かいます。禁煙後3ヶ月程度で胃粘膜の状態は大きく改善することが多いです。
すぐに禁煙が難しい場合は、以下の点に注意しましょう:
- 空腹時の喫煙を避ける(特に朝一番のタバコは胃に負担)
- 食後すぐの喫煙も控える(消化に影響するため)
- 喫煙本数を徐々に減らす
- 胃粘膜保護剤の服用を医師に相談する
また、喫煙者は非喫煙者よりもビタミンCの消費量が多いため、柑橘類や野菜からビタミンCを積極的に摂取することも胃粘膜の保護に役立ちます。
飲酒時の胃腸保護策
飲酒時に胃腸への負担を軽減するためには、以下の点を意識しましょう:
- 空腹時の飲酒は絶対に避ける(前もって乳製品などを食べて胃を保護)
- 適量を守る(ビールなら中瓶1本、日本酒なら1合、ワインならグラス2杯程度)
- ゆっくりと飲む(急速な血中アルコール濃度の上昇を避ける)
- 良質なタンパク質を含むおつまみを選ぶ(枝豆、豆腐料理、白身魚など)
- 強いお酒は薄めて飲む
- 飲酒中・飲酒後にも水分をこまめに摂る
また、アルコール分解に関わる肝臓の負担を減らすためにも、週に2日以上の休肝日を設けることをお勧めします。
胃腸の健康を守るための生活習慣改善
喫煙と飲酒以外にも、胃腸の健康を守るために意識したい生活習慣があります。
食生活の改善
胃に優しい食事を心がけましょう。具体的には以下のポイントが重要です:
- 脂肪分の多い食材や揚げ物を控える(消化に時間がかかるため)
- 香辛料の過剰摂取を避ける(胃粘膜への刺激となる)
- 食事は腹八分目を意識し、ゆっくり良く噛んで食べる
- 就寝直前の食事を避ける(逆流性食道炎のリスクが高まる)
- 規則正しい時間に食事をとる
胃に優しい食材としては、豆腐、白身魚、鶏のささみ、おかゆ、雑炊などがおすすめです。果物ではバナナやリンゴが比較的胃に負担をかけません。
ストレス管理
ストレスは胃酸の過剰分泌を促し、胃腸の動きにも悪影響を与えます。ストレス管理のために以下を心がけましょう:
- 適度な運動で気分転換(ウォーキングなどの有酸素運動がおすすめ)
- 十分な睡眠時間の確保(自律神経のバランスを整える)
- 深呼吸やストレッチなどのリラクゼーション法の実践
- 趣味や好きな活動に時間を使う
特に自律神経のバランスは胃腸の働きに大きく影響します。睡眠不足が続くと、起きている時に活動する「交感神経」と寝ている時に活動する「副交感神経」のバランスが崩れ、胃腸の機能に支障をきたします。
胃腸の健康は全身の健康の基盤です。日々の小さな習慣改善が、長期的な健康維持につながります。
内視鏡検査で胃腸の状態を確認する重要性
喫煙や飲酒の習慣がある方、胃腸の不調が続く方は、定期的に内視鏡検査を受けることをお勧めします。
内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)は、消化管の粘膜を直接観察することで、炎症・潰瘍・ポリープ・がんなどの病変を早期に発見できる重要な検査です。
「辛い・苦しい」というイメージがある内視鏡検査ですが、現在は技術の進歩により、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛内視鏡検査が広く普及しています。半分眠ったような状態で検査を受けることができるため、痛みや不快感をほとんど感じることなく検査が可能です。
特に喫煙や飲酒の習慣がある方は、自覚症状がなくても定期的な検査が重要です。胃がんや大腸がんは早期発見できれば治療成績が良好な疾患ですが、進行すると治療が難しくなります。
当院では最新の内視鏡機器を導入し、経口・経鼻の胃カメラを患者さんのご希望に応じて選択いただけます。また、土曜日の検査にも対応しており、お忙しい方でも受診しやすい環境を整えています。
胃腸の健康に不安がある方は、ぜひ一度消化器内科専門医にご相談ください。
まとめ:喫煙と飲酒が胃腸に与える影響と対策
喫煙と飲酒はどちらも胃腸に悪影響を及ぼします。タバコに含まれるニコチンは胃粘膜の血流を低下させ、胃酸分泌を促進することで胃腸にダメージを与えます。アルコールは直接胃粘膜を刺激し、炎症を引き起こします。特に両者を併用すると、そのリスクは相乗的に高まります。
胃腸を守るためには、禁煙・禁酒が最も効果的ですが、すぐに習慣を変えることが難しい場合は、空腹時の喫煙・飲酒を避ける、適量を守る、胃に優しい食事を心がけるなどの対策が有効です。
また、胃腸の不調が続く場合は、市販薬で対処するのではなく、専門医による適切な診断と治療を受けることが重要です。内視鏡検査は胃腸の状態を直接確認できる有効な手段であり、現在は無痛で受けられる検査方法も普及しています。
胃腸の健康は全身の健康の基盤です。喫煙や飲酒の習慣を見直し、適切な生活習慣を心がけることで、胃腸トラブルの予防と健康維持につなげましょう。
胃腸の健康に不安がある方は、ぜひ当院にご相談ください。消化器・内視鏡専門医として、皆様の健康をサポートいたします。
詳しい情報や予約については、石川消化器内科内視鏡クリニックのウェブサイトをご覧ください。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
胃カメラ検査後の食事〜専門医が教える回復のポイント

胃カメラ検査後の食事はいつから始めるべき?
胃カメラ検査を受けた後、多くの患者さんが「いつから食事を再開していいのか」と不安を感じています。検査で空腹状態が続いた後だけに、早く何か食べたいという気持ちは理解できます。
胃カメラ検査では、のどの麻酔や鎮静剤を使用することが一般的です。当院では、喉の反射を抑えるためにキシロカインビスカスという局所麻酔を使用しています。この麻酔は約1時間程度で効果が切れますが、その間は飲み込む感覚が麻痺しているため、誤嚥のリスクがあります。
鎮静剤を使用した場合は、完全に目が覚めて意識がはっきりするまで食事を控える必要があります。意識がぼんやりしている状態で飲食すると、食べ物や水分が気管に入ってしまう危険性があるからです。
検査後は以下の手順で食事を再開するのが安全です:
- ・検査終了後、少なくとも1時間は飲食を控える
- ・1時間経過後、まず少量の常温の水を飲んでみる
- ・むせずに水が飲めたら、消化の良い食事から少しずつ始める
胃カメラ検査は胃に負担をかけるため、検査直後の胃はとてもデリケートな状態です。特に組織検査(生検)を行った場合は、胃の粘膜に小さな傷がついているため、より慎重に食事を再開する必要があります。
胃カメラ検査後に食べてはいけないものとは?
胃カメラ検査後の胃は敏感な状態にあります。検査で空気を送り込んだことによる膨満感が残っていたり、粘膜が刺激を受けていたりします。そのため、検査当日は胃に優しい食事を心がけることが大切です。
特に避けるべき食品には以下のようなものがあります。これらは胃への負担が大きく、消化不良や胃の不快感を引き起こす可能性があるからです。
- 脂っこい食品:揚げ物、天ぷら、カツ、唐揚げ、フライドポテトなど
- 刺激物:カレー、キムチ、唐辛子などの香辛料を使った料理
- アルコール類:ビール、ワイン、日本酒など全てのアルコール飲料
- 繊維質の多い食品:レンコン、ゴボウ、こんにゃく、海藻類、キノコ類
- 脂質の多い肉・加工肉:ベーコン、ソーセージなど
これらの食品は消化に時間がかかり、胃に負担をかけます。特に組織検査を行った場合は、出血のリスクを高める可能性もあるため、検査当日は避けるようにしましょう。
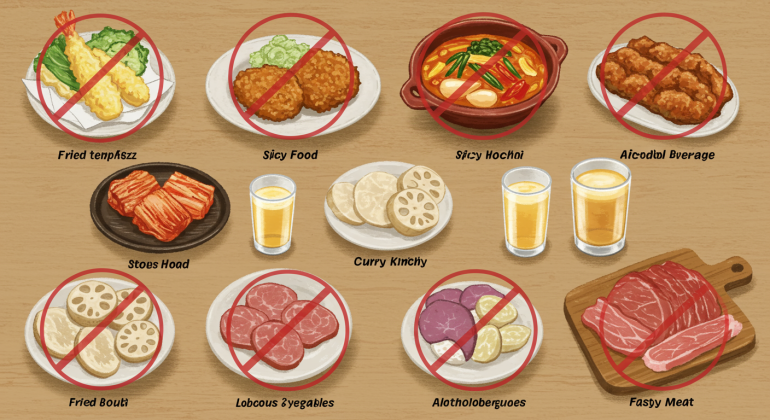
胃カメラ検査後に食べ物や飲み物で気をつけるべきことは他にもあります。キンキンに冷えた飲み物や炭酸飲料も胃を刺激するので避けた方が無難です。また、コーヒーや紅茶などのカフェインを含む飲み物も胃酸の分泌を促進するため、検査当日は控えるようにしましょう。
もし生検を行った場合は、傷口からの出血リスクを考慮して、より慎重に食事を選ぶ必要があります。刺激物や硬い食べ物は特に避け、検査当日だけでなく翌日も胃に優しい食事を続けることをお勧めします。
胃カメラ検査後におすすめの食事メニュー
胃カメラ検査後の食事は、消化が良く胃に負担をかけないものを選ぶことが重要です。検査で疲れた胃を休ませながら、必要な栄養を摂取できるメニューを心がけましょう。
おすすめの食品には以下のようなものがあります:
- ・炭水化物:おかゆ、やわらかいご飯、うどん
- ・タンパク質:豆腐、煮魚、鶏のささみ肉、赤身肉
- ・野菜:みそ汁、大根・にんじん・かぼちゃなどの煮物
- ・果物・デザート:りんご、バナナ、ヨーグルト、プリン
- ・飲み物:麦茶、白湯、スポーツドリンク(常温)

これらの食品は消化が良く、胃への負担が少ないため、検査後の食事として適しています。特に最初の食事は少量から始め、体調を見ながら徐々に量を増やしていくことをお勧めします。
具体的な回復食メニュー例
検査当日の夕食として、以下のようなメニューがおすすめです:
- 卵がゆまたは白がゆ(消化が良く、胃に優しい)
- やわらかく煮た白身魚(タンパク質補給)
- 大根と人参の煮物(やわらかく煮ることで食物繊維も摂取可能)
- 具の少ないみそ汁(水分と塩分の補給)
- デザートにヨーグルトかプリン(カルシウム補給と消化促進)
翌日の朝食には、食パンやロールパンなどのシンプルなパン類と、ヨーグルトや温かいスープなどを組み合わせるのも良いでしょう。脂肪分の多いバターやマヨネーズは控え、ジャムやはちみつなど消化の良いものを選びます。
胃の調子が良ければ、翌日の昼食からは徐々に通常の食事に戻していくことができますが、脂っこいものや刺激物は引き続き控えめにするのが無難です。
胃カメラ検査後に起こりやすい症状と対処法
胃カメラ検査後には、いくつかの症状が現れることがあります。これらの多くは検査の影響による一時的なものですが、適切な対処が必要です。
検査後によくある症状
胃カメラ検査後によく見られる症状には以下のようなものがあります:
- ・のどの違和感・痛み:内視鏡の挿入による刺激で起こります
- ・腹部の膨満感:検査中に送り込まれた空気によるものです
- ・げっぷや放屁:体内に入った空気が出ようとする自然な反応です
- ・軽い吐き気:内視鏡による刺激や鎮静剤の影響で起こることがあります
- ・青い便:色素(インジゴカルミン)を使用した場合に見られることがあります
これらの症状のほとんどは24時間以内に自然に改善します。のどの違和感は2〜3日続くこともありますが、徐々に良くなっていきます。
注意が必要な症状
一方で、以下のような症状が現れた場合は、すぐに医療機関に連絡することが重要です:
- ・強い腹痛:持続する場合や増強する場合は要注意
- ・発熱:38度以上の発熱は感染の可能性があります
- ・黒い便や血便:消化管出血の可能性があります
- ・嘔吐:特に繰り返す場合や血液が混じる場合は危険信号
- ・胸痛や呼吸困難:緊急性の高い症状です
これらの症状は稀ですが、生検部位からの出血や穿孔(せんこう:消化管に穴が開くこと)などの合併症の可能性があります。早期発見・早期治療が重要なので、異常を感じたらためらわずに連絡してください。
症状への対処法
検査後の一般的な症状には、以下のように対処するとよいでしょう:
- ・のどの違和感:冷たすぎない飲み物でこまめに水分補給、のど飴の使用
- ・腹部の膨満感:ゆっくり歩くなど軽い運動で腸の動きを促進
- ・げっぷや放屁:自然に出すことで楽になります、我慢しないでください
- ・軽い吐き気:少量の水分を少しずつ摂取、横になって休む
症状が長引く場合や心配な場合は、遠慮なく医療機関に相談してください。患者さんの不安を取り除くことも、私たち医療者の大切な役割だと考えています。
胃カメラ検査後の生活上の注意点
胃カメラ検査後は、食事だけでなく生活面でもいくつかの注意点があります。適切な過ごし方をすることで、体への負担を減らし、スムーズな回復につながります。
検査当日の過ごし方
検査当日は、以下のような点に注意して過ごしましょう:
- ・入浴:シャワーは問題ありませんが、長時間の入浴や熱いお風呂は血流が増加して出血リスクが高まるため避けましょう
- ・運動:激しい運動や重い物の持ち上げは避け、軽い散歩程度にとどめましょう
- ・飲酒・喫煙:アルコールは胃粘膜を刺激し、喫煙は血管を収縮させるため、どちらも控えましょう
- ・薬の服用:医師から特別な指示がない限り、普段の薬は通常通り服用して構いません
特に鎮静剤を使用した場合は、その日の車の運転や機械操作、重要な判断を要する業務は避けてください。鎮静剤の影響は個人差がありますが、24時間程度は残ることがあります。
検査翌日以降の生活
検査翌日からは、基本的に通常の生活に戻ることができますが、生検を行った場合などは以下の点に注意しましょう:
- ・食事:徐々に普通の食事に戻しますが、刺激物や消化の悪いものは数日間控えめに
- ・運動:激しいスポーツや重労働は3日程度控え、体調を見ながら徐々に再開
- ・飲酒:生検を行った場合は3日程度は控え、その後も適量を心がける
- ・服薬:抗血栓薬(血液をサラサラにする薬)を服用している方は、医師の指示に従って再開
特に気をつけていただきたいのは、検査結果が出るまでの間に体調の変化があった場合は、すぐに医療機関に連絡することです。早期発見・早期対応が重要です。
まとめ:胃カメラ検査後の回復を促進するポイント
胃カメラ検査後の回復をスムーズに進めるためには、適切な食事と生活習慣が重要です。ここまでの内容をまとめると、以下のポイントが大切です:
- ・食事再開のタイミング:麻酔や鎮静剤の効果が切れてから(約1時間後)、少量の水から始める
- ・食事内容:消化の良い食品を選び、脂っこいもの・刺激物・繊維質の多いものは避ける
- ・食べ方:よく噛んでゆっくり食べ、一度に大量に食べない
- ・生活面:検査当日は安静に過ごし、アルコール・喫煙・激しい運動は控える
- ・症状の観察:異常な症状(強い腹痛・発熱・黒い便など)が現れたら速やかに医療機関に連絡
胃カメラ検査は、胃がんをはじめとする消化器疾患の早期発見・早期治療に非常に重要な検査です。検査後の適切なケアを行うことで、体への負担を最小限に抑え、スムーズな回復につなげることができます。
当院では、検査後のフォローも丁寧に行っています。不安なことや気になる症状があれば、遠慮なくご相談ください。皆様の健康を守るために、私たちは常にサポートいたします。
胃カメラ検査に対する「辛い・苦しい」というイメージを払拭し、安心して検査を受けていただけるよう、これからも努めてまいります。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
雇入れ時健康診断で内視鏡検査は必要?医師が解説する重要性と選び方
雇入れ時健康診断とは?法的根拠と基本的な検査項目
雇入れ時健康診断は、企業が新たに従業員を採用する際に実施が義務付けられている健康診断です。労働安全衛生法に基づいて実施され、従業員の健康状態を把握し、適切な職場環境を整えるための重要な取り組みとなっています。
この健康診断は、正社員だけでなく、パートやアルバイトでもフルタイム労働者の4分の3以上の時間で働く方が対象となります。つまり、雇用形態に関わらず、多くの労働者が受ける必要があるのです。
雇入れ時健康診断の基本的な検査項目には、問診・診察、身体測定、視力・聴力検査、血圧測定、尿検査、胸部X線検査、心電図検査、そして血液検査などが含まれます。これらの検査を通じて、従業員の基本的な健康状態を把握することができます。
しかし、基本項目だけで十分なのでしょうか?特に消化器系の疾患は初期段階では自覚症状がないことも多く、基本的な検査だけでは見逃されてしまう可能性があります。
私は消化器内科専門医として、特に胃がんや大腸がんなどの消化器系疾患の早期発見・早期治療の重要性を日々実感しています。これらの疾患は40歳前後から発症リスクが高まることが知られており、適切な検査を受けることで早期発見・早期治療が可能になるのです。
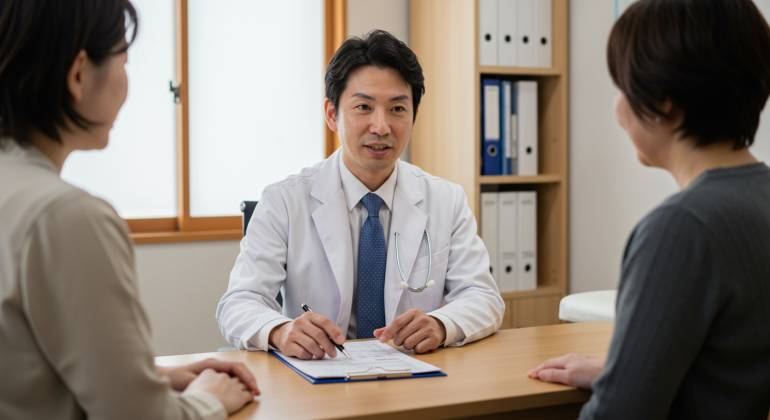
内視鏡検査を雇入れ時健康診断に追加すべき理由
雇入れ時健康診断に内視鏡検査を追加することには、いくつかの重要な理由があります。まず第一に、消化器系疾患の早期発見が可能になるという点が挙げられます。
胃がんや大腸がんは、日本人の死亡原因として上位を占める疾患です。これらの疾患は初期段階では自覚症状がほとんどなく、通常の健康診断では見つけにくいことが特徴です。内視鏡検査を行うことで、これらの疾患を早期に発見し、適切な治療につなげることができます。
特に40歳以上の方や、胃がんや大腸がんの家族歴がある方、胃炎や逆流性食道炎などの症状がある方には、内視鏡検査が強く推奨されます。これらのリスク要因を持つ方は、基本的な健康診断だけでは十分な健康チェックができない可能性があるのです。
また、内視鏡検査は単に疾患を発見するだけでなく、その場でポリープの切除なども行うことができます。大腸ポリープは放置すると大腸がんに発展する可能性があるため、早期に発見して切除することで、がんの予防にもつながります。
さらに、内視鏡検査によって胃炎の原因となるピロリ菌の感染状況も確認できます。ピロリ菌は胃がんの主要な原因の一つとされており、感染が確認されれば除菌治療を行うことで、胃がんのリスクを大幅に減らすことができるのです。
雇入れ時に内視鏡検査を行うことで、従業員の健康状態をより詳細に把握し、将来的な健康リスクを低減することができます。これは従業員個人の健康維持だけでなく、企業にとっても従業員の長期的な健康管理や医療費の削減につながる重要な投資と言えるでしょう。
あなたは自分の健康に投資していますか?
内視鏡検査の種類と特徴
内視鏡検査には主に「上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)」と「下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)」の2種類があります。それぞれの特徴と検査方法について詳しく見ていきましょう。
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)
胃カメラは、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察する検査です。細いカメラを口または鼻から挿入し、上部消化管の状態を詳しく調べます。
この検査では、胃炎や逆流性食道炎、潰瘍、ポリープ、がんなどの病変を早期に発見することができます。また、必要に応じて組織を採取し、病理検査を行うことも可能です。
胃カメラには「経口」と「経鼻」の2つの方法があります。経口では口からカメラを挿入するため、より太いカメラを使用でき、鮮明な画像が得られるというメリットがあります。一方、経鼻では鼻からカメラを挿入するため、オエッという咽頭反射が起こりにくく、比較的楽に検査を受けられるというメリットがあります。
当クリニックでは、患者さんの希望に応じて両方の方法に対応しています。また、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の胃カメラ検査も提供しており、検査への不安や恐怖感を軽減することができます。
下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)
大腸カメラは、大腸全体の粘膜をカメラで観察する検査です。肛門からカメラを挿入し、大腸の状態を詳しく調べます。
この検査では、大腸がんやポリープ、過敏性腸症候群、虚血性大腸炎、炎症性腸疾患などの病変を発見することができます。特に便潜血検査で陽性判定が出た方は、精密検査として大腸カメラ検査を受けることが推奨されます。
大腸カメラの大きな利点は、検査中にポリープが見つかった場合、その場で切除することができる点です。大腸ポリープは放置すると大腸がんに発展する可能性があるため、早期に発見して切除することが重要です。当クリニックでは、日帰りでのポリープ切除にも対応しています。
大腸カメラ検査は胃カメラに比べて時間がかかりますが、鎮静剤を使用することで、ほとんど苦痛を感じることなく検査を受けることができます。
内視鏡検査は、消化器系疾患の早期発見・早期治療に非常に有効な検査方法です。特に40歳以上の方や、消化器系疾患のリスク要因を持つ方には、定期的な内視鏡検査をお勧めします。
雇入れ時健康診断に内視鏡検査を追加する際の選び方
雇入れ時健康診断に内視鏡検査を追加する際には、いくつかのポイントを考慮して適切な医療機関を選ぶことが重要です。ここでは、内視鏡検査を提供する医療機関を選ぶ際のポイントについて解説します。
専門性と経験豊富な医師の存在
内視鏡検査は、高度な専門性と経験が求められる検査です。消化器内科専門医や内視鏡専門医が在籍しているクリニックを選ぶことが重要です。
専門医は最新の知識と技術を持ち、異常所見を見逃さず、適切な診断と治療方針を提案することができます。また、万が一の合併症にも適切に対応できる体制が整っていることも重要なポイントです。
最新の設備と技術の導入
内視鏡検査の精度は、使用する機器の性能に大きく左右されます。拡大内視鏡や特殊光観察など、最新の技術を導入しているクリニックを選ぶことで、より精密な検査が可能になります。
当クリニックでは、特殊な光によって粘膜の微細な変化まで観察できる拡大内視鏡を導入しており、大学病院に劣らない高精度な検査を実現しています。早期のがんやポリープの発見率が高まり、より確実な診断が可能になっています。
患者さんの負担軽減への取り組み
内視鏡検査は、「痛い」「怖い」というイメージを持たれがちです。そのため、患者さんの負担を軽減するための取り組みを行っているクリニックを選ぶことが重要です。
鎮静剤(麻酔)を使用した無痛内視鏡検査の提供や、経鼻胃カメラの選択肢があるクリニック、さらに初診当日の検査対応や土曜日の検査実施など、患者さんの利便性を考慮したサービスを提供しているクリニックがおすすめです。
当クリニックでは、半分眠ったような状態で受けられる無痛の内視鏡検査を提供しており、痛みや恐怖をほとんど感じることなく検査を受けることができます。また、経口・経鼻どちらの胃カメラも選択可能で、患者さんの希望に合わせた検査方法を提案しています。
アクセスの良さと予約のしやすさ
健康診断は定期的に受ける必要があるため、アクセスの良い場所にあるクリニックを選ぶことも重要です。また、予約がスムーズに取れるかどうかも、継続的に通院する上で重要なポイントとなります。
当クリニックは「蒲生四丁目駅」5番出口からすぐの場所に位置しており、アクセスの良さも特徴の一つです。また、電話予約とWEB予約の両方に対応しており、患者さんの利便性を高めています。
雇入れ時健康診断に内視鏡検査を追加する際には、これらのポイントを考慮して、信頼できる医療機関を選ぶことが大切です。適切な医療機関で定期的な検査を受けることで、消化器系疾患の早期発見・早期治療につながります。

企業と従業員双方にとってのメリット
雇入れ時健康診断に内視鏡検査を追加することは、企業と従業員の双方にとって大きなメリットがあります。ここでは、それぞれの立場からのメリットについて詳しく見ていきましょう。
企業側のメリット
企業にとって、従業員の健康管理は重要な経営課題の一つです。内視鏡検査を含む充実した健康診断を提供することで、以下のようなメリットが得られます。
まず、従業員の健康リスクを早期に発見し、適切な対応を取ることができます。消化器系疾患は初期段階では自覚症状がないことが多く、通常の健康診断では見つけにくいため、内視鏡検査による詳細なチェックが有効です。
また、従業員の健康管理を重視する姿勢は、企業イメージの向上にもつながります。健康経営が注目される現代において、従業員の健康に投資する企業は、社会的評価も高まる傾向にあります。
さらに、長期的には医療費の削減や生産性の向上にもつながります。疾患の早期発見・早期治療により、重症化を防ぎ、長期の休職や高額な治療費の発生を防ぐことができるのです。
従業員側のメリット
従業員にとっても、内視鏡検査を含む充実した健康診断を受けることには、多くのメリットがあります。
最も大きなメリットは、消化器系疾患の早期発見・早期治療が可能になることです。特に胃がんや大腸がんは、早期に発見すれば完治率が高く、治療の負担も少なくて済みます。
また、定期的な健康チェックにより、健康への意識が高まり、生活習慣の改善にもつながります。内視鏡検査の結果に基づいて、医師から適切な生活指導を受けることで、より健康的な生活を送ることができるようになります。
さらに、健康不安の軽減というメンタル面でのメリットも大きいです。詳細な検査を受け、「異常なし」という結果が得られれば、健康への不安が解消され、安心して仕事に取り組むことができます。
内視鏡検査は、一見すると負担に感じるかもしれませんが、現代の技術では鎮静剤の使用により、ほとんど苦痛を感じることなく受けることができます。健康という大切な資産を守るための投資として、積極的に検討する価値があります。
あなたの会社では、どのような健康診断を提供していますか?
まとめ:雇入れ時健康診断における内視鏡検査の重要性
雇入れ時健康診断に内視鏡検査を追加することの重要性について、ここまで詳しく解説してきました。最後に、ポイントをまとめておきましょう。
内視鏡検査は、消化器系疾患の早期発見・早期治療に非常に有効な検査方法です。特に胃がんや大腸がんは、日本人の死亡原因として上位を占める疾患であり、初期段階では自覚症状がほとんどないため、定期的な検査が重要となります。
雇入れ時健康診断に内視鏡検査を追加することで、企業は従業員の健康リスクを早期に発見し、適切な対応を取ることができます。また、従業員にとっても、消化器系疾患の早期発見・早期治療が可能になり、健康不安の軽減にもつながります。
内視鏡検査を提供する医療機関を選ぶ際には、専門性と経験豊富な医師の存在、最新の設備と技術の導入、患者さんの負担軽減への取り組み、アクセスの良さと予約のしやすさなどを考慮することが重要です。
当クリニックでは、消化器内科専門医による診察・検査を提供し、鎮静剤を使用した無痛の内視鏡検査や、経口・経鼻どちらの胃カメラも選択可能にするなど、患者さんの負担を軽減するための様々な取り組みを行っています。また、初診当日の検査対応や土曜日の検査実施など、患者さんの利便性も考慮したサービスを提供しています。
健康は何物にも代えがたい大切な資産です。定期的な健康チェックを通じて、自分自身の健康状態を把握し、早期に適切な対応を取ることが、健康寿命の延伸につながります。
雇入れ時健康診断に内視鏡検査を追加することを、ぜひ前向きに検討してみてください。あなたとあなたの大切な従業員の健康を守るための重要な一歩となるはずです。
消化器内科専門医として、皆様の健康をサポートできることを心より願っています。些細なことでも、お気軽に石川消化器内科・内視鏡クリニックにご相談ください。
大阪で健康診断に胃カメラを追加するメリットと選び方のコツ
健康診断に胃カメラを追加する重要性
健康診断は私たちの健康状態を把握するための大切な機会です。特に胃の健康は全身の健康に直結するため、見逃せません。
近年、胃がんは早期発見・早期治療が可能になってきていますが、初期症状が現れにくいという特徴があります。胃の不調を感じてから検査を受けるのでは、すでに病気が進行していることも少なくありません。
定期的な健康診断に胃カメラ検査を追加することで、症状が現れる前の早期段階で胃の異常を発見できる可能性が高まります。これは将来の健康リスクを大きく軽減することにつながるのです。
バリウム検査と胃カメラ検査の違い
健康診断で胃の検査といえば、バリウム検査と胃カメラ検査の2つが主流です。それぞれにどのような違いがあるのでしょうか。
バリウム検査は、バリウムという造影剤と発泡剤を飲み、レントゲンで撮影する検査方法です。胃の形状や動きを観察できる特徴があります。検査時間が約7〜8分と短く、健診車などでも実施できるため、企業の集団検診などで広く採用されています。
一方、胃カメラ検査は、口や鼻から細いカメラを挿入して胃の内部を直接観察する検査です。粘膜の色や微細な変化まで確認でき、必要に応じてその場で組織を採取(生検)することも可能です。検査時間は約15分程度で、バリウム検査よりも詳細な情報が得られます。
最大の違いは精度です。胃カメラは小さな病変や初期のがんも見逃しにくく、バリウム検査で異常が見つかった場合でも、最終的には胃カメラによる精密検査が必要になることが多いのです。

健康診断に胃カメラを追加するメリット
健康診断に胃カメラを追加することには、いくつもの重要なメリットがあります。
最大のメリットは高精度な診断が可能な点です。胃の内壁を直接観察できるため、小さな病変や初期のがんも見逃しにくくなります。胃カメラによる胃がん発見の精度は非常に高く、早期発見・早期治療につながります。
また、検査中にポリープなどが見つかった場合、その場で組織を採取して病理検査を行うことができます。これにより、追加の検査のために再度来院する手間が省けるのです。
さらに、最新の内視鏡技術を使用することで、通常では発見が難しい病変も確認できます。拡大内視鏡や特殊な光を使った観察により、より詳細な診断が可能になっています。
健康診断で「要精密検査」と判定された場合、結局は胃カメラを受けることになるケースが多いため、最初から胃カメラを選択することで、時間と費用の節約にもつながります。
あなたは胃の不調を感じたことはありませんか?
実は、胃の病気は初期症状がないまま進行することも少なくないのです。定期的な胃カメラ検査は、そんな「静かに進行する病気」の早期発見に大きく貢献します。
大阪で胃カメラ検査を受けるメリット
専門医による高度な検査
大阪には消化器内科専門医が多数在籍するクリニックが充実しています。専門医による検査は、一般の医師と比べて病変の見落としが少なく、より正確な診断が期待できます。
特に消化器内視鏡専門医が在籍するクリニックでは、最新の内視鏡技術を駆使した高精度な検査が可能です。拡大内視鏡や特殊光観察など、大学病院レベルの検査を受けられる施設も増えています。
医師が全ての診察、検査、結果説明まで一貫して担当するクリニックを選べば、より安心して検査を受けることができるでしょう。
最新設備による快適な検査
大阪市内の最新のクリニックでは、患者さんの負担を軽減するための工夫が施されています。鎮静剤を使用した「無痛胃カメラ」や、鼻から挿入する「経鼻胃カメラ」など、従来のイメージよりもずっと楽に検査を受けられる選択肢が広がっています。
半分眠ったような状態で検査を受けられる鎮静剤の使用は、「胃カメラは辛い・苦しい」というイメージを大きく変えています。実際に検査を受けた方からは「あっという間に終わった」「ほとんど記憶がない」といった声も多く聞かれます。
また、大阪市内の交通アクセスの良さも大きなメリットです。駅直結や駅近のクリニックも多く、忙しい方でも通院しやすい環境が整っています。
大阪で胃カメラ検査を選ぶ際のポイント
大阪で胃カメラ検査を受けるクリニックを選ぶ際には、いくつかの重要なポイントがあります。
専門医の在籍と経験
消化器内科専門医や内視鏡専門医が在籍しているかどうかは、最も重要なチェックポイントです。専門医資格を持つ医師は、高度な知識と技術を持ち、異常所見の発見率が高いとされています。
医師の経験も重要な要素です。内視鏡検査の経験が豊富な医師ほど、技術が洗練され、患者さんの負担も少なくなる傾向があります。クリニックのウェブサイトなどで医師のプロフィールを確認しておくとよいでしょう。
検査方法の選択肢
鎮静剤を使用した無痛胃カメラや、鼻から挿入する経鼻胃カメラなど、複数の検査方法から選択できるクリニックがおすすめです。自分の状態や希望に合わせて検査方法を選べることは大きなメリットになります。
特に胃カメラ検査が初めての方や、過去に辛い経験をした方は、鎮静剤を使用した検査が心理的な負担を軽減してくれるでしょう。
設備の充実度
最新の内視鏡機器を導入しているクリニックは、より精度の高い検査が期待できます。特に拡大内視鏡や特殊光観察ができる設備があれば、微小な病変も見逃しにくくなります。
また、CT検査や超音波検査なども院内で対応できる総合的な設備が整っていれば、胃以外の臓器も含めた総合的な健康チェックが可能になります。
アクセスと予約のしやすさ
立地条件も重要なポイントです。駅から近い場所にあるクリニックなら、検査当日の移動も楽になります。特に鎮静剤を使用する場合は、公共交通機関の利用が便利です。
予約方法も確認しておきましょう。電話予約だけでなく、ウェブ予約に対応しているクリニックなら、24時間いつでも予約が可能で便利です。また、土曜日や夜間の診療に対応しているクリニックは、平日忙しい方にとって大きなメリットになります。

こうしたポイントを総合的に検討して、自分に合ったクリニックを選ぶことが重要です。
石川消化器内科・内視鏡クリニックの特徴
大阪市城東区にある石川消化器内科・内視鏡クリニックは、消化器内科専門医である石川嶺院長が診察から検査、結果説明まですべてを担当する専門クリニックです。蒲生四丁目駅5番出口からすぐの好立地にあり、アクセスも抜群です。
当院の最大の特徴は、半分眠ったような状態で受けられる無痛の内視鏡検査です。鎮静剤を使用することで、痛みや恐怖をほとんど感じることなく検査を受けることができます。「辛い・苦しい」というイメージのある胃カメラ・大腸カメラ検査を「より気軽に」「よりスピーディーに」受けていただけるよう工夫しています。
経口・経鼻どちらの胃カメラも選択可能で、患者さんの状態や希望に合わせた検査方法を提案しています。特殊な光によって粘膜の微細な変化まで観察できる拡大内視鏡を導入しており、大学病院に劣らない高精度な検査を実現しています。
また、患者さんの利便性を重視し、初診当日の内視鏡検査や土曜日の検査にも対応しています。忙しい方でも予定を立てやすく、健康管理がしやすい環境を整えています。
院内にはCTと超音波エコーも完備しており、胃カメラ検査と合わせて肺がん検診や肝臓、胆嚢、膵臓の精査も可能です。胸部CTは胸部レントゲン同等の被ばく量で検査できる点も特徴的です。
健康診断や予防接種も実施しており、2024年6月からは子宮頸がんワクチン接種も開始しています。患者さんの健康管理を総合的にサポートする体制を整えています。
まとめ:健康診断に胃カメラを追加するメリットと選び方
健康診断に胃カメラ検査を追加することは、胃の病気の早期発見・早期治療につながる重要な選択です。特に症状が現れにくい初期の胃がんを発見するためには、定期的な胃カメラ検査が効果的です。
バリウム検査と比較して、胃カメラ検査は精度が高く、その場で組織採取も可能という大きなメリットがあります。近年は鎮静剤の使用や経鼻内視鏡の普及により、「辛い・苦しい」というイメージも大きく変わってきています。
大阪で胃カメラ検査を受けるクリニックを選ぶ際は、消化器内科専門医や内視鏡専門医の在籍、検査方法の選択肢、設備の充実度、アクセスと予約のしやすさなどを総合的に検討することが大切です。
健康は何物にも代えがたい大切な資産です。定期的な健康診断に胃カメラ検査を追加することで、より安心できる健康管理が実現できるでしょう。
胃の健康に不安がある方、定期的な健康管理をしっかり行いたい方は、ぜひ専門医による胃カメラ検査を検討してみてください。詳しい情報や予約については、石川消化器内科・内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。
内視鏡検査の不安を解消する7つのポイントと体験談
内視鏡検査への不安を抱える患者さんの声
「内視鏡検査は痛いんじゃないか」「検査中に吐き気が止まらなくなったらどうしよう」
私が消化器内科医として診療を行う中で、このような不安の声を日々耳にします。内視鏡検査は消化器疾患の早期発見・早期治療に欠かせない重要な検査です。しかし、多くの方が検査に対して強い不安や恐怖心を抱いているのが現実です。特に初めて検査を受ける方は、想像だけで恐怖が膨らんでしまうことも少なくありません。
実は、内視鏡検査に対する不安は、適切な知識と準備によって大きく軽減できるのです。当院では年間数千件の内視鏡検査を実施していますが、検査後に「思ったより全然楽だった」という感想をいただくことがほとんどです。

内視鏡検査に対する主な不安とその実態
内視鏡検査に対する不安には、いくつかの共通したものがあります。まずは、それらの不安と実際の状況を見ていきましょう。
最も多いのは「痛みや苦しさへの不安」です。口や鼻からカメラを挿入する胃カメラや、肛門から挿入する大腸カメラは、体の中に異物が入るという点で不安を感じるのは当然です。
次に多いのは「吐き気や嘔吐反射への不安」です。特に口から挿入する胃カメラでは、のどの奥に内視鏡が触れることで反射的に吐き気を催すことがあります。この反応は誰にでも起こりうるものですが、その強さには個人差があります。
また、「検査結果への不安」も見逃せません。「何か悪い病気が見つかったらどうしよう」という不安から検査自体を避けてしまう方もいらっしゃいます。
大腸内視鏡検査では特に「下剤の服用への不安」が大きいようです。検査前日からの食事制限に加え、当日は多量の下剤を飲む必要があるため、その準備に対する心理的ハードルが高いと感じる方が多いのです。
内視鏡検査の不安を解消する7つのポイント
では、これらの不安を解消するための具体的なポイントを7つご紹介します。
1. 鎮静剤の活用で検査中の苦痛を大幅に軽減
当院では、患者さんの希望に応じて鎮静剤を使用した「無痛内視鏡検査」を実施しています。鎮静剤を使用すると、半分眠ったような状態で検査を受けることができるため、痛みや恐怖をほとんど感じることなく検査が可能です。
「検査中に何も覚えていない」「あっという間に終わった」という感想をいただくことが多いです。鎮静剤の使用は、内視鏡検査への不安を解消する最も効果的な方法の一つと言えるでしょう。
ただし、鎮静剤の使用には注意点もあります。検査後しばらくは車の運転ができないため、公共交通機関を利用するか、ご家族に送迎をお願いする必要があります。
2. 経鼻内視鏡で嘔吐反射を軽減
口からではなく鼻から細い内視鏡を挿入する「経鼻内視鏡」も選択肢の一つです。経鼻内視鏡は喉の奥を通らないため、嘔吐反射が起こりにくく、検査中に会話もできるというメリットがあります。
経鼻内視鏡は口からの内視鏡に比べて細いため、挿入時の違和感が少ないと感じる方が多いです。ただし、鼻腔の構造によっては挿入が難しい場合や、鼻の痛みを感じることもあります。
3. 最新の内視鏡機器による検査時間の短縮
医療技術の進歩により、内視鏡機器も日々進化しています。当院では最新の拡大内視鏡を導入し、短時間で精度の高い検査を実現しています。
検査時間の短縮は患者さんの負担軽減に直結します。胃カメラであれば通常5〜10分程度、大腸カメラでも15〜30分程度で終了することがほとんどです。
最新の内視鏡機器は、特殊な光によって粘膜の微細な変化まで観察できるため、より早期に病変を発見することが可能になりました。これにより、検査の精度を落とすことなく、患者さんの負担を軽減できるのです。
4. 検査前の適切な説明と心理的準備
不安の多くは「未知のものへの恐怖」から生まれます。検査の流れや起こりうる感覚を事前に知っておくことで、心理的な準備ができ、不安が軽減されます。
当院では検査前のカウンセリングを丁寧に行い、患者さん一人ひとりの不安に寄り添うよう心がけています。質問には何でも答えますので、疑問点や不安なことがあれば、遠慮なくお尋ねください。

どうですか?検査に対する不安は少し和らぎましたか?
5. 大腸内視鏡検査前の下剤選択と服用方法の工夫
大腸内視鏡検査では、腸内をきれいにするための前処置が必要です。従来は大量の下剤を短時間で飲む必要がありましたが、最近では飲みやすい下剤も増えています。
当院では患者さんの状態に合わせて、錠剤タイプや少量高濃度タイプなど、様々な下剤を用意しています。また、下剤の服用方法も工夫することで、負担を軽減できます。例えば、冷やして飲む、レモン汁を加える、間隔を空けてゆっくり飲むなどの方法があります。
前処置は検査の精度に直結する重要なステップです。きちんと行うことで、検査がスムーズに進み、見落としのない正確な診断が可能になります。
6. 検査当日の環境づくりと心のケア
検査当日は、リラックスできる環境づくりも重要です。当院では、待合室から検査室まで、落ち着いた雰囲気を心がけています。
検査中は医師や看護師が常に声かけを行い、患者さんの状態に配慮します。少しでも苦しいと感じたら、遠慮なくお伝えください。検査を一時中断したり、姿勢を調整したりすることも可能です。
また、検査中にリラックスするためのコツとして、深呼吸を意識する、好きな景色や音楽を思い浮かべるなどの方法もあります。
7. 検査結果の丁寧な説明と今後のフォロー
内視鏡検査後は、結果について丁寧に説明することも重要です。当院では検査直後に、撮影した画像を見ながら所見を説明し、患者さんの疑問にお答えしています。
もし何らかの異常が見つかった場合でも、早期発見であれば治療の選択肢は広がります。不安に思われることがあれば、どんな小さなことでもご相談ください。
また、定期的な検査が必要な場合は、患者さんの生活スタイルに合わせた検査計画をご提案します。継続的なフォローアップで、健康を長く維持していただくことが私たちの願いです。
内視鏡検査を受ける際の準備と心構え
最後に、内視鏡検査を受ける際の準備と心構えについてお伝えします。
胃カメラ検査の準備
胃カメラ検査は、基本的に空腹状態で行います。検査当日の食事は控え、水やお茶などの水分も検査の2時間前までにしておきましょう。
また、血圧や心臓の薬を服用されている方は、少量の水で服用していただいて構いません。不安な場合は事前に医師にご相談ください。
当日は楽な服装でお越しいただくと良いでしょう。ネックレスやネクタイなど、首周りを締め付けるものは避けてください。
大腸カメラ検査の準備
大腸カメラ検査では、前日からの準備が必要です。検査前日の昼食までは普通に食べられますが、夕食は消化の良い「低脂肪・低繊維」の食事を摂り、夜8時頃までには済ませておきましょう。
検査当日は、指定された下剤を決められた時間に飲み、腸内をきれいにします。下剤の効果で何度もトイレに行く必要がありますので、検査当日は外出予定を入れないようにしましょう。
水分は下剤服用後も摂取できますが、検査の2時間前には控えてください。
まとめ:内視鏡検査は怖くない
内視鏡検査は、消化器疾患の早期発見・早期治療のために非常に重要な検査です。確かに不安や恐怖を感じる方も多いですが、現代の医療技術の進歩により、以前よりもずっと楽に受けられるようになっています。
鎮静剤の使用、経鼻内視鏡の選択、最新機器による検査時間の短縮など、患者さんの負担を軽減するための選択肢が増えています。また、検査前の丁寧な説明や心理的なサポートも、不安解消に大きく役立ちます。
当院では、患者さん一人ひとりの状態や希望に合わせた内視鏡検査を提供しています。「検査が怖い」「以前つらい思いをした」という方こそ、ぜひ一度ご相談ください。
健康維持のためには定期的な検査が大切です。内視鏡検査への不安を乗り越え、ご自身の健康を守るための第一歩を踏み出してみませんか?
詳しい情報や予約については、石川消化器内科・内視鏡クリニックのウェブサイトをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。皆様の健康維持のお手伝いができることを楽しみにしております。
粉瘤の治療は消化器内科でできる?専門医が教える正しい対処法
粉瘤とは?症状と特徴を理解しよう
皮膚の下にできる「しこり」に気づいて、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。特に「粉瘤(ふんりゅう)」は、日常診療でもよく遭遇する皮膚の良性腫瘍です。
粉瘤は、皮膚からはがれ落ちる垢(角質)や皮脂が、皮膚の内側にある袋状の構造物にたまってできた腫瘍(嚢腫)の総称です。医学的には「表皮嚢腫」とも呼ばれています。
年齢や性別に関係なく誰にでも発症する可能性があり、身体のどの部位にもできる可能性がありますが、特に顔や首、背中などに発生しやすい傾向があります。
粉瘤の特徴的な症状としては、数ミリから数センチ大のやや盛り上がったしこりとして触知でき、中央に黒点状の開口部(毛孔開口部、いわゆる「へそ」)が見られることが多いです。強く押すと、白色〜黄色のドロドロとした内容物が出てくることがあります。この内容物は角質や皮脂が主成分で、独特の臭いを伴うことも特徴です。
粉瘤自体は基本的に良性の腫瘍であり、がんなどの悪性腫瘍とは異なります。しかし、放置すると様々な問題が生じる可能性があるため、適切な対処が必要です。

粉瘤を放置するとどうなるのか?
「小さな粉瘤だから放置しても大丈夫だろう」と考える方も多いかもしれません。では、粉瘤を放置するとどのような経過をたどるのでしょうか?
粉瘤は自然に治癒することはほとんどなく、放置すると以下のような状態になる可能性があります。
徐々に大きくなる
粉瘤の中身である角質や皮脂は袋の外に自然には排出されないため、放置すると少しずつ大きくなっていきます。小さなものでも時間をかけて成長し、野球ボール大になることもあります。
大きくなった粉瘤は見た目の問題だけでなく、周囲の組織を圧迫することで痛みや不快感を引き起こすこともあります。特に肩や背中など、衣服や日常動作による刺激を受けやすい部位では、不快感が増す傾向にあります。
炎症を起こす可能性
粉瘤に炎症が生じると、表面が赤くなり、痛みを伴うようになります。これが「炎症性粉瘤」です。
炎症が進行すると、赤みが拡大し、痛みも強くなります。袋の内容物が膿(うみ)となり、触るとブヨブヨとした感触になることもあります。腫れが限界に達すると、粉瘤が破裂して臭いドロドロの内容物が排出されることもあります。
さらに厄介なのが細菌感染の合併です。細菌感染により炎症症状は悪化し、強い痛みや腫れが生じると、緊急の切開処置が必要になることもあります。
まれに悪性化することがある
粉瘤は基本的に良性腫瘍ですが、非常にまれなケースとして、経過が非常に長く、大きかったり、炎症を繰り返したりした場合に悪性化することがあります。
特に注意が必要なのは、中高年の男性の頭部、顔面、臀部にできた大きな粉瘤で、急速に大きくなったり、表面の皮膚に傷ができたりする場合です。
悪性化を防ぐためにも、小さなうちの早めの手術をおすすめします。
粉瘤は消化器内科で治療できるのか?
「粉瘤ができたけど、どの診療科を受診すればいいのだろう?」と迷われる方も多いでしょう。粉瘤は皮膚の疾患ですが、実際には複数の診療科で治療が可能です。
消化器内科医の立場からお話しすると、粉瘤の治療は基本的に外科的処置が必要となるため、従来は皮膚科や外科が主な受診先でした。しかし、近年では消化器内科クリニックでも粉瘤の日帰り手術に対応しているところが増えています。
消化器内科クリニックでの粉瘤治療のメリット
消化器内科、特に内視鏡検査を専門とするクリニックでは、日常的に様々な処置や小手術を行っているため、粉瘤の切除術にも対応できる医師が多くいます。当院のような消化器内科クリニックでも、粉瘤の日帰り手術を行っています。
消化器内科クリニックで粉瘤治療を受けるメリットとしては以下のような点が挙げられます:
- 内視鏡検査など他の消化器疾患の検査・治療と同時に対応できる
- 局所麻酔の技術が高く、痛みの少ない処置が期待できる
- 日帰り手術に慣れているため、効率的な治療が可能
- かかりつけ医として総合的な健康管理ができる
ただし、大きな粉瘤や複雑な症例の場合は、皮膚科や形成外科などの専門医への紹介が必要になることもあります。
粉瘤の適切な治療法とは?
粉瘤の治療法は、その大きさや状態、発生部位によって異なります。ここでは、主な治療法について解説します。
切開排膿(炎症時の応急処置)
炎症を起こして膿がたまってしまった炎症性粉瘤に対しては、まず切開排膿を行います。これは皮膚を切開して膿を出す処置で、痛みや腫れを軽減するための応急処置です。
ただし、切開排膿だけでは袋状の構造物(嚢胞壁)が残るため、炎症が落ち着いた後に改めて完全摘出の手術が必要になることが多いです。
完全摘出(根本的な治療)
粉瘤の根本的な治療は、袋状の構造物ごと完全に摘出する手術です。これにより再発を防ぐことができます。
手術方法には主に以下の2種類があります:
- 切開法:粉瘤の上の皮膚を切開し、袋状の構造物を丁寧に剥離して取り出す方法。確実に摘出できるため再発率が低いですが、傷跡がやや大きくなる傾向があります。
- くり抜き法:粉瘤の開口部を少し広げるか、小さな穴を開けて、そこから袋状の構造物をくり抜くように取り出す方法。傷跡が目立ちにくいメリットがありますが、完全に摘出できないと再発のリスクがあります。
どちらの手術方法を選択するかは、粉瘤の大きさや場所、患者さんの希望などを考慮して決定します。顔など目立つ部位では、傷跡が目立ちにくいくり抜き法が選ばれることが多いですが、大きな粉瘤の場合は切開法が必要になることもあります。
手術は局所麻酔で行い、通常は日帰りで受けることができます。手術時間は10〜30分程度で、術後1〜2週間程度で抜糸を行います。

粉瘤の治療費はいくらかかる?
粉瘤の治療費は、健康保険が適用されるため、比較的リーズナブルに受けることができます。具体的な費用は、粉瘤の大きさや場所、治療方法によって異なります。
保険適用の場合の治療費目安
粉瘤の手術は保険診療として認められており、3割負担の場合、一般的な費用の目安は以下のとおりです:
- 露出部(顔や首など)
- 2cm未満:約5,000〜6,000円
- 2〜4cm:約11,000〜12,000円
- 4cm以上:約13,000〜14,000円
- 非露出部(背中や臀部など)
- 3cm未満:約4,000〜5,000円
- 3〜6cm:約10,000〜11,000円
- 6cm以上:約12,000〜13,000円
1割負担(高齢者など)の場合は、上記の約3分の1の費用となります。また、初診料や再診料、処方薬がある場合はその費用が別途かかります。
なお、美容目的と判断された場合や保険適用外の特殊な処置を希望する場合は、自費診療となり費用が高くなることがあります。
粉瘤の予防と日常生活での注意点
粉瘤の発生を完全に予防する確実な方法はありませんが、日常生活での注意点をいくつかご紹介します。
清潔を保つ
粉瘤は不潔によって発生するわけではありませんが、皮膚を清潔に保つことで炎症のリスクを減らすことができます。特に汗をかきやすい部位は、こまめに洗い、清潔なタオルでよく拭きましょう。
早期発見・早期治療
小さなしこりを見つけたら、早めに医療機関を受診しましょう。粉瘤は小さいうちに治療すれば、手術も簡単で、傷跡も目立ちにくくなります。
自己処置は避ける
粉瘤を自分で潰したり、針で穴を開けたりする自己処置は、感染や炎症のリスクを高めるため、絶対に避けてください。また、内容物が出ても袋状の構造物が残っていれば再発します。
気になるしこりがある場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。
まとめ:粉瘤は適切な治療で解決できる
粉瘤は日常的によく見られる良性の皮膚腫瘍で、適切な治療を受ければ完治が期待できる疾患です。放置すると大きくなったり、炎症を起こしたりする可能性があるため、早めの治療をおすすめします。
消化器内科クリニックでも粉瘤の治療に対応しているところが増えており、当院のような消化器内科・内視鏡クリニックでも日帰り手術を行っています。他の消化器疾患の検査や治療と合わせて対応できるメリットもあります。
皮膚のしこりや腫れに気づいたら、まずはかかりつけ医に相談し、適切な診療科を紹介してもらうとよいでしょう。粉瘤かどうかの診断と、最適な治療法の提案を受けることができます。
健康な肌を保つためにも、気になる症状があれば早めに医療機関を受診することをおすすめします。
詳しい情報や治療についてのご相談は、石川消化器内科・内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。専門医による適切な診断と治療をご提供いたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
大腸カメラが痛い理由と痛みを軽減する最新アプローチ
大腸カメラ検査で痛みを感じる理由
大腸カメラ検査を受けた方から「出産より大変だった」「痛くて悲鳴を上げてしまった」という声を聞くことがあります。一方で「全く痛くなかった」「楽だった」という方もいらっしゃいます。なぜこのような違いが生じるのでしょうか。
大腸カメラ検査(正式には下部消化管内視鏡検査)は、大腸がんや大腸ポリープなどの早期発見に非常に有効な検査です。しかし、多くの方が痛みへの不安から検査を躊躇されています。
大腸カメラで痛みが生じる主な原因は、S状結腸と横行結腸の通過時に発生します。これらの部位は体内で固定されておらず、曲がりくねった形状をしているため、内視鏡を進めると腸に不要な圧力がかかり痛みが生じるのです。
また、検査中に腸の中に空気を入れて膨らませる必要があるため、腹部が過度に膨張することで痛みを感じることもあります。風船を過剰に膨らませるとパンパンになるのと同じ現象が、お腹の中で起きているのです。
痛みが出やすい方の特徴とは
大腸カメラ検査での痛みの感じ方には個人差がありますが、特に以下のような方は痛みを感じやすい傾向があります。
痩せている方や体が小さい方は、お腹の中で大腸が密に折りたたまれているため、連続するS字カーブが多くなります。そのため、内視鏡を進める際に腸に余計な力がかかりやすく、痛みを感じやすくなります。
- 便秘の方:腸が曲がりくねった状態になりやすく、内視鏡の挿入が難しくなります
- 過敏性腸症候群や炎症性腸疾患の方:腸の過敏性が上昇しており、通常より痛みを感じやすい状態です
- 腹部手術歴のある方:帝王切開や胃の手術などを受けた方は、腸が周囲の組織と癒着している可能性があり、内視鏡挿入時に痛みが生じやすくなります
また、検査前の緊張が強い場合や、検査そのものに過度に意識を向けすぎている方も、違和感を痛みとして強く感じる傾向があります。
さらに、検査前の腸管洗浄のために下剤を飲んだ後、何度も排便することで肛門がただれてしまい、内視鏡の挿入時に痛みを感じることもあります。これは検査そのものの痛みではありませんが、不快な体験として記憶に残りやすいものです。
痛みを軽減する最新の検査方法
大腸カメラ検査の痛みは、適切な方法と技術によって大幅に軽減することが可能です。当院では患者さんの負担を最小限にするため、以下のような最新アプローチを取り入れています。
鎮静剤を用いた無痛内視鏡検査
最も効果的な方法の一つが、鎮静剤を使用した「無痛内視鏡検査」です。鎮静剤を適切に使用することで、患者さんは半分眠ったような状態になり、検査中の痛みや不安をほとんど感じることなく検査を受けることができます。
当院では、患者さん一人ひとりの体質や状態に合わせて鎮静剤の種類や量を調整し、安全かつ快適な検査環境を提供しています。鎮静剤を使用した検査は「あっという間に終わった」という感想をいただくことが多いです。
適切な鎮静により、大腸カメラ検査は「辛い検査」から「気づいたら終わっていた検査」へと変わります。
なお、鎮静剤を使用する場合は、検査当日の車の運転はできませんので、ご家族の送迎や公共交通機関のご利用をお願いしています。

炭酸ガス送気による腹部膨満感の軽減
従来の大腸カメラ検査では、腸内を観察しやすくするために空気を送り込んでいましたが、空気は体内に長時間残りやすく、検査後も腹部膨満感や痛みの原因となっていました。
最新の内視鏡システムでは、空気の代わりに炭酸ガスを使用することで、この問題を大幅に改善しています。炭酸ガスは体内で速やかに吸収され排出されるため、検査中・検査後の腹部膨満感や痛みを軽減できます。
軸保持短縮法による痛みの少ない挿入テクニック
内視鏡医の技術も、検査の痛みを左右する重要な要素です。当院では「軸保持短縮法」と呼ばれる挿入テクニックを採用しています。これは、腸の形状に合わせて内視鏡を操作し、腸に余計な力がかからないようにする方法です。
曲がりくねった腸を直線化しながら内視鏡を進めることで、腸への負担を最小限に抑え、痛みを軽減します。この技術の習得には経験が必要ですが、当院の医師は豊富な経験と高い技術を持ち、患者さんに優しい検査を心がけています。
あなたはどうですか?大腸カメラ検査の経験はありますか?
検査前の準備と心構えで痛みを軽減
大腸カメラ検査の痛みを軽減するためには、検査前の適切な準備と心構えも重要です。以下のポイントを意識することで、より快適な検査体験につながります。
効果的な腸管洗浄で検査をスムーズに
大腸カメラ検査では、腸内をきれいに洗浄するために下剤を飲む必要があります。従来は2リットルもの下剤を飲む必要がありましたが、最新の腸管洗浄剤では量が大幅に減少し、約720mlで済むようになりました。
当院では、患者さんの負担を考慮し、最小限の下剤で効果的な腸管洗浄ができるよう工夫しています。腸がきれいに洗浄されていると、内視鏡の挿入がスムーズになり、検査時間の短縮や痛みの軽減につながります。
リラックスした状態で検査に臨む
検査前の緊張や不安は、痛みの感じ方に大きく影響します。緊張すると筋肉が硬くなり、内視鏡挿入時の痛みが増強する傾向があります。
検査前にはリラックスするよう心がけ、深呼吸などでリラクゼーションを図ることも効果的です。また、検査中は医師や看護師の指示に従い、適切なタイミングで息を吐いたり吸ったりすることで、痛みを軽減できることもあります。
当院では検査前に十分な説明を行い、患者さんの不安や疑問にお答えすることで、リラックスした状態で検査に臨めるよう配慮しています。
当院の大腸カメラ検査の特徴
石川消化器内科・内視鏡クリニックでは、「辛い・苦しい」というイメージのある大腸カメラ検査を、「より気軽に」「よりスピーディーに」、そして安心して受けていただけるよう様々な工夫を行っています。
消化器専門医による高精度な検査
当院では、消化器内科専門医である院長が診察から検査、結果説明まですべてを担当しています。特に内視鏡検査においては、30年以上の豊富な経験と高い専門性を活かし、確かな技術で痛みの少ない検査を実現しています。
また、特殊な光によって粘膜の微細な変化まで観察できる拡大内視鏡を導入し、大学病院に劣らない高精度な検査を提供しています。これにより、早期がんやポリープの発見率を高め、見逃しのない検査を心がけています。
患者さんの負担を考慮した検査環境
当院では患者さんの利便性を重視し、初診当日の内視鏡検査や土曜日の検査にも対応しています。お忙しい方でも、ご自身の都合に合わせて検査を受けていただけます。
また、待ち時間と滞在時間を大幅に削減する工夫を行い、患者さんの負担を最小限に抑えています。電話予約とWEB予約の両方に対応し、アプリ決済、クレジットカード、電子決済も利用可能です。
大腸カメラ検査に対する不安や疑問はありませんか?

大腸カメラ検査を受けるべきタイミング
大腸カメラ検査は、どのようなタイミングで受けるべきなのでしょうか。以下のような症状や状況がある場合は、検査を検討する良いタイミングです。
- 便に血が混じる(血便・下血):大腸がんの代表的な症状です
- 便秘と下痢を繰り返す:腸の状態に変化が生じている可能性があります
- 腹痛が続く:様々な消化器疾患のサインかもしれません
- 便潜血検査で陽性:健康診断で便潜血検査が陽性の場合は、精密検査として大腸カメラを受けることが推奨されています
- 大腸がんの家族歴がある:大腸がんリスクが高まるため、定期的な検査が重要です
- 40歳以上の方:特に症状がなくても、40歳を過ぎたら一度は大腸カメラ検査を受けることをお勧めします
これらの症状は、痔などの良性疾患でも起こりうるものですが、自己判断せずに医療機関を受診することが大切です。早期発見・早期治療が可能な大腸がんは、適切な時期に検査を受けることで予後が大きく改善します。
まとめ:痛みを恐れず大腸カメラ検査を受けましょう
大腸カメラ検査は、大腸がんやポリープの早期発見に非常に有効な検査です。検査時の痛みが心配で躊躇される方も多いですが、現在では様々な工夫や技術の進歩により、痛みを最小限に抑えた検査が可能になっています。
鎮静剤を用いた無痛内視鏡検査、炭酸ガス送気による腹部膨満感の軽減、熟練した医師による軸保持短縮法など、痛みを軽減するための方法は着実に進化しています。また、最新の腸管洗浄剤の導入により、検査前の準備も以前より格段に楽になりました。
当院では消化器専門医による高精度な検査と、患者さん一人ひとりに配慮した検査環境を提供しています。大腸カメラ検査に対する不安や疑問がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
大腸がんは早期発見・早期治療が何より重要です。痛みへの不安から検査を先延ばしにするのではなく、最新の無痛検査を利用して、ぜひ定期的な検査を心がけましょう。
詳しい情報や予約については、石川消化器内科・内視鏡クリニックまでお問い合わせください。経験豊富な医師と専門スタッフが、皆様の健康をサポートいたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
大腸ポリープ切除は日帰りで安全に~最新治療の実際
大腸ポリープ切除の日帰り治療とは
大腸ポリープは大腸の粘膜に発生する盛り上がりで、多くは良性ですが放置すると一部が大腸がんへと進行する可能性があります。そのため、早期発見・早期治療が非常に重要です。
大腸ポリープ切除は、かつては1〜2泊の入院が必要でした。しかし近年の内視鏡技術の進歩により、多くのケースで日帰り治療が可能になっています。
当院では、消化器内科専門医による安全な日帰りポリープ切除を提供しています。鎮静剤を使用した「無痛内視鏡検査」で患者さんの負担を最小限に抑えながら、高度な専門技術で治療を行います。
「大腸ポリープの切除は痛いのでは?」「日帰りで本当に安全なの?」といった不安をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、大腸ポリープ切除の日帰り治療について、その安全性や実際の流れ、メリットなどを詳しく解説します。
大腸ポリープとは?がん化するリスクについて
大腸ポリープとは、大腸の粘膜にできる隆起性の病変です。大きく分けて「腫瘍性ポリープ」と「非腫瘍性ポリープ」の2種類があります。
腫瘍性ポリープの代表は「腺腫」と呼ばれるもので、大腸ポリープの8割以上を占めます。この腺腫は、将来的に大腸がんに進展するリスクを持っています。つまり、「がんの芽」とも言えるわけです。
非腫瘍性ポリープには過形成性ポリープや炎症性ポリープなどがありますが、これらは基本的に良性で、がん化する可能性は低いとされています。
大腸ポリープのがん化リスクは、大きさと密接な関係があります。5mm以下の小さなポリープでがんが含まれる可能性は0.6%程度ですが、20mmを超えると35.8%にまで上昇します。
また、ポリープの形状や表面の性状によってもリスクは変わります。平たく広がるタイプや表面が不整なものは、がん化のリスクが高い傾向があります。
便潜血検査で陽性となった方の30〜50%に大腸腺腫が見つかるとも言われています。そのため、便潜血検査で陽性となった場合は、必ず大腸内視鏡検査を受けることが推奨されます。
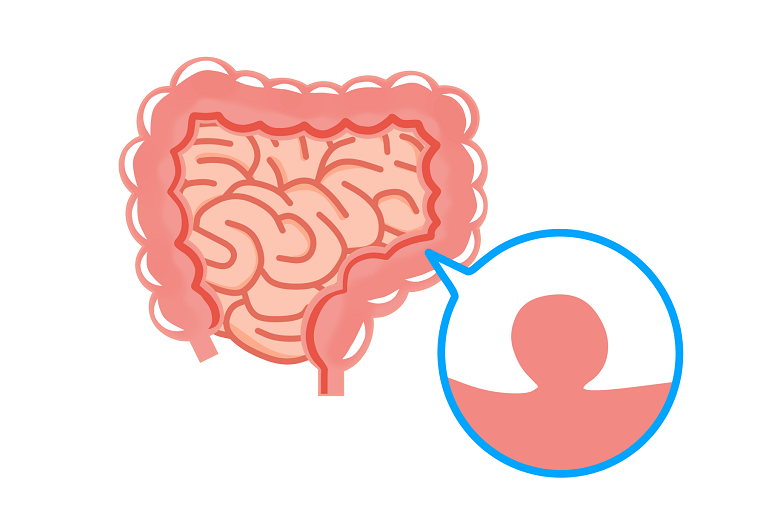
大腸がんの多くはこのポリープを経て発生するため、ポリープの段階で発見して切除することが、大腸がん予防の最も効果的な方法なのです。
日帰り大腸ポリープ切除の安全性
「大腸ポリープの切除は入院が必要なのでは?」と思われる方も多いでしょう。かつては1〜2泊の入院が一般的でした。これは、切除後の出血や穿孔(腸に穴があくこと)などの合併症に対応するためでした。
しかし、内視鏡技術の進歩や高周波装置の安全性向上により、現在では多くの医療機関で日帰り治療が行われるようになっています。
日帰り治療の安全性を担保する要素として、以下の点が重要です。
- 消化器内科専門医・内視鏡専門医による施術
- 高性能な内視鏡システムと安全性の高い高周波装置の使用
- ポリープの性状や大きさを的確に判断する技術
- 切除後の出血予防処置(クリップによる止血など)
- 術後の適切なフォローアップ体制
当院では、消化器内科専門医である私が全ての診察・検査・治療を担当し、安全性を最優先に考えた治療を提供しています。

ただし、すべてのポリープが日帰りで切除できるわけではありません。大きさが20mmを超えるもの、がんが疑われるもの、平坦型で粘膜下層に入り込んでいるものなどは、入院治療が必要な場合があります。
また、抗血栓薬(血液をサラサラにする薬)を服用中の方は、出血リスクが高まるため、主治医と相談のうえで服薬調整が必要になることもあります。
日帰り治療の合併症発生率は非常に低く、術後出血は約1%(数百例に1例程度)、穿孔はさらに稀で数千例に1例程度とされています。
どうですか?意外と安全だと感じませんか?
適切な医療機関で、経験豊富な専門医による施術を受ければ、日帰りでも十分安全に大腸ポリープ切除を受けることができるのです。
大腸ポリープ切除の具体的な方法
大腸ポリープの切除方法は、ポリープの大きさや形状によって異なります。主な切除方法には以下のようなものがあります。
ポリペクトミー(ホットポリペクトミー)
茎のあるキノコ状のポリープに対して行われる最も一般的な方法です。スネアと呼ばれる金属の輪をポリープの茎に掛け、高周波電流を流して焼き切ります。
切除と同時に止血効果もあるため、切除直後の出血は少ないというメリットがあります。ただし、熱による組織障害が強くなると、後出血や穿孔のリスクが高まることがあります。
コールドポリペクトミー
近年普及している方法で、高周波電流を使わずにスネアでポリープを締め付けて切除します。熱による組織障害がないため、後出血や穿孔のリスクが非常に低いとされています。
切除直後は出血することがありますが、多くの場合は2〜3分程度で自然に止まります。5〜10mm程度の小さなポリープに適した方法です。
内視鏡的粘膜切除術(EMR)
平坦なポリープや大きめのポリープに対して行われる方法です。ポリープの下に生理食塩水などを注入して粘膜を持ち上げ(粘膜下層に液体を注入)、その後スネアで切除します。
粘膜下層に液体を注入することで、筋層との間に空間ができ、穿孔のリスクを低減できます。また、病変を持ち上げることで、より確実に切除することが可能になります。
最近では「underwater法」という水中で病変を切除する方法も増えています。これは腸管内を水で満たした状態で切除を行うもので、より安全に切除できるとされています。
当院では、ポリープの性状や大きさに応じて最適な切除方法を選択しています。特に小さなポリープに対しては、安全性の高いコールドポリペクトミーを積極的に取り入れています。
日帰り大腸ポリープ切除の流れ
日帰りでの大腸ポリープ切除は、基本的に大腸内視鏡検査と同日に行われます。その一般的な流れをご紹介します。
検査前の準備
大腸内視鏡検査を受けるためには、腸内をきれいにする「腸管洗浄」が必要です。前日から食事制限を行い、検査当日は腸管洗浄剤を服用します。
腸管洗浄が不十分だと、ポリープの見落としや安全な切除ができない可能性があるため、この準備は非常に重要です。
検査・治療
検査当日は、まず問診や血圧測定などを行います。その後、鎮静剤を使用した「無痛内視鏡検査」を行います。
鎮静剤により、半分眠ったような状態で検査を受けることができるため、痛みや恐怖をほとんど感じることなく検査を受けることができます。
検査中にポリープが発見された場合、その場で切除を行います。切除にかかる時間は、ポリープの数や大きさにもよりますが、通常20〜30分程度です。
術後の経過観察
治療後は、リカバリールームで1〜2時間程度の経過観察を行います。鎮静剤の効果が切れ、体調に問題がないことを確認できれば帰宅可能です。
切除したポリープは病理検査に提出され、1〜2週間後に結果が出ます。結果については後日の診察で説明します。
日帰り治療とはいえ、あくまでも「手術」です。帰宅後も安静にし、激しい運動や飲酒は1週間程度控えていただきます。
日帰り大腸ポリープ切除のメリット
日帰りでの大腸ポリープ切除には、以下のようなメリットがあります。
- 入院の必要がなく、時間的負担が少ない
- 入院費がかからないため、経済的負担が軽減される
- 自宅で過ごせるためリラックスできる
- 社会生活への影響が最小限に抑えられる
- 検査から治療までワンストップで完結する
特に忙しい方や入院に抵抗がある方にとって、日帰り治療は大きなメリットとなります。
また、大腸ポリープを早期に切除することで、大腸がんの予防につながります。大腸がんは早期発見・早期治療が可能ながんの一つであり、ポリープの段階で切除することで、がんになるリスクを大幅に減らすことができます。
便潜血検査で陽性となった方や、大腸がんの家族歴がある方、40歳以上の方は特に定期的な大腸内視鏡検査をお勧めします。
大腸ポリープ切除後の注意点
大腸ポリープ切除後は、傷口が完全に治癒するまで約3週間かかります。その間は以下の点に注意が必要です。
食事について
術後1週間程度は消化の良い食事を心がけましょう。刺激物や脂っこいもの、アルコールは控えてください。また、水分は普段より多めに摂取することをお勧めします。

運動・入浴について
術当日の運動は厳禁です。翌日からは軽い散歩程度は可能ですが、激しい運動や腹圧がかかる動作(重い物を持つなど)は1週間程度控えましょう。
入浴は翌日からシャワー程度なら可能ですが、湯船につかるのは1週間後からにしましょう。
注意すべき症状
以下のような症状が現れた場合は、すぐに医療機関に連絡してください。
- 大量の血便(便全体が真っ赤になるような出血)
- 強い腹痛
- 発熱
- 腹部の張り
少量の出血(便に血が混じる程度)は、切除後によく見られる症状で、多くの場合は自然に止まります。心配な場合は医師に相談しましょう。
術後出血のほとんどは切除後2〜3日以内に起こり、1週間を過ぎると出血のリスクは限りなくゼロに近づきます。
まとめ:安心して受けられる日帰り大腸ポリープ切除
大腸ポリープは放置すると一部が大腸がんに進展する可能性があるため、早期発見・早期治療が重要です。現在の内視鏡技術の進歩により、多くのポリープは日帰りで安全に切除することが可能になっています。
日帰り治療のメリットは、入院の必要がなく時間的・経済的負担が少ないことです。また、検査から治療までワンストップで完結するため、患者さんの負担を最小限に抑えることができます。
当院では、消化器内科専門医による安全な日帰りポリープ切除を提供しています。鎮静剤を使用した「無痛内視鏡検査」で患者さんの負担を最小限に抑えながら、高度な専門技術で治療を行います。
大腸ポリープが心配な方、便潜血検査で陽性となった方、大腸がんの家族歴がある方は、ぜひ一度消化器内科専門医にご相談ください。
安全で快適な内視鏡検査と、必要に応じた日帰りポリープ切除で、大腸がんの予防に努めましょう。
詳しい情報や検査のご予約は、石川消化器内科・内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
胃がんリスクを早期発見する最新検査法と予防戦略
胃がんの現状と早期発見の重要性
胃がんは日本人にとって身近な疾患の一つです。以前は日本人の死因の上位を占めていましたが、食生活の変化やピロリ菌感染率の低下などにより、近年は減少傾向にあります。しかし、依然として多くの方が罹患する疾患であることに変わりはありません。
胃がんの最大の特徴は、初期段階ではほとんど症状が現れないことです。進行してから胃痛や食欲不振、体重減少などの症状が出てくることが多く、その時点では治療が難しくなっていることもあります。だからこそ、定期的な検査による早期発見が非常に重要なのです。
早期に発見できれば、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)などの低侵襲治療で完治できる可能性が高まります。一方、進行がんになると胃の切除など大きな手術が必要になり、術後の生活の質にも影響します。
私が日々の診療で実感するのは、胃がんの早期発見には「定期的な検査」と「リスク要因の把握」が欠かせないということです。特に40歳を過ぎたら、症状がなくても定期的な胃の検査を受けることをお勧めします。
胃がんのリスク要因と自己チェックポイント
胃がん発症には様々なリスク要因が関わっています。最も重要なのはヘリコバクター・ピロリ菌(以下、ピロリ菌)の感染です。ピロリ菌は胃の粘膜に炎症を引き起こし、長期間にわたって感染が続くと胃がんのリスクが高まります。
日本人は特に東アジア型のピロリ菌に感染していることが多く、このタイプは発がん率が高いことが知られています。ピロリ菌感染は、主に幼少期に汚染された水や食物を通じて起こります。
また、塩分の多い食事や喫煙、過度の飲酒も胃がんのリスクを高める要因です。特に塩蔵食品や高塩分食品の摂取は胃の粘膜に負担をかけ、発がんリスクを上昇させます。

胃がんの家族歴も重要なリスク要因です。親や兄弟に胃がんの方がいる場合は、一般の方よりもリスクが高くなります。これは遺伝的要因とともに、家族間で似た生活習慣や食習慣を共有していることも関係しています。
自己チェックポイントとしては、以下のような症状が続く場合は注意が必要です。
- みぞおち付近の痛みや不快感が続く
- 食欲不振や吐き気が続く
- 原因不明の体重減少がある
- 食後のもたれ感や胸やけが頻繁にある
- 貧血の症状がある
これらの症状が見られる場合は、早めに消化器内科を受診することをお勧めします。ただし、初期の胃がんではこれらの症状がほとんど現れないことも多いため、リスク要因がある方は症状がなくても定期検査を受けることが大切です。
最新の胃がん検査法とその特徴
内視鏡検査(胃カメラ)の進化
胃がん検査の基本となるのは内視鏡検査(胃カメラ)です。近年の内視鏡技術の進歩は目覚ましく、従来よりも高精細な画像で胃の粘膜の微細な変化を観察できるようになりました。
特に拡大内視鏡は、粘膜の微細な変化まで観察できる特殊な光を使用しており、早期胃がんの発見率を大幅に向上させています。当院でも導入している拡大内視鏡は、大学病院に劣らない高精度な検査を可能にしています。
また、以前は「辛い・苦しい」というイメージが強かった胃カメラ検査ですが、現在は鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査が普及しています。半分眠ったような状態で検査を受けられるため、痛みや恐怖をほとんど感じることなく検査を受けることができます。
さらに、経鼻内視鏡も選択肢の一つです。口からではなく鼻から細い内視鏡を挿入する方法で、嘔吐反射の少ない検査が可能です。患者さんの状態や希望に応じて、経口・経鼻のどちらかを選択できるクリニックも増えています。
胃がんリスク検査(ABC検診)
胃がんリスク検査(ABC検診)は、血液検査でピロリ菌感染の有無と胃粘膜の萎縮度を調べる検査です。ピロリ菌抗体と血清ペプシノゲン値を測定し、A〜D群の4つのグループに分類します。
A群(ピロリ菌陰性・萎縮なし)は胃がんリスクが最も低く、D群(ピロリ菌陰性・萎縮あり)は最もリスクが高いとされています。この検査は簡便で侵襲性が低く、胃がんのリスク評価に有用です。
ただし、ABC検診はあくまでリスク評価であり、胃がんの有無を直接診断するものではありません。リスクが高いと判定された場合は、内視鏡検査による精密検査が必要です。
CT検査と超音波検査
CT検査は胃の壁の肥厚や周囲のリンパ節腫大、遠隔転移の有無などを評価するのに有用です。当院では胸部CTを導入しており、胸部レントゲン同等の被ばく量で検査が可能です。
超音波検査(エコー)は胃の壁の肥厚や周囲のリンパ節腫大を評価するのに役立ちます。CT検査と比べて被ばくがなく、繰り返し検査が可能という利点があります。
これらの検査は内視鏡検査を補完するものとして用いられることが多く、胃がんの進行度や転移の有無を評価する際に重要な役割を果たします。

ピロリ菌検査と除菌治療の最新動向
ピロリ菌は胃がんの最大のリスク要因であり、その検査と除菌治療は胃がん予防の中心的な戦略となっています。ピロリ菌検査には様々な方法がありますが、主に以下の検査が一般的です。
- 血液検査(抗体検査):過去のピロリ菌感染の有無を調べる
- 尿素呼気試験:現在の活動性のあるピロリ菌感染を調べる
- 便中抗原検査:便からピロリ菌の抗原を検出する
- 内視鏡検査による組織生検:胃粘膜の一部を採取して検査する
これらの検査で陽性と判定された場合、除菌治療が推奨されます。除菌治療は通常、プロトンポンプ阻害剤(PPI)と2種類の抗生物質を組み合わせた三剤併用療法が標準的です。一次除菌で成功しない場合は、抗生物質を変更した二次除菌が行われます。
ピロリ菌の除菌治療は胃がんリスクを確実に低減することが科学的に証明されています。国際がん研究機関(IARC)のワーキンググループは、ピロリ菌除菌による胃がん予防効果を認めており、特に早期の段階で除菌を行うことでその効果が高まるとしています。
日本では2013年から慢性胃炎に対するピロリ菌除菌治療が保険適用となり、多くの方が除菌治療を受けられるようになりました。これにより、将来的な胃がん発症率の低下が期待されています。
ただし、ピロリ菌除菌後も定期的な胃の検査は必要です。除菌によってリスクは低下しますが、完全になくなるわけではないからです。特に、長期間のピロリ菌感染によって胃粘膜の萎縮が進んでいる場合は、除菌後も定期的な内視鏡検査が推奨されます。
胃がん予防のための生活習慣改善
食生活の見直し
胃がん予防には食生活の見直しが重要です。特に注意すべきは塩分摂取量です。塩蔵食品や高塩分食品の過剰摂取は胃がんリスクを高めることが知られています。具体的には、塩辛や漬物、加工肉などの摂取を控えめにし、調理の際の塩分も減らすよう心がけましょう。
反対に、新鮮な野菜や果物には抗酸化物質が豊富に含まれており、胃がん予防に効果があるとされています。特に緑黄色野菜や柑橘類などを積極的に摂取することをお勧めします。
また、熱すぎる飲食物も胃の粘膜にダメージを与え、発がんリスクを高める可能性があります。食べ物や飲み物は適度に冷ましてから摂取するようにしましょう。
禁煙と適度な飲酒
喫煙は胃がんを含む多くのがんのリスク要因です。タバコに含まれる発がん物質が血液を通じて胃に達し、粘膜にダメージを与えます。喫煙者は非喫煙者に比べて胃がんリスクが約1.5倍高いとされています。
飲酒も胃がんリスクを高める要因の一つです。特に大量の飲酒は胃粘膜に直接的なダメージを与えるだけでなく、ピロリ菌感染との相乗効果でリスクを高める可能性があります。飲酒は控えめにし、休肝日を設けることが望ましいでしょう。
定期的な運動と適正体重の維持
定期的な運動は全身の血流を改善し、免疫機能を高める効果があります。これにより、がん細胞の発生を抑制する効果が期待できます。特に有酸素運動は、全身の代謝を活性化させるため効果的です。

また、肥満は様々ながんのリスク要因となることが知られています。適正体重を維持することで、胃がんを含む多くのがんリスクを低減できる可能性があります。
定期検診の重要性と受診のタイミング
胃がんの早期発見には定期的な検診が欠かせません。日本では40歳以上の方を対象に、胃がん検診が実施されています。検診方法には主に胃部X線検査(バリウム検査)と胃内視鏡検査(胃カメラ)があります。
特に50歳以上の方は、胃がん発症リスクが高まる年代であるため、より積極的な検診が推奨されます。多くの自治体では50歳以上の方を対象に、2年に1回の胃内視鏡検査を推奨しています。
また、ピロリ菌感染者や胃がんの家族歴がある方、慢性胃炎や胃ポリープなどの既往がある方は、より頻繁な検査が必要な場合があります。このような方は、消化器内科医と相談の上、適切な検査間隔を決めることをお勧めします。
検診のタイミングとしては、症状がなくても定期的に受けることが大切です。胃がんは初期段階では症状がほとんどないため、症状が出てから検査を受けるのでは遅いことがあります。
当院では初診当日の内視鏡検査や土曜日の検査にも対応しており、お忙しい方でも検査を受けやすい環境を整えています。また、鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査を提供しているため、検査への不安や恐怖感を最小限に抑えることができます。
まとめ:胃がん対策の総合戦略
胃がんは早期発見・早期治療が可能ながんの一つです。特に日本では検診体制が整っており、適切に検診を受けることで早期発見の可能性が高まります。
胃がん対策の総合戦略としては、以下のポイントが重要です。
- ピロリ菌検査と除菌治療:胃がんリスクの最大要因であるピロリ菌の検査と除菌を行う
- 定期的な胃の検査:症状がなくても定期的に内視鏡検査などを受ける
- 生活習慣の改善:塩分控えめの食事、禁煙、適度な飲酒、定期的な運動を心がける
- 早期の受診:気になる症状があれば早めに消化器内科を受診する
胃がんは決して恐れるべき病気ではなく、適切な予防と早期発見によって克服できる疾患です。特に近年の内視鏡技術の進歩により、より早期の段階で発見できるようになっています。
当院では消化器内科専門医として、胃がんの早期発見と予防に力を入れています。無痛内視鏡検査や拡大内視鏡による高精度な検査を提供し、患者さんの健康管理をサポートしています。
胃の調子が気になる方、胃がんリスクが心配な方は、ぜひ一度消化器内科専門医に相談してみてください。早期発見・早期治療が、胃がんから身を守る最大の武器です。
詳しい検査内容や予約方法については、石川消化器内科・内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。皆様の健康を誠心誠意サポートいたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
消化器疾患を自分で見つける8つのセルフチェック法
消化器疾患のセルフチェックが重要な理由
消化器疾患は、初期段階では自覚症状が乏しいことが特徴です。気づいた時には進行していることも少なくありません。私が日々の診療で感じるのは、早期発見の重要性です。
消化器内科医として20年以上診療に携わってきましたが、「もう少し早く来院していれば」と思うケースが少なくありません。特に40代以降の方々は、定期的なセルフチェックを習慣にすることをお勧めします。
日本人の死因の上位には、胃がんや大腸がんなどの消化器がんが含まれています。これらは早期発見できれば治療効果が高い疾患です。自分の体調変化に敏感になり、適切なタイミングで医療機関を受診することが健康寿命を延ばす鍵となります。
今回は、ご自宅で簡単にできる消化器疾患のセルフチェック法を8つご紹介します。これらは日常生活の中で定期的に行うことで、異変を早期に発見するための助けになります。
セルフチェック1:お腹の張りと早期満腹感
食事の際に、いつもより少量でお腹がいっぱいになる感覚はありませんか?
これは「早期飽満感」と呼ばれる症状で、機能性ディスペプシアや胃の病気のサインかもしれません。特に、食事量が変わっていないのに、急に満腹感を感じるようになった場合は注意が必要です。また、食後にお腹が異常に張る感覚も重要なチェックポイントです。
私の臨床経験では、こうした症状を3ヶ月以上継続して感じている患者さんの中に、胃炎や胃潰瘍、まれに胃がんが見つかるケースがあります。特に50歳以上の方は、この症状が続く場合、一度消化器内科を受診されることをお勧めします。

早期飽満感のセルフチェック方法
1週間ほど、食事の量と満腹感を記録してみましょう。以前と比べて明らかに少ない量で満腹を感じる場合は、消化器系に何らかの変化が生じている可能性があります。
また、食後のお腹の張りが日常生活に支障をきたすほど強い場合や、横になると楽になる場合も要注意です。こうした症状は、単なる食べ過ぎではなく、消化器官の機能低下や炎症を示唆していることがあります。
セルフチェック2:胸やけと逆流感
食後に胸やけや酸っぱい液体が喉まで上がってくる感覚はありませんか?
これらは逆流性食道炎の典型的な症状です。日本人の約10〜15%が経験するといわれる一般的な消化器疾患ですが、長期間放置すると食道粘膜のダメージが蓄積し、まれに食道がんのリスク因子となることもあります。
私が診察する患者さんの中には、「胸やけは歳のせい」と何年も放置されてきた方がいらっしゃいます。しかし、週に2回以上の胸やけは正常ではありません。適切な治療で症状を軽減できるケースがほとんどです。
胸やけセルフチェックの方法
夕食後、横になった時に胸やけを感じるかどうかを確認しましょう。また、コーヒーや柑橘系の果物、脂っこい食事の後に症状が悪化するかもチェックポイントです。
胸やけと同時に、咳や喉の違和感、声のかすれなどがある場合は、胃酸が食道だけでなく喉にまで逆流している可能性があります。こうした症状が1ヶ月以上続く場合は、消化器内科の受診をお勧めします。
セルフチェック3:便の性状変化
便の形や色、出る頻度は健康状態を映す鏡です。
便秘と下痢を繰り返す、便が細くなった、色が黒っぽくなった、粘液や血液が混じるようになったなどの変化は、腸の状態に異変が生じているサインかもしれません。特に40代以降の方で、こうした変化が2週間以上続く場合は注意が必要です。
便の性状変化を見逃さなかったことで、大腸ポリープや初期の大腸がんを発見できたケースが少なくありません。自分の便の状態に関心を持つことは、恥ずかしいことではなく、健康管理の重要な一部なのです。
便の性状チェックポイント
理想的な便は、バナナ状でなめらかな表面を持ち、トイレットペーパーにあまり付着せず、排便時に強い力みを必要としないものです。
特に注意すべき変化は、黒い便や血便、白っぽい便、極端に細い便、強いにおいを伴う下痢などです。これらは消化管出血や胆道系の問題、腸閉塞の初期症状である可能性があります。
セルフチェック4:腹痛の特徴と位置
腹痛はさまざまな消化器疾患の共通症状ですが、その特徴や位置から原因を推測できることがあります。
みぞおちの痛みは胃や十二指腸、右上腹部の痛みは胆嚢や肝臓、左下腹部の痛みは大腸の問題を示唆していることが多いです。また、食事との関連性も重要なヒントになります。
空腹時に痛みが強まる場合は胃潰瘍や十二指腸潰瘍、食後に痛みが出る場合は胆石や膵臓の問題の可能性があります。痛みの性質(鈍痛、刺すような痛み、けいれんのような痛みなど)も診断の手がかりとなります。
腹痛のセルフチェック方法
腹痛を感じたら、以下の点に注目して記録してみましょう。
- 痛みの場所(右上、左上、右下、左下、中央など)
- 痛みの性質(鈍い、鋭い、波のように来るなど)
- 食事との関連(食前、食後、特定の食品で悪化するなど)
- 時間帯(朝方、夜間など)
- 随伴症状(吐き気、発熱、下痢など)
これらの情報は、医療機関を受診する際に医師の診断を助ける重要な手がかりとなります。特に、同じ場所の痛みが繰り返し起こる場合や、痛みが強く日常生活に支障をきたす場合は早めの受診をお勧めします。
セルフチェック5:体重変化と食欲不振
意図せぬ体重減少は、さまざまな消化器疾患の重要なサインです。特に3ヶ月で5%以上の体重減少(例:60kgの方なら3kg以上)は注意が必要です。
食欲不振を伴う体重減少は、胃がんや膵臓がんなどの消化器がんの初期症状であることがあります。一方、食欲があるのに体重が減少する場合は、栄養の吸収障害や代謝の問題が疑われます。
私の経験では、「なんとなく食欲がない」「好きな食べ物が食べられなくなった」という変化を軽視せず受診された方の中から、早期の胃がんが見つかったケースがあります。体重と食欲の変化は、ご自身で気づける重要な健康指標です。

体重・食欲のセルフチェック方法
月に1回程度、同じ条件(時間帯、服装など)で体重を測定し記録しましょう。また、食事量や食欲の変化も併せてチェックします。
特に注意すべきは、以下のような変化です。
- 3ヶ月以内の急激な体重減少(5%以上)
- 特定の食品(肉類など)に対する嫌悪感の出現
- すぐにお腹がいっぱいになる感覚
- 食べると胃部不快感が強まる
これらの症状が続く場合は、消化器内科での精密検査をお勧めします。
セルフチェック6:吐き気とげっぷの頻度
吐き気やげっぷの増加は、消化器系のトラブルを示すサインかもしれません。
特に食事と関係なく吐き気を感じる、げっぷが異常に増える、げっぷに酸っぱい味や苦い味がするといった症状は、胃炎や食道炎、胆道系の問題などを示唆していることがあります。
私が診察する患者さんの中には、「げっぷが多いのは年齢のせい」と自己判断して受診が遅れるケースがあります。しかし、これらの症状が新たに出現し、継続する場合は、何らかの消化器疾患の可能性を考慮すべきです。
吐き気・げっぷのセルフチェック方法
1週間程度、吐き気やげっぷの頻度、タイミング、随伴症状を記録してみましょう。特に以下のような場合は注意が必要です。
- 朝起きた時から吐き気がある
- 食事と関係なく吐き気が続く
- げっぷの頻度が急に増えた
- げっぷと共に胸やけを感じる
- げっぷに異臭がある
これらの症状が2週間以上続く場合は、消化器内科を受診することをお勧めします。
セルフチェック7:黄疸と皮膚の変化
目の白い部分や皮膚が黄色みを帯びる黄疸は、肝臓や胆道系の問題を示す重要なサインです。
黄疸は肝炎や胆石、膵臓がんなど、さまざまな消化器疾患で現れることがあります。初期の黄疸は目の白い部分(強膜)に最初に現れることが多いため、定期的に鏡でチェックすることが大切です。
私の臨床経験では、「なんとなく肌の色が変わった気がする」と受診された患者さんの中から、胆管がんや膵臓がんが見つかったケースがあります。特に無痛性黄疸(痛みを伴わない黄疸)は、膵臓や胆道系の悪性腫瘍のサインであることがあり、早急な精査が必要です。
黄疸のセルフチェック方法
自然光の下で、目の白い部分に黄色みがないかチェックしましょう。また、爪床の色や皮膚の色も観察します。
黄疸と併せて注意すべき症状には以下があります。
- 尿の色が濃くなる(コーラ色)
- 便の色が薄くなる(灰白色)
- 皮膚のかゆみ
- 原因不明の倦怠感
これらの症状がある場合は、速やかに医療機関を受診してください。黄疸は進行すると全身症状を伴う深刻な状態になることがあります。
セルフチェック8:機能性ディスペプシアのセルフチェック
機能性ディスペプシアは、内視鏡検査などで器質的な異常が見つからないにもかかわらず、みぞおちを中心とした不快感が続く状態です。
日本では近年、機能性ディスペプシアと診断される患者さんが増えています。以前は胃下垂や慢性胃炎と診断されていた症状の多くが、現在は機能性ディスペプシアとして理解されるようになりました。
この疾患は生活の質を著しく低下させることがありますが、適切な治療で症状を軽減できるケースが多いです。
機能性ディスペプシアのセルフチェック法
以下の症状が3ヶ月以上続いている場合、機能性ディスペプシアの可能性があります。
- 食後の胃もたれ感
- 早期満腹感(少量で満腹になる)
- みぞおちの痛みや灼熱感
- 食前・食後の吐き気
- 頻繁なげっぷ
- お腹の張り
これらの症状が日常生活に支障をきたすほど続く場合は、消化器内科を受診しましょう。内視鏡検査で器質的疾患を除外した上で、適切な治療を受けることが重要です。

セルフチェックで異常を感じたら
ここまでご紹介した8つのセルフチェックで気になる症状があった場合、どうすればよいのでしょうか。
まずは、症状の持続期間や程度を記録しておくことが大切です。医療機関を受診する際、いつからどのような症状があるのか、どのような時に悪化するのかなどの情報は、医師の診断を助ける重要な手がかりとなります。
消化器症状で受診する場合は、消化器内科を標榜しているクリニックや病院を選ぶとよいでしょう。特に内視鏡検査が可能な施設であれば、必要に応じてその場で精密検査まで進めることができます。
消化器疾患は早期発見・早期治療が何よりも重要です。「様子を見よう」と放置せず、気になる症状があれば専門医に相談することをお勧めします。
当院では、患者さんのちょっとした不安や疑問にも丁寧にお答えし、必要に応じて内視鏡検査や超音波検査、CT検査などの精密検査をご案内しています。些細なことでもお気軽にご相談ください。
まとめ:日常的なセルフチェックで消化器健康を守る
消化器疾患のセルフチェックは、特別な道具や知識がなくても日常生活の中で簡単に行えます。今回ご紹介した8つのチェック項目を定期的に確認することで、異変を早期に発見し、適切な医療につなげることができます。
特に40代以降の方は、年に一度の健康診断に加えて、日々のセルフチェックを習慣にすることをお勧めします。自分の体の変化に敏感になることが、健康寿命を延ばす第一歩です。
消化器の健康は、全身の健康と密接に関わっています。ご自身の体調変化を大切にし、必要な時には専門医に相談する勇気を持ちましょう。
健康な消化器は、健やかな毎日の基盤です。日々のセルフチェックで、あなたの健康を守りましょう。
消化器に関する詳しい情報や検査についてのご質問は、石川消化器内科・内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。皆様の健康な毎日をサポートいたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
大腸カメラ検査の準備で失敗しない10のコツを伝授
大腸カメラ検査とは?その重要性を理解しよう
大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)は、大腸の粘膜を直接観察することで、ポリープや炎症、そして大腸がんなどの病変を早期に発見できる重要な検査です。
正式には「下部消化管内視鏡検査」と呼ばれ、大腸全体と小腸の一部(終末回腸)までを観察することができます。この検査の意義は主に3つあります。症状がある方の原因究明、ポリープやがんの早期発見、そして指摘されている病変の経過観察です。
大腸がんは日本人のがん死亡原因の上位を占めており、早期発見が非常に重要です。アメリカからの報告では、大腸内視鏡を行って大腸ポリープをすべて切除することで、大腸がんによる死亡率が53%低下したという結果も出ています。
しかし、多くの方が検査前の準備に不安を感じています。特に下剤の服用や食事制限は「大変そう」というイメージがあるかもしれません。
当院では年間多数の大腸カメラ検査を実施していますが、適切な準備ができているかどうかで検査の精度が大きく変わることを日々実感しています。
では、どうすれば大腸カメラ検査をスムーズに、そして正確に受けることができるのでしょうか?
大腸カメラ検査の準備で失敗しないための10のコツ
大腸カメラ検査の成否を左右する最大の要因は、検査前の腸内洗浄です。腸がきれいに洗浄されていなければ、病変を見落としてしまう可能性があります。
私が消化器内科医として多くの内視鏡検査を行ってきた経験から、確実に成功させるための10のコツをお伝えします。

1. 検査3〜4日前からの食事調整
検査の3〜4日前から、以下の食品を避けるようにしましょう。
- 食物繊維が多い野菜(キャベツ、ほうれん草、白菜など)
- きのこ類(しいたけ、えのき、しめじなど)
- 海藻類(わかめ、昆布、ひじき)
- 玄米、雑穀米、オートミール
- 脂っこい料理(天ぷら、揚げ物、ラーメン)
- 乳製品(ヨーグルト、チーズ、牛乳)
- こんにゃく、豆類(納豆、煮豆など)
- ナッツ類(アーモンド、カシューナッツなど)
これらの食品は腸内に残りやすく、洗浄剤を使用しても完全に排出されないことがあります。腸壁に付着した食物繊維や油分は、検査時の視野を遮り、病変の発見を妨げる原因となります。
2. 検査前日の食事選びを徹底する
検査前日は特に重要です。消化の良い食品を選び、以下のような食事がおすすめです。
- 白ごはん:繊維が少なく消化が良い
- うどん:柔らかく、消化吸収が早い
- 白身魚(タラ、カレイなど):脂肪分が少なく、胃腸への負担が軽い
- 鶏ささみ:高たんぱく・低脂質で消化も良好
- 卵(茹で卵・茶碗蒸し):調理法に注意すれば消化に優しい
- 豆腐(絹ごし):柔らかく、胃腸にやさしい
前日の食事スケジュールの目安は、朝食に白ごはん+温泉卵+具なし味噌汁、昼食にうどん(具なし)またはプレーンおかゆ、夕食は18時〜19時に終了させ、21時までには完全に食事を終えるようにしましょう。
3. 便秘対策は早めに始める
普段から便秘気味の方は、検査の数日前から対策を始めることが重要です。市販の緩下剤を使用するのも一つの方法です。
便秘の方は腸内に便が溜まりやすく、検査前の洗浄が不十分になりがちです。そのため、検査前から腸内環境を整えておくことで、当日の洗浄がスムーズに進みます。
私の臨床経験では、便秘の方が事前に対策をしておくかどうかで、検査の質が大きく変わることを実感しています。
4. 下剤を効果的に飲むコツ
下剤の服用は大腸カメラ検査の準備で最も大変な部分かもしれません。しかし、いくつかのコツを知っておくと、かなり楽になります。
- 冷やして飲む:下剤を冷蔵庫で冷やしておくと飲みやすくなります
- ストローを使う:直接口に入れずに飲めるので抵抗感が減ります
- レモンを添える:レモンを少し舐めてから飲むと、下剤の味が気になりにくくなります
- 飴を舐めながら飲む:甘い飴を舐めながら飲むことで、下剤の味を和らげることができます
- 一気に飲まず、指示された時間内で少しずつ飲む:無理に一気飲みすると吐き気を催すことがあります
下剤を飲み終わったあとは、透明な液体(水やお茶など)をしっかり摂取し続けることも大切です。これにより腸内の洗浄効果が高まります。
あなたはどうですか?下剤を飲むのに苦労した経験はありませんか?
5. 下剤の効果を確認する
下剤を飲んで排便を繰り返すと、最終的には黄色がかった透明な液体が出てくるようになります。これが「腸がきれいになった」サインです。
もし最後の排便でも濁りや固形物が混じっている場合は、腸の洗浄が不十分な可能性があります。このような場合は、検査当日に医療機関で追加の処置(浣腸など)が必要になることがあります。
私の経験では、最後の排便の状態を確認しておくことで、検査当日の心構えができますし、必要に応じて医師に伝えることができます。
6. 検査当日の水分摂取を忘れない
検査当日は食事ができませんが、水分は検査の2時間前まで摂取できる場合が多いです。ただし、必ず医療機関の指示に従ってください。
適切な水分摂取は、体調維持だけでなく、腸内洗浄の効果を持続させる役割もあります。特に夏場は脱水に注意が必要です。
摂取できる飲み物は基本的に透明な液体(水、お茶、透明なスポーツドリンクなど)に限られます。牛乳、ジュース、コーヒー、紅茶などの色のついた飲み物は避けましょう。
7. 服薬について医師に相談する
普段服用している薬がある場合は、事前に医師に相談することが重要です。特に注意が必要なのは以下の薬です。
- 血液をサラサラにする薬(抗凝固薬、抗血小板薬)
- 糖尿病の薬(特にインスリン)
- 便通を整える薬
これらの薬は検査の数日前から調整が必要な場合があります。自己判断で中止せず、必ず医師の指示に従いましょう。
私が診療で特に注意しているのは、抗凝固薬を服用している方です。ポリープ切除を行う場合には出血リスクが高まるため、事前の対応が必要になることがあります。
8. 検査当日の服装を工夫する
検査当日は動きやすく、着脱しやすい服装を選びましょう。特におすすめなのは以下のポイントです。
- ウエストがゴムの服(ジーンズなど固いものは避ける)
- 上下分かれた服(ワンピースは避ける)
- 着脱しやすいシンプルな服
検査中は横向きになったり体位を変えたりすることがあるため、動きやすい服装が望ましいです。また、検査後にお腹が張ることもあるので、締め付けない服装を選ぶと快適です。
9. 検査後の過ごし方を計画しておく
検査後は、腸に空気が入っているため膨満感を感じることがあります。また、鎮静剤を使用した場合は、その日の車の運転はできません。
検査後の過ごし方について、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 帰宅方法を事前に確保しておく(公共交通機関の利用や家族の送迎など)
- 検査後すぐの予定は入れない
- 軽い食事から始め、徐々に通常の食事に戻す
- 水分をしっかり摂る
ポリープ切除を行った場合は、アルコールや激しい運動、入浴(シャワーは可)を数日間控える必要があることもあります。医師の指示に従いましょう。
10. 信頼できる医療機関を選ぶ
大腸カメラ検査は、医療機関や医師の技術によって精度や快適さが大きく変わります。信頼できる医療機関を選ぶポイントとしては以下が挙げられます。
- 消化器内科や内視鏡の専門医がいるか
- 鎮静剤を使用した無痛内視鏡に対応しているか
- 検査実績が豊富か
- 緊急時の対応体制が整っているか
- 検査前の説明が丁寧か
当院では、鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査を提供しており、患者さんの負担を最小限に抑えながら精度の高い検査を実現しています。

大腸カメラ検査の流れと実際の体験
大腸カメラ検査がどのように行われるのか、実際の流れを説明します。
検査当日は、まず問診と体調確認が行われます。その後、検査着に着替え、横になった状態で検査が始まります。鎮静剤を使用する場合は、点滴から投与されます。
私が実際に経験した患者さんの例を紹介します。50代の男性Aさんは、便潜血検査で陽性となり大腸カメラ検査を受けることになりました。初めての検査で不安を感じていましたが、鎮静剤を使用したところ、「気づいたら終わっていた」と驚いていました。
また、60代の女性Bさんは以前別の医療機関で検査を受けた際に強い痛みを感じた経験があり、検査を恐れていました。当院での検査では適切な鎮静と丁寧な内視鏡操作により、「こんなに楽に終わるなんて」と喜ばれました。
検査中は医師が内視鏡を挿入し、大腸内を観察します。必要に応じてポリープの切除や組織採取を行います。検査時間は通常15〜30分程度ですが、鎮静剤を使用すると体感時間はずっと短く感じられます。
検査後は回復室で30分〜1時間程度休息し、体調が安定したら帰宅できます。その日のうちに検査結果の説明を受けられることが多いですが、病理検査が必要な場合は後日の説明となります。
あなたも不安を感じていますか?多くの方が最初は不安を感じますが、適切な準備と鎮静剤の使用により、思ったより楽に検査を終えられることがほとんどです。
大腸カメラ検査で見つかる主な病変
大腸カメラ検査では、様々な病変を発見することができます。主なものとしては以下が挙げられます。
大腸ポリープ
大腸ポリープは大腸の粘膜から突出した隆起性病変です。多くは良性ですが、一部は時間をかけて大腸がんに進行する可能性があります。大きさや形状、色調などから良性か悪性かの判断をしますが、確定診断には病理検査が必要です。
5mm以下の小さなポリープは、その場で切除することが多いです。6mm以上のポリープは、形状や性状によって適切な切除方法を選択します。
大腸がん
大腸がんは早期に発見できれば内視鏡治療で完治する可能性が高い病気です。早期大腸がんの多くは症状がないため、検診での発見が重要です。
進行すると血便や便通異常、腹痛などの症状が現れることがありますが、これらの症状は他の病気でも起こるため、症状があれば早めに医療機関を受診することをお勧めします。
炎症性腸疾患
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患も大腸カメラで診断できます。これらの疾患は腸の粘膜に炎症や潰瘍を生じる慢性疾患で、下痢や血便、腹痛などの症状を引き起こします。
炎症性腸疾患の患者さんは定期的な大腸カメラ検査が必要で、炎症の程度を評価するとともに、長期経過による大腸がんのリスク増加にも注意が必要です。
まとめ:大腸カメラ検査を成功させるために
大腸カメラ検査は、大腸の病変を早期に発見し、適切な治療につなげるための重要な検査です。検査の成否を左右するのは、何よりも検査前の準備です。
今回ご紹介した10のコツを実践することで、検査をスムーズに、そして正確に受けることができます。特に重要なのは、検査前の食事制限と下剤の適切な服用です。
当院では、患者さんの不安や負担を軽減するために、鎮静剤を用いた無痛内視鏡検査を提供しています。また、検査前の準備についても丁寧にご説明し、患者さん一人ひとりに合わせたサポートを心がけています。
大腸カメラ検査に不安を感じている方も、適切な準備と信頼できる医療機関での検査により、安心して検査を受けることができます。ご自身の健康管理のために、定期的な検査をお勧めします。
検査についてのご質問や不安なことがあれば、いつでもご相談ください。皆様の健康を守るために、私たちは誠心誠意サポートいたします。
詳しい情報や予約については、石川消化器内科・内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
胃カメラ検査で嘔吐を防止する5つの最新技術とコツ
胃カメラ検査の嘔吐反射に悩む患者さんへ
胃カメラ検査と聞いて、「オエッ」となる不快な嘔吐反射を思い浮かべる方は少なくありません。消化器内科医として多くの内視鏡検査を行ってきた経験から言えることですが、この検査に対する不安や恐怖感が、適切な時期の検査を避ける原因になっていることを日々感じています。
胃の不調を感じているにもかかわらず、「胃カメラが怖い」という理由だけで検査を先延ばしにしてしまうのは、健康管理の観点からも非常にもったいないことです。
近年、医療技術の進歩により、胃カメラ検査は昔に比べてはるかに受けやすくなっています。特に嘔吐反射の軽減に関しては、さまざまな新しい技術やアプローチが開発されています。
胃カメラ検査で嘔吐が起こるメカニズム
まず、なぜ胃カメラ検査中に「オエッ」となってしまうのか、そのメカニズムを理解しておくことが大切です。
嘔吐反射は、本来、私たちの体を守るための防御反応です。喉の奥(咽頭)に異物が入ると、それを排除しようとする反射が自然と起こります。胃カメラが口から入ると、のど・食道・胃・十二指腸の順番で進んでいきますが、特にのどを通過する際に、この防御反射が強く働くのです。
食道に異物が入ることを防ぐ反射を嘔吐反射と呼び、これが「オエッ」という不快な感覚の正体です。この反射は人によって感度が異なり、非常に敏感な方もいれば、比較的鈍感な方もいます。
また、緊張や不安が強いと、この反射がさらに敏感になることも分かっています。つまり、「胃カメラは苦しい」と思い込んで緊張すればするほど、実際に嘔吐反射が起こりやすくなるという悪循環に陥ってしまうのです。

では、この嘔吐反射を抑え、より快適に胃カメラ検査を受けるための最新技術とコツを見ていきましょう。
嘔吐を防ぐ最新技術①:経鼻内視鏡
従来の胃カメラは口から挿入するタイプ(経口内視鏡)が一般的でしたが、近年では鼻から挿入する経鼻内視鏡が普及してきています。
経鼻内視鏡の最大のメリットは、口から挿入する場合と比較して嘔吐感が大幅に軽減されることです。鼻から挿入することで、喉の嘔吐反射が起こりにくくなるのです。
経鼻内視鏡は、直径5.4mm程度と非常に細いスコープを使用するため、挿入時の違和感も少なくなっています。鼻の奥に専用のゼリー状の麻酔を塗ることで、痛みもほとんど感じることなく検査を受けることができます。
ただし、経鼻内視鏡にもいくつか注意点があります。鼻の奥が生まれつき狭い方や、アレルギーなどで腫れている場合は、挿入時に痛みや出血が生じることがあります。また、鼻や喉への局所麻酔が苦手な方もいらっしゃいます。
当院では患者さんの状態に合わせて、経口・経鼻どちらの胃カメラも選択できるようにしています。事前の診察で、どちらの方法が適しているかを丁寧に説明し、患者さんと相談しながら決めていきます。
嘔吐を防ぐ最新技術②:鎮静剤の使用
近年、胃カメラ検査の際に鎮静剤を使用することが一般的になってきました。鎮静剤を使用すると、半分眠ったような状態で検査を受けることができるため、嘔吐反射や不安感を大幅に軽減することができます。
鎮静剤は点滴から投与され、数分で効果が現れます。完全に意識がなくなる全身麻酔とは異なり、意識はぼんやりと保たれた状態になります。検査中の記憶があいまいになることが多く、「あっという間に終わった」という感想をいただくことがほとんどです。
鎮静剤のメリットは、嘔吐反射が抑えられるだけでなく、身体の力が自然と抜けるため、検査がスムーズに進むことです。また、喉への局所麻酔も不要になるので、麻酔アレルギーがある方にも安心して受けていただけます。
当院では患者さんごとに適切な量の鎮静剤を微調整しながら投与しますので、「検査途中で目が覚めてしまった」ということもほとんどありません。鎮静剤を使用することで、経口内視鏡でも嘔吐反射をほぼ感じることなく検査を受けていただけます。
ただし、鎮静剤を使用する場合は、検査後30分〜1時間程度の休憩が必要になります。また、当日は車の運転や自転車の使用、重要な判断や契約行為などは避けていただく必要があります。

どうしても不安な方や、過去に辛い経験をされた方には、積極的に鎮静剤の使用をお勧めしています。
嘔吐を防ぐ最新技術③:超細径スコープ
内視鏡技術の進歩により、スコープ(胃カメラの管)はどんどん細くなってきています。従来の経口内視鏡は直径9〜10mm程度でしたが、最新の超細径スコープは直径5.9mm程度まで細くなっています。
スコープが細くなることで、喉を通過する際の違和感や圧迫感が大幅に軽減され、嘔吐反射も起こりにくくなります。特に経鼻内視鏡では直径5.4mm程度の非常に細いスコープを使用するため、挿入時の違和感をさらに軽減することができます。
当院では、他の医療機関で使用されているスコープよりも細いものを使用しており、胃カメラが喉を通る時の苦しさを軽減しています。また、超高精細な画像を提供する最新の内視鏡システムを導入しているため、スコープが細くなっても診断の精度は落ちません。
特殊な光によって粘膜の微細な変化まで観察できる拡大内視鏡も導入しており、大学病院に劣らない高精度な検査を実現しています。
嘔吐を防ぐ最新技術④:ウォータージェット機能
最新の内視鏡には、ウォータージェット機能が搭載されています。これは、内視鏡の先端から水を直接噴射できる機能で、胃の中の洗浄や視野の確保に役立ちます。
従来の内視鏡検査では、胃の中の泡や粘液を洗い流すために、検査前に消泡剤や粘液除去剤を飲んでいただく必要がありました。しかし、ウォータージェット機能を使えば、内視鏡で観察しながら直接胃の中に薬剤を入れたり、水で胃内の洗浄・吸引を短時間で行ったりすることができます。
これにより、検査前の準備が簡略化され、患者さんの負担が軽減されます。また、検査中に胃の中をより清潔に保つことができるため、より精度の高い観察が可能になります。
当院では、ウォータージェット機能を搭載した最新の内視鏡システムを導入しており、より快適で効率的な検査を提供しています。
胃の中に空気を入れすぎると膨満感やげっぷが生じやすくなりますが、ウォータージェット機能を使うことで必要最小限の空気で検査を行うことができ、検査後の不快感も軽減されます。
嘔吐を防ぐ最新技術⑤:内視鏡挿入形状観測装置(UPD)
内視鏡挿入形状観測装置(UPD:Ultrasound Probe Detector)は、内視鏡の挿入状態をリアルタイムでモニターに表示する装置です。これにより、医師は内視鏡がどのように体内で曲がっているかを視覚的に確認しながら操作することができます。
UPDを使用することで、内視鏡の無理な屈曲や過度な圧迫を避けることができ、患者さんの負担を軽減することができます。特に大腸内視鏡検査では効果を発揮しますが、上部消化管内視鏡(胃カメラ)においても、食道や胃への挿入をよりスムーズに行うことができます。
当院では、熟練した技術に加え、UPDなどの最新技術を駆使して、できる限り痛みのない、苦しくない内視鏡検査を心がけています。
胃カメラをスムーズに受けるための5つのコツ
最新技術の活用に加えて、患者さん自身ができる工夫もあります。以下に、胃カメラをよりスムーズに受けるためのコツをご紹介します。
コツ①:リラックスする・肩の力を抜く
検査台に乗ったら、まずはリラックスすることを意識しましょう。特に肩の力を抜くことが重要です。肩に力が入ると喉が締まりやすくなり、胃カメラが入りにくくなってしまいます。
検査直前に大きく深呼吸をすると効果的です。鼻からゆっくり吸って、口から「ハー」と吐く呼吸を3回程度繰り返してみましょう。大きく吸って、大きく吐くのがコツです。
また、検査中も静かな呼吸を続けることで、体の緊張を和らげることができます。

コツ②:正しい姿勢をとる
検査中は、顎を突き出し、頬は枕にしっかりとつけるようにしましょう。視線はやや左に向け、ベッドを見るような感じにします。
顎を突き出すことで、胃カメラが入る時の抵抗感を軽減することができます。また、視線をやや下げることで、唾液が気管に流れ込むのを防ぐことができます。
お尻を後ろに突き出し、上体はやや前傾姿勢になるようにすると、「く」の字の姿勢になり、胃カメラの挿入がスムーズになります。
コツ③:唾液は飲み込まない
検査中、唾液は飲み込まないで、だらだらと口の外に出すようにしましょう。喉に麻酔をかけると、飲み込んだ唾などが気管に入りやすくなります(誤嚥)。誤嚥するとむせて苦しくなってしまうので、唾液は飲み込まないことが大切です。
心配いりません。顔の下にシートや受け皿を用意するので、衣服が汚れることはありません。
コツ④:検査中は目を閉じない
検査中は目を閉じないで、遠くを見つめる感じでいましょう。目を閉じてしまうと、意識がどうしても咽頭に集中してしまい、オエッとなりやすくなってしまいます。
また、目を開けておけば視覚が遮られないので、パニックになりにくくなります。リラックスして、何か別のことを考えるようにすると良いでしょう。
コツ⑤:ゲップを我慢する
検査の中盤以降、胃の観察のためにカメラから送気して胃を膨らませます。少しお腹が張った感じになりますが、1〜2分程度なのでなるべくゲップを我慢しましょう。
うまく我慢できると検査が早く終わります。胃の中の空気は検査後に自然と出ていきますので、ご安心ください。
胃カメラ検査前の準備と注意点
胃カメラ検査をスムーズに受けるためには、事前の準備も重要です。以下に、検査前の注意点をまとめました。
食事について
胃の中をくまなく観察するためには、胃の中に食事の残りがないことが重要です。そのため、以下のポイントに注意してください。
・前日の夕食は、遅くても夜9時には済ませましょう
・消化の良いものを選びましょう(ワカメやこんにゃくなどは胃の中に残りやすいので避けましょう)
・検査当日は、朝食を摂らずにお越しください
・水は飲んでいただいて構いませんが、ジュースや牛乳など色のついた飲み物は控えましょう
お薬について
普段服用しているお薬がある場合は、事前に医師に相談してください。特に以下のようなお薬は注意が必要です。
・抗血小板剤・抗凝固薬(血液をさらさらにする薬):通常の検査では継続していただくことが一般的ですが、何か処置をする場合は休薬していただくこともあります
・糖尿病のお薬:検査当日は休薬していただくことが一般的です
どのようなお薬を飲んでいるか、医師・看護師で確認しますので、お薬手帳をお忘れなくご持参ください。
当日の服装
検査当日は、リラックスできる楽な服装でお越しください。特に首元や胸元を圧迫しない服装が望ましいです。また、アクセサリー類(特にネックレス)は外していただく場合があります。
女性の方は、口紅やリップクリームは控えていただくと、検査がスムーズに進みます。
まとめ:安心して胃カメラ検査を受けるために
胃カメラ検査は、食道・胃・十二指腸の病変を早期に発見するための非常に重要な検査です。しかし、「辛い・苦しい」というイメージが先行し、検査を避けてしまう方が多いのが現状です。
今回ご紹介した5つの最新技術(経鼻内視鏡、鎮静剤、超細径スコープ、ウォータージェット機能、UPD)と5つのコツ(リラックスする、正しい姿勢をとる、唾液は飲み込まない、目を閉じない、ゲップを我慢する)を活用することで、胃カメラ検査はかなり楽に受けられるようになっています。
当院では、これらの技術を駆使して、「より気軽に」「よりスピーディーに」、そして安心して検査を受けていただけるよう、さまざまな工夫を行っています。初診当日や土曜日の検査にも対応しており、お忙しい方でも無理なく検査を受けていただけます。
胃の調子が気になる方、ピロリ菌感染が判明した方、過去に胃カメラで辛い思いをした方も、ぜひ一度ご相談ください。最新の技術と丁寧な対応で、これまでとは違う胃カメラ体験をご提供いたします。
健康管理のためにも、定期的な胃カメラ検査をお勧めします。胃の健康は、あなたの毎日の生活の質に大きく関わります。不安なことがあれば、どうぞお気軽に石川消化器内科・内視鏡クリニックまでご相談ください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
肝臓検査の数値が示す健康状態~専門医が徹底解説
肝臓検査の数値が健康状態を映し出す理由
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、痛みや不調を感じにくい特徴があります。健康診断で「肝機能の数値が高い」と言われても、自覚症状がないため軽視してしまう方が少なくありません。
しかし、肝臓は私たちの体内で500以上もの働きを黙々とこなす重要な臓器なのです。食べ物をエネルギーに変換したり、脂肪の消化・吸収に必要な胆汁を生成したり、アルコールなどの有害物質を解毒したりと、その役割は多岐にわたります。
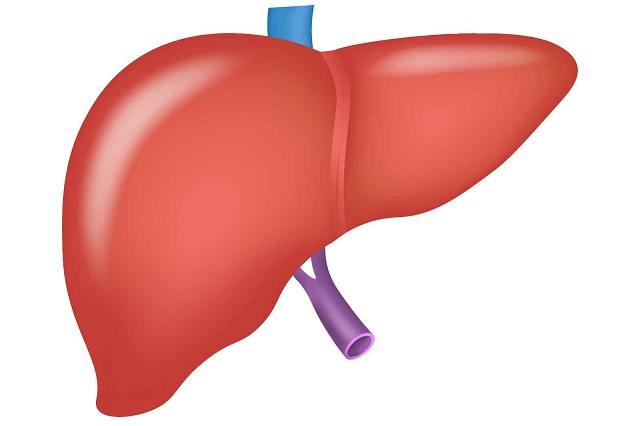
肝臓が悲鳴を上げ始めても、初期段階では症状がほとんど現れません。そのため、血液検査による数値の変化を知ることが、肝臓の健康状態を把握する最も効果的な方法となります。
どうでしょうか?あなたも健康診断で「AST」「ALT」「γ-GTP」といった数値を見たことがあるのではないでしょうか。これらは肝臓の状態を示す重要な指標です。
肝機能検査の主要な数値と基準値
肝臓の健康状態を評価するために、血液検査では主に3つの重要な数値を確認します。これらの数値が基準値を超えると、肝臓に何らかの負担がかかっている可能性があります。
まず、AST(GOT)とALT(GPT)は肝細胞内に存在する酵素です。肝臓に炎症や障害が起きると、これらの酵素が血液中に漏れ出し、数値が上昇します。健康な状態では、AST・ALTともに30 U/L以下が基準値とされています。
AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)は心臓や筋肉にも存在するため、肝臓以外の問題でも上昇することがあります。一方、ALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)は肝臓に特異的な酵素で、この数値が上昇した場合は肝臓の異常を強く疑います。
γ-GTP(ガンマグルタミルトランスペプチダーゼ)は肝臓や胆道の異常を示す酵素で、基準値は50 U/L以下です。特にアルコールに敏感に反応するため、飲酒量の多い方では上昇しやすい傾向があります。
これらの数値の変化から、肝臓の状態をある程度推測することができます。例えば、ASTとALTがともに高い場合は急性肝炎や慢性肝炎、脂肪肝などが疑われます。ASTだけが高い場合は、心筋梗塞や筋肉の病気の可能性も考慮する必要があります。
健康診断で「肝機能の数値が高い」と言われたら、どのような数値がどの程度上昇しているのかを確認し、必要に応じて専門医を受診することをお勧めします。
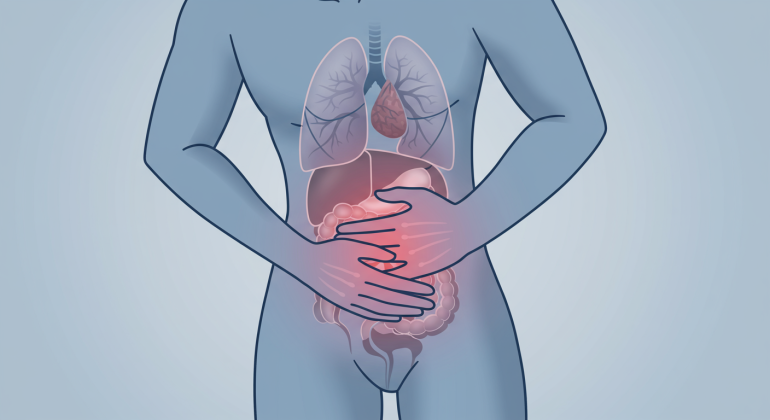
肝臓の数値が示す主な疾患と健康リスク
肝臓の数値異常は、様々な疾患のサインとなります。早期発見と適切な対応が重要なのは、肝臓疾患が進行すると取り返しのつかない状態になる可能性があるからです。
脂肪肝は、肝機能検査で最も頻繁に見られる異常の一つです。過剰な脂肪が肝臓に蓄積する状態で、アルコールの過剰摂取や肥満、糖尿病などが原因となります。初期段階では症状がほとんどなく、軽度であれば生活習慣の改善で回復可能です。
しかし、脂肪肝を放置すると、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)へと進行するリスクがあります。NASHでは肝臓に炎症が起き、肝細胞が徐々に破壊されていきます。さらに進行すると、肝硬変や肝がんといった深刻な疾患につながる可能性があるのです。
アルコール性肝障害も、肝機能検査で発見される重要な疾患です。アルコールの過剰摂取により肝臓に障害が生じる状態で、初期は脂肪肝の形をとりますが、飲酒を続けるとアルコール性肝炎、肝硬変へと進行します。特にγ-GTPの上昇は、アルコール性肝障害の早期サインとして重要です。
ウイルス性肝炎(B型・C型)も肝機能検査で発見されることがあります。これらは肝炎ウイルスの感染により肝臓に炎症が起こる疾患で、慢性化すると肝硬変や肝がんのリスクが高まります。
肝機能検査の数値異常は、薬剤性肝障害の可能性も示唆します。特定の薬剤が肝臓に負担をかけ、肝機能に異常をきたす状態です。医師の指示なく服用している薬やサプリメントがある場合は、必ず医師に伝えましょう。
あなたは健康診断で肝臓の数値が高いと言われたことはありますか?
数値の見方と重症度の判断基準
肝臓の数値を正しく理解するためには、単に「高い・低い」だけでなく、どの程度の異常値なのかを知ることが重要です。日本人間ドック学会の基準によると、肝機能検査の数値は以下のように判定されます。
AST(GOT)とALT(GPT)の場合:
- 30 U/L以下:正常範囲(A判定)
- 31~35 U/L:軽度異常(B判定)
- 36~50 U/L:中等度異常(C判定)
- 51 U/L以上:高度異常(D判定)
γ-GTPの場合:
- 50 U/L以下:正常範囲(A判定)
- 51~80 U/L:軽度異常(B判定)
- 81~100 U/L:中等度異常(C判定)
- 101 U/L以上:高度異常(D判定)
数値が基準値をわずかに超える程度(B判定)であれば、生活習慣の改善で正常化することが多いです。しかし、C判定やD判定の場合は、より詳しい検査や専門医の診察が必要になることがあります。
特に注意が必要なのは、数値が100 U/Lを超えるような高値の場合です。AST・ALTが100 U/L以下であれば、医師によっては経過観察や生活指導で様子を見ることもありますが、肝臓に負担がかかっていることは確かです。
300 U/Lを超えるような著しい高値の場合は、入院が必要となる可能性が高い危険な状態です。500 U/Lを超えると急性肝炎の可能性が強く、非常に危険な状態と言えます。このレベルになると、多くの場合、黄疸や倦怠感などの自覚症状が現れます。
また、数値の変動パターンも重要な情報です。例えば、アルコール性肝障害ではASTがALTよりも高くなる傾向があります。一方、非アルコール性脂肪肝炎ではALTがASTよりも高くなることが多いです。
肝臓の数値は一度の検査だけでなく、経時的な変化も重要です。定期的に検査を受け、数値の推移を追うことで、より正確な健康状態の把握が可能になります。
肝臓の数値を改善するための具体的アプローチ
肝機能検査で異常値が出た場合、まずは生活習慣の改善から始めることが重要です。肝臓は再生能力が高い臓器ですので、適切なケアによって数値を正常化できる可能性が高いのです。
アルコールの摂取量を減らすことは、特にγ-GTPが高い方にとって最も効果的な対策です。お酒を完全に断つことが難しい場合でも、週に2日以上の休肝日を設けることで肝臓の回復を促すことができます。
食生活の見直しも重要です。脂肪肝の改善には、糖質や脂質の過剰摂取を控え、バランスの良い食事を心がけましょう。特に、肝細胞の修復に必要なタンパク質は意識的に摂取することをお勧めします。魚、卵、大豆製品、脂身の少ない赤身肉などが良質なタンパク質源となります。
適度な運動も肝機能改善に効果的です。有酸素運動を中心に、週に3回以上、1回30分程度の運動を継続することで、脂肪肝の改善や肝機能の正常化が期待できます。特に、内臓脂肪の減少は肝臓への負担を軽減します。
十分な睡眠と休息も肝臓の回復に欠かせません。肝臓は睡眠中に最も活発に修復・再生を行うため、質の良い睡眠を確保することが大切です。
肝臓に負担をかける薬剤やサプリメントの見直しも必要です。市販の鎮痛剤や解熱剤の中には、長期連用すると肝機能に影響を与えるものもあります。不要な薬剤は控え、必要な場合も医師や薬剤師に相談しましょう。
あなたは今日から何か生活習慣を変えてみようと思いますか?
専門医が勧める検査と診断アプローチ
肝機能検査で異常値が出た場合、より詳細な検査を行うことで、肝臓の状態をより正確に把握することができます。消化器内科専門医として、どのような検査が有効かをご説明します。
腹部超音波検査(エコー)は、非侵襲的かつ安全に肝臓の状態を観察できる基本的な検査です。脂肪肝の程度、肝臓の大きさや形状、腫瘍の有無などを評価できます。脂肪肝は超音波検査で「輝度の上昇」として観察され、その程度によって軽度・中等度・高度に分類されます。
血液検査では、肝機能検査に加えて、肝炎ウイルス検査(HBs抗原、HCV抗体など)、自己抗体検査、腫瘍マーカー検査なども必要に応じて行います。これにより、肝機能異常の原因を特定することができます。
フィブロスキャン検査は、肝臓の硬さ(線維化の程度)と脂肪量を測定する検査で、肝臓の状態をより詳細に評価できます。非侵襲的な検査であり、肝生検に比べて患者さんの負担が少ないのが特徴です。
CT検査やMRI検査は、肝臓の詳細な画像診断に有用です。特にMRIは脂肪量の定量的評価が可能で、NASHの診断や経過観察に役立ちます。
肝生検は、肝臓の一部を採取して顕微鏡で観察する検査で、最も確実な診断方法です。NASHの確定診断や、原因不明の肝機能異常の評価に用いられますが、侵襲性があるため、必要性を慎重に判断します。
これらの検査結果を総合的に判断し、適切な治療方針を決定することが重要です。肝機能異常の原因によって治療アプローチは大きく異なるため、正確な診断が不可欠です。

当院では、肝機能検査の異常を指摘された方に対して、腹部超音波検査や必要に応じた精密検査を行い、一人ひとりに最適な治療方針をご提案しています。早期発見・早期治療が肝臓疾患の予後を大きく左右しますので、気になる症状や検査結果があれば、ぜひご相談ください。
肝臓ケアの最新トレンドと予防医学の視点
肝臓疾患の治療と予防は、医学の進歩とともに日々進化しています。最近の研究では、肝臓の健康維持には腸内環境が密接に関わっていることが明らかになってきました。腸内細菌のバランスが崩れると、肝臓に負担をかける物質が増加し、肝機能異常を引き起こす可能性があります。
食物繊維を豊富に含む食品や発酵食品を積極的に摂取することで、腸内環境を整え、間接的に肝臓の健康をサポートできることがわかってきました。具体的には、野菜、果物、全粒穀物、ヨーグルト、納豆などが推奨されます。
また、コーヒーの適度な摂取が肝機能の保護に役立つという研究結果も報告されています。コーヒーに含まれるポリフェノールには抗酸化作用があり、肝細胞の損傷を防ぐ効果が期待されます。ただし、砂糖やクリームを多く加えると逆効果になる可能性がありますので、ブラックコーヒーが理想的です。
肝臓に優しい食事として、地中海式食事法も注目されています。オリーブオイル、魚、野菜、果物、ナッツ類を中心とした食事は、肝機能の改善や脂肪肝の軽減に効果があるとされています。
予防医学の観点からは、定期的な健康診断で肝機能検査を受けることが重要です。特に40歳以上の方や、肥満、糖尿病、高血圧などのリスク因子を持つ方は、年に一度は肝機能検査を含む健康診断を受けることをお勧めします。
肝炎ウイルス検査も、一度は受けておくべき重要な検査です。B型・C型肝炎は自覚症状がないまま進行することが多く、知らないうちに肝硬変や肝がんに至るケースもあります。早期発見できれば、適切な治療や経過観察が可能です。
最後に、ストレス管理も肝臓の健康に影響を与える重要な要素です。過度のストレスは自律神経のバランスを崩し、肝機能に悪影響を及ぼす可能性があります。適度な運動、十分な睡眠、リラクゼーション法の実践など、ストレスを軽減する工夫を日常生活に取り入れることも大切です。
まとめ:肝臓の健康を守るための総合アプローチ
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるように、異常があっても自覚症状が現れにくい特徴があります。そのため、健康診断での肝機能検査は肝臓の健康状態を知る貴重な機会となります。
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPといった肝機能検査の数値が基準値を超えた場合は、肝臓からのSOSサインと捉え、適切な対応を取ることが重要です。数値の程度や組み合わせによって、脂肪肝、アルコール性肝障害、ウイルス性肝炎など、様々な肝疾患の可能性が考えられます。
肝機能の改善には、アルコール摂取の制限、バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠など、生活習慣の見直しが基本となります。特に脂肪肝は、生活習慣の改善で十分に回復可能な疾患です。
しかし、数値が高度に異常な場合や、生活習慣の改善だけでは改善しない場合は、専門医による詳細な検査と適切な治療が必要です。腹部超音波検査、CT検査、MRI検査、フィブロスキャン検査などを通じて、肝臓の状態をより詳しく評価することができます。
肝臓は再生能力が高い臓器ですが、長期間にわたって負担がかかり続けると、肝硬変や肝がんといった深刻な疾患に進行するリスクがあります。早期発見・早期対応が、肝臓の健康を守るための鍵となります。
定期的な健康診断を受け、肝機能検査の結果に注意を払うことで、肝臓疾患の早期発見につなげましょう。また、日常生活では肝臓に優しい生活習慣を心がけ、肝臓の健康を積極的に守っていくことが大切です。
肝臓の健康は、全身の健康につながります。「沈黙の臓器」からのわずかなサインを見逃さず、適切なケアを行うことで、健やかな毎日を送りましょう。
肝臓の健康について気になることがある方は、ぜひ当院にご相談ください。消化器内科専門医として、適切な検査と治療をご提案いたします。
石川消化器内科・内視鏡クリニックでは、肝臓をはじめとする消化器疾患の診断・治療に力を入れています。お気軽にご相談ください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
内視鏡検査が怖くない~鎮静剤で実現する無痛検査の全て
内視鏡検査に対する不安と鎮静剤の役割
「胃カメラを受けなければならないけど、あの苦しさが怖い・・・」
内視鏡検査は消化器疾患の診断において非常に重要な検査ですが、多くの方がこのような不安を抱えています。特に胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)は、のどの奥にスコープが触れることによる嘔吐反射や不快感から、「辛い・苦しい」というイメージが先行しているのが現状です。大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)においても、検査中の腹痛や不快感を心配される方は少なくありません。
しかし、現代の内視鏡検査は、このような不安や苦痛を大幅に軽減する方法が確立されています。その代表的な方法が「鎮静剤」の使用です。鎮静剤を適切に使用することで、患者さんは半分眠ったような状態で検査を受けることができ、苦痛や恐怖をほとんど感じることなく検査を終えることができるのです。
私は消化器内科医として長年内視鏡検査に携わってきましたが、鎮静剤の適切な使用によって、以前は内視鏡検査に強い恐怖心を持っていた患者さんが、「あれ?もう終わったの?」と驚かれる場面を数多く経験してきました。
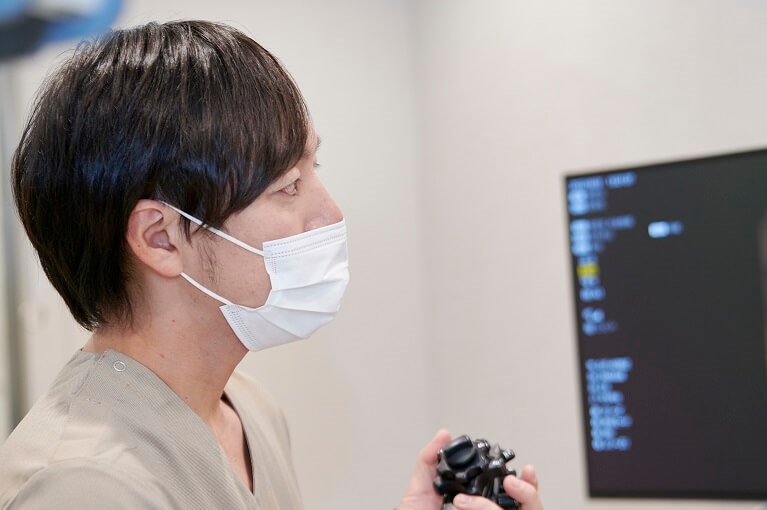
この記事では、内視鏡検査における鎮静剤の役割、メリット・デメリット、そして当院での無痛内視鏡検査の実際について詳しくご説明します。検査に対する不安を和らげ、より安心して検査を受けていただくための情報をお届けします。
鎮静剤とは?内視鏡検査での働きを解説
鎮静剤とは、不安や緊張を和らげ、眠気をもよおす効果のある薬剤です。内視鏡検査で使用される鎮静剤は、完全に意識をなくす全身麻酔とは異なり、呼びかけに反応できる程度の「意識下鎮静」を目指すものです。
内視鏡検査で一般的に使用される鎮静剤には、ミダゾラムやプロポフォールなどがあります。当院では主にミダゾラムを使用しています。これらの薬剤は静脈内に注射することで、リラックス効果や健忘効果(検査の記憶が薄れる効果)をもたらします。
鎮静剤の効果と作用機序
鎮静剤を静脈内に投与すると、多くの患者さんは「頭がぼーっとする」「まぶたが重くなる」といった感覚を経験します。その後、うとうとした状態になり、検査中の苦痛や不安を感じにくくなります。中には完全に眠ってしまう方もいますが、基本的には呼びかけに反応できる程度の鎮静状態を維持します。
鎮静剤の効果には個人差があり、同じ量を投与しても反応が異なることがあります。そのため、当院では患者さん一人ひとりの年齢、体格、既往歴などを考慮して、最適な量を慎重に決定しています。
鎮静剤が効いてくると、多くの方は「あっという間に検査が終わった」と感じます。実際には通常通りの時間がかかっているのですが、鎮静剤の健忘効果により、検査中の記憶が曖昧になるため、時間が短く感じられるのです。
これが、内視鏡検査における鎮静剤の大きな利点の一つです。検査自体の苦痛を軽減するだけでなく、検査の記憶も薄れることで、次回検査への恐怖心も軽減されるのです。
鎮静剤を使用するメリットとデメリット
内視鏡検査で鎮静剤を使用することには、様々なメリットとデメリットがあります。患者さんが自分に合った検査方法を選択できるよう、これらを正しく理解しておくことが大切です。
鎮静剤使用のメリット
鎮静剤を使用する最大のメリットは、検査中の苦痛や不安を大幅に軽減できることです。具体的には以下のようなメリットがあります:
- 嘔吐反射や不快感を感じにくくなる
- 検査への恐怖心や緊張感が和らぐ
- 検査中の記憶が薄れるため、心理的負担が軽減される
- 患者さんがリラックスすることで、医師も精度の高い検査を行いやすくなる
- 次回検査への抵抗感が減少する
特に、過去に内視鏡検査で辛い経験をされた方や、強い嘔吐反射がある方にとって、鎮静剤の使用は検査を受ける大きな助けとなります。
「以前の検査がつらかったので、もう二度と受けたくない」
このように思われていた患者さんが、鎮静剤を使用した検査後に「こんなに楽に受けられるなら、また来年も受けます」とおっしゃることも少なくありません。定期的な検査が必要な方にとって、これは非常に重要なポイントです。
鎮静剤使用のデメリット
一方で、鎮静剤の使用にはいくつかの注意点やデメリットもあります:
- 検査当日は車やバイク、自転車の運転ができない
- 予想以上に眠気が続く場合がある
- 呼吸が弱くなったり、血圧が低下したりする可能性がある
- 検査前後の記憶が低下または消失する(逆行性健忘)
- まれにアレルギー反応が起こる可能性がある
特に高齢の方や、肝機能・腎機能に障害のある方、呼吸器疾患をお持ちの方は、鎮静剤の効果が強く出たり、副作用が出やすくなったりする場合があります。そのため、事前の問診や検査が重要となります。
当院では、鎮静剤使用後の安全確保のため、検査後は専用のリカバリールームでしっかりと休息していただき、血圧や酸素飽和度などのモニタリングを行っています。また、鎮静剤の効果が完全に切れるまでは、ご家族の方に付き添っていただくようお願いしています。

どうですか?鎮静剤を使った内視鏡検査に少し興味が湧いてきましたか?
経口・経鼻内視鏡と鎮静剤の組み合わせ
内視鏡検査には、口から挿入する「経口内視鏡」と鼻から挿入する「経鼻内視鏡」があります。それぞれに特徴があり、鎮静剤との組み合わせによって、さらに快適な検査が可能になります。
経口内視鏡と鎮静剤
経口内視鏡は、口からスコープを挿入する従来の方法です。スコープの直径は約8.9~10mmで、画質や機能性に優れています。しかし、スコープが舌の根元に触れることで嘔吐反射が起こりやすく、多くの方が不快感を感じます。
経口内視鏡に鎮静剤を組み合わせると、この嘔吐反射による不快感をほとんど感じることなく検査を受けることができます。鎮静状態では反射が抑制されるため、スコープの挿入もスムーズに行えます。
当院では、経口内視鏡検査の際に、患者さんの状態に合わせて鎮静剤の量を0.1mg(1gの1万分の1)単位で細かく調整しています。これにより、必要最小限の薬量で効果的な鎮静を実現し、副作用のリスクも最小限に抑えています。
経鼻内視鏡と鎮静剤
経鼻内視鏡は、鼻からスコープを挿入する方法です。スコープの直径は約5.4mmと細く、舌の根元を通過しないため、嘔吐反射が起こりにくいという大きな利点があります。検査中に会話もできるため、初めての方でも安心感があります。
経鼻内視鏡は、鎮静剤なしでも比較的楽に受けられる方法ですが、鼻の構造によっては挿入時に痛みを感じる場合があります。また、鼻腔が狭い方では挿入が難しいこともあります。
当院では、経鼻内視鏡にも鎮静剤を組み合わせることができます。「鎮静剤で眠るのが怖い、でも楽に受けたい」という方には経鼻内視鏡を、「過去に経鼻内視鏡でもつらかった」という方には鎮静剤を併用した経鼻内視鏡を提案しています。
現在の経鼻内視鏡は技術の進歩により、以前のものと比べて視野が広く、画質も向上しています。当院では最新のハイビジョン経鼻内視鏡を導入しており、経口内視鏡と変わらない質の高い検査を提供しています。
患者さんの状態や希望に応じて、経口・経鼻の選択と鎮静剤の使用を組み合わせることで、一人ひとりに最適な検査方法を提案しています。どの方法が自分に合っているか迷われる場合は、ぜひ一度ご相談ください。
当院における無痛内視鏡検査の実際
当院では、患者さん一人ひとりの状態や希望に合わせた内視鏡検査を提供しています。特に「無痛内視鏡検査」は多くの患者さんに選ばれており、検査への恐怖心を軽減する大きな助けとなっています。
検査の流れと所要時間
鎮静剤を使用した内視鏡検査の流れは以下のようになります:
- 問診・説明:検査の内容や鎮静剤の効果・副作用について詳しく説明します
- 前処置:胃カメラの場合は咽頭麻酔、大腸カメラの場合は前日からの食事制限と当日の下剤服用
- 鎮静剤投与:静脈に点滴を行い、鎮静剤を投与します
- 検査実施:半分眠った状態で検査を行います(胃カメラは約5-10分、大腸カメラは約15-30分)
- 回復:専用のリカバリールームで30分〜1時間程度休息していただきます
- 結果説明:鎮静剤の効果が落ち着いた後、検査結果を説明します
検査自体の所要時間は短いですが、鎮静剤の効果が完全に切れるまで安静にしていただく必要があるため、来院から帰宅までの総所要時間は2〜3時間程度を見込んでください。
安全性への取り組み
鎮静剤を使用する際の安全性確保は最も重要な課題です。当院では以下のような取り組みを行っています:
- 検査前の詳細な問診と必要に応じた検査(血液検査など)
- 患者さんの年齢・体格・既往歴に合わせた鎮静剤量の調整
- 検査中の心電図、血圧、酸素飽和度などの継続的なモニタリング
- 万一の事態に備えた救急対応の準備
- 専門の医療スタッフによる検査後のケア
当院では消化器内科専門医である院長自らが診察から検査、結果説明まですべてを担当しています。長年の経験と専門知識を活かし、安全で質の高い内視鏡検査を提供しています。

「内視鏡検査は怖い」と思っている方も多いかもしれませんが、適切な鎮静剤の使用と専門的な技術により、ほとんど苦痛を感じることなく検査を受けることが可能です。
患者さんの声と実際の体験談
当院で鎮静剤を使用した内視鏡検査を受けられた患者さんからは、様々な感想をいただいています。実際の体験談をいくつかご紹介します。
Aさん(50代女性):「以前別の病院で胃カメラを受けた時は、ずっとオエオエして本当に苦しかったです。でも今回は鎮静剤を使ったら、気がついたら終わっていて驚きました。こんなに楽に受けられるなら、定期検査も怖くないです。」
Bさん(40代男性):「大腸カメラは痛いというイメージがあって、ずっと避けていました。でも会社の健診で便潜血陽性と言われ、思い切って受けることにしました。鎮静剤のおかげで検査中のことはほとんど覚えていません。思ったより全然楽でした。」
Cさん(60代男性):「胃カメラも大腸カメラも同日で受けましたが、鎮静剤のおかげで両方とも苦痛なく終えることができました。検査後は少しふらつきがありましたが、リカバリールームでしっかり休ませてもらえたので安心でした。」
このように、多くの患者さんが鎮静剤の効果に驚き、検査への不安が軽減されたと感じています。特に、過去に辛い経験をされた方にとって、鎮静剤を使用した検査は大きな変化をもたらします。
もちろん、鎮静剤の効き方には個人差があり、「少し意識があって検査の記憶がある」という方もいれば、「完全に眠ってしまい何も覚えていない」という方もいます。いずれにしても、従来の検査と比べて苦痛が大幅に軽減されることは間違いありません。
内視鏡検査を受けるタイミングと定期検査の重要性
内視鏡検査は、消化器疾患の早期発見・早期治療において非常に重要な役割を果たします。では、どのようなタイミングで検査を受けるべきでしょうか。
検査を受けるべきタイミング
以下のような症状や状況がある場合は、内視鏡検査を検討する良いタイミングです:
- 胃の症状(胃痛・胃もたれ・吐き気など)が続く
- 胸やけや呑酸(酸っぱい液体が喉まで上がってくる感覚)が頻繁にある
- 便潜血検査で陽性反応が出た
- 血便や下血がある
- 原因不明の貧血がある
- ピロリ菌陽性と診断された
- 家族に胃がんや大腸がんの既往がある
- 過去に胃・大腸ポリープを指摘されたことがある
また、症状がなくても、40歳を過ぎたら定期的な検査をお勧めします。特に50歳以上になると、胃がんや大腸がんのリスクが高まるため、定期検査の重要性が増します。
定期検査の間隔
検査の間隔は、個人のリスク因子や前回の検査結果によって異なりますが、一般的には以下のような目安があります:
- 胃カメラ:1〜2年に1回(ピロリ菌陽性や萎縮性胃炎がある場合は1年に1回)
- 大腸カメラ:3〜5年に1回(ポリープの既往がある場合は1〜3年に1回)
当院では、患者さん一人ひとりの状態に合わせた検査計画を提案しています。定期検査の重要性をご理解いただき、無理なく継続できるよう、鎮静剤を使用した苦痛の少ない検査を提供しています。
内視鏡検査は「辛い・苦しい」というイメージがありますが、鎮静剤の使用によって、そのハードルは大きく下がっています。定期的な検査で早期発見・早期治療を実現し、健康寿命を延ばしましょう。
まとめ:安心して内視鏡検査を受けるために
内視鏡検査は消化器疾患の早期発見・早期治療に欠かせない重要な検査です。しかし、「辛い・苦しい」というイメージから、検査を避けてしまう方も少なくありません。
鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査は、このような不安や恐怖を大幅に軽減し、より多くの方に内視鏡検査を受けていただくための大きな助けとなります。
当院では、患者さん一人ひとりの状態や希望に合わせて、以下のような検査オプションを提供しています:
- 鎮静剤を使用した経口内視鏡(胃カメラ)
- 鎮静剤を使用した経鼻内視鏡(胃カメラ)
- 鎮静剤を使用した大腸内視鏡(大腸カメラ)
- 経口・経鼻の選択可能な胃カメラ
- 初診当日の内視鏡検査
- 土曜日の内視鏡検査
内視鏡検査に不安をお持ちの方、過去に辛い経験をされた方も、ぜひ一度ご相談ください。適切な鎮静剤の使用と専門的な技術により、ほとんど苦痛を感じることなく検査を受けることが可能です。
消化器疾患、特にがんは早期発見が何よりも重要です。鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査で、検査へのハードルを下げ、より多くの方に定期的な検査を受けていただくことが、私たち医療者の願いです。
健康な毎日を送るために、定期的な内視鏡検査を習慣にしましょう。当院では、患者さんの健康を誠心誠意サポートいたします。
詳しい情報や予約については、石川消化器内科・内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
下痢が3日以上続く原因とは?消化器専門医が教える受診の目安
下痢が続くとき、何が起きているのか
下痢とは、水分の多い液状の便が何回も出る状態です。多くの方が経験されるこの症状は、冷えや暴飲暴食など日常的な原因でも起こります。短期間で改善する場合は特に問題ないことが多いのですが、長期間続いたり何度も繰り返したりする場合には注意が必要です。
便の水分含有量は、硬便(70%以下)、通常便(70~80%)、軟便(80~90%)、泥状便(80~90%)、水様便(90%以上)と分類されます。下痢の症状が3日以上続く場合、単なる一過性の不調ではなく、何らかの病気のサインかもしれません。
下痢が続くと、脱水症状を引き起こしたり、体調不良の原因になったりします。特に高齢者や子どもは注意が必要です。また、下痢に加えて発熱や吐き気、体重減少などの症状がある場合は、早めに医療機関を受診することをお勧めします。

下痢が3日程度続く場合の主な原因
2~3日下痢が続いている場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。まず思い当たるのは、食べ過ぎや飲み過ぎ、食あたりです。これは下痢の原因として最も一般的なものです。
また、感染性胃腸炎も短期間の下痢の主な原因となります。ウイルスや細菌への感染によって胃腸が炎症を起こしている状態で、発熱や腹痛を伴うことがあります。
私の臨床経験では、キャンピロバクターという細菌が検出されることもしばしばあります。症状は軽いものから中等度まで、発熱のないものから39℃も出るものまで、また下痢も数日から10日間くらいとまちまちです。
このような細菌は本来そう毒力が強いものではありません。したがって、症状が発生した直前に食べたものが原因というよりは、2-3日前から1週間前に食べたものが原因ということもあるようです。
さらに、薬の副作用によって腸が炎症を起こし、下痢になることもあります。特に抗生物質は腸内細菌のバランスを崩し、下痢を引き起こすことがあります。
これらの原因による下痢は、安静、薬物療法、薬剤の変更によって、比較的短期間での症状改善が期待できます。
しかし、下痢が2日以上続く場合は、単なる食あたりではなく食中毒の可能性も考えられます。特に水のような下痢が続く場合は、医療機関を受診することをお勧めします。
1週間以上続く下痢の場合に考えられる病気
下痢が1週間以上続く場合は、より慎重な対応が必要です。多くの下痢は1週間以内に治りますが、症状が1週間以上続く場合や下痢と便秘を繰り返す場合、重大な病気の可能性があります。
1か月以上続く下痢は「慢性下痢」と呼ばれ、以下のような病気が疑われます。
過敏性腸症候群
精神的ストレスなどが原因で3か月以上にわたって、月に3日以上の腹痛や腹部の不快感がある状態です。ストレスや自律神経の乱れによって腸の働きが低下し、下痢・便秘などの症状をきたします。
過敏性腸症候群の特徴は、数ヶ月にわたって腹痛に悩まされたり、おなかの張りが続いたり、定期的に便秘と下痢を繰り返したりすることです。環境の変化などストレスで症状が出たり悪くなったりすることが特徴で、検査をしても、腸の壁の荒れやポリープなどの異常は見つかりません。
炎症性腸疾患
潰瘍性大腸炎やクローン病などが含まれます。遺伝的要素などによって大腸粘膜にびらんや潰瘍が生じ、下痢、腹痛などの症状をきたします。
潰瘍性大腸炎では、大腸の粘膜に慢性的な炎症が起こり、粘膜がただれたり潰瘍ができたりします。長期間お腹の痛みや下痢が続くことや、粘液や血液が混じった便が出ることもあります。
クローン病は、口から肛門までの消化管が炎症を起こし、びらんや潰瘍が生じます。腹痛や下痢に加えて、血液や粘液が混ざった便が出ます。
その他の疾患
虚血性腸炎は、大腸の血管性病変によって血流障害が生じ、下痢や腹痛などの症状をきたします。中高年に多い病気です。
大腸がんは、主に生活習慣の乱れによって生じ、進行すると下痢・便秘、下血などの症状をきたします。初めは何も症状がなく、気づかれにくいがんです。進行して大きくなると、便秘気味になったり下痢と便秘をくり返すようになったり、便に血が混じる、便が細くなる、体重が減ったといった症状が出たりします。
また、大腸以外の病気として慢性膵炎も下痢の原因となることがあります。膵臓で炎症が繰り返される病気で、血糖値を下げるインスリン、脂肪・タンパク質を分解する消化酵素が十分に機能せず、消化吸収が阻害されます。
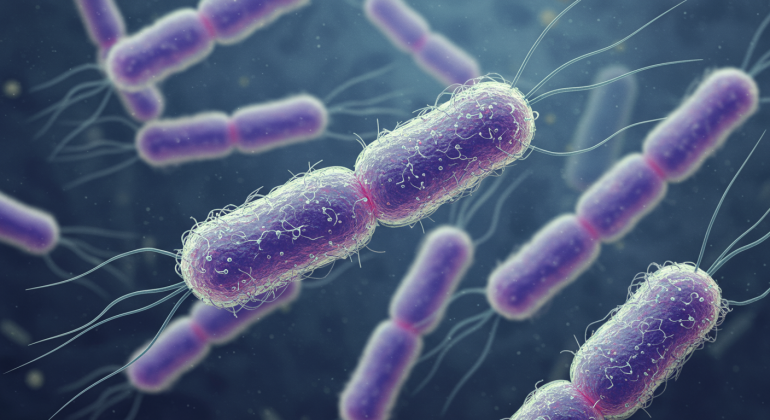
これらの病気は原因となっている疾患の治療が必要です。大腸に生じる疾患については、大腸カメラ検査で発見できます。
下痢が続く時に注意すべき危険信号
下痢の症状があっても、すぐに重大な病気と結びつけて考える人は多くありません。しかし、以下のような症状がある場合は、早めに医療機関を受診することをお勧めします。
受診を検討すべき症状
下痢だけでなく吐き気や嘔吐がある場合、下痢だけでなく熱もある場合、急に激しい下痢が出るようになった場合は注意が必要です。
特に便に血が混じっている場合は、消化管のどこかで出血が起きている可能性があります。便の色によって出血部位のおおよその目安が異なります。鮮やかな赤い便は肛門や直腸など肛門に近い大腸からの出血、暗赤色の便は奥側の大腸や小腸からの出血、黒っぽい便(タール便)は胃や十二指腸など上部消化管からの出血の可能性があります。
また、下痢とともに脱水症状がある場合、便を出した後も腹痛がある場合、時間が経過しても改善せずむしろ悪化している場合も早めに医療機関を受診してください。
さらに、体重が減ってきている場合や、軟便や細い便しか出ない場合も注意が必要です。これらは大腸がんなどの重大な疾患のサインである可能性があります。
下痢が続いておしっこが出ない、水分が取れていない、動けない、呼びかけに応じないといった症状がある場合は、危険な状態になっている可能性があるので救急車を呼んでください。
あなたは一人で悩んでいませんか?下痢の症状で悩んでいるなら、いつでも医療機関を受診してOKです。
無理に我慢する必要はありませんし、「何もなければ安心できる」と思って気軽に相談していただいて大丈夫です。なかには重大な病気が隠れているケースもあるため、特に注意すべき下痢の特徴を知っておくことが大切です。
下痢が続く時の検査と治療
下痢が続く場合、どのような検査や治療が行われるのでしょうか。まずは問診で便の形や臭い、色、暴飲暴食、食中毒の有無などを確認します。
主な検査方法
血液検査では、炎症や貧血、ミネラルバランスの異常などを確認します。便検査では、細菌やウイルス、出血の有無などを調べます。腹部エコー検査では、腸の動きや他の臓器の状態を評価します。
炎症性疾患が疑われる場合、大腸カメラ検査で大腸全体の粘膜を調べ、組織を採取して病理検査を行います。大腸カメラ検査は、鎮痛剤を投与してリラックスした状態で受けることも可能ですので、ご安心ください。
当院では、半分眠ったような状態となる鎮静剤を使用することで、痛みや恐怖をほとんど感じなくなります。体感としても「あっという間」に検査が終えられますので、以前の検査が苦痛だった、初めてなので不安という方も、安心してご相談ください。
治療方法
下痢の治療は原因によって異なります。感染性腸炎の場合は、水分補給と必要に応じて抗菌薬を使用します。炎症性腸疾患(IBD)の場合は、専門的な内服・点滴治療を行います。過敏性腸症候群(IBS)の場合は、腸の運動調整薬やストレスケアを行います。薬剤性の下痢の場合は、内服の見直しや変更を行います。
下痢になると脱水症状や栄養失調になりやすくなります。そのため、水分・栄養補給を意識的に行う必要があります。特に高齢者や子どもは注意が必要です。また、お腹を温めてリラックスし、刺激物の摂取を避け、消化の良いものを摂るようにしてください。

当院では下痢の回数が多く脱水がみられる場合や、吐き気のために水分摂取が困難な場合はすぐに点滴をします。500mlの水分にカロリーと塩分、カリウムを含む内容にします。患者さんは来院時はぐったりしていますが、点滴が終わる頃にはかなり元気になります。脱水というのは怖いものです。
下痢止めについては、下痢便の中には多数の細菌が含まれているため、どんどん下痢をした方がいいのです。大量の水分をとって、どんどん下痢をしたほうが早く治ります。人間が食中毒の時に下痢をするというのは治療の第一歩、とても合目的な防御作用なのです。ですから下痢止めなど禁忌です。
ただし大量の下痢により脱水以外に電解質を大量に失われるので、この補給が重要です。スポーツドリンクがベストです。その他としては、胃腸には固形物は入れないほうが良いでしょう。消化する能力を失っている時に食物が入ってきては、胃腸は悲鳴を上げてしまいます。結果として下痢の回数が増えることになります。牛乳も禁止です。
すこし症状が落ち着いてきたら、少量のおかゆ、うどんなどから食べ始めてよいでしょう。
まとめ:下痢が続く場合の対処法と受診の目安
下痢は多くの人が経験する症状ですが、続く場合は注意が必要です。下痢が3日以上続く場合は、単なる一過性の不調ではなく、何らかの病気のサインかもしれません。
2~3日続く下痢の主な原因は、食べ過ぎや飲み過ぎ、感染性胃腸炎、薬の副作用などです。これらは比較的短期間で改善することが多いですが、水のような下痢が2日以上続く場合は医療機関を受診することをお勧めします。
1週間以上続く下痢の場合は、過敏性腸症候群、炎症性腸疾患、虚血性腸炎、大腸がんなどの可能性があります。これらは専門的な検査と治療が必要です。
特に注意すべき症状としては、下痢に加えて発熱や吐き気、便に血が混じる、脱水症状がある、体重が減少している、などがあります。これらの症状がある場合は早めに医療機関を受診してください。
下痢の治療は原因によって異なりますが、水分・栄養補給を意識的に行い、お腹を温めてリラックスし、刺激物の摂取を避けることが基本です。
「こんなことで受診していいのかな?」と思わず、どうぞお気軽にご相談ください。当院では消化器専門医が一人ひとりの症状に丁寧に向き合い、安心して検査・治療を受けていただける体制を整えています。
下痢が続くとき、我慢するより”安心のために調べる”という選択肢を考えてみてください。それが自分の健康を守る第一歩になります。
詳しい情報や診療時間、予約方法については、石川消化器内科・内視鏡クリニックのホームページをご覧ください。皆様の健康管理を誠心誠意サポートいたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
便秘解消に効果的な10の食べ物〜消化器専門医が選ぶ即効性食材
便秘でお悩みの方は多いのではないでしょうか。日本人の約4人に1人が便秘症状を抱えているといわれています。特に現代社会では、ストレスや運動不足、食生活の乱れなどから便秘に悩む方が増えています。
便秘は単なる不快感だけでなく、腹痛や肌荒れ、集中力低下など様々な体調不良の原因にもなります。薬に頼る前に、まずは日々の食事から改善できることがたくさんあります。
今回は消化器内科専門医として長年の臨床経験から、即効性のある便秘解消食材10選をご紹介します。これらの食材を上手に取り入れることで、自然な形で腸内環境を整え、スムーズな排便につなげていきましょう。
便秘解消の基本メカニズムと食物繊維の重要性
便秘を解消するためには、まず便秘のメカニズムを理解することが大切です。便秘は大腸での水分吸収が過剰になり、便が硬くなることで起こります。また、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)が弱まることも原因の一つです。
食物繊維は便秘解消の要となる栄養素です。食物繊維には大きく分けて「不溶性食物繊維」と「水溶性食物繊維」の2種類があります。不溶性食物繊維は水分を吸収して便のかさを増やし、腸を刺激することで蠕動運動を促進します。一方、水溶性食物繊維は水分を保持して便をやわらかくする働きがあります。

最近の研究では、「発酵性食物繊維」の重要性も注目されています。これは腸内の善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える働きがあります。わかめなどの海藻類に含まれるアルギン酸は、この発酵性食物繊維に分類され、便秘解消に効果的です。
便秘解消には、1日に必要な食物繊維量(成人で20〜25g程度)をバランスよく摂取することが理想的です。ただし、急に食物繊維を増やすとかえってお腹が張ったり、ガスが溜まったりすることもあるため、少しずつ増やしていくことをおすすめします。
それでは、便秘解消に効果的な食材を具体的に見ていきましょう。
即効性が期待できる果物5選
果物には食物繊維だけでなく、自然な形で腸を刺激する成分が含まれているものが多くあります。特に即効性が期待できる果物を5つご紹介します。
1. キウイフルーツ
キウイフルーツは便秘解消の王様といっても過言ではありません。実際の臨床研究でも、キウイフルーツを摂取すると小腸や結腸内の水分が増加して胃腸を刺激し、便秘に対して効果があることが確認されています。
キウイフルーツには水溶性・不溶性両方の食物繊維がバランスよく含まれているうえ、アクチニジンという消化酵素も豊富です。この酵素がタンパク質の消化を助け、腸の動きを活発にします。
毎日1〜2個を食後に食べることで、3日程度で効果を実感できる方が多いです。皮ごと食べるとさらに食物繊維を摂取できますが、アレルギー反応が出ることもあるため注意が必要です。
2. プルーン(ドライプラム)
プルーンは古くから便秘解消に効果があるとされてきました。豊富な食物繊維に加え、ソルビトールという天然の糖アルコールが含まれており、これが腸を刺激して蠕動運動を促進します。
また、プルーンにはフェノール化合物も含まれており、これが腸内の善玉菌を増やす効果があります。朝食時に3〜4粒のプルーンを食べるか、プルーンジュースを100ml程度飲むことで効果が期待できます。
3. りんご
「一日一個のりんごは医者を遠ざける」ということわざがあるように、りんごは健康に良い果物として知られています。りんごにはペクチンという水溶性食物繊維が豊富に含まれており、これが腸内で水分を吸収して便をやわらかくします。
りんごは皮ごと食べることで不溶性食物繊維も摂取でき、より効果的です。朝食代わりにりんご1個を食べる「りんご断食」を1日行うだけでも、腸内環境が整うことがあります。
4. バナナ
バナナは完熟したものと、少し青みがかったものでは効果が異なります。完熟バナナは消化が良く、整腸作用があるため下痢気味の方に向いています。一方、少し青みがかったバナナには「レジスタントスターチ」という難消化性でんぷんが含まれており、これが腸内細菌のエサとなって善玉菌を増やし、便秘解消に役立ちます。
朝食にヨーグルトと一緒に食べると、相乗効果で腸内環境を整えることができます。
5. いちじく
いちじくは生でも乾燥させたものでも便秘解消に効果的です。特に乾燥いちじくは食物繊維が凝縮されており、少量でも効果が期待できます。また、いちじくに含まれる「フィシン」という酵素には、タンパク質を分解する作用があり、消化を助けます。
乾燥いちじくを3〜4個、寝る前に水で戻して食べると、翌朝の排便を促す効果が期待できます。
腸内環境を整える発酵食品と油
便秘解消には腸内環境を整えることが重要です。発酵食品や良質な油は腸内細菌のバランスを整え、腸の動きを活発にする効果があります。
ヨーグルト
ヨーグルトに含まれる乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスは、腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整えます。特に「生きて腸まで届く」タイプのヨーグルトを選ぶと効果的です。
毎日朝食に食べることで、1〜2週間で腸内環境が改善されることが多いです。ただし、乳糖不耐症の方は腹部膨満感などの症状が出ることもあるため、少量から始めることをおすすめします。
オリーブオイル
良質な油、特にオリーブオイルは便秘解消に効果的です。オリーブオイルに含まれる不飽和脂肪酸は腸の粘膜を保護し、便のすべりを良くする効果があります。また、腸内の善玉菌を増やし、腸の動きを活発にする働きも期待できます。
朝起きたときに空腹状態でオリーブオイルを小さじ1杯飲むと、胃腸の動きが活発になり、排便を促す効果があります。サラダにかけたり、温野菜に回しかけたりするのも効果的な摂取方法です。
どうですか?オリーブオイルを毎日取り入れるだけでも、便通に変化を感じる方は多いですよ。
納豆
納豆は日本が誇る発酵食品で、食物繊維が豊富なだけでなく、納豆菌が腸内環境を整えます。納豆に含まれるナットウキナーゼという酵素には血液をサラサラにする効果もあり、腸への血流を改善することで腸の動きを活発にします。
朝食に毎日1パックの納豆を食べることで、腸内環境が整い、便秘解消につながります。ねばねば成分が苦手な方は、納豆キムチや納豆ふりかけなど、アレンジして摂取するのも良いでしょう。
水分補給と即効性のある飲み物
便秘解消には適切な水分摂取が欠かせません。特に朝起きたときの水分補給は、腸の動きを活発にし、排便を促す効果があります。
ミネラルウォーター
便秘解消の基本は「1日1.5〜2リットルの水分摂取」です。特にマグネシウムや硫酸塩を豊富に含むミネラルウォーターは、便秘に効果があることが臨床試験でも実証されています。
マグネシウムは腸で吸収されにくいため、水分を引き寄せる浸透圧効果があります。また、腸の動きを活発にするホルモンの分泌を促したり、腸の筋肉に作用する物質を増やしたりする働きも期待できます。
2016年の臨床試験では、便秘症の方がミネラルウォーターを1日1リットル摂取することで、3週間後には排便回数が週に2回以上増加したという結果が報告されています。朝起きてすぐにコップ1杯のミネラルウォーターを飲むことで、腸が刺激され、排便を促す効果が期待できます。
トウモロコシ茶(コーン茶)
トウモロコシの実ではなく、トウモロコシのひげを乾燥させて作るトウモロコシ茶(コーン茶)には、利尿作用と緩やかな便通改善効果があります。特に夏の時期に冷やして飲むと、体を冷やし過ぎず、腸の動きを促進する効果が期待できます。
トウモロコシ自体にも豊富な不溶性食物繊維が含まれており、便のかさを増やして腸を刺激します。トウモロコシに含まれる食物繊維は腸内の善玉菌のエサとなり、発酵して短鎖脂肪酸を作り出します。この短鎖脂肪酸には腸内の悪玉菌の活動を抑え、腸の動きを活発にする効果があります。
1日2〜3杯のトウモロコシ茶を飲むことで、自然な形で便通を改善することができます。市販のティーバッグタイプを使うと手軽に取り入れられますよ。

便秘解消食材の効果的な取り入れ方
これまでご紹介した10の食材を日常生活にどのように取り入れれば良いのでしょうか。効果的な摂取方法をいくつかご紹介します。
朝食での取り入れ方
朝食は便秘解消のカギとなる重要な食事です。朝食を摂ることで胃結腸反射が起こり、腸の蠕動運動が活発になります。理想的な便秘解消朝食の例をご紹介します。
ヨーグルト100gに、バナナ半分とキウイフルーツ1個を刻んで加え、小さじ1杯のオリーブオイルとはちみつを回しかけます。これに小さじ1杯のチアシードを加えると、さらに食物繊維が豊富になります。食前にコップ1杯のミネラルウォーターを飲むことで、効果を高めることができます。
この朝食を1週間続けるだけでも、多くの方が便通の改善を実感されています。
間食での取り入れ方
間食にはドライフルーツがおすすめです。プルーン3〜4粒、ドライいちじく2粒、ナッツ類を少量組み合わせると、食物繊維と良質な油を同時に摂取できます。これを午後3時頃に食べると、夕方から夜にかけて腸が刺激され、翌朝の排便につながります。
便秘でお悩みの方は、ぜひお試しになってみませんか?
夕食での取り入れ方
夕食では消化に良い食事を心がけましょう。温かい汁物から始めると、胃腸が温まり、消化を助けます。納豆や海藻類を取り入れた和食中心の食事が理想的です。食物繊維が豊富な根菜類や緑黄色野菜を多めに摂り、良質なタンパク質と組み合わせることで、腸内環境を整えることができます。
夕食後すぐに横になるのは避け、食後2〜3時間は立位または座位を保つことで、消化を助けることができます。
便秘が改善しない場合の対処法
食事の改善を1〜2週間続けても便秘症状が改善しない場合は、他の原因が考えられます。以下のような点を確認してみましょう。
運動不足の改善
適度な運動は腸の蠕動運動を促進し、便秘解消に効果的です。特に有酸素運動やウォーキングは腸への血流を増やし、腸の動きを活発にします。毎日30分程度のウォーキングを取り入れるだけでも効果が期待できます。
また、腹筋を鍛えることで腹圧をかけやすくなり、排便がスムーズになります。朝起きたときに腹式呼吸を10回程度行うことも効果的です。
ストレス管理
ストレスは自律神経のバランスを崩し、腸の動きを鈍らせる原因となります。ストレスを感じたときは、深呼吸やストレッチなどでリラックスする時間を作りましょう。入浴時にお腹を時計回りにマッサージするのも効果的です。
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、精神状態と密接に関連しています。心と体のバランスを整えることが、便秘解消につながります。
医療機関の受診を検討すべき場合
以下のような症状がある場合は、便秘の背景に他の疾患が隠れている可能性があります。消化器内科の受診をおすすめします。
- 食事や運動の改善を1ヶ月以上続けても全く効果がない
- 便秘と下痢を繰り返す
- 便に血が混じる
- 急に便秘になった(特に50歳以上の方)
- 原因不明の腹痛や体重減少を伴う
- 家族に大腸がんや炎症性腸疾患の既往がある
これらの症状がある場合は、大腸カメラなどの検査を行い、原因を特定することが重要です。早期発見・早期治療が可能になりますので、遠慮なく医療機関を受診してください。

まとめ:継続的な食習慣改善が便秘解消の鍵
今回ご紹介した10の食材は、いずれも日常的に取り入れやすく、自然な形で便秘解消に役立つものです。特に効果が期待できるのは、キウイフルーツ、プルーン、ヨーグルト、オリーブオイル、ミネラルウォーターの5つです。
便秘解消には一時的な対策ではなく、継続的な食習慣の改善が重要です。これらの食材を毎日の食事に取り入れ、適度な運動と十分な水分摂取を心がけることで、多くの方が自然な形で便通を改善できます。
また、規則正しい生活リズムを保ち、朝食をしっかり摂ることも大切です。朝起きたときに水分を摂り、トイレに座る習慣をつけることで、自然な排便リズムを作ることができます。
便秘でお悩みの方は、まずはこれらの食材を取り入れた食事改善から始めてみてください。それでも改善が見られない場合は、消化器内科専門医への相談をおすすめします。
当院では便秘でお悩みの方に対して、食事指導や生活習慣のアドバイス、必要に応じた検査や治療を行っています。お気軽にご相談ください。
健康な腸は健康な体の基本です。毎日の食事を見直すことから、便秘解消への第一歩を踏み出しましょう。
詳しい診療内容や予約方法については、石川消化器内科・内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
胃もたれの7つの原因と即効性のある対処法〜消化器専門医が解説
胃もたれは多くの方が経験する不快な症状です。食後に胃が重く感じたり、胸やけや吐き気を伴ったりすることもあります。日常生活に支障をきたすこともある胃もたれについて、消化器内科専門医の立場から原因と対処法を詳しく解説します。
胃もたれは一過性のものであればセルフケアで改善することもありますが、長期間続く場合は何らかの疾患が隠れていることもあります。適切な対処法を知り、必要に応じて医療機関を受診することが大切です。
この記事では、胃もたれの主な原因と即効性のある対処法、そして受診を検討すべきタイミングについて詳しく解説していきます。

胃もたれとは?症状の特徴を理解しよう
胃もたれとは、食べたものが胃の中に長時間残っているように感じる不快な症状のことです。みぞおちの辺りが重苦しく感じたり、胃がムカムカしたりする感覚を伴います。
胃もたれの主な症状には以下のようなものがあります。
- 食後、胃の中にいつまでも食べ物が残っているような感覚
- みぞおちの辺りが重く、圧迫感がある
- 食事をするとすぐにお腹がいっぱいになる
- 胃にガスが溜まってお腹が張る(膨満感)
- 吐き気を伴うことがある
- げっぷが出やすくなる
これらの症状は食後に現れることが多いですが、空腹時にも感じることがあります。特に食べ過ぎた後や脂っこい食事の後に症状が強く出ることが特徴的です。
胃もたれは一時的なものであれば心配ありませんが、症状が長く続く場合は注意が必要です。それでは、胃もたれを引き起こす主な原因について見ていきましょう。
胃もたれの7つの主な原因
胃もたれはさまざまな原因で起こります。日常生活の乱れから疾患まで、幅広い要因が関わっています。ここでは主な7つの原因について解説します。
1. 食生活の乱れ
胃もたれの最も一般的な原因は食生活の乱れです。特に以下のような食習慣が胃もたれを引き起こしやすくなります。
- 食べ過ぎ・飲み過ぎ
- 脂っこい食事や消化に時間のかかる食品の摂取
- 早食い
- 不規則な食事時間
- アルコールやカフェインの過剰摂取
食べ過ぎた場合、胃に入った食物の量が多すぎて消化能力を超えてしまいます。また、脂肪分の多い食事は消化に時間がかかり、胃の中に食べ物が長く留まることになります。
特に揚げ物や脂っこい料理、ケーキなどの消化に時間のかかる食べ物は、6時間以上かけて消化されることもあります。そのため、翌日になっても胃の中に残ってしまい、胃もたれの原因となるのです。
2. ストレス
胃は精神面の影響を受けやすい臓器です。強いストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、胃の機能に影響を与えます。
ストレスにより交感神経が優位になると、胃の血管が収縮して血流が減少し、胃の運動と胃を守る粘液の分泌が減少します。一方で、副交感神経も働いて胃酸の分泌が活発になることがあります。
この状態が続くと、胃酸の働きが胃粘液の防御力を上回り、胃粘膜を痛めるようになります。その結果、胃もたれや胃痛などの症状が現れるのです。

3. 加齢による胃機能の低下
年齢を重ねると、胃の機能は徐々に低下していきます。加齢により胃の粘膜が萎縮し、胃酸や消化酵素の分泌が減少します。また、胃の筋肉の弾力性も失われ、蠕動運動(食べ物を送り出す動き)も弱まります。
これらの変化により、胃の消化能力が低下し、食べ物が胃内に長く留まりやすくなります。その結果、若い頃には問題なく食べられていた量や種類の食事でも、胃もたれを感じるようになるのです。
4. 消化器系の疾患
胃もたれが長期間続く場合は、消化器系の疾患が原因となっていることがあります。代表的な疾患には以下のようなものがあります。
- 機能性ディスペプシア
- 胃炎
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍
- 逆流性食道炎
- 胃がん
特に注意が必要なのが「胃がん」です。一般的に高齢者に多いイメージがありますが、若年層でも発症する可能性があります。ピロリ菌未感染の若年女性でもスキルス胃がんが見つかることもあるため、胃もたれが長く続く場合は医療機関を受診することをお勧めします。
5. ピロリ菌感染
ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)は胃の粘膜に感染し、胃炎や消化性潰瘍を引き起こす細菌です。日本人は特に高齢者を中心にピロリ菌感染者が多いことが知られています。
ピロリ菌に感染すると、胃粘膜や十二指腸粘膜に炎症が起き、胃もたれや胃痛などの症状が現れることがあります。また、ピロリ菌は胃がんのリスク因子としても知られています。
健康診断や人間ドックでピロリ菌感染が指摘された場合は、放置せずに医療機関を受診して適切な治療を受けることが重要です。
6. 薬剤の影響
一部の薬剤は胃粘膜に影響を与え、胃もたれの原因となることがあります。特に注意が必要なのは以下のような薬剤です。
- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):ロキソニンやボルタレンなど
- ステロイド薬
- 一部の抗生物質
- 鉄剤
これらの薬剤を服用している場合は、医師や薬剤師に相談し、胃粘膜保護剤の併用や服用方法の工夫などの対策を検討することが大切です。
7. 生活習慣の乱れ
不規則な生活習慣も胃もたれの原因となります。特に以下のような生活習慣が胃の機能に影響を与えます。
- 睡眠不足
- 運動不足
- 喫煙
- 過度の疲労
これらの生活習慣は自律神経のバランスを崩し、胃の機能低下を招きます。規則正しい生活を心がけることが、胃もたれの予防につながります。
胃もたれの即効性のある対処法
胃もたれが起きたときは、適切な対処をすることで症状を和らげることができます。ここでは即効性のある対処法をご紹介します。
1. 白湯を飲む
胃もたれを感じたら、まず白湯(お湯)を飲むことをお勧めします。冷たい水や熱すぎるお湯は胃に負担をかけるため、人肌程度の温度の白湯が適しています。
白湯を飲むことで脂肪分などの消化を助け、胃の中の食物を十二指腸に送り出す働きを促進します。ゆっくりと少量ずつ飲むことがポイントです。
2. 消化の良い食事を摂る
胃もたれが起きている時は、胃に負担をかけない消化の良い食事を心がけましょう。うどんやおかゆ、野菜のスープなど、形が柔らかく消化しやすい炭水化物中心の食事がおすすめです。
消化の良い食事を摂ることで、胃の中では消化酵素が分泌され、残っている食物の消化を助けてくれます。脂っこいものや刺激物は避け、少量ずつゆっくり食べることが大切です。
3. 軽い運動をする
胃もたれを感じたら、横になるのではなく、できるだけ立っている状態を保ち、可能であれば軽く散歩をすることをお勧めします。
寝転がっていると胃の中の食物が逆流して消化が進みにくくなります。体を動かすことで胃腸の蠕動運動も活発になり、胃から十二指腸への食物の移動を促進します。
ただし、激しい運動は逆効果になるため、軽い散歩程度にとどめましょう。
4. 上体を起こして安静にする
散歩ができないほど胃もたれがひどい場合は、上体を起こした状態で安静にしましょう。横になると胃の内容物が逆流する可能性があるため、座った状態や上半身を少し高くした状態で休むことをお勧めします。
重力を利用して胃の内容物が十二指腸や小腸へと流れるように促すことが大切です。
5. つぼ押しやマッサージ
胃の周辺のつぼを刺激することで、胃の働きを活性化させる効果が期待できます。特に「中脘(ちゅうかん)」と呼ばれるみぞおちの真ん中あたりのつぼや、「内関(ないかん)」と呼ばれる手首の内側のつぼを優しく押すと良いでしょう。
また、お腹を時計回りに優しくマッサージすることで、腸の蠕動運動を促進し、胃の内容物の移動を助ける効果があります。ただし、強く押したり激しくマッサージしたりすると逆効果になるため、優しく行うことが大切です。
6. 市販薬の利用
胃もたれがひどい場合は、市販の胃薬を利用するのも一つの方法です。胃薬には主に以下のようなタイプがあります。
- 消化酵素配合薬:消化を助ける
- 制酸剤:胃酸を中和する
- 胃粘膜保護剤:胃の粘膜を保護する
- 胃の運動を改善する薬:胃の働きを活性化する
症状に合わせて適切な薬を選ぶことが大切ですが、使用前に説明書をよく読み、用法・用量を守って服用しましょう。また、症状が長引く場合は自己判断での服用を続けず、医療機関を受診することをお勧めします。
7. 温める
胃の周りを温めることで、血行が促進され、胃の働きが活性化することがあります。カイロや湯たんぽなどをタオルで包み、みぞおちの辺りに当てると良いでしょう。
ただし、熱すぎると皮膚を傷める可能性があるため、適度な温度で行うことが大切です。また、食後すぐの温めは消化を遅らせる可能性があるため、食後1〜2時間経ってから行うことをお勧めします。
胃もたれが続く場合の受診目安
胃もたれは一過性のものであれば自己対処で改善することが多いですが、以下のような場合は医療機関を受診することをお勧めします。
1. 症状が1週間以上続く
胃もたれの症状が1週間以上続く場合は、何らかの疾患が隠れている可能性があります。自己対処で改善しない長引く胃もたれは、医療機関での精査が必要です。
2. 市販薬を服用しても症状が改善しない
市販の胃薬を適切に服用しても症状が改善しない場合は、より専門的な診断と治療が必要かもしれません。自己判断での薬の服用を続けるのではなく、医師の診察を受けることをお勧めします。
3. 以下の症状を伴う場合
胃もたれに加えて、以下のような症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
- 体重の急激な減少
- 嘔吐(特に血液が混じっている場合)
- 黒色便や血便
- 強い腹痛
- 飲み込みにくさ
- 食欲不振が続く
- 貧血症状(めまい、倦怠感など)
これらの症状は、胃がんや消化性潰瘍などの重大な疾患のサインである可能性があります。特に45歳以上の方や、胃がんの家族歴がある方は注意が必要です。

4. 精密検査を受けるべきタイミング
胃もたれの原因を特定するために、以下のような検査が行われることがあります。
- 胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)
- 血液検査(ピロリ菌検査、貧血の有無など)
- 腹部超音波検査
- CT検査
特に胃カメラ検査は、胃の粘膜の状態を直接観察できるため、胃炎や胃潰瘍、胃がんなどの診断に有用です。当院では鎮静剤を使用した無痛の胃カメラ検査を行っており、苦痛を最小限に抑えて検査を受けていただくことが可能です。
胃もたれを予防するための生活習慣
胃もたれを予防するためには、日常生活での心がけが大切です。以下のような生活習慣の改善を心がけましょう。
1. 食生活の改善
胃もたれを予防するためには、以下のような食生活の改善が効果的です。
- 腹八分目を心がけ、食べ過ぎを避ける
- 脂っこい食事や刺激物を控える
- よく噛んでゆっくり食べる
- 規則正しい時間に食事をする
- 就寝前2〜3時間は食事を避ける
- アルコールやカフェインの摂取を控える
特に夕食は寝る前に胃に負担をかけないよう、軽めの食事にすることをお勧めします。また、水分はこまめに摂取することで、消化を助ける効果があります。
2. ストレス管理
ストレスは胃の機能に大きな影響を与えます。ストレスを完全に避けることは難しいですが、上手に管理する方法を身につけることが大切です。
- 十分な睡眠をとる
- 趣味や運動でリフレッシュする時間を持つ
- 深呼吸やストレッチなどのリラクゼーション法を取り入れる
- 無理なスケジュールを避け、休息時間を確保する
自分に合ったストレス解消法を見つけ、定期的に実践することで、胃への負担を軽減することができます。
3. 適度な運動
適度な運動は胃腸の働きを活性化し、消化を促進する効果があります。ただし、食後すぐの激しい運動は避け、食後1〜2時間経ってから軽い運動を行うことをお勧めします。
ウォーキングやヨガなどの軽い運動から始め、徐々に強度を上げていくと良いでしょう。運動習慣を身につけることで、胃腸の健康だけでなく、全身の健康維持にもつながります。
4. 禁煙
喫煙は胃粘膜を刺激し、胃酸の分泌を促進するため、胃もたれや胃炎、胃潰瘍のリスクを高めます。禁煙することで、胃の健康を守ることができます。
禁煙が難しい場合は、喫煙本数を減らす、食前食後の喫煙を避けるなどの工夫をしましょう。また、禁煙外来などの専門的なサポートを利用することも一つの方法です。
まとめ:胃もたれを理解して快適な生活を
胃もたれは多くの方が経験する不快な症状ですが、その原因を理解し、適切に対処することで症状を和らげることができます。また、生活習慣の改善により、胃もたれの予防も可能です。
胃もたれの主な原因は、食生活の乱れ、ストレス、加齢による胃機能の低下、消化器系の疾患、ピロリ菌感染、薬剤の影響、生活習慣の乱れなどです。症状が長引く場合や、体重減少、嘔吐、黒色便などの症状を伴う場合は、早めに医療機関を受診することをお勧めします。
当院では、胃もたれなどの消化器症状でお悩みの方に対して、丁寧な診察と必要に応じた検査を行っています。特に内視鏡検査(胃カメラ)は、鎮静剤を使用した無痛検査を実施しており、苦痛を最小限に抑えて受けていただくことが可能です。
胃の健康は全身の健康につながります。胃もたれでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。適切な診断と治療で、快適な生活を取り戻しましょう。
詳しい情報や検査のご予約は、石川消化器内科・内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
粉瘤を放置するリスクと早期治療のメリット
粉瘤とは?基本的な知識を解説
皮膚にできるしこりや膨らみの中でも、粉瘤(ふんりゅう)は比較的よく見られる皮膚疾患です。粉瘤は表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ)とも呼ばれ、皮膚の下に袋状の構造ができて、その中に角質や皮脂が溜まることで形成される良性の腫瘍です。
粉瘤の特徴として、中央に小さな黒点(ヘソ)が見られることが多く、ここから白い粥状の内容物が排出されることがあります。この内容物は脂肪ではなく、垢(角質)のカタマリなのです。
粉瘤は年齢や性別に関係なく誰にでもできる可能性があり、全身のどこにでも発生します。特に顔、首、背中、耳の後ろなどの皮脂腺が多い部位にできやすい傾向があります。
なぜ粉瘤ができるのでしょうか?
粉瘤の明確な原因は完全には解明されていませんが、外傷や毛穴の閉塞によって表皮細胞が皮膚内部に取り込まれ、増殖することで形成されると考えられています。本来なら垢となって剥がれ落ちるはずの表皮細胞が、袋の外に出られずに蓄積され、徐々に大きくなっていくのです。

粉瘤を放置するとどうなる?主なリスク
「小さな粉瘤だから大丈夫」と放置してしまう方は少なくありません。しかし、粉瘤は自然に治ることがほとんどなく、放置すると様々なリスクが生じます。
粉瘤を放置した場合に起こりうる主なリスクを詳しく見ていきましょう。
徐々に大きくなる
粉瘤の中身である角質や皮脂は、袋の外に自然に排出されることがないため、放置すると少しずつ大きくなっていきます。初期は小さなしこりでも、時間の経過とともに成長し、野球ボール大になることもあるのです。
特に顔や首など、人目につきやすい部位にできた粉瘤が大きくなると、見た目の問題も生じてきます。自分の外見に自信を持てなくなったり、人目が気になったりするなど、精神的な負担も増えていくでしょう。
炎症を起こす(炎症性粉瘤)
粉瘤に炎症が生じると、表面が赤くなり、痛みを伴うようになります。これが炎症性粉瘤です。炎症が進行すると、赤みが拡大し、痛みも強くなります。
炎症を起こした粉瘤は、袋の内容物が膿となってブヨブヨとした感触になることもあります。腫れが限界に達すると、粉瘤が破裂して臭いドロドロの内容物が排出される場合もあるのです。
さらに、炎症に細菌感染が加わると症状は悪化し、強い痛みや腫れが生じます。このような状態になると、日常生活に支障をきたすだけでなく、緊急の切開処置が必要になることもあります。
あなたは粉瘤の炎症に悩まされたことがありますか?
悪性化するリスク
粉瘤は基本的に良性の腫瘍ですが、経過が非常に長く、大きかったり、炎症を繰り返したりした場合、ごくまれに悪性化したという報告もあります。
特に、中高年の男性の頭部、顔面、臀部の大きな粉瘤が急速に大きくなったり、表面の皮膚に傷ができたりした場合には注意が必要です。悪性化のリスクは低いものの、完全には否定できないということを覚えておきましょう。

粉瘤の早期治療がもたらすメリット
粉瘤は放置せず、早期に適切な治療を受けることで様々なメリットがあります。小さなうちに治療することで、手術の負担も少なく、回復も早くなります。
粉瘤の早期治療がもたらす主なメリットを見ていきましょう。
簡単な手術で治療できる
粉瘤が小さいうちであれば、比較的簡単な手術で治療することができます。小さな粉瘤の場合、手術時間は約5分程度と非常に短時間で済むことも多いのです。
早期の治療では、最小限の切開で済むため、患者さんへの身体的負担が軽減されます。また、小さな粉瘤であれば、くり抜き法という特殊な器具を用いた治療法も選択肢となります。
くり抜き法は、粉瘤に小さな穴をあけ、内容物を排出した後に袋を抜き取る方法です。傷口が小さく済み、手術時間も短いというメリットがあります。
一方、粉瘤が大きくなってからの治療では、切開法という方法が必要になることが多くなります。切開法では傷口が比較的大きくなる可能性があり、手術時間も長くなります。
手術痕が残りにくい
粉瘤が小さいうちに治療を行うことで、切開の範囲を最小限に抑えることができます。その結果、術後の傷跡が目立ちにくくなるというメリットがあります。
特に顔や首など、外見上重要な部位に粉瘤ができた場合には、早期治療によって美容面での影響を最小限に抑えることができます。これは、日常生活や社会活動において大きなメリットとなるでしょう。
粉瘤が大きくなってから摘出すると、どうしても傷跡が目立ちやすくなります。早期治療は見た目の観点からも非常に重要なのです。
再発予防になる
粉瘤を早期に治療することで、嚢胞を完全に除去することが可能となり、再発のリスクを大幅に減少させることができます。
炎症を起こした粉瘤は、袋が破れて内容物が周囲に漏れ出している可能性があります。このような状態では、完全に袋を取り除くことが難しくなり、再発のリスクが高まります。
早期治療を行うことで、これらの合併症を未然に防ぎ、粉瘤の完全除去がより確実になります。結果として、再発の可能性を最小限に抑えることができるのです。
粉瘤の治療方法と選択肢
粉瘤の治療には、主に「くり抜き法」と「切開法」という2つの方法があります。それぞれの特徴を理解し、自分の状態に合った治療法を選ぶことが大切です。
ここでは、粉瘤の主な治療方法について詳しく解説します。
くり抜き法
くり抜き法は、特殊な器具(デルマパンチ)を用いて粉瘤に小さな穴をあけ、その穴から粉瘤の内容物を絞り出した後、しぼんだ粉瘤の袋を抜き取る方法です。
この方法のメリットは、傷口が小さく済むため、手術時間が短く、術後の回復も早い点です。特に小さな粉瘤であれば、手術時間は約5分程度と非常に短時間で行うことができます。また、傷跡が目立ちにくいという利点もあります。
ただし、くり抜き法にはデメリットもあります。粉瘤の袋を完全に取り除けない可能性があり、その場合は再発のリスクが高まります。また、大きな粉瘤や炎症を起こしている粉瘤には適さない場合があります。
切開法
切開法は、粉瘤が大きい場合や複雑な形状をしている場合に適用される治療法です。この手術では、粉瘤の部位を切開して内部の内容物を取り除き、続いて粉瘤の袋(嚢胞)を完全に摘出します。
切開法は、特に炎症が進行しているケースや、再発を防ぐために確実に粉瘤を除去する必要がある場合に選択されることが多い治療方法です。
この方法では、傷口が比較的大きくなる可能性がありますが、袋を完全に除去することで再発のリスクを大幅に低減できます。また、大きな粉瘤や複雑な形状の粉瘤にも対応できるというメリットがあります。
炎症性粉瘤の治療
炎症を起こして膿がたまってしまった炎症性粉瘤に対しては、まず切開排膿という処置が必要になることがあります。これは、皮膚を切開して、たまっている膿を排出する処置です。
炎症が強くなり膿がたまってしまった状態では、膿を物理的に取り除かない限り炎症の改善が見込めません。切開排膿は局所麻酔で行いますが、切開部分は縫わずに開放したままにします。
切開排膿はあくまで応急処置であり、炎症が落ち着いた後に改めて粉瘤の摘出手術を行うことになります。そのため、感染のない場合に比べ治療期間が長くなります。

粉瘤の予防と日常生活での注意点
粉瘤の原因が明確に分かっていないため、確実な予防方法も確立されていません。しかし、日常生活での注意点を守ることで、粉瘤のリスクを減らせる可能性があります。
ここでは、粉瘤の予防と日常生活での注意点について解説します。
清潔な肌を保つ
粉瘤は皮下に角質や皮脂が溜まったものであるため、毎日お風呂に入って肌を清潔に保つことは大切です。特に、皮脂腺が多い顔や首、背中などは丁寧に洗いましょう。
ただし、過剰な洗浄や強いこすり洗いは肌を傷つけ、かえって皮膚トラブルの原因になることもあります。適切な洗浄料を使い、優しく洗うことを心がけましょう。
粉瘤を見つけたら早めに受診
皮膚にしこりを見つけたら、それが粉瘤かどうかにかかわらず、早めに皮膚科や形成外科を受診することをおすすめします。早期発見・早期治療が、治療の負担を軽減し、合併症のリスクを減らす鍵となります。
「ニキビだから大丈夫」と自己判断せず、医師の診断を受けることが大切です。特に、しこりが徐々に大きくなっている場合や、赤みや痛みがある場合は、すぐに受診しましょう。
粉瘤を自分で潰さない
粉瘤を自分で潰そうとすると、感染のリスクが高まり、炎症が悪化する可能性があります。また、袋を完全に取り除くことができないため、再発の原因にもなります。
粉瘤を見つけたら、決して自分で潰さず、専門医の診察を受けましょう。適切な治療を受けることで、安全かつ確実に粉瘤を取り除くことができます。
まとめ:粉瘤の早期治療で健やかな肌を保とう
粉瘤は放置すると徐々に大きくなり、炎症を起こすリスクが高まります。炎症を起こすと痛みを伴い、日常生活に支障をきたす可能性もあります。また、まれに悪性化するリスクもあります。
一方、早期に治療することで、簡単な手術で済み、手術痕も残りにくく、再発のリスクも低減できるというメリットがあります。粉瘤の治療には主に「くり抜き法」と「切開法」があり、粉瘤の大きさや状態に応じて適切な方法が選択されます。
皮膚にしこりを見つけたら、自己判断せず、早めに専門医を受診することが大切です。適切な診断と治療を受けることで、健やかな肌を保つことができるでしょう。
当院では、消化器内科・内視鏡専門医である院長が診察を担当し、患者様一人ひとりに合わせた丁寧な診療を心がけています。皮膚のお悩みも含め、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
詳しい情報や予約については、石川消化器内科・内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。皆様の健康をサポートするために、誠心誠意対応させていただきます。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
粉瘤は自宅ケアで改善できる?医師が教える真実
粉瘤とは?皮膚の下に潜む袋状の腫瘤
皮膚の下にできる小さなしこり。気づいたときには少し大きくなっていて、触ると硬く、時に痛みを感じることもある。これが「粉瘤(ふんりゅう)」と呼ばれる皮膚のできものです。
粉瘤は医学的には「表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ)」または「アテローム」とも呼ばれ、皮膚の下に袋状の構造ができ、その中に皮脂や角質(垢)が溜まることで形成される良性の腫瘍です。
この袋の中には、皮脂腺からの分泌物や垢が溜まっているため、万が一袋が破けると、チーズと汗が混じったような強烈な臭いがすることもあります。中からは白いクリームのような液体や、カッテージチーズのようなボロボロしたものが出てくることが特徴です。
粉瘤は全身どこにでもできる可能性がありますが、特に皮脂腺が多い顔、首、背中、耳の後ろなどにできやすい傾向があります。サイズは数ミリから数センチまでさまざまで、放置すると徐々に大きくなることが多いです。
通常は痛みを伴わないことが多いですが、感染すると赤く腫れて痛みやかゆみを伴うことがあります。このような状態になると、中に溜まった内容物がにじみ出たり、破裂したりすることもあるのです。

粉瘤の原因と発生メカニズム
なぜ粉瘤ができるのか、その原因について詳しく見ていきましょう。粉瘤の発生には複数の要因が関わっています。
まず最も一般的な原因は「毛穴の詰まり」です。私たちの皮膚には皮脂を分泌する皮脂腺が存在し、通常は毛穴を通して皮脂が排出されます。しかし、何らかの理由で毛穴が詰まると、皮脂が排出されずに皮膚の中に溜まり、それをきっかけとして粉瘤が形成されるのです。
次に「皮膚の摩擦や刺激」も原因となります。衣服などで摩擦や圧力など刺激が多くなる部分は、皮膚にダメージを受けやすく、粉瘤が発生しやすいと言われています。首、背中、顔などは粉瘤ができやすい部位です。
また、「感染や炎症の影響」も見逃せません。ニキビや皮膚の炎症が悪化し、皮膚の中で角質が異常に分泌されてしまうことがあります。この角質が嚢胞内にたまり、粉瘤の原因となることがあるのです。
「ホルモンバランスの乱れ」も関係しています。思春期やストレス、ホルモンの変化によって皮脂の分泌が増えると、毛穴が詰まりやすくなり、粉瘤ができるリスクが高まります。
さらに、「先天的な要因」も考えられます。一部の粉瘤は遺伝的な要因や先天的な皮膚の構造により、幼少期から形成されやすいとされています。生まれつき皮脂腺が詰まりやすい傾向にある人は粉瘤ができやすいことがあります。
粉瘤は男性に多く見られ、特に20歳から60歳の間で発症することが多いことがわかっています。これは、皮脂腺からの分泌が盛んに行われ、新陳代謝が活発な時期であることが関係していると考えられます。
自宅でできる粉瘤のケア方法
「粉瘤は自宅でケアできるのか?」これは多くの方が抱く疑問です。結論から言うと、粉瘤を完全に治すには医療機関での適切な処置が必要ですが、症状を悪化させないための自宅ケアは可能です。
軽度の粉瘤で炎症や痛みが少ない場合には、自宅ケアを取り入れることで症状が悪化するのを防ぐことができます。ただし、これらのケアは「治療」ではなく「悪化防止」のためのものであることを理解しておきましょう。
清潔に保つ
粉瘤ができた部分は、これ以上毛穴詰まりを防ぐために清潔に保つことが大切です。優しく洗い、汗や汚れをためないようにしましょう。
刺激の強い石鹸や洗顔料は避け、敏感肌用の製品などを使用するのがおすすめです。ゴシゴシと強くこすると炎症を悪化させる可能性があるので、優しく丁寧に洗うことを心がけてください。
保湿ケア
乾燥した肌は皮脂の分泌が活発になりやすいため、適度な保湿を心がけます。特に顔や首のような皮膚が薄い部分は、保湿クリームを使ってケアするとよいでしょう。
ただし、油分の多すぎる製品は毛穴を詰まらせる原因になることがあるため、「ノンコメドジェニック」(毛穴を詰まらせない)と表示された製品を選ぶことをお勧めします。
刺激を避ける
粉瘤を無理に押し出したり、触ったりすることは絶対に避けましょう。圧迫や刺激により炎症が悪化し、感染や膿が溜まってしまう場合があるからです。
また、粉瘤のある部分を強く擦ったり、きつい衣類で圧迫したりすることも避けるべきです。特に首や背中など、衣類が擦れやすい部分にある粉瘤は注意が必要です。
これらの自宅ケアを行っても症状が軽減しない場合や、痛みや腫れが強くなった場合には、すぐに医療機関を受診しましょう。自己判断での対処には限界があります。

粉瘤に対する医療機関での治療法
自宅ケアには限界があり、粉瘤を根本的に治すためには医療機関での適切な治療が必要です。粉瘤が大きくなったり、炎症や膿がある場合には、特に医療機関での治療が重要になります。
ここでは、医療機関で行われる主な治療法について解説します。
切開排膿
粉瘤が炎症を起こし膿が溜まっている場合には、切開して排膿します。局所麻酔を用いて切開し、膿を排出して炎症を和らげます。
ただし、この治療法は一時的なもので、嚢胞自体が残っている場合には再発の可能性があります。切開排膿は応急処置的な治療であり、約3ヶ月後に粉瘤の芯が残っていないかを確認し、改めて袋ごと完全に除去することが重要です。
腫瘍摘出手術
再発を防ぐためには、嚢胞(袋状の部分)を完全に取り除くことが大切です。局所麻酔のもと、皮膚を切開して嚢胞を取り出す手術を行います。嚢胞を取り除くことで、粉瘤の再発リスクが軽減されます。
手術方法には主に「くり抜き法」と「切除縫縮法」があります。
くり抜き法は、皮膚の下にできた粉瘤(嚢胞)を完全に除去する手術です。通常は局所麻酔を使用し、専用のパンチを用いて粉瘤を慎重にくり抜き、嚢胞の袋ごと除去します。傷跡が目立ちにくいというメリットがありますが、完全に袋を取り除けない場合は再発のリスクがあります。
一方、切除縫縮法は粉瘤の標準的な治療法です。通常は局所麻酔を使用し、患部の大きさや深さ・種類に応じて切除範囲を決定し、中央の毛穴を含んだ皮膚を葉っぱの形に切り取り摘出します。確実に袋を取り除けるため再発のリスクが低いですが、粉瘤の大きさによっては同じ長さの線の傷跡が残る場合もあります。
レーザー治療
レーザーを使って嚢胞を取り除く治療法も限定的ですが、効果的な場合があります。切開手術よりも傷跡が小さくなりますが、粉瘤の状態や大きさによってはレーザー治療をできないこともあります。また保険は適用されません。
どの治療法が最適かは、粉瘤の大きさや状態、場所によって異なります。医師とよく相談し、適切な治療を選択することが大切です。

粉瘤の再発を防ぐための予防法
粉瘤は一度治療しても、正しいケアができていなければ再発しやすい皮膚トラブルです。ここでは、粉瘤を繰り返さないための予防法について解説します。
1. 皮膚を清潔に保つ
毎日のシャワーや入浴で皮膚を清潔に保ちましょう。特に汗をかきやすい部位や皮脂の分泌が多い部位は丁寧に洗い、皮脂や汚れが毛穴に詰まるのを防ぎます。
ただし、ゴシゴシと強くこすると皮膚を傷つけ、かえって炎症を引き起こす可能性があります。優しく丁寧に洗うことを心がけてください。
2. 適切な保湿を心がける
乾燥した肌は皮脂の過剰分泌を促し、毛穴詰まりの原因になります。適切な保湿ケアを行い、肌の水分バランスを整えましょう。
特に季節の変わり目や冬場など、肌が乾燥しやすい時期は入念な保湿が大切です。ただし、油分の多すぎる製品は避け、「ノンコメドジェニック」表示のある製品を選びましょう。
3. 摩擦や圧迫を避ける
きつい衣類や首回りがきつい服は、皮膚への摩擦や圧迫を増やし、粉瘤の原因になることがあります。特に粉瘤ができやすい首や背中などは、ゆったりとした服を選び、摩擦や圧迫を減らしましょう。
また、長時間同じ姿勢でいることも特定の部位への圧迫につながります。定期的に姿勢を変えたり、ストレッチをしたりして、血行を促進させることも大切です。
4. 規則正しい生活とバランスの良い食事
不規則な生活習慣やストレスは、ホルモンバランスを乱し、皮脂の過剰分泌を引き起こすことがあります。規則正しい生活と十分な睡眠を心がけましょう。
また、脂っこい食事や糖分の多い食事は皮脂分泌を増やす可能性があります。野菜や果物、良質なタンパク質を中心としたバランスの良い食事を心がけることも、肌の健康維持には重要です。
5. 定期的な皮膚チェック
小さな粉瘤は自覚症状がないことも多いため、定期的に皮膚の状態をチェックしましょう。早期発見できれば、小さいうちに適切な処置を受けることができます。
特に以前粉瘤ができたことがある部位は、再発の可能性があるため、注意深く観察することが大切です。何か気になる変化があれば、早めに皮膚科を受診しましょう。

粉瘤に関する誤解と真実
粉瘤に関しては、さまざまな誤解や間違った情報が広まっていることがあります。ここでは、よくある誤解と真実について解説します。
誤解1:「粉瘤は自分で潰せば治る」
粉瘤を自分で潰すことは絶対にやめましょう。確かに内容物を出すことはできますが、袋(嚢胞壁)が残っていれば再発します。また、不適切な処置による感染リスクもあります。
真実は、粉瘤を根本的に治すには、医療機関で袋ごと完全に摘出する必要があります。自己処置では完治せず、かえって症状を悪化させる可能性があるのです。
誤解2:「粉瘤はすべて同じ」
粉瘤にはさまざまな種類や状態があります。大きさ、場所、炎症の有無などによって、適切な治療法も異なります。
真実は、粉瘤の状態に応じた適切な治療が必要です。小さな粉瘤と大きな粉瘤、炎症を起こしている粉瘤と起こしていない粉瘤では、治療アプローチが異なります。医師の診断に基づいた治療を受けることが大切です。
誤解3:「粉瘤は必ず手術が必要」
小さく、症状がない粉瘤の場合、必ずしも即座に手術が必要というわけではありません。医師と相談の上、経過観察という選択肢もあります。
真実は、粉瘤の大きさ、場所、症状の有無によって、治療の緊急性や必要性が変わります。ただし、完全に治すためには最終的には手術が必要になることが多いです。
誤解4:「粉瘤は美容の問題だけ」
粉瘤は単なる見た目の問題ではありません。放置すると大きくなったり、炎症を起こしたりする可能性があります。
真実は、粉瘤は医学的な皮膚疾患であり、適切な治療が必要です。特に炎症を起こした場合は痛みを伴い、日常生活に支障をきたすこともあります。健康保険も適用される医学的治療の対象です。
誤解5:「粉瘤の手術は高額」
粉瘤の手術は、医学的治療として健康保険が適用されるため、自己負担額は比較的抑えられます。
真実は、健康保険が適用される場合の医療費自己負担割合は、年齢や所得に応じて異なりますが、一般的には3割です。粉瘤の切除手術における自己負担額の目安は、保険診療での全国平均で8,200円(3割負担換算)程度と報告されています。個別のケースでは数千円から2万円程度となることが多いようです。

粉瘤が疑われる場合の受診タイミング
粉瘤が疑われる場合、どのタイミングで医療機関を受診すべきでしょうか。以下のような症状や状況がある場合は、早めに皮膚科を受診することをお勧めします。
受診が必要なケース
まず、「急に大きくなった」「痛みや赤みが出てきた」という場合は要注意です。粉瘤が炎症を起こしている可能性があり、早めの処置が必要です。炎症を起こした粉瘤は痛みを伴い、触れると熱を持っていることもあります。
また、「自分で潰してしまった」という場合も受診が必要です。自己処置によって感染リスクが高まっている可能性があります。医師による適切な処置を受けましょう。
「大きさが気になる」「目立つ場所にある」という場合も、医師に相談するとよいでしょう。特に顔や首など、人目につきやすい場所にある粉瘤は、早めに処置することで目立ちにくい傷跡で済むことがあります。
さらに、「以前に粉瘤の手術をしたが再発した」という場合も受診が必要です。前回の手術で袋が完全に取り除かれていなかった可能性があります。
医療機関選びのポイント
粉瘤の治療を受ける際は、皮膚科や形成外科を選ぶとよいでしょう。特に粉瘤の手術実績が豊富な医療機関を選ぶことで、再発リスクの低い適切な治療を受けられる可能性が高まります。
受診の際は、いつから症状があるか、大きさの変化、痛みの有無などを医師に伝えましょう。また、以前に粉瘤の治療を受けたことがある場合は、その情報も伝えることが大切です。
粉瘤は放置すると大きくなったり、炎症を起こしたりする可能性があります。気になる症状がある場合は、自己判断せず、専門医に相談することをお勧めします。
まとめ:粉瘤との上手な付き合い方
粉瘤は皮膚の下に袋状の構造ができ、その中に皮脂や角質が溜まることで形成される良性の腫瘍です。顔、首、背中など、皮脂腺が多い部位にできやすく、放置すると徐々に大きくなる傾向があります。
粉瘤の原因としては、毛穴の詰まり、皮膚の摩擦や刺激、感染や炎症の影響、ホルモンバランスの乱れ、先天的な要因などが考えられます。特に20歳から60歳の男性に多く見られます。
自宅でのケアとしては、患部を清潔に保つ、適切な保湿を心がける、刺激を避けるなどが挙げられますが、これらは「治療」ではなく「悪化防止」のためのものです。粉瘤を根本的に治すには、医療機関での適切な処置が必要です。
医療機関での主な治療法には、切開排膿、腫瘍摘出手術(くり抜き法、切除縫縮法)、レーザー治療などがあります。どの治療法が最適かは、粉瘤の大きさや状態、場所によって異なりますので、医師とよく相談して決めることが大切です。
粉瘤の再発を防ぐためには、皮膚を清潔に保つ、適切な保湿を心がける、摩擦や圧迫を避ける、規則正しい生活とバランスの良い食事を心がける、定期的な皮膚チェックを行うなどの予防法があります。
粉瘤に関する誤解も多く、「自分で潰せば治る」「すべての粉瘤は同じ」「必ず手術が必要」「美容の問題だけ」「手術は高額」などがありますが、これらは正しくありません。粉瘤は医学的な皮膚疾患であり、適切な治療が必要です。
粉瘤が疑われる場合は、急に大きくなった、痛みや赤みが出てきた、自分で潰してしまった、大きさが気になる、目立つ場所にある、以前の手術部位に再発したなどの症状や状況がある場合は、早めに皮膚科や形成外科を受診しましょう。
粉瘤は適切な治療と予防法で上手に付き合うことができます。気になる症状がある場合は、自己判断せず、専門医に相談することをお勧めします。
当院では、消化器内科・内視鏡専門医として皆様の健康をサポートしています。皮膚のお悩みも含め、どんな小さな症状でもお気軽にご相談ください。
詳しい情報や診療時間については、石川消化器内科・内視鏡クリニックのホームページをご覧ください。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
雇入れ時健康診断とは?義務と実施方法を完全解説
雇入れ時健康診断の基本と法的義務
雇入れ時健康診断とは、企業が新たに従業員を雇い入れる際に実施が義務付けられている健康診断です。労働安全衛生法に基づき、労働者の安全と健康を守るために設けられた重要な制度となっています。
この健康診断は、新しく雇用する従業員の健康状態を把握し、適切な職場配置や健康管理に役立てることが目的です。単なる形式的な手続きではなく、従業員の健康を守り、企業の安全配慮義務を果たすための重要なステップなのです。
雇入れ時健康診断は、労働安全衛生規則第43条において「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない」と明確に規定されています。この規定に違反した場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰則が科される可能性もあるため、企業側は確実に実施する必要があります。
消化器内科医としての経験から申し上げると、健康診断は病気の早期発見・早期治療につながる重要な機会です。特に新たに職場に入る方々にとっては、これから長く働く環境で健康を維持するための第一歩となります。

雇入れ時健康診断の対象者と実施時期
雇入れ時健康診断の対象となるのは「常時使用する労働者」です。これは正社員だけでなく、一定の条件を満たすパートタイマーやアルバイトも含まれます。
具体的には、以下のいずれかに該当し、かつ1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である場合は、健康診断を実施する必要があります。
- 雇用期間の定めのない者
- 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定の者
- 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用されている者
例えば、正社員の労働時間が週40時間の企業であれば、週30時間以上勤務するパートタイマーやアルバイトも対象となります。なお、4分の3未満であっても、週の所定労働時間が通常の労働者のおおむね2分の1以上であれば、健康診断の実施が望ましいとされています。
実施時期については、「雇入れるとき」と規定されていますが、具体的には雇入れの直前または直後が適切とされています。明確な期限は定められていませんが、雇入れ前後3ヶ月以内の実施が望ましいと考えられます。
臨床現場で多くの健康診断を担当してきた経験から言えることですが、入社直後は業務に慣れることで精一杯になりがちです。そのため、可能であれば入社前、あるいは配属前に健康診断を済ませておくことをお勧めします。
また、入社前3ヶ月以内に医師による健康診断を受けた結果を提出できる場合は、その項目については雇入れ時健康診断を省略することができます。これは求職者の負担軽減にもつながる重要なポイントです。
雇入れ時健康診断の検査項目と特徴
雇入れ時健康診断では、労働安全衛生規則第43条に基づき、以下の11項目について検査を行うことが義務付けられています。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無)
- 心電図検査
これらの項目は、年に1回行われる定期健康診断とほぼ同じですが、いくつか重要な違いがあります。
まず、定期健康診断では医師の判断により一部の検査項目を省略できますが、雇入れ時健康診断では全項目の実施が必須です。また、定期健康診断では胸部エックス線検査に加えて喀痰検査が含まれることがありますが、雇入れ時健康診断では喀痰検査は含まれません。
消化器内科医の立場から特に注目すべきは、肝機能検査や血中脂質検査です。これらの検査結果は、脂肪肝や脂質異常症などの生活習慣病の早期発見につながります。また、血糖検査は糖尿病のリスク評価に重要で、尿検査は腎機能の基本的な評価ができます。
健康診断の実施方法としては、事業所が医療機関と契約して一斉に受診させる方法と、従業員が個別に医療機関で受診する方法があります。個別受診の場合は、検査項目の漏れや受診遅延が生じやすいため、企業側は項目や期日の通知だけでなく、予約や受診状況の確認など細やかなフォローが必要です。

雇入れ時健康診断の目的と位置づけ
雇入れ時健康診断の主な目的は、労働者を適切な職場に配置するための情報収集と、入社後の健康管理の基礎データを得ることにあります。ここで非常に重要なのは、雇入れ時健康診断の結果を採用の判断材料にしてはならないという点です。
厚生労働省は「採用選考時に同規則を根拠として採用可否決定のための健康診断を実施することは適切さを欠くもの」としています。つまり、企業の採用担当者が求職者の健康診断結果をみて、それだけを理由に不採用にすることは不適切な行為とされています。
雇入れ時健康診断は労働安全衛生法に基づく一般健康診断の一つです。一般健康診断には、雇入れ時健康診断のほかに、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便などがあります。
医師として強調したいのは、健康診断は単なる法的義務の履行ではなく、従業員の健康を守るための重要な機会だということです。特に生活習慣病は初期には自覚症状がほとんどないため、健康診断による早期発見が非常に重要です。
また、雇入れ時健康診断の結果は、その後の定期健康診断と比較することで、職場環境が従業員の健康に与える影響を評価する基準にもなります。このように、雇入れ時健康診断は従業員の健康管理における出発点として重要な位置を占めているのです。
雇入れ時健康診断の費用と実施手順
雇入れ時健康診断の費用は、全額を事業者が負担することになっています。これは公的医療保険の対象外であり、いわゆる「保険がきかない検査」となるためです。企業は労働者に雇入れ時健康診断の費用を請求したり負担させたりしてはいけません。
健康診断の費用は医療機関によって異なりますが、一般的には1人あたり1万円前後が相場です。検査項目の追加や詳細な検査を行う場合は、さらに費用が増加することもあります。
雇入れ時健康診断の実施手順としては、まず対象となる従業員を特定し、健康診断を実施する医療機関を選定します。次に、従業員に健康診断の日程や場所、準備事項などを通知します。健康診断実施後は、結果を記録し、必要に応じて医師の意見を聴取します。
私が院長を務める医療機関でも企業の健康診断を多数実施していますが、スムーズな実施のためには事前の準備が重要です。特に、従業員への説明や当日の流れの確認など、細かな配慮が必要になります。
また、健康診断の結果は「健康診断個人票」として5年間保存することが義務付けられています。近年はデータでの保存も認められており、2025年1月からは健康診断結果報告の電子申請が義務化されることもあり、データ管理の重要性が高まっています。
健康診断結果の取り扱いには注意が必要です。健康診断の結果は「要配慮個人情報」に該当するため、適切な管理が求められます。特に、第三者への提供には本人の同意が必要となります。

雇入れ時健康診断後の措置と注意点
雇入れ時健康診断を実施した後は、いくつかの措置を講じる必要があります。まず、健康診断の結果を受診者全員に通知することが義務付けられています。また、健康診断の結果に基づいて、医師等からの意見を聴取し、必要に応じて就業上の措置を講じなければなりません。
特に注意が必要なのは、健康診断で異常所見が認められた場合の対応です。二次検査が必要と判断された従業員には、再検査を受けるよう促すことが重要です。
雇入れ時健康診断を実施した場合、その後1年間は定期健康診断を省略することができます。ただし、特定業務に従事する労働者については、配置後6ヶ月以内に特殊健康診断を実施する必要があります。
消化器内科医としての経験から申し上げると、健康診断で異常所見が見つかった場合、早期に専門医を受診することが非常に重要です。特に消化器系の異常は、早期発見・早期治療により予後が大きく改善することが多いです。
また、企業側としては、健康診断の結果を単に記録するだけでなく、従業員の健康管理に積極的に活用することが望ましいです。例えば、生活習慣病のリスクが高い従業員には、保健指導を行うなどの支援が効果的です。
健康診断の結果は、個人の健康状態を示す重要な情報であると同時に、企業全体の健康課題を把握するためのデータでもあります。従業員の健康状態を分析し、職場環境の改善や健康増進施策の立案に活用することで、企業全体の健康レベルの向上につなげることができます。
まとめ:雇入れ時健康診断の重要性と適切な実施
雇入れ時健康診断は、労働安全衛生法に基づく企業の義務であり、従業員の健康管理の第一歩となる重要な制度です。常時使用する労働者を雇い入れる際には、11項目の法定検査を含む健康診断を実施し、その結果を適切に管理・活用することが求められます。
実施対象は正社員だけでなく、一定条件を満たすパートタイマーやアルバイトも含まれます。実施時期は雇入れの前後3ヶ月以内が望ましく、費用は全額事業者負担となります。
雇入れ時健康診断の目的は採用判断ではなく、適正配置や健康管理にあります。健康診断の結果は5年間保存する義務があり、2025年1月からは結果報告の電子申請が義務化されます。
医師として強調したいのは、健康診断は単なる法的義務の履行ではなく、従業員の健康を守るための重要な機会だということです。特に生活習慣病は初期には自覚症状がほとんどないため、健康診断による早期発見が非常に重要です。
企業と従業員が共に健康管理の重要性を認識し、雇入れ時健康診断を適切に実施・活用することで、働きやすい職場環境の構築と生産性の向上につなげることができるでしょう。
健康診断でお悩みの方は、ぜひ専門医にご相談ください。当院では各種健康診断も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
詳細は石川消化器内科・内視鏡クリニックのホームページをご覧ください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
悩まされる慢性便秘!根本改善するための5つの方法を消化器内科医が解説
慢性便秘とは?医学的に正しい理解から始めよう
便秘は誰もが一度は経験したことがある身近な症状です。しかし、その多くは一時的なものであり、生活習慣の改善や市販薬で解消されることがほとんどです。
ところが、3ヶ月以上にわたって症状が続く「慢性便秘症」となると話は別です。これは単なる不快な症状ではなく、生活の質を著しく低下させ、さらには様々な健康リスクをもたらす可能性がある病態なのです。近年の研究では、慢性便秘は長期生存率の低下や冠動脈疾患、パーキンソン病との関連も示唆されています。
私は消化器内科医として多くの便秘に悩む患者さんを診てきましたが、実は便秘で医療機関を受診する方は全体の5%にも満たないというデータがあります。多くの方が「恥ずかしい」「大したことない」と思い、自己流の対処を続けているのが現状です。
慢性便秘症の定義は、「3ヶ月以上にわたり、週に3回以下の排便、または排便時の過度のいきみ、硬い便、残便感、直腸肛門の閉塞感、排便のための用手的補助が必要など、複数の症状が見られる状態」です。これらの症状が1つでもあれば、慢性便秘症の可能性を考える必要があります。

便秘が引き起こす5つの健康リスク
便秘は単なる不快な症状ではありません。長期間放置すると、思いもよらない健康リスクをもたらします。
まず第一に、慢性便秘は腸内環境の悪化を招きます。便が腸内に長時間滞留することで腸内細菌のバランスが崩れ、有害物質が産生されやすくなります。これが腸内環境の悪化を招き、免疫機能の低下にもつながるのです。実際、最新の研究では腸内細菌叢の乱れが様々な全身疾患と関連していることが明らかになっています。
第二に、便秘は痔や肛門裂傷などの肛門疾患のリスクを高めます。硬い便を排出しようと強くいきむことで、肛門周囲の血管に負担がかかり、痔核(いわゆる「いぼ痔」)や裂肛(肛門の切れ目)を引き起こすことがあります。これらは出血や激しい痛みを伴い、日常生活に大きな支障をきたします。
第三に、慢性便秘は大腸憩室症のリスク因子です。腸管内の圧力が高まることで腸壁が外側に押し出され、小さな袋状の突出(憩室)が形成されます。憩室自体は無症状のことが多いですが、炎症を起こすと(憩室炎)激しい腹痛や発熱を引き起こし、時に入院治療が必要になることもあります。
さらに、長期的な便秘は大腸がんのリスク因子である可能性も指摘されています。便の滞留時間が長くなることで、発がん物質と腸粘膜の接触時間が増加するためと考えられています。
最後に、意外かもしれませんが、便秘は心血管疾患のリスクを高める可能性があります。排便時の過度のいきみは血圧を急上昇させ、心臓に負担をかけます。特に高齢者や心疾患のある方は注意が必要です。
これらのリスクを考えると、慢性便秘は単なる生活の質の問題ではなく、健康上の重要な課題であることがわかります。
便秘の原因を知り、タイプ別に対策を立てる
便秘を効果的に改善するためには、まず自分の便秘のタイプを知ることが重要です。便秘には大きく分けて3つのタイプがあります。
一つ目は「機能性便秘」です。これは最も一般的なタイプで、腸の動きが鈍くなる「腸管運動機能低下型」と、排便時に力を入れても便が出にくい「排便困難型」に分けられます。生活習慣の乱れ、ストレス、運動不足、食物繊維の摂取不足などが主な原因です。
二つ目は「器質性便秘」です。これは大腸がんや腸閉塞、腸管狭窄など、腸に器質的な異常がある場合に起こります。突然の便通異常、血便、体重減少などの症状を伴う場合は、この可能性を考える必要があります。
三つ目は「薬剤性便秘」です。鎮痛薬(特にオピオイド)、抗うつ薬、抗コリン薬、抗ヒスタミン薬、降圧薬など、様々な薬が便秘を引き起こす可能性があります。特に高齢者は複数の薬を服用していることが多く、薬剤性便秘のリスクが高まります。
便秘のタイプによって適切な対処法は異なります。たとえば、腸管運動機能低下型の便秘には運動療法や食事療法が効果的ですが、排便困難型には骨盤底筋のリハビリテーションが必要なこともあります。
あなたはどのタイプの便秘でしょうか?
自分の便秘のタイプを知るためには、症状の特徴を観察することが大切です。排便回数だけでなく、便の硬さ、排便時の感覚、腹部の不快感なども重要な手がかりになります。
便秘の原因が明らかになれば、それに合わせた対策を立てることができます。次からは、私が臨床経験から効果的だと実感している5つの改善方法をご紹介します。

方法1:腸内環境を整える食事療法
便秘改善の基本は、やはり食事です。特に重要なのは食物繊維の摂取です。
食物繊維には水溶性と不溶性の2種類があります。水溶性食物繊維は水に溶けて粘性のあるゲル状になり、便のかさを増やして腸の中をスムーズに移動させる効果があります。不溶性食物繊維は水に溶けずに便のかさを増やし、腸の蠕動運動を促進します。
水溶性食物繊維が豊富な食品としては、海藻類(わかめ、昆布)、果物(りんご、バナナ、キウイ)、オクラ、なめこなどがあります。不溶性食物繊維が多い食品には、玄米、全粒粉パン、こんにゃく、ごぼう、さつまいもなどがあります。
私の臨床経験では、特に効果的だと感じるのは、キウイフルーツと干しプルーンです。キウイフルーツには食物繊維だけでなく、タンパク質分解酵素のアクチニジンが含まれており、消化を助ける効果があります。干しプルーンには食物繊維に加え、ソルビトールという天然の緩下成分が含まれています。
また、発酵食品も腸内環境を整えるのに効果的です。ヨーグルト、納豆、キムチ、ぬか漬けなどの発酵食品には、腸内の善玉菌を増やす効果があります。特に乳酸菌やビフィズス菌を含む食品は、腸の蠕動運動を促進し、便通を改善する効果が期待できます。
一方で、便秘を悪化させる食品もあります。精製された炭水化物(白米、白パン、菓子パンなど)、加工食品、脂肪分の多い食品、カフェインやアルコールの過剰摂取は避けるべきです。
食事の摂り方も重要です。規則正しい時間に食事をとることで、胃結腸反射(食事をとると大腸の蠕動運動が活発になる反応)を利用できます。特に朝食をしっかりとることで、朝の排便習慣が身につきやすくなります。
私がよく患者さんに勧めるのは、朝起きたらまず常温の水を一杯飲むことです。これは腸の動きを活性化させ、排便を促す簡単な方法です。
方法2:効果的な運動習慣で腸の動きを活性化
運動不足は便秘の大きな原因の一つです。適度な運動は腸の蠕動運動を促進し、便通を改善する効果があります。
特に有効なのは、有酸素運動です。ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動は、全身の血流を改善し、腸への血流も増加させます。これにより腸の動きが活発になり、便の移動がスムーズになります。
私が特におすすめするのは、朝の時間帯に20〜30分程度のウォーキングを行うことです。朝の運動は体内時計をリセットし、腸の動きを活性化させる効果があります。実際、多くの患者さんが朝のウォーキングを習慣化することで便通が改善したと報告しています。
また、腹筋運動も効果的です。腹筋を鍛えることで腹圧をかけやすくなり、排便がスムーズになります。ただし、過度な腹筋運動は逆効果になることもあるので、無理のない範囲で行いましょう。
ヨガも便秘改善に効果的です。特に「ねじりのポーズ」や「風の抜けるポーズ」など、腸を刺激するポーズは便秘の改善に役立ちます。深い呼吸と組み合わせることで、腸へのマッサージ効果も期待できます。
運動を習慣化するコツは、無理なく続けられる強度と時間から始めることです。いきなり高強度の運動を長時間行うのではなく、まずは5分間のウォーキングから始め、徐々に時間を延ばしていくのがおすすめです。
私の患者さんで印象的だったのは、70代の女性です。長年の便秘に悩み、様々な下剤を試してきましたが効果は一時的でした。そこで毎朝15分の近所の散歩と、簡単なヨガのポーズを取り入れたところ、2週間ほどで便通が改善し、下剤の量を減らすことができました。
日常生活の中でも、エレベーターやエスカレーターの代わりに階段を使う、一駅分歩く、デスクワークの合間に立ち上がって軽くストレッチするなど、小さな運動を取り入れることが大切です。
運動は便秘改善だけでなく、全身の健康にも良い影響を与えます。自分に合った運動を見つけて、無理なく続けていきましょう。

方法3:ストレス管理と排便習慣の確立
便秘とストレスは密接に関連しています。ストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、腸の動きが鈍くなります。これが便秘を引き起こす一因となるのです。
私の外来でも、仕事や家庭のストレスが増えた時期に便秘が悪化したという患者さんは少なくありません。特に過敏性腸症候群(IBS)の方は、ストレスによって症状が大きく変動することがあります。
ストレス管理の方法としては、深呼吸、瞑想、ヨガ、アロマテラピー、入浴など、自分に合ったリラックス法を見つけることが大切です。特に腹式呼吸は、副交感神経を優位にし、腸の動きを活性化させる効果があります。
十分な睡眠も重要です。睡眠不足は自律神経のバランスを崩し、便秘を悪化させることがあります。規則正しい睡眠習慣を心がけましょう。
次に重要なのが、規則正しい排便習慣の確立です。毎日決まった時間にトイレに座る習慣をつけることで、体内時計が整い、自然な排便リズムが生まれます。
特に朝食後は胃結腸反射により腸の動きが活発になるため、排便に適した時間です。朝食後15〜30分程度、時間に余裕をもってトイレに座りましょう。この時、スマートフォンやタブレットを見ながらではなく、リラックスした状態で腹圧をかけることが大切です。
また、排便を我慢することは避けましょう。便意を感じたらなるべく早くトイレに行くことが重要です。便意を繰り返し我慢すると、次第に便意そのものを感じにくくなる「直腸感覚の鈍化」が起こることがあります。
トイレ環境も排便に影響します。和式トイレよりも洋式トイレの方が排便姿勢として適しています。また、足元に小さな台を置いて膝を高くすると、より自然な排便姿勢になります。
私の患者さんで、長年便秘に悩んでいた30代の男性は、朝の排便習慣を意識的に作ることで症状が改善しました。毎朝同じ時間に起き、水を一杯飲み、軽い体操をした後に朝食をとり、その後トイレに座る習慣をつけたところ、2週間ほどで自然な排便リズムが生まれたそうです。
便秘改善には、身体的なアプローチだけでなく、心理的なアプローチも重要です。ストレスを適切に管理し、規則正しい生活リズムと排便習慣を確立することで、薬に頼らない自然な排便を目指しましょう。
方法4:適切な水分摂取と腸活サポート成分
便秘改善には十分な水分摂取が欠かせません。水分が不足すると、大腸で水分が過剰に吸収され、便が硬くなってしまいます。
一日に必要な水分量は、体重や活動量、気候によって異なりますが、一般的には1.5〜2リットル程度が目安です。ただし、単に「水をたくさん飲めば良い」というわけではありません。
私がおすすめするのは、常温の水を少量ずつこまめに飲む方法です。特に朝起きた時と食事の30分前に一杯の水を飲むことで、腸の動きを促進する効果が期待できます。
また、水だけでなく、食物繊維を含む野菜や果物からも水分を摂取することが大切です。これらの食品は水分と食物繊維を同時に摂取できるため、便秘改善に効果的です。
一方で、カフェインを含む飲料(コーヒー、紅茶、緑茶など)やアルコールは利尿作用があり、過剰摂取は体内の水分を奪ってしまうことがあります。これらの飲み物を摂取した場合は、追加で水分を補給するよう心がけましょう。
次に、腸内環境を整えるサポート成分についてお話しします。
プロバイオティクスは、腸内の善玉菌のバランスを整える生きた微生物です。ビフィズス菌や乳酸菌などが代表的で、ヨーグルトや発酵食品に含まれています。サプリメントとしても摂取可能です。
プレバイオティクスは、善玉菌のエサとなる成分です。オリゴ糖、食物繊維、レジスタントスターチなどが該当します。これらを摂取することで、腸内の善玉菌が増え、腸内環境が改善します。
私の臨床経験では、プロバイオティクスとプレバイオティクスを組み合わせて摂取する「シンバイオティクス」が最も効果的です。例えば、オリゴ糖入りのヨーグルトや、食物繊維が豊富な野菜と発酵食品を一緒に摂取するなどの工夫が有効です。
また、マグネシウムも便秘改善に役立つ成分です。マグネシウムには腸に水分を引き寄せる作用があり、便を柔らかくする効果があります。ナッツ類、緑黄色野菜、海藻類、豆類などに多く含まれています。
ただし、サプリメントによる過剰摂取は下痢などの副作用を引き起こす可能性があるため、適切な量を守ることが重要です。特に腎機能に問題がある方は、医師に相談してから摂取するようにしましょう。
水分摂取と腸活サポート成分の摂取は、日々の生活に無理なく取り入れられる便秘改善策です。まずは朝起きた時に水を一杯飲む習慣から始めてみてはいかがでしょうか。

方法5:専門医による適切な薬物療法と治療法
ここまでご紹介した生活習慣の改善で多くの便秘は改善しますが、それでも症状が続く場合は、専門医による適切な薬物療法や治療法を検討する必要があります。
便秘治療薬には大きく分けて数種類あります。それぞれ作用機序が異なるため、症状や原因に合わせて適切な薬剤を選択することが重要です。
浸透圧性下剤(酸化マグネシウムなど)は、腸内に水分を引き寄せて便を柔らかくする薬剤です。比較的副作用が少なく、長期使用も可能ですが、腎機能障害のある方は注意が必要です。
刺激性下剤(センノシドなど)は、腸の蠕動運動を直接刺激して排便を促します。即効性がありますが、長期使用により腸が薬に依存してしまう可能性があるため、短期間の使用が原則です。
クロライドチャネルアクチベーター(ルビプロストンなど)は、腸管内に水分を分泌させて便の通過を促進します。慢性便秘症の治療薬として近年注目されています。
グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト(リナクロチドなど)は、腸管内の水分分泌を促進し、腸の運動も活性化させる薬剤です。特に過敏性腸症候群に伴う便秘に効果的です。
これらの薬剤は、症状や原因、年齢、併存疾患などを考慮して選択します。自己判断での服用は避け、必ず医師の指導のもとで適切な薬剤を選択することが重要です。
薬物療法以外にも、バイオフィードバック療法という治療法があります。これは排便時の筋肉の使い方を学び直す治療法で、特に排便困難型の便秘に効果的です。
バイオフィードバック療法では、排便時に腹圧をかけながら肛門括約筋をリラックスさせる正しい排便法を学びます。センサーを使って筋肉の動きを視覚的に確認しながらトレーニングを行うため、自分の体の状態を客観的に理解できるのが特徴です。
また、重度の便秘で他の治療法が効果がない場合には、外科的治療が検討されることもあります。ただし、これはあくまで最終手段であり、慎重に適応を判断する必要があります。
私の臨床経験では、多くの患者さんは適切な生活習慣の改善と、必要に応じた薬物療法の組み合わせで症状が改善します。重要なのは、自己判断で市販薬に頼り続けるのではなく、症状が長期間続く場合は専門医に相談することです。
特に、便秘に加えて血便や急激な体重減少、強い腹痛などの症状がある場合は、大腸がんなどの重大な疾患の可能性もあるため、速やかに医療機関を受診してください。
まとめ:便秘とさよならするための総合アプローチ
慢性便秘は単なる不快な症状ではなく、生活の質を大きく低下させ、様々な健康リスクをもたらす可能性がある問題です。しかし、適切なアプローチで多くの場合は改善が可能です。
今回ご紹介した5つの方法を総合的に取り入れることで、便秘を根本から改善していきましょう。
まず、食物繊維と水分を十分に摂取し、腸内環境を整える食事を心がけましょう。特に水溶性と不溶性の食物繊維をバランスよく摂ることが重要です。
次に、適度な運動を習慣化し、腸の動きを活性化させましょう。特に朝のウォーキングやヨガは効果的です。
ストレス管理と規則正しい排便習慣の確立も重要です。特に朝食後にトイレに座る習慣をつけることで、自然な排便リズムが生まれやすくなります。
プロバイオティクスやプレバイオティクスなどの腸活サポート成分も積極的に取り入れ、腸内環境を整えましょう。
そして、これらの生活習慣の改善で効果が見られない場合は、専門医に相談し、適切な薬物療法や治療法を検討することが大切です。
便秘は一朝一夕で改善するものではありません。根気よく継続することが重要です。また、便秘の原因や症状は人それぞれ異なるため、自分に合った方法を見つけることが大切です。
最後に、便秘に加えて血便や急激な体重減少、強い腹痛などの症状がある場合は、速やかに医療機関を受診してください。これらは大腸がんなどの重大な疾患のサインである可能性があります。
便秘は恥ずかしいことではなく、適切な対処が必要な健康問題です。この記事が皆さんの便秘改善の一助となれば幸いです。
健康な腸は健康な体と心の基盤です。便秘を根本から改善し、快適な毎日を取り戻しましょう。
便秘でお悩みの方は、ぜひ石川消化器内科・内視鏡クリニックにご相談ください。消化器内科専門医として、あなたの症状に合わせた最適な治療法をご提案いたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
胃潰瘍の初期症状から完治まで〜専門医が教える最新治療法
胃潰瘍とは?基本的な理解から始めましょう
胃潰瘍は、胃の内壁にできる傷のことです。具体的には、胃の粘膜が胃酸によって損傷し、粘膜下の組織が露出した状態を指します。
私たちの胃は毎日、食べ物を消化するために強い酸性の胃液を分泌しています。この胃液には塩酸やペプシンといった消化液が含まれており、通常は胃粘膜の保護機能によって胃自体が消化されることはありません。しかし、何らかの原因でこのバランスが崩れると、胃酸が胃の組織を溶かしてしまい、粘膜がただれた状態になってしまうのです。
胃潰瘍が進行すると、組織がえぐられるように欠損し、場合によっては胃の壁に穴が開く「穿孔」という重篤な状態に至ることもあります。また、潰瘍部分から出血することもあり、放置すると命に関わる危険性もある疾患です。
胃潰瘍は十二指腸潰瘍とともに「消化性潰瘍」と呼ばれることもあります。これらは症状や治療法が似ているため、しばしばまとめて扱われますが、発生する場所や症状の特徴に若干の違いがあります。

胃潰瘍の初期症状を見逃さないために
胃潰瘍の初期症状は人によって異なりますが、いくつかの典型的な症状があります。これらの症状を早期に認識することで、重症化を防ぐことができます。
最も一般的な症状は「みぞおちの痛み」です。特に胃潰瘍の場合は、食後に痛みを感じることが多いのが特徴です。十二指腸潰瘍では空腹時に痛むことが多いのとは対照的です。
ただし、初期の胃潰瘍ではほとんど痛みを感じないケースも少なくありません。このような「無症状の胃潰瘍」は、定期的な健康診断で偶然発見されることもあります。
みぞおちの不快感や消化不良、胃もたれといった漠然とした症状も初期段階でよく見られます。「何となく胃の調子が悪い」という感覚から始まることも多いのです。
その他の初期症状として、以下のようなものが挙げられます:
- 胸やけやゲップの増加
- 吐き気や食欲不振
- 膨満感や消化不良感
- 体重減少
- 口臭の悪化
これらの症状が2週間以上続く場合は、専門医への受診をお勧めします。特に40歳以上の方は、同様の症状があれば早めに消化器内科を受診することが重要です。
なぜでしょうか?
それは、胃潰瘍の症状は胃がんの初期症状と似ている場合があるからです。年齢が上がるにつれて胃がんのリスクも高まりますので、確実な診断を受けることが大切です。
胃潰瘍の主な原因と危険因子
胃潰瘍の原因は複数あります。かつては「ストレスや辛い食べ物が原因」と単純に考えられていましたが、現在では医学的にさまざまな要因が明らかになっています。
最も重要な原因の一つが「ヘリコバクター・ピロリ菌(H.pylori)」の感染です。この細菌は胃の粘膜に住み着き、長期間にわたって炎症を引き起こします。日本人の約半数が保有していると言われていますが、すべての人が胃潰瘍を発症するわけではありません。
ピロリ菌は胃の保護機能を弱め、胃酸から胃を守る粘液の分泌を減少させます。その結果、胃酸が胃の粘膜を傷つけやすくなり、潰瘍が形成されるのです。
もう一つの主要な原因は、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の使用です。アスピリンやイブプロフェンなどの痛み止めや解熱剤として広く使われている薬剤ですが、これらを長期間服用すると胃の粘膜を保護するプロスタグランジンの生成が抑制され、胃潰瘍のリスクが高まります。
特に高齢者や過去に胃潰瘍の既往がある方は、NSAIDsによる胃潰瘍のリスクが高いとされています。
また、ステロイド薬も長期間または高用量で使用すると、胃潰瘍を引き起こすことがあります。ステロイドは炎症を抑える効果がある一方で、胃粘膜の防御機能も低下させてしまうのです。
その他の危険因子としては、以下のようなものが挙げられます:
- 過度のストレス
- 喫煙(胃の血流を減少させる)
- 過度の飲酒
- 不規則な食生活
- 高齢
- 家族歴(遺伝的要因)
これらの要因が複合的に作用することで、胃潰瘍のリスクは高まります。特に複数の危険因子を持つ方は注意が必要です。

胃潰瘍の診断方法と最新の検査技術
胃潰瘍の診断には、いくつかの検査方法があります。症状だけでは他の消化器疾患との区別が難しいため、確定診断には精密検査が必要です。
最も確実な診断方法は「上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)」です。内視鏡を口または鼻から挿入し、食道、胃、十二指腸を直接観察します。この検査では、潰瘍の有無だけでなく、その大きさや深さ、出血の状況なども詳細に確認できます。
当院では、患者さんの負担を軽減するために、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の内視鏡検査を提供しています。半分眠ったような状態で検査を受けることができるため、「辛い・苦しい」というイメージがある胃カメラ検査のハードルを下げることができます。
また、経鼻内視鏡も導入しており、患者さんの希望に応じて経口・経鼻の選択が可能です。さらに、高性能な拡大内視鏡を使用することで、通常の内視鏡では見えにくい微細な変化も観察できます。
内視鏡検査では、必要に応じて組織を採取する「生検」も行います。採取した組織は病理検査に回され、潰瘍の性質や悪性所見の有無、ピロリ菌感染の有無などを調べます。
その他の診断方法としては、以下のようなものがあります:
- 胃X線検査(バリウム検査):バリウムを飲んで胃のレントゲン撮影を行う検査
- 血液検査:貧血の有無や炎症反応、ピロリ菌抗体などを調べる
- 便検査:潜血検査やピロリ菌抗原検査
- 呼気検査:ピロリ菌の有無を調べる非侵襲的な検査
当院では、これらの検査を患者さんの状態に合わせて適切に組み合わせ、正確な診断を行っています。特に初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しており、忙しい方でも受診しやすい環境を整えています。
胃潰瘍の最新治療法と薬物療法
胃潰瘍の治療は、この30年で大きく進化しました。現在の治療は、原因に応じた適切なアプローチと、症状の緩和を組み合わせて行います。
治療の第一歩は、原因の特定です。特にピロリ菌感染が確認された場合は、除菌治療が最優先となります。ピロリ菌の除菌に成功すると、潰瘍の再発率が大幅に低下することが分かっています。
ピロリ菌の除菌治療は、通常、以下の薬剤を組み合わせて行います:
- プロトンポンプ阻害薬(PPI):胃酸の分泌を強力に抑制
- 抗生物質(アモキシシリン、クラリスロマイシンなど):ピロリ菌を殺菌
この「三剤併用療法」を1週間程度続けることで、約70-80%の確率でピロリ菌を除菌できます。もし一次除菌に失敗した場合は、抗生物質を変更した二次除菌、さらには三次除菌を行うことがあります。
ピロリ菌が関与していない場合や、NSAIDs起因性の胃潰瘍の場合は、以下のような薬物療法を行います:
- プロトンポンプ阻害薬(PPI):オメプラゾール、ランソプラゾールなど
- H2受容体拮抗薬:ファモチジン、ラニチジンなど
- 粘膜保護薬:スクラルファート、レバミピドなど
- 制酸薬:水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウムなど
特にPPIは強力な酸分泌抑制効果があり、現在の胃潰瘍治療の中心的な薬剤となっています。PPIを8週間程度服用することで、多くの胃潰瘍は治癒に向かいます。
また、NSAIDsが原因の場合は、可能であれば使用を中止するか、胃に優しいタイプのCOX-2選択的阻害薬に変更することも検討します。どうしてもNSAIDsの使用が必要な場合は、PPIなどの胃粘膜保護薬を併用することが推奨されています。
重症の出血性胃潰瘍の場合は、内視鏡的止血術が必要になることがあります。当院では最新の内視鏡技術を用いて、クリッピング法、熱凝固法、局注法などの止血処置を行っています。
さらに重篤な場合、穿孔(胃に穴が開く状態)や狭窄(胃の出口が狭くなる状態)が生じた場合には、外科的治療が必要になることもあります。しかし、早期発見・早期治療により、手術が必要になるケースは減少しています。

胃潰瘍の生活習慣改善と再発防止策
胃潰瘍の治療において、薬物療法と並んで重要なのが生活習慣の改善です。適切な生活習慣は治癒を促進するだけでなく、再発防止にも大きく貢献します。
まず、食事に関しては、胃に負担をかけない食べ方を心がけましょう。具体的には以下のポイントが重要です:
- 規則正しい時間に食事をとる
- 一度にたくさん食べず、少量ずつ複数回に分けて食べる
- よく噛んでゆっくり食べる
- 極端に熱いものや冷たいものを避ける
- 刺激の強い香辛料や酸味の強い食品を控える
飲酒と喫煙は胃潰瘍の悪化要因となるため、できるだけ控えることが望ましいです。特に喫煙は胃の血流を減少させ、潰瘍の治癒を遅らせるため、禁煙が強く推奨されます。
アルコールは胃粘膜を直接刺激し、胃酸分泌も促進するため、治療中は避けるべきです。治癒後も適量を守ることが大切です。
ストレス管理も重要な要素です。ストレスは自律神経のバランスを崩し、胃酸の過剰分泌を招きます。以下のようなストレス軽減法を日常に取り入れましょう:
- 十分な睡眠をとる
- 適度な運動を行う
- リラクゼーション技法(深呼吸、瞑想など)を実践する
- 趣味や楽しみの時間を確保する
薬の服用に関しては、医師の指示通りに継続することが極めて重要です。症状が改善したからといって自己判断で服薬を中止すると、潰瘍が完全に治癒する前に再発するリスクが高まります。
特にNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)は胃潰瘍の原因となるため、使用する場合は必ず医師に相談しましょう。市販の痛み止めにもNSAIDsが含まれていることがあるため、注意が必要です。
ピロリ菌の除菌に成功した場合でも、定期的な検診は重要です。除菌後も一定の確率で再発することがあるため、症状がなくても定期的に胃カメラ検査を受けることをお勧めします。
これらの生活習慣改善と定期検診を組み合わせることで、胃潰瘍の再発リスクを大幅に低減することができます。
胃潰瘍の合併症と注意すべき危険信号
胃潰瘍は適切に治療すれば完治する病気ですが、放置すると重篤な合併症を引き起こす可能性があります。特に注意すべき合併症と、その危険信号について解説します。
最も一般的な合併症は「出血」です。潰瘍が深くなると、胃の壁にある血管が露出して出血することがあります。軽度の出血であれば黒色便(タール便)として現れますが、大量出血の場合は吐血(鮮血や暗赤色の血液を吐く)が起こることもあります。
次に重篤な合併症が「穿孔(せんこう)」です。これは潰瘍が胃壁を完全に貫通し、胃に穴が開いた状態を指します。穿孔が起こると、胃の内容物が腹腔内に漏れ出し、腹膜炎という命に関わる状態を引き起こします。
穿孔の症状は突然の激しい腹痛で、特に上腹部全体に広がる痛みが特徴です。腹部が板のように硬くなり、触れると強い痛みを感じます。発熱や冷や汗、血圧低下などのショック症状を伴うこともあります。
また、潰瘍が治癒する過程で「狭窄(きょうさく)」が生じることもあります。特に胃の出口付近(幽門部)に潰瘍ができた場合、治癒時の瘢痕(はんこん)形成により通路が狭くなることがあります。
狭窄の症状としては、食後の膨満感、嘔吐、食欲不振、体重減少などが挙げられます。食べ物が胃から十二指腸へうまく移動できないため、これらの症状が現れるのです。
以下のような症状が現れたら、すぐに医療機関を受診してください:
- 黒色便(タール便)や血便
- 吐血(鮮血や暗赤色の血液を吐く)
- 突然の激しい腹痛
- 冷や汗を伴う腹痛
- 繰り返す嘔吐
- 急激な体重減少
- 原因不明の貧血症状(めまい、倦怠感、息切れなど)
これらの症状は胃潰瘍の合併症の可能性があり、緊急の対応が必要です。特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、合併症のリスクが高いため、より注意が必要です。
当院では、胃潰瘍の合併症に対しても迅速に対応できる体制を整えています。出血に対しては内視鏡的止血術、穿孔や狭窄に対しては適切な治療を提供しています。
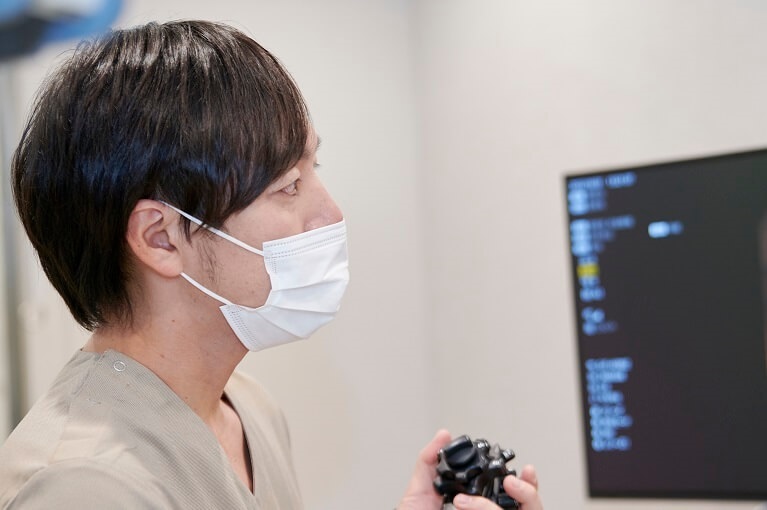
胃潰瘍治療の最新トレンドと将来展望
胃潰瘍の治療は、医学の進歩とともに日々進化しています。ここでは、最新の治療トレンドと今後の展望について解説します。
まず、薬物療法の分野では、より効果的で副作用の少ない新世代のプロトンポンプ阻害薬(PPI)が開発されています。従来のPPIよりも作用時間が長く、一日一回の服用で効果が持続するタイプや、より速やかに効果を発揮するタイプなど、患者さんのニーズに合わせた選択肢が増えています。
また、ピロリ菌除菌療法においても進展があります。従来の三剤併用療法(PPI+抗生物質2種)に加え、四剤併用療法や、抗生物質耐性菌に対応した新しい除菌レジメンが研究されています。これにより、一次除菌で成功しなかった場合でも、より高い確率で除菌を達成できるようになってきました。
内視鏡技術の進歩も目覚ましいものがあります。当院でも導入している拡大内視鏡や特殊光観察(NBI、BLIなど)を用いることで、従来では見逃していた微細な病変も発見できるようになりました。
さらに、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)などの技術の向上により、早期胃がんと胃潰瘍の鑑別がより正確になり、適切な治療選択が可能になっています。
近年注目されているのが「マイクロバイオーム(腸内細菌叢)」の研究です。胃腸の健康維持における腸内細菌の役割が明らかになるにつれ、プロバイオティクスやプレバイオティクスを用いた胃潰瘍治療の補助療法が研究されています。
これらの善玉菌は胃腸の免疫機能を強化し、ピロリ菌の定着を阻害する可能性があります。また、抗生物質による除菌治療後の腸内環境を整える効果も期待されています。
個別化医療(Precision Medicine)のアプローチも進んでいます。患者さんの遺伝的背景や生活習慣、ピロリ菌の薬剤耐性パターンなどを考慮した、よりパーソナライズされた治療計画が可能になりつつあります。
例えば、特定の遺伝子多型を持つ患者さんでは、特定のPPIの代謝速度が異なることが分かっており、それに基づいた薬剤選択や用量調整が行われるようになってきました。
また、ピロリ菌の薬剤耐性検査を事前に行うことで、より効果的な抗生物質の組み合わせを選択できるようになっています。
このように、胃潰瘍治療は単なる対症療法から、原因に基づいた根本治療、さらには個々の患者さんに最適化された精密医療へと進化しています。当院でも、これらの最新知見を取り入れながら、患者さん一人ひとりに最適な治療を提供できるよう努めています。
まとめ:胃潰瘍の早期発見と適切な治療の重要性
胃潰瘍は、適切な治療を受ければ完治する病気です。しかし、放置すると重篤な合併症を引き起こす可能性もあります。この記事のポイントをまとめてみましょう。
胃潰瘍の初期症状は、みぞおちの痛み(特に食後)、胃もたれ、胸やけなどですが、症状がない場合もあります。40歳以上の方や、症状が2週間以上続く場合は、早めに専門医を受診することが重要です。
胃潰瘍の主な原因は、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染と非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の使用です。その他、ストレス、喫煙、過度の飲酒なども危険因子となります。
診断には上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)が最も確実です。当院では鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査や、経鼻内視鏡など、患者さんの負担を軽減する検査方法を提供しています。
治療は原因に応じて行います。ピロリ菌が原因の場合は除菌治療、NSAIDsが原因の場合はその使用を見直し、いずれの場合も胃酸分泌を抑える薬(PPI、H2ブロッカーなど)を使用します。
生活習慣の改善も重要です。規則正しい食事、禁煙、節酒、ストレス管理などが治癒を促進し、再発を防ぎます。
黒色便、吐血、激しい腹痛などの症状が現れた場合は、合併症の可能性があるため、すぐに医療機関を受診してください。
胃潰瘍治療は日々進化しており、より効果的で副作用の少ない薬物療法や、個別化医療のアプローチが進んでいます。
胃の不調を感じたら、「様子を見よう」と放置せず、専門医に相談することが大切です。当院では、最新の医療設備と専門知識を活かし、患者さん一人ひとりに最適な診断・治療を提供しています。
胃カメラ検査に不安がある方も、鎮静剤を使用した無痛検査や経鼻内視鏡など、患者さんの希望に合わせた検査方法をご用意しています。
胃の健康は全身の健康の基盤です。定期的な検診と適切な生活習慣で、胃潰瘍を予防し、健やかな毎日を送りましょう。
胃の不調でお悩みの方は、ぜひ石川消化器内科・内視鏡クリニックにご相談ください。消化器・内視鏡専門医として、皆様の健康をサポートいたします。
詳しい情報や予約方法については、石川消化器内科・内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
十二指腸潰瘍の3大原因と予防・治療の最新アプローチ
十二指腸潰瘍とは~基本知識と症状
十二指腸潰瘍は、胃の出口から続く十二指腸の粘膜が深く傷つく疾患です。胃潰瘍と合わせて「消化性潰瘍」と呼ばれることもあります。この疾患は、粘膜の防御機能と胃酸などの攻撃因子のバランスが崩れることで発症します。
十二指腸潰瘍の特徴的な症状として、空腹時に痛みが現れ、食事をすると一時的に改善することが挙げられます。これは「空腹時痛」と呼ばれ、胃潰瘍の「食後痛」とは対照的です。
夜間に痛みで目が覚めることもあり、この「夜間性」の症状は十二指腸潰瘍の特徴的なサインです。また、上腹部痛、胸やけ、胃もたれ、吐き気、嘔吐などの症状も見られます。重症化すると黒色便(タール便)が出ることもあり、これは消化管出血のサインとして注意が必要です。
十二指腸潰瘍は、胃潰瘍と比べるとやや発症率は低いものの、若年層から中年層にかけての罹患が目立ちます。男性に多い傾向がありますが、女性も一定の罹患率を示しています。

十二指腸潰瘍の3大原因
十二指腸潰瘍の発症には主に3つの要因が関わっています。これらの原因を理解することが、効果的な予防と治療の第一歩となります。
1. ヘリコバクター・ピロリ菌感染
十二指腸潰瘍の最も重要な原因は、ヘリコバクター・ピロリ菌(H. pylori)の感染です。世界全体の約半数がこの細菌に感染しているとされています。
ピロリ菌は胃に定着し、胃酸分泌を増加させるとともに、十二指腸粘膜の防御機能を低下させます。十二指腸潰瘍患者の約90%がピロリ菌に感染しているというデータもあり、その関連性の高さがうかがえます。
興味深いことに、同じピロリ菌が原因であるにもかかわらず、十二指腸潰瘍の患者は胃癌になりにくいことが知られています。2012年の研究では、この違いがPSCA遺伝子の違いによることが明らかになりました。
PSCA遺伝子のタイプによって、十二指腸潰瘍と胃癌のリスクが逆相関することが分かっています。十二指腸潰瘍になりやすいタイプの人(CC型)では潰瘍のリスクが1.84倍増える一方、胃癌のリスクが約半分(0.59倍)になるというデータが示されています。
2. 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の使用
アスピリンをはじめとする非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の使用は、十二指腸潰瘍の重要な原因の一つです。NSAIDsは、プロスタグランジンの生成を抑制することで、胃や十二指腸の粘膜防御機能を低下させます。
NSAIDsを3か月以上継続して使用すると、10-15%で胃潰瘍、3%で十二指腸潰瘍、1%で出血性潰瘍が生じるというデータがあります。これは酸分泌抑制薬を併用しない場合の数値です。
特に注意すべきは、NSAIDs潰瘍の出血を起こしても無症状の患者さんが多いという点です。痛みなどの自覚症状がなくても、潜在的に潰瘍が進行している可能性があります。
3. 胃酸の過剰分泌
十二指腸潰瘍の発症には、胃酸の過剰分泌も重要な役割を果たしています。通常、十二指腸は胃酸を中和する機能を持っていますが、胃酸の分泌が過剰になると、この防御機能が追いつかなくなります。
ピロリ菌感染は胃酸分泌を増加させる一因となります。また、ストレスや特定の食品(カフェイン、アルコール、香辛料の多い食品など)も胃酸分泌を促進することがあります。
胃酸の過剰分泌は、十二指腸粘膜の炎症と組織破壊を引き起こし、潰瘍形成につながります。特に夜間の胃酸分泌増加が、夜間痛という特徴的な症状の原因となっています。
十二指腸潰瘍のリスク因子
十二指腸潰瘍の発症リスクを高める要因には、上記の3大原因に加えて、いくつかの重要な因子があります。これらのリスク因子を理解することで、予防対策をより効果的に行うことができます。
高リスク群の特徴
以下のような状態がある場合、NSAIDs潰瘍を含む十二指腸潰瘍の高リスク群と考えられます:
- 高齢(65歳以上)
- 重篤な全身疾患を有する
- 消化性潰瘍の既往がある
- 副腎皮質ステロイドの併用
- 抗凝固薬と抗血小板薬の併用
- 高用量あるいは複数のNSAIDsの併用
- ビスホスホネートの併用
- ヘリコバクターピロリ陽性
特に注目すべきは、複数の薬剤を併用している高齢者です。高齢化社会の進展に伴い、このようなハイリスク患者が増加しています。
生活習慣関連因子
喫煙とアルコール摂取も、NSAIDs潰瘍を含む十二指腸潰瘍のリスクを高める可能性があります。喫煙は胃粘膜の血流を減少させ、アルコールは胃粘膜を直接刺激することで防御機能を低下させます。
不規則な食生活やストレスも、十二指腸潰瘍の発症や悪化に関連していると考えられています。特に長期間の精神的ストレスは、自律神経系を介して胃酸分泌に影響を与える可能性があります。
遺伝的要因も無視できません。前述のPSCA遺伝子の他にも、ABO血液型がリスクに影響することが分かっています。O型の人はA型に比べて1.43倍、十二指腸潰瘍になりやすいというデータがあります。
これらのリスク因子を複数持つ場合、十二指腸潰瘍の発症リスクは相乗的に高まる可能性があります。自分のリスクを知り、適切な予防策を講じることが重要です。

十二指腸潰瘍の診断方法
十二指腸潰瘍の確定診断には、いくつかの検査方法が用いられます。症状だけでは胃潰瘍や機能性ディスペプシアなど他の疾患との区別が難しいため、適切な検査による診断が重要です。
内視鏡検査(上部消化管内視鏡)
十二指腸潰瘍の診断の基本となるのが上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)です。この検査では、口または鼻から細い内視鏡を挿入し、食道、胃、十二指腸の粘膜を直接観察します。
内視鏡検査の最大の利点は、潰瘍を直接目で見て確認できることです。潰瘍の大きさ、深さ、位置、数などを正確に評価できるほか、必要に応じて組織を採取(生検)し、悪性疾患との鑑別も可能です。
近年では、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の内視鏡検査が普及しています。半分眠ったような状態で検査を受けられるため、従来の「辛い・苦しい」というイメージを払拭し、患者さんの負担を大幅に軽減しています。
ヘリコバクター・ピロリ菌の検査
十二指腸潰瘍の主要原因であるピロリ菌の感染を調べる検査も重要です。検査方法には以下のようなものがあります:
- 内視鏡検査時の生検による検査(培養検査、迅速ウレアーゼ試験、組織検査)
- 尿素呼気試験(13C-尿素呼気試験)
- 血液検査(抗ピロリ菌抗体検査)
- 便検査(ピロリ菌抗原検査)
これらの検査を組み合わせることで、ピロリ菌感染の有無を高い精度で判定することができます。感染が確認された場合は、除菌治療の適応となります。
その他の検査
状況に応じて、以下のような検査が追加で行われることもあります:
- 血液検査:貧血の有無、炎症反応などを調べます
- 便潜血検査:消化管出血の有無を調べます
- X線検査(上部消化管造影):バリウムを飲んでX線撮影を行い、潰瘍の位置や大きさを評価します
- CT検査:合併症(穿孔など)が疑われる場合に行われます
これらの検査を総合的に評価することで、十二指腸潰瘍の確定診断だけでなく、重症度や合併症の有無も判断することができます。早期の適切な診断が、効果的な治療につながります。
十二指腸潰瘍の予防法と生活習慣の改善
十二指腸潰瘍は適切な予防策により、発症リスクを大幅に低減することができます。特にリスク因子を持つ方は、以下の予防法を積極的に取り入れることをお勧めします。
ピロリ菌感染の検査と除菌
ピロリ菌感染が十二指腸潰瘍の主要原因であることから、感染が確認された場合は除菌治療を検討することが重要です。特に以下のような方は検査をお勧めします:
- 消化性潰瘍の既往がある方
- 消化性潰瘍の家族歴がある方
- 慢性的な胃の不調がある方
- 胃癌のリスクが心配な方
除菌治療により、十二指腸潰瘍の再発率は著しく低下します。一度除菌に成功すれば、再感染率は年間0.5%程度と低く、長期的な予防効果が期待できます。
NSAIDs使用時の注意点
NSAIDsを使用する必要がある場合は、以下の点に注意することで潰瘍リスクを軽減できます:
- 必要最小限の用量と期間にとどめる
- 高リスク患者では、PPIやP-CABを併用する
- 可能であれば、胃腸への影響が少ないCOX-2選択的阻害薬の使用を検討する
- アルコールや喫煙を避ける
NSAIDs潰瘍のリスクが高いと予想される場合、潰瘍歴のない患者さんにおいてもNSAIDs潰瘍の予防投与が望ましいとされています。潰瘍歴のある患者さんの予防には、PPIやボノプラザンが推奨されます。
生活習慣の改善
十二指腸潰瘍の予防と再発防止には、以下のような生活習慣の改善が効果的です:
- 禁煙:喫煙は潰瘍治癒を遅らせ、再発リスクを高めます
- 節酒:過度のアルコール摂取は胃粘膜を刺激します
- 規則正しい食生活:空腹の時間を長くしないよう、規則的に食事をとりましょう
- ストレス管理:リラクゼーション法や適度な運動でストレスを軽減しましょう
- 十分な睡眠:良質な睡眠は自律神経のバランスを整えます
特に注目すべきは、喫煙の影響です。喫煙は胃粘膜の血流を減少させ、潰瘍治癒を遅らせるだけでなく、ピロリ菌除菌の成功率も低下させることが知られています。
定期的な健康チェック
十二指腸潰瘍の既往がある方や、リスク因子を持つ方は、定期的な健康チェックが重要です。特に以下のような場合は、早めに医療機関を受診しましょう:
- 上腹部に持続する痛みがある
- 黒色便(タール便)が出る
- 貧血の症状(めまい、倦怠感など)がある
- NSAIDsを長期服用している
早期発見・早期治療が、重篤な合併症を防ぐ鍵となります。特に高齢者では、症状が典型的でない場合もあるため、注意が必要です。

十二指腸潰瘍の合併症と注意点
十二指腸潰瘍は適切に治療されなければ、いくつかの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。これらの合併症を理解し、早期に対処することが重要です。
出血
十二指腸潰瘍の最も一般的な合併症は出血です。潰瘍が深くなり、血管を侵食することで発生します。出血の症状には以下のようなものがあります:
- 黒色便(タール便):消化管上部からの出血を示します
- 吐血:鮮血や「コーヒー残渣様」の嘔吐物
- めまい、立ちくらみ、倦怠感:貧血の症状
- 頻脈、血圧低下:大量出血時に見られます
出血性潰瘍は緊急処置が必要な状態です。内視鏡的止血術が第一選択となりますが、止血困難例ではIVRや外科的治療が検討されます。
特に注意すべきは、NSAIDs潰瘍の出血を起こしても無症状の患者さんが多いという点です。定期的な検査と予防的な対策が重要となります。
穿孔
穿孔は、潰瘍が十二指腸壁を完全に貫通し、内容物が腹腔内に漏れ出す状態です。突然の激しい腹痛で発症し、腹部全体の痛みと硬直(板状硬)が特徴的です。
穿孔は生命を脅かす緊急事態であり、速やかな外科的処置が必要となります。CT検査で診断され、多くの場合、緊急手術が行われます。
近年では、腹腔鏡を用いた低侵襲手術も行われるようになってきました。早期に適切な治療を行うことで、予後は大きく改善します。
狭窄
十二指腸潰瘍が治癒する過程で瘢痕組織が形成され、十二指腸の内腔が狭くなることがあります。これを狭窄と呼びます。主な症状には以下のようなものがあります:
- 食後の膨満感、不快感
- 嘔吐(特に食後)
- 体重減少
- 上腹部痛
狭窄の治療には、内視鏡的バルーン拡張術や外科的治療が検討されます。ピロリ菌除菌治療の普及により、狭窄を含む潰瘍の合併症は減少傾向にありますが、高齢者や複数の疾患を持つ患者では依然として注意が必要です。
高齢者における注意点
高齢者の十二指腸潰瘍には、いくつかの特徴と注意点があります:
- 症状が非典型的であることが多い(痛みを訴えないケースも)
- NSAIDsや抗血栓薬の使用頻度が高く、出血リスクが増加
- 合併症発生時の重症化リスクが高い
- 複数の疾患や薬剤使用による複雑な病態
本邦の超高齢社会において、併存疾患の存在や抗血栓薬ならびに非ステロイド性抗炎症薬内服患者の増加によって、患者背景が変化していることに注意が必要です。高齢者では予防的なアプローチと定期的な健康チェックがより重要となります。
まとめ~十二指腸潰瘍との上手な付き合い方
十二指腸潰瘍は、ヘリコバクター・ピロリ菌感染、NSAIDsの使用、胃酸の過剰分泌という3大原因によって引き起こされる疾患です。かつては難治性とされていましたが、現在では適切な治療により高い確率で治癒が可能となっています。
ピロリ菌感染が確認された場合は、除菌療法が第一選択となります。除菌成功により潰瘍再発率は著しく低下します。NSAIDs起因性の潰瘍では、可能であれば使用中止、または酸分泌抑制薬の併用が推奨されます。
予防においては、ピロリ菌検査と除菌、NSAIDs使用時の注意、生活習慣の改善が重要です。特に喫煙、過度のアルコール摂取、不規則な食生活、ストレスは潰瘍のリスクを高めるため、これらの改善が効果的です。
十二指腸潰瘍の症状として特徴的なのは、空腹時の痛みと夜間痛です。黒色便や吐血などの出血症状、突然の激しい腹痛などの穿孔症状がある場合は、緊急の医療処置が必要です。
高齢者では症状が非典型的であることが多く、NSAIDsや抗血栓薬の使用頻度も高いため、特に注意が必要です。定期的な健康チェックと予防的なアプローチが重要となります。
十二指腸潰瘍は、適切な知識と予防・治療により、上手に付き合っていくことが可能な疾患です。気になる症状がある場合は、早めに消化器専門医に相談することをお勧めします。
当院では、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の内視鏡検査を提供しており、十二指腸潰瘍を含む消化器疾患の早期発見・早期治療に力を入れています。些細な症状でもお気軽にご相談ください。
詳細な情報や検査のご予約については、石川消化器内科・内視鏡クリニックまでお問い合わせください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
【2025年最新】大腸カメラ人間ドックの費用相場と選び方ガイド
大腸カメラ検査とは?人間ドックでの重要性
大腸カメラ検査は、下剤で大腸内を空にした後、内視鏡を肛門から挿入して大腸全体を観察する検査です。直径10mm前後の内視鏡を使用し、リアルタイムで腸内の状態を確認します。
この検査では、大腸がんやポリープ、炎症性腸疾患など、さまざまな病変を早期に発見することができるのです。
近年、大腸がんは日本人の罹患数第1位、死亡数では男性が第3位、女性が第1位となっている深刻な疾患です。食生活の欧米化や高齢化により増加傾向にあり、30代でも発症するケースが見られます。
私は消化器内科医として多くの患者さんを診てきましたが、早期発見できれば治療効果が高いのが大腸がんの特徴です。ステージⅠで発見された場合の5年生存率は92.3%と非常に高いのです。
大腸がんの初期段階では自覚症状がほとんどないため、定期的な検査が何よりも重要になります。
「検査は痛そう」「恥ずかしい」と躊躇される方も多いですが、現在は鎮静剤を使用した無痛検査や、患者さんの負担を軽減する様々な工夫が進んでいます。

大腸カメラ人間ドックの費用相場(2025年最新)
大腸カメラ検査の費用は、受ける医療機関や検査内容によって異なります。2025年現在の費用相場を詳しく見ていきましょう。
自費で検査を受ける場合と、自治体の補助を利用する場合では大きく金額が変わってきます。また、保険適用となるケースもあるので、状況に応じた選択が可能です。
自費で検査する場合の費用
人間ドックなど自費で大腸カメラ検査を受ける場合、医療機関によって金額や対象年齢が異なります。自分の希望するタイミングで検査を受けられる利点があります。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)単独の場合、一般的な費用相場は約20,000円程度です。ただし、医療機関によって15,000円~30,000円程度の幅があります。
人間ドックのオプションとして大腸カメラを追加する場合は、単独で受けるよりも割安になることが多く、15,000円前後で受けられる医療機関も少なくありません。
また、胃カメラと大腸カメラをセットで受ける「胃大腸カメラセット」は、45,000円前後が相場となっています。
検査中にポリープが見つかり、その場で切除した場合は追加費用が発生します。ポリープ切除を含めると、20,000円~30,000円程度の費用がかかることが一般的です。
自治体の補助を利用した場合の費用
各地方自治体(都道府県、市町村、特別区)では、大腸がん検診の補助制度を設けています。ただし、多くの自治体で補助対象となるのは便潜血検査(検便)であり、大腸カメラ検査自体への直接的な補助は限られています。
自治体の補助を利用した便潜血検査の自己負担額は、無料から有料でも500円~1,000円程度と非常に安価です。
便潜血検査で陽性反応が出た場合、精密検査として大腸カメラ検査を受けることになりますが、この場合は健康保険が適用されるため、自己負担額は6,000円~9,000円程度になります。
保険診療となる場合の費用
便潜血検査などで異常が見つかった場合や、腹痛・下血などの症状がある場合は、大腸カメラ検査が保険診療の対象となります。この場合の自己負担額は、検査内容によって以下のように変わります。
- 観察のみの場合:5,000円~7,000円程度
- 組織を一部採取して病理検査を行う場合:5,000円~15,000円程度
- ポリープ切除を行った場合:20,000円~30,000円程度
保険診療の場合、3割負担で計算していますが、高額療養費制度や各種医療費助成制度を利用できる場合もあります。
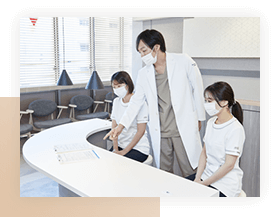
大腸カメラ検査の種類と選び方
大腸カメラ検査には、いくつかの種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った検査方法を選ぶことが大切です。
通常の大腸内視鏡検査
最も一般的な検査方法で、肛門から内視鏡を挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体を観察します。検査時間は15分程度ですが、前処置や待機時間を含めると2~3時間ほどかかります。
がんやポリープに対する診断精度が非常に高く、病変が見つかった場合はその場で組織採取や小さなポリープの切除が可能です。
ただし、内視鏡挿入時の不快感や痛みを感じる方もいらっしゃいます。そのため、最近では鎮静剤(麻酔)を使用した無痛検査が普及しています。
S状結腸内視鏡検査
大腸の入り口部分(S状結腸まで)のみを観察する検査です。検査時間が短く、前処置も比較的簡単なのが特徴です。費用も通常の大腸内視鏡検査より安く、保険診療で約3,000円程度です。
ただし、大腸全体を観察するわけではないため、奥の方にある病変を見逃す可能性があります。大腸がんは直腸やS状結腸に多く発生するため、スクリーニング検査としては有用ですが、全体を確認するには通常の大腸内視鏡検査が必要です。
CTによる大腸検査(CTコロノグラフィ)
肛門から炭酸ガスを注入してCTで撮影する検査方法です。内視鏡を使わないため、挿入時の痛みがなく、穿孔などのリスクも低いのが特徴です。費用相場は20,000円~30,000円程度です。
ただし、病変が見つかっても組織採取やポリープ切除はできないため、異常があれば改めて通常の大腸内視鏡検査が必要になります。また、小さなポリープの発見率は内視鏡検査より劣ります。
どうですか?ご自身の状況や不安要素に合わせて検査方法を選ぶことができますね。

大腸カメラ検査を受けるべき人とタイミング
大腸カメラ検査は誰もが定期的に受けるべきものではありませんが、特定の条件に当てはまる方は積極的に検討すべき検査です。
大腸カメラ検査を受けたほうがよい方
以下のような方は、大腸カメラ検査を受けることをお勧めします。
- 便潜血検査で陽性反応が出た方
- 血便や下痢、便秘の繰り返しなど腸の症状がある方
- 大腸がんの家族歴がある方
- 過去にポリープや大腸がんが見つかった方
- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)と診断された方
- 50歳以上の方(特にリスク因子がある場合)
特に40歳を超えると大腸がんのリスクは徐々に高まり始めます。50歳以上になると、症状がなくても定期的な検査を検討すべき年齢といえるでしょう。
私の臨床経験から言えば、家族歴のある方は特に注意が必要です。親や兄弟に大腸がんの既往がある場合、リスクは約2倍に高まるとされています。
大腸カメラ検査の推奨頻度
大腸カメラ検査の受診頻度は、個人のリスク因子や過去の検査結果によって異なります。
一般的な目安としては以下のようになります:
- 異常がなかった場合:5~10年ごと
- 小さなポリープが見つかり切除した場合:3~5年ごと
- 複数または大きなポリープが見つかった場合:1~3年ごと
- 大腸がんの治療後:医師の指示に従う(通常は1年ごと)
- 炎症性腸疾患がある場合:1~2年ごと
ただし、これはあくまで一般的な目安です。実際の検査間隔は、医師が患者さん一人ひとりの状況を考慮して判断します。
あなたはいかがですか?定期的な検査を受けていますか?
大腸カメラ検査の流れと準備
大腸カメラ検査を受ける際には、事前の準備が非常に重要です。検査の精度を高め、スムーズに進めるためにも、正しい準備を行いましょう。
検査前の食事制限と下剤
大腸内視鏡検査では、腸内をきれいにしておく必要があります。食物が消化されて排泄されるまでには24~48時間かかるため、検査前日からの準備が必要です。
検査前日の朝食からは、消化の良いものを摂るようにしましょう。おかゆや素うどんなどがおすすめです。医療機関によっては専用の検査食が用意されている場合もあります。
前日の夕食は軽めの消化の良いものを20時までに済ませ、その後は水分のみの摂取となります。就寝前に下剤を服用し、早めに就寝するのが良いでしょう。
検査当日の朝は食事ができません。ただし、脱水予防のために水分摂取は積極的に行ってください。検査の1~2時間前からは大腸内視鏡用の下剤(約1.5リットル)を服用し、便が透明になるまで続けます。
下剤の効果には個人差があり、服用開始から効果が現れるまで30分~2時間程度かかります。トイレに何度も行く必要があるため、検査当日は余裕をもったスケジュールを組むことをお勧めします。
検査当日の流れ
検査当日の一般的な流れは以下のようになります:
- 来院・受付
- 問診・検査の説明
- 下剤の服用(便が透明になるまで)
- 検査着に着替え
- 鎮静剤の使用(希望する場合)
- 検査台で左側を向いて横になる
- 内視鏡検査(約15分程度)
- 回復・休憩(鎮静剤使用の場合は30分程度)
- 結果説明
- 帰宅
鎮静剤を使用した場合は、検査後すぐに車の運転はできません。公共交通機関を利用するか、家族に送迎してもらうようにしましょう。
検査後の注意点
検査後は通常の食事に戻れますが、腸が空気で膨らんでいるため、軽い腹部膨満感を感じることがあります。これは徐々に改善していきます。
ポリープ切除を行った場合は、出血のリスクがあるため、数日間は激しい運動や入浴、飲酒を控える必要があります。また、食事内容も制限される場合があるので、医師の指示に従いましょう。
検査中に組織を採取した場合は、病理検査の結果が出るまで1~2週間かかります。結果を聞くために再度来院する必要があります。

大腸カメラ検査の負担を軽減する方法
「大腸カメラは辛い」というイメージをお持ちの方も多いでしょう。しかし、近年は患者さんの負担を軽減するための様々な工夫が進んでいます。
鎮静剤(麻酔)を使用した無痛検査
最も効果的な負担軽減方法は、鎮静剤(麻酔)の使用です。鎮静剤を使用すると、半分眠ったような状態になり、痛みや不快感をほとんど感じることなく検査を受けられます。
私のクリニックでも、多くの患者さんが鎮静剤を使用した検査を選択されています。「あっという間に終わった」「全く覚えていない」という感想をよくいただきます。
鎮静剤の使用には追加費用がかかる場合がありますが、検査の苦痛を大幅に軽減できるため、特に初めて検査を受ける方や過去に辛い経験をした方にはおすすめです。
CO2送気を用いた検査
従来の大腸内視鏡検査では空気を送り込んで腸を膨らませていましたが、最近ではCO2(二酸化炭素)を使用する医療機関が増えています。
CO2は空気よりも体内への吸収が早いため、検査後の腹部膨満感や不快感が軽減されます。検査中の痛みも軽減される傾向にあります。
細径スコープの使用
通常の内視鏡よりも細い「細径スコープ」を使用することで、挿入時の痛みや不快感を軽減できます。
ただし、細径スコープは画質や機能面で若干の制限があるため、すべての医療機関で導入されているわけではありません。検査前に医療機関に確認してみるとよいでしょう。
水浸法による挿入
水浸法は、空気の代わりに水を注入しながら内視鏡を挿入する方法です。腸管が伸びにくくなるため、痛みを軽減できます。
この方法は技術的に難しい面もありますが、患者さんの負担軽減に効果的であるため、導入する医療機関が増えています。

大腸カメラ検査の医療機関選びのポイント
大腸カメラ検査を受ける医療機関を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントがあります。適切な医療機関を選ぶことで、より安全で精度の高い検査を受けることができます。
専門医の在籍と経験
最も重要なのは、消化器内視鏡専門医が在籍しているかどうかです。専門医は高度な技術と知識を持ち、安全かつ精度の高い検査を提供できます。
医師の経験も重要な要素です。年間の内視鏡検査実施件数が多い医師ほど、技術が安定しており、偶発症のリスクも低くなります。
医療機関のホームページや電話での問い合わせで、専門医の在籍状況や経験を確認することをお勧めします。
設備と検査環境
最新の内視鏡機器を導入している医療機関では、より高精度な検査が可能です。特に「拡大内視鏡」や「NBI(狭帯域光観察)」などの特殊光観察が可能な機器があると、微細な病変も見逃しにくくなります。
また、ポリープが見つかった場合にその場で切除できる体制が整っているかも重要なポイントです。設備が整っていないと、改めて別の医療機関を受診する必要が生じます。
患者負担への配慮
鎮静剤の使用や、CO2送気、水浸法など、患者さんの負担を軽減する工夫を行っているかどうかも選択の基準になります。
また、検査前の説明が丁寧で、不安や疑問に対応してくれる医療機関を選ぶことも大切です。
女性の方は、女性医師や女性スタッフによる対応が可能かどうかも確認するとよいでしょう。
アクセスと予約のしやすさ
検査当日は下剤の影響でトイレに何度も行く必要があるため、自宅や職場からアクセスしやすい医療機関を選ぶことも重要です。
また、土曜日や夜間の検査に対応しているか、WEB予約が可能かなど、予約のしやすさも考慮すると良いでしょう。
私のクリニックでは、患者さんの利便性を考慮し、土曜日の検査や初診当日の検査にも対応しています。お仕事で平日に時間が取れない方にも検査を受けていただけるよう配慮しています。
まとめ:大腸カメラ検査で健康を守るために
大腸カメラ検査は、大腸がんをはじめとする様々な疾患の早期発見・早期治療に非常に有効な検査です。特に大腸がんは早期発見できれば治療効果が高く、5年生存率も90%を超えます。
2025年現在の費用相場としては、自費診療で約20,000円、保険適用で5,000円~7,000円程度が一般的です。ポリープ切除などを行うと追加費用がかかりますが、健康を守るための投資と考えれば決して高くはないでしょう。
検査に対する不安や恐怖感をお持ちの方も多いと思いますが、鎮静剤の使用やCO2送気など、患者さんの負担を軽減する様々な工夫が進んでいます。「辛い・苦しい」というイメージは、現在の医療技術ではかなり解消されています。
医療機関を選ぶ際は、消化器内視鏡専門医の在籍、最新設備の導入状況、患者負担への配慮などをポイントに検討することをお勧めします。
大腸がんは増加傾向にある疾患ですが、定期的な検査で早期発見できれば怖い病気ではありません。特に50歳を超えたら、症状がなくても一度は検査を検討されることをお勧めします。
健康は何よりも大切な財産です。「検査が怖い」という気持ちは理解できますが、その不安を乗り越えて検査を受けることで、より長く健康な生活を送ることができます。
詳しい検査内容や最新の無痛検査についてもっと知りたい方は、ぜひ 石川消化器内科・内視鏡クリニック にご相談ください。消化器・内視鏡専門医として、皆様の健康をサポートいたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
消化不良と胃痛を根本から改善する4つの専門的アプローチ
胃の不調は日常生活の質を著しく低下させます。食後の胃もたれや胸やけ、胃痛などに悩まされると、食事の楽しみが半減してしまいますよね。
消化不良や胃痛は、実は単なる一時的な症状ではなく、生活習慣や自律神経の乱れ、さらには潜在的な疾患のサインかもしれません。
私は消化器内科医として多くの患者さんの胃腸トラブルと向き合ってきました。その経験から言えるのは、消化器症状の改善には対症療法だけでなく、根本的な原因にアプローチすることが重要だということです。
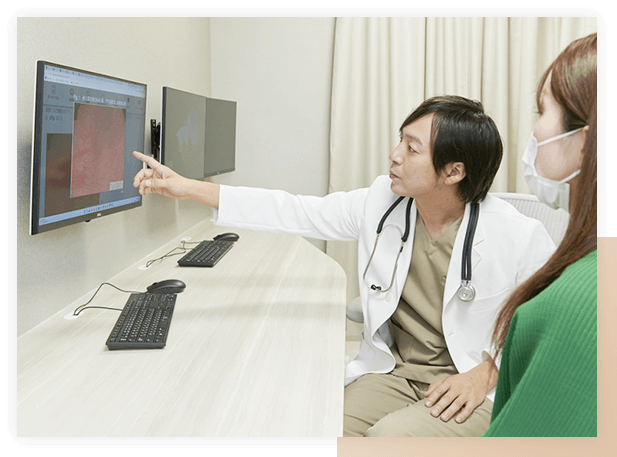
消化不良と胃痛の主な原因と症状
まず、消化不良と胃痛がなぜ起こるのか、その原因と症状を正しく理解しましょう。
消化不良とは、胃腸の働きが低下することでさまざまな不快な症状が現れる状態です。主な症状には、胃もたれ、胸やけ、吐き気、腹痛、膨満感などがあります。
胃痛については、みぞおちや上腹部辺りに痛みを感じるのが特徴で、時に胃がねじれるように痛むこともあります。これは胃痙攣と呼ばれる状態で、胃の筋肉が異常に収縮することで起こります。
消化不良と胃痛の主な原因は以下の4つに分類できます。
1. 食生活の乱れ
食べ過ぎや飲み過ぎは胃に大きな負担をかけます。特に脂肪の多い食べ物、香辛料や刺激物の多い食べ物、アルコールや炭酸飲料の過剰摂取は、胃酸や消化酵素の分泌を乱し、消化不良を引き起こしやすくなります。
また、早食いも消化不良の原因となります。噛む回数が少ないと食べ物の消化に時間がかかり、胃に負担をかけてしまうのです。
2. ストレスと自律神経の乱れ
胃の働きは自律神経によってコントロールされています。ストレスや疲労が溜まると自律神経のバランスが崩れ、胃腸の機能に悪影響を及ぼします。
具体的には、ストレスによって交感神経が優位になると、胃の運動が抑制され、消化機能が低下します。また、胃酸の分泌が増加し、胃粘膜を刺激することで胃痛を引き起こすこともあります。
夏場は特に注意が必要です。暑い屋外とクーラーの効いた屋内との寒暖差の影響で自律神経が乱れやすくなります。また、冷たい飲食物の摂取機会が増えることで、胃腸が冷えて胃の働きが低下しやすくなるのです。
3. 疾患による消化不良
消化不良や胃痛が長期間続く場合は、何らかの疾患が隠れている可能性があります。
胃食道逆流症は、胃と食道の境目にある下部食道括約筋が緩むことで、胃酸が食道に逆流し、胸やけや胃のむかつきを引き起こします。加齢による筋力低下や肥満、妊娠、姿勢の悪さなどが原因となることがあります。
胃炎は胃の粘膜に炎症が起きている状態で、急性胃炎と慢性胃炎があります。急性胃炎は食べ過ぎや飲み過ぎ、ストレス過多などが原因となり、慢性胃炎はピロリ菌感染が主な原因とされています。
機能性ディスペプシアは、器質的な異常がないにもかかわらず、上腹部の痛みや不快感、胃もたれなどの症状が続く状態です。ストレスや自律神経の乱れが関与していると考えられています。
4. 胃切除後症候群
胃の手術を受けた方に見られる症状です。胃を切除することで胃の機能が失われ、食べ物が一時的に溜まらなくなったり、消化吸収に影響が出たりします。
特に「ダンピング症候群」と呼ばれる症状では、食後5~30分で冷や汗、動悸、めまいなどの全身症状や、腹痛、下痢などの腹部症状が現れることがあります。また、食後2~3時間で頭痛、倦怠感、発汗などの症状が出ることもあります。

消化不良と胃痛を根本から改善する4つのアプローチ
消化不良と胃痛の改善には、対症療法だけでなく根本的な原因にアプローチすることが重要です。ここでは、私が臨床経験から効果的だと実感している4つの専門的アプローチをご紹介します。
1. 食事療法による胃腸環境の改善
消化不良や胃痛の改善には、まず食生活の見直しが欠かせません。以下のポイントを意識して食事をとりましょう。
- 少量多食:一度に大量の食事をとるのではなく、少量ずつ回数を分けて食べる
- よく噛む:一口30回を目安によく噛んで食べる
- 食事のバランス:高たんぱく、低脂肪、低炭水化物の食事を心がける
- 刺激物を避ける:辛い食べ物、酸味の強い食べ物、アルコール、カフェインなどは控える
- 食後の姿勢:食後すぐに横にならず、30分程度は座った状態を保つ
胃に優しい食材を選ぶことも大切です。消化の良い食材としては、お粥、うどん、豆腐、蒸した野菜、脂肪の少ない魚や肉などがおすすめです。発酵食品(ヨーグルトや味噌など)は腸内環境を整えるのに役立ちます。
一方で、脂っこい食べ物、生の野菜や果物、パンや麺類などの小麦製品、乳製品は消化に負担がかかる場合があるので、症状がひどい時は控えめにしましょう。
2. 自律神経バランスの調整
自律神経のバランスを整えることは、消化機能の改善に直結します。以下の方法を日常生活に取り入れてみましょう。
- 規則正しい生活:決まった時間に起床・就寝し、食事も規則的にとる
- 適度な運動:ウォーキングやヨガなど、リラックスできる運動を取り入れる
- ストレス管理:瞑想や深呼吸などのリラクゼーション法を実践する
- 十分な睡眠:質の良い睡眠をとることで自律神経のバランスを整える
- 温冷交代浴:ぬるめのお湯に浸かり、最後に冷水で締めることで自律神経を刺激する
特に深呼吸は、いつでもどこでも簡単にできるストレス軽減法です。腹式呼吸を意識して、ゆっくりと鼻から息を吸い、口からゆっくりと吐き出す。これを5分程度続けるだけでも、副交感神経が優位になり、胃腸の働きが活性化します。
ストレスを感じたときこそ、意識的に副交感神経を優位にする時間を作ることが大切です。「忙しくてそんな時間はない」と思うかもしれませんが、5分でも10分でも良いので、自分をリラックスさせる時間を作りましょう。
3. 胃腸機能を高める漢方薬と薬物療法
消化不良や胃痛に対しては、症状や原因に応じた薬物療法が効果的です。
消化酵素剤は、食べ物の消化を助ける酵素を補充することで、消化不良を改善します。食後の胃もたれや膨満感に効果的です。
制酸剤や胃粘膜保護剤は、胃酸の過剰分泌を抑えたり、胃粘膜を保護したりすることで、胃痛や胸やけを緩和します。
漢方薬も消化器症状の改善に効果的です。例えば、六君子湯(りっくんしとう)は、胃腸の働きを高め、食欲不振や胃もたれを改善します。半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)は、胃腸の熱を冷まし、胸やけや胃痛を和らげる効果があります。
ただし、薬物療法は自己判断で行うのではなく、必ず医師の診察を受けた上で適切な薬を処方してもらうことが重要です。特に漢方薬は、体質や症状に合わせて選ぶ必要があります。
4. 専門的検査による原因特定と治療
消化不良や胃痛が長期間続く場合は、専門的な検査を受けて原因を特定することが重要です。
胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)は、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察することで、胃炎や逆流性食道炎、潰瘍、がん・ポリープなどの病変を早期に発見できます。
ピロリ菌検査も重要です。ピロリ菌感染が確認された場合は、除菌治療を行うことで胃炎や胃潰瘍の改善、さらには胃がんの予防にもつながります。
また、腹部超音波検査やCT検査は、胃だけでなく、肝臓、胆嚢、膵臓など周辺臓器の状態も確認できるため、腹部症状の原因を幅広く探ることができます。
これらの検査結果に基づいて、適切な治療計画を立てることが、消化不良や胃痛を根本から改善する鍵となります。

症状別の対処法と注意点
消化不良や胃痛の症状は人によって異なります。ここでは、症状別の具体的な対処法と注意点をご紹介します。
胃もたれ・胸やけの場合
胃もたれや胸やけは、食後に特に感じやすい症状です。以下の対処法が効果的です。
- 食後すぐに横にならず、30分程度は座った状態を保つ
- 食後に軽い散歩をして、胃の消化を促す
- 就寝前3時間は食事を控える
- 枕を高くして寝ることで、胃酸の逆流を防ぐ
- 制酸剤や胃粘膜保護剤を服用する(医師の指示に従って)
胸やけが頻繁に起こる場合は、逆流性食道炎の可能性があります。特に就寝時に症状が悪化する場合や、咳や喉の痛みを伴う場合は、医療機関での検査をおすすめします。
胃痛・腹痛の場合
胃痛や腹痛がある場合は、まず胃を休ませることが大切です。
- 消化の良い食事を少量ずつとる
- 温かい飲み物(白湯など)を少しずつ飲む
- 腹部を温める(カイロや湯たんぽを使用)
- ストレスを軽減するリラクゼーション法を実践する
- 胃痛に効果的なツボ(中脘、内関など)を押す
ただし、以下のような場合は、すぐに医療機関を受診してください。
- 激しい痛みが続く場合
- 痛みが徐々に強くなる場合
- 吐き気や嘔吐を伴う場合
- 血便や黒い便が出る場合
- 発熱を伴う場合
吐き気・嘔吐の場合
吐き気や嘔吐がある場合は、脱水症状に注意が必要です。
- 水分を少量ずつ、こまめに摂取する
- 固形物は控え、消化の良い流動食から始める
- 生姜茶や薄い塩水を飲む
- 内関(手首の内側)のツボを押す
- 安静にして体を休める
嘔吐が続く場合や、嘔吐物に血液が混じっている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
ダンピング症候群の場合
胃の手術後に起こりやすいダンピング症候群には、以下の対処法が効果的です。
- 食事は一度にたくさん食べず、少しずつ回数を多くする
- 食べ物はよく噛み、唾液と混ぜ合わせてから飲み込む
- 高たんぱく、低脂肪、低炭水化物の食事を心がける
- 食後は横になって休む(早期ダンピング症候群の場合)
- 飴などで糖分を補給する(晩期ダンピング症候群の場合)
ダンピング症候群の症状が強い場合は、医師に相談することをおすすめします。薬物療法が効果的なこともあります。

予防と日常生活での注意点
消化不良や胃痛を予防するためには、日常生活での心がけが重要です。ここでは、予防のためのポイントをご紹介します。
規則正しい食生活
胃腸の健康を維持するためには、規則正しい食生活が基本です。
- 決まった時間に食事をとる
- よく噛んでゆっくり食べる
- 食べ過ぎ・飲み過ぎを避ける
- バランスの良い食事を心がける
- 空腹時のアルコール摂取を避ける
- 就寝前の食事を控える
特に夜遅い時間の食事は、胃酸の分泌を促し、就寝中の胃酸逆流を引き起こしやすくなります。夕食は就寝の3時間前までに済ませるようにしましょう。
ストレス管理と生活リズム
ストレスは消化不良や胃痛の大きな原因の一つです。ストレスを完全に排除することは難しいですが、上手に管理することは可能です。
- 自分なりのストレス発散法を見つける(趣味、運動など)
- 十分な睡眠をとる
- リラクゼーション法を実践する
- 無理なスケジュールを避け、休息時間を確保する
- 人間関係のストレスに対しては、コミュニケーションを大切にする
また、生活リズムを整えることも重要です。不規則な生活は自律神経のバランスを崩し、胃腸の機能低下を招きます。できるだけ同じ時間に起床・就寝し、規則正しい生活を心がけましょう。
定期的な健康チェック
消化不良や胃痛が長期間続く場合は、定期的な健康チェックが重要です。
- 年に一度は健康診断を受ける
- 40歳以上の方は、胃がん検診を定期的に受ける
- ピロリ菌検査を受け、陽性であれば除菌治療を検討する
- 気になる症状があれば、早めに医療機関を受診する
特に、以下のような症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。
- 急激な体重減少
- 嘔吐物や便に血液が混じる
- 強い腹痛が続く
- 黒色便が出る
- 飲み込みにくさを感じる
これらの症状は、重大な疾患のサインである可能性があります。早期発見・早期治療が重要です。
まとめ:消化不良と胃痛の根本改善に向けて
消化不良と胃痛は、単なる一時的な症状ではなく、生活習慣や自律神経の乱れ、さらには潜在的な疾患のサインかもしれません。
本記事でご紹介した4つのアプローチ(食事療法、自律神経バランスの調整、薬物療法、専門的検査による原因特定と治療)を組み合わせることで、消化不良と胃痛を根本から改善することが可能です。
特に重要なのは、症状が長期間続く場合は、自己判断せずに専門医の診察を受けることです。胃カメラ検査やピロリ菌検査などの専門的な検査を受けることで、早期に原因を特定し、適切な治療を受けることができます。
日常生活では、規則正しい食生活、ストレス管理、生活リズムの改善を心がけましょう。これらの取り組みは、消化不良や胃痛の予防だけでなく、全身の健康維持にもつながります。
消化器の不調は生活の質を大きく左右します。「胃の調子が悪いのは仕方ない」と諦めずに、ぜひ根本的な改善を目指してください。
当院では、消化器内科専門医による診察はもちろん、内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)、ピロリ菌検査、超音波検査、CT検査など、消化器疾患の診断に必要な検査を一通り行うことができます。消化器の不調でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
詳しい情報や予約方法については、石川消化器内科・内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。皆様の健康的な生活をサポートいたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
ピロリ菌検査と除菌治療の全知識〜成功率98%の最新方法を解説します
ピロリ菌とは?感染経路と胃への影響
ピロリ菌は正式名称をヘリコバクター・ピロリといい、胃の粘膜に生息するらせん形の細菌です。通常、胃の中は強い酸性環境のため細菌が生存できないのですが、ピロリ菌は「ウレアーゼ」という特殊な酵素を持っています。
この酵素によって胃酸を中和し、自らの周りをアルカリ性環境に変えることで生き延びる特殊な能力を持っているのです。まさに胃の中で生き抜くために進化した細菌といえるでしょう。
ピロリ菌の感染経路はまだ完全には解明されていませんが、主に口を介した感染(経口感染)と考えられています。特に幼少期に感染するケースが多く、上下水道が十分に整備されていなかった時代に育った世代ほど感染率が高い傾向にあります。
ピロリ菌に感染すると、胃の粘膜に炎症が起こります。この炎症が長期間続くと慢性胃炎へと進行し、医学的には「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」と呼ばれる状態になります。
さらに長期間にわたって炎症が続くと、胃粘膜の萎縮や腸上皮化生といった変化が生じ、一部の方では胃がんへと発展するリスクが高まります。
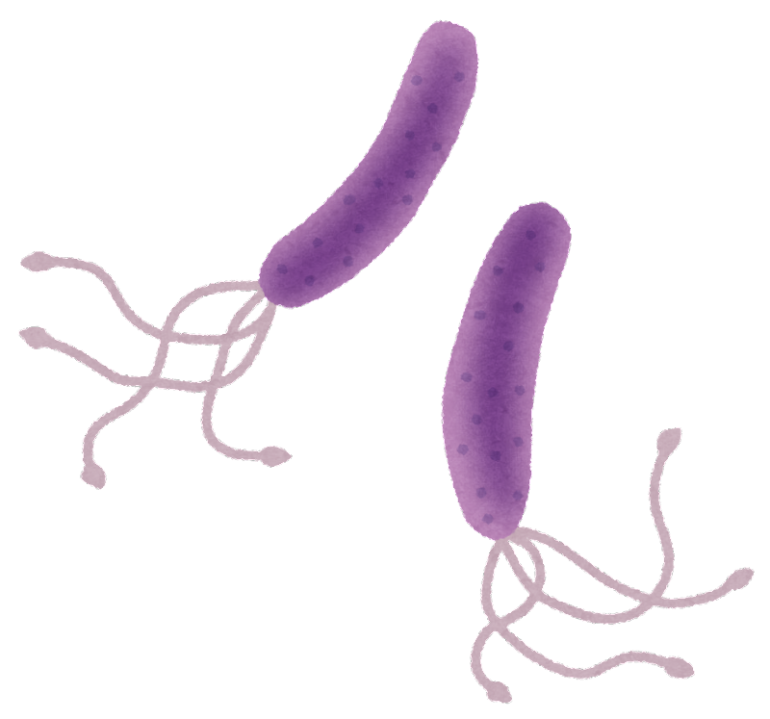
ピロリ菌が引き起こす病気とリスク
ピロリ菌感染が長期間続くと、様々な胃の病気を引き起こすリスクが高まります。特に注目すべきは、胃がんとの関連性です。
日本人のピロリ菌感染者は約3,500万人と推定されており、多くの方が自覚症状のないまま感染している状態です。ピロリ菌に感染している方が85歳までに胃がんに罹患する確率は、男性で約17%、女性で7.7%と報告されています。一方、非感染者ではそれぞれ1.0%、0.5%と大きな差があるのです。
ピロリ菌は胃がん以外にも、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の発症・再発と密接に関連しています。潰瘍患者さんのピロリ菌感染率は80〜90%と非常に高いことが分かっています。
また、胃MALTリンパ腫や特発性血小板減少性紫斑病など、胃以外の病気との関連も指摘されています。
これらのリスクを考えると、ピロリ菌に感染している場合は、適切な検査と除菌治療を受けることが重要です。特に胃がん予防の観点からは、早期の除菌が効果的とされています。
日本ヘリコバクター学会のガイドラインでは、ピロリ菌感染者全員に除菌療法を受けることを強く推奨しています。胃の健康を守るためにも、ピロリ菌検査を受けてみませんか?
ピロリ菌検査の種類と特徴
ピロリ菌の検査方法は大きく分けて、内視鏡を使う方法と使わない方法があります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
内視鏡を使わない検査方法
内視鏡検査を受けずに済むというメリットがあり、胃全体を診断できる「面診断」と呼ばれています。
尿素呼気試験は、診断薬を服用し、服用前後の呼気を集めて診断する方法です。簡単に行える上に精度が高く、現在の主流となっている検査法です。
抗体測定検査は、ピロリ菌に感染すると体内に作られる抗体を血液や尿から検出する方法です。過去の感染も含めて判定するため、現在の感染状況を正確に反映しない場合があります。
便中抗原検査は、便の中のピロリ菌の抗原を調べる方法です。非侵襲的で比較的精度が高いのが特徴です。
内視鏡を使う検査方法
内視鏡検査を利用して胃粘膜や胃組織の一部を採取して診断する方法です。胃の一部を調べる「点診断」となるため、偽陰性(実際は陽性なのに陰性と判定されること)の可能性があります。
迅速ウレアーゼ試験は、胃粘膜の一部を採取し、ピロリ菌が持つウレアーゼ酵素の活性を利用して判定します。特殊な反応液に粘膜を入れ、色の変化でピロリ菌の有無を判断します。
組織鏡検法は、採取した胃粘膜に特殊な染色を施し、顕微鏡でピロリ菌を直接観察する方法です。
培養法は、胃粘膜を採取してすりつぶし、ピロリ菌の発育環境で5〜7日間培養して判定します。
核酸増幅法は、内視鏡後の胃廃液をPCR検査にかけてピロリ菌とその薬剤感受性を調べる方法です。偽陰性が非常に少ない面診断が可能です。
ピロリ菌の検査は1つの方法だけでは偽陰性の可能性もあるため、疑わしい場合は複数の検査法を組み合わせて診断することが重要です。

ピロリ菌除菌治療の方法と成功率
ピロリ菌の除菌治療は、胃酸の分泌を抑える薬と2種類の抗生物質を組み合わせた「三剤併用療法」が基本となります。この3種類の薬を1日2回、7日間服用するのが標準的な治療法です。
胃酸を抑える薬には、従来のプロトンポンプ阻害薬(PPI)に加え、より強力な効果を持つカリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)も使用されるようになりました。
一次除菌療法の成功率は約70〜90%と報告されています。もし一次除菌に失敗した場合は、抗生物質の種類を変えて二次除菌を行います。
二次除菌まで含めると、除菌成功率は約97〜99%にまで上昇します。つまり、ほとんどの方が一次または二次除菌で成功するということです。
除菌治療後は、必ず除菌が成功したかどうかを確認するための検査(除菌判定)を行います。当院では便中抗原検査による除菌判定を実施しています。
保険診療では2回まで除菌治療を行うことができます。万が一、二次除菌でも成功しなかった場合は、三次除菌という選択肢もありますが、これは保険適用外となるため自費診療となります。
除菌治療の副作用としては、軟便・下痢(10〜30%)、嘔気・味覚障害(2〜5%)、皮疹(1〜2%)などが報告されていますが、皮疹を除けばほとんどは服薬終了後に改善します。
また、除菌に成功すると約10%の方に一時的に胸やけや胃もたれなどの逆流性食道炎の症状が現れることがありますが、これは胃炎が改善して胃酸分泌が回復することによるもので、多くの場合は一過性で治療を必要としません。
除菌治療の対象となる方と保険適用
ピロリ菌の除菌治療は、2013年から保険適用の範囲が拡大され、より多くの方が治療を受けられるようになりました。現在、以下の5つの条件に当てはまる方が保険診療の対象となっています。
保険適用となる5つの条件
- 内視鏡検査で胃炎と診断された方(ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎)
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍の方
- 胃MALTリンパ腫の方
- 特発性血小板減少性紫斑病の方
- 早期胃がんに対する内視鏡的治療後の方
特に1番目の「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」は2013年に保険適用となり、これによって多くの方が保険診療で除菌治療を受けられるようになりました。
ただし、除菌治療を受けるためには必ず内視鏡検査を受ける必要があります。これは胃の状態を確認し、適切な治療方針を立てるために重要なステップです。
上記の条件に当てはまらない方でも、ピロリ菌除菌を希望される場合は医師と相談の上、自費診療として治療を受けることも可能です。
胃がん予防の観点からは、ピロリ菌に感染している方は全員が除菌治療の対象となると考えられています。特に胃がんの家族歴がある方は、胃がんのリスクが2〜3倍高いとされており、積極的に検査・除菌を検討すべきでしょう。
あなたも胃の健康が気になるなら、一度検査を受けてみませんか?

除菌後のフォローアップと胃がんリスク
ピロリ菌の除菌に成功したからといって、胃がんのリスクがゼロになるわけではありません。除菌後も定期的な検査が必要な理由について説明します。
胃がんのリスクは、ピロリ菌を除菌することで約1/3程度にまで減少します。これは大きな効果ですが、それでもピロリ菌に一度も感染したことがない方と比べると、胃がんのリスクは75〜100倍ほど高い状態が続きます。
実際、除菌成功後も数年以内に、除菌成功者100人に1〜2人の割合で胃がんが発見されると報告されています。このため、除菌後も定期的に胃の検査(特に胃カメラ検査)を受けることが非常に重要です。
除菌後の再感染率は年率1%以下と言われており、除菌成功例でのピロリ菌の再陽性化率は0.2〜2%と低いことが報告されています。再陽性化の多くは、検査でも検出できないほどの微量のピロリ菌が胃の中に残っていて、それが増殖することによるものと考えられています。
また、除菌後に胃の状態が完全に元に戻るわけではありません。特に萎縮性胃炎が進行した状態で除菌した場合、胃粘膜の回復には時間がかかります。中には、逆流性食道炎や機能性ディスペプシアなどの症状が残る方もいます。
2025年4月に発表された国立がん研究センターの研究では、ピロリ菌除菌後の方でも、胃粘膜のDNAメチル化異常を測定することで、胃がんリスクを精密に予測できることが明らかになりました。今後はこのような検査も活用して、よりきめ細かなフォローアップが可能になるかもしれません。
当院では、ピロリ菌除菌後の方にも定期的な胃カメラ検査をお勧めしています。鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査で、負担を最小限に抑えながら胃の健康状態を確認できます。
若年層のピロリ菌検査と除菌の重要性
ピロリ菌は主に幼少期に感染し、その後長期間にわたって胃に炎症を引き起こします。胃がん予防の観点からは、胃粘膜の萎縮が進む前、つまりできるだけ若いうちに除菌することが理想的です。
近年、中学生を対象としたピロリ菌検査が全国的に広がっています。2023年の全国調査によると、105の自治体が中学生に対するピロリ菌検査を実施しており、年間約5万人の中学生が検査を受けています。
中学生を対象とした検査では、主に尿中ピロリ菌抗体測定が一次検査として用いられ、陽性の場合は尿素呼気試験や便中抗原検査などで確認が行われます。感染が確定した場合は、本人と保護者の希望により除菌治療が行われます。
若年層での除菌は、将来の胃がんリスクを大きく低減できる可能性があります。胃粘膜の萎縮がほとんど進んでいない段階で除菌することで、胃がん予防効果が最大限に発揮されるからです。
また、若いうちに除菌することで、将来的な胃潰瘍や十二指腸潰瘍などのリスクも減らすことができます。
ピロリ菌の感染率は年々低下していますが、家族内感染の可能性もあるため、ご家族にピロリ菌感染者がいる場合は、お子さんも検査を受けることをお勧めします。
当院では、中学生・高校生を含む若年層の方にも適切なピロリ菌検査と除菌治療を提供しています。胃の健康は一生の財産です。早期発見・早期治療で、将来の胃の病気リスクを減らしましょう。
まとめ:ピロリ菌除菌で胃の健康を守るために
ピロリ菌は胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、そして胃がんなど、様々な胃の病気と密接に関連しています。日本人のピロリ菌感染者は約3,500万人と推定されており、多くの方が自覚症状のないまま感染している状態です。
ピロリ菌検査には内視鏡を使う方法と使わない方法があり、それぞれ特徴があります。検査で感染が確認された場合は、胃酸分泌抑制薬と2種類の抗生物質を組み合わせた除菌治療を行います。
一次除菌の成功率は約70〜90%、二次除菌まで含めると約97〜99%と非常に高い成功率です。除菌治療は保険適用の範囲も広がり、胃炎と診断された方も保険診療で治療を受けられるようになりました。
ただし、除菌に成功しても胃がんのリスクがゼロになるわけではありません。除菌後も定期的な胃カメラ検査でフォローアップすることが重要です。
若年層、特に中学生を対象としたピロリ菌検査と除菌も広がっており、早期に除菌することで将来の胃がんリスクを大きく低減できる可能性があります。
胃の健康は一生の財産です。ピロリ菌検査と除菌治療で、胃の病気リスクを減らし、健康な胃を維持しましょう。
当院では、鎮静剤を使用した無痛の胃カメラ検査や、最新の方法によるピロリ菌検査・除菌治療を提供しています。胃の調子が気になる方、ピロリ菌検査をご希望の方は、お気軽に石川消化器内科・内視鏡クリニックにご相談ください。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
消化器内科を受診すべき症状と受診目安は?〜専門医が詳しく解説〜
消化器内科とはどのような診療科なのか
消化器内科は、食べ物の通り道である消化管(口から肛門まで)と、肝臓・胆のう・膵臓などの実質臓器に関する症状を診察・治療する診療科です。食道、胃、小腸、大腸といった消化管の病気から、肝臓、胆嚢、膵臓といった消化に関わる臓器の疾患まで幅広く対応しています。
消化器内科では、腹痛・吐き気・嘔吐・便秘・下痢・食欲不振・胸やけ・げっぷ・お腹の張りなどの症状を診ています。これらの症状が気になるときが、消化器内科を受診する目安となります。
風邪の症状である咳・鼻づまり・くしゃみなどは消化器の症状ではないため、消化器内科ではなく一般内科での受診をおすすめします。また、新型コロナウイルス感染症が疑われる発熱の場合も、発熱対応をしている内科を受診しましょう。

消化器内科を受診すべき主な症状
消化器内科を受診すべき症状は多岐にわたります。どのような症状があれば消化器内科を受診すべきか、具体的に見ていきましょう。
腹痛や胃痛は、消化器内科を受診する最も一般的な理由の一つです。みぞおちの痛みや下腹部痛など、お腹の痛み全般が対象となります。胃炎、胃潰瘍、腸炎、虫垂炎などが原因となることがあります。
特に痛みが強く、長時間続く場合や、痛みに加えて発熱や吐き気を伴う場合は、早めに受診することをおすすめします。
胃もたれや胸やけも消化器内科でよく診る症状です。胃が重苦しい、食後にもたれる感じ、胸やけがするといった症状は、逆流性食道炎や機能性ディスペプシア(消化不良)などが原因かもしれません。
下痢や便秘が続く場合も消化器内科の受診をおすすめします。ウイルス性腸炎から過敏性腸症候群まで様々な原因が考えられます。特に、普段と違う便通の変化が2週間以上続く場合は、一度専門医に相談しましょう。
吐き気・嘔吐は胃腸の不調による症状で、急性胃腸炎、食あたり、胃潰瘍の悪化などが原因として考えられます。特に嘔吐が激しく脱水症状がある場合や、嘔吐物に血液が混じる場合は早急に受診が必要です。
消化器内科で診断・治療できる主な疾患
消化器内科では様々な疾患の診断・治療を行っています。代表的なものをご紹介します。
食道の疾患
逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流することで起こる炎症です。胸やけや胸の痛み、喉の違和感などの症状が特徴的です。食道がんは早期発見が重要で、進行すると飲み込みにくさなどの症状が現れます。
食道裂孔ヘルニアは、胃の一部が横隔膜の食道裂孔を通って胸腔内に入り込む状態です。胸やけや胸痛の原因となることがあります。
胃の疾患
胃炎は胃の粘膜に炎症が起きる状態で、急性と慢性があります。ピロリ菌感染や薬剤、ストレスなどが原因となることが多いです。胃潰瘍は胃の粘膜や粘膜下層が損傷した状態で、みぞおちの痛みや胃もたれなどの症状が現れます。
機能性ディスペプシアは、胃もたれや胃の痛みなどの症状があるにもかかわらず、内視鏡検査などで器質的な異常が見つからない機能的な障害です。ストレスや生活習慣が関与していることが多いです。
胃がんは日本人に多いがんの一つで、早期発見・早期治療が重要です。初期には症状がないことも多く、定期的な検診が大切です。
腸の疾患
過敏性腸症候群は、腹痛と便通異常(下痢や便秘)を繰り返す機能性疾患です。ストレスや食事との関連が指摘されています。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)は、腸に慢性的な炎症が起こる疾患です。血便や腹痛、下痢などの症状が特徴的です。
大腸ポリープは大腸の粘膜から突出した隆起性病変で、多くは良性ですが、一部は大腸がんに進行する可能性があります。大腸がんは早期発見すれば内視鏡治療で完治することも多い疾患です。
肝臓・胆嚢・膵臓の疾患
消化器内科では、消化管だけでなく肝臓・胆嚢・膵臓の疾患も診療しています。
肝臓の疾患
肝炎はウイルス感染(B型・C型肝炎ウイルスなど)やアルコール、薬剤、脂肪の蓄積などによって肝臓に炎症が起こる疾患です。慢性化すると肝硬変や肝がんのリスクが高まります。
脂肪肝は肝臓に脂肪が蓄積した状態で、アルコールの過剰摂取や肥満、糖尿病などが原因となります。初期には自覚症状がほとんどありませんが、進行すると肝機能障害を引き起こすことがあります。
肝硬変は肝臓の線維化が進行した状態で、肝機能の低下や門脈圧亢進症による食道静脈瘤などの合併症を引き起こします。肝がんは肝細胞が悪性化したもので、肝硬変患者さんに発生することが多いです。

胆嚢・胆道の疾患
胆石症は胆嚢や胆管に結石ができる疾患です。右上腹部痛や背部痛、発熱などの症状が現れることがあります。胆嚢炎・胆管炎は胆石などが原因で胆嚢や胆管に炎症が起こる状態で、激しい腹痛や発熱、黄疸などの症状が現れます。
胆嚢ポリープは胆嚢内に生じる隆起性病変で、多くは良性ですが、大きさや形状によっては悪性の可能性もあります。胆道がん(胆嚢がん・胆管がん)は初期症状に乏しく、進行してから黄疸などの症状で発見されることが多いです。
膵臓の疾患
急性膵炎は膵酵素の活性化により膵臓自体が消化されて起こる急性炎症で、激しい腹痛や嘔吐などの症状が特徴です。慢性膵炎は膵臓の慢性的な炎症により、膵機能が徐々に低下していく疾患です。
膵がんは初期症状に乏しく、進行してから黄疸や腹痛などの症状が現れることが多い予後不良のがんです。早期発見が難しいため、リスク因子を持つ方は定期的な検査が重要です。
消化器内科での検査方法
消化器内科では様々な検査を行い、症状の原因を特定します。主な検査方法をご紹介します。
血液検査・尿検査
血液検査では、貧血・炎症反応・電解質バランス・腎機能・血糖値などの一般検査のほか、肝機能検査、肝炎ウイルス検査、ピロリ菌検査、がんの状態を調べる腫瘍マーカーなどを調べることができます。
尿検査では、尿中のビリルビンや尿ウロビリノーゲンなどを調べることで、肝臓や胆道系の異常を発見することができます。
内視鏡検査
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)は、口または鼻から内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸を直接観察する検査です。胃炎や逆流性食道炎、潰瘍、がん・ポリープなどの病変を発見することができます。
下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)は、肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体を観察する検査です。大腸ポリープや大腸がん、炎症性腸疾患などの診断に役立ちます。
小腸内視鏡検査(ダブルバルーン内視鏡、カプセル内視鏡)は、従来検査が難しかった小腸の観察を可能にした検査方法です。原因不明の消化管出血や小腸腫瘍の診断などに用いられます。
画像検査
腹部超音波検査(エコー)は、肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓などの臓器の状態を非侵襲的に観察できる検査です。脂肪肝や胆石、腫瘍などの診断に役立ちます。
CT検査は、X線を用いて体の断層画像を撮影する検査で、腹部全体の詳細な観察が可能です。腫瘍の有無や大きさ、周囲臓器との関係などを評価することができます。
MRI検査は、磁気を利用して体の断層画像を撮影する検査で、特に軟部組織の描出に優れています。MRCP(MR胆管膵管撮影)は、胆管や膵管の状態を非侵襲的に観察できる検査です。
消化器内科を受診する目安と注意点
消化器内科を受診すべきタイミングや、受診時の注意点についてご説明します。
受診を検討すべき症状と状況
次のような症状や状況がある場合は、消化器内科の受診を検討しましょう。
- 腹痛や胃痛が続く、または強い痛みがある
- 吐き気や嘔吐が続く、または嘔吐物に血液が混じる
- 胸やけや胃もたれが続く
- 便秘や下痢が2週間以上続く
- 便に血液が混じる、または黒い便が出る
- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)がある
- 原因不明の体重減少や食欲不振がある
- 健康診断で肝機能異常や便潜血陽性を指摘された
特に、以下のような緊急性の高い症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。
- 激しい腹痛が続く
- 吐血や下血がある
- 高熱を伴う腹痛がある
- 腹部が硬く張っている
- 意識障害や強い倦怠感がある
受診時の注意点
消化器内科を受診する際は、以下の点に注意しましょう。
まず、腹部の検査は基本的に空腹の状態で行うため、なるべく直前の食事は摂らないでください。特に腹痛や吐き気などのお腹の症状があって受診するときは、食事を摂らずに受診したほうがすぐに検査できる場合があります。
また、症状の詳細をメモしておくと診察がスムーズに進みます。いつから症状が始まったか、どのような状況で症状が出るか、痛みの場所や性質、食事との関連などを記録しておくと良いでしょう。
服用中の薬がある場合は、お薬手帳や薬の名前がわかるものを持参してください。特に胃薬や痛み止め、抗血栓薬(血液をサラサラにする薬)は消化器症状や検査に影響を与えることがあります。
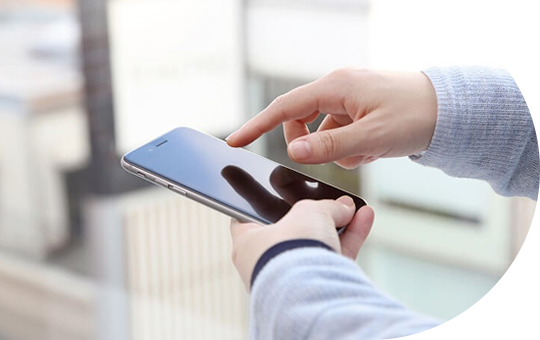
消化器内科での治療法
消化器内科では、症状や疾患に応じて様々な治療法が選択されます。主な治療法をご紹介します。
薬物療法
消化器疾患の多くは、まず薬物療法が行われます。胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬、H2ブロッカーなど)、胃腸の動きを整える薬(消化管運動改善薬)、腸の炎症を抑える薬(5-ASA製剤、ステロイド、免疫調節薬など)、肝機能を改善する薬(肝庇護薬)などが使用されます。
また、ウイルス性肝炎に対する抗ウイルス薬、ピロリ菌感染に対する除菌療法、がんに対する抗がん剤治療なども行われます。
内視鏡治療
内視鏡を用いた治療は、消化器内科の大きな特徴の一つです。早期の消化管がんに対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)や内視鏡的粘膜切除術(EMR)、大腸ポリープに対するポリペクトミーなどが行われます。
また、消化管出血に対する内視鏡的止血術、食道静脈瘤に対する内視鏡的結紮術、胆石や膵石に対する内視鏡的結石除去術、胆管・膵管狭窄に対するステント留置術なども行われます。
インターベンショナルラジオロジー
画像診断装置を用いて行う低侵襲治療も消化器疾患の治療に用いられます。肝がんに対するラジオ波焼灼療法(RFA)や肝動脈塞栓術(TAE)、膵がんなどによる閉塞性黄疸に対する経皮経肝胆道ドレナージ(PTBD)などが代表的です。
生活習慣の改善・食事療法
多くの消化器疾患は生活習慣と密接に関連しています。適切な食事、適度な運動、禁煙、節酒などの生活習慣の改善が治療の基本となることも少なくありません。
特に、逆流性食道炎や過敏性腸症候群、脂肪肝などは、生活習慣の改善だけで症状が軽減することもあります。医師や栄養士の指導のもと、疾患に応じた食事療法を行うことも重要です。

消化器疾患の予防と日常生活での注意点
消化器疾患を予防し、健康な消化器を維持するための日常生活での注意点をご紹介します。
バランスの良い食生活
消化器の健康を維持するためには、バランスの良い食生活が基本です。野菜、果物、全粒穀物などの食物繊維を十分に摂取し、脂肪や糖分の過剰摂取を避けましょう。
また、規則正しい食事時間を心がけ、よく噛んでゆっくり食べることも大切です。過食や早食いは消化器に負担をかけ、様々な症状の原因となります。
適度な運動習慣
適度な運動は、腸の蠕動運動を促進し、便秘の予防に役立ちます。また、肥満を防ぐことで、脂肪肝や胆石症などのリスクも低減できます。
ウォーキングやサイクリングなどの有酸素運動を週に3回以上、30分程度行うことを目標にしましょう。
アルコールと喫煙
過度のアルコール摂取は、肝臓や膵臓に大きな負担をかけます。アルコールは適量を守り、週に2日以上の休肝日を設けることをおすすめします。
喫煙は食道がんや胃がん、膵がんなどのリスク因子となります。禁煙することで、これらのがんのリスクを低減できます。
定期的な健康診断
消化器疾患、特にがんは早期発見が重要です。40歳以上の方は、年に1回の健康診断を受け、胃がん検診や大腸がん検診を定期的に受けることをおすすめします。
また、肝炎ウイルス検査やピロリ菌検査も、一度は受けておくと良いでしょう。
まとめ
消化器内科は、食道から肛門までの消化管と、肝臓・胆嚢・膵臓などの実質臓器に関する疾患を診療する診療科です。腹痛、胃もたれ、下痢、便秘など、日常生活でよく経験する症状の多くが消化器内科の受診対象となります。
消化器疾患は早期発見・早期治療が重要です。特に、長引く症状や、血便、黄疸、急激な体重減少などの警告症状がある場合は、すぐに消化器内科を受診しましょう。
当院では、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の内視鏡検査を提供しており、「辛い・苦しい」というイメージのある胃カメラ・大腸カメラ検査を「より気軽に」「よりスピーディーに」、そして安心して受けていただける体制を整えています。
また、高性能な拡大内視鏡を導入し、特殊な光によって粘膜の微細な変化まで観察できる大学病院レベルの検査が可能です。患者様の利便性を考慮し、初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しています。
消化器の健康は全身の健康につながります。気になる症状があれば、お気軽に石川消化器内科・内視鏡クリニックにご相談ください。
詳細な情報や予約方法については、石川消化器内科・内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。皆様の健康管理を誠心誠意サポートいたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
痔の放置は危険?自然治癒と専門治療の正しい選択とは
痔の症状と種類〜放置するリスクを理解する
痔の症状に悩まされている方は少なくありません。「このまま放置しても大丈夫だろうか」「自然に治るのを待った方がいいのか」と迷われる方も多いでしょう。
痔は肛門の病気の総称で、主に「いぼ痔(痔核)」「切れ痔(裂肛)」「痔ろう」の3種類に分けられます。それぞれ症状や進行度によって治療法が異なるため、正しい知識を持つことが重要です。
痔の放置は思わぬリスクを伴います。軽度の症状であれば自然治癒する可能性もありますが、悪化すると日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、より深刻な病気を見逃す可能性もあるのです。
いぼ痔(痔核)の症状と進行度
いぼ痔は最も一般的な痔の症状で、肛門の内側にできる「内痔核」と外側にできる「外痔核」に分けられます。肛門の中間あたり、直腸粘膜と皮膚の境目を「歯状線」と言い、この内側にできるものを内痔核、外側にできるものを外痔核と呼びます。
内痔核は比較的痛みが少ないのが特徴です。主な症状は排便時の出血で、トイレットペーパーに付く程度から便器が赤くなるほどの出血まで様々です。進行すると排便時に肛門から飛び出す脱肛の症状が現れることもあります。
内痔核は進行度によって4段階に分類されます。
- 1度:いぼが常に歯状線の内側に留まっている段階。時々、出血や痛みがあります。
- 2度:排便時などのいきんだ拍子にいぼが歯状線の外側に出てしまい(脱肛)、その後自然に元に戻ります。
- 3度:排便時などにいぼが出て、自然には戻らず、指などで戻す必要があります。
- 4度:常にいぼが歯状線の外に出ている状態。さらに悪化すると「嵌頓痔核」となり、肛門周囲がひどく腫れ、強い痛みを伴います。
一方、外痔核は歯状線の外側にできるいぼ痔で、皮膚の上にできるため痛みを伴うことが多いです。急に腫れる「血栓性外痔核」は特に強い痛みを感じます。
切れ痔(裂肛)と痔ろうの症状
切れ痔は肛門の粘膜に傷ができる状態です。硬い便による排便時の痛みと出血が主な症状です。便秘や下痢を繰り返すことで悪化しやすく、慢性化すると治りにくくなります。
痔ろうは肛門腺という小さな腺から細菌が入り込み、炎症を起こして膿がたまる状態です。肛門周囲の皮膚に膿を出すためのトンネル(瘻管)ができ、そこから膿が出続けます。痔ろうは自然治癒がほとんど期待できず、放置すると悪化するため注意が必要です。
鮫島病院の鮫島隆志院長によると、「痔ろうは10年以上放置するとがん化した例があります。定年退職後にゆっくり治そうと放っておいた結果、がんになっていたということもある」とのことです。痔ろうの放置は非常に危険といえるでしょう。

痔は自然治癒する?医学的見解と現実
「痔は自然に治るのだろうか?」これは多くの患者さんが抱く疑問です。結論から言うと、痔の種類や進行度によって自然治癒の可能性は大きく異なります。
軽度のいぼ痔や切れ痔は、生活習慣の改善や適切なセルフケアによって症状が緩和し、自然治癒する可能性があります。しかし、進行した痔や痔ろうは自然治癒がほとんど期待できません。
痔の自然治癒に関して、いくつかの重要なポイントを見ていきましょう。
いぼ痔の自然治癒の可能性
いぼ痔(痔核)は初期段階であれば、適切なセルフケアによって症状が改善する可能性があります。特に1度から2度の内痔核は、生活習慣の改善(食物繊維の摂取増加、十分な水分補給、適度な運動など)によって症状が緩和することがあります。
しかし、3度以上に進行した内痔核や、強い痛みを伴う外痔核(特に血栓性外痔核)は、自然治癒を期待するのは難しいでしょう。これらの場合は専門的な治療が必要となります。
血栓性外痔核は、発症から48〜72時間以内であれば、専門医による切開排血処置で劇的に症状が改善することがあります。放置すると痛みは徐々に和らぐものの、いぼとして残ってしまう可能性があります。
切れ痔と痔ろうの自然治癒
切れ痔(裂肛)は初期であれば、便通の改善や局所的なケアによって自然治癒する可能性があります。しかし、慢性化すると肛門の括約筋が緊張して血流が悪くなり、治りにくくなります。
痔ろうに関しては、自然治癒はほとんど期待できません。所沢肛門病院の栗原浩幸院長によると、「痔ろうの患者さんには、複雑化する前に手術を勧めています。再発を繰り返すうちに膿が今までとは違う場所から出たりして複雑な形になることがあるからです」とのことです。
痔ろうは放置すると悪化するだけでなく、長期間(10年以上)の放置によってがん化するリスクもあります。このことからも、痔ろうは早期の専門的治療が必要といえるでしょう。
痔を放置するリスク〜見逃せない危険信号
痔の症状を放置することには、様々なリスクが伴います。特に注意すべきは、痔と似た症状を示す他の深刻な疾患を見逃してしまう可能性です。
出血や痛みといった症状は、大腸がんなどの重大な病気のサインである可能性もあります。札幌いしやま病院の石山元太郎理事長は「一番やってはいけないのが、何度も出血を繰り返しているのに勝手に痔だと思い込んで放置しておくことです。大腸がんのリスクもあるからです」と警告しています。
大腸がんとの見分け方と注意点
痔と大腸がんは症状が似ていることがあり、特に出血症状は両方に共通しています。松田病院の松田聡院長によると、「痔の手術をする前の患者さんに大腸カメラを施行すると約13%の人にポリープが見つかり、0.4%の人にがんが見つかる」とのことです。
以下のような症状がある場合は、痔だと自己判断せず、専門医の診察を受けることが重要です。
- 繰り返しの出血(特に1年以上続くもの)
- 便の形状の変化(細くなった、柔らかい便しか出ないなど)
- 排便習慣の変化(便秘や下痢が続くなど)
- 原因不明の体重減少や食欲不振
- 強い痛みや違和感が続く
岡崎外科消化器肛門クリニックの岡崎啓介院長は「おしりからの出血の場合、一番にがんを疑わなければなりません。安易におしりの病気と診断せず、まずはがんのリスクを疑い、そのリスクを消してあげることは、私たち医師の責任でもあります」と述べています。
痔ろうの放置による合併症
痔ろうを放置すると、膿瘍が広がり、複雑な瘻管(ろうかん)を形成することがあります。これにより手術が困難になるだけでなく、長期間の放置によってがん化するリスクもあります。
痔ろうは保存療法ではほとんど治癒せず、完治させるためには手術が必要です。早期に適切な治療を受けることで、より簡単な手術で済み、回復も早くなります。

痔の専門的治療法〜最新の選択肢
痔の症状が重い場合や自然治癒が期待できない場合は、専門的な治療が必要になります。現在では様々な治療法があり、症状や進行度に応じて最適な方法が選択されます。
ここでは、いぼ痔(痔核)と痔ろうの主な治療法について解説します。
いぼ痔の治療法
いぼ痔(痔核)の治療法は、症状の程度によって異なります。軽度から中等度の場合は保存的治療が選択されますが、重度の場合は手術が必要になることがあります。
主な治療法には以下のようなものがあります。
- 薬物療法:内服薬や外用薬を使用して、腫れ、痛み、出血などの症状を緩和します。薬物療法によってほとんどの症状は改善されますが、いぼそのものがなくなるわけではありません。
- ジオン注射(ALTA療法):痔核へと流れ込む血液の量を減らし、線維化させる薬剤を注射する治療です。「切らない内痔核治療」として注目されていますが、内痔核の治療にのみ適用されます。
- ゴム輪結紮療法:輪ゴムで痔核を結紮し、血流を断つことで痔核を脱落させます。簡便で痛みも少ないというメリットがありますが、術後の出血には注意が必要です。
- 結紮切除術:古くから行われている手術で、どのような痔核にも対応できます。痔核に栄養を届ける動脈を結紮(縛ること)し、痔核そのものを取り除きます。
石川消化器内科・内視鏡クリニックでは、痛みの少ないALTA療法を提供しており、2023年7月にはこの治療法がドクターズファイルに掲載されました。ALTA療法は切らずに治療できるため、患者さんの負担が少ないのが特徴です。
痔ろうの治療法
痔ろうの治療は基本的に手術が必要です。主な手術法には以下のようなものがあります。
- 従来の手術法:肛門内から肛門外の皮膚に貫通する膿が通るトンネル(瘻管)をくり抜き、輪ゴムを通して徐々に小さくしていく方法です。
- 括約筋温存術(LIFT手術など):近年各専門病院で行われている方法で、筋肉を全く切らない手術です。膿の管を糸で縛って膿の交通を遮断し、外側の筋肉と関係ないところだけをくり抜きます。
痔ろうの手術では、麻酔も重要なポイントです。札幌いしやま病院では「仙骨硬膜外麻酔」を使用しており、これにより麻酔自体の痛みが軽減され、患者さんの負担が少なくなるとのことです。
痔の自己管理と予防法〜再発を防ぐために
痔の症状を改善し、再発を防ぐためには、日常生活での自己管理が非常に重要です。特に生活習慣の改善は、軽度の痔の自然治癒を促すだけでなく、治療後の再発予防にも効果的です。
ここでは、痔の自己管理と予防のための具体的な方法を紹介します。
効果的な生活習慣の改善
痔の予防と改善に効果的な生活習慣の改善点には、以下のようなものがあります。
- 食物繊維の摂取:野菜、果物、全粒穀物などの食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取しましょう。食物繊維は便のかさを増し、柔らかくすることで排便を容易にします。
- 十分な水分補給:1日に1.5〜2リットルの水分を摂取することで、便が硬くなるのを防ぎます。特に食物繊維を増やす場合は、水分摂取も増やすことが重要です。
- 適度な運動:定期的な運動は腸の働きを活発にし、便秘の予防に役立ちます。ウォーキングや水泳など、無理のない運動を継続しましょう。
- トイレを我慢しない:便意を感じたらなるべく早くトイレに行きましょう。便意を我慢すると便が硬くなり、排便時に強くいきむ必要が生じます。
- 長時間のトイレ滞在を避ける:トイレで長時間座っていると、肛門周辺の血流が悪くなります。スマートフォンや本を読むなどの習慣は控えましょう。
- 適切な排便姿勢:膝を腰より高い位置に上げると、直腸と肛門の角度が自然になり、いきまずに排便しやすくなります。
これらの生活習慣の改善は、痔の症状を和らげるだけでなく、便秘や下痢といった痔の原因となる症状の改善にも効果的です。
市販薬の適切な使用法
軽度の痔の症状には、市販薬が効果的な場合があります。特に外痔核は、市販の軟膏タイプの薬を使用して自己治療できることもあります。
しかし、市販薬には以下のような注意点があります。
- 内痔核と外痔核では適切な薬剤が異なります。症状に合った薬を選びましょう。
- 市販薬で症状が改善しない場合や、2週間以上症状が続く場合は、専門医の診察を受けましょう。
- 出血が続く場合は、痔以外の病気の可能性もあるため、自己判断せず医療機関を受診しましょう。
市販薬はあくまで対症療法であり、根本的な治療ではありません。症状が重い場合や繰り返す場合は、専門医による適切な診断と治療が必要です。

痔の専門医を受診するタイミング〜見極めのポイント
痔の症状があるとき、「このくらいなら自然に治るだろう」と考えて放置してしまうことがありますが、適切なタイミングで専門医を受診することが重要です。
では、どのようなタイミングで医療機関を受診すべきでしょうか。ここでは、痔の種類別に受診の目安を紹介します。
内痔核・外痔核の受診目安
内痔核の場合、以下のような症状があれば医療機関を受診しましょう。
- 排便時に繰り返し出血がある
- 排便時にいぼが脱出し、自分で戻せない
- いぼが常に脱出したままになっている
- 市販薬を使用しても2週間以上症状が改善しない
- 痛みや違和感が強く、日常生活に支障がある
外痔核の場合は、以下のような症状があれば受診が必要です。
- 強い痛みを伴う腫れがある
- 腫れが急に大きくなった(血栓性外痔核の可能性)
- 市販薬を使用しても症状が改善しない
- 出血が続く
特に血栓性外痔核は、発症から48〜72時間以内に専門医による処置を受けると、痛みが劇的に改善することがあります。早めの受診が重要です。
切れ痔・痔ろうの受診目安
切れ痔(裂肛)の場合、以下のような症状があれば受診しましょう。
- 排便時に強い痛みがある
- 出血が続く
- 市販薬を使用しても症状が改善しない
- 慢性的に症状を繰り返す
痔ろうの場合は、以下のような症状があれば早急に受診が必要です。
- 肛門周囲に膿がたまり、痛みや腫れがある
- 肛門周囲の皮膚から膿や分泌物が出る
- 発熱や全身倦怠感がある
痔ろうは自然治癒がほとんど期待できないため、症状があれば早めに専門医を受診することが重要です。
まとめ〜痔の放置と専門治療の選択
痔の症状は多くの方が経験するものですが、放置することで悪化したり、より深刻な病気を見逃したりするリスクがあります。
軽度のいぼ痔や切れ痔は、生活習慣の改善や適切なセルフケアによって自然治癒する可能性もありますが、症状が重い場合や長期間続く場合は、専門医による適切な診断と治療が必要です。
特に注意すべきは、痔と似た症状を示す大腸がんなどの重大な疾患を見逃さないことです。繰り返しの出血や便の形状の変化などがある場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。
痔ろうに関しては、自然治癒はほとんど期待できず、放置することで複雑化したり、長期間の放置でがん化するリスクもあります。早期の専門的治療が重要です。
石川消化器内科・内視鏡クリニックでは、痛みの少ないALTA療法など、患者さんの負担を軽減する治療法を提供しています。痔の症状でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
痔の症状は恥ずかしいと感じて受診をためらう方も多いですが、早期の適切な治療によって症状の改善や合併症の予防が可能です。自分の健康のために、適切なタイミングで専門医を受診することをお勧めします。
当院では患者さんのプライバシーに配慮した診療を心がけておりますので、些細な症状でもお気軽にご相談ください。
詳しい情報や診療時間については、石川消化器内科・内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
粉瘤の手術は痛くない?日帰り治療の全知識
粉瘤とは?基本知識と症状
皮膚の下にしこりを感じたことはありませんか?それは「粉瘤(ふんりゅう)」かもしれません。粉瘤は別名「アテローム」や「表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ)」とも呼ばれる良性腫瘍です。皮膚の内側に袋状の構造物ができ、本来皮膚から剥がれ落ちるはずの角質や皮脂などの老廃物が袋の中に溜まってしまうことで発生します。
この袋の中に溜まった老廃物は外に排出されないため、時間とともに少しずつ大きくなっていきます。初期の段階では小さなしこりとして現れますが、放置すると袋状に変化し、大きくなっていくのが特徴です。
粉瘤は身体のどこにでもできる可能性がありますが、特に顔、首、背中、耳の後ろなどにできやすい傾向があります。やや盛り上がった数ミリから数センチの半球状のしこりとして現れ、中央に黒点状の開口部があることが多いです。
粉瘤の特徴的な症状として、強く圧迫すると中央の開口部からドロドロとした白っぽい物質が出てくることがあります。この内容物は特有の臭いを持っていることが多く、これが粉瘤の特徴の一つです。
ニキビと間違われることもありますが、大きな違いがあります。ニキビは自然治癒することが多いのに対し、粉瘤は皮膚の奥にできる腫瘍のため、自然に治ることはありません。また、ニキビと違って独特の臭いを放つことも特徴です。
 粉瘤の手術は本当に痛くない?麻酔の種類と効果
粉瘤の手術は本当に痛くない?麻酔の種類と効果
「粉瘤の手術は痛いのでは?」と心配される方は多いです。結論からいうと、適切な麻酔を使用すれば、手術中の痛みはほとんど感じません。実際の手術では局所麻酔を使用するため、麻酔注射時にわずかな痛みを感じる程度です。
私が日々の診療で行っている粉瘤手術では、患者さんの痛みを最小限に抑えるために細心の注意を払っています。麻酔注射の際には極めて細い針を使用し、注射の痛みを「ちょっとした筋肉痛程度」と表現される方がほとんどです。麻酔が効いてしまえば、その後の手術操作による痛みはほぼ感じません。
麻酔には主に以下の種類があります:
- 局所麻酔:粉瘤の周囲に直接麻酔薬を注射し、その部分のみを麻痺させる方法です。日帰り手術で最も一般的に使用されます。
- 表面麻酔:皮膚表面に麻酔クリームを塗布して、注射の痛みを軽減する方法です。特に痛みに敏感な方や子どもに使用されることがあります。
- 全身麻酔:大きな粉瘤や複数の粉瘤を同時に切除する場合など、特殊なケースで使用されることがあります。
一般的な粉瘤の手術では局所麻酔が十分効果的です。麻酔が効くまでには約5分程度かかりますが、その後は痛みを感じることなく手術を受けることができます。
患者さんの中には「麻酔の注射が怖い」という方もいらっしゃいますが、現在は非常に細い針を使用するため、チクッとした痛みを感じる程度です。また、麻酔薬を体温に近い温度にしたり、ゆっくりと注入したりすることで、痛みをさらに軽減する工夫も行っています。
粉瘤の日帰り手術の流れと所要時間
粉瘤の日帰り手術は、一般的に30分程度で終了する比較的簡単な処置です。手術の流れを詳しく見ていきましょう。
まず診察で粉瘤と確定診断されると、その日のうちに手術が可能なケースも多いです。特に小さな粉瘤(5mm程度)であれば、診察後すぐに手術を行うことができます。
手術前の準備
手術前には、手術部位の消毒を行います。清潔な環境で手術を行うために、手術部位の周囲を消毒用アルコールや消毒液でしっかりと消毒します。その後、清潔なドレープ(布)で手術部位以外を覆います。
手術の実施
局所麻酔を注射した後、麻酔が効いてきたら(約5分後)、手術を開始します。粉瘤の手術方法には主に「切開法」と「くりぬき法(パンチ法)」の2種類があります。
- 切開法:粉瘤の上の皮膚を小さく切開し、袋ごと粉瘤を摘出する方法です。比較的大きな粉瘤や炎症を起こしている粉瘤に適しています。
- くりぬき法(パンチ法):特殊な器具(パンチ)を使って粉瘤に小さな穴を開け、そこから内容物と袋を取り出す方法です。傷跡が小さく済むため、美容的に目立ちにくい利点があります。
手術中は痛みをほとんど感じませんが、圧迫感や引っ張られる感覚はあるかもしれません。手術時間は粉瘤の大きさや場所によって異なりますが、一般的には5〜20分程度です。
手術後の処置
粉瘤を摘出した後は、傷口を縫合します。使用する糸は自然に溶ける吸収糸の場合と、後日抜糸が必要な非吸収糸の場合があります。その後、傷口に消毒薬を塗り、ガーゼや保護テープで覆います。
手術直後から痛みを感じる方もいますが、多くの場合は軽度で、市販の痛み止めで対応できる程度です。医師から処方される痛み止めを服用すれば、痛みの心配はほとんどありません。

炎症を起こした粉瘤の対処法と手術のタイミング
粉瘤に細菌が侵入すると、炎症を起こすことがあります。これを「炎症性粉瘤」と呼びます。赤み、腫れ、熱感、強い痛みなどの症状が現れ、膿が溜まることもあります。
炎症を起こした粉瘤は非常に痛みを伴うことがあります。なぜなら、粉瘤の袋の中には本来、体内に入った菌などを排除する免疫機能を担う細胞が存在していないため、細菌感染に弱いという性質があるからです。
炎症を起こした粉瘤を自己判断で潰したり、触ったりするのは厳禁です。細菌感染を悪化させ、より広範囲に炎症が広がる可能性があります。特に顔面の粉瘤は、炎症が脳に近い部位に波及する危険性もあるため、専門医の診察を早急に受けることが重要です。
炎症性粉瘤の対処法は、その状態によって異なります:
- 軽度の炎症の場合:抗生物質の内服や外用薬で炎症を抑え、落ち着いてから手術を行います。
- 強い炎症や膿がたまっている場合:まず排膿処置(切開して膿を出す)を行い、炎症が落ち着いてから改めて粉瘤の摘出手術を行います。
では、粉瘤の手術を受けるベストなタイミングはいつでしょうか?基本的には、炎症を起こしていない状態が手術に適しています。炎症がある場合は、まず炎症を抑える治療を行い、落ち着いてから手術を検討します。
しかし、炎症を繰り返す粉瘤や大きくなってきた粉瘤は、早めに手術を受けることをお勧めします。小さいうちに手術を受ければ、手術時間も短く、傷跡も小さく済みます。
粉瘤を見つけたら、「痛くないから」と放置せず、一度専門医に相談することが大切です。適切な時期に適切な治療を受けることで、より安全で効果的な治療が可能になります。
粉瘤手術後の注意点と回復期間
粉瘤の手術後は、適切なケアを行うことで順調な回復が期待できます。手術後の注意点と回復期間について詳しく見ていきましょう。
手術当日の注意点
手術当日は、激しい運動や入浴(シャワーは可能な場合が多い)を避けることが一般的です。また、アルコールの摂取も控えましょう。手術部位に痛みがある場合は、処方された痛み止めを指示通りに服用してください。
手術部位は清潔に保つことが重要です。医師から特別な指示がない限り、手術当日からシャワーを浴びることができる場合が多いです。ただし、傷口を直接こすらないよう注意しましょう。
手術後数日間の過ごし方
手術後数日間は、傷口の保護と感染予防が最も重要です。医師の指示に従って、傷口の消毒やガーゼ交換を行いましょう。一般的には、以下のようなケアが必要です:
- 傷口を清潔に保つ(指示された方法で消毒)
- ガーゼ交換(医師の指示に従う)
- 傷口が濡れないよう注意(入浴時はラップなどで保護)
- 激しい運動や重い物の持ち上げを避ける
手術後に異常な痛み、出血、発熱、傷口からの膿などの症状がある場合は、すぐに医師に相談してください。これらは感染の兆候かもしれません。
回復期間と傷跡について
粉瘤手術後の回復期間は、粉瘤の大きさや場所、手術方法によって異なります。一般的には以下のような経過をたどります:
- 1週間以内:傷口の痛みや腫れがピークを迎え、その後徐々に軽減
- 1〜2週間後:抜糸(非吸収糸を使用した場合)
- 2〜4週間後:日常生活に完全復帰可能
傷跡については、手術方法や個人の肌質、手術部位によって異なります。くりぬき法では傷跡が小さく済みますが、大きな粉瘤の場合は切開法が必要となり、やや大きな傷跡が残ることがあります。
傷跡を目立たなくするためには、日焼けを避け、医師の指示に従ったケアを行うことが重要です。必要に応じて、傷跡用のクリームやテープを使用することもあります。
粉瘤の手術は比較的簡単な処置ですが、適切なアフターケアを行うことで、より良い治癒と美容的な結果が期待できます。不安なことがあれば、遠慮なく担当医に相談しましょう!

粉瘤手術の費用と保険適用について
粉瘤の手術費用について気になる方も多いでしょう。良いニュースとして、粉瘤の手術は基本的に健康保険が適用される治療です。診断、検査、手術、病理検査のすべてで保険適用が可能です。
健康保険を使用した場合の粉瘤手術の費用は、粉瘤の大きさや手術方法、病院の種類(診療所、総合病院など)によって異なりますが、一般的には以下のような費用が目安となります:
- 初診料:約1,000〜3,000円
- 手術費用:約5,000〜30,000円(粉瘤の大きさや数による)
- 病理検査(必要な場合):約3,000〜10,000円
これらはあくまで目安であり、実際の費用は医療機関によって異なります。また、3割負担の場合の金額であり、高齢者や小児などは負担割合が異なる場合があります。
粉瘤の手術が保険適用となる条件は、基本的に「医学的に必要と判断される場合」です。具体的には以下のような状況が該当します:
- 粉瘤が大きくなり、日常生活に支障をきたしている
- 炎症を起こしている、または繰り返している
- 痛みや不快感がある
- 悪性の可能性を否定するために摘出が必要と判断される
一方、単に美容的な理由だけで粉瘤の除去を希望する場合は、保険適用外(自費診療)となることがあります。自費診療の場合、費用は医療機関によって大きく異なりますが、一般的には20,000〜100,000円程度です。
また、医療保険に加入されている方は、手術給付金を受けられる場合もあります。ご自身の保険内容を確認してみるとよいでしょう。
費用面で不安がある場合は、事前に医療機関に問い合わせることをお勧めします。また、複数の医療機関で見積もりを取ることも一つの方法です。
粉瘤の再発リスクと予防法
粉瘤の手術を受けた後、気になるのが再発のリスクです。粉瘤の再発率は、手術方法や粉瘤の状態によって異なります。
粉瘤の再発率は、袋(嚢胞壁)を完全に摘出できた場合は非常に低いとされています。しかし、炎症を起こしている場合や、袋の一部が残ってしまった場合は再発のリスクが高まります。
再発のリスク要因
粉瘤が再発する主な原因は以下のようなものです:
- 袋の不完全な摘出:粉瘤の袋が完全に摘出されなかった場合、残った袋から再び粉瘤が発生することがあります。
- 炎症性粉瘤の手術:炎症を起こしている粉瘤は、組織が脆くなっているため、袋を完全に摘出することが難しい場合があります。
- 体質的要因:粉瘤ができやすい体質の方は、別の場所に新たな粉瘤ができることがあります。
再発を防ぐための対策
粉瘤の再発リスクを減らすためには、以下のような対策が有効です:
- 専門医による適切な手術:粉瘤の手術に慣れた医師に手術を依頼することで、袋の完全摘出率が高まります。
- 炎症がない状態での手術:可能であれば、炎症を起こしていない状態で手術を受けることが望ましいです。
- 適切なアフターケア:医師の指示に従った傷口のケアを行うことで、感染リスクを減らし、治癒を促進します。
- 定期的な皮膚チェック:新たな粉瘤の早期発見のため、定期的に皮膚の状態をチェックしましょう。
抗生物質による保存的治療(いわゆる「抗生剤で散らす」治療)を選択した場合、再発率は約30%と言われています。そのため、完全に治療するためには、最終的には外科的な摘出が必要となる場合が多いです。
粉瘤が再発した場合や、新たな粉瘤ができた場合は、早めに医師に相談することをお勧めします。小さいうちに対処することで、より簡単に、傷跡も小さく治療することができます。
まとめ:粉瘤治療で知っておくべきポイント
粉瘤の手術と治療について、重要なポイントをまとめてみましょう。
粉瘤は皮膚の内側に袋状の構造物ができ、角質や皮脂などの老廃物が溜まってできる良性腫瘍です。自然治癒することはなく、時間とともに大きくなる傾向があります。
粉瘤の手術は局所麻酔で行われるため、麻酔注射時にわずかな痛みを感じる程度で、手術中の痛みはほとんどありません。手術方法には主に「切開法」と「くりぬき法」があり、粉瘤の状態や場所によって適切な方法が選択されます。
手術は一般的に日帰りで行われ、所要時間は5〜30分程度です。手術後は適切なケアを行うことで、1〜2週間程度で日常生活に完全復帰できることがほとんどです。
粉瘤の手術は健康保険が適用されるため、経済的な負担も比較的軽いと言えます。ただし、単に美容的な理由だけの場合は、自費診療となることがあります。
粉瘤の再発を防ぐためには、袋を完全に摘出することが重要です。炎症を起こしている粉瘤は再発リスクが高まるため、可能であれば炎症がない状態での手術が望ましいです。
粉瘤を見つけたら、「痛くないから」「小さいから」と放置せず、早めに専門医に相談することをお勧めします。小さいうちに手術を受ければ、手術時間も短く、傷跡も小さく済みます。
最後に、粉瘤の治療や手術について不安や疑問がある方は、ぜひ専門医に相談してください。正確な診断と適切な治療計画を立てることで、安心して治療を受けることができます。
当院では粉瘤をはじめとする皮膚の腫瘍に対して、患者さん一人ひとりの状態に合わせた最適な治療を提供しています。些細なことでもお気軽にご相談ください。
詳細な情報や診療予約については、石川消化器内科・内視鏡クリニックのホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。皆様の健康をサポートするために、誠心誠意対応させていただきます。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
大腸がん検診の種類と選び方〜早期発見のための最適な方法
大腸がん検診の重要性と現状
大腸がんは現在、日本人がかかるがんの中で最も罹患数が多く、年間15万人以上が診断されています。40年前と比較すると約6倍にまで増加しており、男性では前立腺がんに次いで第2位、女性では乳がんに次いで第2位の罹患率となっています。
さらに深刻なのは、大腸がんによる死亡者数です。毎年約5万人が大腸がんで命を落としており、男性では肺がんに次いで第2位、女性では死亡原因のがんとしては第1位となっています。
この増加の主な原因は、日本人の食生活の欧米化です。高脂肪の食品、特に牛肉・豚肉などの摂取量増加が大きく影響していると考えられています。女性の場合は、便秘による腸内環境の悪化も大腸がんリスクを高める要因として指摘されています。
大腸がんの怖さは、進行するまでほとんど自覚症状がないことです。早期発見できれば完治も十分可能ながんですが、症状が現れた時にはすでに進行している場合も少なくありません。だからこそ、定期的な検診が非常に重要なのです。

大腸がんの基礎知識と検診の必要性
大腸は、食べ物が通る順に「盲腸」、「上行結腸」、「横行結腸」、「下行結腸」、「S状結腸」、「直腸」に分けられます。「盲腸」から「S状結腸」までにできるがんを「結腸がん」、「直腸」にできるがんを「直腸がん」と呼び、これらを合わせて「大腸がん」と総称しています。
大腸がんは進行するまで明確な自覚症状がないことが特徴です。進行すると血便、便秘、下痢、貧血、腹痛、嘔吐などの症状が現れます。また、便が細くなった、便が残っている感じがするといった症状を訴える患者さんもいます。
がんは正常な組織ではないため出血しやすく、大腸にできたがんから出血すると、便に血液が付着して血便になったり、下血や貧血を起こすことがあります。また、がんが大きくなって便が通りにくくなると、便秘や下痢、腹痛などの症状が現れることもあります。
どうですか?心当たりはありませんか?
しかし、これらの症状は大腸がんが進行してから現れることが多いのです。早期発見・早期治療のためには、症状が出る前の定期的な検診が不可欠です。40歳以上の方は、年に1回の大腸がん検診を受けることが推奨されています。

大腸がん検診の種類と特徴
大腸がん検診には様々な種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った検査方法を選ぶことが大切です。ここでは主な検査方法について詳しく解説します。
便潜血検査(一次検診)
便潜血検査は、最も一般的な大腸がん検診の方法です。2日分の便を採取し、便に混じった血液(肉眼では見えない微量の血液)を検出する検査です。がんやポリープなどの大腸疾患があると大腸内に出血することがあり、その血液を検出します。
この検査は簡便で、痛みもなく、特別な準備も必要ありません。国が推奨する対策型検診として、40歳以上の方に年1回の受診が推奨されています。費用も比較的安価で、自治体によっては無料で受けられる場合もあります。
ただし、便潜血検査には限界もあります。がんやポリープが常に出血しているわけではないため、検査のタイミングによっては見逃す可能性があります。また、痔などの他の原因で血液が混じることもあるため、陽性結果が出ても必ずしもがんとは限りません。
便潜血検査で陽性結果が出た場合は、必ず精密検査(大腸内視鏡検査など)を受ける必要があります。ここで重要なのは、便潜血検査を再度受けることは精密検査の代わりにはならないということです。1日分でも陽性であれば、精密検査を受けましょう。
大腸内視鏡検査(精密検査)
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)は、大腸がんの精密検査として最も精度が高い検査です。下剤で大腸を空にした後に肛門から内視鏡を挿入して、直腸から盲腸までの大腸全体を観察します。
この検査の最大の利点は、がんやポリープを直接目で見て確認できることです。さらに、検査中に組織を採取(生検)したり、小さなポリープであれば切除することも可能です。ポリープを切除することで、将来がんになる可能性のある前がん病変を取り除くことができます。
一方で、大腸内視鏡検査には以下のような短所もあります。検査前の食事制限や下剤による腸管洗浄が必要で、身体的・精神的負担が大きいこと。検査時間が20〜30分と比較的長く、内視鏡挿入時に痛みや不快感を伴うことがあります。また、まれに出血や穿孔(腸に穴が開く)などの合併症が起こる可能性もあります。
当院では、このような負担を軽減するために、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の大腸内視鏡検査を提供しています。半分眠ったような状態で検査を受けることができるため、痛みや恐怖をほとんど感じることなく検査を受けることが可能です。
大腸CT検査(CTコロノグラフィー)
大腸CT検査(CTコロノグラフィー)は、比較的新しい大腸がん検査方法です。大腸に炭酸ガスを注入し腸管を膨らませた状態でCT撮影を行い、3次元画像を作成して大腸の病気を診断します。
大腸内視鏡検査に比べて飲用する下剤量が少なく、体への負担が少ないのが特徴です。また、検査時間も約10〜15分と短時間で済みます。腹部の手術歴から癒着があり大腸カメラが入りにくい方や、痛みが心配で内視鏡検査を受ける決心がつかない方におすすめです。
さらに、大腸の診断だけでなく、CT装置で腹部全体を撮影するため、肝臓、膵臓、胆のう、腎臓、子宮、卵巣、前立腺などの腹部臓器も同時に診断できる利点があります。
ただし、この検査にも限界があります。組織の採取ができないため、異常が検出された場合は大腸内視鏡検査を受ける必要があります。また、病変の色や硬さの情報は得られず、平坦な病変や5mm以下の小さなポリープは検出しにくいという欠点もあります。X線を使用するため、妊娠の可能性のある方は受けることができません。

大腸がん検診の選び方と受け方
大腸がん検診を選ぶ際には、自分の状況や希望に合わせて最適な検査方法を選ぶことが大切です。以下に、検診の選び方と受け方についてのポイントをまとめました。
年齢と受診頻度
大腸がん検診は、40歳以上の方に年1回の受診が推奨されています。特に、大腸がんの家族歴がある方や、大腸ポリープの既往がある方は、より早期からの定期的な検診が重要です。
国が推奨する対策型検診では、40歳以上の方に対して便潜血検査を年1回実施することが基本となっています。便潜血検査で陽性となった場合は、必ず精密検査を受けることが重要です。
検診を受けたことがない方は、まず便潜血検査から始めるのが一般的です。ただし、より精度の高い検査を希望する場合や、大腸がんのリスクが高い方は、最初から大腸内視鏡検査や大腸CT検査を選択することも考えられます。
検診施設の選び方
大腸がん検診を受ける施設を選ぶ際には、以下のポイントを考慮するとよいでしょう。
便潜血検査については、勤務先で大腸がん検診があればそれを利用するとよいでしょう。それ以外の方は、40歳以上であれば市区町村で検診を受けられます。自己負担額は自治体によって異なりますが、無料から500円程度のところが多いようです。
大腸内視鏡検査を受ける場合は、経験豊かな医師による検査を受けることが重要です。見落としが少なく、精度の高い検診が受けられるだけでなく、検査時の苦痛も軽減される可能性が高くなります。
医療機関を選ぶ際のチェックポイントとしては、大腸内視鏡検査の実施件数やポリープ・早期がんの切除件数などを公表しているところ、拡大内視鏡の設備がある医療機関などが挙げられます。これらの情報はホームページで確認したり、医療機関に直接問い合わせたりして調べることができます。
当院では、消化器・内視鏡専門医である私が全ての診察、検査、検査結果説明までを担当しています。高性能な拡大内視鏡を導入しており、特殊な光によって粘膜の微細な変化まで観察できる大学病院レベルの検査が可能です。また、鎮静剤を使用した無痛の内視鏡検査を提供しており、患者さんの負担を最小限に抑えることを心がけています。
検査前の準備と注意点
便潜血検査は特別な準備は必要ありませんが、大腸内視鏡検査や大腸CT検査では、検査前の食事制限や下剤による腸管洗浄が必要です。
大腸内視鏡検査の場合、通常は検査前日の夕食は消化の良いものを摂り、検査当日は絶食となります。また、検査前日の夜と当日の朝に下剤を服用して腸内をきれいにします。
大腸CT検査では、大腸内視鏡検査よりも下剤の量が少なく済む場合が多いですが、やはり検査前の食事制限や下剤の服用は必要です。検査前日に消化の良い専用の検査食をとり、少量のバリウムを飲んで残便を白く色付けし、就寝前に少量の下剤を飲むという流れが一般的です。
いずれの検査も、事前に医療機関から詳しい説明と指示があります。不安なことや分からないことがあれば、遠慮なく医療機関に相談しましょう。

大腸がん検診の費用と保険適用
大腸がん検診の費用は、検査方法や受診する医療機関、自治体の助成制度などによって異なります。ここでは、各検査方法の一般的な費用と保険適用の有無について解説します。
便潜血検査の費用
便潜血検査は比較的安価で、自治体の住民検診として受ける場合は、無料から500円程度のところが多いです。横浜市では令和7年度は無料で受けられるようです。職場の健康診断の一環として受ける場合も、多くは無料または低額で受けられます。
医療機関で自費で受ける場合でも、1,000円〜2,000円程度で受けられることが多いです。
大腸内視鏡検査の費用
大腸内視鏡検査の費用は、検診として受ける場合と保険診療として受ける場合で大きく異なります。
検診として自費で受ける場合は、医療機関にもよりますが、2万円〜3万円程度かかることが一般的です。ただし、検査中にポリープや早期がんが見つかって内視鏡で切除した場合には、保険診療に切り替わります。
一方、便潜血検査で陽性となり、精密検査として大腸内視鏡検査を受ける場合や、血便などの症状があって診察を受ける場合は、保険診療となります。この場合、3割負担の方で5,000円〜1万円程度の自己負担となることが多いです。
大腸CT検査の費用
大腸CT検査(CTコロノグラフィー)の費用も、医療機関によって異なりますが、検診として自費で受ける場合は2万円〜4万円程度かかることが多いです。
便潜血検査陽性後の精密検査として受ける場合でも、現時点では大腸CT検査は保険適用外の検査であることが多く、自費負担となる場合がほとんどです。ただし、医療機関によっては保険適用となる場合もありますので、事前に確認するとよいでしょう。
助成制度の活用
大腸がん検診には、様々な助成制度があります。自治体の住民検診では、対象年齢の方は低額または無料で便潜血検査を受けられます。また、年齢によっては無料クーポンが配布される場合もあります。
横浜市の場合、70歳以上の方は無料で大腸がん検診を受けられるようです。また、精密検査費用の助成制度もあるようです。
職場の健康保険組合によっては、人間ドックや各種がん検診の費用補助を行っているところもあります。自分が加入している健康保険組合の制度を確認してみるとよいでしょう。

大腸がん検診で異常が見つかった場合の対応
大腸がん検診で異常が見つかった場合、適切な対応をすることが重要です。ここでは、検査結果ごとの対応方法について解説します。
便潜血検査で陽性となった場合
便潜血検査で「陽性」と判定された場合は、必ず精密検査を受ける必要があります。便潜血検査は、大腸がんの可能性を示唆するスクリーニング検査であり、陽性だからといって必ずしもがんであるとは限りません。しかし、がんの可能性を否定できないため、精密検査が必要なのです。
ここで重要なのは、便潜血検査を再度受けることは精密検査の代わりにはならないということです。大腸がんは毎日出血しているわけではありませんので、1日分でも便潜血検査陽性となったら精密検査を受ける必要があります。
また、もともと痔がある場合でも、痔が原因で出血しているのか、あるいは大腸がんやポリープのために出血しているのかは精密検査をしないと分かりません。自己判断をせずに、必ず精密検査を受けましょう。
大腸内視鏡検査でポリープが見つかった場合
大腸内視鏡検査でポリープが見つかった場合、その大きさや形状、場所などによって対応が異なります。
小さなポリープ(5mm以下)で数が少ない場合は、その場で切除することもありますし、経過観察となることもあります。一方、大きなポリープや数が多い場合は、別日に改めてポリープ切除の処置を行うことがあります。
ポリープを切除した場合は、その組織を病理検査に提出し、がん細胞が含まれているかどうかを調べます。結果によって、その後の治療方針が決まります。
当院では、日帰りでの大腸ポリープ切除にも対応しています。患者さんの負担を最小限に抑えながら、適切な治療を提供できるよう努めています。
大腸がんと診断された場合
大腸内視鏡検査や組織検査の結果、大腸がんと診断された場合は、がんの進行度(ステージ)を確認するための追加検査が必要になります。CT検査やMRI検査などを行い、がんの大きさや深さ、リンパ節転移や他臓器への転移の有無などを調べます。
これらの検査結果をもとに、手術、内視鏡治療、化学療法(抗がん剤治療)、放射線治療などの中から最適な治療方法を選択します。治療方針は、がんの進行度だけでなく、患者さんの年齢や全身状態、希望なども考慮して決定します。
大腸がんと診断されても、早期であれば内視鏡治療だけで完治する可能性も高いです。早期発見・早期治療が何よりも重要なのです。

まとめ:大腸がん検診で早期発見を目指そう
大腸がんは日本人がかかるがんの中で最も罹患数が多く、女性のがん死亡原因の第1位、男性では第2位となっています。しかし、早期に発見できれば完治も十分可能ながんです。
大腸がんの怖さは、進行するまでほとんど自覚症状がないことです。そのため、定期的な検診が非常に重要となります。40歳以上の方は、年に1回の大腸がん検診を受けることが推奨されています。
大腸がん検診には、便潜血検査、大腸内視鏡検査、大腸CT検査などの方法があります。それぞれに特徴があり、自分の状況や希望に合わせて最適な検査方法を選ぶことが大切です。
便潜血検査は簡便で負担が少なく、スクリーニング検査として適しています。陽性となった場合は、必ず精密検査を受けることが重要です。
大腸内視鏡検査は精度が高く、ポリープの切除も同時に行えますが、検査前の準備や検査時の負担が大きいという短所もあります。当院では、鎮静剤を使用した無痛の大腸内視鏡検査を提供し、患者さんの負担軽減に努めています。
大腸CT検査は、大腸内視鏡検査に比べて負担が少なく、短時間で検査が完了するという利点がありますが、組織の採取ができないという限界もあります。
いずれの検査方法を選ぶにしても、定期的に検診を受けることが何よりも重要です。「辛い・苦しい」というイメージから検診を避けるのではなく、早期発見・早期治療のために、ぜひ定期的な検診を心がけてください。
当院では、患者さんの負担を最小限に抑えながら、高精度の検査を提供できるよう様々な工夫を行っています。大腸がん検診についてご不明な点やご不安な点がありましたら、お気軽に当院までご相談ください。皆様の健康を守るために、誠心誠意サポートさせていただきます。
詳細は石川消化器内科・内視鏡クリニックのホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
慢性便秘を根本から改善!消化器内科での検査と治療法を紹介
慢性便秘とは?症状と定義を正しく理解する
便秘は多くの方が一度は経験したことのある症状です。しかし、「何日間排便がないと便秘なのか」という明確な基準はありません。
慢性便秘症は「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態が長期間続くこと」と定義されています。単に排便回数が少ないだけでなく、排便時の苦痛や残便感なども重要な症状です。
便秘の三大症状は「排便回数の減少」「排便困難感」「残便感」です。これらの症状が1ヶ月以上続く場合は、慢性便秘症を疑う必要があります。
国民生活基礎調査によると、便秘に悩む方の割合は男性2.5%、女性4.6%とされています。20~60歳では女性に多く、60歳以降は男女とも加齢に伴って増加する傾向があります。
便秘は「たかが便秘」と軽視されがちですが、重症化すれば腸閉塞や腸穿孔といった深刻な合併症を引き起こすこともあります。また、大腸がんや心疾患、脳卒中との関連も指摘されており、適切な治療が重要です。

便秘の種類と原因を知り、自分のタイプを見極める
便秘には大きく分けて4つのタイプがあります。自分がどのタイプに当てはまるかを知ることで、適切な治療法を選択できます。
便秘の種類は大きく「機能性便秘」「器質性便秘」「薬剤性便秘」「その他の原因による便秘」に分類されます。それぞれの特徴と原因を詳しく見ていきましょう。
機能性便秘の特徴と原因
最も多いのが「機能性便秘」です。これは大腸や直腸の働きに異常が生じるタイプの便秘で、さらに3つのサブタイプに分けられます。
弛緩性便秘は、大腸を動かす筋肉がゆるみ、腸の蠕動運動が弱くなることで便が停滞するタイプです。生活習慣の乱れや加齢が主な原因とされています。
痙攣性便秘は、大腸の蠕動運動が不規則になることで起こります。ストレスが大きく関与していると考えられています。
直腸性便秘は、便意を習慣的に我慢することで直腸の神経の働きが弱くなり、便意を感じにくくなるタイプです。女性や温水洗浄便座の水を肛門の奥まで入れてしまう方に多く見られます。
器質性便秘と薬剤性便秘
器質性便秘は、大腸がんや手術後の癒着、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患によって、大腸内の便の通過が物理的に妨げられることで起こります。
薬剤性便秘は、服用している薬の副作用によって起こる便秘です。喘息や頻尿、パーキンソン病の治療薬、抗うつ薬、抗コリン薬、咳止めなどには腸の動きを鈍くする副作用があります。
女性に便秘が多い理由
女性に便秘が多い理由は主に3つあります。
1つ目は筋力の低下です。男性に比べて排便に必要な括約筋や腹筋の力が弱いため、特に女性は骨盤が広く腸が下方に垂れ下がりやすいという解剖学的特徴があります。
2つ目はダイエットの影響です。食事量が少なくなると、腸の蠕動運動が低下します。
3つ目はホルモンの影響です。黄体ホルモン(プロゲステロン)は腸の蠕動運動を抑制し、水分・塩分の吸収を促進するため、月経前や妊娠中に便秘になりやすくなります。
便秘が引き起こす健康リスクと合併症
便秘は単なる不快な症状ではなく、放置すると様々な健康リスクを引き起こす可能性があります。
慢性的な便秘は腸内環境の悪化を招き、腸内細菌のバランスが崩れることで様々な健康問題につながります。便秘が長期間続くと、どのような合併症のリスクが高まるのでしょうか。
便秘が重症化すると、腸閉塞や腸穿孔といった命に関わる合併症を引き起こす可能性があります。また、排便時に強くいきむことで痔や裂肛、直腸脱などの肛門疾患のリスクも高まります。
さらに、便秘の方は大腸がんのリスクが高まることが研究で明らかになっています。全国を対象とした大規模コホート研究(JACC Study)によると、女性の場合、6日以上の便秘では、2~3日おきに排便がある方と比べて、大腸がんのリスクが2.5倍高くなるという結果が報告されています。
便秘は心疾患や脳卒中との関連も指摘されており、予後にも影響を及ぼすことがわかっています。快便の方が長生きするという研究結果もあります。
これらの研究結果からも、便秘は単なる不快な症状ではなく、全身の健康に影響を与える重要な問題であることがわかります。適切な治療を行い、健康的な腸内環境を維持することが大切です。
消化器内科での便秘の検査方法
便秘の原因を特定するためには、適切な検査が必要です。消化器内科では、どのような検査を行うのでしょうか。
便秘の検査は、まず問診から始まります。排便の頻度や便の性状、排便時の症状、生活習慣、服用中の薬剤などを詳しく聞き取ります。その上で、必要に応じて以下の検査を行います。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)
便秘を引き起こす最も重要な疾患の一つが大腸がんです。大腸カメラを一度も受けたことがない方には、まず大腸カメラ検査をお勧めしています。
当院では鎮静剤を使用した無痛の大腸カメラ検査を行っています。眠っている間に検査を行うため、痛みや不快感をほとんど感じることなく検査を受けることができます。
大腸カメラでは、大腸がんやポリープだけでなく、炎症性腸疾患や虚血性大腸炎などの便秘の原因となる疾患を直接観察することができます。必要に応じて組織を採取し、詳しい検査を行うこともあります。
腹部レントゲン検査
腹部レントゲンでは、大腸のどこに便が貯まっているかを確認することができます。便秘のタイプによって治療方針が異なるため、便の貯留部位を知ることは重要です。
例えば、S状結腸や直腸に便が多く貯まっている場合は直腸性便秘の可能性が高く、上行結腸から下行結腸にかけて便が広く分布している場合は弛緩性便秘の可能性が考えられます。
排便造影検査と直腸肛門内圧検査
排便時の問題を詳しく調べるために、排便造影検査や直腸肛門内圧検査を行うこともあります。
排便造影検査では、バリウムを直腸に注入し、排便時のX線撮影を行います。これにより、直腸瘤や直腸脱、骨盤底筋協調運動障害などの診断が可能です。
直腸肛門内圧検査では、肛門括約筋の圧力や直腸感覚閾値を測定します。これにより、排便障害のメカニズムを詳しく調べることができます。
これらの検査結果に基づいて、便秘のタイプを正確に診断し、最適な治療法を選択します。
便秘の内科的治療法と最新薬物療法
便秘の治療は、症状の程度や原因によって異なります。ここでは、消化器内科で行われる便秘の内科的治療法について解説します。
便秘治療の目的は、単に排便回数を増やすだけでなく、排便時の苦痛や残便感を改善し、患者さんのQOL(生活の質)を向上させることです。
生活習慣の改善と食事療法
便秘治療の基本は生活習慣の改善です。適度な運動やお腹のマッサージが便秘改善に効果的であることが報告されています。
食物繊維の推奨摂取量は1日20g以上ですが、現代の日本人の平均摂取量は15g程度と不足しています。食物繊維は便のかさを増やし排便を促進しますが、摂りすぎるとかえって便秘を悪化させることもあるため注意が必要です。
水分摂取も重要です。1日に1.5〜2リットルの水分を摂ることで、便を柔らかく保ち排便を促進します。
また、朝食を摂ることで胃結腸反射を促し、大腸の蠕動運動を活発にすることができます。朝食後にトイレに行く習慣をつけることも効果的です。
便秘治療薬の種類と特徴
生活習慣の改善だけでは効果が不十分な場合は、薬物療法を行います。便秘治療薬には大きく分けて以下の種類があります。
浸透圧性下剤は、腸管内に水分を引き込むことで便を軟らかくし、排便を促進します。代表的なものに酸化マグネシウムがあります。日本で古くから使用されており、大腸通過時間を短縮し、便回数や便形状を改善する効果が研究で確認されています。
刺激性下剤は、腸の蠕動運動を直接刺激します。センナやピコスルファートナトリウムなどがありますが、長期使用すると耐性が生じる可能性があります。
近年では新しいタイプの便秘治療薬も登場しています。粘膜上皮機能変容薬(ルビプロストン、リナクロチド)は腸管内の水分分泌を促進し、胆汁酸トランスポーター阻害薬(エロビキシバット)は胆汁酸の再吸収を阻害することで大腸の蠕動運動を促進します。
これらの新薬は従来の下剤とは異なるメカニズムで作用するため、従来の治療で効果が不十分だった方にも効果が期待できます。
難治性便秘への対応
一般的な治療で改善しない難治性便秘の場合は、より専門的な治療が必要になります。
バイオフィードバック療法は、直腸肛門協調運動障害による便秘に効果的です。排便時の筋肉の使い方を視覚的に確認しながら、正しい排便法を学びます。
また、浣腸や坐薬、摘便などの対症療法も状況に応じて行います。重症例では逆行性洗腸法を行うこともあります。
薬物療法では、複数の薬剤を組み合わせることで効果を高めることもあります。例えば、浸透圧性下剤と刺激性下剤の併用や、新薬と従来薬の併用などです。
どのような治療法を選択するかは、便秘のタイプや重症度、患者さんの状態によって異なります。消化器内科専門医による適切な診断と治療が重要です。
便秘と大腸がんの関係性
便秘と大腸がんの関係については、多くの研究が行われています。便秘が大腸がんのリスク因子となる可能性があることがわかってきました。
便秘が続くと、腸内に便が長時間滞留することになります。この状態が続くと、便に含まれる発がん物質と腸粘膜の接触時間が長くなり、大腸がんのリスクが高まる可能性があります。
1988年から20年以上かけて行われた全国規模の大規模コホート研究(JACC Study)では、排便頻度と大腸がんの関連が調査されました。その結果、女性の場合、6日以上便秘が続く方は、2〜3日おきに排便がある方と比べて、大腸がんのリスクが2.5倍高くなることが明らかになりました。
便秘と大腸がんの関連については、まだ研究段階の部分もありますが、長期間の便秘は大腸がんのリスク因子となる可能性が高いと考えられています。
特に、便秘に加えて、血便や体重減少、貧血などの症状がある場合は、大腸がんの可能性を考慮して早急に消化器内科を受診することをお勧めします。
当院では、便秘の症状がある方に対して、必要に応じて大腸カメラ検査を行い、大腸がんやポリープの早期発見・早期治療に努めています。鎮静剤を使用した無痛の大腸カメラ検査を行っていますので、検査への不安や恐怖感を最小限に抑えることができます。
便秘外来を受診するタイミングと準備
便秘の症状があるとき、どのようなタイミングで医療機関を受診すべきでしょうか。また、受診の際にはどのような準備をしておくと良いでしょうか。
便秘は1週間程度であれば様子を見ても良いとされていますが、以下のような場合は消化器内科の受診をお勧めします。
・便が出ない、あるいは便が出てもすっきりしない状態が1ヶ月以上続く場合
・市販の便秘薬を使っても効果がない、または効果が徐々に弱くなってきた場合
・便秘に加えて、血便、腹痛、発熱、体重減少などの症状がある場合
・50歳以上で便通の変化がある場合(大腸がんのリスクが高まるため)
・便秘が急に始まり、以前とは排便パターンが明らかに変わった場合
受診前の準備と問診のポイント
便秘外来を受診する際は、以下の情報を整理しておくと診察がスムーズに進みます。
・便秘の期間(いつから続いているか)
・排便の頻度と便の性状(ブリストル便形状スケールを参考に)
・排便時の症状(いきみ、痛み、残便感など)
・現在服用中の薬(便秘を引き起こす可能性のある薬もあります)
・これまでに試した便秘対策とその効果
・食事内容や水分摂取量、運動習慣などの生活習慣
・家族歴(特に大腸がんや炎症性腸疾患など)
これらの情報を事前にメモしておくと、医師に正確に伝えることができます。
当院での便秘治療の特徴
当院では、消化器・内視鏡専門医である院長が全ての診察、検査、検査結果説明を担当しています。便秘の症状一つひとつに丁寧に向き合い、患者さん一人ひとりに最適な治療法を提案しています。
便秘の検査では、必要に応じて大腸カメラ検査を行います。当院では鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の大腸カメラ検査を提供しており、半分眠ったような状態で検査を受けることができます。「辛い・苦しい」というイメージがある大腸カメラ検査のハードルを下げ、患者さんの負担を軽減しています。
また、高性能な拡大内視鏡を導入しており、特殊な光によって粘膜の微細な変化まで観察できる大学病院レベルの検査が可能です。初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しており、お忙しい方でも安心して検査を受けていただけます。
便秘治療では、生活習慣の改善から薬物療法まで、便秘のタイプや重症度に応じた最適な治療を提供しています。新しい便秘治療薬も積極的に取り入れ、従来の治療で効果が不十分だった方にも効果的な治療を提案しています。

まとめ:便秘治療で生活の質を向上させよう
慢性便秘症は「たかが便秘」と軽視されがちですが、適切な治療を行わないと様々な健康リスクを引き起こす可能性があります。
便秘の種類は大きく「機能性便秘」「器質性便秘」「薬剤性便秘」に分類され、それぞれ原因と治療法が異なります。自分の便秘のタイプを知ることが、効果的な治療の第一歩です。
便秘の治療は、生活習慣の改善から始まります。適度な運動、十分な水分摂取、食物繊維の適切な摂取などが基本です。それでも改善しない場合は、浸透圧性下剤や刺激性下剤、新しいタイプの便秘治療薬などの薬物療法を行います。
便秘が1ヶ月以上続く場合や、市販薬で効果がない場合、血便や腹痛などの症状を伴う場合は、消化器内科の受診をお勧めします。特に50歳以上の方は、大腸がんのリスクも考慮して、一度大腸カメラ検査を受けることが重要です。
当院では、消化器・内視鏡専門医による丁寧な診察と、鎮静剤を使用した無痛の大腸カメラ検査を提供しています。便秘でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
便秘を根本から改善することで、腸内環境が整い、全身の健康状態も向上します。快適な排便習慣を取り戻し、生活の質を高めましょう。
詳しい情報や診療予約については、石川消化器内科・内視鏡クリニックのホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。皆様の健康管理を誠心誠意サポートいたします。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
内視鏡検査の保険適用条件と自己負担額ガイド〜2025年最新情報
内視鏡検査とは?保険適用の基本的な考え方
内視鏡検査は、食道・胃・十二指腸や大腸などの消化管を直接カメラで観察する検査です。胃カメラや大腸カメラとも呼ばれ、消化器疾患の診断において非常に重要な役割を果たしています。
「内視鏡検査は保険が適用されるの?」「自己負担額はどのくらい?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
内視鏡検査の保険適用には、症状や検査目的によって大きく異なる条件があります。健康診断などの予防目的と、症状がある場合の診療目的では、適用される保険制度や自己負担額が変わってくるのです。
当院でも多くの患者さんから保険適用に関するご質問をいただきます。この記事では、2025年最新の内視鏡検査における保険適用条件と自己負担額について、医師の立場から詳しく解説していきます。

保険診療と自費診療の違い〜内視鏡検査の場合
内視鏡検査を受ける際、保険診療と自費診療の2つの選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、まずはその違いを理解しましょう。
保険診療とは、健康保険が適用される診療のことです。何らかの症状があり、医師が必要と判断した場合に適用されます。一方、自費診療は健康保険が適用されず、検査費用の全額を自己負担する診療形態です。
「なぜ自費診療を選ぶ人がいるの?」と思われるかもしれません。
実は、症状がなく単に健康確認のために受ける人間ドックや健康診断の一環としての内視鏡検査は、原則として保険適用外となるのです。また、保険診療では制約がある一方、自費診療ではより自由度の高い検査が可能な場合もあります。
私の臨床経験から言えば、多くの患者さんは保険診療を希望されますが、定期的な健康管理として自費での検査を選ぶ方も少なくありません。
以下の表で、保険診療と自費診療の主な違いをまとめてみました。
- 保険診療:何らかの症状がある場合や、医師が必要と判断した場合に適用
- 自費診療:症状がなく健康確認目的の場合や、保険適用外の検査方法を希望する場合
- 費用負担:保険診療は3割負担(年齢により1〜2割の場合も)、自費診療は全額自己負担
- 検査内容:保険診療は保険で認められた範囲内、自費診療はより自由度が高い場合も
どちらを選ぶべきかは、ご自身の健康状態や目的によって異なります。症状がある場合は、まずは保険診療での受診をお勧めします。
内視鏡検査が保険適用される条件【2025年最新】
2025年現在、内視鏡検査が保険適用される条件は明確に定められています。主な条件をご紹介します。
まず、保険適用の大前提として「医学的必要性」があることが重要です。具体的には以下のような場合に保険適用となります。
症状がある場合
腹痛、胸やけ、嘔吐、下血、便通異常など消化器系の症状がある場合は、医師の判断により内視鏡検査が保険適用となります。当院でも、こうした症状を訴える患者さんには積極的に内視鏡検査をお勧めしています。
「症状が軽いから我慢しよう」と思われる方もいますが、早期発見・早期治療のためにも、気になる症状があればためらわずに受診されることをお勧めします。
検査結果で異常が見つかった場合
健康診断や他の検査で異常が見つかり、精密検査として内視鏡検査が必要と判断された場合も保険適用となります。例えば、胃部X線検査(バリウム検査)で異常陰影が見つかった場合や、便潜血検査で陽性となった場合などが該当します。
健康診断の結果をお持ちの方は、受診時に必ずご提示ください。医師の判断材料として重要です。
経過観察が必要な場合
過去に消化器疾患の治療歴がある方や、ポリープなどを指摘されている方の経過観察目的の内視鏡検査も、医師が必要と判断すれば保険適用となります。
当院では、患者さん一人ひとりの状態に合わせた適切な検査間隔をご提案しています。定期的な経過観察は、病変の早期発見につながります。
年齢による条件
2025年度の各自治体のがん検診では、胃内視鏡検査は主に50歳以上を対象としています。例えば、戸田市では50歳以上の市民で、前年度に市の胃内視鏡検査を受けていない方が対象となっています。また、検診は2年に1回の頻度で受けることができます。
自治体によって対象年齢や条件が異なりますので、お住まいの地域の最新情報をご確認ください。
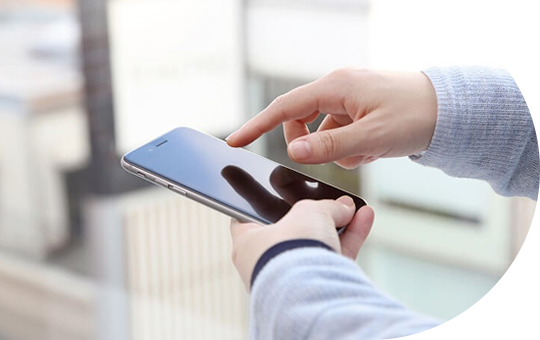
内視鏡検査の自己負担額はいくら?
内視鏡検査の自己負担額は、保険適用か自費診療か、また検査の種類によって大きく異なります。2025年現在の一般的な費用をご紹介します。
保険診療の場合の自己負担額
保険診療の場合、自己負担割合は年齢や所得によって1割から3割と異なります。一般的な3割負担の方の場合、おおよその自己負担額は以下の通りです。
- 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ):3,000円〜5,000円程度
- 下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ):5,000円〜8,000円程度
ただし、これはあくまで検査基本料の目安です。生検(組織採取)や処置を行った場合は、別途費用が発生します。また、鎮静剤(麻酔)を使用する場合も追加費用がかかることがあります。
当院では、患者さんの不安や苦痛を軽減するため、鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査を提供しています。半分眠ったような状態で検査を受けることができるため、「辛い・苦しい」というイメージのある内視鏡検査のハードルを下げることができます。
保険診療の場合、高額療養費制度も適用されます。同月内の医療費が一定額を超えた場合、超過分が後日払い戻されるシステムです。
自費診療の場合の費用
自費診療の場合は、医療機関によって料金設定が大きく異なります。一般的な相場は以下の通りです。
- 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ):10,000円〜20,000円程度
- 下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ):20,000円〜40,000円程度
自費診療では、鎮静剤の使用や、より詳細な検査、当日の検査結果説明なども含まれていることが多いです。
費用面で不安がある場合は、事前に医療機関に確認することをお勧めします。当院では、検査前に費用の目安をご説明し、患者さんが安心して検査を受けられるよう配慮しています。
自治体のがん検診における内視鏡検査
各自治体では、がん検診の一環として内視鏡検査を実施しています。2025年度の最新情報をご紹介します。
自治体のがん検診は、一般的な保険診療よりも自己負担額が少なく設定されているのが特徴です。積極的に活用したい制度と言えるでしょう。
胃がん検診(内視鏡検査)
2025年度の各自治体の胃がん内視鏡検診の情報を見ていきましょう。
八王子市では、50歳以上の方を対象に、2年に1回の頻度で胃がん内視鏡検診を実施しています。自己負担額は3,080円です。西宮市の場合は、50歳以上の偶数年齢の方が対象で、個別検診の費用は3,800円となっています。
戸田市では、50歳以上の市民で前年度に市の胃内視鏡検査を受けていない方を対象に、自己負担金2,500円で検査を提供しています。定員は1,000人で、申し込みが必要です。
このように、自治体によって対象年齢や自己負担額、申込方法などが異なります。お住まいの地域の広報やホームページで最新情報をご確認ください。
大腸がん検診
大腸がん検診は、多くの自治体で40歳以上の方を対象に実施されています。ただし、一次検診は便潜血検査が一般的で、その結果で陽性となった場合に大腸内視鏡検査(精密検査)が推奨されます。
八王子市では大腸がん検診の自己負担額は880円、西宮市では600円(集団検診の場合)となっています。福岡市や戸田市でも同様に40歳以上の方を対象に大腸がん検診を実施しています。
便潜血検査で陽性となった場合は、必ず精密検査を受けることをお勧めします。早期発見・早期治療が大腸がんの予後を大きく左右します。
内視鏡検査の保険適用に関するよくある質問
内視鏡検査の保険適用について、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。
症状がなくても保険は適用される?
基本的に、症状がない場合は保険適用外となります。ただし、過去の検査で異常が見つかり経過観察が必要な場合や、家族歴などのリスク要因がある場合は、医師の判断により保険適用となることがあります。
症状がなくても定期的な検査を希望される場合は、自治体のがん検診や人間ドックの活用をご検討ください。
前立腺がん検査も同時に受けられる?
内視鏡検査と前立腺がん検査は別の検査ですが、同日に受けることは可能な場合があります。戸田市では、50歳以上の男性市民を対象に、前立腺がん検査(PSA検査)を実施しています。自己負担金は2,000円です。
ただし、前立腺がん検査は血液検査であり、内視鏡検査とは検査方法が異なります。医療機関や自治体の検診プログラムによって、同時実施の可否や費用が変わりますので、事前に確認することをお勧めします。
高額療養費制度は使える?
保険診療で内視鏡検査を受けた場合、高額療養費制度の対象となります。同月内の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が後日払い戻されます。
高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みますので、ご検討ください。
市民税非課税世帯は検診費用が免除される?
多くの自治体では、市民税非課税世帯や生活保護受給世帯の方は、がん検診の費用が免除される制度があります。例えば、八王子市や福岡市では、市県民税非課税世帯の人、生活保護受給世帯の人は、市の実施するがん検診が無料となります(証明書が必要)。
費用免除を受けるためには、予約前に市への申請が必要な場合もありますので、お住まいの自治体にお問い合わせください。
内視鏡検査を安心して受けるためのポイント
最後に、内視鏡検査を安心して受けるためのポイントをご紹介します。
内視鏡検査は「辛い・苦しい」というイメージがあるかもしれませんが、技術の進歩により、以前よりもずっと受けやすくなっています。当院では、患者さんの不安や苦痛を軽減するためのさまざまな工夫を行っています。
鎮静剤(麻酔)の活用
鎮静剤を使用することで、半分眠ったような状態で検査を受けることができます。痛みや恐怖をほとんど感じることなく、「あっという間」に検査が終わります。
当院では、患者さんの状態や希望に合わせて適切な鎮静を行い、できるだけ苦痛の少ない検査を心がけています。
経鼻内視鏡の選択肢
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)は、口からだけでなく鼻から挿入する方法(経鼻内視鏡)も選択できます。経鼻内視鏡は、嘔吐反射が少なく、会話もできるため、口からの挿入に抵抗がある方に適しています。
当院では、経口・経鼻どちらの内視鏡検査も対応可能です。患者さんのご希望に応じて最適な方法をご提案しています。
検査前の適切な準備
検査の種類によって、事前の準備が異なります。上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)の場合は検査前の絶食、下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)の場合は腸管洗浄が必要です。
医師や看護師の指示に従って適切な準備を行うことで、より正確で安全な検査が可能になります。不明点があれば、遠慮なくお尋ねください。
専門医による検査
内視鏡検査は、専門的な知識と技術を持った医師が行うことが重要です。日本消化器内視鏡学会の専門医資格を持つ医師による検査は、より安全で正確な診断につながります。
当院では、消化器・内視鏡専門医である院長が全ての診察、検査、検査結果説明を担当しています。安心して検査をお受けください。

まとめ:内視鏡検査の保険適用と自己負担額
内視鏡検査の保険適用条件と自己負担額について、2025年最新情報をご紹介しました。
内視鏡検査は、症状がある場合や医師が必要と判断した場合に保険適用となります。自己負担額は保険診療の場合、上部消化管内視鏡検査で3,000円〜5,000円程度、下部消化管内視鏡検査で5,000円〜8,000円程度が一般的です。
自治体のがん検診も積極的に活用したい制度です。胃がん内視鏡検診は主に50歳以上の方を対象に、2年に1回の頻度で実施されています。自己負担額は自治体によって異なりますが、一般的な保険診療よりも安く設定されています。
内視鏡検査は「辛い・苦しい」というイメージがありますが、鎮静剤の使用や経鼻内視鏡の選択など、患者さんの負担を軽減するための工夫が進んでいます。
消化器症状がある場合や、健康診断で異常を指摘された場合は、早めに専門医を受診することをお勧めします。早期発見・早期治療が、消化器疾患の予後を大きく左右します。
当院では、患者さん一人ひとりの状態に合わせた適切な検査と治療を提供しています。内視鏡検査についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
詳細は石川消化器内科・内視鏡クリニックのホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。皆様の健康管理を誠心誠意サポートいたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
【医師監修】胸焼け・ムカムカが続く時に知っておくべき7つの対処法
胸焼け・ムカムカの原因とは?なぜ不快な症状が起こるのか
胸焼けやムカムカといった不快な症状は、多くの方が一度は経験したことがあるのではないでしょうか。特に食後に感じることが多い、みぞおちから胸にかけての焼けるような感覚や、胃がむかむかする感じは日常生活に大きな支障をきたします。
これらの症状が起こる主な原因は、胃酸の過剰分泌と食道への逆流です。通常、食道と胃の境目にある下部食道括約筋が胃酸の逆流を防いでいますが、この機能が低下すると胃酸が食道に逆流し、胸やけを引き起こします。
胸やけとムカムカの症状は似ていますが、少し異なります。胸やけは主に胃酸が食道に逆流することで起こる、みぞおちの上部がヒリヒリ・ジリジリと焼けるような感覚です。一方、ムカムカは胃の内容物が長時間とどまることで起こる、胃が重く苦しい感覚を指します。
これらの症状を引き起こす要因には、以下のようなものがあります。
- 食生活の乱れ:脂っこい食事、食べ過ぎ、飲み過ぎ
- 生活習慣:食後すぐの横になる習慣、喫煙、不規則な食事
- ストレス:精神的なストレスによる自律神経の乱れ
- 加齢:下部食道括約筋の筋力低下
- 肥満:腹圧の上昇による胃内容物の逆流
特に食べ過ぎると胃の中の圧力が高まり、下部食道括約筋が緩んで胃酸が逆流しやすくなります。また、高脂肪食は胃の排出機能を低下させ、胃もたれを引き起こす原因となります。

胸焼け・ムカムカの7つの症状と見分け方
胸焼けやムカムカの症状は人によって感じ方が異なります。自分の症状を正確に把握することで、適切な対処法を見つけることができます。
主な症状には次のようなものがあります。それぞれの特徴を知り、自分の状態を確認してみましょう。
1. 胸やけ(胸が焼けるような感覚)
みぞおちの上部から胸にかけて、ヒリヒリ・ジリジリとした焼けるような感覚があります。食後に特に強く感じることが多く、横になると症状が悪化する傾向があります。
これは胃酸が食道に逆流し、食道の粘膜を刺激することで起こります。食道は胃と違って胃酸から身を守る粘液層が薄いため、胃酸に触れると強い刺激を感じるのです。
2. 胃もたれ(胃が重い感覚)
胃が重く、食べ物が長時間胃に残っているような不快感があります。食後に特に感じやすく、消化不良の状態を示しています。
胃の排出機能が低下していると、食べ物が胃に長くとどまり、この症状が現れます。脂っこい食事や食べ過ぎが主な原因です。
3. 吐き気・嘔吐感
胃の内容物を吐き出したいという不快な感覚や、実際に嘔吐することがあります。ウイルス性胃腸炎などの感染症が原因の場合もありますが、胃酸の過剰分泌や胃の炎症によっても起こります。
ストレスや自律神経の乱れも吐き気の原因となることがあります。
4. 呑酸(酸っぱいものが込み上げる感覚)
胃から酸っぱい液体が食道を通って喉まで上がってくる感覚です。口の中が酸っぱくなることもあります。
これは胃酸が食道を通って上がってくる典型的な症状で、逆流性食道炎の特徴的な症状の一つです。
5. 胸の痛み・圧迫感
胸に痛みや圧迫感を感じることがあります。時に心臓の痛みと間違えられることもありますが、食事との関連性がある場合は消化器系の問題である可能性が高いです。
ただし、胸痛が激しい場合や、左腕や顎に放散する痛みがある場合は、心臓の問題の可能性もあるため、すぐに医療機関を受診してください。
6. のどの違和感・イガイガ感
喉に何かが詰まっているような感覚や、イガイガした違和感を感じることがあります。これも胃酸の逆流によって喉の粘膜が刺激されることで起こります。
朝起きたときに特に感じることが多く、夜間に寝ている間に胃酸が逆流した可能性を示しています。
7. 食欲不振
胃の不快感から食べる意欲が減退し、食欲が低下することがあります。長期間続くと栄養不足や体重減少につながる可能性もあります。
これらの症状が一時的なものであれば心配ありませんが、2週間以上続く場合や、日常生活に支障をきたす場合は、医療機関での検査をお勧めします。
胸焼け・ムカムカを改善する7つの対処法
胸焼けやムカムカの症状に悩まされている方に、効果的な7つの対処法をご紹介します。これらの方法を日常生活に取り入れることで、不快な症状の改善が期待できます。
1. 食生活の見直し
胸焼けやムカムカの最も効果的な対処法は、食生活の見直しです。まずは食べ過ぎを避け、腹八分目を心がけましょう。胃に負担をかける脂っこい食事、辛い食べ物、酸味の強い食品、カフェイン、アルコールなどは控えめにすることが大切です。
また、早食いは空気を一緒に飲み込みやすく、胃に負担をかけます。ゆっくりよく噛んで食べることで、消化を助け、満腹感も得やすくなります。
2. 食後の姿勢と活動
食後すぐに横になると、胃酸が逆流しやすくなります。食後は少なくとも2〜3時間は横にならず、軽い散歩などの適度な活動を行うことで消化を促進させましょう。
どうしても横になる必要がある場合は、上半身を少し高くした姿勢をとることで、胃酸の逆流を防ぐことができます。
食後すぐに激しい運動をするのも避けた方が良いでしょう。食後の激しい運動は胃酸の逆流を促進させる可能性があります。
3. 水分摂取の工夫
適切な水分摂取は胃酸を薄め、症状を和らげる効果があります。ただし、食事中に大量の水を飲むと胃を膨らませ、かえって症状を悪化させることがあります。
食事と水分摂取は分けて行い、少量ずつこまめに水分を取ることをお勧めします。炭酸飲料やアルコール、カフェインを含む飲み物は胃酸の分泌を促進するため、控えめにしましょう。
4. 睡眠姿勢の改善
夜間の胸やけを防ぐには、睡眠時の姿勢が重要です。枕やマットレスを使って上半身を少し高くすることで、胃酸の逆流を防ぐことができます。
また、左側を下にして横になると、胃の出口が上になるため胃酸が逆流しにくくなります。右側を下にすると逆に胃酸が逆流しやすくなるので注意しましょう。
5. ストレス管理
ストレスは胃酸の過剰分泌を促し、胸やけやムカムカの原因となります。深呼吸、瞑想、ヨガなどのリラクゼーション法を取り入れ、ストレスを軽減することが大切です。
十分な睡眠も重要です。睡眠不足は自律神経のバランスを崩し、胃腸の働きに悪影響を与えます。規則正しい生活リズムを心がけましょう。
6. 衣服の選択
きつい衣服やベルトは腹部を圧迫し、胃酸の逆流を促進します。特に食後は、お腹を締め付けない緩やかな衣服を選ぶことで、症状の軽減につながります。
また、就寝時にもきつい衣服は避け、リラックスできる服装を選びましょう。
7. 市販薬の適切な使用
症状が辛い場合は、市販の胃薬の使用も検討しましょう。胃酸を中和する制酸薬、胃酸の分泌を抑えるH2ブロッカーなど、症状に合わせた薬を選ぶことが大切です。
ただし、市販薬で症状が改善しない場合や、症状が長期間続く場合は、医療機関での診察をお勧めします。
これらの対処法を組み合わせることで、胸やけやムカムカの症状を効果的に軽減することができます。ただし、個人差があるため、自分に合った方法を見つけることが大切です。

食事療法:胸焼け・ムカムカを和らげる食べ物と避けるべき食品
胸焼けやムカムカの症状を改善するためには、食事内容の見直しが非常に重要です。症状を和らげる食べ物と、逆に症状を悪化させる食品を知ることで、効果的な食事療法を実践できます。
症状を和らげる食べ物
以下の食品は胃に優しく、症状の緩和に役立ちます。
- 消化の良い炭水化物:おかゆ、うどん、食パンなど
- 低脂肪の蛋白質:鶏むね肉、白身魚、豆腐など
- アルカリ性の野菜:ほうれん草、ブロッコリー、キャベツなど
- 消化を助ける食品:バナナ、りんご(すりおろし)、ヨーグルトなど
- 胃粘膜を保護する食品:オートミール、はちみつ、アーモンドなど
これらの食品は消化が良く、胃酸の過剰分泌を抑える効果があります。また、少量ずつ頻繁に食べることで、胃に一度に大きな負担をかけないようにすることも大切です。
避けるべき食品
以下の食品は胃酸の分泌を促進したり、下部食道括約筋を緩めたりするため、症状を悪化させる可能性があります。
- 高脂肪食:揚げ物、脂身の多い肉、クリーム系の料理など
- 刺激物:唐辛子、わさび、カレー粉などの香辛料
- 酸味の強い食品:柑橘類、トマト、酢を使った料理など
- カフェイン:コーヒー、紅茶、エナジードリンクなど
- アルコール:特に蒸留酒や赤ワインなど
- 炭酸飲料:炭酸水、コーラなどの清涼飲料水
- チョコレート:特にダークチョコレート
- ミント:ミントティー、ミント菓子など
これらの食品は個人差がありますので、自分の体調と相談しながら調整することが大切です。食事日記をつけて、どのような食品が症状を悪化させるかを把握するのも良い方法です。
食事のタイミングと量
食事の内容だけでなく、食べ方も重要です。以下のポイントに注意しましょう。
- 一度に大量に食べるのではなく、少量ずつ頻繁に食べる
- 食事と就寝の間に少なくとも3時間空ける
- ゆっくりよく噛んで食べる
- 食事中の水分摂取は控えめにし、食間に水分を取る
- 規則正しい時間に食事をとる
これらの食事療法を継続することで、胸やけやムカムカの症状が徐々に改善されることが期待できます。ただし、症状が長期間続く場合は、単なる食生活の問題ではなく、何らかの疾患が隠れている可能性もありますので、医療機関での検査をお勧めします。
受診の目安:いつ医師に相談すべきか
胸やけやムカムカの症状は一時的なものであれば心配ありませんが、以下のような場合は医療機関を受診することをお勧めします。
すぐに受診すべき症状
以下の症状がある場合は、緊急性が高いため、すぐに医療機関を受診してください。
- 胸痛が強く、左腕や顎に放散する:心臓の問題の可能性があります
- 呼吸困難を伴う:肺や心臓の問題の可能性があります
- 黒色や赤色の吐血・下血がある:消化管出血の可能性があります
- 激しい腹痛が続く:急性腹症の可能性があります
- 嘔吐が止まらず、脱水症状がある:緊急の治療が必要です
早めに受診すべき症状
以下の症状がある場合は、緊急ではありませんが、早めに医療機関を受診することをお勧めします。
- 症状が2週間以上続く:慢性的な問題がある可能性があります
- 市販薬で症状が改善しない:より専門的な治療が必要かもしれません
- 食事が摂れず、体重が減少している:栄養状態の悪化が懸念されます
- 嚥下困難(食べ物が飲み込みにくい)がある:食道の問題の可能性があります
- 50歳以上で症状が初めて現れた:加齢に伴う疾患の可能性があります
検査と診断
医療機関では、症状や病歴の聴取、身体診察に加えて、必要に応じて以下のような検査が行われることがあります。
- 内視鏡検査:食道、胃、十二指腸の粘膜を直接観察します
- 食道pH測定:食道内の酸度を測定し、胃酸の逆流を評価します
- バリウム造影検査:食道や胃の形態を評価します
- 血液検査:炎症マーカーや貧血の有無を調べます
- ピロリ菌検査:胃炎や胃潰瘍の原因となるピロリ菌の感染を調べます
これらの検査結果に基づいて、適切な治療方針が決定されます。
考えられる疾患
胸やけやムカムカの症状の背景には、以下のような疾患が隠れている可能性があります。
- 逆流性食道炎(GERD):胃酸が食道に逆流し、食道粘膜に炎症を起こす疾患
- 機能性ディスペプシア:明らかな器質的異常がなくても胃の不快症状が続く状態
- 胃炎:胃粘膜の炎症
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍:胃や十二指腸の粘膜に潰瘍ができる疾患
- 食道裂孔ヘルニア:胃の一部が横隔膜の食道裂孔を通って胸腔内に入り込む状態
これらの疾患は適切な治療を行うことで、多くの場合症状の改善が期待できます。早期発見・早期治療が重要ですので、気になる症状がある場合は、ぜひ消化器内科の専門医にご相談ください。

薬物療法:医師が処方する薬と市販薬の違い
胸やけやムカムカの症状が強い場合や、生活習慣の改善だけでは症状が良くならない場合は、薬物療法が検討されます。ここでは、医師が処方する薬と市販薬の違いについて解説します。
医師が処方する薬
医療機関で処方される薬は、市販薬よりも強い効果が期待できます。主な種類は以下の通りです。
- プロトンポンプ阻害薬(PPI):胃酸の分泌を強力に抑制する薬です。逆流性食道炎の第一選択薬として使用されます。
- H2受容体拮抗薬:胃酸分泌を抑制する薬で、PPIよりはやや効果が弱いですが、即効性があります。
- 消化管運動改善薬:胃や食道の動きを改善し、胃内容物の排出を促進する薬です。
- 制酸薬:胃酸を中和する薬で、即効性があります。
- 粘膜保護薬:胃や食道の粘膜を保護し、炎症を抑える薬です。
これらの薬は症状や疾患の種類、重症度に応じて、単独または組み合わせて処方されます。医師の指示に従って正しく服用することが大切です。
市販薬の種類と選び方
市販の胃腸薬にもさまざまな種類があり、症状に合わせて選ぶことが重要です。
- 制酸薬:胃酸を中和する成分を含み、胸やけに効果的です。
- H2ブロッカー:胃酸の分泌を抑制する成分を含み、持続的な効果が期待できます。
- 健胃薬:胃の働きを活発にし、消化を促進する薬です。
- 整腸薬:腸内環境を整える薬で、下痢や便秘の改善に役立ちます。
- 総合胃腸薬:複数の成分を含み、様々な胃腸症状に対応します。
市販薬を選ぶ際は、自分の症状に合った薬を選ぶことが大切です。不明な点があれば、薬剤師に相談するとよいでしょう。
市販薬使用の注意点
市販薬を使用する際は、以下の点に注意しましょう。
- 用法・用量を守って正しく服用する
- 他の薬との飲み合わせに注意する
- 長期間連用しない(一般的に2週間程度が目安)
- 症状が改善しない場合は医療機関を受診する
- 妊娠中や授乳中、持病がある場合は事前に医師や薬剤師に相談する
市販薬はあくまで一時的な対処法です。症状が長引く場合や、繰り返し発生する場合は、根本的な原因を調べるために医療機関を受診することをお勧めします。
胸焼け・ムカムカを予防するための生活習慣改善
胸やけやムカムカの症状を予防するためには、日常生活の中での継続的な取り組みが重要です。以下に、効果的な予防法をご紹介します。
規則正しい食生活
食生活の改善は予防の基本です。以下のポイントを意識しましょう。
- 一日三食、規則正しく食べる
- 食べ過ぎを避け、腹八分目を心がける
- ゆっくりよく噛んで食べる
- 就寝前3時間は食事を避ける
- 脂っこい食事や刺激物を控える
- アルコールやカフェインの摂取を減らす
食事の内容だけでなく、食べ方や食べるタイミングも重要です。特に夜遅い食事は胃酸の逆流を促進するため、避けるようにしましょう。
適度な運動
適度な運動は消化機能を高め、ストレス解消にも役立ちます。ただし、食後すぐの激しい運動は避け、食後1〜2時間経ってから軽い運動を行うのが理想的です。
ウォーキング、水泳、ヨガなどの有酸素運動が特におすすめです。また、腹筋を鍛えることで、腹圧をコントロールし、胃酸の逆流を防ぐ効果も期待できます。
体重管理
肥満は腹圧を上昇させ、胃酸の逆流を促進します。適正体重を維持することで、胸やけやムカムカの症状を予防できる可能性があります。
急激なダイエットは逆に胃に負担をかけるため、バランスの良い食事と適度な運動で、ゆっくりと体重を減らしていくことが大切です。
ストレス管理
ストレスは胃酸の分泌を増加させ、胃腸の動きを乱す原因となります。ストレスを溜め込まないよう、以下のような方法でリラックスする時間を作りましょう。
- 深呼吸や瞑想
- 趣味や好きな活動に時間を使う
- 十分な睡眠をとる
- 適度な運動でストレス発散
- 必要に応じてカウンセリングを受ける
睡眠環境の整備
良質な睡眠は胃腸の健康にも影響します。特に胸やけがある方は、以下のような工夫をしてみましょう。
- 上半身を少し高くして寝る(枕やマットレスの調整)
- 左側を下にして横になる
- 就寝前の飲食を避ける
- 寝る前にリラックスする時間を持つ
- 規則正しい就寝・起床時間を守る
これらの生活習慣改善を継続的に行うことで、胸やけやムカムカの症状を予防し、快適な毎日を送ることができるでしょう。
症状が気になる方は、ぜひ石川消化器内科・内視鏡クリニックにご相談ください。消化器専門医による適切な診断と治療で、あなたの症状改善をサポートいたします。
石川消化器内科・内視鏡クリニックでは、胃カメラ・大腸カメラ検査を「より気軽に」「よりスピーディーに」、そして安心して受けていただけるよう、さまざまな工夫を行っております。お気軽にご相談ください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院
消化器内科受診の目安となる症状チェックリスト〜自己診断の方法とは
お腹の調子が悪いとき、「これは病院に行くべきなのか」と迷った経験はありませんか?消化器の不調は日常的に感じることも多く、どの症状が受診の目安になるのか判断が難しいものです。
消化器内科は、食道・胃・腸・肝臓・胆のう・膵臓など、消化に関わる臓器の病気を専門とする診療科です。これらの臓器に問題が生じると、様々な症状が現れます。
私は消化器内科医として長年診療に携わってきましたが、多くの患者さんが「もっと早く受診すればよかった」と話されます。早期発見・早期治療が可能な病気も少なくありません。
消化器内科を受診すべき主な症状
消化器の不調は様々な形で現れます。以下の症状が見られたら、消化器内科の受診を検討しましょう。
特に重要なのは、症状が長く続く場合や、急に強い症状が現れた場合です。自分の体調の変化に敏感になり、異変を感じたら我慢せずに医療機関を受診することをお勧めします。
腹痛・胃痛
腹痛は消化器疾患でもっとも多い症状の一つです。痛みの場所や性質によって、原因となる臓器や疾患が異なります。
みぞおちの痛みは胃や十二指腸の問題を示すことが多く、右上腹部の痛みは肝臓や胆のう、左上腹部の痛みは膵臓や脾臓の問題が考えられます。下腹部の痛みは主に腸の問題を示唆します。
以下のような腹痛がある場合は、消化器内科を受診しましょう。
- 1週間以上続く腹痛
- 徐々に強くなる痛み
- 夜間に痛みで目が覚める
- 食事と関係なく起こる強い痛み
- これまで経験したことのないような強い痛み
特に注意が必要なのは、持続的な痛みです。腹部に何らかの炎症が生じている可能性があるため、「いつもの痛みだから」と放置せず、受診することをお勧めします。

吐き気・嘔吐
吐き気や嘔吐は、胃腸の問題だけでなく、肝臓や膵臓の疾患でも起こります。一時的な吐き気は食あたりや胃腸炎などが原因のことが多いですが、長く続く場合は注意が必要です。
特に以下のような場合は、早めに受診しましょう。
- 24時間以上続く嘔吐
- 嘔吐物に血液や「コーヒー残渣様」の黒い物質が混じる
- 激しい腹痛を伴う嘔吐
- 頭痛や意識障害を伴う嘔吐
- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)を伴う嘔吐
嘔吐に血液が混じっている場合は、食道や胃に出血がある可能性があり、緊急性が高い状態です。すぐに医療機関を受診してください。
便通の異常と消化器疾患
便通の変化は消化器疾患の重要なサインです。下痢や便秘、血便などの症状は、様々な病気を示唆します。
便通の異常は一時的なものであれば心配ありませんが、長期間続く場合や、他の症状を伴う場合は、消化器内科の受診を検討しましょう。
下痢
下痢は、腸の動きが活発になり、便が水っぽくなる状態です。ウイルスや細菌による感染、食中毒、過敏性腸症候群、炎症性腸疾患などが原因となります。
以下のような下痢の場合は、消化器内科を受診しましょう。
- 2週間以上続く下痢
- 血液や粘液が混じる下痢
- 38度以上の発熱を伴う下痢
- 激しい腹痛を伴う下痢
- 体重減少を伴う下痢
- 夜間に下痢で目が覚める
特に血便を伴う下痢は、炎症性腸疾患や感染性腸炎、大腸がんなどの可能性があるため、早めに受診することが重要です。
便秘
便秘は、排便回数の減少や排便時の困難さを特徴とします。生活習慣の乱れや食事内容、ストレスなどが原因となることが多いですが、腸閉塞や大腸がんなどの重篤な疾患のサインのこともあります。
以下のような便秘の場合は、消化器内科を受診しましょう。
- 3週間以上続く便秘
- 急に始まった頑固な便秘
- 腹痛や腹部膨満感を伴う便秘
- 血便や黒色便を伴う便秘
- 体重減少を伴う便秘
- 便秘と下痢を繰り返す
特に50歳以上で急に便通が変化した場合は、大腸がんの可能性も考えられるため、早めに検査を受けることをお勧めします。
血便・黒色便
便に血液が混じる、または便が黒くなる症状は、消化管のどこかで出血が起きている可能性を示します。鮮血が混じる場合は主に肛門や直腸、S状結腸からの出血、黒色便は上部消化管(食道・胃・十二指腸)からの出血が考えられます。
どう思いますか?血便や黒色便は、痔による出血以外は重大な疾患のサインであることが多いです。
以下のような場合は、すぐに消化器内科を受診しましょう。
- 繰り返す血便
- タール状の黒色便
- めまいや立ちくらみを伴う血便
- 腹痛を伴う血便
- 発熱を伴う血便
血便は大腸ポリープや大腸がん、炎症性腸疾患、感染性腸炎などが原因となることがあります。黒色便は胃潰瘍や十二指腸潰瘍、食道静脈瘤などからの出血が考えられます。
胸やけ・呑酸・げっぷと消化器疾患
胸やけや呑酸(胃酸が喉まで上がってくる感覚)、頻繁なげっぷは、上部消化管の問題を示すことが多い症状です。
これらの症状は一時的なものであれば心配ありませんが、頻繁に起こる場合や、他の症状を伴う場合は、消化器内科の受診を検討しましょう。
胸やけ・呑酸
胸やけは胸の奥や喉の付近に感じる灼熱感や不快感、呑酸は胃酸が喉まで上がってくる感覚です。これらの症状は主に逆流性食道炎によって引き起こされます。
以下のような場合は、消化器内科を受診しましょう。
- 週に2回以上の胸やけや呑酸
- 3ヶ月以上続く症状
- 市販薬で改善しない症状
- 食べ物や飲み物を飲み込みにくい
- 胸痛を伴う胸やけ
- 体重減少を伴う症状
胸やけや呑酸が長期間続く場合、食道粘膜が慢性的に傷つき、バレット食道という状態になることがあります。これは食道がんのリスク因子となるため、適切な治療が必要です。
げっぷ・腹部膨満感
頻繁なげっぷや食後の腹部膨満感は、機能性ディスペプシア(機能性胃腸症)や胃食道逆流症などが原因となることがあります。
以下のような場合は、消化器内科を受診しましょう。
- 3ヶ月以上続く頻繁なげっぷ
- 食後の強い腹部膨満感
- 体重減少を伴うげっぷや膨満感
- 嚥下困難を伴う症状
- 胸痛を伴うげっぷ
これらの症状は生活習慣の改善で軽減することもありますが、長期間続く場合は消化器内科での精査が必要です。
黄疸・腹水と消化器疾患
黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)や腹水(お腹に水がたまる)は、肝臓や胆道系の重篤な疾患を示すことが多い症状です。
これらの症状が見られた場合は、すぐに医療機関を受診してください。
黄疸
黄疸は、ビリルビンという物質が体内に蓄積することで、皮膚や白目が黄色くなる状態です。肝炎、肝硬変、胆石、膵臓がん、胆道がんなどが原因となります。
黄疸を自覚した場合は、以下のような随伴症状にも注意しましょう。
- 皮膚のかゆみ
- 尿の色が濃くなる
- 便の色が白っぽくなる
- 右上腹部の痛み
- 全身の倦怠感
- 発熱
黄疸は重篤な肝胆膵疾患のサインであることが多いため、発見したらすぐに消化器内科を受診してください。
腹水
腹水は、腹腔内に液体がたまる状態です。肝硬変、肝がん、膵臓がん、卵巣がんなどが原因となります。
腹水を疑う症状には以下のようなものがあります。
- お腹の膨満感
- 体重の急激な増加
- 足のむくみ
- 呼吸困難
- へそが出てくる
腹水は進行した肝疾患や悪性腫瘍に伴うことが多いため、これらの症状が見られたら早急に消化器内科を受診してください。
消化器内科での検査と診断
消化器内科を受診すると、症状や疑われる疾患に応じて、様々な検査が行われます。ここでは、主な検査について説明します。
検査の内容や準備については、事前に医師や看護師から説明がありますので、不安なことがあれば遠慮なく質問してください。
血液検査
血液検査では、肝機能、膵機能、炎症反応、貧血の有無などを調べます。肝臓の状態を示すAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、膵臓の状態を示すアミラーゼ、リパーゼ、炎症の指標となるCRPなどが主な検査項目です。
また、ピロリ菌感染の有無を調べる抗体検査や、B型・C型肝炎ウイルスの検査も行われることがあります。
血液検査は比較的簡単で、短時間で結果が得られる検査です。多くの消化器疾患の診断の第一歩となります。
内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)
内視鏡検査は、口や肛門から細い管状の機器(内視鏡)を挿入し、消化管の内部を直接観察する検査です。
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)では、食道・胃・十二指腸を観察します。逆流性食道炎、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食道がん、胃がんなどの診断に役立ちます。
大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)では、大腸全体を観察します。大腸ポリープ、大腸がん、炎症性腸疾患、虚血性大腸炎などの診断に役立ちます。
内視鏡検査では、必要に応じて組織を採取(生検)して、詳しく調べることもできます。
当院では、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の内視鏡検査を提供しており、半分眠ったような状態で楽に検査を受けていただけます。経鼻内視鏡にも対応しており、患者さんの希望に合わせて経口・経鼻の選択が可能です。
超音波検査(エコー)
超音波検査は、体の表面から超音波を当て、内臓の状態を観察する検査です。肝臓、胆のう、膵臓、脾臓などの状態を調べることができます。
痛みもなく、放射線被ばくもない安全な検査です。脂肪肝、胆石、胆のうポリープ、肝腫瘍などの診断に役立ちます。
当院では高性能な超音波装置を導入しており、肝臓、胆嚢、膵臓の精査が可能です。
CT検査・MRI検査
CT検査は、X線を使って体の断層写真を撮影する検査です。肝臓、膵臓、胆のう、腸などの状態を詳しく調べることができます。
MRI検査は、強い磁気を使って体の断層写真を撮影する検査です。特に肝臓や胆道、膵臓の詳細な観察に適しています。
これらの検査は、腫瘍の有無や大きさ、周囲への広がりなどを調べるのに役立ちます。
当院では院内にCTを設置しており、必要に応じて速やかに検査を行うことができます。胸部CTは胸部レントゲン同等の被ばく量で検査できる点も特徴です。
症状別の自己チェックリスト
ここでは、主な消化器症状について、自己チェックリストを紹介します。該当する項目が多い場合は、消化器内科の受診を検討してください。
ただし、このチェックリストはあくまで目安です。心配な症状がある場合は、チェックリストの結果に関わらず、医療機関を受診することをお勧めします。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍チェックリスト
胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、胃や十二指腸の粘膜が傷つき、くぼみ(潰瘍)ができる病気です。以下の症状がないか確認しましょう。
- みぞおちの痛み(特に空腹時や食後)
- 胸やけ
- げっぷが多い
- 吐き気がある
- 嘔吐することがある
- 胃もたれがする
- 口臭が気になる
- 食欲不振
- 体重減少
- 背中が痛い
- 黒い便が出る
- 吐血することがある
特に黒い便や吐血は、潰瘍からの出血を示す重篤なサインです。これらの症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。
逆流性食道炎チェックリスト
逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流することで、食道粘膜が炎症を起こす病気です。以下の症状がないか確認しましょう。
- 胸やけがする(特に食後や横になったとき)
- 酸っぱい液体が喉まで上がってくる
- 胸の痛みがある
- のどの違和感や痛みがある
- 咳が続く(特に夜間)
- 声がかすれる
- 食べ物を飲み込みにくい
- 食後に胃もたれがする
- げっぷが多い
- 口臭が気になる
これらの症状が週に2回以上ある場合や、3ヶ月以上続く場合は、消化器内科を受診しましょう。
過敏性腸症候群チェックリスト
過敏性腸症候群は、腸の機能に問題があり、腹痛や便通異常が起こる病気です。以下の症状がないか確認しましょう。
- 腹痛がある(特に排便で軽減する)
- 下痢と便秘を繰り返す
- 便の形状が変わりやすい(硬い、柔らかい、水様など)
- 便意を我慢できないことがある
- 排便後も残便感がある
- 腹部膨満感がある
- おならが多い
- 粘液便が出ることがある
- ストレスで症状が悪化する
- 食事で症状が変化する
これらの症状が3ヶ月以上続く場合は、消化器内科を受診しましょう。過敏性腸症候群は命に関わる病気ではありませんが、生活の質を大きく低下させることがあります。
「腸は第二の脳」と言われるほど、私たちの心と体に大きな影響を与えます。腸の健康を守ることは、全身の健康を守ることにつながります。
炎症性腸疾患チェックリスト
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)は、腸に慢性的な炎症が起こる病気です。以下の症状がないか確認しましょう。
- 血便がある
- 慢性的な下痢(1日4回以上、夜間も)
- 腹痛がある
- 体重減少
- 発熱
- 全身倦怠感
- 関節痛
- 肛門周囲の痛みや膿瘍
- 口内炎が繰り返し起こる
- 眼の炎症
これらの症状、特に血便が続く場合は、早めに消化器内科を受診しましょう。炎症性腸疾患は早期治療が重要です。

消化器内科受診の目安まとめ
消化器内科を受診すべき主な症状をまとめました。以下の症状がある場合は、消化器内科の受診を検討しましょう。
- 1週間以上続く腹痛・胃痛
- 24時間以上続く嘔吐、または血液が混じる嘔吐
- 2週間以上続く下痢、または血液が混じる下痢
- 3週間以上続く便秘、または急に始まった頑固な便秘
- 血便・黒色便
- 週に2回以上の胸やけや呑酸、または3ヶ月以上続く症状
- 3ヶ月以上続く頻繁なげっぷや腹部膨満感
- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)
- 腹水(お腹に水がたまる)
- 原因不明の体重減少
- 50歳以上で急に始まった消化器症状
特に、血便・黒色便、黄疸、腹水などの症状は、重篤な疾患のサインであることが多いため、すぐに医療機関を受診してください。
また、症状が軽くても、長期間続く場合や、日常生活に支障をきたす場合は、早めに受診することをお勧めします。
消化器の病気は早期発見・早期治療が重要です。「様子を見よう」と思って放置していると、症状が悪化し、治療が難しくなることがあります。
当院では、患者さんの負担を軽減するため、鎮静剤を使用した無痛の内視鏡検査や、初診当日の検査、土曜日の検査にも対応しています。消化器の不調でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
健康な消化器は、健康な生活の基盤です。少しでも気になる症状があれば、専門医に相談することが、あなたの健康を守る第一歩となります。
詳細はこちら:石川消化器内科・内視鏡クリニック

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院