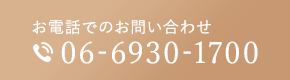大腸カメラ検査とは?その重要性を理解しよう
大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)は、大腸の粘膜を直接観察することで、ポリープや炎症、そして大腸がんなどの病変を早期に発見できる重要な検査です。
正式には「下部消化管内視鏡検査」と呼ばれ、大腸全体と小腸の一部(終末回腸)までを観察することができます。この検査の意義は主に3つあります。症状がある方の原因究明、ポリープやがんの早期発見、そして指摘されている病変の経過観察です。
大腸がんは日本人のがん死亡原因の上位を占めており、早期発見が非常に重要です。アメリカからの報告では、大腸内視鏡を行って大腸ポリープをすべて切除することで、大腸がんによる死亡率が53%低下したという結果も出ています。
しかし、多くの方が検査前の準備に不安を感じています。特に下剤の服用や食事制限は「大変そう」というイメージがあるかもしれません。
当院では年間多数の大腸カメラ検査を実施していますが、適切な準備ができているかどうかで検査の精度が大きく変わることを日々実感しています。
では、どうすれば大腸カメラ検査をスムーズに、そして正確に受けることができるのでしょうか?
大腸カメラ検査の準備で失敗しないための10のコツ
大腸カメラ検査の成否を左右する最大の要因は、検査前の腸内洗浄です。腸がきれいに洗浄されていなければ、病変を見落としてしまう可能性があります。
私が消化器内科医として多くの内視鏡検査を行ってきた経験から、確実に成功させるための10のコツをお伝えします。

1. 検査3〜4日前からの食事調整
検査の3〜4日前から、以下の食品を避けるようにしましょう。
- 食物繊維が多い野菜(キャベツ、ほうれん草、白菜など)
- きのこ類(しいたけ、えのき、しめじなど)
- 海藻類(わかめ、昆布、ひじき)
- 玄米、雑穀米、オートミール
- 脂っこい料理(天ぷら、揚げ物、ラーメン)
- 乳製品(ヨーグルト、チーズ、牛乳)
- こんにゃく、豆類(納豆、煮豆など)
- ナッツ類(アーモンド、カシューナッツなど)
これらの食品は腸内に残りやすく、洗浄剤を使用しても完全に排出されないことがあります。腸壁に付着した食物繊維や油分は、検査時の視野を遮り、病変の発見を妨げる原因となります。
2. 検査前日の食事選びを徹底する
検査前日は特に重要です。消化の良い食品を選び、以下のような食事がおすすめです。
- 白ごはん:繊維が少なく消化が良い
- うどん:柔らかく、消化吸収が早い
- 白身魚(タラ、カレイなど):脂肪分が少なく、胃腸への負担が軽い
- 鶏ささみ:高たんぱく・低脂質で消化も良好
- 卵(茹で卵・茶碗蒸し):調理法に注意すれば消化に優しい
- 豆腐(絹ごし):柔らかく、胃腸にやさしい
前日の食事スケジュールの目安は、朝食に白ごはん+温泉卵+具なし味噌汁、昼食にうどん(具なし)またはプレーンおかゆ、夕食は18時〜19時に終了させ、21時までには完全に食事を終えるようにしましょう。
3. 便秘対策は早めに始める
普段から便秘気味の方は、検査の数日前から対策を始めることが重要です。市販の緩下剤を使用するのも一つの方法です。
便秘の方は腸内に便が溜まりやすく、検査前の洗浄が不十分になりがちです。そのため、検査前から腸内環境を整えておくことで、当日の洗浄がスムーズに進みます。
私の臨床経験では、便秘の方が事前に対策をしておくかどうかで、検査の質が大きく変わることを実感しています。
4. 下剤を効果的に飲むコツ
下剤の服用は大腸カメラ検査の準備で最も大変な部分かもしれません。しかし、いくつかのコツを知っておくと、かなり楽になります。
- 冷やして飲む:下剤を冷蔵庫で冷やしておくと飲みやすくなります
- ストローを使う:直接口に入れずに飲めるので抵抗感が減ります
- レモンを添える:レモンを少し舐めてから飲むと、下剤の味が気になりにくくなります
- 飴を舐めながら飲む:甘い飴を舐めながら飲むことで、下剤の味を和らげることができます
- 一気に飲まず、指示された時間内で少しずつ飲む:無理に一気飲みすると吐き気を催すことがあります
下剤を飲み終わったあとは、透明な液体(水やお茶など)をしっかり摂取し続けることも大切です。これにより腸内の洗浄効果が高まります。
あなたはどうですか?下剤を飲むのに苦労した経験はありませんか?
5. 下剤の効果を確認する
下剤を飲んで排便を繰り返すと、最終的には黄色がかった透明な液体が出てくるようになります。これが「腸がきれいになった」サインです。
もし最後の排便でも濁りや固形物が混じっている場合は、腸の洗浄が不十分な可能性があります。このような場合は、検査当日に医療機関で追加の処置(浣腸など)が必要になることがあります。
私の経験では、最後の排便の状態を確認しておくことで、検査当日の心構えができますし、必要に応じて医師に伝えることができます。
6. 検査当日の水分摂取を忘れない
検査当日は食事ができませんが、水分は検査の2時間前まで摂取できる場合が多いです。ただし、必ず医療機関の指示に従ってください。
適切な水分摂取は、体調維持だけでなく、腸内洗浄の効果を持続させる役割もあります。特に夏場は脱水に注意が必要です。
摂取できる飲み物は基本的に透明な液体(水、お茶、透明なスポーツドリンクなど)に限られます。牛乳、ジュース、コーヒー、紅茶などの色のついた飲み物は避けましょう。
7. 服薬について医師に相談する
普段服用している薬がある場合は、事前に医師に相談することが重要です。特に注意が必要なのは以下の薬です。
- 血液をサラサラにする薬(抗凝固薬、抗血小板薬)
- 糖尿病の薬(特にインスリン)
- 便通を整える薬
これらの薬は検査の数日前から調整が必要な場合があります。自己判断で中止せず、必ず医師の指示に従いましょう。
私が診療で特に注意しているのは、抗凝固薬を服用している方です。ポリープ切除を行う場合には出血リスクが高まるため、事前の対応が必要になることがあります。
8. 検査当日の服装を工夫する
検査当日は動きやすく、着脱しやすい服装を選びましょう。特におすすめなのは以下のポイントです。
- ウエストがゴムの服(ジーンズなど固いものは避ける)
- 上下分かれた服(ワンピースは避ける)
- 着脱しやすいシンプルな服
検査中は横向きになったり体位を変えたりすることがあるため、動きやすい服装が望ましいです。また、検査後にお腹が張ることもあるので、締め付けない服装を選ぶと快適です。
9. 検査後の過ごし方を計画しておく
検査後は、腸に空気が入っているため膨満感を感じることがあります。また、鎮静剤を使用した場合は、その日の車の運転はできません。
検査後の過ごし方について、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 帰宅方法を事前に確保しておく(公共交通機関の利用や家族の送迎など)
- 検査後すぐの予定は入れない
- 軽い食事から始め、徐々に通常の食事に戻す
- 水分をしっかり摂る
ポリープ切除を行った場合は、アルコールや激しい運動、入浴(シャワーは可)を数日間控える必要があることもあります。医師の指示に従いましょう。
10. 信頼できる医療機関を選ぶ
大腸カメラ検査は、医療機関や医師の技術によって精度や快適さが大きく変わります。信頼できる医療機関を選ぶポイントとしては以下が挙げられます。
- 消化器内科や内視鏡の専門医がいるか
- 鎮静剤を使用した無痛内視鏡に対応しているか
- 検査実績が豊富か
- 緊急時の対応体制が整っているか
- 検査前の説明が丁寧か
当院では、鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査を提供しており、患者さんの負担を最小限に抑えながら精度の高い検査を実現しています。

大腸カメラ検査の流れと実際の体験
大腸カメラ検査がどのように行われるのか、実際の流れを説明します。
検査当日は、まず問診と体調確認が行われます。その後、検査着に着替え、横になった状態で検査が始まります。鎮静剤を使用する場合は、点滴から投与されます。
私が実際に経験した患者さんの例を紹介します。50代の男性Aさんは、便潜血検査で陽性となり大腸カメラ検査を受けることになりました。初めての検査で不安を感じていましたが、鎮静剤を使用したところ、「気づいたら終わっていた」と驚いていました。
また、60代の女性Bさんは以前別の医療機関で検査を受けた際に強い痛みを感じた経験があり、検査を恐れていました。当院での検査では適切な鎮静と丁寧な内視鏡操作により、「こんなに楽に終わるなんて」と喜ばれました。
検査中は医師が内視鏡を挿入し、大腸内を観察します。必要に応じてポリープの切除や組織採取を行います。検査時間は通常15〜30分程度ですが、鎮静剤を使用すると体感時間はずっと短く感じられます。
検査後は回復室で30分〜1時間程度休息し、体調が安定したら帰宅できます。その日のうちに検査結果の説明を受けられることが多いですが、病理検査が必要な場合は後日の説明となります。
あなたも不安を感じていますか?多くの方が最初は不安を感じますが、適切な準備と鎮静剤の使用により、思ったより楽に検査を終えられることがほとんどです。
大腸カメラ検査で見つかる主な病変
大腸カメラ検査では、様々な病変を発見することができます。主なものとしては以下が挙げられます。
大腸ポリープ
大腸ポリープは大腸の粘膜から突出した隆起性病変です。多くは良性ですが、一部は時間をかけて大腸がんに進行する可能性があります。大きさや形状、色調などから良性か悪性かの判断をしますが、確定診断には病理検査が必要です。
5mm以下の小さなポリープは、その場で切除することが多いです。6mm以上のポリープは、形状や性状によって適切な切除方法を選択します。
大腸がん
大腸がんは早期に発見できれば内視鏡治療で完治する可能性が高い病気です。早期大腸がんの多くは症状がないため、検診での発見が重要です。
進行すると血便や便通異常、腹痛などの症状が現れることがありますが、これらの症状は他の病気でも起こるため、症状があれば早めに医療機関を受診することをお勧めします。
炎症性腸疾患
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患も大腸カメラで診断できます。これらの疾患は腸の粘膜に炎症や潰瘍を生じる慢性疾患で、下痢や血便、腹痛などの症状を引き起こします。
炎症性腸疾患の患者さんは定期的な大腸カメラ検査が必要で、炎症の程度を評価するとともに、長期経過による大腸がんのリスク増加にも注意が必要です。
まとめ:大腸カメラ検査を成功させるために
大腸カメラ検査は、大腸の病変を早期に発見し、適切な治療につなげるための重要な検査です。検査の成否を左右するのは、何よりも検査前の準備です。
今回ご紹介した10のコツを実践することで、検査をスムーズに、そして正確に受けることができます。特に重要なのは、検査前の食事制限と下剤の適切な服用です。
当院では、患者さんの不安や負担を軽減するために、鎮静剤を用いた無痛内視鏡検査を提供しています。また、検査前の準備についても丁寧にご説明し、患者さん一人ひとりに合わせたサポートを心がけています。
大腸カメラ検査に不安を感じている方も、適切な準備と信頼できる医療機関での検査により、安心して検査を受けることができます。ご自身の健康管理のために、定期的な検査をお勧めします。
検査についてのご質問や不安なことがあれば、いつでもご相談ください。皆様の健康を守るために、私たちは誠心誠意サポートいたします。
詳しい情報や予約については、石川消化器内科・内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院