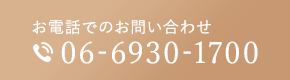粉瘤とは?基本的な知識を解説
皮膚にできるしこりや膨らみの中でも、粉瘤(ふんりゅう)は比較的よく見られる皮膚疾患です。粉瘤は表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ)とも呼ばれ、皮膚の下に袋状の構造ができて、その中に角質や皮脂が溜まることで形成される良性の腫瘍です。
粉瘤の特徴として、中央に小さな黒点(ヘソ)が見られることが多く、ここから白い粥状の内容物が排出されることがあります。この内容物は脂肪ではなく、垢(角質)のカタマリなのです。
粉瘤は年齢や性別に関係なく誰にでもできる可能性があり、全身のどこにでも発生します。特に顔、首、背中、耳の後ろなどの皮脂腺が多い部位にできやすい傾向があります。
なぜ粉瘤ができるのでしょうか?
粉瘤の明確な原因は完全には解明されていませんが、外傷や毛穴の閉塞によって表皮細胞が皮膚内部に取り込まれ、増殖することで形成されると考えられています。本来なら垢となって剥がれ落ちるはずの表皮細胞が、袋の外に出られずに蓄積され、徐々に大きくなっていくのです。

粉瘤を放置するとどうなる?主なリスク
「小さな粉瘤だから大丈夫」と放置してしまう方は少なくありません。しかし、粉瘤は自然に治ることがほとんどなく、放置すると様々なリスクが生じます。
粉瘤を放置した場合に起こりうる主なリスクを詳しく見ていきましょう。
徐々に大きくなる
粉瘤の中身である角質や皮脂は、袋の外に自然に排出されることがないため、放置すると少しずつ大きくなっていきます。初期は小さなしこりでも、時間の経過とともに成長し、野球ボール大になることもあるのです。
特に顔や首など、人目につきやすい部位にできた粉瘤が大きくなると、見た目の問題も生じてきます。自分の外見に自信を持てなくなったり、人目が気になったりするなど、精神的な負担も増えていくでしょう。
炎症を起こす(炎症性粉瘤)
粉瘤に炎症が生じると、表面が赤くなり、痛みを伴うようになります。これが炎症性粉瘤です。炎症が進行すると、赤みが拡大し、痛みも強くなります。
炎症を起こした粉瘤は、袋の内容物が膿となってブヨブヨとした感触になることもあります。腫れが限界に達すると、粉瘤が破裂して臭いドロドロの内容物が排出される場合もあるのです。
さらに、炎症に細菌感染が加わると症状は悪化し、強い痛みや腫れが生じます。このような状態になると、日常生活に支障をきたすだけでなく、緊急の切開処置が必要になることもあります。
あなたは粉瘤の炎症に悩まされたことがありますか?
悪性化するリスク
粉瘤は基本的に良性の腫瘍ですが、経過が非常に長く、大きかったり、炎症を繰り返したりした場合、ごくまれに悪性化したという報告もあります。
特に、中高年の男性の頭部、顔面、臀部の大きな粉瘤が急速に大きくなったり、表面の皮膚に傷ができたりした場合には注意が必要です。悪性化のリスクは低いものの、完全には否定できないということを覚えておきましょう。

粉瘤の早期治療がもたらすメリット
粉瘤は放置せず、早期に適切な治療を受けることで様々なメリットがあります。小さなうちに治療することで、手術の負担も少なく、回復も早くなります。
粉瘤の早期治療がもたらす主なメリットを見ていきましょう。
簡単な手術で治療できる
粉瘤が小さいうちであれば、比較的簡単な手術で治療することができます。小さな粉瘤の場合、手術時間は約5分程度と非常に短時間で済むことも多いのです。
早期の治療では、最小限の切開で済むため、患者さんへの身体的負担が軽減されます。また、小さな粉瘤であれば、くり抜き法という特殊な器具を用いた治療法も選択肢となります。
くり抜き法は、粉瘤に小さな穴をあけ、内容物を排出した後に袋を抜き取る方法です。傷口が小さく済み、手術時間も短いというメリットがあります。
一方、粉瘤が大きくなってからの治療では、切開法という方法が必要になることが多くなります。切開法では傷口が比較的大きくなる可能性があり、手術時間も長くなります。
手術痕が残りにくい
粉瘤が小さいうちに治療を行うことで、切開の範囲を最小限に抑えることができます。その結果、術後の傷跡が目立ちにくくなるというメリットがあります。
特に顔や首など、外見上重要な部位に粉瘤ができた場合には、早期治療によって美容面での影響を最小限に抑えることができます。これは、日常生活や社会活動において大きなメリットとなるでしょう。
粉瘤が大きくなってから摘出すると、どうしても傷跡が目立ちやすくなります。早期治療は見た目の観点からも非常に重要なのです。
再発予防になる
粉瘤を早期に治療することで、嚢胞を完全に除去することが可能となり、再発のリスクを大幅に減少させることができます。
炎症を起こした粉瘤は、袋が破れて内容物が周囲に漏れ出している可能性があります。このような状態では、完全に袋を取り除くことが難しくなり、再発のリスクが高まります。
早期治療を行うことで、これらの合併症を未然に防ぎ、粉瘤の完全除去がより確実になります。結果として、再発の可能性を最小限に抑えることができるのです。
粉瘤の治療方法と選択肢
粉瘤の治療には、主に「くり抜き法」と「切開法」という2つの方法があります。それぞれの特徴を理解し、自分の状態に合った治療法を選ぶことが大切です。
ここでは、粉瘤の主な治療方法について詳しく解説します。
くり抜き法
くり抜き法は、特殊な器具(デルマパンチ)を用いて粉瘤に小さな穴をあけ、その穴から粉瘤の内容物を絞り出した後、しぼんだ粉瘤の袋を抜き取る方法です。
この方法のメリットは、傷口が小さく済むため、手術時間が短く、術後の回復も早い点です。特に小さな粉瘤であれば、手術時間は約5分程度と非常に短時間で行うことができます。また、傷跡が目立ちにくいという利点もあります。
ただし、くり抜き法にはデメリットもあります。粉瘤の袋を完全に取り除けない可能性があり、その場合は再発のリスクが高まります。また、大きな粉瘤や炎症を起こしている粉瘤には適さない場合があります。
切開法
切開法は、粉瘤が大きい場合や複雑な形状をしている場合に適用される治療法です。この手術では、粉瘤の部位を切開して内部の内容物を取り除き、続いて粉瘤の袋(嚢胞)を完全に摘出します。
切開法は、特に炎症が進行しているケースや、再発を防ぐために確実に粉瘤を除去する必要がある場合に選択されることが多い治療方法です。
この方法では、傷口が比較的大きくなる可能性がありますが、袋を完全に除去することで再発のリスクを大幅に低減できます。また、大きな粉瘤や複雑な形状の粉瘤にも対応できるというメリットがあります。
炎症性粉瘤の治療
炎症を起こして膿がたまってしまった炎症性粉瘤に対しては、まず切開排膿という処置が必要になることがあります。これは、皮膚を切開して、たまっている膿を排出する処置です。
炎症が強くなり膿がたまってしまった状態では、膿を物理的に取り除かない限り炎症の改善が見込めません。切開排膿は局所麻酔で行いますが、切開部分は縫わずに開放したままにします。
切開排膿はあくまで応急処置であり、炎症が落ち着いた後に改めて粉瘤の摘出手術を行うことになります。そのため、感染のない場合に比べ治療期間が長くなります。

粉瘤の予防と日常生活での注意点
粉瘤の原因が明確に分かっていないため、確実な予防方法も確立されていません。しかし、日常生活での注意点を守ることで、粉瘤のリスクを減らせる可能性があります。
ここでは、粉瘤の予防と日常生活での注意点について解説します。
清潔な肌を保つ
粉瘤は皮下に角質や皮脂が溜まったものであるため、毎日お風呂に入って肌を清潔に保つことは大切です。特に、皮脂腺が多い顔や首、背中などは丁寧に洗いましょう。
ただし、過剰な洗浄や強いこすり洗いは肌を傷つけ、かえって皮膚トラブルの原因になることもあります。適切な洗浄料を使い、優しく洗うことを心がけましょう。
粉瘤を見つけたら早めに受診
皮膚にしこりを見つけたら、それが粉瘤かどうかにかかわらず、早めに皮膚科や形成外科を受診することをおすすめします。早期発見・早期治療が、治療の負担を軽減し、合併症のリスクを減らす鍵となります。
「ニキビだから大丈夫」と自己判断せず、医師の診断を受けることが大切です。特に、しこりが徐々に大きくなっている場合や、赤みや痛みがある場合は、すぐに受診しましょう。
粉瘤を自分で潰さない
粉瘤を自分で潰そうとすると、感染のリスクが高まり、炎症が悪化する可能性があります。また、袋を完全に取り除くことができないため、再発の原因にもなります。
粉瘤を見つけたら、決して自分で潰さず、専門医の診察を受けましょう。適切な治療を受けることで、安全かつ確実に粉瘤を取り除くことができます。
まとめ:粉瘤の早期治療で健やかな肌を保とう
粉瘤は放置すると徐々に大きくなり、炎症を起こすリスクが高まります。炎症を起こすと痛みを伴い、日常生活に支障をきたす可能性もあります。また、まれに悪性化するリスクもあります。
一方、早期に治療することで、簡単な手術で済み、手術痕も残りにくく、再発のリスクも低減できるというメリットがあります。粉瘤の治療には主に「くり抜き法」と「切開法」があり、粉瘤の大きさや状態に応じて適切な方法が選択されます。
皮膚にしこりを見つけたら、自己判断せず、早めに専門医を受診することが大切です。適切な診断と治療を受けることで、健やかな肌を保つことができるでしょう。
当院では、消化器内科・内視鏡専門医である院長が診察を担当し、患者様一人ひとりに合わせた丁寧な診療を心がけています。皮膚のお悩みも含め、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
詳しい情報や予約については、石川消化器内科・内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。皆様の健康をサポートするために、誠心誠意対応させていただきます。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院