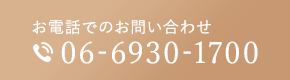胃もたれは多くの方が経験する不快な症状です。食後に胃が重く感じたり、胸やけや吐き気を伴ったりすることもあります。日常生活に支障をきたすこともある胃もたれについて、消化器内科専門医の立場から原因と対処法を詳しく解説します。
胃もたれは一過性のものであればセルフケアで改善することもありますが、長期間続く場合は何らかの疾患が隠れていることもあります。適切な対処法を知り、必要に応じて医療機関を受診することが大切です。
この記事では、胃もたれの主な原因と即効性のある対処法、そして受診を検討すべきタイミングについて詳しく解説していきます。

胃もたれとは?症状の特徴を理解しよう
胃もたれとは、食べたものが胃の中に長時間残っているように感じる不快な症状のことです。みぞおちの辺りが重苦しく感じたり、胃がムカムカしたりする感覚を伴います。
胃もたれの主な症状には以下のようなものがあります。
- 食後、胃の中にいつまでも食べ物が残っているような感覚
- みぞおちの辺りが重く、圧迫感がある
- 食事をするとすぐにお腹がいっぱいになる
- 胃にガスが溜まってお腹が張る(膨満感)
- 吐き気を伴うことがある
- げっぷが出やすくなる
これらの症状は食後に現れることが多いですが、空腹時にも感じることがあります。特に食べ過ぎた後や脂っこい食事の後に症状が強く出ることが特徴的です。
胃もたれは一時的なものであれば心配ありませんが、症状が長く続く場合は注意が必要です。それでは、胃もたれを引き起こす主な原因について見ていきましょう。
胃もたれの7つの主な原因
胃もたれはさまざまな原因で起こります。日常生活の乱れから疾患まで、幅広い要因が関わっています。ここでは主な7つの原因について解説します。
1. 食生活の乱れ
胃もたれの最も一般的な原因は食生活の乱れです。特に以下のような食習慣が胃もたれを引き起こしやすくなります。
- 食べ過ぎ・飲み過ぎ
- 脂っこい食事や消化に時間のかかる食品の摂取
- 早食い
- 不規則な食事時間
- アルコールやカフェインの過剰摂取
食べ過ぎた場合、胃に入った食物の量が多すぎて消化能力を超えてしまいます。また、脂肪分の多い食事は消化に時間がかかり、胃の中に食べ物が長く留まることになります。
特に揚げ物や脂っこい料理、ケーキなどの消化に時間のかかる食べ物は、6時間以上かけて消化されることもあります。そのため、翌日になっても胃の中に残ってしまい、胃もたれの原因となるのです。
2. ストレス
胃は精神面の影響を受けやすい臓器です。強いストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、胃の機能に影響を与えます。
ストレスにより交感神経が優位になると、胃の血管が収縮して血流が減少し、胃の運動と胃を守る粘液の分泌が減少します。一方で、副交感神経も働いて胃酸の分泌が活発になることがあります。
この状態が続くと、胃酸の働きが胃粘液の防御力を上回り、胃粘膜を痛めるようになります。その結果、胃もたれや胃痛などの症状が現れるのです。

3. 加齢による胃機能の低下
年齢を重ねると、胃の機能は徐々に低下していきます。加齢により胃の粘膜が萎縮し、胃酸や消化酵素の分泌が減少します。また、胃の筋肉の弾力性も失われ、蠕動運動(食べ物を送り出す動き)も弱まります。
これらの変化により、胃の消化能力が低下し、食べ物が胃内に長く留まりやすくなります。その結果、若い頃には問題なく食べられていた量や種類の食事でも、胃もたれを感じるようになるのです。
4. 消化器系の疾患
胃もたれが長期間続く場合は、消化器系の疾患が原因となっていることがあります。代表的な疾患には以下のようなものがあります。
- 機能性ディスペプシア
- 胃炎
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍
- 逆流性食道炎
- 胃がん
特に注意が必要なのが「胃がん」です。一般的に高齢者に多いイメージがありますが、若年層でも発症する可能性があります。ピロリ菌未感染の若年女性でもスキルス胃がんが見つかることもあるため、胃もたれが長く続く場合は医療機関を受診することをお勧めします。
5. ピロリ菌感染
ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)は胃の粘膜に感染し、胃炎や消化性潰瘍を引き起こす細菌です。日本人は特に高齢者を中心にピロリ菌感染者が多いことが知られています。
ピロリ菌に感染すると、胃粘膜や十二指腸粘膜に炎症が起き、胃もたれや胃痛などの症状が現れることがあります。また、ピロリ菌は胃がんのリスク因子としても知られています。
健康診断や人間ドックでピロリ菌感染が指摘された場合は、放置せずに医療機関を受診して適切な治療を受けることが重要です。
6. 薬剤の影響
一部の薬剤は胃粘膜に影響を与え、胃もたれの原因となることがあります。特に注意が必要なのは以下のような薬剤です。
- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):ロキソニンやボルタレンなど
- ステロイド薬
- 一部の抗生物質
- 鉄剤
これらの薬剤を服用している場合は、医師や薬剤師に相談し、胃粘膜保護剤の併用や服用方法の工夫などの対策を検討することが大切です。
7. 生活習慣の乱れ
不規則な生活習慣も胃もたれの原因となります。特に以下のような生活習慣が胃の機能に影響を与えます。
- 睡眠不足
- 運動不足
- 喫煙
- 過度の疲労
これらの生活習慣は自律神経のバランスを崩し、胃の機能低下を招きます。規則正しい生活を心がけることが、胃もたれの予防につながります。
胃もたれの即効性のある対処法
胃もたれが起きたときは、適切な対処をすることで症状を和らげることができます。ここでは即効性のある対処法をご紹介します。
1. 白湯を飲む
胃もたれを感じたら、まず白湯(お湯)を飲むことをお勧めします。冷たい水や熱すぎるお湯は胃に負担をかけるため、人肌程度の温度の白湯が適しています。
白湯を飲むことで脂肪分などの消化を助け、胃の中の食物を十二指腸に送り出す働きを促進します。ゆっくりと少量ずつ飲むことがポイントです。
2. 消化の良い食事を摂る
胃もたれが起きている時は、胃に負担をかけない消化の良い食事を心がけましょう。うどんやおかゆ、野菜のスープなど、形が柔らかく消化しやすい炭水化物中心の食事がおすすめです。
消化の良い食事を摂ることで、胃の中では消化酵素が分泌され、残っている食物の消化を助けてくれます。脂っこいものや刺激物は避け、少量ずつゆっくり食べることが大切です。
3. 軽い運動をする
胃もたれを感じたら、横になるのではなく、できるだけ立っている状態を保ち、可能であれば軽く散歩をすることをお勧めします。
寝転がっていると胃の中の食物が逆流して消化が進みにくくなります。体を動かすことで胃腸の蠕動運動も活発になり、胃から十二指腸への食物の移動を促進します。
ただし、激しい運動は逆効果になるため、軽い散歩程度にとどめましょう。
4. 上体を起こして安静にする
散歩ができないほど胃もたれがひどい場合は、上体を起こした状態で安静にしましょう。横になると胃の内容物が逆流する可能性があるため、座った状態や上半身を少し高くした状態で休むことをお勧めします。
重力を利用して胃の内容物が十二指腸や小腸へと流れるように促すことが大切です。
5. つぼ押しやマッサージ
胃の周辺のつぼを刺激することで、胃の働きを活性化させる効果が期待できます。特に「中脘(ちゅうかん)」と呼ばれるみぞおちの真ん中あたりのつぼや、「内関(ないかん)」と呼ばれる手首の内側のつぼを優しく押すと良いでしょう。
また、お腹を時計回りに優しくマッサージすることで、腸の蠕動運動を促進し、胃の内容物の移動を助ける効果があります。ただし、強く押したり激しくマッサージしたりすると逆効果になるため、優しく行うことが大切です。
6. 市販薬の利用
胃もたれがひどい場合は、市販の胃薬を利用するのも一つの方法です。胃薬には主に以下のようなタイプがあります。
- 消化酵素配合薬:消化を助ける
- 制酸剤:胃酸を中和する
- 胃粘膜保護剤:胃の粘膜を保護する
- 胃の運動を改善する薬:胃の働きを活性化する
症状に合わせて適切な薬を選ぶことが大切ですが、使用前に説明書をよく読み、用法・用量を守って服用しましょう。また、症状が長引く場合は自己判断での服用を続けず、医療機関を受診することをお勧めします。
7. 温める
胃の周りを温めることで、血行が促進され、胃の働きが活性化することがあります。カイロや湯たんぽなどをタオルで包み、みぞおちの辺りに当てると良いでしょう。
ただし、熱すぎると皮膚を傷める可能性があるため、適度な温度で行うことが大切です。また、食後すぐの温めは消化を遅らせる可能性があるため、食後1〜2時間経ってから行うことをお勧めします。
胃もたれが続く場合の受診目安
胃もたれは一過性のものであれば自己対処で改善することが多いですが、以下のような場合は医療機関を受診することをお勧めします。
1. 症状が1週間以上続く
胃もたれの症状が1週間以上続く場合は、何らかの疾患が隠れている可能性があります。自己対処で改善しない長引く胃もたれは、医療機関での精査が必要です。
2. 市販薬を服用しても症状が改善しない
市販の胃薬を適切に服用しても症状が改善しない場合は、より専門的な診断と治療が必要かもしれません。自己判断での薬の服用を続けるのではなく、医師の診察を受けることをお勧めします。
3. 以下の症状を伴う場合
胃もたれに加えて、以下のような症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
- 体重の急激な減少
- 嘔吐(特に血液が混じっている場合)
- 黒色便や血便
- 強い腹痛
- 飲み込みにくさ
- 食欲不振が続く
- 貧血症状(めまい、倦怠感など)
これらの症状は、胃がんや消化性潰瘍などの重大な疾患のサインである可能性があります。特に45歳以上の方や、胃がんの家族歴がある方は注意が必要です。

4. 精密検査を受けるべきタイミング
胃もたれの原因を特定するために、以下のような検査が行われることがあります。
- 胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)
- 血液検査(ピロリ菌検査、貧血の有無など)
- 腹部超音波検査
- CT検査
特に胃カメラ検査は、胃の粘膜の状態を直接観察できるため、胃炎や胃潰瘍、胃がんなどの診断に有用です。当院では鎮静剤を使用した無痛の胃カメラ検査を行っており、苦痛を最小限に抑えて検査を受けていただくことが可能です。
胃もたれを予防するための生活習慣
胃もたれを予防するためには、日常生活での心がけが大切です。以下のような生活習慣の改善を心がけましょう。
1. 食生活の改善
胃もたれを予防するためには、以下のような食生活の改善が効果的です。
- 腹八分目を心がけ、食べ過ぎを避ける
- 脂っこい食事や刺激物を控える
- よく噛んでゆっくり食べる
- 規則正しい時間に食事をする
- 就寝前2〜3時間は食事を避ける
- アルコールやカフェインの摂取を控える
特に夕食は寝る前に胃に負担をかけないよう、軽めの食事にすることをお勧めします。また、水分はこまめに摂取することで、消化を助ける効果があります。
2. ストレス管理
ストレスは胃の機能に大きな影響を与えます。ストレスを完全に避けることは難しいですが、上手に管理する方法を身につけることが大切です。
- 十分な睡眠をとる
- 趣味や運動でリフレッシュする時間を持つ
- 深呼吸やストレッチなどのリラクゼーション法を取り入れる
- 無理なスケジュールを避け、休息時間を確保する
自分に合ったストレス解消法を見つけ、定期的に実践することで、胃への負担を軽減することができます。
3. 適度な運動
適度な運動は胃腸の働きを活性化し、消化を促進する効果があります。ただし、食後すぐの激しい運動は避け、食後1〜2時間経ってから軽い運動を行うことをお勧めします。
ウォーキングやヨガなどの軽い運動から始め、徐々に強度を上げていくと良いでしょう。運動習慣を身につけることで、胃腸の健康だけでなく、全身の健康維持にもつながります。
4. 禁煙
喫煙は胃粘膜を刺激し、胃酸の分泌を促進するため、胃もたれや胃炎、胃潰瘍のリスクを高めます。禁煙することで、胃の健康を守ることができます。
禁煙が難しい場合は、喫煙本数を減らす、食前食後の喫煙を避けるなどの工夫をしましょう。また、禁煙外来などの専門的なサポートを利用することも一つの方法です。
まとめ:胃もたれを理解して快適な生活を
胃もたれは多くの方が経験する不快な症状ですが、その原因を理解し、適切に対処することで症状を和らげることができます。また、生活習慣の改善により、胃もたれの予防も可能です。
胃もたれの主な原因は、食生活の乱れ、ストレス、加齢による胃機能の低下、消化器系の疾患、ピロリ菌感染、薬剤の影響、生活習慣の乱れなどです。症状が長引く場合や、体重減少、嘔吐、黒色便などの症状を伴う場合は、早めに医療機関を受診することをお勧めします。
当院では、胃もたれなどの消化器症状でお悩みの方に対して、丁寧な診察と必要に応じた検査を行っています。特に内視鏡検査(胃カメラ)は、鎮静剤を使用した無痛検査を実施しており、苦痛を最小限に抑えて受けていただくことが可能です。
胃の健康は全身の健康につながります。胃もたれでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。適切な診断と治療で、快適な生活を取り戻しましょう。
詳しい情報や検査のご予約は、石川消化器内科・内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院