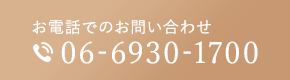粉瘤とは?症状と特徴を理解しよう
皮膚の下にできる「しこり」に気づいて、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。特に「粉瘤(ふんりゅう)」は、日常診療でもよく遭遇する皮膚の良性腫瘍です。
粉瘤は、皮膚からはがれ落ちる垢(角質)や皮脂が、皮膚の内側にある袋状の構造物にたまってできた腫瘍(嚢腫)の総称です。医学的には「表皮嚢腫」とも呼ばれています。
年齢や性別に関係なく誰にでも発症する可能性があり、身体のどの部位にもできる可能性がありますが、特に顔や首、背中などに発生しやすい傾向があります。
粉瘤の特徴的な症状としては、数ミリから数センチ大のやや盛り上がったしこりとして触知でき、中央に黒点状の開口部(毛孔開口部、いわゆる「へそ」)が見られることが多いです。強く押すと、白色〜黄色のドロドロとした内容物が出てくることがあります。この内容物は角質や皮脂が主成分で、独特の臭いを伴うことも特徴です。
粉瘤自体は基本的に良性の腫瘍であり、がんなどの悪性腫瘍とは異なります。しかし、放置すると様々な問題が生じる可能性があるため、適切な対処が必要です。

粉瘤を放置するとどうなるのか?
「小さな粉瘤だから放置しても大丈夫だろう」と考える方も多いかもしれません。では、粉瘤を放置するとどのような経過をたどるのでしょうか?
粉瘤は自然に治癒することはほとんどなく、放置すると以下のような状態になる可能性があります。
徐々に大きくなる
粉瘤の中身である角質や皮脂は袋の外に自然には排出されないため、放置すると少しずつ大きくなっていきます。小さなものでも時間をかけて成長し、野球ボール大になることもあります。
大きくなった粉瘤は見た目の問題だけでなく、周囲の組織を圧迫することで痛みや不快感を引き起こすこともあります。特に肩や背中など、衣服や日常動作による刺激を受けやすい部位では、不快感が増す傾向にあります。
炎症を起こす可能性
粉瘤に炎症が生じると、表面が赤くなり、痛みを伴うようになります。これが「炎症性粉瘤」です。
炎症が進行すると、赤みが拡大し、痛みも強くなります。袋の内容物が膿(うみ)となり、触るとブヨブヨとした感触になることもあります。腫れが限界に達すると、粉瘤が破裂して臭いドロドロの内容物が排出されることもあります。
さらに厄介なのが細菌感染の合併です。細菌感染により炎症症状は悪化し、強い痛みや腫れが生じると、緊急の切開処置が必要になることもあります。
まれに悪性化することがある
粉瘤は基本的に良性腫瘍ですが、非常にまれなケースとして、経過が非常に長く、大きかったり、炎症を繰り返したりした場合に悪性化することがあります。
特に注意が必要なのは、中高年の男性の頭部、顔面、臀部にできた大きな粉瘤で、急速に大きくなったり、表面の皮膚に傷ができたりする場合です。
悪性化を防ぐためにも、小さなうちの早めの手術をおすすめします。
粉瘤は消化器内科で治療できるのか?
「粉瘤ができたけど、どの診療科を受診すればいいのだろう?」と迷われる方も多いでしょう。粉瘤は皮膚の疾患ですが、実際には複数の診療科で治療が可能です。
消化器内科医の立場からお話しすると、粉瘤の治療は基本的に外科的処置が必要となるため、従来は皮膚科や外科が主な受診先でした。しかし、近年では消化器内科クリニックでも粉瘤の日帰り手術に対応しているところが増えています。
消化器内科クリニックでの粉瘤治療のメリット
消化器内科、特に内視鏡検査を専門とするクリニックでは、日常的に様々な処置や小手術を行っているため、粉瘤の切除術にも対応できる医師が多くいます。当院のような消化器内科クリニックでも、粉瘤の日帰り手術を行っています。
消化器内科クリニックで粉瘤治療を受けるメリットとしては以下のような点が挙げられます:
- 内視鏡検査など他の消化器疾患の検査・治療と同時に対応できる
- 局所麻酔の技術が高く、痛みの少ない処置が期待できる
- 日帰り手術に慣れているため、効率的な治療が可能
- かかりつけ医として総合的な健康管理ができる
ただし、大きな粉瘤や複雑な症例の場合は、皮膚科や形成外科などの専門医への紹介が必要になることもあります。
粉瘤の適切な治療法とは?
粉瘤の治療法は、その大きさや状態、発生部位によって異なります。ここでは、主な治療法について解説します。
切開排膿(炎症時の応急処置)
炎症を起こして膿がたまってしまった炎症性粉瘤に対しては、まず切開排膿を行います。これは皮膚を切開して膿を出す処置で、痛みや腫れを軽減するための応急処置です。
ただし、切開排膿だけでは袋状の構造物(嚢胞壁)が残るため、炎症が落ち着いた後に改めて完全摘出の手術が必要になることが多いです。
完全摘出(根本的な治療)
粉瘤の根本的な治療は、袋状の構造物ごと完全に摘出する手術です。これにより再発を防ぐことができます。
手術方法には主に以下の2種類があります:
- 切開法:粉瘤の上の皮膚を切開し、袋状の構造物を丁寧に剥離して取り出す方法。確実に摘出できるため再発率が低いですが、傷跡がやや大きくなる傾向があります。
- くり抜き法:粉瘤の開口部を少し広げるか、小さな穴を開けて、そこから袋状の構造物をくり抜くように取り出す方法。傷跡が目立ちにくいメリットがありますが、完全に摘出できないと再発のリスクがあります。
どちらの手術方法を選択するかは、粉瘤の大きさや場所、患者さんの希望などを考慮して決定します。顔など目立つ部位では、傷跡が目立ちにくいくり抜き法が選ばれることが多いですが、大きな粉瘤の場合は切開法が必要になることもあります。
手術は局所麻酔で行い、通常は日帰りで受けることができます。手術時間は10〜30分程度で、術後1〜2週間程度で抜糸を行います。

粉瘤の治療費はいくらかかる?
粉瘤の治療費は、健康保険が適用されるため、比較的リーズナブルに受けることができます。具体的な費用は、粉瘤の大きさや場所、治療方法によって異なります。
保険適用の場合の治療費目安
粉瘤の手術は保険診療として認められており、3割負担の場合、一般的な費用の目安は以下のとおりです:
- 露出部(顔や首など)
- 2cm未満:約5,000〜6,000円
- 2〜4cm:約11,000〜12,000円
- 4cm以上:約13,000〜14,000円
- 非露出部(背中や臀部など)
- 3cm未満:約4,000〜5,000円
- 3〜6cm:約10,000〜11,000円
- 6cm以上:約12,000〜13,000円
1割負担(高齢者など)の場合は、上記の約3分の1の費用となります。また、初診料や再診料、処方薬がある場合はその費用が別途かかります。
なお、美容目的と判断された場合や保険適用外の特殊な処置を希望する場合は、自費診療となり費用が高くなることがあります。
粉瘤の予防と日常生活での注意点
粉瘤の発生を完全に予防する確実な方法はありませんが、日常生活での注意点をいくつかご紹介します。
清潔を保つ
粉瘤は不潔によって発生するわけではありませんが、皮膚を清潔に保つことで炎症のリスクを減らすことができます。特に汗をかきやすい部位は、こまめに洗い、清潔なタオルでよく拭きましょう。
早期発見・早期治療
小さなしこりを見つけたら、早めに医療機関を受診しましょう。粉瘤は小さいうちに治療すれば、手術も簡単で、傷跡も目立ちにくくなります。
自己処置は避ける
粉瘤を自分で潰したり、針で穴を開けたりする自己処置は、感染や炎症のリスクを高めるため、絶対に避けてください。また、内容物が出ても袋状の構造物が残っていれば再発します。
気になるしこりがある場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。
まとめ:粉瘤は適切な治療で解決できる
粉瘤は日常的によく見られる良性の皮膚腫瘍で、適切な治療を受ければ完治が期待できる疾患です。放置すると大きくなったり、炎症を起こしたりする可能性があるため、早めの治療をおすすめします。
消化器内科クリニックでも粉瘤の治療に対応しているところが増えており、当院のような消化器内科・内視鏡クリニックでも日帰り手術を行っています。他の消化器疾患の検査や治療と合わせて対応できるメリットもあります。
皮膚のしこりや腫れに気づいたら、まずはかかりつけ医に相談し、適切な診療科を紹介してもらうとよいでしょう。粉瘤かどうかの診断と、最適な治療法の提案を受けることができます。
健康な肌を保つためにも、気になる症状があれば早めに医療機関を受診することをおすすめします。
詳しい情報や治療についてのご相談は、石川消化器内科・内視鏡クリニックまでお気軽にお問い合わせください。専門医による適切な診断と治療をご提供いたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院