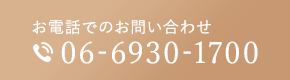痔の症状と種類〜放置するリスクを理解する
痔の症状に悩まされている方は少なくありません。「このまま放置しても大丈夫だろうか」「自然に治るのを待った方がいいのか」と迷われる方も多いでしょう。
痔は肛門の病気の総称で、主に「いぼ痔(痔核)」「切れ痔(裂肛)」「痔ろう」の3種類に分けられます。それぞれ症状や進行度によって治療法が異なるため、正しい知識を持つことが重要です。
痔の放置は思わぬリスクを伴います。軽度の症状であれば自然治癒する可能性もありますが、悪化すると日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、より深刻な病気を見逃す可能性もあるのです。
いぼ痔(痔核)の症状と進行度
いぼ痔は最も一般的な痔の症状で、肛門の内側にできる「内痔核」と外側にできる「外痔核」に分けられます。肛門の中間あたり、直腸粘膜と皮膚の境目を「歯状線」と言い、この内側にできるものを内痔核、外側にできるものを外痔核と呼びます。
内痔核は比較的痛みが少ないのが特徴です。主な症状は排便時の出血で、トイレットペーパーに付く程度から便器が赤くなるほどの出血まで様々です。進行すると排便時に肛門から飛び出す脱肛の症状が現れることもあります。
内痔核は進行度によって4段階に分類されます。
- 1度:いぼが常に歯状線の内側に留まっている段階。時々、出血や痛みがあります。
- 2度:排便時などのいきんだ拍子にいぼが歯状線の外側に出てしまい(脱肛)、その後自然に元に戻ります。
- 3度:排便時などにいぼが出て、自然には戻らず、指などで戻す必要があります。
- 4度:常にいぼが歯状線の外に出ている状態。さらに悪化すると「嵌頓痔核」となり、肛門周囲がひどく腫れ、強い痛みを伴います。
一方、外痔核は歯状線の外側にできるいぼ痔で、皮膚の上にできるため痛みを伴うことが多いです。急に腫れる「血栓性外痔核」は特に強い痛みを感じます。
切れ痔(裂肛)と痔ろうの症状
切れ痔は肛門の粘膜に傷ができる状態です。硬い便による排便時の痛みと出血が主な症状です。便秘や下痢を繰り返すことで悪化しやすく、慢性化すると治りにくくなります。
痔ろうは肛門腺という小さな腺から細菌が入り込み、炎症を起こして膿がたまる状態です。肛門周囲の皮膚に膿を出すためのトンネル(瘻管)ができ、そこから膿が出続けます。痔ろうは自然治癒がほとんど期待できず、放置すると悪化するため注意が必要です。
鮫島病院の鮫島隆志院長によると、「痔ろうは10年以上放置するとがん化した例があります。定年退職後にゆっくり治そうと放っておいた結果、がんになっていたということもある」とのことです。痔ろうの放置は非常に危険といえるでしょう。

痔は自然治癒する?医学的見解と現実
「痔は自然に治るのだろうか?」これは多くの患者さんが抱く疑問です。結論から言うと、痔の種類や進行度によって自然治癒の可能性は大きく異なります。
軽度のいぼ痔や切れ痔は、生活習慣の改善や適切なセルフケアによって症状が緩和し、自然治癒する可能性があります。しかし、進行した痔や痔ろうは自然治癒がほとんど期待できません。
痔の自然治癒に関して、いくつかの重要なポイントを見ていきましょう。
いぼ痔の自然治癒の可能性
いぼ痔(痔核)は初期段階であれば、適切なセルフケアによって症状が改善する可能性があります。特に1度から2度の内痔核は、生活習慣の改善(食物繊維の摂取増加、十分な水分補給、適度な運動など)によって症状が緩和することがあります。
しかし、3度以上に進行した内痔核や、強い痛みを伴う外痔核(特に血栓性外痔核)は、自然治癒を期待するのは難しいでしょう。これらの場合は専門的な治療が必要となります。
血栓性外痔核は、発症から48〜72時間以内であれば、専門医による切開排血処置で劇的に症状が改善することがあります。放置すると痛みは徐々に和らぐものの、いぼとして残ってしまう可能性があります。
切れ痔と痔ろうの自然治癒
切れ痔(裂肛)は初期であれば、便通の改善や局所的なケアによって自然治癒する可能性があります。しかし、慢性化すると肛門の括約筋が緊張して血流が悪くなり、治りにくくなります。
痔ろうに関しては、自然治癒はほとんど期待できません。所沢肛門病院の栗原浩幸院長によると、「痔ろうの患者さんには、複雑化する前に手術を勧めています。再発を繰り返すうちに膿が今までとは違う場所から出たりして複雑な形になることがあるからです」とのことです。
痔ろうは放置すると悪化するだけでなく、長期間(10年以上)の放置によってがん化するリスクもあります。このことからも、痔ろうは早期の専門的治療が必要といえるでしょう。
痔を放置するリスク〜見逃せない危険信号
痔の症状を放置することには、様々なリスクが伴います。特に注意すべきは、痔と似た症状を示す他の深刻な疾患を見逃してしまう可能性です。
出血や痛みといった症状は、大腸がんなどの重大な病気のサインである可能性もあります。札幌いしやま病院の石山元太郎理事長は「一番やってはいけないのが、何度も出血を繰り返しているのに勝手に痔だと思い込んで放置しておくことです。大腸がんのリスクもあるからです」と警告しています。
大腸がんとの見分け方と注意点
痔と大腸がんは症状が似ていることがあり、特に出血症状は両方に共通しています。松田病院の松田聡院長によると、「痔の手術をする前の患者さんに大腸カメラを施行すると約13%の人にポリープが見つかり、0.4%の人にがんが見つかる」とのことです。
以下のような症状がある場合は、痔だと自己判断せず、専門医の診察を受けることが重要です。
- 繰り返しの出血(特に1年以上続くもの)
- 便の形状の変化(細くなった、柔らかい便しか出ないなど)
- 排便習慣の変化(便秘や下痢が続くなど)
- 原因不明の体重減少や食欲不振
- 強い痛みや違和感が続く
岡崎外科消化器肛門クリニックの岡崎啓介院長は「おしりからの出血の場合、一番にがんを疑わなければなりません。安易におしりの病気と診断せず、まずはがんのリスクを疑い、そのリスクを消してあげることは、私たち医師の責任でもあります」と述べています。
痔ろうの放置による合併症
痔ろうを放置すると、膿瘍が広がり、複雑な瘻管(ろうかん)を形成することがあります。これにより手術が困難になるだけでなく、長期間の放置によってがん化するリスクもあります。
痔ろうは保存療法ではほとんど治癒せず、完治させるためには手術が必要です。早期に適切な治療を受けることで、より簡単な手術で済み、回復も早くなります。

痔の専門的治療法〜最新の選択肢
痔の症状が重い場合や自然治癒が期待できない場合は、専門的な治療が必要になります。現在では様々な治療法があり、症状や進行度に応じて最適な方法が選択されます。
ここでは、いぼ痔(痔核)と痔ろうの主な治療法について解説します。
いぼ痔の治療法
いぼ痔(痔核)の治療法は、症状の程度によって異なります。軽度から中等度の場合は保存的治療が選択されますが、重度の場合は手術が必要になることがあります。
主な治療法には以下のようなものがあります。
- 薬物療法:内服薬や外用薬を使用して、腫れ、痛み、出血などの症状を緩和します。薬物療法によってほとんどの症状は改善されますが、いぼそのものがなくなるわけではありません。
- ジオン注射(ALTA療法):痔核へと流れ込む血液の量を減らし、線維化させる薬剤を注射する治療です。「切らない内痔核治療」として注目されていますが、内痔核の治療にのみ適用されます。
- ゴム輪結紮療法:輪ゴムで痔核を結紮し、血流を断つことで痔核を脱落させます。簡便で痛みも少ないというメリットがありますが、術後の出血には注意が必要です。
- 結紮切除術:古くから行われている手術で、どのような痔核にも対応できます。痔核に栄養を届ける動脈を結紮(縛ること)し、痔核そのものを取り除きます。
石川消化器内科・内視鏡クリニックでは、痛みの少ないALTA療法を提供しており、2023年7月にはこの治療法がドクターズファイルに掲載されました。ALTA療法は切らずに治療できるため、患者さんの負担が少ないのが特徴です。
痔ろうの治療法
痔ろうの治療は基本的に手術が必要です。主な手術法には以下のようなものがあります。
- 従来の手術法:肛門内から肛門外の皮膚に貫通する膿が通るトンネル(瘻管)をくり抜き、輪ゴムを通して徐々に小さくしていく方法です。
- 括約筋温存術(LIFT手術など):近年各専門病院で行われている方法で、筋肉を全く切らない手術です。膿の管を糸で縛って膿の交通を遮断し、外側の筋肉と関係ないところだけをくり抜きます。
痔ろうの手術では、麻酔も重要なポイントです。札幌いしやま病院では「仙骨硬膜外麻酔」を使用しており、これにより麻酔自体の痛みが軽減され、患者さんの負担が少なくなるとのことです。
痔の自己管理と予防法〜再発を防ぐために
痔の症状を改善し、再発を防ぐためには、日常生活での自己管理が非常に重要です。特に生活習慣の改善は、軽度の痔の自然治癒を促すだけでなく、治療後の再発予防にも効果的です。
ここでは、痔の自己管理と予防のための具体的な方法を紹介します。
効果的な生活習慣の改善
痔の予防と改善に効果的な生活習慣の改善点には、以下のようなものがあります。
- 食物繊維の摂取:野菜、果物、全粒穀物などの食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取しましょう。食物繊維は便のかさを増し、柔らかくすることで排便を容易にします。
- 十分な水分補給:1日に1.5〜2リットルの水分を摂取することで、便が硬くなるのを防ぎます。特に食物繊維を増やす場合は、水分摂取も増やすことが重要です。
- 適度な運動:定期的な運動は腸の働きを活発にし、便秘の予防に役立ちます。ウォーキングや水泳など、無理のない運動を継続しましょう。
- トイレを我慢しない:便意を感じたらなるべく早くトイレに行きましょう。便意を我慢すると便が硬くなり、排便時に強くいきむ必要が生じます。
- 長時間のトイレ滞在を避ける:トイレで長時間座っていると、肛門周辺の血流が悪くなります。スマートフォンや本を読むなどの習慣は控えましょう。
- 適切な排便姿勢:膝を腰より高い位置に上げると、直腸と肛門の角度が自然になり、いきまずに排便しやすくなります。
これらの生活習慣の改善は、痔の症状を和らげるだけでなく、便秘や下痢といった痔の原因となる症状の改善にも効果的です。
市販薬の適切な使用法
軽度の痔の症状には、市販薬が効果的な場合があります。特に外痔核は、市販の軟膏タイプの薬を使用して自己治療できることもあります。
しかし、市販薬には以下のような注意点があります。
- 内痔核と外痔核では適切な薬剤が異なります。症状に合った薬を選びましょう。
- 市販薬で症状が改善しない場合や、2週間以上症状が続く場合は、専門医の診察を受けましょう。
- 出血が続く場合は、痔以外の病気の可能性もあるため、自己判断せず医療機関を受診しましょう。
市販薬はあくまで対症療法であり、根本的な治療ではありません。症状が重い場合や繰り返す場合は、専門医による適切な診断と治療が必要です。

痔の専門医を受診するタイミング〜見極めのポイント
痔の症状があるとき、「このくらいなら自然に治るだろう」と考えて放置してしまうことがありますが、適切なタイミングで専門医を受診することが重要です。
では、どのようなタイミングで医療機関を受診すべきでしょうか。ここでは、痔の種類別に受診の目安を紹介します。
内痔核・外痔核の受診目安
内痔核の場合、以下のような症状があれば医療機関を受診しましょう。
- 排便時に繰り返し出血がある
- 排便時にいぼが脱出し、自分で戻せない
- いぼが常に脱出したままになっている
- 市販薬を使用しても2週間以上症状が改善しない
- 痛みや違和感が強く、日常生活に支障がある
外痔核の場合は、以下のような症状があれば受診が必要です。
- 強い痛みを伴う腫れがある
- 腫れが急に大きくなった(血栓性外痔核の可能性)
- 市販薬を使用しても症状が改善しない
- 出血が続く
特に血栓性外痔核は、発症から48〜72時間以内に専門医による処置を受けると、痛みが劇的に改善することがあります。早めの受診が重要です。
切れ痔・痔ろうの受診目安
切れ痔(裂肛)の場合、以下のような症状があれば受診しましょう。
- 排便時に強い痛みがある
- 出血が続く
- 市販薬を使用しても症状が改善しない
- 慢性的に症状を繰り返す
痔ろうの場合は、以下のような症状があれば早急に受診が必要です。
- 肛門周囲に膿がたまり、痛みや腫れがある
- 肛門周囲の皮膚から膿や分泌物が出る
- 発熱や全身倦怠感がある
痔ろうは自然治癒がほとんど期待できないため、症状があれば早めに専門医を受診することが重要です。
まとめ〜痔の放置と専門治療の選択
痔の症状は多くの方が経験するものですが、放置することで悪化したり、より深刻な病気を見逃したりするリスクがあります。
軽度のいぼ痔や切れ痔は、生活習慣の改善や適切なセルフケアによって自然治癒する可能性もありますが、症状が重い場合や長期間続く場合は、専門医による適切な診断と治療が必要です。
特に注意すべきは、痔と似た症状を示す大腸がんなどの重大な疾患を見逃さないことです。繰り返しの出血や便の形状の変化などがある場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。
痔ろうに関しては、自然治癒はほとんど期待できず、放置することで複雑化したり、長期間の放置でがん化するリスクもあります。早期の専門的治療が重要です。
石川消化器内科・内視鏡クリニックでは、痛みの少ないALTA療法など、患者さんの負担を軽減する治療法を提供しています。痔の症状でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
痔の症状は恥ずかしいと感じて受診をためらう方も多いですが、早期の適切な治療によって症状の改善や合併症の予防が可能です。自分の健康のために、適切なタイミングで専門医を受診することをお勧めします。
当院では患者さんのプライバシーに配慮した診療を心がけておりますので、些細な症状でもお気軽にご相談ください。
詳しい情報や診療時間については、石川消化器内科・内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院