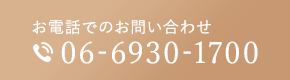消化器内科とはどのような診療科なのか
消化器内科は、食べ物の通り道である消化管(口から肛門まで)と、肝臓・胆のう・膵臓などの実質臓器に関する症状を診察・治療する診療科です。食道、胃、小腸、大腸といった消化管の病気から、肝臓、胆嚢、膵臓といった消化に関わる臓器の疾患まで幅広く対応しています。
消化器内科では、腹痛・吐き気・嘔吐・便秘・下痢・食欲不振・胸やけ・げっぷ・お腹の張りなどの症状を診ています。これらの症状が気になるときが、消化器内科を受診する目安となります。
風邪の症状である咳・鼻づまり・くしゃみなどは消化器の症状ではないため、消化器内科ではなく一般内科での受診をおすすめします。また、新型コロナウイルス感染症が疑われる発熱の場合も、発熱対応をしている内科を受診しましょう。

消化器内科を受診すべき主な症状
消化器内科を受診すべき症状は多岐にわたります。どのような症状があれば消化器内科を受診すべきか、具体的に見ていきましょう。
腹痛や胃痛は、消化器内科を受診する最も一般的な理由の一つです。みぞおちの痛みや下腹部痛など、お腹の痛み全般が対象となります。胃炎、胃潰瘍、腸炎、虫垂炎などが原因となることがあります。
特に痛みが強く、長時間続く場合や、痛みに加えて発熱や吐き気を伴う場合は、早めに受診することをおすすめします。
胃もたれや胸やけも消化器内科でよく診る症状です。胃が重苦しい、食後にもたれる感じ、胸やけがするといった症状は、逆流性食道炎や機能性ディスペプシア(消化不良)などが原因かもしれません。
下痢や便秘が続く場合も消化器内科の受診をおすすめします。ウイルス性腸炎から過敏性腸症候群まで様々な原因が考えられます。特に、普段と違う便通の変化が2週間以上続く場合は、一度専門医に相談しましょう。
吐き気・嘔吐は胃腸の不調による症状で、急性胃腸炎、食あたり、胃潰瘍の悪化などが原因として考えられます。特に嘔吐が激しく脱水症状がある場合や、嘔吐物に血液が混じる場合は早急に受診が必要です。
消化器内科で診断・治療できる主な疾患
消化器内科では様々な疾患の診断・治療を行っています。代表的なものをご紹介します。
食道の疾患
逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流することで起こる炎症です。胸やけや胸の痛み、喉の違和感などの症状が特徴的です。食道がんは早期発見が重要で、進行すると飲み込みにくさなどの症状が現れます。
食道裂孔ヘルニアは、胃の一部が横隔膜の食道裂孔を通って胸腔内に入り込む状態です。胸やけや胸痛の原因となることがあります。
胃の疾患
胃炎は胃の粘膜に炎症が起きる状態で、急性と慢性があります。ピロリ菌感染や薬剤、ストレスなどが原因となることが多いです。胃潰瘍は胃の粘膜や粘膜下層が損傷した状態で、みぞおちの痛みや胃もたれなどの症状が現れます。
機能性ディスペプシアは、胃もたれや胃の痛みなどの症状があるにもかかわらず、内視鏡検査などで器質的な異常が見つからない機能的な障害です。ストレスや生活習慣が関与していることが多いです。
胃がんは日本人に多いがんの一つで、早期発見・早期治療が重要です。初期には症状がないことも多く、定期的な検診が大切です。
腸の疾患
過敏性腸症候群は、腹痛と便通異常(下痢や便秘)を繰り返す機能性疾患です。ストレスや食事との関連が指摘されています。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)は、腸に慢性的な炎症が起こる疾患です。血便や腹痛、下痢などの症状が特徴的です。
大腸ポリープは大腸の粘膜から突出した隆起性病変で、多くは良性ですが、一部は大腸がんに進行する可能性があります。大腸がんは早期発見すれば内視鏡治療で完治することも多い疾患です。
肝臓・胆嚢・膵臓の疾患
消化器内科では、消化管だけでなく肝臓・胆嚢・膵臓の疾患も診療しています。
肝臓の疾患
肝炎はウイルス感染(B型・C型肝炎ウイルスなど)やアルコール、薬剤、脂肪の蓄積などによって肝臓に炎症が起こる疾患です。慢性化すると肝硬変や肝がんのリスクが高まります。
脂肪肝は肝臓に脂肪が蓄積した状態で、アルコールの過剰摂取や肥満、糖尿病などが原因となります。初期には自覚症状がほとんどありませんが、進行すると肝機能障害を引き起こすことがあります。
肝硬変は肝臓の線維化が進行した状態で、肝機能の低下や門脈圧亢進症による食道静脈瘤などの合併症を引き起こします。肝がんは肝細胞が悪性化したもので、肝硬変患者さんに発生することが多いです。

胆嚢・胆道の疾患
胆石症は胆嚢や胆管に結石ができる疾患です。右上腹部痛や背部痛、発熱などの症状が現れることがあります。胆嚢炎・胆管炎は胆石などが原因で胆嚢や胆管に炎症が起こる状態で、激しい腹痛や発熱、黄疸などの症状が現れます。
胆嚢ポリープは胆嚢内に生じる隆起性病変で、多くは良性ですが、大きさや形状によっては悪性の可能性もあります。胆道がん(胆嚢がん・胆管がん)は初期症状に乏しく、進行してから黄疸などの症状で発見されることが多いです。
膵臓の疾患
急性膵炎は膵酵素の活性化により膵臓自体が消化されて起こる急性炎症で、激しい腹痛や嘔吐などの症状が特徴です。慢性膵炎は膵臓の慢性的な炎症により、膵機能が徐々に低下していく疾患です。
膵がんは初期症状に乏しく、進行してから黄疸や腹痛などの症状が現れることが多い予後不良のがんです。早期発見が難しいため、リスク因子を持つ方は定期的な検査が重要です。
消化器内科での検査方法
消化器内科では様々な検査を行い、症状の原因を特定します。主な検査方法をご紹介します。
血液検査・尿検査
血液検査では、貧血・炎症反応・電解質バランス・腎機能・血糖値などの一般検査のほか、肝機能検査、肝炎ウイルス検査、ピロリ菌検査、がんの状態を調べる腫瘍マーカーなどを調べることができます。
尿検査では、尿中のビリルビンや尿ウロビリノーゲンなどを調べることで、肝臓や胆道系の異常を発見することができます。
内視鏡検査
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)は、口または鼻から内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸を直接観察する検査です。胃炎や逆流性食道炎、潰瘍、がん・ポリープなどの病変を発見することができます。
下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)は、肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体を観察する検査です。大腸ポリープや大腸がん、炎症性腸疾患などの診断に役立ちます。
小腸内視鏡検査(ダブルバルーン内視鏡、カプセル内視鏡)は、従来検査が難しかった小腸の観察を可能にした検査方法です。原因不明の消化管出血や小腸腫瘍の診断などに用いられます。
画像検査
腹部超音波検査(エコー)は、肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓などの臓器の状態を非侵襲的に観察できる検査です。脂肪肝や胆石、腫瘍などの診断に役立ちます。
CT検査は、X線を用いて体の断層画像を撮影する検査で、腹部全体の詳細な観察が可能です。腫瘍の有無や大きさ、周囲臓器との関係などを評価することができます。
MRI検査は、磁気を利用して体の断層画像を撮影する検査で、特に軟部組織の描出に優れています。MRCP(MR胆管膵管撮影)は、胆管や膵管の状態を非侵襲的に観察できる検査です。
消化器内科を受診する目安と注意点
消化器内科を受診すべきタイミングや、受診時の注意点についてご説明します。
受診を検討すべき症状と状況
次のような症状や状況がある場合は、消化器内科の受診を検討しましょう。
- 腹痛や胃痛が続く、または強い痛みがある
- 吐き気や嘔吐が続く、または嘔吐物に血液が混じる
- 胸やけや胃もたれが続く
- 便秘や下痢が2週間以上続く
- 便に血液が混じる、または黒い便が出る
- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)がある
- 原因不明の体重減少や食欲不振がある
- 健康診断で肝機能異常や便潜血陽性を指摘された
特に、以下のような緊急性の高い症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。
- 激しい腹痛が続く
- 吐血や下血がある
- 高熱を伴う腹痛がある
- 腹部が硬く張っている
- 意識障害や強い倦怠感がある
受診時の注意点
消化器内科を受診する際は、以下の点に注意しましょう。
まず、腹部の検査は基本的に空腹の状態で行うため、なるべく直前の食事は摂らないでください。特に腹痛や吐き気などのお腹の症状があって受診するときは、食事を摂らずに受診したほうがすぐに検査できる場合があります。
また、症状の詳細をメモしておくと診察がスムーズに進みます。いつから症状が始まったか、どのような状況で症状が出るか、痛みの場所や性質、食事との関連などを記録しておくと良いでしょう。
服用中の薬がある場合は、お薬手帳や薬の名前がわかるものを持参してください。特に胃薬や痛み止め、抗血栓薬(血液をサラサラにする薬)は消化器症状や検査に影響を与えることがあります。
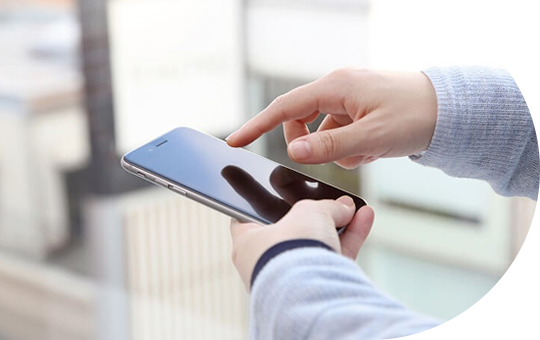
消化器内科での治療法
消化器内科では、症状や疾患に応じて様々な治療法が選択されます。主な治療法をご紹介します。
薬物療法
消化器疾患の多くは、まず薬物療法が行われます。胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬、H2ブロッカーなど)、胃腸の動きを整える薬(消化管運動改善薬)、腸の炎症を抑える薬(5-ASA製剤、ステロイド、免疫調節薬など)、肝機能を改善する薬(肝庇護薬)などが使用されます。
また、ウイルス性肝炎に対する抗ウイルス薬、ピロリ菌感染に対する除菌療法、がんに対する抗がん剤治療なども行われます。
内視鏡治療
内視鏡を用いた治療は、消化器内科の大きな特徴の一つです。早期の消化管がんに対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)や内視鏡的粘膜切除術(EMR)、大腸ポリープに対するポリペクトミーなどが行われます。
また、消化管出血に対する内視鏡的止血術、食道静脈瘤に対する内視鏡的結紮術、胆石や膵石に対する内視鏡的結石除去術、胆管・膵管狭窄に対するステント留置術なども行われます。
インターベンショナルラジオロジー
画像診断装置を用いて行う低侵襲治療も消化器疾患の治療に用いられます。肝がんに対するラジオ波焼灼療法(RFA)や肝動脈塞栓術(TAE)、膵がんなどによる閉塞性黄疸に対する経皮経肝胆道ドレナージ(PTBD)などが代表的です。
生活習慣の改善・食事療法
多くの消化器疾患は生活習慣と密接に関連しています。適切な食事、適度な運動、禁煙、節酒などの生活習慣の改善が治療の基本となることも少なくありません。
特に、逆流性食道炎や過敏性腸症候群、脂肪肝などは、生活習慣の改善だけで症状が軽減することもあります。医師や栄養士の指導のもと、疾患に応じた食事療法を行うことも重要です。

消化器疾患の予防と日常生活での注意点
消化器疾患を予防し、健康な消化器を維持するための日常生活での注意点をご紹介します。
バランスの良い食生活
消化器の健康を維持するためには、バランスの良い食生活が基本です。野菜、果物、全粒穀物などの食物繊維を十分に摂取し、脂肪や糖分の過剰摂取を避けましょう。
また、規則正しい食事時間を心がけ、よく噛んでゆっくり食べることも大切です。過食や早食いは消化器に負担をかけ、様々な症状の原因となります。
適度な運動習慣
適度な運動は、腸の蠕動運動を促進し、便秘の予防に役立ちます。また、肥満を防ぐことで、脂肪肝や胆石症などのリスクも低減できます。
ウォーキングやサイクリングなどの有酸素運動を週に3回以上、30分程度行うことを目標にしましょう。
アルコールと喫煙
過度のアルコール摂取は、肝臓や膵臓に大きな負担をかけます。アルコールは適量を守り、週に2日以上の休肝日を設けることをおすすめします。
喫煙は食道がんや胃がん、膵がんなどのリスク因子となります。禁煙することで、これらのがんのリスクを低減できます。
定期的な健康診断
消化器疾患、特にがんは早期発見が重要です。40歳以上の方は、年に1回の健康診断を受け、胃がん検診や大腸がん検診を定期的に受けることをおすすめします。
また、肝炎ウイルス検査やピロリ菌検査も、一度は受けておくと良いでしょう。
まとめ
消化器内科は、食道から肛門までの消化管と、肝臓・胆嚢・膵臓などの実質臓器に関する疾患を診療する診療科です。腹痛、胃もたれ、下痢、便秘など、日常生活でよく経験する症状の多くが消化器内科の受診対象となります。
消化器疾患は早期発見・早期治療が重要です。特に、長引く症状や、血便、黄疸、急激な体重減少などの警告症状がある場合は、すぐに消化器内科を受診しましょう。
当院では、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の内視鏡検査を提供しており、「辛い・苦しい」というイメージのある胃カメラ・大腸カメラ検査を「より気軽に」「よりスピーディーに」、そして安心して受けていただける体制を整えています。
また、高性能な拡大内視鏡を導入し、特殊な光によって粘膜の微細な変化まで観察できる大学病院レベルの検査が可能です。患者様の利便性を考慮し、初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しています。
消化器の健康は全身の健康につながります。気になる症状があれば、お気軽に石川消化器内科・内視鏡クリニックにご相談ください。
詳細な情報や予約方法については、石川消化器内科・内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。皆様の健康管理を誠心誠意サポートいたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院