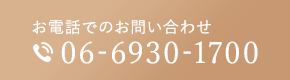慢性便秘とは?症状と定義を正しく理解する
便秘は多くの方が一度は経験したことのある症状です。しかし、「何日間排便がないと便秘なのか」という明確な基準はありません。
慢性便秘症は「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態が長期間続くこと」と定義されています。単に排便回数が少ないだけでなく、排便時の苦痛や残便感なども重要な症状です。
便秘の三大症状は「排便回数の減少」「排便困難感」「残便感」です。これらの症状が1ヶ月以上続く場合は、慢性便秘症を疑う必要があります。
国民生活基礎調査によると、便秘に悩む方の割合は男性2.5%、女性4.6%とされています。20~60歳では女性に多く、60歳以降は男女とも加齢に伴って増加する傾向があります。
便秘は「たかが便秘」と軽視されがちですが、重症化すれば腸閉塞や腸穿孔といった深刻な合併症を引き起こすこともあります。また、大腸がんや心疾患、脳卒中との関連も指摘されており、適切な治療が重要です。

便秘の種類と原因を知り、自分のタイプを見極める
便秘には大きく分けて4つのタイプがあります。自分がどのタイプに当てはまるかを知ることで、適切な治療法を選択できます。
便秘の種類は大きく「機能性便秘」「器質性便秘」「薬剤性便秘」「その他の原因による便秘」に分類されます。それぞれの特徴と原因を詳しく見ていきましょう。
機能性便秘の特徴と原因
最も多いのが「機能性便秘」です。これは大腸や直腸の働きに異常が生じるタイプの便秘で、さらに3つのサブタイプに分けられます。
弛緩性便秘は、大腸を動かす筋肉がゆるみ、腸の蠕動運動が弱くなることで便が停滞するタイプです。生活習慣の乱れや加齢が主な原因とされています。
痙攣性便秘は、大腸の蠕動運動が不規則になることで起こります。ストレスが大きく関与していると考えられています。
直腸性便秘は、便意を習慣的に我慢することで直腸の神経の働きが弱くなり、便意を感じにくくなるタイプです。女性や温水洗浄便座の水を肛門の奥まで入れてしまう方に多く見られます。
器質性便秘と薬剤性便秘
器質性便秘は、大腸がんや手術後の癒着、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患によって、大腸内の便の通過が物理的に妨げられることで起こります。
薬剤性便秘は、服用している薬の副作用によって起こる便秘です。喘息や頻尿、パーキンソン病の治療薬、抗うつ薬、抗コリン薬、咳止めなどには腸の動きを鈍くする副作用があります。
女性に便秘が多い理由
女性に便秘が多い理由は主に3つあります。
1つ目は筋力の低下です。男性に比べて排便に必要な括約筋や腹筋の力が弱いため、特に女性は骨盤が広く腸が下方に垂れ下がりやすいという解剖学的特徴があります。
2つ目はダイエットの影響です。食事量が少なくなると、腸の蠕動運動が低下します。
3つ目はホルモンの影響です。黄体ホルモン(プロゲステロン)は腸の蠕動運動を抑制し、水分・塩分の吸収を促進するため、月経前や妊娠中に便秘になりやすくなります。
便秘が引き起こす健康リスクと合併症
便秘は単なる不快な症状ではなく、放置すると様々な健康リスクを引き起こす可能性があります。
慢性的な便秘は腸内環境の悪化を招き、腸内細菌のバランスが崩れることで様々な健康問題につながります。便秘が長期間続くと、どのような合併症のリスクが高まるのでしょうか。
便秘が重症化すると、腸閉塞や腸穿孔といった命に関わる合併症を引き起こす可能性があります。また、排便時に強くいきむことで痔や裂肛、直腸脱などの肛門疾患のリスクも高まります。
さらに、便秘の方は大腸がんのリスクが高まることが研究で明らかになっています。全国を対象とした大規模コホート研究(JACC Study)によると、女性の場合、6日以上の便秘では、2~3日おきに排便がある方と比べて、大腸がんのリスクが2.5倍高くなるという結果が報告されています。
便秘は心疾患や脳卒中との関連も指摘されており、予後にも影響を及ぼすことがわかっています。快便の方が長生きするという研究結果もあります。
これらの研究結果からも、便秘は単なる不快な症状ではなく、全身の健康に影響を与える重要な問題であることがわかります。適切な治療を行い、健康的な腸内環境を維持することが大切です。
消化器内科での便秘の検査方法
便秘の原因を特定するためには、適切な検査が必要です。消化器内科では、どのような検査を行うのでしょうか。
便秘の検査は、まず問診から始まります。排便の頻度や便の性状、排便時の症状、生活習慣、服用中の薬剤などを詳しく聞き取ります。その上で、必要に応じて以下の検査を行います。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)
便秘を引き起こす最も重要な疾患の一つが大腸がんです。大腸カメラを一度も受けたことがない方には、まず大腸カメラ検査をお勧めしています。
当院では鎮静剤を使用した無痛の大腸カメラ検査を行っています。眠っている間に検査を行うため、痛みや不快感をほとんど感じることなく検査を受けることができます。
大腸カメラでは、大腸がんやポリープだけでなく、炎症性腸疾患や虚血性大腸炎などの便秘の原因となる疾患を直接観察することができます。必要に応じて組織を採取し、詳しい検査を行うこともあります。
腹部レントゲン検査
腹部レントゲンでは、大腸のどこに便が貯まっているかを確認することができます。便秘のタイプによって治療方針が異なるため、便の貯留部位を知ることは重要です。
例えば、S状結腸や直腸に便が多く貯まっている場合は直腸性便秘の可能性が高く、上行結腸から下行結腸にかけて便が広く分布している場合は弛緩性便秘の可能性が考えられます。
排便造影検査と直腸肛門内圧検査
排便時の問題を詳しく調べるために、排便造影検査や直腸肛門内圧検査を行うこともあります。
排便造影検査では、バリウムを直腸に注入し、排便時のX線撮影を行います。これにより、直腸瘤や直腸脱、骨盤底筋協調運動障害などの診断が可能です。
直腸肛門内圧検査では、肛門括約筋の圧力や直腸感覚閾値を測定します。これにより、排便障害のメカニズムを詳しく調べることができます。
これらの検査結果に基づいて、便秘のタイプを正確に診断し、最適な治療法を選択します。
便秘の内科的治療法と最新薬物療法
便秘の治療は、症状の程度や原因によって異なります。ここでは、消化器内科で行われる便秘の内科的治療法について解説します。
便秘治療の目的は、単に排便回数を増やすだけでなく、排便時の苦痛や残便感を改善し、患者さんのQOL(生活の質)を向上させることです。
生活習慣の改善と食事療法
便秘治療の基本は生活習慣の改善です。適度な運動やお腹のマッサージが便秘改善に効果的であることが報告されています。
食物繊維の推奨摂取量は1日20g以上ですが、現代の日本人の平均摂取量は15g程度と不足しています。食物繊維は便のかさを増やし排便を促進しますが、摂りすぎるとかえって便秘を悪化させることもあるため注意が必要です。
水分摂取も重要です。1日に1.5〜2リットルの水分を摂ることで、便を柔らかく保ち排便を促進します。
また、朝食を摂ることで胃結腸反射を促し、大腸の蠕動運動を活発にすることができます。朝食後にトイレに行く習慣をつけることも効果的です。
便秘治療薬の種類と特徴
生活習慣の改善だけでは効果が不十分な場合は、薬物療法を行います。便秘治療薬には大きく分けて以下の種類があります。
浸透圧性下剤は、腸管内に水分を引き込むことで便を軟らかくし、排便を促進します。代表的なものに酸化マグネシウムがあります。日本で古くから使用されており、大腸通過時間を短縮し、便回数や便形状を改善する効果が研究で確認されています。
刺激性下剤は、腸の蠕動運動を直接刺激します。センナやピコスルファートナトリウムなどがありますが、長期使用すると耐性が生じる可能性があります。
近年では新しいタイプの便秘治療薬も登場しています。粘膜上皮機能変容薬(ルビプロストン、リナクロチド)は腸管内の水分分泌を促進し、胆汁酸トランスポーター阻害薬(エロビキシバット)は胆汁酸の再吸収を阻害することで大腸の蠕動運動を促進します。
これらの新薬は従来の下剤とは異なるメカニズムで作用するため、従来の治療で効果が不十分だった方にも効果が期待できます。
難治性便秘への対応
一般的な治療で改善しない難治性便秘の場合は、より専門的な治療が必要になります。
バイオフィードバック療法は、直腸肛門協調運動障害による便秘に効果的です。排便時の筋肉の使い方を視覚的に確認しながら、正しい排便法を学びます。
また、浣腸や坐薬、摘便などの対症療法も状況に応じて行います。重症例では逆行性洗腸法を行うこともあります。
薬物療法では、複数の薬剤を組み合わせることで効果を高めることもあります。例えば、浸透圧性下剤と刺激性下剤の併用や、新薬と従来薬の併用などです。
どのような治療法を選択するかは、便秘のタイプや重症度、患者さんの状態によって異なります。消化器内科専門医による適切な診断と治療が重要です。
便秘と大腸がんの関係性
便秘と大腸がんの関係については、多くの研究が行われています。便秘が大腸がんのリスク因子となる可能性があることがわかってきました。
便秘が続くと、腸内に便が長時間滞留することになります。この状態が続くと、便に含まれる発がん物質と腸粘膜の接触時間が長くなり、大腸がんのリスクが高まる可能性があります。
1988年から20年以上かけて行われた全国規模の大規模コホート研究(JACC Study)では、排便頻度と大腸がんの関連が調査されました。その結果、女性の場合、6日以上便秘が続く方は、2〜3日おきに排便がある方と比べて、大腸がんのリスクが2.5倍高くなることが明らかになりました。
便秘と大腸がんの関連については、まだ研究段階の部分もありますが、長期間の便秘は大腸がんのリスク因子となる可能性が高いと考えられています。
特に、便秘に加えて、血便や体重減少、貧血などの症状がある場合は、大腸がんの可能性を考慮して早急に消化器内科を受診することをお勧めします。
当院では、便秘の症状がある方に対して、必要に応じて大腸カメラ検査を行い、大腸がんやポリープの早期発見・早期治療に努めています。鎮静剤を使用した無痛の大腸カメラ検査を行っていますので、検査への不安や恐怖感を最小限に抑えることができます。
便秘外来を受診するタイミングと準備
便秘の症状があるとき、どのようなタイミングで医療機関を受診すべきでしょうか。また、受診の際にはどのような準備をしておくと良いでしょうか。
便秘は1週間程度であれば様子を見ても良いとされていますが、以下のような場合は消化器内科の受診をお勧めします。
・便が出ない、あるいは便が出てもすっきりしない状態が1ヶ月以上続く場合
・市販の便秘薬を使っても効果がない、または効果が徐々に弱くなってきた場合
・便秘に加えて、血便、腹痛、発熱、体重減少などの症状がある場合
・50歳以上で便通の変化がある場合(大腸がんのリスクが高まるため)
・便秘が急に始まり、以前とは排便パターンが明らかに変わった場合
受診前の準備と問診のポイント
便秘外来を受診する際は、以下の情報を整理しておくと診察がスムーズに進みます。
・便秘の期間(いつから続いているか)
・排便の頻度と便の性状(ブリストル便形状スケールを参考に)
・排便時の症状(いきみ、痛み、残便感など)
・現在服用中の薬(便秘を引き起こす可能性のある薬もあります)
・これまでに試した便秘対策とその効果
・食事内容や水分摂取量、運動習慣などの生活習慣
・家族歴(特に大腸がんや炎症性腸疾患など)
これらの情報を事前にメモしておくと、医師に正確に伝えることができます。
当院での便秘治療の特徴
当院では、消化器・内視鏡専門医である院長が全ての診察、検査、検査結果説明を担当しています。便秘の症状一つひとつに丁寧に向き合い、患者さん一人ひとりに最適な治療法を提案しています。
便秘の検査では、必要に応じて大腸カメラ検査を行います。当院では鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の大腸カメラ検査を提供しており、半分眠ったような状態で検査を受けることができます。「辛い・苦しい」というイメージがある大腸カメラ検査のハードルを下げ、患者さんの負担を軽減しています。
また、高性能な拡大内視鏡を導入しており、特殊な光によって粘膜の微細な変化まで観察できる大学病院レベルの検査が可能です。初診当日の検査や土曜日の検査にも対応しており、お忙しい方でも安心して検査を受けていただけます。
便秘治療では、生活習慣の改善から薬物療法まで、便秘のタイプや重症度に応じた最適な治療を提供しています。新しい便秘治療薬も積極的に取り入れ、従来の治療で効果が不十分だった方にも効果的な治療を提案しています。

まとめ:便秘治療で生活の質を向上させよう
慢性便秘症は「たかが便秘」と軽視されがちですが、適切な治療を行わないと様々な健康リスクを引き起こす可能性があります。
便秘の種類は大きく「機能性便秘」「器質性便秘」「薬剤性便秘」に分類され、それぞれ原因と治療法が異なります。自分の便秘のタイプを知ることが、効果的な治療の第一歩です。
便秘の治療は、生活習慣の改善から始まります。適度な運動、十分な水分摂取、食物繊維の適切な摂取などが基本です。それでも改善しない場合は、浸透圧性下剤や刺激性下剤、新しいタイプの便秘治療薬などの薬物療法を行います。
便秘が1ヶ月以上続く場合や、市販薬で効果がない場合、血便や腹痛などの症状を伴う場合は、消化器内科の受診をお勧めします。特に50歳以上の方は、大腸がんのリスクも考慮して、一度大腸カメラ検査を受けることが重要です。
当院では、消化器・内視鏡専門医による丁寧な診察と、鎮静剤を使用した無痛の大腸カメラ検査を提供しています。便秘でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
便秘を根本から改善することで、腸内環境が整い、全身の健康状態も向上します。快適な排便習慣を取り戻し、生活の質を高めましょう。
詳しい情報や診療予約については、石川消化器内科・内視鏡クリニックのホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。皆様の健康管理を誠心誠意サポートいたします。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院