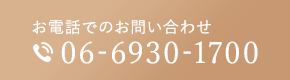大腸がん検診の重要性と現状
大腸がんは現在、日本人がかかるがんの中で最も罹患数が多く、年間15万人以上が診断されています。40年前と比較すると約6倍にまで増加しており、男性では前立腺がんに次いで第2位、女性では乳がんに次いで第2位の罹患率となっています。
さらに深刻なのは、大腸がんによる死亡者数です。毎年約5万人が大腸がんで命を落としており、男性では肺がんに次いで第2位、女性では死亡原因のがんとしては第1位となっています。
この増加の主な原因は、日本人の食生活の欧米化です。高脂肪の食品、特に牛肉・豚肉などの摂取量増加が大きく影響していると考えられています。女性の場合は、便秘による腸内環境の悪化も大腸がんリスクを高める要因として指摘されています。
大腸がんの怖さは、進行するまでほとんど自覚症状がないことです。早期発見できれば完治も十分可能ながんですが、症状が現れた時にはすでに進行している場合も少なくありません。だからこそ、定期的な検診が非常に重要なのです。

大腸がんの基礎知識と検診の必要性
大腸は、食べ物が通る順に「盲腸」、「上行結腸」、「横行結腸」、「下行結腸」、「S状結腸」、「直腸」に分けられます。「盲腸」から「S状結腸」までにできるがんを「結腸がん」、「直腸」にできるがんを「直腸がん」と呼び、これらを合わせて「大腸がん」と総称しています。
大腸がんは進行するまで明確な自覚症状がないことが特徴です。進行すると血便、便秘、下痢、貧血、腹痛、嘔吐などの症状が現れます。また、便が細くなった、便が残っている感じがするといった症状を訴える患者さんもいます。
がんは正常な組織ではないため出血しやすく、大腸にできたがんから出血すると、便に血液が付着して血便になったり、下血や貧血を起こすことがあります。また、がんが大きくなって便が通りにくくなると、便秘や下痢、腹痛などの症状が現れることもあります。
どうですか?心当たりはありませんか?
しかし、これらの症状は大腸がんが進行してから現れることが多いのです。早期発見・早期治療のためには、症状が出る前の定期的な検診が不可欠です。40歳以上の方は、年に1回の大腸がん検診を受けることが推奨されています。

大腸がん検診の種類と特徴
大腸がん検診には様々な種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った検査方法を選ぶことが大切です。ここでは主な検査方法について詳しく解説します。
便潜血検査(一次検診)
便潜血検査は、最も一般的な大腸がん検診の方法です。2日分の便を採取し、便に混じった血液(肉眼では見えない微量の血液)を検出する検査です。がんやポリープなどの大腸疾患があると大腸内に出血することがあり、その血液を検出します。
この検査は簡便で、痛みもなく、特別な準備も必要ありません。国が推奨する対策型検診として、40歳以上の方に年1回の受診が推奨されています。費用も比較的安価で、自治体によっては無料で受けられる場合もあります。
ただし、便潜血検査には限界もあります。がんやポリープが常に出血しているわけではないため、検査のタイミングによっては見逃す可能性があります。また、痔などの他の原因で血液が混じることもあるため、陽性結果が出ても必ずしもがんとは限りません。
便潜血検査で陽性結果が出た場合は、必ず精密検査(大腸内視鏡検査など)を受ける必要があります。ここで重要なのは、便潜血検査を再度受けることは精密検査の代わりにはならないということです。1日分でも陽性であれば、精密検査を受けましょう。
大腸内視鏡検査(精密検査)
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)は、大腸がんの精密検査として最も精度が高い検査です。下剤で大腸を空にした後に肛門から内視鏡を挿入して、直腸から盲腸までの大腸全体を観察します。
この検査の最大の利点は、がんやポリープを直接目で見て確認できることです。さらに、検査中に組織を採取(生検)したり、小さなポリープであれば切除することも可能です。ポリープを切除することで、将来がんになる可能性のある前がん病変を取り除くことができます。
一方で、大腸内視鏡検査には以下のような短所もあります。検査前の食事制限や下剤による腸管洗浄が必要で、身体的・精神的負担が大きいこと。検査時間が20〜30分と比較的長く、内視鏡挿入時に痛みや不快感を伴うことがあります。また、まれに出血や穿孔(腸に穴が開く)などの合併症が起こる可能性もあります。
当院では、このような負担を軽減するために、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の大腸内視鏡検査を提供しています。半分眠ったような状態で検査を受けることができるため、痛みや恐怖をほとんど感じることなく検査を受けることが可能です。
大腸CT検査(CTコロノグラフィー)
大腸CT検査(CTコロノグラフィー)は、比較的新しい大腸がん検査方法です。大腸に炭酸ガスを注入し腸管を膨らませた状態でCT撮影を行い、3次元画像を作成して大腸の病気を診断します。
大腸内視鏡検査に比べて飲用する下剤量が少なく、体への負担が少ないのが特徴です。また、検査時間も約10〜15分と短時間で済みます。腹部の手術歴から癒着があり大腸カメラが入りにくい方や、痛みが心配で内視鏡検査を受ける決心がつかない方におすすめです。
さらに、大腸の診断だけでなく、CT装置で腹部全体を撮影するため、肝臓、膵臓、胆のう、腎臓、子宮、卵巣、前立腺などの腹部臓器も同時に診断できる利点があります。
ただし、この検査にも限界があります。組織の採取ができないため、異常が検出された場合は大腸内視鏡検査を受ける必要があります。また、病変の色や硬さの情報は得られず、平坦な病変や5mm以下の小さなポリープは検出しにくいという欠点もあります。X線を使用するため、妊娠の可能性のある方は受けることができません。

大腸がん検診の選び方と受け方
大腸がん検診を選ぶ際には、自分の状況や希望に合わせて最適な検査方法を選ぶことが大切です。以下に、検診の選び方と受け方についてのポイントをまとめました。
年齢と受診頻度
大腸がん検診は、40歳以上の方に年1回の受診が推奨されています。特に、大腸がんの家族歴がある方や、大腸ポリープの既往がある方は、より早期からの定期的な検診が重要です。
国が推奨する対策型検診では、40歳以上の方に対して便潜血検査を年1回実施することが基本となっています。便潜血検査で陽性となった場合は、必ず精密検査を受けることが重要です。
検診を受けたことがない方は、まず便潜血検査から始めるのが一般的です。ただし、より精度の高い検査を希望する場合や、大腸がんのリスクが高い方は、最初から大腸内視鏡検査や大腸CT検査を選択することも考えられます。
検診施設の選び方
大腸がん検診を受ける施設を選ぶ際には、以下のポイントを考慮するとよいでしょう。
便潜血検査については、勤務先で大腸がん検診があればそれを利用するとよいでしょう。それ以外の方は、40歳以上であれば市区町村で検診を受けられます。自己負担額は自治体によって異なりますが、無料から500円程度のところが多いようです。
大腸内視鏡検査を受ける場合は、経験豊かな医師による検査を受けることが重要です。見落としが少なく、精度の高い検診が受けられるだけでなく、検査時の苦痛も軽減される可能性が高くなります。
医療機関を選ぶ際のチェックポイントとしては、大腸内視鏡検査の実施件数やポリープ・早期がんの切除件数などを公表しているところ、拡大内視鏡の設備がある医療機関などが挙げられます。これらの情報はホームページで確認したり、医療機関に直接問い合わせたりして調べることができます。
当院では、消化器・内視鏡専門医である私が全ての診察、検査、検査結果説明までを担当しています。高性能な拡大内視鏡を導入しており、特殊な光によって粘膜の微細な変化まで観察できる大学病院レベルの検査が可能です。また、鎮静剤を使用した無痛の内視鏡検査を提供しており、患者さんの負担を最小限に抑えることを心がけています。
検査前の準備と注意点
便潜血検査は特別な準備は必要ありませんが、大腸内視鏡検査や大腸CT検査では、検査前の食事制限や下剤による腸管洗浄が必要です。
大腸内視鏡検査の場合、通常は検査前日の夕食は消化の良いものを摂り、検査当日は絶食となります。また、検査前日の夜と当日の朝に下剤を服用して腸内をきれいにします。
大腸CT検査では、大腸内視鏡検査よりも下剤の量が少なく済む場合が多いですが、やはり検査前の食事制限や下剤の服用は必要です。検査前日に消化の良い専用の検査食をとり、少量のバリウムを飲んで残便を白く色付けし、就寝前に少量の下剤を飲むという流れが一般的です。
いずれの検査も、事前に医療機関から詳しい説明と指示があります。不安なことや分からないことがあれば、遠慮なく医療機関に相談しましょう。

大腸がん検診の費用と保険適用
大腸がん検診の費用は、検査方法や受診する医療機関、自治体の助成制度などによって異なります。ここでは、各検査方法の一般的な費用と保険適用の有無について解説します。
便潜血検査の費用
便潜血検査は比較的安価で、自治体の住民検診として受ける場合は、無料から500円程度のところが多いです。横浜市では令和7年度は無料で受けられるようです。職場の健康診断の一環として受ける場合も、多くは無料または低額で受けられます。
医療機関で自費で受ける場合でも、1,000円〜2,000円程度で受けられることが多いです。
大腸内視鏡検査の費用
大腸内視鏡検査の費用は、検診として受ける場合と保険診療として受ける場合で大きく異なります。
検診として自費で受ける場合は、医療機関にもよりますが、2万円〜3万円程度かかることが一般的です。ただし、検査中にポリープや早期がんが見つかって内視鏡で切除した場合には、保険診療に切り替わります。
一方、便潜血検査で陽性となり、精密検査として大腸内視鏡検査を受ける場合や、血便などの症状があって診察を受ける場合は、保険診療となります。この場合、3割負担の方で5,000円〜1万円程度の自己負担となることが多いです。
大腸CT検査の費用
大腸CT検査(CTコロノグラフィー)の費用も、医療機関によって異なりますが、検診として自費で受ける場合は2万円〜4万円程度かかることが多いです。
便潜血検査陽性後の精密検査として受ける場合でも、現時点では大腸CT検査は保険適用外の検査であることが多く、自費負担となる場合がほとんどです。ただし、医療機関によっては保険適用となる場合もありますので、事前に確認するとよいでしょう。
助成制度の活用
大腸がん検診には、様々な助成制度があります。自治体の住民検診では、対象年齢の方は低額または無料で便潜血検査を受けられます。また、年齢によっては無料クーポンが配布される場合もあります。
横浜市の場合、70歳以上の方は無料で大腸がん検診を受けられるようです。また、精密検査費用の助成制度もあるようです。
職場の健康保険組合によっては、人間ドックや各種がん検診の費用補助を行っているところもあります。自分が加入している健康保険組合の制度を確認してみるとよいでしょう。

大腸がん検診で異常が見つかった場合の対応
大腸がん検診で異常が見つかった場合、適切な対応をすることが重要です。ここでは、検査結果ごとの対応方法について解説します。
便潜血検査で陽性となった場合
便潜血検査で「陽性」と判定された場合は、必ず精密検査を受ける必要があります。便潜血検査は、大腸がんの可能性を示唆するスクリーニング検査であり、陽性だからといって必ずしもがんであるとは限りません。しかし、がんの可能性を否定できないため、精密検査が必要なのです。
ここで重要なのは、便潜血検査を再度受けることは精密検査の代わりにはならないということです。大腸がんは毎日出血しているわけではありませんので、1日分でも便潜血検査陽性となったら精密検査を受ける必要があります。
また、もともと痔がある場合でも、痔が原因で出血しているのか、あるいは大腸がんやポリープのために出血しているのかは精密検査をしないと分かりません。自己判断をせずに、必ず精密検査を受けましょう。
大腸内視鏡検査でポリープが見つかった場合
大腸内視鏡検査でポリープが見つかった場合、その大きさや形状、場所などによって対応が異なります。
小さなポリープ(5mm以下)で数が少ない場合は、その場で切除することもありますし、経過観察となることもあります。一方、大きなポリープや数が多い場合は、別日に改めてポリープ切除の処置を行うことがあります。
ポリープを切除した場合は、その組織を病理検査に提出し、がん細胞が含まれているかどうかを調べます。結果によって、その後の治療方針が決まります。
当院では、日帰りでの大腸ポリープ切除にも対応しています。患者さんの負担を最小限に抑えながら、適切な治療を提供できるよう努めています。
大腸がんと診断された場合
大腸内視鏡検査や組織検査の結果、大腸がんと診断された場合は、がんの進行度(ステージ)を確認するための追加検査が必要になります。CT検査やMRI検査などを行い、がんの大きさや深さ、リンパ節転移や他臓器への転移の有無などを調べます。
これらの検査結果をもとに、手術、内視鏡治療、化学療法(抗がん剤治療)、放射線治療などの中から最適な治療方法を選択します。治療方針は、がんの進行度だけでなく、患者さんの年齢や全身状態、希望なども考慮して決定します。
大腸がんと診断されても、早期であれば内視鏡治療だけで完治する可能性も高いです。早期発見・早期治療が何よりも重要なのです。

まとめ:大腸がん検診で早期発見を目指そう
大腸がんは日本人がかかるがんの中で最も罹患数が多く、女性のがん死亡原因の第1位、男性では第2位となっています。しかし、早期に発見できれば完治も十分可能ながんです。
大腸がんの怖さは、進行するまでほとんど自覚症状がないことです。そのため、定期的な検診が非常に重要となります。40歳以上の方は、年に1回の大腸がん検診を受けることが推奨されています。
大腸がん検診には、便潜血検査、大腸内視鏡検査、大腸CT検査などの方法があります。それぞれに特徴があり、自分の状況や希望に合わせて最適な検査方法を選ぶことが大切です。
便潜血検査は簡便で負担が少なく、スクリーニング検査として適しています。陽性となった場合は、必ず精密検査を受けることが重要です。
大腸内視鏡検査は精度が高く、ポリープの切除も同時に行えますが、検査前の準備や検査時の負担が大きいという短所もあります。当院では、鎮静剤を使用した無痛の大腸内視鏡検査を提供し、患者さんの負担軽減に努めています。
大腸CT検査は、大腸内視鏡検査に比べて負担が少なく、短時間で検査が完了するという利点がありますが、組織の採取ができないという限界もあります。
いずれの検査方法を選ぶにしても、定期的に検診を受けることが何よりも重要です。「辛い・苦しい」というイメージから検診を避けるのではなく、早期発見・早期治療のために、ぜひ定期的な検診を心がけてください。
当院では、患者さんの負担を最小限に抑えながら、高精度の検査を提供できるよう様々な工夫を行っています。大腸がん検診についてご不明な点やご不安な点がありましたら、お気軽に当院までご相談ください。皆様の健康を守るために、誠心誠意サポートさせていただきます。
詳細は石川消化器内科・内視鏡クリニックのホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院