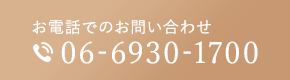ピロリ菌とは?感染経路と胃への影響
ピロリ菌は正式名称をヘリコバクター・ピロリといい、胃の粘膜に生息するらせん形の細菌です。通常、胃の中は強い酸性環境のため細菌が生存できないのですが、ピロリ菌は「ウレアーゼ」という特殊な酵素を持っています。
この酵素によって胃酸を中和し、自らの周りをアルカリ性環境に変えることで生き延びる特殊な能力を持っているのです。まさに胃の中で生き抜くために進化した細菌といえるでしょう。
ピロリ菌の感染経路はまだ完全には解明されていませんが、主に口を介した感染(経口感染)と考えられています。特に幼少期に感染するケースが多く、上下水道が十分に整備されていなかった時代に育った世代ほど感染率が高い傾向にあります。
ピロリ菌に感染すると、胃の粘膜に炎症が起こります。この炎症が長期間続くと慢性胃炎へと進行し、医学的には「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」と呼ばれる状態になります。
さらに長期間にわたって炎症が続くと、胃粘膜の萎縮や腸上皮化生といった変化が生じ、一部の方では胃がんへと発展するリスクが高まります。
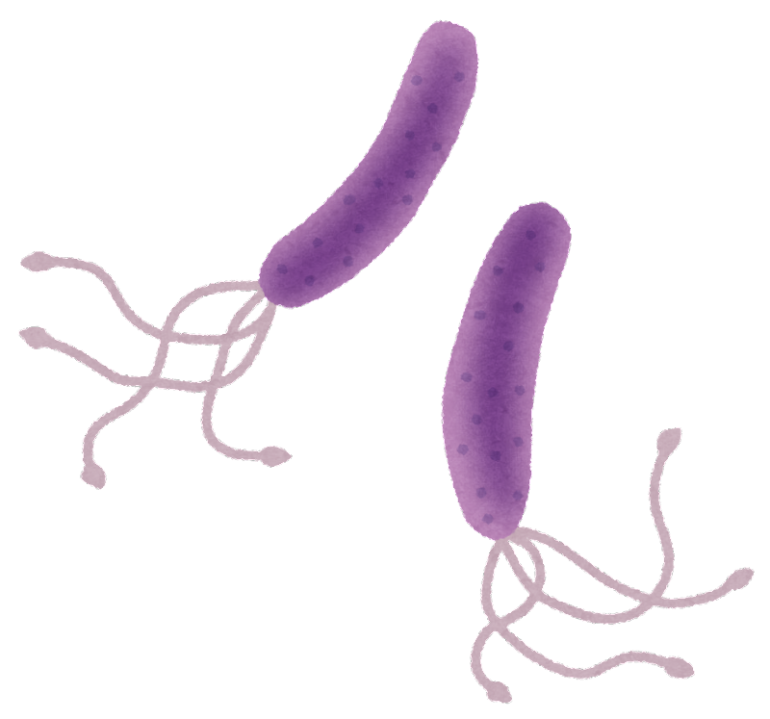
ピロリ菌が引き起こす病気とリスク
ピロリ菌感染が長期間続くと、様々な胃の病気を引き起こすリスクが高まります。特に注目すべきは、胃がんとの関連性です。
日本人のピロリ菌感染者は約3,500万人と推定されており、多くの方が自覚症状のないまま感染している状態です。ピロリ菌に感染している方が85歳までに胃がんに罹患する確率は、男性で約17%、女性で7.7%と報告されています。一方、非感染者ではそれぞれ1.0%、0.5%と大きな差があるのです。
ピロリ菌は胃がん以外にも、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の発症・再発と密接に関連しています。潰瘍患者さんのピロリ菌感染率は80〜90%と非常に高いことが分かっています。
また、胃MALTリンパ腫や特発性血小板減少性紫斑病など、胃以外の病気との関連も指摘されています。
これらのリスクを考えると、ピロリ菌に感染している場合は、適切な検査と除菌治療を受けることが重要です。特に胃がん予防の観点からは、早期の除菌が効果的とされています。
日本ヘリコバクター学会のガイドラインでは、ピロリ菌感染者全員に除菌療法を受けることを強く推奨しています。胃の健康を守るためにも、ピロリ菌検査を受けてみませんか?
ピロリ菌検査の種類と特徴
ピロリ菌の検査方法は大きく分けて、内視鏡を使う方法と使わない方法があります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
内視鏡を使わない検査方法
内視鏡検査を受けずに済むというメリットがあり、胃全体を診断できる「面診断」と呼ばれています。
尿素呼気試験は、診断薬を服用し、服用前後の呼気を集めて診断する方法です。簡単に行える上に精度が高く、現在の主流となっている検査法です。
抗体測定検査は、ピロリ菌に感染すると体内に作られる抗体を血液や尿から検出する方法です。過去の感染も含めて判定するため、現在の感染状況を正確に反映しない場合があります。
便中抗原検査は、便の中のピロリ菌の抗原を調べる方法です。非侵襲的で比較的精度が高いのが特徴です。
内視鏡を使う検査方法
内視鏡検査を利用して胃粘膜や胃組織の一部を採取して診断する方法です。胃の一部を調べる「点診断」となるため、偽陰性(実際は陽性なのに陰性と判定されること)の可能性があります。
迅速ウレアーゼ試験は、胃粘膜の一部を採取し、ピロリ菌が持つウレアーゼ酵素の活性を利用して判定します。特殊な反応液に粘膜を入れ、色の変化でピロリ菌の有無を判断します。
組織鏡検法は、採取した胃粘膜に特殊な染色を施し、顕微鏡でピロリ菌を直接観察する方法です。
培養法は、胃粘膜を採取してすりつぶし、ピロリ菌の発育環境で5〜7日間培養して判定します。
核酸増幅法は、内視鏡後の胃廃液をPCR検査にかけてピロリ菌とその薬剤感受性を調べる方法です。偽陰性が非常に少ない面診断が可能です。
ピロリ菌の検査は1つの方法だけでは偽陰性の可能性もあるため、疑わしい場合は複数の検査法を組み合わせて診断することが重要です。

ピロリ菌除菌治療の方法と成功率
ピロリ菌の除菌治療は、胃酸の分泌を抑える薬と2種類の抗生物質を組み合わせた「三剤併用療法」が基本となります。この3種類の薬を1日2回、7日間服用するのが標準的な治療法です。
胃酸を抑える薬には、従来のプロトンポンプ阻害薬(PPI)に加え、より強力な効果を持つカリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)も使用されるようになりました。
一次除菌療法の成功率は約70〜90%と報告されています。もし一次除菌に失敗した場合は、抗生物質の種類を変えて二次除菌を行います。
二次除菌まで含めると、除菌成功率は約97〜99%にまで上昇します。つまり、ほとんどの方が一次または二次除菌で成功するということです。
除菌治療後は、必ず除菌が成功したかどうかを確認するための検査(除菌判定)を行います。当院では便中抗原検査による除菌判定を実施しています。
保険診療では2回まで除菌治療を行うことができます。万が一、二次除菌でも成功しなかった場合は、三次除菌という選択肢もありますが、これは保険適用外となるため自費診療となります。
除菌治療の副作用としては、軟便・下痢(10〜30%)、嘔気・味覚障害(2〜5%)、皮疹(1〜2%)などが報告されていますが、皮疹を除けばほとんどは服薬終了後に改善します。
また、除菌に成功すると約10%の方に一時的に胸やけや胃もたれなどの逆流性食道炎の症状が現れることがありますが、これは胃炎が改善して胃酸分泌が回復することによるもので、多くの場合は一過性で治療を必要としません。
除菌治療の対象となる方と保険適用
ピロリ菌の除菌治療は、2013年から保険適用の範囲が拡大され、より多くの方が治療を受けられるようになりました。現在、以下の5つの条件に当てはまる方が保険診療の対象となっています。
保険適用となる5つの条件
- 内視鏡検査で胃炎と診断された方(ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎)
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍の方
- 胃MALTリンパ腫の方
- 特発性血小板減少性紫斑病の方
- 早期胃がんに対する内視鏡的治療後の方
特に1番目の「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」は2013年に保険適用となり、これによって多くの方が保険診療で除菌治療を受けられるようになりました。
ただし、除菌治療を受けるためには必ず内視鏡検査を受ける必要があります。これは胃の状態を確認し、適切な治療方針を立てるために重要なステップです。
上記の条件に当てはまらない方でも、ピロリ菌除菌を希望される場合は医師と相談の上、自費診療として治療を受けることも可能です。
胃がん予防の観点からは、ピロリ菌に感染している方は全員が除菌治療の対象となると考えられています。特に胃がんの家族歴がある方は、胃がんのリスクが2〜3倍高いとされており、積極的に検査・除菌を検討すべきでしょう。
あなたも胃の健康が気になるなら、一度検査を受けてみませんか?

除菌後のフォローアップと胃がんリスク
ピロリ菌の除菌に成功したからといって、胃がんのリスクがゼロになるわけではありません。除菌後も定期的な検査が必要な理由について説明します。
胃がんのリスクは、ピロリ菌を除菌することで約1/3程度にまで減少します。これは大きな効果ですが、それでもピロリ菌に一度も感染したことがない方と比べると、胃がんのリスクは75〜100倍ほど高い状態が続きます。
実際、除菌成功後も数年以内に、除菌成功者100人に1〜2人の割合で胃がんが発見されると報告されています。このため、除菌後も定期的に胃の検査(特に胃カメラ検査)を受けることが非常に重要です。
除菌後の再感染率は年率1%以下と言われており、除菌成功例でのピロリ菌の再陽性化率は0.2〜2%と低いことが報告されています。再陽性化の多くは、検査でも検出できないほどの微量のピロリ菌が胃の中に残っていて、それが増殖することによるものと考えられています。
また、除菌後に胃の状態が完全に元に戻るわけではありません。特に萎縮性胃炎が進行した状態で除菌した場合、胃粘膜の回復には時間がかかります。中には、逆流性食道炎や機能性ディスペプシアなどの症状が残る方もいます。
2025年4月に発表された国立がん研究センターの研究では、ピロリ菌除菌後の方でも、胃粘膜のDNAメチル化異常を測定することで、胃がんリスクを精密に予測できることが明らかになりました。今後はこのような検査も活用して、よりきめ細かなフォローアップが可能になるかもしれません。
当院では、ピロリ菌除菌後の方にも定期的な胃カメラ検査をお勧めしています。鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査で、負担を最小限に抑えながら胃の健康状態を確認できます。
若年層のピロリ菌検査と除菌の重要性
ピロリ菌は主に幼少期に感染し、その後長期間にわたって胃に炎症を引き起こします。胃がん予防の観点からは、胃粘膜の萎縮が進む前、つまりできるだけ若いうちに除菌することが理想的です。
近年、中学生を対象としたピロリ菌検査が全国的に広がっています。2023年の全国調査によると、105の自治体が中学生に対するピロリ菌検査を実施しており、年間約5万人の中学生が検査を受けています。
中学生を対象とした検査では、主に尿中ピロリ菌抗体測定が一次検査として用いられ、陽性の場合は尿素呼気試験や便中抗原検査などで確認が行われます。感染が確定した場合は、本人と保護者の希望により除菌治療が行われます。
若年層での除菌は、将来の胃がんリスクを大きく低減できる可能性があります。胃粘膜の萎縮がほとんど進んでいない段階で除菌することで、胃がん予防効果が最大限に発揮されるからです。
また、若いうちに除菌することで、将来的な胃潰瘍や十二指腸潰瘍などのリスクも減らすことができます。
ピロリ菌の感染率は年々低下していますが、家族内感染の可能性もあるため、ご家族にピロリ菌感染者がいる場合は、お子さんも検査を受けることをお勧めします。
当院では、中学生・高校生を含む若年層の方にも適切なピロリ菌検査と除菌治療を提供しています。胃の健康は一生の財産です。早期発見・早期治療で、将来の胃の病気リスクを減らしましょう。
まとめ:ピロリ菌除菌で胃の健康を守るために
ピロリ菌は胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、そして胃がんなど、様々な胃の病気と密接に関連しています。日本人のピロリ菌感染者は約3,500万人と推定されており、多くの方が自覚症状のないまま感染している状態です。
ピロリ菌検査には内視鏡を使う方法と使わない方法があり、それぞれ特徴があります。検査で感染が確認された場合は、胃酸分泌抑制薬と2種類の抗生物質を組み合わせた除菌治療を行います。
一次除菌の成功率は約70〜90%、二次除菌まで含めると約97〜99%と非常に高い成功率です。除菌治療は保険適用の範囲も広がり、胃炎と診断された方も保険診療で治療を受けられるようになりました。
ただし、除菌に成功しても胃がんのリスクがゼロになるわけではありません。除菌後も定期的な胃カメラ検査でフォローアップすることが重要です。
若年層、特に中学生を対象としたピロリ菌検査と除菌も広がっており、早期に除菌することで将来の胃がんリスクを大きく低減できる可能性があります。
胃の健康は一生の財産です。ピロリ菌検査と除菌治療で、胃の病気リスクを減らし、健康な胃を維持しましょう。
当院では、鎮静剤を使用した無痛の胃カメラ検査や、最新の方法によるピロリ菌検査・除菌治療を提供しています。胃の調子が気になる方、ピロリ菌検査をご希望の方は、お気軽に石川消化器内科・内視鏡クリニックにご相談ください。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院