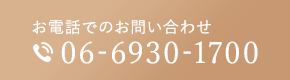胃の不調は日常生活の質を著しく低下させます。食後の胃もたれや胸やけ、胃痛などに悩まされると、食事の楽しみが半減してしまいますよね。
消化不良や胃痛は、実は単なる一時的な症状ではなく、生活習慣や自律神経の乱れ、さらには潜在的な疾患のサインかもしれません。
私は消化器内科医として多くの患者さんの胃腸トラブルと向き合ってきました。その経験から言えるのは、消化器症状の改善には対症療法だけでなく、根本的な原因にアプローチすることが重要だということです。
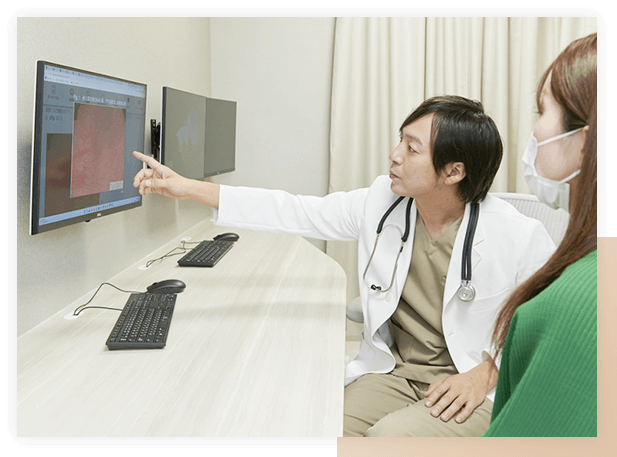
消化不良と胃痛の主な原因と症状
まず、消化不良と胃痛がなぜ起こるのか、その原因と症状を正しく理解しましょう。
消化不良とは、胃腸の働きが低下することでさまざまな不快な症状が現れる状態です。主な症状には、胃もたれ、胸やけ、吐き気、腹痛、膨満感などがあります。
胃痛については、みぞおちや上腹部辺りに痛みを感じるのが特徴で、時に胃がねじれるように痛むこともあります。これは胃痙攣と呼ばれる状態で、胃の筋肉が異常に収縮することで起こります。
消化不良と胃痛の主な原因は以下の4つに分類できます。
1. 食生活の乱れ
食べ過ぎや飲み過ぎは胃に大きな負担をかけます。特に脂肪の多い食べ物、香辛料や刺激物の多い食べ物、アルコールや炭酸飲料の過剰摂取は、胃酸や消化酵素の分泌を乱し、消化不良を引き起こしやすくなります。
また、早食いも消化不良の原因となります。噛む回数が少ないと食べ物の消化に時間がかかり、胃に負担をかけてしまうのです。
2. ストレスと自律神経の乱れ
胃の働きは自律神経によってコントロールされています。ストレスや疲労が溜まると自律神経のバランスが崩れ、胃腸の機能に悪影響を及ぼします。
具体的には、ストレスによって交感神経が優位になると、胃の運動が抑制され、消化機能が低下します。また、胃酸の分泌が増加し、胃粘膜を刺激することで胃痛を引き起こすこともあります。
夏場は特に注意が必要です。暑い屋外とクーラーの効いた屋内との寒暖差の影響で自律神経が乱れやすくなります。また、冷たい飲食物の摂取機会が増えることで、胃腸が冷えて胃の働きが低下しやすくなるのです。
3. 疾患による消化不良
消化不良や胃痛が長期間続く場合は、何らかの疾患が隠れている可能性があります。
胃食道逆流症は、胃と食道の境目にある下部食道括約筋が緩むことで、胃酸が食道に逆流し、胸やけや胃のむかつきを引き起こします。加齢による筋力低下や肥満、妊娠、姿勢の悪さなどが原因となることがあります。
胃炎は胃の粘膜に炎症が起きている状態で、急性胃炎と慢性胃炎があります。急性胃炎は食べ過ぎや飲み過ぎ、ストレス過多などが原因となり、慢性胃炎はピロリ菌感染が主な原因とされています。
機能性ディスペプシアは、器質的な異常がないにもかかわらず、上腹部の痛みや不快感、胃もたれなどの症状が続く状態です。ストレスや自律神経の乱れが関与していると考えられています。
4. 胃切除後症候群
胃の手術を受けた方に見られる症状です。胃を切除することで胃の機能が失われ、食べ物が一時的に溜まらなくなったり、消化吸収に影響が出たりします。
特に「ダンピング症候群」と呼ばれる症状では、食後5~30分で冷や汗、動悸、めまいなどの全身症状や、腹痛、下痢などの腹部症状が現れることがあります。また、食後2~3時間で頭痛、倦怠感、発汗などの症状が出ることもあります。

消化不良と胃痛を根本から改善する4つのアプローチ
消化不良と胃痛の改善には、対症療法だけでなく根本的な原因にアプローチすることが重要です。ここでは、私が臨床経験から効果的だと実感している4つの専門的アプローチをご紹介します。
1. 食事療法による胃腸環境の改善
消化不良や胃痛の改善には、まず食生活の見直しが欠かせません。以下のポイントを意識して食事をとりましょう。
- 少量多食:一度に大量の食事をとるのではなく、少量ずつ回数を分けて食べる
- よく噛む:一口30回を目安によく噛んで食べる
- 食事のバランス:高たんぱく、低脂肪、低炭水化物の食事を心がける
- 刺激物を避ける:辛い食べ物、酸味の強い食べ物、アルコール、カフェインなどは控える
- 食後の姿勢:食後すぐに横にならず、30分程度は座った状態を保つ
胃に優しい食材を選ぶことも大切です。消化の良い食材としては、お粥、うどん、豆腐、蒸した野菜、脂肪の少ない魚や肉などがおすすめです。発酵食品(ヨーグルトや味噌など)は腸内環境を整えるのに役立ちます。
一方で、脂っこい食べ物、生の野菜や果物、パンや麺類などの小麦製品、乳製品は消化に負担がかかる場合があるので、症状がひどい時は控えめにしましょう。
2. 自律神経バランスの調整
自律神経のバランスを整えることは、消化機能の改善に直結します。以下の方法を日常生活に取り入れてみましょう。
- 規則正しい生活:決まった時間に起床・就寝し、食事も規則的にとる
- 適度な運動:ウォーキングやヨガなど、リラックスできる運動を取り入れる
- ストレス管理:瞑想や深呼吸などのリラクゼーション法を実践する
- 十分な睡眠:質の良い睡眠をとることで自律神経のバランスを整える
- 温冷交代浴:ぬるめのお湯に浸かり、最後に冷水で締めることで自律神経を刺激する
特に深呼吸は、いつでもどこでも簡単にできるストレス軽減法です。腹式呼吸を意識して、ゆっくりと鼻から息を吸い、口からゆっくりと吐き出す。これを5分程度続けるだけでも、副交感神経が優位になり、胃腸の働きが活性化します。
ストレスを感じたときこそ、意識的に副交感神経を優位にする時間を作ることが大切です。「忙しくてそんな時間はない」と思うかもしれませんが、5分でも10分でも良いので、自分をリラックスさせる時間を作りましょう。
3. 胃腸機能を高める漢方薬と薬物療法
消化不良や胃痛に対しては、症状や原因に応じた薬物療法が効果的です。
消化酵素剤は、食べ物の消化を助ける酵素を補充することで、消化不良を改善します。食後の胃もたれや膨満感に効果的です。
制酸剤や胃粘膜保護剤は、胃酸の過剰分泌を抑えたり、胃粘膜を保護したりすることで、胃痛や胸やけを緩和します。
漢方薬も消化器症状の改善に効果的です。例えば、六君子湯(りっくんしとう)は、胃腸の働きを高め、食欲不振や胃もたれを改善します。半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)は、胃腸の熱を冷まし、胸やけや胃痛を和らげる効果があります。
ただし、薬物療法は自己判断で行うのではなく、必ず医師の診察を受けた上で適切な薬を処方してもらうことが重要です。特に漢方薬は、体質や症状に合わせて選ぶ必要があります。
4. 専門的検査による原因特定と治療
消化不良や胃痛が長期間続く場合は、専門的な検査を受けて原因を特定することが重要です。
胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)は、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察することで、胃炎や逆流性食道炎、潰瘍、がん・ポリープなどの病変を早期に発見できます。
ピロリ菌検査も重要です。ピロリ菌感染が確認された場合は、除菌治療を行うことで胃炎や胃潰瘍の改善、さらには胃がんの予防にもつながります。
また、腹部超音波検査やCT検査は、胃だけでなく、肝臓、胆嚢、膵臓など周辺臓器の状態も確認できるため、腹部症状の原因を幅広く探ることができます。
これらの検査結果に基づいて、適切な治療計画を立てることが、消化不良や胃痛を根本から改善する鍵となります。

症状別の対処法と注意点
消化不良や胃痛の症状は人によって異なります。ここでは、症状別の具体的な対処法と注意点をご紹介します。
胃もたれ・胸やけの場合
胃もたれや胸やけは、食後に特に感じやすい症状です。以下の対処法が効果的です。
- 食後すぐに横にならず、30分程度は座った状態を保つ
- 食後に軽い散歩をして、胃の消化を促す
- 就寝前3時間は食事を控える
- 枕を高くして寝ることで、胃酸の逆流を防ぐ
- 制酸剤や胃粘膜保護剤を服用する(医師の指示に従って)
胸やけが頻繁に起こる場合は、逆流性食道炎の可能性があります。特に就寝時に症状が悪化する場合や、咳や喉の痛みを伴う場合は、医療機関での検査をおすすめします。
胃痛・腹痛の場合
胃痛や腹痛がある場合は、まず胃を休ませることが大切です。
- 消化の良い食事を少量ずつとる
- 温かい飲み物(白湯など)を少しずつ飲む
- 腹部を温める(カイロや湯たんぽを使用)
- ストレスを軽減するリラクゼーション法を実践する
- 胃痛に効果的なツボ(中脘、内関など)を押す
ただし、以下のような場合は、すぐに医療機関を受診してください。
- 激しい痛みが続く場合
- 痛みが徐々に強くなる場合
- 吐き気や嘔吐を伴う場合
- 血便や黒い便が出る場合
- 発熱を伴う場合
吐き気・嘔吐の場合
吐き気や嘔吐がある場合は、脱水症状に注意が必要です。
- 水分を少量ずつ、こまめに摂取する
- 固形物は控え、消化の良い流動食から始める
- 生姜茶や薄い塩水を飲む
- 内関(手首の内側)のツボを押す
- 安静にして体を休める
嘔吐が続く場合や、嘔吐物に血液が混じっている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
ダンピング症候群の場合
胃の手術後に起こりやすいダンピング症候群には、以下の対処法が効果的です。
- 食事は一度にたくさん食べず、少しずつ回数を多くする
- 食べ物はよく噛み、唾液と混ぜ合わせてから飲み込む
- 高たんぱく、低脂肪、低炭水化物の食事を心がける
- 食後は横になって休む(早期ダンピング症候群の場合)
- 飴などで糖分を補給する(晩期ダンピング症候群の場合)
ダンピング症候群の症状が強い場合は、医師に相談することをおすすめします。薬物療法が効果的なこともあります。

予防と日常生活での注意点
消化不良や胃痛を予防するためには、日常生活での心がけが重要です。ここでは、予防のためのポイントをご紹介します。
規則正しい食生活
胃腸の健康を維持するためには、規則正しい食生活が基本です。
- 決まった時間に食事をとる
- よく噛んでゆっくり食べる
- 食べ過ぎ・飲み過ぎを避ける
- バランスの良い食事を心がける
- 空腹時のアルコール摂取を避ける
- 就寝前の食事を控える
特に夜遅い時間の食事は、胃酸の分泌を促し、就寝中の胃酸逆流を引き起こしやすくなります。夕食は就寝の3時間前までに済ませるようにしましょう。
ストレス管理と生活リズム
ストレスは消化不良や胃痛の大きな原因の一つです。ストレスを完全に排除することは難しいですが、上手に管理することは可能です。
- 自分なりのストレス発散法を見つける(趣味、運動など)
- 十分な睡眠をとる
- リラクゼーション法を実践する
- 無理なスケジュールを避け、休息時間を確保する
- 人間関係のストレスに対しては、コミュニケーションを大切にする
また、生活リズムを整えることも重要です。不規則な生活は自律神経のバランスを崩し、胃腸の機能低下を招きます。できるだけ同じ時間に起床・就寝し、規則正しい生活を心がけましょう。
定期的な健康チェック
消化不良や胃痛が長期間続く場合は、定期的な健康チェックが重要です。
- 年に一度は健康診断を受ける
- 40歳以上の方は、胃がん検診を定期的に受ける
- ピロリ菌検査を受け、陽性であれば除菌治療を検討する
- 気になる症状があれば、早めに医療機関を受診する
特に、以下のような症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。
- 急激な体重減少
- 嘔吐物や便に血液が混じる
- 強い腹痛が続く
- 黒色便が出る
- 飲み込みにくさを感じる
これらの症状は、重大な疾患のサインである可能性があります。早期発見・早期治療が重要です。
まとめ:消化不良と胃痛の根本改善に向けて
消化不良と胃痛は、単なる一時的な症状ではなく、生活習慣や自律神経の乱れ、さらには潜在的な疾患のサインかもしれません。
本記事でご紹介した4つのアプローチ(食事療法、自律神経バランスの調整、薬物療法、専門的検査による原因特定と治療)を組み合わせることで、消化不良と胃痛を根本から改善することが可能です。
特に重要なのは、症状が長期間続く場合は、自己判断せずに専門医の診察を受けることです。胃カメラ検査やピロリ菌検査などの専門的な検査を受けることで、早期に原因を特定し、適切な治療を受けることができます。
日常生活では、規則正しい食生活、ストレス管理、生活リズムの改善を心がけましょう。これらの取り組みは、消化不良や胃痛の予防だけでなく、全身の健康維持にもつながります。
消化器の不調は生活の質を大きく左右します。「胃の調子が悪いのは仕方ない」と諦めずに、ぜひ根本的な改善を目指してください。
当院では、消化器内科専門医による診察はもちろん、内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)、ピロリ菌検査、超音波検査、CT検査など、消化器疾患の診断に必要な検査を一通り行うことができます。消化器の不調でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
詳しい情報や予約方法については、石川消化器内科・内視鏡クリニックの公式サイトをご覧ください。皆様の健康的な生活をサポートいたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院