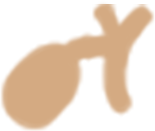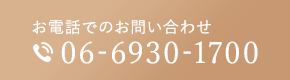大腸カメラ検査とは?人間ドックでの重要性
大腸カメラ検査は、下剤で大腸内を空にした後、内視鏡を肛門から挿入して大腸全体を観察する検査です。直径10mm前後の内視鏡を使用し、リアルタイムで腸内の状態を確認します。
この検査では、大腸がんやポリープ、炎症性腸疾患など、さまざまな病変を早期に発見することができるのです。
近年、大腸がんは日本人の罹患数第1位、死亡数では男性が第3位、女性が第1位となっている深刻な疾患です。食生活の欧米化や高齢化により増加傾向にあり、30代でも発症するケースが見られます。
私は消化器内科医として多くの患者さんを診てきましたが、早期発見できれば治療効果が高いのが大腸がんの特徴です。ステージⅠで発見された場合の5年生存率は92.3%と非常に高いのです。
大腸がんの初期段階では自覚症状がほとんどないため、定期的な検査が何よりも重要になります。
「検査は痛そう」「恥ずかしい」と躊躇される方も多いですが、現在は鎮静剤を使用した無痛検査や、患者さんの負担を軽減する様々な工夫が進んでいます。

大腸カメラ人間ドックの費用相場(2025年最新)
大腸カメラ検査の費用は、受ける医療機関や検査内容によって異なります。2025年現在の費用相場を詳しく見ていきましょう。
自費で検査を受ける場合と、自治体の補助を利用する場合では大きく金額が変わってきます。また、保険適用となるケースもあるので、状況に応じた選択が可能です。
自費で検査する場合の費用
人間ドックなど自費で大腸カメラ検査を受ける場合、医療機関によって金額や対象年齢が異なります。自分の希望するタイミングで検査を受けられる利点があります。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)単独の場合、一般的な費用相場は約20,000円程度です。ただし、医療機関によって15,000円~30,000円程度の幅があります。
人間ドックのオプションとして大腸カメラを追加する場合は、単独で受けるよりも割安になることが多く、15,000円前後で受けられる医療機関も少なくありません。
また、胃カメラと大腸カメラをセットで受ける「胃大腸カメラセット」は、45,000円前後が相場となっています。
検査中にポリープが見つかり、その場で切除した場合は追加費用が発生します。ポリープ切除を含めると、20,000円~30,000円程度の費用がかかることが一般的です。
自治体の補助を利用した場合の費用
各地方自治体(都道府県、市町村、特別区)では、大腸がん検診の補助制度を設けています。ただし、多くの自治体で補助対象となるのは便潜血検査(検便)であり、大腸カメラ検査自体への直接的な補助は限られています。
自治体の補助を利用した便潜血検査の自己負担額は、無料から有料でも500円~1,000円程度と非常に安価です。
便潜血検査で陽性反応が出た場合、精密検査として大腸カメラ検査を受けることになりますが、この場合は健康保険が適用されるため、自己負担額は6,000円~9,000円程度になります。
保険診療となる場合の費用
便潜血検査などで異常が見つかった場合や、腹痛・下血などの症状がある場合は、大腸カメラ検査が保険診療の対象となります。この場合の自己負担額は、検査内容によって以下のように変わります。
- 観察のみの場合:5,000円~7,000円程度
- 組織を一部採取して病理検査を行う場合:5,000円~15,000円程度
- ポリープ切除を行った場合:20,000円~30,000円程度
保険診療の場合、3割負担で計算していますが、高額療養費制度や各種医療費助成制度を利用できる場合もあります。
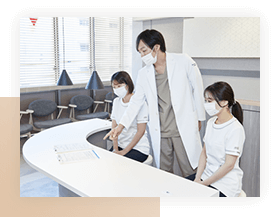
大腸カメラ検査の種類と選び方
大腸カメラ検査には、いくつかの種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った検査方法を選ぶことが大切です。
通常の大腸内視鏡検査
最も一般的な検査方法で、肛門から内視鏡を挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体を観察します。検査時間は15分程度ですが、前処置や待機時間を含めると2~3時間ほどかかります。
がんやポリープに対する診断精度が非常に高く、病変が見つかった場合はその場で組織採取や小さなポリープの切除が可能です。
ただし、内視鏡挿入時の不快感や痛みを感じる方もいらっしゃいます。そのため、最近では鎮静剤(麻酔)を使用した無痛検査が普及しています。
S状結腸内視鏡検査
大腸の入り口部分(S状結腸まで)のみを観察する検査です。検査時間が短く、前処置も比較的簡単なのが特徴です。費用も通常の大腸内視鏡検査より安く、保険診療で約3,000円程度です。
ただし、大腸全体を観察するわけではないため、奥の方にある病変を見逃す可能性があります。大腸がんは直腸やS状結腸に多く発生するため、スクリーニング検査としては有用ですが、全体を確認するには通常の大腸内視鏡検査が必要です。
CTによる大腸検査(CTコロノグラフィ)
肛門から炭酸ガスを注入してCTで撮影する検査方法です。内視鏡を使わないため、挿入時の痛みがなく、穿孔などのリスクも低いのが特徴です。費用相場は20,000円~30,000円程度です。
ただし、病変が見つかっても組織採取やポリープ切除はできないため、異常があれば改めて通常の大腸内視鏡検査が必要になります。また、小さなポリープの発見率は内視鏡検査より劣ります。
どうですか?ご自身の状況や不安要素に合わせて検査方法を選ぶことができますね。

大腸カメラ検査を受けるべき人とタイミング
大腸カメラ検査は誰もが定期的に受けるべきものではありませんが、特定の条件に当てはまる方は積極的に検討すべき検査です。
大腸カメラ検査を受けたほうがよい方
以下のような方は、大腸カメラ検査を受けることをお勧めします。
- 便潜血検査で陽性反応が出た方
- 血便や下痢、便秘の繰り返しなど腸の症状がある方
- 大腸がんの家族歴がある方
- 過去にポリープや大腸がんが見つかった方
- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)と診断された方
- 50歳以上の方(特にリスク因子がある場合)
特に40歳を超えると大腸がんのリスクは徐々に高まり始めます。50歳以上になると、症状がなくても定期的な検査を検討すべき年齢といえるでしょう。
私の臨床経験から言えば、家族歴のある方は特に注意が必要です。親や兄弟に大腸がんの既往がある場合、リスクは約2倍に高まるとされています。
大腸カメラ検査の推奨頻度
大腸カメラ検査の受診頻度は、個人のリスク因子や過去の検査結果によって異なります。
一般的な目安としては以下のようになります:
- 異常がなかった場合:5~10年ごと
- 小さなポリープが見つかり切除した場合:3~5年ごと
- 複数または大きなポリープが見つかった場合:1~3年ごと
- 大腸がんの治療後:医師の指示に従う(通常は1年ごと)
- 炎症性腸疾患がある場合:1~2年ごと
ただし、これはあくまで一般的な目安です。実際の検査間隔は、医師が患者さん一人ひとりの状況を考慮して判断します。
あなたはいかがですか?定期的な検査を受けていますか?
大腸カメラ検査の流れと準備
大腸カメラ検査を受ける際には、事前の準備が非常に重要です。検査の精度を高め、スムーズに進めるためにも、正しい準備を行いましょう。
検査前の食事制限と下剤
大腸内視鏡検査では、腸内をきれいにしておく必要があります。食物が消化されて排泄されるまでには24~48時間かかるため、検査前日からの準備が必要です。
検査前日の朝食からは、消化の良いものを摂るようにしましょう。おかゆや素うどんなどがおすすめです。医療機関によっては専用の検査食が用意されている場合もあります。
前日の夕食は軽めの消化の良いものを20時までに済ませ、その後は水分のみの摂取となります。就寝前に下剤を服用し、早めに就寝するのが良いでしょう。
検査当日の朝は食事ができません。ただし、脱水予防のために水分摂取は積極的に行ってください。検査の1~2時間前からは大腸内視鏡用の下剤(約1.5リットル)を服用し、便が透明になるまで続けます。
下剤の効果には個人差があり、服用開始から効果が現れるまで30分~2時間程度かかります。トイレに何度も行く必要があるため、検査当日は余裕をもったスケジュールを組むことをお勧めします。
検査当日の流れ
検査当日の一般的な流れは以下のようになります:
- 来院・受付
- 問診・検査の説明
- 下剤の服用(便が透明になるまで)
- 検査着に着替え
- 鎮静剤の使用(希望する場合)
- 検査台で左側を向いて横になる
- 内視鏡検査(約15分程度)
- 回復・休憩(鎮静剤使用の場合は30分程度)
- 結果説明
- 帰宅
鎮静剤を使用した場合は、検査後すぐに車の運転はできません。公共交通機関を利用するか、家族に送迎してもらうようにしましょう。
検査後の注意点
検査後は通常の食事に戻れますが、腸が空気で膨らんでいるため、軽い腹部膨満感を感じることがあります。これは徐々に改善していきます。
ポリープ切除を行った場合は、出血のリスクがあるため、数日間は激しい運動や入浴、飲酒を控える必要があります。また、食事内容も制限される場合があるので、医師の指示に従いましょう。
検査中に組織を採取した場合は、病理検査の結果が出るまで1~2週間かかります。結果を聞くために再度来院する必要があります。

大腸カメラ検査の負担を軽減する方法
「大腸カメラは辛い」というイメージをお持ちの方も多いでしょう。しかし、近年は患者さんの負担を軽減するための様々な工夫が進んでいます。
鎮静剤(麻酔)を使用した無痛検査
最も効果的な負担軽減方法は、鎮静剤(麻酔)の使用です。鎮静剤を使用すると、半分眠ったような状態になり、痛みや不快感をほとんど感じることなく検査を受けられます。
私のクリニックでも、多くの患者さんが鎮静剤を使用した検査を選択されています。「あっという間に終わった」「全く覚えていない」という感想をよくいただきます。
鎮静剤の使用には追加費用がかかる場合がありますが、検査の苦痛を大幅に軽減できるため、特に初めて検査を受ける方や過去に辛い経験をした方にはおすすめです。
CO2送気を用いた検査
従来の大腸内視鏡検査では空気を送り込んで腸を膨らませていましたが、最近ではCO2(二酸化炭素)を使用する医療機関が増えています。
CO2は空気よりも体内への吸収が早いため、検査後の腹部膨満感や不快感が軽減されます。検査中の痛みも軽減される傾向にあります。
細径スコープの使用
通常の内視鏡よりも細い「細径スコープ」を使用することで、挿入時の痛みや不快感を軽減できます。
ただし、細径スコープは画質や機能面で若干の制限があるため、すべての医療機関で導入されているわけではありません。検査前に医療機関に確認してみるとよいでしょう。
水浸法による挿入
水浸法は、空気の代わりに水を注入しながら内視鏡を挿入する方法です。腸管が伸びにくくなるため、痛みを軽減できます。
この方法は技術的に難しい面もありますが、患者さんの負担軽減に効果的であるため、導入する医療機関が増えています。

大腸カメラ検査の医療機関選びのポイント
大腸カメラ検査を受ける医療機関を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントがあります。適切な医療機関を選ぶことで、より安全で精度の高い検査を受けることができます。
専門医の在籍と経験
最も重要なのは、消化器内視鏡専門医が在籍しているかどうかです。専門医は高度な技術と知識を持ち、安全かつ精度の高い検査を提供できます。
医師の経験も重要な要素です。年間の内視鏡検査実施件数が多い医師ほど、技術が安定しており、偶発症のリスクも低くなります。
医療機関のホームページや電話での問い合わせで、専門医の在籍状況や経験を確認することをお勧めします。
設備と検査環境
最新の内視鏡機器を導入している医療機関では、より高精度な検査が可能です。特に「拡大内視鏡」や「NBI(狭帯域光観察)」などの特殊光観察が可能な機器があると、微細な病変も見逃しにくくなります。
また、ポリープが見つかった場合にその場で切除できる体制が整っているかも重要なポイントです。設備が整っていないと、改めて別の医療機関を受診する必要が生じます。
患者負担への配慮
鎮静剤の使用や、CO2送気、水浸法など、患者さんの負担を軽減する工夫を行っているかどうかも選択の基準になります。
また、検査前の説明が丁寧で、不安や疑問に対応してくれる医療機関を選ぶことも大切です。
女性の方は、女性医師や女性スタッフによる対応が可能かどうかも確認するとよいでしょう。
アクセスと予約のしやすさ
検査当日は下剤の影響でトイレに何度も行く必要があるため、自宅や職場からアクセスしやすい医療機関を選ぶことも重要です。
また、土曜日や夜間の検査に対応しているか、WEB予約が可能かなど、予約のしやすさも考慮すると良いでしょう。
私のクリニックでは、患者さんの利便性を考慮し、土曜日の検査や初診当日の検査にも対応しています。お仕事で平日に時間が取れない方にも検査を受けていただけるよう配慮しています。
まとめ:大腸カメラ検査で健康を守るために
大腸カメラ検査は、大腸がんをはじめとする様々な疾患の早期発見・早期治療に非常に有効な検査です。特に大腸がんは早期発見できれば治療効果が高く、5年生存率も90%を超えます。
2025年現在の費用相場としては、自費診療で約20,000円、保険適用で5,000円~7,000円程度が一般的です。ポリープ切除などを行うと追加費用がかかりますが、健康を守るための投資と考えれば決して高くはないでしょう。
検査に対する不安や恐怖感をお持ちの方も多いと思いますが、鎮静剤の使用やCO2送気など、患者さんの負担を軽減する様々な工夫が進んでいます。「辛い・苦しい」というイメージは、現在の医療技術ではかなり解消されています。
医療機関を選ぶ際は、消化器内視鏡専門医の在籍、最新設備の導入状況、患者負担への配慮などをポイントに検討することをお勧めします。
大腸がんは増加傾向にある疾患ですが、定期的な検査で早期発見できれば怖い病気ではありません。特に50歳を超えたら、症状がなくても一度は検査を検討されることをお勧めします。
健康は何よりも大切な財産です。「検査が怖い」という気持ちは理解できますが、その不安を乗り越えて検査を受けることで、より長く健康な生活を送ることができます。
詳しい検査内容や最新の無痛検査についてもっと知りたい方は、ぜひ 石川消化器内科・内視鏡クリニック にご相談ください。消化器・内視鏡専門医として、皆様の健康をサポートいたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院