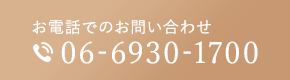十二指腸潰瘍とは~基本知識と症状
十二指腸潰瘍は、胃の出口から続く十二指腸の粘膜が深く傷つく疾患です。胃潰瘍と合わせて「消化性潰瘍」と呼ばれることもあります。この疾患は、粘膜の防御機能と胃酸などの攻撃因子のバランスが崩れることで発症します。
十二指腸潰瘍の特徴的な症状として、空腹時に痛みが現れ、食事をすると一時的に改善することが挙げられます。これは「空腹時痛」と呼ばれ、胃潰瘍の「食後痛」とは対照的です。
夜間に痛みで目が覚めることもあり、この「夜間性」の症状は十二指腸潰瘍の特徴的なサインです。また、上腹部痛、胸やけ、胃もたれ、吐き気、嘔吐などの症状も見られます。重症化すると黒色便(タール便)が出ることもあり、これは消化管出血のサインとして注意が必要です。
十二指腸潰瘍は、胃潰瘍と比べるとやや発症率は低いものの、若年層から中年層にかけての罹患が目立ちます。男性に多い傾向がありますが、女性も一定の罹患率を示しています。

十二指腸潰瘍の3大原因
十二指腸潰瘍の発症には主に3つの要因が関わっています。これらの原因を理解することが、効果的な予防と治療の第一歩となります。
1. ヘリコバクター・ピロリ菌感染
十二指腸潰瘍の最も重要な原因は、ヘリコバクター・ピロリ菌(H. pylori)の感染です。世界全体の約半数がこの細菌に感染しているとされています。
ピロリ菌は胃に定着し、胃酸分泌を増加させるとともに、十二指腸粘膜の防御機能を低下させます。十二指腸潰瘍患者の約90%がピロリ菌に感染しているというデータもあり、その関連性の高さがうかがえます。
興味深いことに、同じピロリ菌が原因であるにもかかわらず、十二指腸潰瘍の患者は胃癌になりにくいことが知られています。2012年の研究では、この違いがPSCA遺伝子の違いによることが明らかになりました。
PSCA遺伝子のタイプによって、十二指腸潰瘍と胃癌のリスクが逆相関することが分かっています。十二指腸潰瘍になりやすいタイプの人(CC型)では潰瘍のリスクが1.84倍増える一方、胃癌のリスクが約半分(0.59倍)になるというデータが示されています。
2. 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の使用
アスピリンをはじめとする非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の使用は、十二指腸潰瘍の重要な原因の一つです。NSAIDsは、プロスタグランジンの生成を抑制することで、胃や十二指腸の粘膜防御機能を低下させます。
NSAIDsを3か月以上継続して使用すると、10-15%で胃潰瘍、3%で十二指腸潰瘍、1%で出血性潰瘍が生じるというデータがあります。これは酸分泌抑制薬を併用しない場合の数値です。
特に注意すべきは、NSAIDs潰瘍の出血を起こしても無症状の患者さんが多いという点です。痛みなどの自覚症状がなくても、潜在的に潰瘍が進行している可能性があります。
3. 胃酸の過剰分泌
十二指腸潰瘍の発症には、胃酸の過剰分泌も重要な役割を果たしています。通常、十二指腸は胃酸を中和する機能を持っていますが、胃酸の分泌が過剰になると、この防御機能が追いつかなくなります。
ピロリ菌感染は胃酸分泌を増加させる一因となります。また、ストレスや特定の食品(カフェイン、アルコール、香辛料の多い食品など)も胃酸分泌を促進することがあります。
胃酸の過剰分泌は、十二指腸粘膜の炎症と組織破壊を引き起こし、潰瘍形成につながります。特に夜間の胃酸分泌増加が、夜間痛という特徴的な症状の原因となっています。
十二指腸潰瘍のリスク因子
十二指腸潰瘍の発症リスクを高める要因には、上記の3大原因に加えて、いくつかの重要な因子があります。これらのリスク因子を理解することで、予防対策をより効果的に行うことができます。
高リスク群の特徴
以下のような状態がある場合、NSAIDs潰瘍を含む十二指腸潰瘍の高リスク群と考えられます:
- 高齢(65歳以上)
- 重篤な全身疾患を有する
- 消化性潰瘍の既往がある
- 副腎皮質ステロイドの併用
- 抗凝固薬と抗血小板薬の併用
- 高用量あるいは複数のNSAIDsの併用
- ビスホスホネートの併用
- ヘリコバクターピロリ陽性
特に注目すべきは、複数の薬剤を併用している高齢者です。高齢化社会の進展に伴い、このようなハイリスク患者が増加しています。
生活習慣関連因子
喫煙とアルコール摂取も、NSAIDs潰瘍を含む十二指腸潰瘍のリスクを高める可能性があります。喫煙は胃粘膜の血流を減少させ、アルコールは胃粘膜を直接刺激することで防御機能を低下させます。
不規則な食生活やストレスも、十二指腸潰瘍の発症や悪化に関連していると考えられています。特に長期間の精神的ストレスは、自律神経系を介して胃酸分泌に影響を与える可能性があります。
遺伝的要因も無視できません。前述のPSCA遺伝子の他にも、ABO血液型がリスクに影響することが分かっています。O型の人はA型に比べて1.43倍、十二指腸潰瘍になりやすいというデータがあります。
これらのリスク因子を複数持つ場合、十二指腸潰瘍の発症リスクは相乗的に高まる可能性があります。自分のリスクを知り、適切な予防策を講じることが重要です。

十二指腸潰瘍の診断方法
十二指腸潰瘍の確定診断には、いくつかの検査方法が用いられます。症状だけでは胃潰瘍や機能性ディスペプシアなど他の疾患との区別が難しいため、適切な検査による診断が重要です。
内視鏡検査(上部消化管内視鏡)
十二指腸潰瘍の診断の基本となるのが上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)です。この検査では、口または鼻から細い内視鏡を挿入し、食道、胃、十二指腸の粘膜を直接観察します。
内視鏡検査の最大の利点は、潰瘍を直接目で見て確認できることです。潰瘍の大きさ、深さ、位置、数などを正確に評価できるほか、必要に応じて組織を採取(生検)し、悪性疾患との鑑別も可能です。
近年では、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の内視鏡検査が普及しています。半分眠ったような状態で検査を受けられるため、従来の「辛い・苦しい」というイメージを払拭し、患者さんの負担を大幅に軽減しています。
ヘリコバクター・ピロリ菌の検査
十二指腸潰瘍の主要原因であるピロリ菌の感染を調べる検査も重要です。検査方法には以下のようなものがあります:
- 内視鏡検査時の生検による検査(培養検査、迅速ウレアーゼ試験、組織検査)
- 尿素呼気試験(13C-尿素呼気試験)
- 血液検査(抗ピロリ菌抗体検査)
- 便検査(ピロリ菌抗原検査)
これらの検査を組み合わせることで、ピロリ菌感染の有無を高い精度で判定することができます。感染が確認された場合は、除菌治療の適応となります。
その他の検査
状況に応じて、以下のような検査が追加で行われることもあります:
- 血液検査:貧血の有無、炎症反応などを調べます
- 便潜血検査:消化管出血の有無を調べます
- X線検査(上部消化管造影):バリウムを飲んでX線撮影を行い、潰瘍の位置や大きさを評価します
- CT検査:合併症(穿孔など)が疑われる場合に行われます
これらの検査を総合的に評価することで、十二指腸潰瘍の確定診断だけでなく、重症度や合併症の有無も判断することができます。早期の適切な診断が、効果的な治療につながります。
十二指腸潰瘍の予防法と生活習慣の改善
十二指腸潰瘍は適切な予防策により、発症リスクを大幅に低減することができます。特にリスク因子を持つ方は、以下の予防法を積極的に取り入れることをお勧めします。
ピロリ菌感染の検査と除菌
ピロリ菌感染が十二指腸潰瘍の主要原因であることから、感染が確認された場合は除菌治療を検討することが重要です。特に以下のような方は検査をお勧めします:
- 消化性潰瘍の既往がある方
- 消化性潰瘍の家族歴がある方
- 慢性的な胃の不調がある方
- 胃癌のリスクが心配な方
除菌治療により、十二指腸潰瘍の再発率は著しく低下します。一度除菌に成功すれば、再感染率は年間0.5%程度と低く、長期的な予防効果が期待できます。
NSAIDs使用時の注意点
NSAIDsを使用する必要がある場合は、以下の点に注意することで潰瘍リスクを軽減できます:
- 必要最小限の用量と期間にとどめる
- 高リスク患者では、PPIやP-CABを併用する
- 可能であれば、胃腸への影響が少ないCOX-2選択的阻害薬の使用を検討する
- アルコールや喫煙を避ける
NSAIDs潰瘍のリスクが高いと予想される場合、潰瘍歴のない患者さんにおいてもNSAIDs潰瘍の予防投与が望ましいとされています。潰瘍歴のある患者さんの予防には、PPIやボノプラザンが推奨されます。
生活習慣の改善
十二指腸潰瘍の予防と再発防止には、以下のような生活習慣の改善が効果的です:
- 禁煙:喫煙は潰瘍治癒を遅らせ、再発リスクを高めます
- 節酒:過度のアルコール摂取は胃粘膜を刺激します
- 規則正しい食生活:空腹の時間を長くしないよう、規則的に食事をとりましょう
- ストレス管理:リラクゼーション法や適度な運動でストレスを軽減しましょう
- 十分な睡眠:良質な睡眠は自律神経のバランスを整えます
特に注目すべきは、喫煙の影響です。喫煙は胃粘膜の血流を減少させ、潰瘍治癒を遅らせるだけでなく、ピロリ菌除菌の成功率も低下させることが知られています。
定期的な健康チェック
十二指腸潰瘍の既往がある方や、リスク因子を持つ方は、定期的な健康チェックが重要です。特に以下のような場合は、早めに医療機関を受診しましょう:
- 上腹部に持続する痛みがある
- 黒色便(タール便)が出る
- 貧血の症状(めまい、倦怠感など)がある
- NSAIDsを長期服用している
早期発見・早期治療が、重篤な合併症を防ぐ鍵となります。特に高齢者では、症状が典型的でない場合もあるため、注意が必要です。

十二指腸潰瘍の合併症と注意点
十二指腸潰瘍は適切に治療されなければ、いくつかの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。これらの合併症を理解し、早期に対処することが重要です。
出血
十二指腸潰瘍の最も一般的な合併症は出血です。潰瘍が深くなり、血管を侵食することで発生します。出血の症状には以下のようなものがあります:
- 黒色便(タール便):消化管上部からの出血を示します
- 吐血:鮮血や「コーヒー残渣様」の嘔吐物
- めまい、立ちくらみ、倦怠感:貧血の症状
- 頻脈、血圧低下:大量出血時に見られます
出血性潰瘍は緊急処置が必要な状態です。内視鏡的止血術が第一選択となりますが、止血困難例ではIVRや外科的治療が検討されます。
特に注意すべきは、NSAIDs潰瘍の出血を起こしても無症状の患者さんが多いという点です。定期的な検査と予防的な対策が重要となります。
穿孔
穿孔は、潰瘍が十二指腸壁を完全に貫通し、内容物が腹腔内に漏れ出す状態です。突然の激しい腹痛で発症し、腹部全体の痛みと硬直(板状硬)が特徴的です。
穿孔は生命を脅かす緊急事態であり、速やかな外科的処置が必要となります。CT検査で診断され、多くの場合、緊急手術が行われます。
近年では、腹腔鏡を用いた低侵襲手術も行われるようになってきました。早期に適切な治療を行うことで、予後は大きく改善します。
狭窄
十二指腸潰瘍が治癒する過程で瘢痕組織が形成され、十二指腸の内腔が狭くなることがあります。これを狭窄と呼びます。主な症状には以下のようなものがあります:
- 食後の膨満感、不快感
- 嘔吐(特に食後)
- 体重減少
- 上腹部痛
狭窄の治療には、内視鏡的バルーン拡張術や外科的治療が検討されます。ピロリ菌除菌治療の普及により、狭窄を含む潰瘍の合併症は減少傾向にありますが、高齢者や複数の疾患を持つ患者では依然として注意が必要です。
高齢者における注意点
高齢者の十二指腸潰瘍には、いくつかの特徴と注意点があります:
- 症状が非典型的であることが多い(痛みを訴えないケースも)
- NSAIDsや抗血栓薬の使用頻度が高く、出血リスクが増加
- 合併症発生時の重症化リスクが高い
- 複数の疾患や薬剤使用による複雑な病態
本邦の超高齢社会において、併存疾患の存在や抗血栓薬ならびに非ステロイド性抗炎症薬内服患者の増加によって、患者背景が変化していることに注意が必要です。高齢者では予防的なアプローチと定期的な健康チェックがより重要となります。
まとめ~十二指腸潰瘍との上手な付き合い方
十二指腸潰瘍は、ヘリコバクター・ピロリ菌感染、NSAIDsの使用、胃酸の過剰分泌という3大原因によって引き起こされる疾患です。かつては難治性とされていましたが、現在では適切な治療により高い確率で治癒が可能となっています。
ピロリ菌感染が確認された場合は、除菌療法が第一選択となります。除菌成功により潰瘍再発率は著しく低下します。NSAIDs起因性の潰瘍では、可能であれば使用中止、または酸分泌抑制薬の併用が推奨されます。
予防においては、ピロリ菌検査と除菌、NSAIDs使用時の注意、生活習慣の改善が重要です。特に喫煙、過度のアルコール摂取、不規則な食生活、ストレスは潰瘍のリスクを高めるため、これらの改善が効果的です。
十二指腸潰瘍の症状として特徴的なのは、空腹時の痛みと夜間痛です。黒色便や吐血などの出血症状、突然の激しい腹痛などの穿孔症状がある場合は、緊急の医療処置が必要です。
高齢者では症状が非典型的であることが多く、NSAIDsや抗血栓薬の使用頻度も高いため、特に注意が必要です。定期的な健康チェックと予防的なアプローチが重要となります。
十二指腸潰瘍は、適切な知識と予防・治療により、上手に付き合っていくことが可能な疾患です。気になる症状がある場合は、早めに消化器専門医に相談することをお勧めします。
当院では、鎮静剤(麻酔)を使用した無痛の内視鏡検査を提供しており、十二指腸潰瘍を含む消化器疾患の早期発見・早期治療に力を入れています。些細な症状でもお気軽にご相談ください。
詳細な情報や検査のご予約については、石川消化器内科・内視鏡クリニックまでお問い合わせください。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院