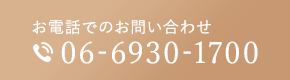慢性便秘とは?医学的に正しい理解から始めよう
便秘は誰もが一度は経験したことがある身近な症状です。しかし、その多くは一時的なものであり、生活習慣の改善や市販薬で解消されることがほとんどです。
ところが、3ヶ月以上にわたって症状が続く「慢性便秘症」となると話は別です。これは単なる不快な症状ではなく、生活の質を著しく低下させ、さらには様々な健康リスクをもたらす可能性がある病態なのです。近年の研究では、慢性便秘は長期生存率の低下や冠動脈疾患、パーキンソン病との関連も示唆されています。
私は消化器内科医として多くの便秘に悩む患者さんを診てきましたが、実は便秘で医療機関を受診する方は全体の5%にも満たないというデータがあります。多くの方が「恥ずかしい」「大したことない」と思い、自己流の対処を続けているのが現状です。
慢性便秘症の定義は、「3ヶ月以上にわたり、週に3回以下の排便、または排便時の過度のいきみ、硬い便、残便感、直腸肛門の閉塞感、排便のための用手的補助が必要など、複数の症状が見られる状態」です。これらの症状が1つでもあれば、慢性便秘症の可能性を考える必要があります。

便秘が引き起こす5つの健康リスク
便秘は単なる不快な症状ではありません。長期間放置すると、思いもよらない健康リスクをもたらします。
まず第一に、慢性便秘は腸内環境の悪化を招きます。便が腸内に長時間滞留することで腸内細菌のバランスが崩れ、有害物質が産生されやすくなります。これが腸内環境の悪化を招き、免疫機能の低下にもつながるのです。実際、最新の研究では腸内細菌叢の乱れが様々な全身疾患と関連していることが明らかになっています。
第二に、便秘は痔や肛門裂傷などの肛門疾患のリスクを高めます。硬い便を排出しようと強くいきむことで、肛門周囲の血管に負担がかかり、痔核(いわゆる「いぼ痔」)や裂肛(肛門の切れ目)を引き起こすことがあります。これらは出血や激しい痛みを伴い、日常生活に大きな支障をきたします。
第三に、慢性便秘は大腸憩室症のリスク因子です。腸管内の圧力が高まることで腸壁が外側に押し出され、小さな袋状の突出(憩室)が形成されます。憩室自体は無症状のことが多いですが、炎症を起こすと(憩室炎)激しい腹痛や発熱を引き起こし、時に入院治療が必要になることもあります。
さらに、長期的な便秘は大腸がんのリスク因子である可能性も指摘されています。便の滞留時間が長くなることで、発がん物質と腸粘膜の接触時間が増加するためと考えられています。
最後に、意外かもしれませんが、便秘は心血管疾患のリスクを高める可能性があります。排便時の過度のいきみは血圧を急上昇させ、心臓に負担をかけます。特に高齢者や心疾患のある方は注意が必要です。
これらのリスクを考えると、慢性便秘は単なる生活の質の問題ではなく、健康上の重要な課題であることがわかります。
便秘の原因を知り、タイプ別に対策を立てる
便秘を効果的に改善するためには、まず自分の便秘のタイプを知ることが重要です。便秘には大きく分けて3つのタイプがあります。
一つ目は「機能性便秘」です。これは最も一般的なタイプで、腸の動きが鈍くなる「腸管運動機能低下型」と、排便時に力を入れても便が出にくい「排便困難型」に分けられます。生活習慣の乱れ、ストレス、運動不足、食物繊維の摂取不足などが主な原因です。
二つ目は「器質性便秘」です。これは大腸がんや腸閉塞、腸管狭窄など、腸に器質的な異常がある場合に起こります。突然の便通異常、血便、体重減少などの症状を伴う場合は、この可能性を考える必要があります。
三つ目は「薬剤性便秘」です。鎮痛薬(特にオピオイド)、抗うつ薬、抗コリン薬、抗ヒスタミン薬、降圧薬など、様々な薬が便秘を引き起こす可能性があります。特に高齢者は複数の薬を服用していることが多く、薬剤性便秘のリスクが高まります。
便秘のタイプによって適切な対処法は異なります。たとえば、腸管運動機能低下型の便秘には運動療法や食事療法が効果的ですが、排便困難型には骨盤底筋のリハビリテーションが必要なこともあります。
あなたはどのタイプの便秘でしょうか?
自分の便秘のタイプを知るためには、症状の特徴を観察することが大切です。排便回数だけでなく、便の硬さ、排便時の感覚、腹部の不快感なども重要な手がかりになります。
便秘の原因が明らかになれば、それに合わせた対策を立てることができます。次からは、私が臨床経験から効果的だと実感している5つの改善方法をご紹介します。

方法1:腸内環境を整える食事療法
便秘改善の基本は、やはり食事です。特に重要なのは食物繊維の摂取です。
食物繊維には水溶性と不溶性の2種類があります。水溶性食物繊維は水に溶けて粘性のあるゲル状になり、便のかさを増やして腸の中をスムーズに移動させる効果があります。不溶性食物繊維は水に溶けずに便のかさを増やし、腸の蠕動運動を促進します。
水溶性食物繊維が豊富な食品としては、海藻類(わかめ、昆布)、果物(りんご、バナナ、キウイ)、オクラ、なめこなどがあります。不溶性食物繊維が多い食品には、玄米、全粒粉パン、こんにゃく、ごぼう、さつまいもなどがあります。
私の臨床経験では、特に効果的だと感じるのは、キウイフルーツと干しプルーンです。キウイフルーツには食物繊維だけでなく、タンパク質分解酵素のアクチニジンが含まれており、消化を助ける効果があります。干しプルーンには食物繊維に加え、ソルビトールという天然の緩下成分が含まれています。
また、発酵食品も腸内環境を整えるのに効果的です。ヨーグルト、納豆、キムチ、ぬか漬けなどの発酵食品には、腸内の善玉菌を増やす効果があります。特に乳酸菌やビフィズス菌を含む食品は、腸の蠕動運動を促進し、便通を改善する効果が期待できます。
一方で、便秘を悪化させる食品もあります。精製された炭水化物(白米、白パン、菓子パンなど)、加工食品、脂肪分の多い食品、カフェインやアルコールの過剰摂取は避けるべきです。
食事の摂り方も重要です。規則正しい時間に食事をとることで、胃結腸反射(食事をとると大腸の蠕動運動が活発になる反応)を利用できます。特に朝食をしっかりとることで、朝の排便習慣が身につきやすくなります。
私がよく患者さんに勧めるのは、朝起きたらまず常温の水を一杯飲むことです。これは腸の動きを活性化させ、排便を促す簡単な方法です。
方法2:効果的な運動習慣で腸の動きを活性化
運動不足は便秘の大きな原因の一つです。適度な運動は腸の蠕動運動を促進し、便通を改善する効果があります。
特に有効なのは、有酸素運動です。ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動は、全身の血流を改善し、腸への血流も増加させます。これにより腸の動きが活発になり、便の移動がスムーズになります。
私が特におすすめするのは、朝の時間帯に20〜30分程度のウォーキングを行うことです。朝の運動は体内時計をリセットし、腸の動きを活性化させる効果があります。実際、多くの患者さんが朝のウォーキングを習慣化することで便通が改善したと報告しています。
また、腹筋運動も効果的です。腹筋を鍛えることで腹圧をかけやすくなり、排便がスムーズになります。ただし、過度な腹筋運動は逆効果になることもあるので、無理のない範囲で行いましょう。
ヨガも便秘改善に効果的です。特に「ねじりのポーズ」や「風の抜けるポーズ」など、腸を刺激するポーズは便秘の改善に役立ちます。深い呼吸と組み合わせることで、腸へのマッサージ効果も期待できます。
運動を習慣化するコツは、無理なく続けられる強度と時間から始めることです。いきなり高強度の運動を長時間行うのではなく、まずは5分間のウォーキングから始め、徐々に時間を延ばしていくのがおすすめです。
私の患者さんで印象的だったのは、70代の女性です。長年の便秘に悩み、様々な下剤を試してきましたが効果は一時的でした。そこで毎朝15分の近所の散歩と、簡単なヨガのポーズを取り入れたところ、2週間ほどで便通が改善し、下剤の量を減らすことができました。
日常生活の中でも、エレベーターやエスカレーターの代わりに階段を使う、一駅分歩く、デスクワークの合間に立ち上がって軽くストレッチするなど、小さな運動を取り入れることが大切です。
運動は便秘改善だけでなく、全身の健康にも良い影響を与えます。自分に合った運動を見つけて、無理なく続けていきましょう。

方法3:ストレス管理と排便習慣の確立
便秘とストレスは密接に関連しています。ストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、腸の動きが鈍くなります。これが便秘を引き起こす一因となるのです。
私の外来でも、仕事や家庭のストレスが増えた時期に便秘が悪化したという患者さんは少なくありません。特に過敏性腸症候群(IBS)の方は、ストレスによって症状が大きく変動することがあります。
ストレス管理の方法としては、深呼吸、瞑想、ヨガ、アロマテラピー、入浴など、自分に合ったリラックス法を見つけることが大切です。特に腹式呼吸は、副交感神経を優位にし、腸の動きを活性化させる効果があります。
十分な睡眠も重要です。睡眠不足は自律神経のバランスを崩し、便秘を悪化させることがあります。規則正しい睡眠習慣を心がけましょう。
次に重要なのが、規則正しい排便習慣の確立です。毎日決まった時間にトイレに座る習慣をつけることで、体内時計が整い、自然な排便リズムが生まれます。
特に朝食後は胃結腸反射により腸の動きが活発になるため、排便に適した時間です。朝食後15〜30分程度、時間に余裕をもってトイレに座りましょう。この時、スマートフォンやタブレットを見ながらではなく、リラックスした状態で腹圧をかけることが大切です。
また、排便を我慢することは避けましょう。便意を感じたらなるべく早くトイレに行くことが重要です。便意を繰り返し我慢すると、次第に便意そのものを感じにくくなる「直腸感覚の鈍化」が起こることがあります。
トイレ環境も排便に影響します。和式トイレよりも洋式トイレの方が排便姿勢として適しています。また、足元に小さな台を置いて膝を高くすると、より自然な排便姿勢になります。
私の患者さんで、長年便秘に悩んでいた30代の男性は、朝の排便習慣を意識的に作ることで症状が改善しました。毎朝同じ時間に起き、水を一杯飲み、軽い体操をした後に朝食をとり、その後トイレに座る習慣をつけたところ、2週間ほどで自然な排便リズムが生まれたそうです。
便秘改善には、身体的なアプローチだけでなく、心理的なアプローチも重要です。ストレスを適切に管理し、規則正しい生活リズムと排便習慣を確立することで、薬に頼らない自然な排便を目指しましょう。
方法4:適切な水分摂取と腸活サポート成分
便秘改善には十分な水分摂取が欠かせません。水分が不足すると、大腸で水分が過剰に吸収され、便が硬くなってしまいます。
一日に必要な水分量は、体重や活動量、気候によって異なりますが、一般的には1.5〜2リットル程度が目安です。ただし、単に「水をたくさん飲めば良い」というわけではありません。
私がおすすめするのは、常温の水を少量ずつこまめに飲む方法です。特に朝起きた時と食事の30分前に一杯の水を飲むことで、腸の動きを促進する効果が期待できます。
また、水だけでなく、食物繊維を含む野菜や果物からも水分を摂取することが大切です。これらの食品は水分と食物繊維を同時に摂取できるため、便秘改善に効果的です。
一方で、カフェインを含む飲料(コーヒー、紅茶、緑茶など)やアルコールは利尿作用があり、過剰摂取は体内の水分を奪ってしまうことがあります。これらの飲み物を摂取した場合は、追加で水分を補給するよう心がけましょう。
次に、腸内環境を整えるサポート成分についてお話しします。
プロバイオティクスは、腸内の善玉菌のバランスを整える生きた微生物です。ビフィズス菌や乳酸菌などが代表的で、ヨーグルトや発酵食品に含まれています。サプリメントとしても摂取可能です。
プレバイオティクスは、善玉菌のエサとなる成分です。オリゴ糖、食物繊維、レジスタントスターチなどが該当します。これらを摂取することで、腸内の善玉菌が増え、腸内環境が改善します。
私の臨床経験では、プロバイオティクスとプレバイオティクスを組み合わせて摂取する「シンバイオティクス」が最も効果的です。例えば、オリゴ糖入りのヨーグルトや、食物繊維が豊富な野菜と発酵食品を一緒に摂取するなどの工夫が有効です。
また、マグネシウムも便秘改善に役立つ成分です。マグネシウムには腸に水分を引き寄せる作用があり、便を柔らかくする効果があります。ナッツ類、緑黄色野菜、海藻類、豆類などに多く含まれています。
ただし、サプリメントによる過剰摂取は下痢などの副作用を引き起こす可能性があるため、適切な量を守ることが重要です。特に腎機能に問題がある方は、医師に相談してから摂取するようにしましょう。
水分摂取と腸活サポート成分の摂取は、日々の生活に無理なく取り入れられる便秘改善策です。まずは朝起きた時に水を一杯飲む習慣から始めてみてはいかがでしょうか。

方法5:専門医による適切な薬物療法と治療法
ここまでご紹介した生活習慣の改善で多くの便秘は改善しますが、それでも症状が続く場合は、専門医による適切な薬物療法や治療法を検討する必要があります。
便秘治療薬には大きく分けて数種類あります。それぞれ作用機序が異なるため、症状や原因に合わせて適切な薬剤を選択することが重要です。
浸透圧性下剤(酸化マグネシウムなど)は、腸内に水分を引き寄せて便を柔らかくする薬剤です。比較的副作用が少なく、長期使用も可能ですが、腎機能障害のある方は注意が必要です。
刺激性下剤(センノシドなど)は、腸の蠕動運動を直接刺激して排便を促します。即効性がありますが、長期使用により腸が薬に依存してしまう可能性があるため、短期間の使用が原則です。
クロライドチャネルアクチベーター(ルビプロストンなど)は、腸管内に水分を分泌させて便の通過を促進します。慢性便秘症の治療薬として近年注目されています。
グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト(リナクロチドなど)は、腸管内の水分分泌を促進し、腸の運動も活性化させる薬剤です。特に過敏性腸症候群に伴う便秘に効果的です。
これらの薬剤は、症状や原因、年齢、併存疾患などを考慮して選択します。自己判断での服用は避け、必ず医師の指導のもとで適切な薬剤を選択することが重要です。
薬物療法以外にも、バイオフィードバック療法という治療法があります。これは排便時の筋肉の使い方を学び直す治療法で、特に排便困難型の便秘に効果的です。
バイオフィードバック療法では、排便時に腹圧をかけながら肛門括約筋をリラックスさせる正しい排便法を学びます。センサーを使って筋肉の動きを視覚的に確認しながらトレーニングを行うため、自分の体の状態を客観的に理解できるのが特徴です。
また、重度の便秘で他の治療法が効果がない場合には、外科的治療が検討されることもあります。ただし、これはあくまで最終手段であり、慎重に適応を判断する必要があります。
私の臨床経験では、多くの患者さんは適切な生活習慣の改善と、必要に応じた薬物療法の組み合わせで症状が改善します。重要なのは、自己判断で市販薬に頼り続けるのではなく、症状が長期間続く場合は専門医に相談することです。
特に、便秘に加えて血便や急激な体重減少、強い腹痛などの症状がある場合は、大腸がんなどの重大な疾患の可能性もあるため、速やかに医療機関を受診してください。
まとめ:便秘とさよならするための総合アプローチ
慢性便秘は単なる不快な症状ではなく、生活の質を大きく低下させ、様々な健康リスクをもたらす可能性がある問題です。しかし、適切なアプローチで多くの場合は改善が可能です。
今回ご紹介した5つの方法を総合的に取り入れることで、便秘を根本から改善していきましょう。
まず、食物繊維と水分を十分に摂取し、腸内環境を整える食事を心がけましょう。特に水溶性と不溶性の食物繊維をバランスよく摂ることが重要です。
次に、適度な運動を習慣化し、腸の動きを活性化させましょう。特に朝のウォーキングやヨガは効果的です。
ストレス管理と規則正しい排便習慣の確立も重要です。特に朝食後にトイレに座る習慣をつけることで、自然な排便リズムが生まれやすくなります。
プロバイオティクスやプレバイオティクスなどの腸活サポート成分も積極的に取り入れ、腸内環境を整えましょう。
そして、これらの生活習慣の改善で効果が見られない場合は、専門医に相談し、適切な薬物療法や治療法を検討することが大切です。
便秘は一朝一夕で改善するものではありません。根気よく継続することが重要です。また、便秘の原因や症状は人それぞれ異なるため、自分に合った方法を見つけることが大切です。
最後に、便秘に加えて血便や急激な体重減少、強い腹痛などの症状がある場合は、速やかに医療機関を受診してください。これらは大腸がんなどの重大な疾患のサインである可能性があります。
便秘は恥ずかしいことではなく、適切な対処が必要な健康問題です。この記事が皆さんの便秘改善の一助となれば幸いです。
健康な腸は健康な体と心の基盤です。便秘を根本から改善し、快適な毎日を取り戻しましょう。
便秘でお悩みの方は、ぜひ石川消化器内科・内視鏡クリニックにご相談ください。消化器内科専門医として、あなたの症状に合わせた最適な治療法をご提案いたします。

著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院