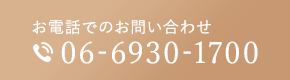粉瘤とは?皮膚の下に潜む袋状の腫瘤
皮膚の下にできる小さなしこり。気づいたときには少し大きくなっていて、触ると硬く、時に痛みを感じることもある。これが「粉瘤(ふんりゅう)」と呼ばれる皮膚のできものです。
粉瘤は医学的には「表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ)」または「アテローム」とも呼ばれ、皮膚の下に袋状の構造ができ、その中に皮脂や角質(垢)が溜まることで形成される良性の腫瘍です。
この袋の中には、皮脂腺からの分泌物や垢が溜まっているため、万が一袋が破けると、チーズと汗が混じったような強烈な臭いがすることもあります。中からは白いクリームのような液体や、カッテージチーズのようなボロボロしたものが出てくることが特徴です。
粉瘤は全身どこにでもできる可能性がありますが、特に皮脂腺が多い顔、首、背中、耳の後ろなどにできやすい傾向があります。サイズは数ミリから数センチまでさまざまで、放置すると徐々に大きくなることが多いです。
通常は痛みを伴わないことが多いですが、感染すると赤く腫れて痛みやかゆみを伴うことがあります。このような状態になると、中に溜まった内容物がにじみ出たり、破裂したりすることもあるのです。

粉瘤の原因と発生メカニズム
なぜ粉瘤ができるのか、その原因について詳しく見ていきましょう。粉瘤の発生には複数の要因が関わっています。
まず最も一般的な原因は「毛穴の詰まり」です。私たちの皮膚には皮脂を分泌する皮脂腺が存在し、通常は毛穴を通して皮脂が排出されます。しかし、何らかの理由で毛穴が詰まると、皮脂が排出されずに皮膚の中に溜まり、それをきっかけとして粉瘤が形成されるのです。
次に「皮膚の摩擦や刺激」も原因となります。衣服などで摩擦や圧力など刺激が多くなる部分は、皮膚にダメージを受けやすく、粉瘤が発生しやすいと言われています。首、背中、顔などは粉瘤ができやすい部位です。
また、「感染や炎症の影響」も見逃せません。ニキビや皮膚の炎症が悪化し、皮膚の中で角質が異常に分泌されてしまうことがあります。この角質が嚢胞内にたまり、粉瘤の原因となることがあるのです。
「ホルモンバランスの乱れ」も関係しています。思春期やストレス、ホルモンの変化によって皮脂の分泌が増えると、毛穴が詰まりやすくなり、粉瘤ができるリスクが高まります。
さらに、「先天的な要因」も考えられます。一部の粉瘤は遺伝的な要因や先天的な皮膚の構造により、幼少期から形成されやすいとされています。生まれつき皮脂腺が詰まりやすい傾向にある人は粉瘤ができやすいことがあります。
粉瘤は男性に多く見られ、特に20歳から60歳の間で発症することが多いことがわかっています。これは、皮脂腺からの分泌が盛んに行われ、新陳代謝が活発な時期であることが関係していると考えられます。
自宅でできる粉瘤のケア方法
「粉瘤は自宅でケアできるのか?」これは多くの方が抱く疑問です。結論から言うと、粉瘤を完全に治すには医療機関での適切な処置が必要ですが、症状を悪化させないための自宅ケアは可能です。
軽度の粉瘤で炎症や痛みが少ない場合には、自宅ケアを取り入れることで症状が悪化するのを防ぐことができます。ただし、これらのケアは「治療」ではなく「悪化防止」のためのものであることを理解しておきましょう。
清潔に保つ
粉瘤ができた部分は、これ以上毛穴詰まりを防ぐために清潔に保つことが大切です。優しく洗い、汗や汚れをためないようにしましょう。
刺激の強い石鹸や洗顔料は避け、敏感肌用の製品などを使用するのがおすすめです。ゴシゴシと強くこすると炎症を悪化させる可能性があるので、優しく丁寧に洗うことを心がけてください。
保湿ケア
乾燥した肌は皮脂の分泌が活発になりやすいため、適度な保湿を心がけます。特に顔や首のような皮膚が薄い部分は、保湿クリームを使ってケアするとよいでしょう。
ただし、油分の多すぎる製品は毛穴を詰まらせる原因になることがあるため、「ノンコメドジェニック」(毛穴を詰まらせない)と表示された製品を選ぶことをお勧めします。
刺激を避ける
粉瘤を無理に押し出したり、触ったりすることは絶対に避けましょう。圧迫や刺激により炎症が悪化し、感染や膿が溜まってしまう場合があるからです。
また、粉瘤のある部分を強く擦ったり、きつい衣類で圧迫したりすることも避けるべきです。特に首や背中など、衣類が擦れやすい部分にある粉瘤は注意が必要です。
これらの自宅ケアを行っても症状が軽減しない場合や、痛みや腫れが強くなった場合には、すぐに医療機関を受診しましょう。自己判断での対処には限界があります。

粉瘤に対する医療機関での治療法
自宅ケアには限界があり、粉瘤を根本的に治すためには医療機関での適切な治療が必要です。粉瘤が大きくなったり、炎症や膿がある場合には、特に医療機関での治療が重要になります。
ここでは、医療機関で行われる主な治療法について解説します。
切開排膿
粉瘤が炎症を起こし膿が溜まっている場合には、切開して排膿します。局所麻酔を用いて切開し、膿を排出して炎症を和らげます。
ただし、この治療法は一時的なもので、嚢胞自体が残っている場合には再発の可能性があります。切開排膿は応急処置的な治療であり、約3ヶ月後に粉瘤の芯が残っていないかを確認し、改めて袋ごと完全に除去することが重要です。
腫瘍摘出手術
再発を防ぐためには、嚢胞(袋状の部分)を完全に取り除くことが大切です。局所麻酔のもと、皮膚を切開して嚢胞を取り出す手術を行います。嚢胞を取り除くことで、粉瘤の再発リスクが軽減されます。
手術方法には主に「くり抜き法」と「切除縫縮法」があります。
くり抜き法は、皮膚の下にできた粉瘤(嚢胞)を完全に除去する手術です。通常は局所麻酔を使用し、専用のパンチを用いて粉瘤を慎重にくり抜き、嚢胞の袋ごと除去します。傷跡が目立ちにくいというメリットがありますが、完全に袋を取り除けない場合は再発のリスクがあります。
一方、切除縫縮法は粉瘤の標準的な治療法です。通常は局所麻酔を使用し、患部の大きさや深さ・種類に応じて切除範囲を決定し、中央の毛穴を含んだ皮膚を葉っぱの形に切り取り摘出します。確実に袋を取り除けるため再発のリスクが低いですが、粉瘤の大きさによっては同じ長さの線の傷跡が残る場合もあります。
レーザー治療
レーザーを使って嚢胞を取り除く治療法も限定的ですが、効果的な場合があります。切開手術よりも傷跡が小さくなりますが、粉瘤の状態や大きさによってはレーザー治療をできないこともあります。また保険は適用されません。
どの治療法が最適かは、粉瘤の大きさや状態、場所によって異なります。医師とよく相談し、適切な治療を選択することが大切です。

粉瘤の再発を防ぐための予防法
粉瘤は一度治療しても、正しいケアができていなければ再発しやすい皮膚トラブルです。ここでは、粉瘤を繰り返さないための予防法について解説します。
1. 皮膚を清潔に保つ
毎日のシャワーや入浴で皮膚を清潔に保ちましょう。特に汗をかきやすい部位や皮脂の分泌が多い部位は丁寧に洗い、皮脂や汚れが毛穴に詰まるのを防ぎます。
ただし、ゴシゴシと強くこすると皮膚を傷つけ、かえって炎症を引き起こす可能性があります。優しく丁寧に洗うことを心がけてください。
2. 適切な保湿を心がける
乾燥した肌は皮脂の過剰分泌を促し、毛穴詰まりの原因になります。適切な保湿ケアを行い、肌の水分バランスを整えましょう。
特に季節の変わり目や冬場など、肌が乾燥しやすい時期は入念な保湿が大切です。ただし、油分の多すぎる製品は避け、「ノンコメドジェニック」表示のある製品を選びましょう。
3. 摩擦や圧迫を避ける
きつい衣類や首回りがきつい服は、皮膚への摩擦や圧迫を増やし、粉瘤の原因になることがあります。特に粉瘤ができやすい首や背中などは、ゆったりとした服を選び、摩擦や圧迫を減らしましょう。
また、長時間同じ姿勢でいることも特定の部位への圧迫につながります。定期的に姿勢を変えたり、ストレッチをしたりして、血行を促進させることも大切です。
4. 規則正しい生活とバランスの良い食事
不規則な生活習慣やストレスは、ホルモンバランスを乱し、皮脂の過剰分泌を引き起こすことがあります。規則正しい生活と十分な睡眠を心がけましょう。
また、脂っこい食事や糖分の多い食事は皮脂分泌を増やす可能性があります。野菜や果物、良質なタンパク質を中心としたバランスの良い食事を心がけることも、肌の健康維持には重要です。
5. 定期的な皮膚チェック
小さな粉瘤は自覚症状がないことも多いため、定期的に皮膚の状態をチェックしましょう。早期発見できれば、小さいうちに適切な処置を受けることができます。
特に以前粉瘤ができたことがある部位は、再発の可能性があるため、注意深く観察することが大切です。何か気になる変化があれば、早めに皮膚科を受診しましょう。

粉瘤に関する誤解と真実
粉瘤に関しては、さまざまな誤解や間違った情報が広まっていることがあります。ここでは、よくある誤解と真実について解説します。
誤解1:「粉瘤は自分で潰せば治る」
粉瘤を自分で潰すことは絶対にやめましょう。確かに内容物を出すことはできますが、袋(嚢胞壁)が残っていれば再発します。また、不適切な処置による感染リスクもあります。
真実は、粉瘤を根本的に治すには、医療機関で袋ごと完全に摘出する必要があります。自己処置では完治せず、かえって症状を悪化させる可能性があるのです。
誤解2:「粉瘤はすべて同じ」
粉瘤にはさまざまな種類や状態があります。大きさ、場所、炎症の有無などによって、適切な治療法も異なります。
真実は、粉瘤の状態に応じた適切な治療が必要です。小さな粉瘤と大きな粉瘤、炎症を起こしている粉瘤と起こしていない粉瘤では、治療アプローチが異なります。医師の診断に基づいた治療を受けることが大切です。
誤解3:「粉瘤は必ず手術が必要」
小さく、症状がない粉瘤の場合、必ずしも即座に手術が必要というわけではありません。医師と相談の上、経過観察という選択肢もあります。
真実は、粉瘤の大きさ、場所、症状の有無によって、治療の緊急性や必要性が変わります。ただし、完全に治すためには最終的には手術が必要になることが多いです。
誤解4:「粉瘤は美容の問題だけ」
粉瘤は単なる見た目の問題ではありません。放置すると大きくなったり、炎症を起こしたりする可能性があります。
真実は、粉瘤は医学的な皮膚疾患であり、適切な治療が必要です。特に炎症を起こした場合は痛みを伴い、日常生活に支障をきたすこともあります。健康保険も適用される医学的治療の対象です。
誤解5:「粉瘤の手術は高額」
粉瘤の手術は、医学的治療として健康保険が適用されるため、自己負担額は比較的抑えられます。
真実は、健康保険が適用される場合の医療費自己負担割合は、年齢や所得に応じて異なりますが、一般的には3割です。粉瘤の切除手術における自己負担額の目安は、保険診療での全国平均で8,200円(3割負担換算)程度と報告されています。個別のケースでは数千円から2万円程度となることが多いようです。

粉瘤が疑われる場合の受診タイミング
粉瘤が疑われる場合、どのタイミングで医療機関を受診すべきでしょうか。以下のような症状や状況がある場合は、早めに皮膚科を受診することをお勧めします。
受診が必要なケース
まず、「急に大きくなった」「痛みや赤みが出てきた」という場合は要注意です。粉瘤が炎症を起こしている可能性があり、早めの処置が必要です。炎症を起こした粉瘤は痛みを伴い、触れると熱を持っていることもあります。
また、「自分で潰してしまった」という場合も受診が必要です。自己処置によって感染リスクが高まっている可能性があります。医師による適切な処置を受けましょう。
「大きさが気になる」「目立つ場所にある」という場合も、医師に相談するとよいでしょう。特に顔や首など、人目につきやすい場所にある粉瘤は、早めに処置することで目立ちにくい傷跡で済むことがあります。
さらに、「以前に粉瘤の手術をしたが再発した」という場合も受診が必要です。前回の手術で袋が完全に取り除かれていなかった可能性があります。
医療機関選びのポイント
粉瘤の治療を受ける際は、皮膚科や形成外科を選ぶとよいでしょう。特に粉瘤の手術実績が豊富な医療機関を選ぶことで、再発リスクの低い適切な治療を受けられる可能性が高まります。
受診の際は、いつから症状があるか、大きさの変化、痛みの有無などを医師に伝えましょう。また、以前に粉瘤の治療を受けたことがある場合は、その情報も伝えることが大切です。
粉瘤は放置すると大きくなったり、炎症を起こしたりする可能性があります。気になる症状がある場合は、自己判断せず、専門医に相談することをお勧めします。
まとめ:粉瘤との上手な付き合い方
粉瘤は皮膚の下に袋状の構造ができ、その中に皮脂や角質が溜まることで形成される良性の腫瘍です。顔、首、背中など、皮脂腺が多い部位にできやすく、放置すると徐々に大きくなる傾向があります。
粉瘤の原因としては、毛穴の詰まり、皮膚の摩擦や刺激、感染や炎症の影響、ホルモンバランスの乱れ、先天的な要因などが考えられます。特に20歳から60歳の男性に多く見られます。
自宅でのケアとしては、患部を清潔に保つ、適切な保湿を心がける、刺激を避けるなどが挙げられますが、これらは「治療」ではなく「悪化防止」のためのものです。粉瘤を根本的に治すには、医療機関での適切な処置が必要です。
医療機関での主な治療法には、切開排膿、腫瘍摘出手術(くり抜き法、切除縫縮法)、レーザー治療などがあります。どの治療法が最適かは、粉瘤の大きさや状態、場所によって異なりますので、医師とよく相談して決めることが大切です。
粉瘤の再発を防ぐためには、皮膚を清潔に保つ、適切な保湿を心がける、摩擦や圧迫を避ける、規則正しい生活とバランスの良い食事を心がける、定期的な皮膚チェックを行うなどの予防法があります。
粉瘤に関する誤解も多く、「自分で潰せば治る」「すべての粉瘤は同じ」「必ず手術が必要」「美容の問題だけ」「手術は高額」などがありますが、これらは正しくありません。粉瘤は医学的な皮膚疾患であり、適切な治療が必要です。
粉瘤が疑われる場合は、急に大きくなった、痛みや赤みが出てきた、自分で潰してしまった、大きさが気になる、目立つ場所にある、以前の手術部位に再発したなどの症状や状況がある場合は、早めに皮膚科や形成外科を受診しましょう。
粉瘤は適切な治療と予防法で上手に付き合うことができます。気になる症状がある場合は、自己判断せず、専門医に相談することをお勧めします。
当院では、消化器内科・内視鏡専門医として皆様の健康をサポートしています。皮膚のお悩みも含め、どんな小さな症状でもお気軽にご相談ください。
詳しい情報や診療時間については、石川消化器内科・内視鏡クリニックのホームページをご覧ください。
著者情報
石川消化器内科・内視鏡クリニック
院長 石川 嶺 (いしかわ れい)
経歴
平成24年 近畿大学医学部医学科卒業
平成24年 和歌山県立医科大学臨床研修センター
平成26年 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科
平成29年 近畿大学病院 消化器内科医局
令和4年11月2日 石川消化器内科内視鏡クリニック開院